インタビュー
早稲田大学大学院 谷口真美氏
ダイバシティ組織の創造とリーダーシップ
- 公開日:2006/09/01
- 更新日:2024/03/25

ここ2、3年の間にダイバシティという言葉をよく耳にするようになりました。外部の環境変化が激しいなかで、いち早くダイバシティ・マネジメントに取り組む企業も出てきています。日本の企業においてどのようにダイバシティ組織を創造するべきか、またそのような組織を率いるにはどのようなリーダーシップが必要なのか、ダイバシティ研究の国内第一人者である谷口先生にお話をうかがいました。
- 目次
- 日本にも押し寄せるダイバシティの波
- ダイバシティは組織変革のツール
- ダイバシティ組織を創造するヒント
- ダイバシティ・リーダーに求められるもの―リーダーの要件
- ダイバシティ研究への想い ―ダイバシティに取り組まれる人事担当者の皆様へ
日本にも押し寄せるダイバシティの波
― ダイバシティという言葉はいろいろな意味で使われていますが、先生はどのようにお考えです?
ダイバシティとは、性別や年齢、人種・国籍の違いといった表層的な次元にとどまらず、勤続年数や役職、経歴、生育環境、価値観、働き方などの深層的な次元をも対象とする幅広い概念です。ダイバシティ・マネジメントは女性活用の問題だとか企業のグローバル化のことだと誤解されることも多いですが、それらはダイバシティの概念のほんの一部にすぎません。
― ダイバシティ・マネジメントという言葉は日本ではどの程度浸透しているのでしょうか?
先日、ある講演会の際に700社近くの人事の方にうかがってみたのですが、「ダイバシティ」という言葉を聞いたことがあるという方は全体の4割程度でした。そのなかで自社にダイバシティに関するプロジェクトがある、自身がダイバシティ推進にかかわっているというのは5社だけでした。首都圏でその状況ですから、その他の地域ではもっと割合は低くなるのではないでしょうか。日本ではまだまだ浸透していないといえますね。
― ダイバシティという観点で、日本の組織の現状はどうですか?
今の日本企業もダイバシティという意味ではバラエティに富んでいます。たとえば、退職年齢の延長や再雇用によって高齢者が確保されるので、組織内の年齢の幅が広がる。あるいは合併などで出身母体が違う人や異なる雇用形態の人がいる……というように、様々な価値観をもった人たちがいる企業はたくさんあります。実はダイバシティに触れたことがない企業はほとんどないのではないでしょうか。
ダイバシティは組織変革のツール
― なぜダイバシティを組織に取り込む必要があるのでしょうか?
ダイバシティの目的は、多様な人材の“違い”をプラスと見ていかし、チームの成果につなげていくことです。たとえば女性活用は今最も注目されているテーマのひとつですが、単に女性を採用すること、管理職に登用すること、女性がいきいきと働くことは、本来の目的ではありません。あくまでも女性を活用することによって組織のパワーバランスを変革させ、ビジネスのパフォーマンスを上げていくことが目的なのです。
― 日本ではCSR(企業が果たすべき社会的責任)の文脈で語られることが多いように思いますが。
残念ながらそうですね。でも、ダイバシティは社会的潮流に後押しされた「やらなければならないこと」ではありません。ビジネスのパフォーマンスを上げるための組織変革のツールなのです。多様性をうまくいかしたほうが企業にとって絶対に合理的ですよね。
― ダイバシティに取り組むにあたって、何から取り掛かればよいでしょうか?
まず、自組織のダイバシティの現状と、期待されるレベルを確認することからです。組織にどのような人がいてどう変わる必要があるのか、診断してみるとよいですね。それをやってから初めて、女性を活用するのか、マネジメントを変革するのかといった施策を考えればよいと思います。
ダイバシティ組織を創造するヒント
― ダイバシティによって組織が進化するモデルについて教えてください。
ダイバシティに対して企業がとる行動には、抵抗-同化-分離-統合の4つのパターンがあります。
図表 ダイバシティに対する企業行動 出所:谷口(2005)
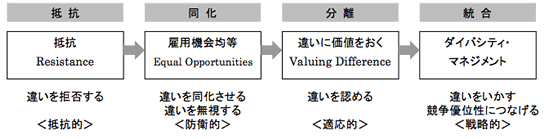
多くの企業は、“違い”を拒否する「抵抗」の段階か、“違い”を同化させたり無視したりする「同化」の段階だと思います。ダイバシティに取り組もうとして多様な人材を採用してみても、従来の行動規範をそのまま押し付けたのでは何も変わりません。合併した企業でも同じことで、両者のよさをいかすにはどうしたらよいかを考えなければなりません。一方に「同化」させてしまうことは、本来組織が持っていた良さや可能性を潰してしまうことになりかねないからです。
― ダイバシティによって組織を活性化するためには何から始めたらよいでしょうか?
まずは“違い”を認める段階の「分離」から始めることですね。「分離」は組織全体の変容を伴わず、企業のなかの特定の一部分だけにダイバシティを取り入れた状態のことをいいます。ダイバシティをいつでも取り込むことができ、それをパフォーマンスにつなげられる状態のことを「統合」といいますが、拙速に「統合」の段階に進もうとすると、多様の良さを失って結局「同化」に戻ってしまったりもします。
― 一部の組織だけにダイバシティを取り入れるとは、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?
たとえば小売業でも、顧客に外国人が多ければ、その国の言語だけでなく文化や価値観も理解しようとしますよね。この場合、その顧客接点のある部署だけがダイバシティになります。“違い”を認めるとは、実は必要性に応じた行為なのです。
著書のなかでも紹介していますが、イオンも「分離」から始めて成功した例ですね。店長というリーダー職に初めて女性を登用したんですが、それと同時に女性管理職の育成経験をもつ上司を配置したり、店長に期待する役割を柔軟に変えたりしたのです。そうした仕組みのサポートもあり、しだいに“違い”が成果に結びつくようになり、今までのように「販売経験豊富な男性社員」でなくてもパフォーマンスを上げられることが理解され、全社的に女性や若手、経歴の異なる人を店長に登用しようという展開へと広がっていったのです。
― まずは特定のチームで成功例を作るということですね。
全員が平等になるように最初から制度を作るのではなく、できるところから始める。うまくいったらその事例を他の部署にも水平展開して……というように、段階的にやるとよいと思います。全社的に「統合」へ向かうには、それに加えて経営トップのコミットメントも重要になってきます。
ダイバシティ・リーダーに求められるもの―リーダーの要件
― ダイバシティ組織のリーダーが直面する課題には、どのようなものがありますか?
それぞれのメンバーがもっているよいものをいかすために、組織のパワーバランスを変えていく必要がありますね。
また、さまざまな価値観をもった人の間では、どうしてもミスコミュニケーションやコンフリクトが生じてしまいます。組織のメンバー間でお互いへの共感が欠如したり、レッテル張りに陥ったりもします。多様な人材を単に「入れる」だけでなく、きちんと「参加させる」ことが重要なのです。
さらに、ダイバシティを取り入れて変化していこうということ自体への抵抗も起きることが考えられます。そのような従来のメンバーへの対処も必要となります。
― そのような環境で、リーダーに求められるのは何ですか?
ダイバシティ・リーダーには行動レベルの能力も必要になりますが、鍵になるのはやはり価値観やものの見方・捉え方ですね。特に、偏見を含めた自己の特性に関する認知(Self Awareness)や、曖昧な状況やストレスに耐えられるのかなどの要件は、必ず求められると考えています。
たとえば、偏見をもたない人はいないですよね。偏見は、もたないことが大切なのではなく、自分の偏見に気づくことが大切なのです。特にこのようなSelf Awarenessは日本人に欠けているといわれますね。
― スキルや行動だけでなく、リーダーには資質的な面も重要だということですね。
このあたりについては現在研究を進めているところです。スキルや行動レベルのものは開発可能な部分が多いですが、やはりそれだけではないと思っています。ダイバシティ・リーダーシップの開発とリーダーの選抜が、今後注目のテーマになると考えています。
ダイバシティ研究への想い ―ダイバシティに取り組まれる人事担当者の皆様へ
― 先生がダイバシティに興味をもたれたきっかけを教えてください。
AOM(Academy of Management:アメリカ経営学会)に参加するようになり、たくさんの優秀な研究者と知り合うことができました。ある時「おもしろいセッションがあるからおいで」と誘われ参加すると、そこはものすごく活気を帯びていました。実はそこにはダイバシティの中核的メンバーが集まっていて、企業のケースごとに「こうやったらどんなふうにパフォーマンスが上がる」というダイバシティのモデルが集まってきていたんです。こんなおもしろい研究があるのか、と(笑)。たとえばフェミニズムの問題などは価値観の議論で終わってしまいがちですが、ダイバシティでは理論やモデルが作れるし、ビジネスのアウトプットに直結するテーマで研究できるのがおもしろいですね。
― 研究をされるうえでこだわりをもっていることは何ですか?
それまでされてきた研究は失敗例に焦点をあてて、なぜ失敗したのかという理由を探していました。たとえば日本企業に外国人トップが来ても結局活躍できないのはなぜか――それは日本が特殊だから、といったように。でも、私は成功例にこそヒントがあると思い、そこに着目してきました。女性管理職の研究などをしながら、うまくパフォーマンスが上がったケースを見て、そこでどんな組織の変化が起きたかとか、何が変わったのかということに目を向けるようにしています。
― 最後に、日本企業の人事担当者へのメッセージをお願いします。
女性管理職を全体の何%にしようといったように、単に多様性を確保するためにダイバシティに取り組んでもマネジメント効果は発揮できないと考えます。繰り返しになりますが、ダイバシティの目的は、あくまでも組織のパフォーマンスを上げること。目的を履き違えてダイバシティを進めてしまうと、かえってもともとあった同質性のよさを失いかねません。もともとのよさをいかしつつ、試行錯誤しながら新しいものを段階的に導入することで、ダイバシティというテーマに取り組んでいただくほうがよいと思います。
― どうもありがとうございました。
(インタビュアー:小方 真・文:黒田 知紗)
研究者PROFILE
谷口 真美 (たにぐち まみ)氏
早稲田大学大学院商学研究科 助教授

特技
限られた時間で素早くショッピングをすること。
海外出張も多く、免税店でのわずかな時間をいかした買い物技はかなりのもの。
略歴
1996年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)取得。広島経済大学経済学部経営学科助教授、広島大学大学院社会科学研究科助教授を経て、2000年米国ボストン大学大学院組織行動学科・エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員。2003年より現職。
主要著書・論文
『ダイバシティ・マネジメント 多様性をいかす組織』 白桃書房 2005年
「経営モデルの融合プロセス:フォード資本提携強化後のマツダの経営革新」(共著) 『国民経済雑誌』 神戸大学経済経営研究所 平成15年3月号
「女性にとっての日本型経営」(分担執筆) 『ジェンダー・マネジメント』東洋経済新報社 2001年
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で