特集
主体性を引き出しエンゲージメントを高める
能動的に企業価値の創造を志向するガバナンスとは
- 公開日:2008/08/18
- 更新日:2024/04/11

現在、日本企業は厳しい環境におかれています。昨今の需要予測は先行きが読めない一方、原材料物価の高騰はとまりません。ITバブル崩壊後、日本経済には復活の兆しがありましたが、環境が急速に変化した今では、残念ながら今後の先行きは不透明と言わざるをえません。
企業はこのような状況下で、厳しいコーポレートガバナンスを迫られています。企業を監視するための機構である、経営者報酬、日本版SOXなどのキーワードが新聞紙上に掲載されない日のほうが少ないのかもしれません。しかし、こうした「監視機構」としてのガバナンスは受動的で、本来企業が目指すべき価値の創出には能動的につながるものではありません。本来、ガバナンス(統治)でなすべき最終的な目的は、企業の社会的・経済的な使命を全うし価値を生み出すための組織体制を維持することです。その実現のために、社員を企業にエンゲージするチームとし、企業価値を高めていく組織体制を築く。それこそがあるべきガバナンスの姿なのではないでしょうか。
では、「ガバナンスのあるべき姿」とは具体的にはどういうものか? 先進企業がそれをどのように達成してきたのか? 今回は簡単ではありますが、その考え方と事例をご紹介いたします。厳しい環境下で、企業の統治に苦心する経営者、経営企画担当者、人事担当者の皆様が現在悩んでいらっしゃる問題の解決の一助になれば幸いです。
- 目次
- 事業環境は厳しさを増しつつある
- 今、求められるガバナンスとは?
- 事例:社会的な意義を、経済的な意義と紐付け、全社に浸透させる ~医療サービス機関A社~
- 事例:現在の危機を正しく認識し、その危機を乗り越えるための改善目標を現場に落とし込む ~飲料メーカーB社~
- 事例:経営陣と現場の社員が、事業として達成すべき目標をベースに対話を繰り返すことで、組織を束ねる ~アウトソース業者C社~
事業環境は厳しさを増しつつある
まずは、日本企業がおかれている現在の事業環境を再確認しましょう。
日本の主要な企業は、2002年から2007年にかけて、企業規模(総資産の規模)を拡大しつつ、事業効率(ROA)を改善し、企業価値を創造してきました。(図1)
しかしながら現在は、原材料が高騰し続ける一方で、企業業績の悪化を見通す株価の下落が見られ、マクロ経済全体は今後落ち込むことが考えられます。いわゆるスタグフレーションの発生が予測される事態となっています。
■石油や鉄鋼といった主要工業製品の価格は上昇しており、物価の総平均も上昇している(図2.3)
■株価は下落傾向に転換しつつある(図4)
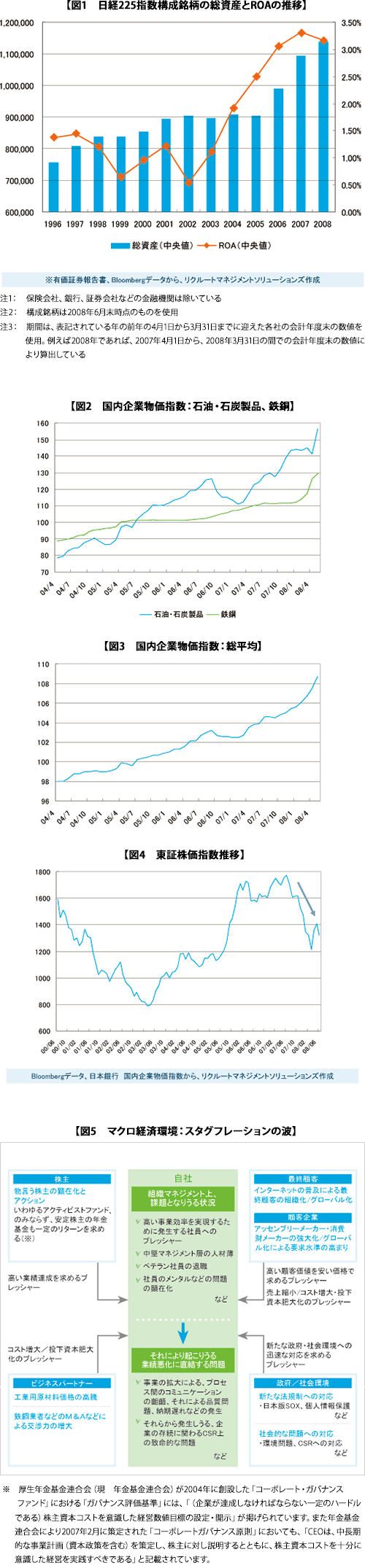
こうしたマクロ環境の中、社員は高い生産性を実現するために、常にさまざまな強いプレッシャーにさらされています。また、社内の人材リソースは、中堅マネジメント層の人材薄、ベテラン社員の退職などに伴い、枯渇しつつあります。社員自身もこのような厳しい環境下では、スキル不足やプロセス間のコミュニケーションの齟齬による品質問題・納期遅れなど、業績の悪化に直結する業務上の問題や、企業の存続に関わるCSR上の致命的な問題が、起きないとは言い切れません。(図5)
今、求められるガバナンスとは?
では、こうした厳しい状況の中で、企業にはどのようなコーポレートガバナンスが求められているのでしょうか。
通常、コーポレートガバナンス、という文脈で語られるものとしては、ストックオプション制度などの役員報酬、日本版SOX、外部監査役や外部取締役などがあります。これらは外部から企業のトップを監視する仕組みであり、受動的なガバナンス、と言い換えることもできるでしょう。しかし、厳しい事業環境を踏まえると、経営陣を監視するための機構としての受動的なガバナンス制度の導入に終始していいのでしょうか。
いえ、決して十分とは言えません。現在は、社会的な使命と経済的な使命の両方を持続的に実現する体制をより能動的に維持することが、求められています。そのために、経営陣のみならず、事業部・組織・職場、そして社員が一つのチームとして、組織目標の実現にコミットし、自走するチームを築き上げる、『全社のエンゲージメントを高める』ことが現在求められているガバナンスの本質ではないでしょうか。
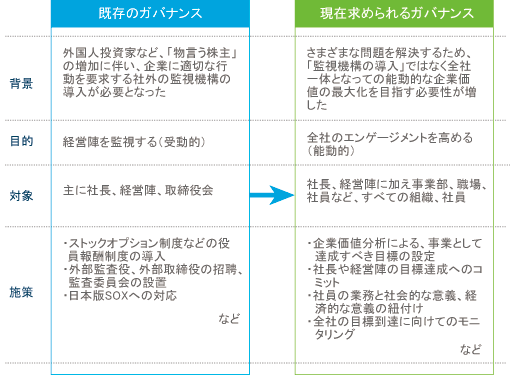
エンゲージメントを高めるガバナンスを実現するためのポイント
エンゲージメントを高めるガバナンスを実現するためには以下のポイントを踏まえることが重要となります。
1 社会的な意義を、経済的な意義と紐付け、全社に浸透させる
創業期のベンチャー企業であれば別ですが、ある一定の規模を持つ企業、複数の事業所や事業部を抱える企業では、経営陣自らが自分の考えを社員に直接語ることで企業を束ねていくことには限界があります。
そこで、企業の社会への貢献と業績目標、そして業務との関係性を現場マネージャーを巻き込んで考えることで、全ての組織の社員が自らの業務の自社への貢献、ひいては社会への貢献がどのようなものであるかを理解することが重要です。
2 現在の危機を正しく認識し、その危機を乗り越えるための改善目標を現場に落とし込む
全社・事業の目標と大きな戦略があっても、それを改善目標として指標を構築し、さらに現場に落とし込まなければ、社員は何をどの程度改善しなければならないのか理解できません。
目標を実現するための道筋を想定し、現場に落とし込むことで社員が担当業務の全社への価値創造の貢献を理解することが必要です。
3 経営陣と現場の社員が、事業として達成すべき目標をベースに対話を繰り返すことで、組織を束ねる
厳しい環境の中で、意義を理解してない目標を押し付けられると、現場の社員の力は小さくなるばかりです。
事業として達成すべき理にかなった目標をベースに経営陣と現場の社員が対話を繰り返すことで、社員がその目標の意義を理解することが大切です。
事例:社会的な意義を、経済的な意義と紐付け、全社に浸透させる ~医療サービス機関A社~
状況:カリスマ経営者による業績拡大
A社は市場需要の拡大に伴い、業績も大きく伸ばしてきました。カリスマティックな経営者が力強く牽引し、一見、A社の今後の展望は明るく見えました。
課題:社員の疲弊とミスの多発
しかし急速な業容の拡大により、社員は疲弊し、また医療サービス機関として起こってはならないミスも複数件発生していました。現在の成長が順調でもこうしたことが続けば、ブランドは大きく傷つき、今後企業価値の致命的な毀損が発生しうることが危惧されていました。
取り組み:社会的・経済的な意義の確認と、現場への浸透
そこで、A社では、社長や経営陣がもう一度、目指すべき社会的意義とその道筋を可視化し、経済的な目標とその道筋との関係を明らかにするとともに、その議論に現場のマネジャーが参加し、納得感を持って現場レベルでの計画管理やMBOに紐付けられるためのセッションを全社横断で実施しました。
成果:経営陣~現場マネジャーまでの社会的、経済的な意義の再確認による一体感の醸成
上記の取り組みは、社長から現場のマネジャーが参加する大規模なものとなりましたが、そこでのヒアリングや、道筋構築のためのセッションの中で社長や経営陣は日頃感じることのない経営上の問題点を痛感することで、その解決へと邁進することができました。
一方、現場マネジャーはこのセッションに参加することにより、単調な作業に思われた自分の部署の業務が、会社が業績を高めるためにいかに大事なのか、という経済的な意義と、病気に苦しむ顧客にどのように役に立っているのか、という社会的な意義を理解するに至りました。
こうして全社を一丸にし掲げた目標に邁進するA社は、現在においても半期に1回、目標とその道筋を現場レベルも含めたディスカッションにより刷新し、あるべき姿に向けて進んでいます。
成功の要因:現場の積極的な取り込み
こうした取り組みは経営陣が作った戦略を現場に押し付けるという形になりがちで、ともすると現場には「やらされ感」が醸成されてしまいます。しかしA社の場合は、現場マネジャーがミーティングに積極的に参加することにより、現場マネジャーや、彼らと直接コミュニケーションを取るメンバーが会社の戦略と自分たちの行う業務のつながりを理解し、業務の戦略的な意義、ひいては社会的な意義を理解し、業務と組織への両方のエンゲージメントを高めることになったのです。
事例:現在の危機を正しく認識し、その危機を乗り越えるための改善目標を現場に落とし込む ~飲料メーカーB社~
状況:製品ブームの終焉に伴う売上の低下
B社は危機に直面していました。B社が供給する製品のブームが終わり、業績が急降下していたのです。売上にブレーキがかかり(非常に大きなPL上の赤字を記録しました)、B社も含めた業界には、製品在庫があふれかえっていました。このまま手をこまねいていてはB社がその存続を問われるような状態に陥るのは目に見えていました。
課題:自社の現状課題への薄い認識
経営陣の間で自社の状況が十分に共有されていませんでした。製品ブームの終焉は明らかで、経営陣は、「このままではいけない」とはなんとなく思っていましたが、「今すぐ行動を起こさなければならない」というほどの切迫感を抱いていませんでした。また、当然のことながら、経営陣以上に、現場には危機的な状況と課題は浸透していませんでした。
取り組み:経営陣による現状の再確認と、現場に踏み込んだ経営改革の徹底遂行
ヨーロッパの先進企業の社外取締役を経験していたB社の社長は、現状を把握し、経営陣と危機感を共有する必要を感じました。そのため、まず、財務分析、ポートフォリオ分析でB社が明らかに危機に陥っていることを理解し、正しい企業努力により生き残ることが可能であることを確認しました。次に、全社に向けて現状を何度も発信しながら、事業再編などの戦略面にとどまらず、成果を明示して評価に結びつけるなど、社員全体のガバナンスに関わる改革が徹底的に行われました。
成果:サプライチェーン改革の実現によるキャッシュフローの改善
社長や経営陣の現状認識とそれに基づく明確な目標が何度も共有された結果、社員は目標達成をそれまで以上に重視して活動するようになりました。厳しい市場環境のもとで、売上はなかなか伸びませんでしたが、社員は必死になってサプライチェーンの改革に挑み、在庫の適正化を行いました。それにより、経済紙でも批判を浴びた過大な資産は大きく減少し、キャッシュフローの改善が見られました。同社はその後は順調な経営を行っています。
成功の要因:社長・経営陣の決断と現場への具体目標の提示と共有
社長や経営陣が現在の危機を正しく認識し「腹決め」をした上で、社員に現在の危機と今後への課題を訴え、そして状況を正しく認識することのできる新しい経営指標が今後生き残るためにどうしても必要だ、ということを繰り返し伝えました。
成果が分かりやすく表される新しい経営指標により、全社員がサプライチェーン改革による在庫の適正化を数値として確認することが可能となり、社員のエンゲージメントを高めました。
事例:経営陣と現場の社員が、事業として達成すべき目標をベースに対話を繰り返すことで、組織を束ねる ~アウトソース業者C社~
状況:経営陣と現場の目標金額の大きな相違
C社では、目標設定の時期に、いつも現場からうんざりしたため息が聞こえていました。経営トップが掲げる目標が、あまりに現場の現実とかけ離れていたのです。現場からは達成可能と思われる目標金額が提示されますが、経営陣の目標とは大きなギャップがあり、議論にもならないまま、結局現場には達成不可能に思われる目標が設定されていました。
課題:現場にとって現実感のない目標に対する緊張感の減退
経営トップが掲げ、設定される目標と、現場が感じている達成可能な金額とのギャップの大きさに、現場からは業績を高めるための緊張感が消えうせていました。
取り組み:競合をも視野に入れた、現場に受け入れられる目標の設定
この状況に危機感を持った経営陣は、企業価値を元に分析した事業として達成すべき目標をもとに、社長と事業部の責任者、そして全社経営企画の責任者が目標設定の議論を行いました。企業価値分析による目標に比べると事業部の掲げた目標は低すぎ、しかし、経営トップが繰り出した目標は高すぎたことが分かりました。また、競合他社の過去の実績を見ても、企業価値分析による目標とほぼ同水準の改善を達成していることがわかり、この事業を行っている以上、企業価値分析による事業として達成すべき目標にはどうしても到達しなければならないことを理解しました。
成果:現場の意欲喚起を引き起こす、適切な目標の設定
C社では、企業価値に基づく目標を必達目標とし、トップからの目標をストレッチ目標としました。さらに競合が必達目標程度のことは実際に到達していることに社員はショックを受け、自らを奮いおこしました。その期以降、C社は規模の成長と、事業効率の改善の両方を実現し、価値創造を続けています。
成功の要因:事業として達成すべき目標の分析と議論
C社では、経営トップと現場の双方が掲げる目標のギャップが、そのまま経営陣と現場のコミュニケーションギャップを意味していました。そのコミュニケーションを仲介するためには、「事業として達成すべき目標」を分析し、それを元に議論を重ねることが必要でした。これによって、互いのコミュニケーションギャップを埋めることが可能となり、互いのおかれている状況を理解し、必ず達成しなければならない目標に向けて動き出すことで、現場の閉塞感を打破することができました。
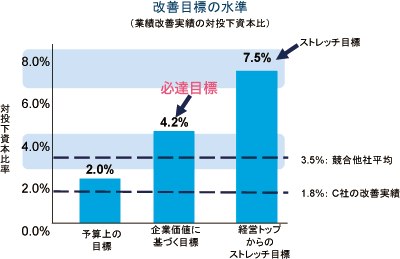
さいごに
昨今の経営環境が非常に厳しいのは事実ですが、そんな中にあっても、全社の社員を、社会的な使命と経済的な使命の両方にエンゲージする一つのチームとして組織した企業は、前述のように確実な成果を残しています。
無論、こうしたことが容易に実現できないのは皆様が日頃感じていらっしゃることと存じますが、皆様が現在悩んでいらっしゃる課題解決の一助になれば幸いです。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












