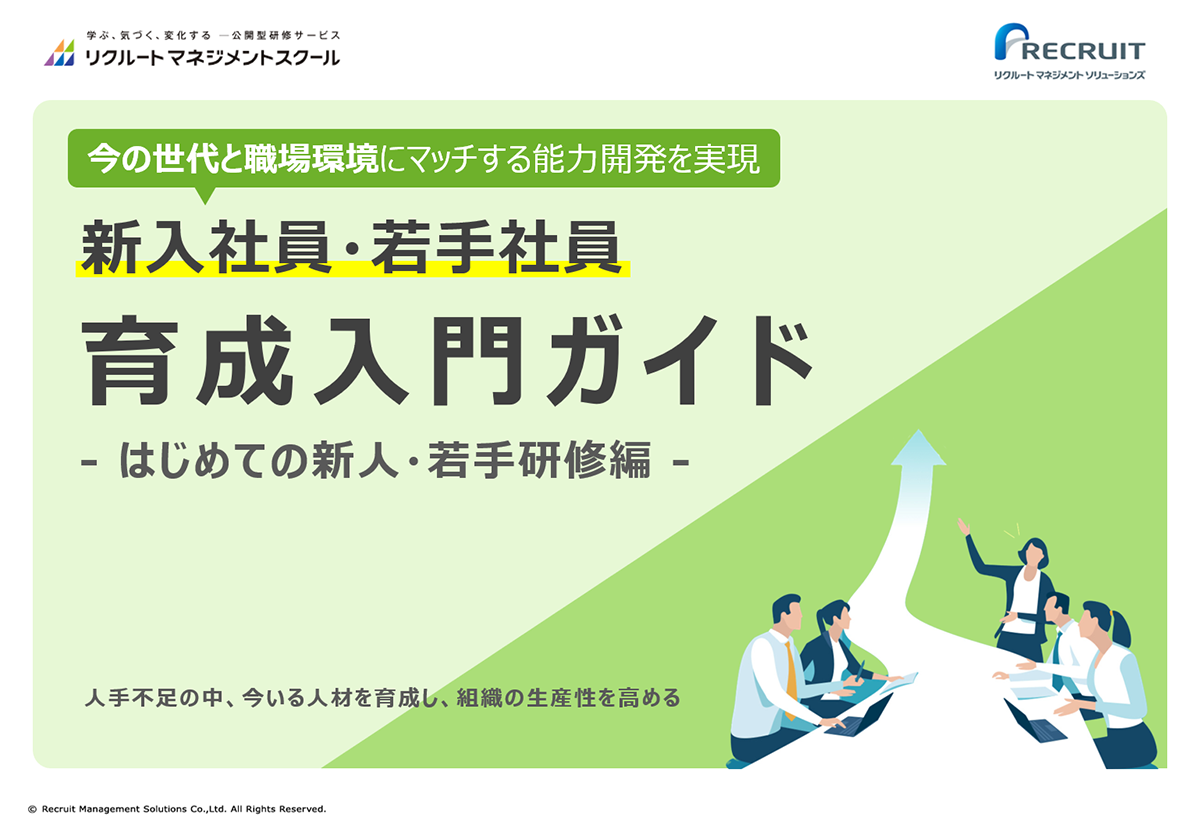連載・コラム
【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 公開日:2025/11/17
- 更新日:2025/11/17

「若手社員をどのように育成すればよいのか分からない」「どうやって良い関係を築けばよいのか分からない」「若手社員をどう捉え、どう理解したらよいのか分からない」といった声をよく耳にします。永遠の課題といってよいのかもしれません。
専門家をお呼びして、コミュニケーションやダイバーシティといった観点から新人・若手社員育成を考える本コラムシリーズ。第1弾は大学院大学至善館副学長・教授の枝廣淳子氏をお迎えし、「ダイバーシティ実現を目指すなかでの、若手との向き合い方」についてお話を伺いました。第2弾はコーチ・エィの鈴木義幸氏をお招きし、具体的な対話のノウハウを伺いました。第3弾の今回は、労働経済学の専門家であり、『ニート』(共著、幻冬舎文庫)、『仕事のなかの曖昧な不安』(中公文庫)などの仕事論・若者雇用論や希望学研究で知られる東京大学社会科学研究所教授の玄田有史氏を訪問し、「若手社員との向き合い方」についてお話を伺いました。
対談メンバー
●玄田 有史氏(東京大学社会科学研究所教授)
●桑原 正義(リクルートマネジメントソリューションズ サービス統括部 主任研究員)
●武石 美有紀(リクルートマネジメントソリューションズ サービス統括部 研究員)
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
若手社員に“上手に失敗させる”のが上司の仕事
桑原:今の日本企業には「若手社員への対応が難しい」「若手社員との距離がなかなか縮まらない」といった悩みを持つ人事やマネジャーがたくさんいます。玄田先生は、若手社員にどのように接したらよいと思いますか?
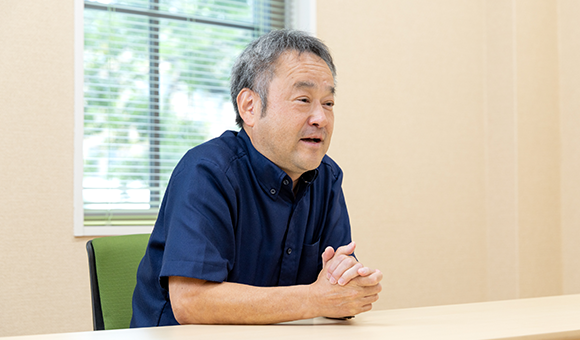
玄田:このようなお悩みは今に始まった話ではありません。若手社員への対応が簡単だった時期などありませんでした。『働く過剰―大人のための若者読本』(NTT出版)のまえがき冒頭に書いたとおり、いつの時代でも若者は、大人にとって「よく分からない」存在です。
武石:若手社員の多くは、働き始めた後、必ず何らかの壁にぶつかります。そのようなとき、失敗への不安や恐れから一歩踏み出すことができないなどの声をよく聞きます。上司の皆さんはそんな彼らをどのようにサポートすれば、より若手社員が動きやすくなるでしょう。
玄田:そのままでよいと思いますよ。壁にぶつかっても、その壁を無理に乗り越えようとする必要はないと考えています。
というのも、私は昔から、「仕事で壁にぶつかったときは、無理に乗り越えようとしなくてもいい。逃げずに“ウロウロ”していれば、そのうちに誰かが助けてくれて高い壁もいつの間にか乗り越えられたりする」と若者たちに話してきました。その姿勢は今も変わっていません。
逃げずに壁の近くで“ウロウロ”しているうちに、ひょんなことで壁を乗り越えるためのヒントが見つかったり、ヘリコプターが飛んできて壁の向こうに連れて行ってくれたり、壁が勝手に崩れて先に進めたりするものなのです。無理に壁を乗り越えなくても、時が来れば何とかなるのです。
今お話ししたことは「ネガティブ・ケイパビリティ」というような言葉でも言い換えることができるのかもしれません。
上司に対しては、「若手社員に上手に失敗させるのが、上司の大事な仕事の1つ」だとお伝えしたいです。

武石:“上手に失敗させる”という観点、とても興味深いですね。詳しく聞かせてください。
玄田:私は仲間たちと共に希望と社会の関係を考察するための「希望学」を研究してきましたが、そのなかで「希望は修正の旅である」と考えるようになりました。私たちの人生は、うまくいかないことが多いものです。叶うことなく失望に変わっていくこともあるでしょう。ですが、希望の修正を重ねていると、どこかでやりがいに出会えることも多いのです。
この修正の旅のなかで、若手社員たちは、必ずどこかで失敗して痛い目に遭います。彼らはそのときはじめて、「これからどうしたらよいのだろう?」と真剣に考え始めるのです。その際の上司の大事な役割の1つは、若手社員が失敗から大きなダメージを受けすぎないように、“ほどほどの失敗”にとどまるように調整することです。
もう1つの大事な役割は、「希望を修正するヒントを渡す」ことです。失敗して真剣に考え始めたタイミングで、「次はこういう道もあるんじゃない?」と選択肢を提案するのです。もちろん最終的に選ぶのは本人ですが、若手社員が独りで軌道修正するのは大変ですから、上司が手助けするのはまったくかまわないと思います。上司がこの2つの役割を果たすことができれば、若手社員はきっと上手に失敗して次に進めるはずです。
【関連】育成担当者研修はこちら
人と人の出会いのなかで生まれる“偶然”が若手社員の気づきを促すことも
武石:最近は「配属ガチャ」という言葉が広まるなど、職種や勤務地などの希望が通らない会社には就職したくない、という若手社員も増えています。一方の企業は、このニーズに合わせて、職種別採用やコース別採用を増やしています。先生はこうした流れをどのように見ていますか?
玄田:昔も今も、若手社員たちは自己理解の最中です。職務経験や人生経験がまだ少ないために、自分が何に向いているか、どのようなキャリアを歩めばよいかといったことが十分に分からないのです。これは当然のことです。ただそう考えると、多くの新卒学生は、職種別採用・コース別採用では本当に自分に合った道を選べないともいえるかもしれませんね。
ですが、若者たちだけでなく、大人の私たちだって、自分のことや人のことを深く理解できているかと聞かれるとそうともいえないですよね。とはいえ、上司や人事の方が、職務経験や人生経験がある分だけ、若手社員本人よりも若手社員の向き不向きや伸びしろなどが見えているはずです。だからこそ、上司や人事は、若手社員の個々の適性などを踏まえて、新しい業務やチャレンジをうまく促していくことが大事です。

桑原:うまく促していくことは大切ですね。
玄田:小さくでもやってみると、そのなかで思いがけない方向に能力を伸ばして「化ける」若手社員が出てきます。それこそが人材育成の醍醐味でしょう。「自分が想定していた以上に、化けたな」が、人材育成側への最高の誉め言葉ではないでしょうか。
武石:若手が一歩踏み出して、上司や人事が想定する以上に成長する様子を思い描くとワクワクしますね。成長する若手もいれば、逆に、とまどう人や壁にぶつかる人も出てきますよね。
玄田:そのとおりです。仕事で壁にぶつかったときは、無理に乗り越えようとしなくてもいいということを思い出していただきたいです。実際の例を1つ紹介しましょう。ある会社で、若い女性が重要なポジションに抜擢されました。しかし、彼女はその役割を十分に果たすことができず、上司に退職を申し出る寸前までいったそうです。最後に、休憩スペースで落ち着いてから上司に「辞めます」と言いに行こうと思って休憩スペースに入ったら、そこに1人の先輩がいました。その人はそれほど関係の近い人ではなかったそうですが、思わず「仕事がうまくいかなくて……」と本音を漏らしたら、「みんなそんなものだから、あまり気にしなくていいよ」と言ってくれたのだそうです。その一言が当時の彼女に刺さったようで、彼女は退職を思いとどまりました。
武石:たった一言でそんなに変わるものなんですね。
玄田:多くの若手社員が、このような偶然の出会いや対話を重ねるなかで、ピンチを乗り切ったり、何とか前に進んだりします。そのうち、何かの拍子に化けるものなのです。
また、そのような偶然を引き起こす鍵の1つは、社内外のいろいろな人と関わり、そのなかで多くの人と出会うことです。交流での何気ない一言が、彼らの心を動かしたり、発想の転換を引き起こしたりして、成長のきっかけになるのです。ですから、上司は意識的に若手社員を社内外の多くの人たちに引き合わせてみるとよいかもしれません。
武石:さいごに、育成に取り組む上司や育成担当者の方へ、メッセージをいただければ幸いです。
玄田:大事だと思うことが「縁助」です。縁助とは、たまたま何かの縁でつながった人たちが、その場でお互いに助け合うことです。会社組織も縁助ででき上がっています。上司と部下も、何かの巡り合わせで同じ会社で働くことになったのだから、助け合おうじゃないか、育ててみようじゃないか、という捉え方をしてみると、気が楽になるかもしれません。

育成に強い責任感を持つのもいいですが、育成側がつらくなってしまうこともあるでしょう。私は、気楽さとつながりが同居しているような緩やかな状態が、育成にもよい影響をもたらすのではないかと思います。
若手社員向けの研修については、若手社員研修特集ページをご覧ください
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)