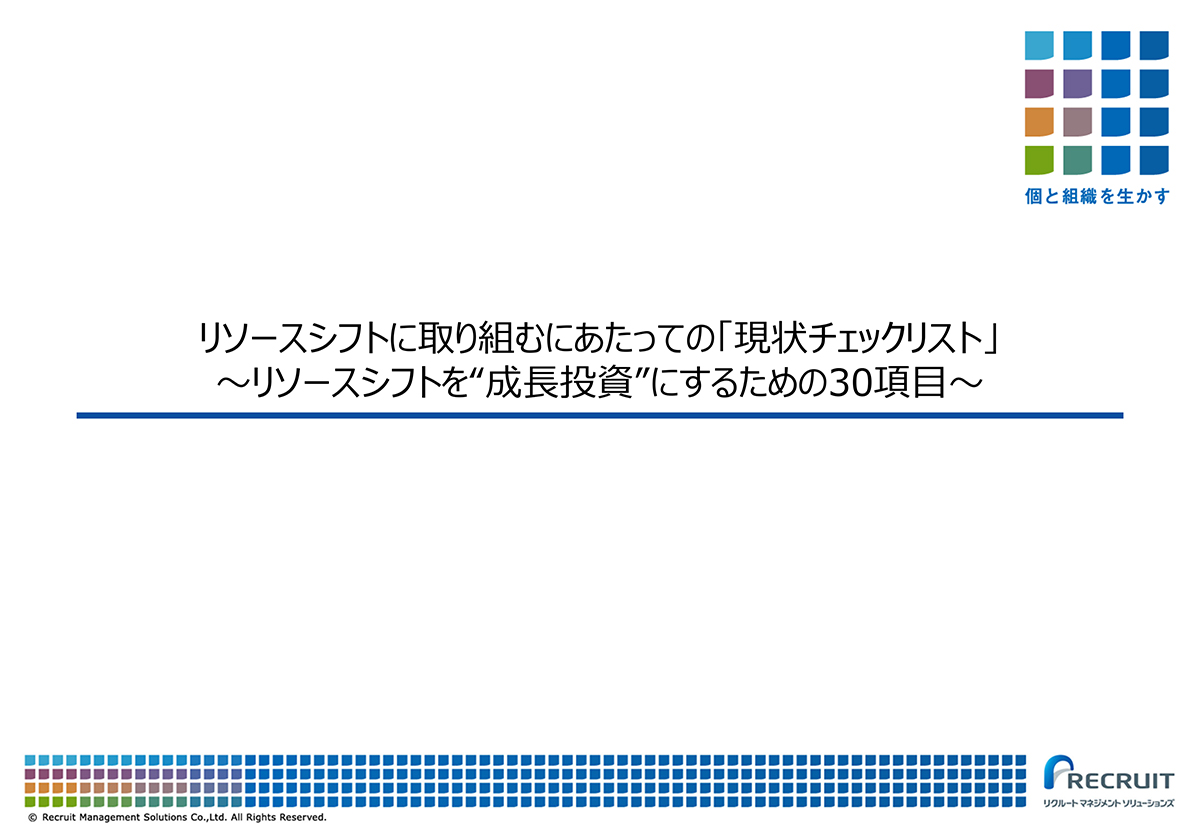連載・コラム
これからの組織のあり方を考える 第1回
なぜ組織に「個の自律」が必要なのか?
- 公開日:2022/03/18
- 更新日:2025/04/15
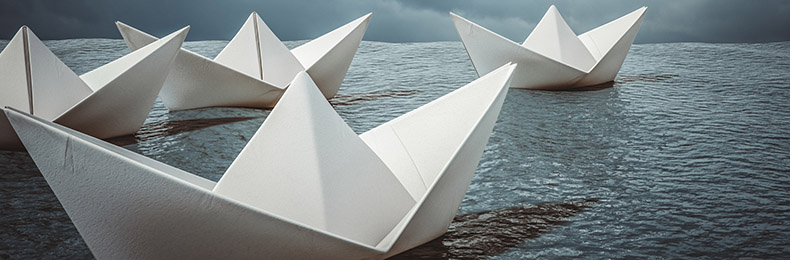
世界でも日本でも、社会の大きなパラダイムシフトが起きています。では、その環境変化のなかで、組織はこれから、どのように変わっていけばよいのでしょうか。今後数回にわたって、「これからの組織のあり方」について連載していきます。第1回となる本記事では弊社研究員の桑原が中心となり、弊社若手社員たちと共に未来を語り合う「これからの組織のあり方を考える」対談をお送りします。
- これからの組織のあり方を考える 第3回
- 「何をしたいのか」「なぜしたいのか」をメンバー自身が考え、発信し合う職場づくりが大切だ
- これからの組織のあり方を考える 第2回
- マネジャーは万能主義を捨てて「自分なりのマネジメントのあり方」を決めた方が楽しい
- これからの組織のあり方を考える 第1回
- なぜ組織に「個の自律」が必要なのか?
- 目次
- 個の尊重・自律へと向かう変化は早く浸透するのではないか
- 個の尊重や Well-being がもたらす効果が注目されている
- 自己決定の尊重が大切なのではないか
- 不純物を許容する自由がなければイノベーションは生まれない
個の尊重・自律へと向かう変化は早く浸透するのではないか
対談メンバー
● 桑原 正義(HRD統括部 HRDサービス開発部 主任研究員)
● 後藤 麻佑(HRD統括部 HRDサービス開発部 企画スタッフ)
● 奥崎 由貴奈(営業統括部営業2部 ソリューションプランナー)
● 一杉 元嗣(営業統括部営業2部 ソリューションプランナー)
桑原:今日の話の大前提として、社会の大きな環境変化・パラダイムシフトに触れておきます(図表1)。ごく簡単にいえば、これまでのビジネス社会は組織中心の世界であり、組織のために個の意思や価値観を抑えるのは仕方ないというものでした。しかしこれからは、個の尊重・自律と組織目的の実現の両立を目指す世界に進むと思われ、現在は、この変化の真っ只中にあるわけですが、果たして日本の組織のなかでは、個の尊重・自律はどこまで進むのでしょうか。これが皆さんと最初に話し合いたい論点です。なぜなら、特に日本社会は組織の力が強いからです。本当に日本の組織は個を尊重し、自律を促すようになるでしょうか。
<図表1>社会レベルで進むパラダイムシフト
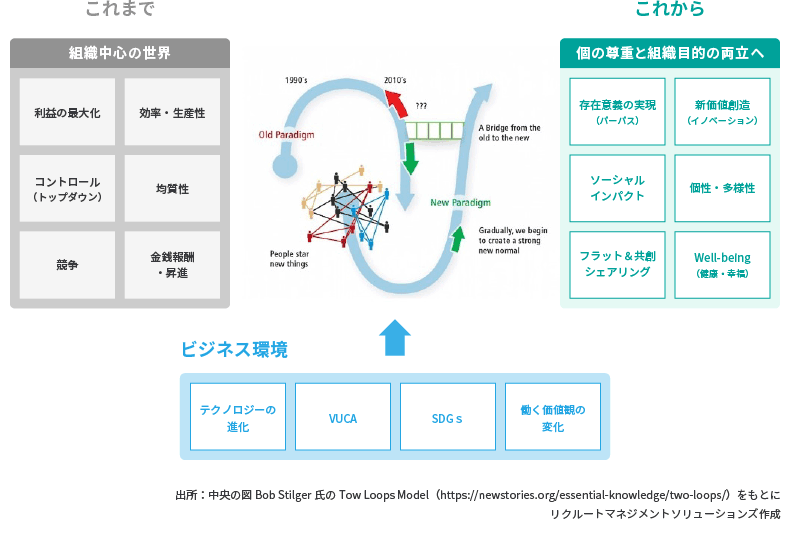
一杉:私の感覚では、日本企業はこの10年である程度は確実に変わりました。10年前、私は新入社員のときに研修で叱られましたが、今やそのタイプの研修はかなり少なくなったと感じます。少なくとも、新人をそういうふうに抑えつけてはダメ、という考えの企業が一般的になりました。
奥崎:私は新卒で入ったのが外資系企業だったので、ああしろこうしろとうるさく言われることはありませんでしたが、組織都合の異動はありました。ところが最近は、企業が個の尊重と自律を大事にし始めていて、組織都合の異動を減らす企業が多くなりましたよね。この点でも日本企業は変わってきています。
桑原:この1、2年でさらに進んできている印象があります。日本を代表する企業の1つトヨタ自動車のミッションは、「わたしたちは、幸せを量産する」と再定義されました。企業の目的に“幸せ”という概念が入るのは、とても大きな分岐点だと感じます。Well-being経営の推進を目指して、日本経済新聞社などが創設した「日本版Well-being Initiative」にも、多くの企業が参画しています。こうした動きを見ると、個の尊重や自律を通じて企業の目的や成果を実現していく経営モデルは、思った以上に早く浸透するのではないかという気がします。
一杉:私の担当するお客様でも、もはや「自律」を打ち出す企業がほとんどです。個の自律を尊重しないと、働く個人から選ばれなくなってきていると思います。
個の尊重や Well-being がもたらす効果が注目されている
後藤:確かに、個を大事にする流れが生まれています。一人ひとりを大切にしたいという会社の意識の変化も感じます。一方で、私は「自律」がバズワード化しているように感じることもあります。自律は、本当に良いことばかりなのでしょうか。極端ですが、企業側が求める人物像に照らしてポストオフを進めることが目的のケースもあるように感じます。
桑原:そう、さまざまな背景や目的がありますよね。今、企業が個の尊重や自律を重視する目的として、「新たな価値の創造」と「エンゲージメント(による採用・定着)」を促進する効果があるとみています。ビジネス環境として「新たな価値の創造」が重要になっており、そのためにも、求める人材を惹きつける、エンゲージメントが高まる魅力的な組織づくりが重要テーマになっています。
そのなかで、従業員の幸福度やWell-beingが高まることで、生産性、創造性、エンゲージメントに効果があることが近年の研究で明らかになってきました。こうした点に注目し、自社の経営やマネジメントに取り入れる動きが加速しているのだと思います。
ただ一方で、従業員の方が、自律してほしいと言われたときに「怖い」と感じる人もいるのではないか、という気がしますね。その辺はどう思いますか?
後藤:自律とは生き方を自分で律することであり、「自分のあり方」を考えることだと捉えています。とすると、従業員は「自律してほしい」というメッセージを受け、「今までそんなことは考えてこなかった」と不安になるところがあると思います。
一杉:つまり、自律とは「個として強くなること」なのですよね。私の場合、前職でお世話になったメンターが、「実力をつけたら会社を出ていっていいよ」とすぐに言ってくれたので、若いときから自律心が根づきましたが、そうした環境は個人差がかなり大きいように思います。
自己決定の尊重が大切なのではないか
桑原:そこで考えたいのですが、自律はすべての人に必要なことだと思いますか? また、全従業員に自律を求めることが、果たして企業に好循環をもたらすのでしょうか?
後藤:一人ひとりのWell-beingを高めたら、その総和としての社会が良くなるという流れには違和感がありません。でも、企業のなかで一人ひとりのWell-beingはどう高められるのでしょうか?
奥崎:「言われたことをやりたい」という選択をするのも自律なのでしょうか?
一杉:Well-beingを高めたら仕事の成果が高まるというのは、自分の実感としても間違いないことだろうと思います。ただ、自律するとWell-beingが高まる、というつながりがイメージできません。
桑原:「自律」という言葉は、何か強さや厳しさをも連想させ、必ずしもポジティブに受け取る人ばかりではないですよね。自律の本質は自分で決めること、「自己決定」にあると思います。仕事であれ、普段の生活であれ、自分で決められるというのは個の尊重の原点であり、自尊心や自己信頼、ひいてはWell-beingにつながる重要な要素だと思います。
一杉:デンマークのような自律が進んでいる国では、ルーティンワークのような仕事でも意義を見出すことで楽しく取り組んでいるという話も聞きます。
桑原:そうですよね。自分で決めて行ったことが、意味のあることにつながっているとか、誰かの役に立っていると感じられたら、なおさら嬉しいですよね。人間の基本的な心理ニーズの研究(Deci & Ryan1985)でも、自律性(自己決定)だけでは十分ではなく、関係性(人と良好なつながりを持っていること)と有能性(決めた行動を実行する能力があること)の3つが満たされることが重要だとされています。
奥崎:「自己決定」という言葉だと、従業員の拒否感は一気に弱まりそうですね。
不純物を許容する自由がなければイノベーションは生まれない
桑原:もう1つ考えたいのが、組織はどこまで自己決定を重視すべきかという点です。自己決定を広く尊重すれば、自分のやりたいことのために離職する人が出てくる場合もあります。しかし、それは組織にとっては困ることですよね。ですから、これまでの日本の組織には、本当の意味での自己決定の尊重は難しかった面があります。ところが最近では、「個の自律を尊重した結果、従業員が自社を辞めても仕方がない」という考え方の企業も出てきています(参考:キャリア自律を促進する人事改革 カゴメ)。これは今までにない個と組織の関係ですよね。これらの考えの背景には、たとえ離職の可能性が出るとしても、それ以上に、個の尊重や自律を進めることのプラス面が大きいという判断があります。このことを理解した企業が、個の尊重やWell-beingを大切にした経営を推し進め、Z世代をはじめ、新たな価値観を持ち始めた従業員の支持を得るようになってきています。
もちろん、自己決定の結果、自組織や自社に意味を見出し活躍してもらえるような組織を目指していきたいですよね。ここで重要になるのが「パーパス」です。「何のために私たちは存在するのか」という企業の存在意義であり、社会への貢献をも含めてこの再定義に取り組む企業が増えています。企業や組織のパーパスを示していくことで、従業員は今ここで働く意味を感じやすくなり、自身とパーパスのつながりも生まれやすくなります。パーパスと自律は両輪で考えた方がよいでしょう。
奥崎:これからは特に、会社・組織のパーパスが大事になってくると思います。組織でも個人でも存在意義を考える人が増えていくと思います。先に組織がパーパスをいくつも打ち出すと、個人もパーパスを考えやすくなるのではないでしょうか。
後藤:私もそう思います。個人がパーパスを明確にしていくために、組織と個人のパーパスを交流させる仕組作りをすることがポイントになりそうですね。パーパスを交流させる仕組み作りというと壮大に聞こえますが、組織のパーパスをめぐって各人の想いを対話で伝えていくなかで、個人のパーパスについても考えていく。その活動を通じて組織だけでなく個の存在意義が明確になっていく、という成功体験を創出することが大事だと思います。
桑原:ところで個の尊重を考えるとき、リクルートマネジメントソリューションズが創業時から大切にしてきた「個をあるがままに生かす」という理念が頭に浮かびます。創業者の大沢武志氏は、著書『心理学的経営―個をあるがままに生かす』(PHP研究所)において、経営における個の尊重について触れています。
個の尊重はきれいごとではなく、組織にとってはネガティブなものも生まれ、それは避けては通れないのだと思います。しかし表も裏もあるのが人間であり、それをあるがままに受け入れ生かす姿勢を持つことで、本来持っている個性のエネルギーが解放され、パフォーマンスやイノベーションにつながり、組織への信頼度やエンゲージメントが上がっていく、そういう理念だと捉えています。こういう個と組織のあり方はこれまで特殊だったかもしれませんが、ビジネス環境と働く人々の価値観の大きな変化によって、今まさに求められている、そう感じています。
一杉:今、日本の教育も自律を重視する方向に大きく変わっていっています。近い将来には、個の自律を当たり前だと考える若者たちが社会に出てくるでしょう。個を尊重せず、自律も求めない会社には、若手社員が定着しなくなる可能性があります。個の尊重は待ったなしだと思います。
桑原:最後に、個の尊重と組織目的の両立を目指すマネジメントの実現に向けて、具体的なテーマをまとめて挙げておきます(図表2)。今日は組織のパーパス浸透[1]や本人の個性・自律発揮[4]の話をしましたが、それに加えて、マネジャーがメンバーの自律を促す「自律推進のマネジメント[2]」や、「個が生き自律が進む職場づくり[3]」というテーマも含め、同時に進めていくことが効果を上げるポイントだと思います。
自律推進のマネジメントと本人の個性・自律発揮については、次回以降のコラムで詳しくお伝えしていきます。
<図表2>自律を進めていくためのテーマ
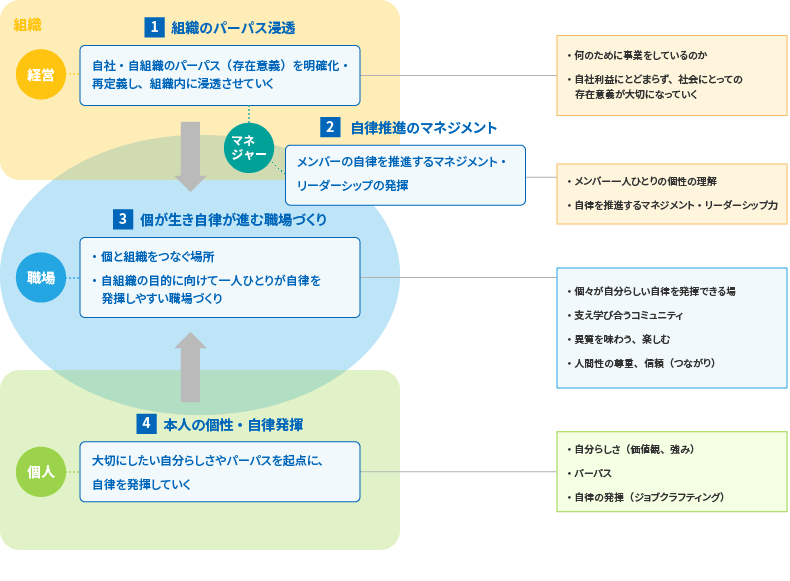
【text:米川 青馬】
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
- これからの組織のあり方を考える 第3回
- 「何をしたいのか」「なぜしたいのか」をメンバー自身が考え、発信し合う職場づくりが大切だ
- これからの組織のあり方を考える 第2回
- マネジャーは万能主義を捨てて「自分なりのマネジメントのあり方」を決めた方が楽しい
- これからの組織のあり方を考える 第1回
- なぜ組織に「個の自律」が必要なのか?
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)