課題解決のポイント
経営者・人事・部門が、多様な目で選抜してリスクを減らす
選抜は多角的な視点で
次世代リーダーの候補者を決める際、最も多いのが、「各部門による指名・推薦」に基づく人選です。部門推薦の場合、現場での実態や事実を踏まえて選抜できることは大きなメリットですが、一方で将来性(ポテンシャル)にスポットが当たりにくいことがデメリットとなります。また、現在の業務から離したくないとの理由でエース人材の選抜を現場がためらうケースもあり、最適な人選が行われないリスクもあります。
そこで、現場部門だけでなく、「経営トップ」や「人事部門」も人選に関与することをお薦めします。経営者独自の視点、データを踏まえた人事的視点を加えることで、優秀人材が選抜から漏れるリスクを減らすと同時に、人選に対する納得度を高めることができます。
徐々に選抜を進めていく
弊社調査によると、「課長層」までに最初の選抜を行う企業が多数です。また、より早いタイミングで選抜を行って育成をスタートさせている企業の方が、全体的には自社の育成施策に満足していることも明らかになっています。早くから選抜を開始することで、最初は候補者を多めに選んでプールしておき、その後に研修や異動によるチャレンジの様子を踏まえて徐々に候補者を絞り込めることが、満足度が高い理由だと考えられます。
選抜の理由と期待を伝える
選抜した社員には、「なぜ候補者に選抜したのか」「会社がどのような期待をもっているのか」を丁寧に伝えることが、候補者のモチベーションを高める上で重要です。一人ひとり対面で伝えると、その効果はより高まります。その際は、一方的に会社からの期待を伝えるだけでなく、候補者のとまどいや不安、疑問などを払拭する機会とすることも大切です。
<図表> 選抜の主体者とメリット・デメリット
選抜の主体者 |
メリット |
デメリット |
|---|---|---|
各部門による指名・推薦 72.8% |
|
|
人事部門による指名・推薦 54.8% |
|
|
経営トップによる指名・推薦 44.4% |
|
|
自薦(≒手上げ) 6.2% |
|
|
RMS Research「昇進昇格実態調査2009」
(早期選抜・育成施策対象者を「誰がどのように選ぶか」への回答率)
施策事例
事例1医薬品関連企業
経営人材要件の言語化・活用による人材プール管理
- 背景
-
- ホールディングス制への移行に伴い、分社化による人材の個別最適化が懸念されていた
- 組織規模の急激な拡大により、各部門の人材把握の難度が増していた
- 事業拡大のスピードをより一層上げるため、ハイポテンシャル人材の早期登用・育成が急務となっていた
- 施策
-
- グループ共通の経営人材要件を、全経営層参加の合宿を行って整理し、言語化した
- 要件に照らした360°サーベイによるアセスメントを年に一度実施し、「短期」と「中長期」の時間軸の異なる人材プールを設定した上で、人材開発委員会で管理する体制を整えた
- 経営層と人事による候補者の評価を踏まえ、人材プールの入れ替えや候補者本人への能力開発を促進する仕組みを構築した
- 人材開発委員会によるタレントマネジメント(人材の評価・選抜・育成・配置)が効率的に行われるようになった
- 人材開発委員会や研修の場面だけでなく、日常のマネジメントの場面でも人材要件を意識したコミュニケーションや関わりがなされるようになった
関連するダウンロード資料
Download
関連するサービス
Service
おすすめの
無料オンラインセミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

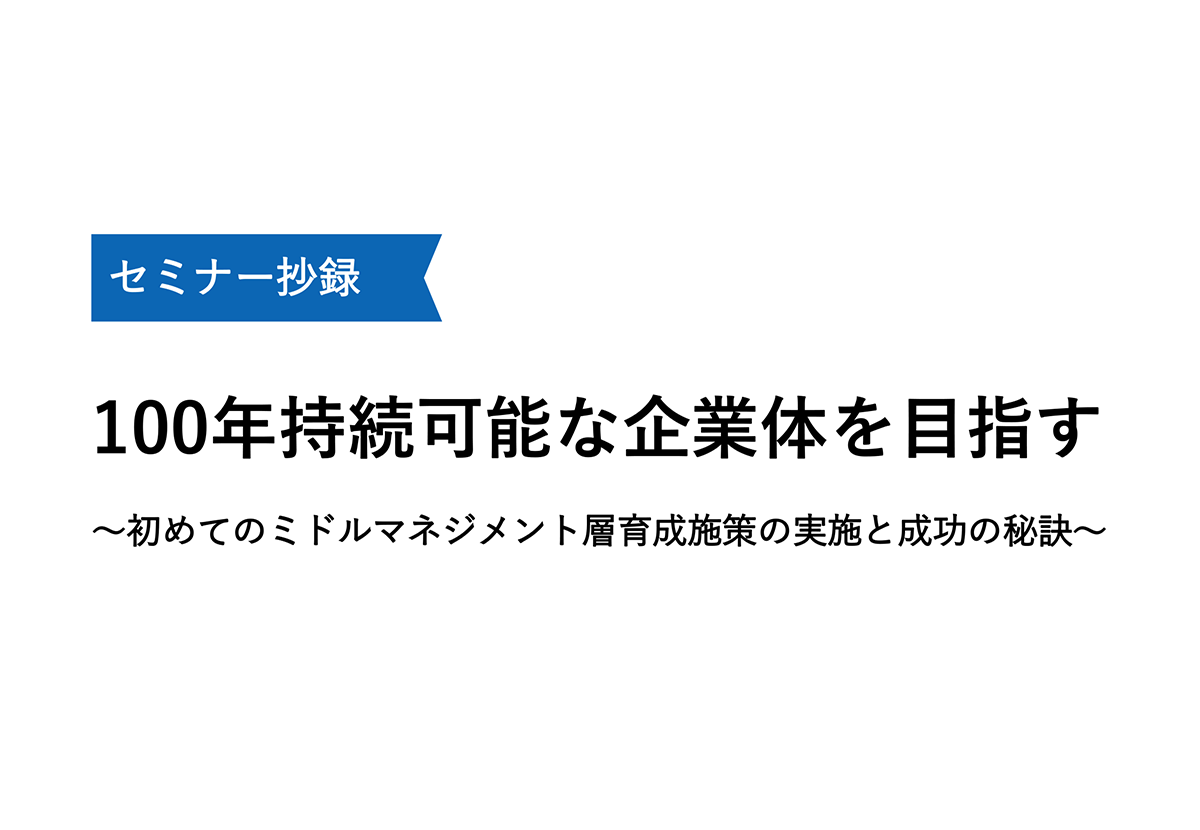
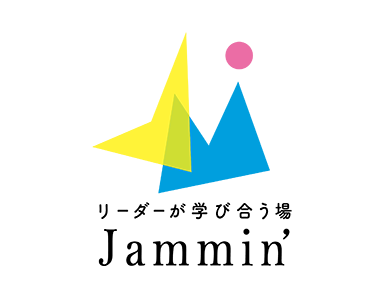












 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての