用語集
管理職の目標設定のコツとは? 考え方や手順、フレームワークを紹介
- 公開日:2023/11/02
- 更新日:2025/06/25
目標設定は、管理職にとってとても大切な業務です。目標が不明確だと部下のモチベーションが上がらず、細かく指示を出さなければならなくなります。どのようにして目標設定を行えばよいのか、考え方や手順について詳しく解説します。
◆メルマガ登録者様限定資料を公開中
中間管理職(マネジャー)に関する意識調査【前編】~オーバーワークについての傾向と考察~
◆無料動画セミナー
部長職の育成施策を考える なぜ、部長職にコーチングが有効なのか
◆研修サービス
評価者研修・目標設定研修
目標設定とは?
目標設定とは、自分や企業が望むゴール(目的)にたどり着くために、具体的なプランを決めることです。「どんなことを」「いつまでに」「どのようにやるのか」を段階的に設定することで、目的に至るためのステップを明確にする効果があります。
目標と目的の違いとは
目標とよく似た言葉として「目的」がありますが、両者の意味はまったく異なります。
まず目的とは、文字通り「目でねらう的」であり、自分または複数名で到達したいゴールを意味します。企業なら「ゆくゆくはこんな企業にしていきたい」といった経営ビジョン、個人なら「こんな人になりたい」といった将来的な理想像など、最終的にたどり着きたい目的地のイメージで設定されることが多いです。
一方、目標とは「標」という言葉のとおり、目指すゴールから外れないように設定する目印を意味します。目的地にたどり着くための、ナビの機能を果たすものと考えるとよいでしょう。
例えばビジネスにおいて、「健康食でお客様を幸せにする」という目的(ゴール)をつくったとします。そのゴールに至るために立てる指針が、目標です。具体例を挙げると、「3年後までに健康食事業のトップシェアを獲得する」「健康経営のサポートサービスを立ち上げる」といった施策が目標になります。
このように、目標を立てることで「次に何をすればいいか」が分かりやすくなるため、仕事においても積極的に目標設定を行うことが大切といえます。
目標設定を行うメリット
目標設定を行うメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
目標達成に向けて行うことが明確になる
前述したとおり、目標設定とは「目的を達成するための指針」です。目標設定によって、自分が叶えたい事柄のために今やるべきことが明確になり、生産性の向上が期待できます。
また、目標設定はチームの統率にも役立ちます。チーム全体の目標を持つことで「皆で今やるべきこと」が分かるようになり、仕事の優先順位も決めやすくなるところがメリットです。同じ目標を持つことでチームに一体感が生まれ、仲間意識が芽生えやすくなるところも利点といえるでしょう。
自信や成長につながる
2つ目のメリットは、目標を達成することで自信や成長につながる点です。
目標とは一般的に努力を要する事柄であり、時には達成に際して困難が伴います。状況に応じて新しいスキルを身につける必要もあることから、個々の成長にもつながりやすいところがメリットです。
さらに、目標を達成したときの充足感から、自信がつくことも期待できます。自信はモチベーションにつながり、新たな目標に取り組むきっかけにもなるでしょう。
進捗を確認しやすくなる
3つ目のメリットは、現状の進捗を確認できることです。
目標とは、目的の達成に向けて段階的に踏むべきチェックポイントと言い換えることができます。目標を設定しておくことで進捗を見える化し、作業の大幅な遅れなどのトラブルを避けることが可能です。
また、設定した目標の進捗が遅れている場合は、手が空いている人にサポートを頼んだり、業務の進め方を見直したりといった対策によって軌道修正を行うこともできます。複数名で作業をする場合は、目標設定を通して「どのメンバーが」「何をするのか」を明確に分担することができ、負担の分散にもつながります。「この作業を今、誰がやっているのか」も自然と共有されるため、コミュニケーションコストの削減にもつながる点がメリットです。
管理職が目標設定を行う際のコツ

1. 全社や自部署の方針への理解を深める
まず組織の目標設定を行うにあたり、全社や自部署の方針と実情への理解を深めることが重要になります。それらを無視して目標設定をしてしまうと、上位方針と合わない目標になってしまう可能性が生じます。
そのため、まず会社や自部署がどのような方針を持ち、現在どのような状況にあるのかを理解することが重要です。方針をしっかり理解することで実現不可能な目標を立てたり、目標の実現可能性が部下によってばらついたりすることを防げるでしょう。一例としては、チーム内で会社の方針について確認し合う会議を設定する方法が効果的です。
また通年の目標を立ててしまうと時とともに気持ちがゆるんでしまうので、月単位やQ(クオーター)単位で達成する目標を設定することも重要になります。
2. 組織の課題や理想を明らかにする
組織や管理職者個人、さらに部下の目標設定においては、具体的かつ明確な目標を定めるため、会社の方針を達成するにあたって障害となる部署やチームの課題、改善点を特定する必要があります。課題を掘り下げ理想を明らかにすることで、目標設定の焦点を明確にでき、チームとして目指すべき方向性を明確にすることができます。
会社の上位方針を自チームの具体策にまで落とし込むことで、実現可能性のある最適な目標設定ができます。なお、管理職にとっての目標設定は、自身が管理するチームの業務管理や人材育成のためのものであることを忘れてはなりません。
3. 何を、どのように、いつまでに達成するのか明確にする
目標設定においては、具体的かつ測定可能なものを設定すると効果的です。
ただ目標を立てるだけでなく、目標達成のためのアクションプランや手段を計画し、必要なリソースを確保することも大切です。このとき、達成に向けて実際に部下が行動を起こしたか否かがわかるようにすることも重要です。ただし、目標達成の可否のみを重視しすぎると部下のモチベーション低下につながるため、注意が必要です。
目標を設定し、実現のためのアクションプランを立てたら、目標達成の期限を設定します。次に、どのようにして進捗管理するか、その方法を考えます。お薦めなのは、短期的な中間目標を設定することです。月単位やQ(クオーター)単位の目標も設定し、最終目標の達成に向かって徐々に近づいていることがわかるようにするのもよいでしょう。
4. 部下がモチベーションを維持できるよう工夫をする
目標設定のコツとしては、「部下の立場から見て、やる気が出るようなものにすること」が大切です。例えば、部下の立場から見て「無理なく達成できる小さい目標」を与えて自信をつけさせたり、達成具合によって給料にインセンティブを付与したりなどのケースが挙げられます。
過度に難しい目標や、達成するやりがいが薄い目標は、部下にとって億劫なだけの「形だけの目標」になりかねません。部下を含めた社員皆が1つの目標に向かってモチベーションを維持できるよう、「なぜやるのか」「その人が達成できることなのか」「達成するとどうなるか」の3点を踏まえて目標を立てるとよいでしょう。
目標や評価を軸にマネジメントの質を高め、個人の成長と組織の成果創出を実現するための、マネジメント研修
評価者研修・目標設定研修
管理職が目標設定をするときの手順

管理職が組織や部下、自身の目標を設定する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。ここでは、そうしたポイントを押さえながらどのように目標を設定していけばよいか、その手順を詳しく解説します。
1. 目標の種類を理解する
まずは、ひと言で目標といっても3つに分けられることを理解することが必要です。その3つとは、意義目標、成果目標、行動目標です。
意義目標とは、抽象的ではあるものの、達成することで現状を打破し、ブレイクスルーを起こせるような目標をいいます。成果目標は、具体的な数値などで成果が目に見える目標です。達成度合いを可視化しやすいというメリットがあるものの、一方で数字を追うことだけにとらわれがちになるというデメリットがあります。
具体的な行動に関する目標が、行動目標です。行動目標は何をすれば良いのか明確に示されているため、誰にでも取り組みやすいものの、行動だけしても成果につながるとは限りません。これら3種の目標は、どれが良くてどれが良くない、というものではありません。会社やチームの現状に合わせて使い分けることが大切です。
2. 達成や実行可能性がある目標にする
目標には、現実的なリソースや制約条件を考慮する必要があります。いくら壮大な目標を掲げても、それが実現不可能であれば何の意味もありません。そのため、目標を設定したら、その目標はどのようにすれば達成可能なのか、具体策にまで落とし込んでいきましょう。
その際、「何を(目標項目)」「いつまでにどこまで(達成基準項目)」「どのように(計画)」するのかを決めることが大切です。
目標だけがあって計画がないのは、目標を設定していないのと同じことです。それは部下のモチベーション低下につながってしまうでしょう。管理職における目標設定は、部下の成長を促す機会でもあることを忘れてはなりません。
3. 具体的な数値を用いる
「何を」「どのように」するのか、を明確にすることも大切ですが、同じくらい重要なのは、「いつまでにどこまで」するのか、を客観的に判断できるレベルで明確にすることです。
数値目標を設定することは、目標に対する行動を評価する際の明確な基準になります。進捗や成果が測定可能になると、計画の具体化にもつながります。
なぜなら、明確な数値目標があれば、部下はその目標の達成に向けた具体的な行動計画を立てられるからです。例えば、設定する数値目標としては、売上や人件費などが挙げられます。それらの達成に向けて、営業強化やコスト削減といった具体策を考えることができます。
4. 目標を共有する
社内やチームの方針や設定した目標は、メンバー全員が理解できるように共有しましょう。共有することで、目標へのコミットメントや協力体制が形成されるほか、達成への意欲が上がる、目標達成のための情報が増える、などのメリットがあります。例えば、定例会議の際などに目標について話し合い、コミュニケーションを通して認識のズレをなくすとよいでしょう。
また、目標をうまく共有するために、イラストや図表などの視覚情報を有効活用したり、他社や他部署の事例を共有したりするのもよいでしょう。
5. 目標設定後は定期的に見直しを行う
目標管理においては、上司が進捗状況の確認やフィードバックを行い、定期的に評価し見直すことが大切です。
設定した目標とその施策に対する検証と改善が行われないままでいると、施策を実行する過程で浮かび上がった問題点が放置されてしまいます。そうすると施策の効果が低下してしまうばかりか、会社の方向性とズレる可能性も生じます。
そのようなことにならないよう、必要に応じて修正や調整を行いながらPDCAサイクル(※)を回していくことが大切です。
※PDCAサイクルとは、「Plan(計画)、Do(計画)、Check(評価)、Action(改善)」というプロセスを繰り返し行い、業務改善や効率化をはかる手法の1つです。
目標設定で活用できるフレームワーク5選
ここからは、目標を設定する際に有用なフレームワークを5つ紹介します。
1. SMART
SMARTは目標設定のための代表的なフレームワークです。具体的な目標を設定し、それらを達成するためのガイドラインを提供してくれます。SMARTとは、効果的な目標設定に必要な要素である、以下5つの要素の頭文字をとったものです。
Sは「Specific(具体的)」。目標は明確かつ具体的でなければなりません。何を達成したいのか、どのような結果を求めているのかを明確に定義します。
Mは「Measurable(測定可能)」を意味します。目標の進捗や達成度を測定できるようにすることが大事です。具体的な数値や指標を設定し、進捗をトラッキングできるようにします。
Aは「Achievable(達成可能)」です。現実的に考えたうえで達成可能な水準の目標にするのがポイントになります。
Rは「Related(上位目標と関連する)」です。目標が組織の上位目標の達成に貢献するように設定します。
Tは「Timely(明確な期限)」です。目標には期限が設定されていなければなりません。目標達成までの時間枠を設けましょう。
2. ベーシック法
目標設定におけるベーシック法は、効果的な目標達成のために使用される基本的なアプローチや原則です。このフレームワークでは、目標項目、達成基準、期限設定、達成計画という4つのステップに合わせて目標を設定していきます。
目標項目のステップでは、「目標の強化」「改善や解消」「維持や継続」「開発」の4つの項目に分けて整理します。目標を細かくこの4つに振り分けても、どれかに絞ってもかまいません。
達成基準では、数値化や定性的な状態を具体的に設定します。どのような状態だと達成したといえるのか、その基準を明確にするステップです。達成基準には、数値で表す定量的な基準と状態を表す定性的な基準、スケジュールによる基準の3種類があります。
目標項目と達成基準が決まったら、その目標をいつまでに達成するのか、期限を設定します。これら3つを設定したら最後に、どのようにして目標を達成するのか、達成計画で、具体的に行動するための計画を立てます。
3. 三点セット法
三点セット法は、ベーシック法を深く追求した目標設定フレームワークです。テーマ、達成レベル、達成手段の3点で構成されており、まずは構成内容であるテーマを決めます。その際、よく使われるのは安正早楽(あんせいそうらく)(※)や自己否定、プロセスチェックです。
※安正早楽とは、「より安く、より正しく、より早く、より楽に」の頭文字をとった言葉で、業務はこのように行われるべきであることを示したもの。
達成すべきテーマを決めたら、次はそのテーマをどのレベルまで達成するかを考えます。なるべく数値化し、達成レベルを測定できるようにします。最後に、具体的な行動計画である達成手段を決めます。この達成手段は、ベーシック法における達成計画に相当します。今までのやり方を少し変えることはできるか、今だからこそできることはあるかを考えるとよいでしょう。
4. KPIツリー
KPIツリーとは、組織の最終目標(KGI)を達成するために必要な要素(KPI)をツリー状にし、見える化したものです。
例えば「売上高をアップさせたい」という組織の最終目標(KGI)を達成するためには、「店舗数を増やす」「問い合わせ数を増やす」「受注件数を増やす」「顧客1人あたりの購入単価を上げる」などの方法があります。最終目標に至るためのこういったアプローチをKPI(重要業績評価指標)といい、KGIを頂点としてKPIを樹形図状に並べたものがKPIツリーです。目標を達成するために必要な要素の洗い出しに役立つフレームワークといえます。
5. OKR
OKR(Objectives and Key Results)は、目標設定の手法のなかでも「あえて難度の高い目標を立てる」ことを是としているフレームワークです。チームにとって挑戦しがいのあるシンプルな目標(Objectives)を立て、個々にやや難しい課題(Key Results)を与えることで、企業と個人の目標をリンクさせながらスピーディに目標達成を目指せるところが特徴といえます。
また、OKRで個々に与えられるKey Resultsは、一人ひとりにとって最大限努力しても達成できるかどうか分からない難易度に設定されることから、報酬制度とは結びつけない点も特徴です。企業全体で野心的な課題を設定しやすく、個々の成長を促しやすい目標設定の手法といえるでしょう。
管理職の具体的な目標設定例

管理職の方が自身の目標を設定する際、どのように設定すればいいのでしょうか。本項では役職別に具体的な設定例を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
管理職全般にあてはまる目標設定例
まず、どのような役職の人であっても重要なポイントが3つあります。それは、目標が達成可能であること、目標が具体的であること、目標に納得感があることです。多くの場合、実際の業務は部下が担当することになります。そのため、これら3つを押さえていなければ、期待した効果が得られない可能性があります。
おすすめの方法は、チーム全体の目標を定量的に設定することです。売上や人件費といった会社の利益に直結するような目標はもちろん、定性的に設定しがちな目標でも可能な限り定量的に設定します。具体的である方が、何をするべきかが明確になり、達成したかどうかについて共通認識が持てるため、部下の間にも納得感が生まれやすいでしょう。
これらのポイントを押さえた目標設定の例としては、次のようなものが挙げられます。
「業務の効率化をはかることで、〇〇までに残業時間を月あたり〇〇時間削減する」
「商品〇〇を〇〇までに〇〇個販売する」
部長の目標設定例
部長の場合、複数のチームやグループを管理しなければなりません。そのため、部長の目標設定で重要なポイントは、管轄するそれぞれのチームごとの適切な生産性を把握することです。そのうえで、それらのチームの生産性をマネジメントする必要があります。部下のマネジメントに加え、会社の利益を追求する必要があることを忘れてはなりません。
部長の目標設定の例として、次のようなものがあります。
「課長との定例的なミーティングを実施し、部の売上目標達成率を〇〇%にする」
「今年度の各チームにおける離職率と休職率をそれぞれ〇〇%未満に抑える」
課長の目標設定例
課長は、実務上の責任者であることが多いため、どうしてもチームの数値目標をいかに達成するかに意識がいきがちです。しかし、課長には、同時に部下のマネジメントや育成という仕事があることを忘れてはなりません。
部下の育成をしながら、組織の目標を達成するにはどうすれば良いのか、を記載する必要があります。
具体的な目標設定例としては、次のようなものがあります。
「〇〇名以上のプロジェクトリーダー育成のために月1回の研修会を行う」
「〇〇名の部下にプロジェクトリーダーとしての経験を積ませることで、チームの売上高を前年比〇〇%以上にする」
まとめ
管理職における目標設定は、ただチームの数値目標を掲げるだけでなく、部下の育成につながるものでなければなりません。また、管理職の場合、役職ごとに適切な目標設定は異なります。部署やチームとして優れたパフォーマンスを発揮できるように、先の例を参考にするなどしてふさわしい目標を考えましょう。
なお昨今の管理職は、事業変革への挑戦と、現場でのプレイングの両立が求められる傾向にあります。マネジメントの難しさがより一層高まる現代において、我流では適応できない場面も珍しくありません。必要に応じて社外研修なども活用し、管理職としての応用力を磨いてみてはいかがでしょうか。
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

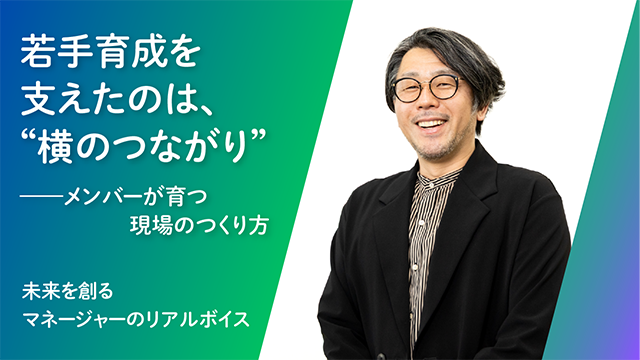
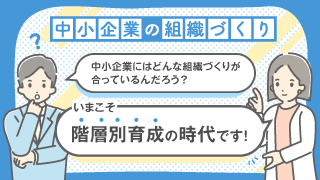















 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての