用語集
昇進とは? 昇格との違いや目的、昇進のポイント
- 公開日:2020/08/25
- 更新日:2025/06/25
昇進とは、社内における役職が上がることです。この記事では、昇進の目的から昇格との違い、昇進によるメリット・デメリット、昇進を決める際のポイントまで分かりやすく解説します。
昇進者を育成する
「部長職の育成施策を考える なぜ、部長職にコーチングが有効なのか」
昇進とは
昇進とは「一般社員から主任になる」「主任から課長になる」「課長から部長になる」など、会社での役職が上がることを指します。一般的に昇進することで、より責任の大きな仕事に携わることになり、給与が上がります。昇進にともなって、社外に向けた肩書も新しくなります。
昇進は、それぞれの会社が定めた制度や条件によって決まります。多くの企業では人事評価のほか、本人の業績や能力、勤続年数、昇進試験の結果などをもとに決定しています。役職に就任できる人数は限られているため、優秀な社員がすべて昇進できるわけではありません。
昇進・昇格の違い

職能資格制度では、職位と職能資格には一定の対応関係がありますが、「昇進=昇格」とは限りません。昇進しても資格は変わらない、あるいは昇格しても職位は変わらないということも起こり得ます。
例えば、課長職に対応する資格を7~8等級、その上位職位である部長職に対応する資格を8~9等級とした場合、課長職にある8等級の社員が部長に昇進した場合、資格は8等級のままで変わらないこともあるのです。
また、課長職にある7等級の社員が8等級に昇格した場合、この社員は部長職に就くための資格条件を満たしていますが、部長職のポストに空きがなく、部長に昇進できないということも考えられます。
昇進させる目的(理由)
会社が社員を昇進させる目的は、主に2つあります。
昇進前より大きな役割を果たしてもらうため
昇進するということは、役割が変わるということです。例えば一般社員から管理職へ昇進した場合、「個人に任された業務の成果を出す」という役割から「チームを率いて成果を出す」という役割に変化します。会社は社員に対し、それまでのステージから1つ上に進み、より大きな役割を果たすことを期待しているのです。
管理職を育成して組織運営を円滑にするため
強い組織をつくるには、人をまとめて目標達成に導く管理職が不可欠です。またトップと現場の橋渡しも、管理職の大切な役目。会社の規模が大きくなればなるほど、管理職の存在は重要となるでしょう。昇進制度を活用して管理職を育成すれば、組織の運営を円滑に行うことができます。
昇進することのメリット・デメリット
昇進と聞くと喜ばしいイメージがありますが、昇進してメリットを感じる社員もいれば、デメリットがあると捉える社員もいます。
昇進のメリット
昇進することによるメリットは、主に2点です。
裁量権を持つことができる
管理職になると裁量権を持ち、担当する業務やプロジェクトを自分の判断で進めることができます。チームに誰を入れるかといった人事の要望も出しやすくなり、仕事を進めやすくなるでしょう。やりがいがあり、うまく進めば大きな達成感を得ることができます。管理職として大きな成果を出せば、周囲から認められ、その後のキャリアにも弾みがつくでしょう。
手当が付くなど給与が増える
昇進することで、一般的に基本給が上がったり役職手当が付いたりして、給与が増えます。しかしなかには、管理職になることで残業代が出なくなる会社もあります。また会社によっては出張手当が増額されたり、出張経費を多く使えたりする場合もあります。退職金の算定に役職や等級を考慮する会社もあり、そのような会社ならば退職金も増えるでしょう。
昇進のデメリット
昇進にはデメリットもあり、最近では昇進をためらう人が増えています。企業側はデメリットを理解したうえで、社員に昇進への意欲を持ってもらえるような施策を講じることが重要です。
責任が増す
管理職になると、自分の成果だけでなく、責任者としてチームで成果を上げることを求められます。大きな責任を担うことになり、プレッシャーを感じるかもしれません。自分が経験したことがない業務について判断や意思決定を下す場面も増えるでしょう。そうした難度の高い業務や慣れない業務に対応するには、研修などを通して役職に合ったスキルを身につけることが重要です。
昇進による業務の難易度向上や、責任者など慣れない仕事に対応するスキルの向上については、以下の研修をご利用いただけます。
人間関係に悩む
管理職は、性格や能力が異なるメンバーをまとめあげなくてはいけません。メンバーと価値観が合わずに悩んだり、メンバー同士のトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるでしょう。また上司や部下との間で板挟みになったり、他部署との調整で苦労したりすることも考えられます。
昇給とは
昇給とは、年齢や勤続年数、人事評価などによる基本給の上昇を意味する言葉です。
中でも、年齢や勤続年数によって自動的に生じる昇給を自動昇給、人事評価に基づく昇給を査定昇給と呼びます。職能資格も基本給を決定する要因の1つであり、資格の上昇が昇給につながります。
なお、昇進した場合は役職手当が加算されるため、職能資格が同じで職位が異なる2人の社員がいる場合、当然給与に差が生じます。
社員の昇進を決める際のポイント
昇進を決める際、進め方によっては社員の不満を招く可能性もあります。そうした事態を防ぐため、3つのポイントを紹介します。
評価基準を定める
昇進の基準が「上司による推薦だけ」といった曖昧なものだと、社員は不公平さを感じてしまいます。誰もが納得できる人事を目指すためには、評価基準を明確にすることが重要です。人材要件や能力要件、業務実績など、そのポジションに必要な要件を具体的に定めましょう。策定した基準は、社内で公開して周知・浸透させることも大切です。
役職や等級の役割を明確にする
役割が曖昧だと、社員が何をすべきか分からず、「昇進したのに活躍できない」という事態になるかもしれません。責任の所在も曖昧になってしまいます。自社のビジョンや事業計画に基づいて、「この役職は何をしなければいけないのか」という役割を明確にしましょう。役割がはっきりすれば、必要となるスキルが見えてくるので、育成もしやすくなります。
公平な評価を行う
評価者によって評価にバラツキがあるのも、社員の不満を招く要因の1つです。公平に昇進を決めるには、評価の目的や基準を明確にしたうえで、評価者の認識を一致させておくことが重要です。また1人の上司が多くの部下を評価する場合は、主観が入りがちになります。評価者と評価対象者の、人数のバランスも考慮しましょう。
昇進・昇格それぞれの判断方法とは
社員を昇進・昇格させる際の判断はどのように行えば良いのでしょうか。ここでは、昇進・昇格それぞれの判断方法について考えてみます(昇進の判断にあたっては、昇進に必要な資格条件を満たしているとします)。
昇進の判断方法
主な判断手法としては、勤続年数、人事評価、知識テスト、論文作成、経営者や役員との面談などが挙げられます。
特に注意したいのは、管理職昇進の判断です。管理職の業務は部下のマネジメントや育成が中心となるため、これまでに培ってきた専門的なスキルを生かせるとは限りません。
また、会社経営や事業運営にも関わるため、一般社員よりも広い視野が求められます。したがって、直近の実績だけではなく、管理職としてのポテンシャルを含めて判断することが重要です。
昇格の判断方法
昇格選考のプロセスは、基本的には昇進選考のときと変わりません。昇格基準には、資格等級に定められた要件を満たした場合に上位等級に昇格させる「卒業方式」と、上位等級で求められる要件を満たした場合に現在の等級から昇格させる「入学方式」の2つがあります。
卒業方式を採用している場合は、現在の等級の要件を満たしていること、入学方式を採用している場合は、上位等級の要件を満たしていることを確実に見極めましょう。
ただし、上位等級に求められる要件を身につけているかどうかの判断は一般的に難しいため、アセスメントツールも利用することをお薦めします。
おわりに
昇進することで、求められる役割が変わります。それまでの経験に基づいたやり方では対応できない場面もあることでしょう。業務の難易が上がることで、社員がストレスを抱える可能性もあります。昇進が決定した際は、その役職に求められる役割を明確にしたうえで、社員に理解してもらうことが重要です。さらに研修などを通じて実践的なスキルを身につけてもらうことで、昇進後の活躍を後押しできるでしょう。
管理職の目標設定やマネジメントについては、こちらのコラムでも詳しくご介しています。
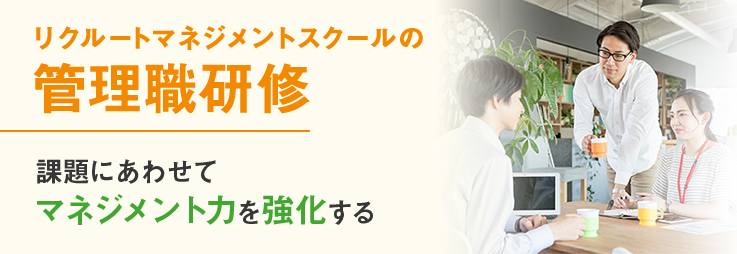
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



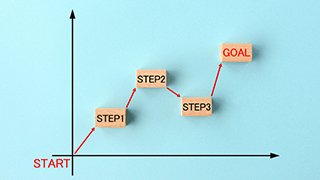













 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての