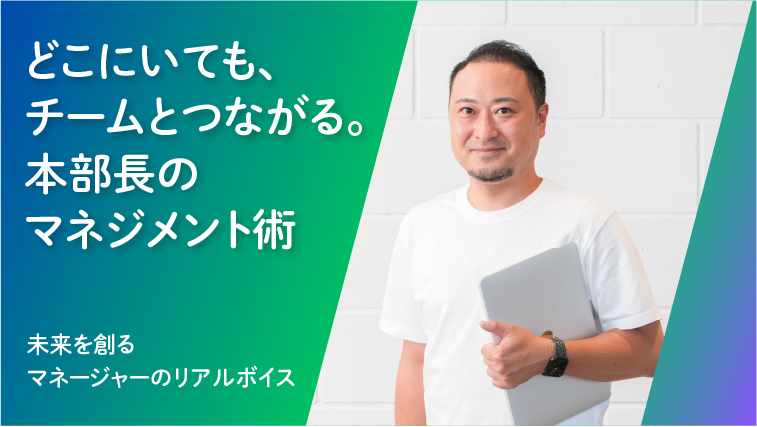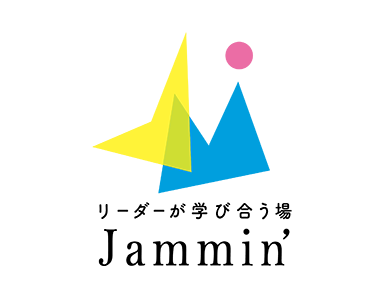用語集
フィードバック 意味や効果、具体的な手法を解説
- 公開日:2014/04/18
- 更新日:2026/02/09
職場やチームの成長には「フィードバック」が欠かせませんが、伝え方次第では逆効果になることもあります。効果的な伝え方や相手のモチベーションを下げずに改善点を伝える方法に悩む方も多いでしょう。本記事では、フィードバックの基本やメリット、効果的な手法について詳しく解説します。
- 目次
- フィードバックとは
- フィードバックの種類・方向性
- フィードバックを実施するメリットや効果
- フィードバックの手法・フレームワーク
- フィードバックを適切に行うためのポイント
- フィードバックの効果が見られないときの対処法
- まとめ
フィードバックとは
フィードバックとは、もともと英語で「反応」や「帰還」を意味する言葉です。 電子工学の分野で用いられていましたが、今ではさまざまな場面で使われています。ビジネスシーンでは「仕事を行った社員に、評価や改善点を伝えること」を指します。本人に現状を理解してもらい、課題解決や成長につなげることを目的に行います。
企業などの組織においてフィードバックが行われるのは、主に日常業務やOJT、人事評価面談、1on1などの場面です。基本的には上司から部下に行いますが、リーダーからメンバー、先輩から後輩、同僚から同僚などへ行うこともあります。また、360度サーベイなどを活用して部下から上司へのフィードバックの機会を設けている企業も増えてきました。フィードバックを小まめに行うことで、従業員の成長だけでなく、組織の活性化も期待できます。
ビジネスにおけるフィードバックの意味とは
ビジネスにおけるフィードバックとは、上司から部下、同僚同士、さらには顧客から企業へと、目標達成に向けた行動や成果について指摘・評価し、成長や改善を促すためのコミュニケーションです。フィードバックを行う際は、個人の性格や人格を否定するのではなく、具体的な行動や結果に焦点を合わせることが重要です。適切なフィードバックを行うことで、個々の業務改善やチームの生産性向上が期待できます。また、単なる指摘ではなく、相手の成長を促す建設的な内容であることが重要です。ポジティブなフィードバックと改善点を伝えるバランスを意識することで、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
フィードバックが必要とされている理由とは
フィードバックが重視される理由の1つは、社員のモチベーション向上とスキルアップに直結するためです。適切なフィードバックがなければ、自身の課題を把握できず、成長の機会を失ってしまいます。また、チーム内の円滑なコミュニケーションを促進し、目標達成に向けた改善策を素早く実行できる点も重要です。特に、継続的なフィードバックを取り入れることで、組織の柔軟性が高まり、変化に対応しやすい環境が整います。
フィードバックの種類・方向性
フィードバックには、相手の成長を促し、行動の改善につなげる役割があります。特に、ポジティブな内容で行動を強化するものと、改善を促すネガティブなものに大別されます。
ポジティブフィードバック
ポジティブフィードバックは、前向きな表現を使った肯定的なフィードバックのことです。仕事での良い面に注目し、優れている点や成長した点などを伝えます。例えば「会議で積極的に発言してくれるおかげで、周りも刺激を受けている。今後もこの調子で頑張ってほしい」といった具合です。ポジティブフィードバックを受けた部下は自己肯定感が高まり、自信を持つことができます。仕事へのモチベーションも上がり、積極的に取り組めるようになるでしょう。
ネガティブフィードバック
ネガティブフィードバックは、批判的なフィードバックのことです。仕事での良くない点や問題点などを指摘して、改善を促します。例えば「会議での発言が長すぎて要点を掴みにくい。今後気をつけよう」といった具合です。仕事がうまく進まないときに、原因が把握できていない部下もいることでしょう。そのようなときに有効な方法です。誤りや改善点をしっかり伝えることで、パフォーマンスの向上が期待できます。
フィードバックを実施するメリットや効果
フィードバックを行うことで、さまざまなメリットがあります。ここでは主に4つを説明します。
目標達成につながる
部下が仕事を進めていて「行動や努力の方向性がズレている」ということもあるでしょう。フィードバックをすることで、そのズレを早めに解消することができます。定期的に行えば、その都度軌道修正ができるため、より効率的に目標達成に近づくことができるはずです。管理職については、メンバー個々を的確に軌道修正していくことで、組織全体の生産性アップにつながるでしょう。
モチベーション向上が期待できる
部下のなかには、上司からの反応がないと「放置されている」と思う人もいます。フィードバックを行うことで「自分のことをきちんと見てくれている」と、安心して業務に取り組むことができるでしょう。良い点を褒めたり、称賛の言葉送ったりすることでモチベーションもアップするはずです。また改善点や次に取るべき行動について理解すれば、目標達成に向けた行動が取りやすくなります。仕事の質も上がり、ますますやる気が高まるでしょう。
従業員の成長につながる
フィードバックは、部下にとって「気づき」を得る機会でもあります。自分では気づきにくい現状の立ち位置や強み・弱み、改善点などを客観的に知ることができるでしょう。例えば「会議での発言が分かりやすい」と言われたら、「もっと積極的に発言しよう」と考えるかもしれません。「発言の要点が掴みにくい」と言われれば、「先に結論から話すようにしよう」と工夫するきっかけになるでしょう。上司と部下が一緒に課題解決や目標達成に向けて考えることで、成長を後押しすることができます。
上司と部下の関係性が深まる
上司は、フィードバックをするために部下の行動を把握する必要があるため、部下への理解が自然と深まります。部下も、フィードバックの内容に納得すれば「自分のことをよく理解してくれている」と実感し、上司への信頼が増すでしょう。また定期的にフィードバックを行うことによって、コミュニケーションを取る機会が増えます。お互いの認識のズレを解消して目標を共有することで、信頼関係も一層高まるでしょう。
フィードバックの手法・フレームワーク
フィードバックを効果的に行うためには、適切な手法やフレームワークを活用することが重要です。適切な場面で使い分けることで、より実践的なフィードバックが可能になります。
手法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
SBI型 | 状況・行動・影響を明確に伝える | 具体的で分かりやすい |
サンドイッチ型 | 良い点 → 改善点 → 良い点の順で伝える | 受け入れやすく、モチベーションを維持できる |
ペンドルトン型 | 相手に考えさせながらフィードバックする | 自発的な気づきを促し、主体性を育てる |
SBI型
SBIとは「Situation(状況)」「Behavior(行動)」「Impact(影響)」の頭文字を取ったものです。「いつ、どこで起こったことか」→「どのような行動を取ったのか」→「行動の結果どのような影響があったか、または上司が感じたこと」の順に伝えます。SBI型のメリットは、部下が内容を理解しやすいことです。そのため現状や今後取るべき行動に納得してもらいやすくなります。
S「今日の会議のことだけど」
B「積極的に発言していて良かったよ」
I「他の参加者にも良い刺激になった」
サンドイッチ型
ポジティブフィードバックの間にネガティブフィードバックを挟む手法です。「褒める」→「改善点を伝える」→「褒める」という順番で伝えます。改善点だけ指摘すると部下のモチベーションが下がってしまう恐れがありますが、前後に褒めることでモチベーションの低下を防ぎ、改善点の指摘が受け入れやすくなります。
ポジティブ「今日の会議、積極的に発言していて良かったよ」
ネガティブ「ただし、発言が長くて要点が掴みにくいところもあったから、最初に結論を言うようにしよう」
ポジティブ「でも他の参加者の刺激になった。この調子で頑張って」
ペンドルトン型
上司から部下へ一方的にフィードバックをするのではなく、上司と部下が話し合いながら進める手法です。心理学者のペンドルトンによって開発されました。部下の反省点をもとに、部下自身に改善点を考えてもらうため、主体性を引き出すことができます。
【話し合いの流れ】
- 確認(何を話すのか)
- 良かった点
- 改善点
- 行動計画(今後どうするのか)
- まとめ
上司(内容の確認):
「先日作成してくれた会議資料について、」
上司(良かった点を伝える):
「データが効果的に整理されていて、分かりやすかったよ。周りの評価も高かったよ。」
上司(改善点を引き出す):
「今回の件で、改善できる点があるとすれば、どんなところだと思う?」
部下:「提出が予定より遅れてしまった点が反省点だと感じています。」
上司(行動計画を考えさせる):
「そうだね。次回はどのように進めれば、スムーズに提出できると思う?」
部下:「スケジュールに余裕を持たせ、最低でも3日前には提出できるように取り組みます。」
上司(まとめ):
「いいね。時間に余裕を持って進めることで、さらに質の高い資料が作れるはずだね。次回も期待しているよ。」
フィードバックを適切に行うためのポイント
フィードバックは、従業員の成長を促し、組織全体の生産性向上につながる重要なプロセスです。しかし、効果的なフィードバックを行うには、伝え方やタイミングに工夫が必要です。
フィードバックの目的を明確にする
フィードバックの目的が曖昧なままでは、相手が受け取る情報も不明確になり、期待する成果を得ることが難しくなります。例えば、成長を促すためのフィードバックと、問題点を指摘するフィードバックでは、伝え方や内容が異なります。事前に「何を伝えるべきか」「どのような変化を期待するか」を整理し、相手にとって意義のあるフィードバックを心がけましょう。
適切なタイミングで行う
フィードバックは、適切なタイミングで行うことが重要です。例えば、行動や成果に対するフィードバックが遅れると、当事者の記憶が曖昧になり、効果が薄れてしまいます。そのため、できるだけ迅速に伝えることが理想です。また、相手が受け入れやすい状況を考慮し、精神的に余裕のあるタイミングで行うことも大切です。
具体的かつ定量的に伝えることを心がける
抽象的なフィードバックでは、相手がどのように改善すればよいのか分からず、効果が半減します。「最近のプレゼンは良かった」ではなく、「先日のプレゼンでは、データを根拠に説明していたため、説得力が増していた」と伝えることで、相手は自身の強みを正しく認識できます。また、「売上が伸びた」ではなく、「先月比で売上が20%増加した」と数値を用いると、より具体的なフィードバックになります。
フィードバックの効果が見られないときの対処法
フィードバックしても期待する効果が得られない場合、伝え方や受け取り手の状況に問題がある可能性が考えられます。フィードバックは一度伝えて終わりではなく、適切な方法で継続的に行うことで効果を発揮します。
継続的にフィードバックを行う
フィードバックは一度で完結するものではなく、定期的に行うことで成長を促す効果が高まります。例えば、一度の指摘だけでは変化が見られなくても、継続的なフォローや小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に行動が改善されることがあります。また、成果が出ていない段階でも、進捗や努力を認めることでモチベーション維持につながります。定期的にチェックし、長期的な視点でフィードバックを続けることが大切です。
フィードバック方法を変えてみる
同じ方法で何度もフィードバックしているのに改善が見られない場合、伝え方を変えてみることも重要です。例えば、口頭でのフィードバックが効果を発揮しない場合、メールやチャットなどの文書で伝えると、相手がじっくり考える時間を持てるため、理解しやすくなります。また、直接的な指摘ではなく、質問形式で気づきを促す方法も効果的です。相手の性格や理解度に合わせた伝え方を工夫しましょう。
関係性を見直してフィードバックする
フィードバックの効果が出ない要因の1つに、上司や指導者との関係性が影響していることがあります。相手がフィードバックを素直に受け入れられる環境をつくるためには、普段からの信頼関係が重要です。日常的なコミュニケーションを増やし、相手の意見に耳を傾けることで、受け入れやすい雰囲気を醸成しましょう。フィードバックの効果が見られない場合、継続性や伝え方、関係性を見直すことで改善できる可能性があります。
ポジティブフィードバックも行う
フィードバックには、ネガティブフィードバックだけでなく、ポジティブフィードバックも必要です。ポジティブフィードバックには、従業員の成果や努力を認め、モチベーションを向上させる効果があります。一方、ネガティブフィードバックも重要であり、改善点を明確に伝えることで、個人やチームの成長を促進します。ポジティブフィードバックも含めることで、受け手がフィードバックを前向きに受け入れやすくなり、改善に取り組む意欲が高まります。
今回紹介したポイントを活用し、より効果的なフィードバックを実践していきましょう。
まとめ
フィードバックは、マネジメントにおける重要な要素です。なんとなく行うのではなく、原則を理解したうえで実践的なスキルを身につけましょう。フィードバック以外にも、組織の目標達成やメンバーのモチベーション管理など、企業の中核を担う管理職やマネジャーには多くの能力が求められます。マネジメントの難しさがより一層高まる現代において、今までのやり方では対応できない場面も増えています。外部の研修やセミナーを上手に活用してマネジメント力を強化し、組織全体の成長につなげてほしいと思います。
管理職のマネジメントや、フィードバック面談を用いたマネジメント能力の向上については、以下の研修をご利用いただけます。
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)