
テーマ
キャリア自律
こんなお悩みは
ありませんか?
- 若手・中堅社員に、次のステージを目指そうというモチベーションが感じられない
- 若手・中堅社員が、ライフイベントを想定した上でのキャリアを考えられていない
- 管理職ポストにつけていない中堅以降の社員のモチベーションが低下している
- この先雇用延長となる予定の中高年社員が、ポストオフ後の働き方を真剣に考えられていない
問題・背景
多くの企業が重要テーマに掲げているのに、一向に進んでいない
弊社の2018年の人材マネジメント調査で人事の方々に組織・人材マネジメントの現状としてお聞きしたところ6割超(67.8%)の企業が「従業員が自律的なキャリア形成ができていない」と回答しています。また「中堅社員が小粒化している(76.4%)」「難しい仕事に挑戦する人が減っている(71.6%)」「従業員の自発的な活動が減っている(71.2%)」といった問題も挙げられています。そのような課題感が挙げられる中、2030年の人的リソース調達(若手の確保以外で重要なこと)については多い順に「65歳までの中高年人材の活用(28.8%)」「機械(AI・ロボット)の活用(21.6%)」「65歳以上の高齢者の活用(21.2%)」と中高年齢層の活用も重要なテーマとして挙げられており、従業員には中高年、高齢者というステージまで働くことを期待していることが伺えます。
また2030年の従業員を動機づけるものとしては「2030年頃」では「多様な働き方の選択」「幸福感(この職場で働くことに幸せを感じること)」が挙げられており、今後、キャリア自律の必要性はさらに増すことが考えられます。
しかし、既述のように6割超(67.8%)の企業が「従業員が自律的なキャリア形成ができていない」と回答しており、キャリア自律の必要性は以前から声が上がっていましたが、なかなか進展が難しいようです。キャリア自律が進まない要因は、以下の3点にまとめることができます。
(1)キャリア形成の捉え方が人によって異なる
キャリアという言葉は多義的で、出世、昇格、異動などの外形的なものを想起する人もいれば、専門性や資格だと捉えている人、あるいはライフも含めた幸せな生き方だと考える人もいます。また、中高年社員のなかには、キャリア=リストラというネガティブイメージを抱く人もいます。そのため、キャリア自律をなぜ進めるのかについて組織で共通認識を形成するのが難しくなっています。「キャリア」にどのような意味をもたせるのか、それをどう伝えていくのかが十分検討されていないことも、キャリア自律が進まない要因の1つです。
(2)機会と施策が分断されている
このように、キャリアについて共通認識ができていないこともあり、キャリア研修などを実施しても、受講者の上司が部下のキャリア形成に関心がなく、研修後のフォローに協力してもらえないといったケースもよくみられます。また、目標設定面談や評価フィードバック面談も実は受講者のキャリアを語り合う貴重な機会となるのですが、短期的業績のことしか話題にならないことも少なくありません。このようにキャリア形成を支援する機会と施策が分断されていることも、キャリア自律が進まない要因の1つとなっています。
(3)キャリア形成と組織での期待役割を果たすことが分断されている
社員が組織の中で役割を果たして力をつけていくことと、キャリア形成していくことは表裏一体のものであるものの、その2つの側面がどのような関係があるのかを統合的に考えてきた企業は少ないのが実情です。期待役割行動を発揮していくこととキャリア形成は別物という認識が、キャリア自律を遅らせている要因でもあります。
主な課題
各世代に合わせたキャリア自律支援が必要
では、どうすればキャリア自律支援がうまく機能するのでしょうか。一般的には、課題となっている層に施策が実施されます。最近では、雇用延長を想定してミドル・シニア層のモチベーション向上を目的に、キャリア研修を導入するケースが増えています。また、モチベーションが下がっているのはマネジャー職に就けていない人なのだから、管理職は対象外でよいという意見も多く聞かれます。
しかし実際は、現管理職層にもポストオフへの心の準備をしてもらう必要があります。若手・中堅社員についても、現在のミドル・シニア層と異なるキャリア観をもっている世代と言われているものの、日常の仕事に埋没し、将来の準備を怠りがちです。したがって、各世代のキャリア観を踏まえつつ、節目でキャリアを考える機会を設定し、世代に応じたキャリア意識をもってもらうことが重要です。世代による主な課題としては、次の3点が挙げられます。
(1)キャリア形成のジレンマの払拭(20・30歳代)
現在の若手・中堅社員は、大学時代からキャリア教育を受けており、ある意味キャリアを考えることへの関心は高い世代です。だからこそ、若手・中堅社員の多くは、日常の仕事に左右され、キャリア形成の機会を十分にもつことができていないのではないかと焦りを感じています。同時に、上の年齢層が多数を占める環境のため、管理職や次のステージへの動機付けが難しくなってきているのも特徴です。そのため、組織の中で成長することが自分のキャリアとどう関係しているのかを明確に示して意味付けする施策を仕掛けていく必要があります。
課題「キャリア形成のジレンマの払拭(20・30歳代)」を詳しく見る
(2)ミドルからのキャリアチャレンジ(40歳代)
40代は会社の中でのステージでもライフのステージでも様々な問題が生じる時期です。また、40代はその多くが就職氷河期にあまり本意でない就職をした人が多いものの、キャリア意識を持ち続けている人と、その入った組織の風土に慣れてあまりキャリアを考える機会を持てなかった人と、意識面でもばらつきが多くなっています。企業側としては、雇用延長の流れもあって40代にまだまだ頑張ってほしいと考えているケースが多く見られます。そのため、40代に改めて今後の10~20年のキャリアを見直し、チャレンジしてもらうことが重要です。
課題「ミドルからのキャリアチャレンジ(40歳代)」を詳しく見る
(3)シニアならではの貢献領域の設定(50歳代)
かつての時代は、50代は早期に引退するかあるいは社外へ出向するというパターンで職業人生を閉じていくことが多くありました。しかし、雇用延長の義務化と人員構成上の要請から、その世代が引退や社外転出してしまうと組織が機能しなくなると捉える企業が増えています。また、役職定年制を導入する企業は、ポストオフした管理職のモチベーションを維持する必要もあります。改めてどのような貢献ができるのかを再設定した上で、今後も活躍してもらうための策を講じなくてはならないのです。
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



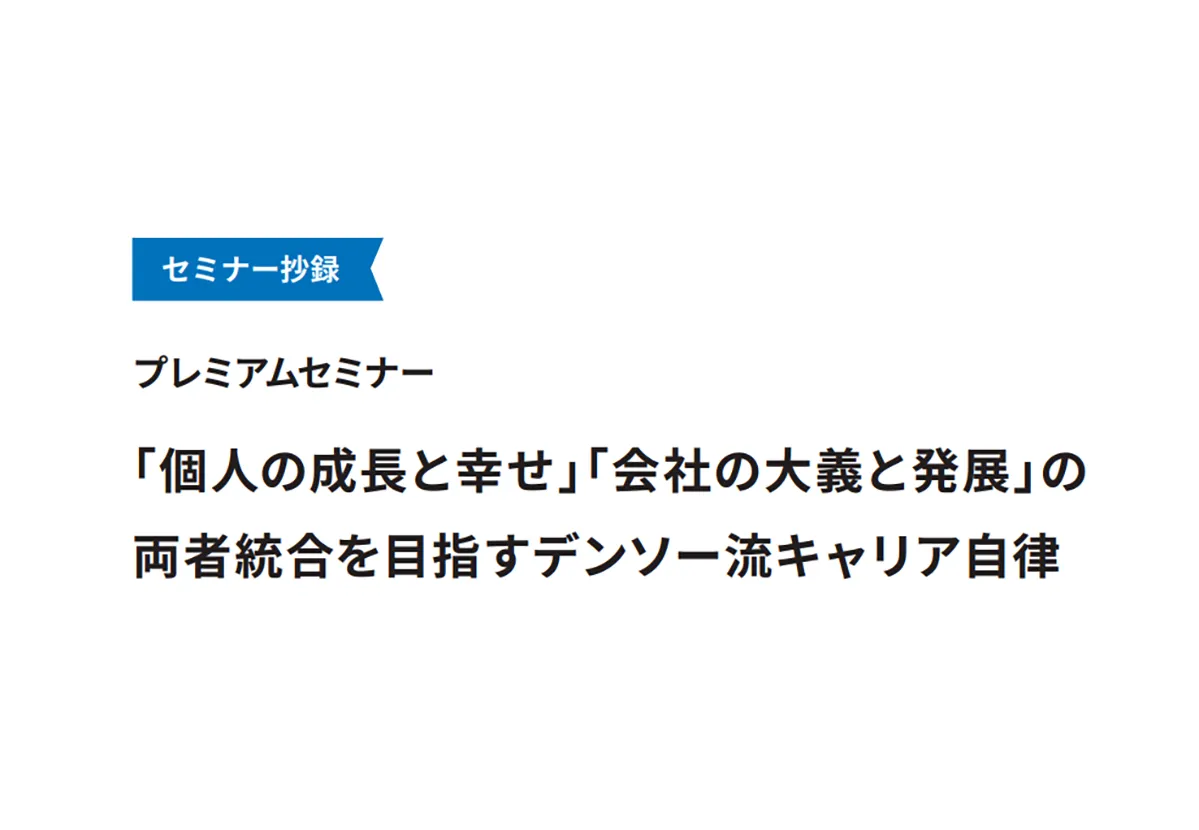













 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての