連載・コラム
国際経営研究の現場から 第4回
海外赴任における適応
- 公開日:2014/10/22
- 更新日:2025/04/15

「次はインドネシアに行ってほしい。君にとっては初めての海外赴任になるな。あちらでは、営業組織の管理職として、主に販売網の整備を担当してもらうことになる。インドネシアは中国の次の市場として、全社的に注目されている。存分に君の力を発揮してほしい。着任は1カ月後。前任者の帰任も決まっているので、現地での引き継ぎを考えたら、早々に着任する方が良いだろう。家族についてどうするかは、人事と相談してほしい。」
このような人事異動を命じられたら、あなたなら何を思うだろうか?
インドネシアといえば、人口も多く、BRICSの次のマーケットとして注目が集まるアジアの大国である。新たなキャリアのステップを踏む市場としては、十分な舞台だ。また、日本ではなかなかポストが回ってこない管理職の経験を積めるというのも、良い機会である。
一方、現地でのビジネスに上手く適応できるか、という心配も頭をよぎる。自分が培ってきた国内での経験は、文化やビジネス慣行も違う異国で活かせるのだろうか? そもそも、英語はどれくらい通じるのか? そして、インドネシアといえば、アジア最大のイスラム教の国だが、ビジネスにどのように影響してくるのだろうか?
また、家族のことも心配である。配偶者は「一緒に行きたい」と言うだろうか? そして、子供の教育については? 新興国であることを考えれば、慣れ親しんだ日本のような生活は無理だろう・・・・・・
このような、様々な思いが頭をよぎるのではないだろうか。
日本企業のグローバルな事業展開がますます加速するなか、海外赴任は珍しいことではなくなった。日本人を海外現地法人に送り出すだけでなく、海外で現地採用した外国人を国内に赴任させるといった例も以前に比べれば比較的耳にするようになっている。さらに言えば、アジア圏内でマネジャーをローテーションしたいが、なかなか進まない、といったご相談を企業から受けることも多くなっている。国内から海外、海外から国内、海外から海外、とさまざまな形での海外赴任が起きている。
今回は、こうした「慣れ親しんだ母国を離れ、他国に赴任する」際の「適応」について考えていきたい。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
適応を構成する3つの要素
そもそも、海外赴任と国内の異動で決定的に違うこととは何だろうか? 海外赴任を通常の国内の赴任と同じように捉えて良いものだろうか?
このことについて考える上で参考になるのが、Black, Mendenhall & Oddou (1991) らによる海外赴任時の適応のフレームワークである。彼らは適応を「仕事への適応」「人間関係への適応」「生活への適応」という3つに分けて議論している。
このフレームワークについては、実際に定量的にアンケート等でデータを取ってみると、フレームワークどおりに3分類がきれいに分かれない、といった批判も一部にある。しかし、理屈として分かりやすく、赴任者の適応について議論したり、考察したりする上では便利なフレームワークである。そのためか、海外赴任における研究においては、最も広く言及されているフレームワークといえるだろう。
さて、3つの適応の中身について見ていこう。「仕事への適応」とは、国内で担当していた仕事と海外で担当する仕事の変化への適応を意味している。多くの場合、赴任者は仕事の変化に直面する。例えば、国内でのポジションよりも1段階、あるいは2段階上位の管理職ポジションにつくことになる、というのは、よく見られる変化だ。これまでよりも大きな視野で仕事や組織を考えること、そして、戦略立案、業績管理、組織運営等、新たなスキルを学ぶことが必要になる。さらに、仕事の中身自体も大きく変化することが多い。冒頭の例で言えば、販路も整備されている国内の環境から、新興国で、新たに販路を開拓するところから始めなければならない環境に移る訳で、同じ営業といっても状況はずいぶん異なる。判断のポイントや、求められる行動も大きく変わるため、「慣れ親しんだやり方」に拘らず、「新しいやり方」を学ぶ必要も出てくるかもしれない。
次に、「人間関係への適応」とは、現地の従業員やビジネスパートナーとの関係についてのものだ。海外に赴任する以上、多かれ少なかれ、現地の人々と関わり、ビジネスを行うことが必要になる。文化やビジネス慣行の違う環境で育った人々と信頼関係を築き、相互理解を深めていくことは、簡単なことではない。Earley & Mosakowskiが2000 年の論文で示したとおり、人は国籍や文化が異なる人々を無意識に「よそ者」として捉え、「心理的な壁」を作りがちである。彼らの研究からは、多国籍の人々が混在する組織よりもむしろ、2つの国の出身者が混在する組織の方が一体感が生まれにくく、国籍ごとに組織が分断されるリスクが高い、ということが示されている。例えば、日本人赴任者と現地採用の人材が混在する組織で、ついつい日本人同士、現地人同士で固まってしまい、両者の間に見えない壁ができてしまう、といったことである。こうした分断は無意識に起きてしまうため、乗り越えるのは容易ではない。
さらに、国が変われば、指示の与え方、褒めたり叱ったりといったフィードバックの方法、業務外での付き合い方など、さまざまな場面で「適切」とされる行動は異なる。それらは当事者にとっては「当たり前」のことであり、皆、殆ど意識せずにその「当たり前」に沿って生活し、働いている。そのため、異なる文化をもつ国から来た人々が共に働くと、必然的にすれ違いが起きる。お互いに自分にとっては「当たり前」の振る舞いをしているのに、相手からしてみると「なぜこの人はこんな変なことをするんだ」と感じる、といった出来事が、さまざまな場面で生じるのである。
最後の「生活への適応」とは、そのものずばり、仕事以外の生活に関する適応である。国内の話であるが、筆者にとっては、就職して3年目に、出身地の関西から東京に転勤になったことが、まさに「生活への適応」に直面した最初の経験であった。まず、東京の巨大な鉄道網に途方に暮れ、当時は今のようにスマートフォンが経路案内もしてくれなかったため、よく電車を乗り間違えたりしたものだ(まあ、筆者が人一倍どんくさい、ということも多分に寄与しているとは思うが)。
もちろん、海外に出て経験する「生活への適応」の苦労はこの比ではない。例えば筆者が現在暮らすイギリスであれば、地下鉄などの鉄道は日々の運行が当てにならない、硬度の高い水のために水道管がよく詰まったり水漏れしたりする、郵便が予定通りの日数で届かない、インターネットの開通に下手をすると何週間もかかる、といった、「なぜ?」と感じる出来事の目白押しである。また、店舗での顧客対応も日本と比べるとぞんざいで、顧客に対する敬意が感じられない、とイライラする人もいるだろう。
こう考えれば、Black & Gregersen (1991)らが、「配偶者や子供の現地適応」が海外赴任の成否に大きく影響する、ということを発見したのも、不思議ではない。先日、古い友人で、ご主人の赴任に帯同してのドイツでの駐在生活を経て、半年ほど前にロンドンに引っ越してきた女性と話す機会があったのだが、「私は、イギリス暮らしは平気なんだけど」と前置きした上で、こちらで知り合ったママ友達のなかに「ロンドンの環境になじめなくて、一日でも早く帰りたい、と嘆いている奥さんがいる」と話していた。先進国であり、日本人には相対的になじみがある英語が公用語のイギリスですら、そうした不適応が起きてしまうのである。このように、配偶者や子供が適応に苦しんでいる状況では、赴任者もなかなか仕事に集中し辛いのではないだろうか。
以上、3つの適応という観点で、海外赴任について考えてみた。こうしてみると、海外赴任には、国内赴任と似たような部分もある。少なからず仕事に変化があり(ご存じのとおり、未経験の部門への異動は、日本では珍しいことではない)、筆者の例で挙げたとおり、生活環境も多かれ少なかれ変化するからである。しかし、適応の必要性の度合いを比較すれば、海外赴任の方が大きいことは、議論の余地がない。特に、国内でマネジメント経験のない人材を、文化的に日本と大きく違う環境の国に送り込む、といった赴任に伴う適応の難しさは、かなりのものだろう。過去の研究でも、文化適応の失敗が原因となって、海外赴任者が任期終了前に帰国する、赴任先でのパフォーマンスをあげられない、といった問題が多く指摘されている(Black, Gregersen, Mendenhall & Stroh, 1999(白木三秀・永井裕久・梅澤隆監訳『海外派遣とグローバルビジネス:異文化マネジメント戦略』白桃書房、2001年)が参考になる)。
特に、文化の違いに起因する「人間関係への適応」は、国内では殆ど意識する必要がなく、海外赴任に固有のチャレンジといえるだろう。このためか、国際経営研究のなかでは、「異文化適応」は古くからさまざまな研究者が着目し、多くの研究の蓄積が行われてきた分野である。次のセクションでは、この分野における代表的な研究成果と、最近の動きについてご紹介したい。
異文化適応:どのような人が適応に向くのか?
「海外赴任先の異文化に適応できず、パフォーマンスを出せない人がいる一方で、上手く適応し、成果をあげる人材もいる」となれば、「では、どんな人だと異なる文化に上手く適応できるのか?」というのが気になるところである。
Johnson, Lenartowicz & Apudらは、2006年の論文で大きく3つのカテゴリーからなるCross-Cultural Competenceという概念を提唱している。本セクションでは、彼らの枠組みに則り、「知識」「スキル」「個人的特性」の3つの観点で、異文化適応に求められるものについて研究成果をご紹介したい。
「知識」に関しては、(1)文化に関する一般的な知識、(2)特定の文化に関連する知識を挙げている。(1)の一般的な知識とは、そもそも文化には違いがあるということ、さらに言えば、典型的にどのような違いが存在するのかといった知見をもっていることである。そして、(2)は、具体的に言えば赴任先の文化に関する知識のことである。現地での慣行、宗教、ものの考え方、人間関係のあり方などについて知っていることが、適応の基礎になるということである。
これについては、赴任前の教育でまかなえる部分も多いだろう。HofstedeやTrompenaars等、世界中の文化を比較研究した書籍も出版されており、こうしたものを読むことで理解を深めることも可能だ。
次に、「スキル」については、Johnsonらは、現地言語を使う、現地の慣行に合わせて行動を変える、ストレスを管理する、コンフリクトマネジメント(人間関係の衝突への対処)等を挙げている。
日本では、スキルといえば英語力がまず、赴任者を選ぶ上での条件として挙げられることが多い。英語を苦手とする人が多いことを考えれば当然といえるだろう。また、赴任先で仕事をするために必要な業務上のスキルも、赴任者を選ぶ上では、重視される観点である。
しかし、現地の人々と人間関係を構築しなければならない以上、これらに加え、いわゆるソフトスキルが重要なのは明らかなように思われる。Johnsonらが挙げているコンフリクトマネジメントもまさにこれにあたるだろう。ソニーで海外拠点のマネジメントのプロとして長年活躍された糸木氏によれば、海外で活躍する上で重要なのにも関わらず軽視されがちなのが、「リレーショナルスキル(=人間関係構築スキル)」ということであった(セミナー報告「RMSmessageライブ2013 グローバル競争力再考―現地マネジメントの視点から―」)。
そして、最後の観点が「個人的特性」である。これらは、異文化環境で成果をあげるための知識やスキルを身につけていく上でベースとなるもの、と定義されており、要素としては、フレキシビリティ、我慢強さ、自己信頼などが挙げられている。
Johnsonらの挙げた要素を裏返せば、「頭が固くて自分と異なる考え方に目を向けられない」「曖昧で理解し難い状況に耐えられない」「今は理解できない人々とも、自分は分かり合えるはずだ、といった自己信頼がない」といった人々は、異文化適応に向いていない、ということになる。
この指摘は、Earley & Mosakowski (2004)が、異文化適応に重要な適性として、「価値判断の棚上げ」また、「メタ認知能力」を挙げている点に通じるものがある。上述のとおり、異文化の環境では自分の「当たり前」に反するような「おかしな」出来事が日々生じる。しかし、そこで「彼らは分かってない」「おかしい」と判断していては、異文化への理解を深めることにはつながらない。このような善し悪しの価値判断を敢えてせずに、むしろ「なぜ彼らはこのような言動をするのか」という疑問をもち、観察を続け、理解を深める努力を意図的に行うことが、異文化適応の重要な資質なのだ、というのが、Earley & Mosakowskiの指摘のポイントである。
確かに、私自身の経験を振り返っても、適応は、ある程度の期間をかけて行う学習のようなものだと感じる。仮に教科書で文化について学んでいたとしても、現実に日々、異なる文化の人々と接していると、教科書にないような、思わぬ言動に出くわす。また、日本人にもさまざまな人がいるように、文化の違いと個人の違いの両方が存在するため、一人の言動が文化の現れなのか彼/彼女の個性なのかは、そう簡単には分からない。そのため、観察と経験を通じて、時間をかけて適応していくことが必要なのだ。
従来の適応の研究では、こうした、時間をかけて起きる「プロセス」としての異文化適応はあまり着目されてこなかった。しかし、昨年発表されたMolinsky (2013)の研究は、この点に着目している点で非常に興味深い。個人は、異文化に直面したときに何を経験し、どのような心理の変化を経て、どのように新たな文化への対処法を学んでいくのか? その課程で何に苦労するのか? こうしたことが明らかになることで、異文化適応を支援する上での新たなヒントが得られるのではないかと、筆者としては期待している。
Multiculturals:複数の文化を内包した人々
最後に、この海外適応に関連する、比較的新しい研究分野をご紹介したい。Biculturals、あるいはMulticulturalsといわれる分野である。Bilinguals(バイリンガル)、Multilinguals(マルチリンガル)という言葉は、ご存じのとおり、2つ、あるいはそれ以上の言語を話せる人々のことを指す。同じように、Biculturals(バイカルチュラル)、Multiculturals(マルチカルチュラル)という言葉は、2つ、あるいはそれ以上の文化のものの考え方を自らのなかに内包している人々、と定義される(Fitzsimmons, 2013)。
昨今、日本企業で盛んに行われている留学生の採用は、まさにこうした点に着目した取り組みと考えられる。日本からアメリカに留学し、数年を過ごした人材であれば、生まれ育った日本の文化を理解、体現しているだけでなく、アメリカ文化も合わせて身につけているかもしれない。逆に、中国から日本に来て大学時代を過ごした留学生であれば、中国文化だけでなく、日本文化も理解しているのではないか、と企業としては期待する。彼ら、彼女らは、まさに、Multiculturalsであることが期待されている。
また、海外赴任の増加に伴って、子供の頃から多くの国を経験して育つ人々も次第に増えている。例えば、前述の私の友人の息子さんは、1歳からドイツで育ち、今はイギリスで小学校に通っている。そして、今後、数年で日本に帰国する見込みだという。彼も、ドイツ、イギリス、日本の文化を経験しながら育つという点で、まさにMulticulturalsである。
このような異文化経験は、個人にどのような影響をもたらすのだろうか? 現在、主流となっている説は、「さまざまな文化を経験することで、異文化適応能力そのものが高まる」という考え方である。ここで中心となるのが、Cultural Frame Switchingという考え方である。この概念が意味するのは「頭のなかに複数の文化のものの見方の枠組みをもち、状況に応じてそれを切り替える」ということだ。そして、このswitching能力自体が、異文化経験を通じて高まるのではないか、と考えられている(Hong, Morris, Chiu & Benet-Martinez, 2000)。
実際、Nguyuen & Benet-Martinez (2013)は、メタアナリシスという分析手法を用いて、multiculturalsは、異文化適応に成功しやすい、ということを報告している。このことは、赴任者の適応失敗に悩む多国籍企業にとっては朗報である。留学生を採用している日本企業にとっても明るい知らせだろう。
ただし、異文化圏で過ごすことが、必ずしも両文化を内包することにつながる訳ではないのではないか、という指摘もある。例えばRudmin(2003)は、「元の自国の文化と、新しい文化の両者を融合した価値観をもつ」といった、一般的に創造されるMulticulturalの姿だけでなく、「元の文化を固持し、新しい文化に適応しない」「新しい文化に適応し、元の文化を捨ててしまう」「両方と距離を置き、独立した価値観を持つ」の4つのパターンがあり得る、と指摘している。
この指摘が示唆するのは、留学生が国籍上は日本人だとしても、日本企業になじみやすいとは限らないかもしれない、ということだ。彼ら、彼女らが、留学後も日本的な価値観を留学後も保持しているとは限らず、もしかすると、留学先の文化に「染まって」しまっているかもしれないからである。そうした人は、伝統的な日本企業の文化には、フィットしないかもしれない。実際に、留学生を採用している企業の担当者の方のなかには、こうした点を選考上の観点として置かれている企業もあるのではないだろうか?
グローバル化にしたがい、企業活動だけでなく、個人の活動もまた、グローバル化している。そう考えれば、こうしたMulticulturalsが世界的に増加していくことはほぼ間違いないだろう。そのなかで、異文化への適応ということのもつ意味も変化していくのかもしれない。
REFERENCES
Black, J. S., & Gregersen, H. B. (1991). The Other Half of the Picture - Antecedents of Spouse Cross-cultural Adjustment. Journal of International Business Studies, 22(3), 461-477.
Black, J. S., Gregersen, H. B., Mendenhall, M. E., & Stroh, L. K. (1999). Globalizing people through international assignments: Addison-Wesley Reading, MA.
(白木三秀・永井裕久・梅澤隆監訳『海外派遣とグローバルビジネス:異文化マネジメント戦略』白桃書房、2001年)
Black, J. S., Mendenhall, M., & Oddou, G. (1991). Toward a Comprehensive Model of International Adjustment - An Integraiton of Multiple Theoretical Perspectives. Academy of Management Review, 16(2), 291-317. doi: 10.2307/258863
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures: Stanford University Press.
Earley, P. C., & Mosakowski, E. (2000). Creating hybrid team cultures: an empirical test of transnational team functioning. Academy of Management Journal, 43(1), 26-49.
Fitzsimmons, S. R. (2013). Multicultural Employees: A Framework for Understanding How They Contribute to Organizations. Academy of Management Review, 38(4), 525-549. doi: 10.5465/amr.2011.0234
Johnson, J. P., Lenartowicz, T., & Apud, S. (2006). Cross-cultural competence in international business: toward a definition and a model. Journal of International Business Studies, 37(4), 525-543. doi: 10.1057/palgrave.jibs.8400205
Molinsky, A. L. (2013). The Psychological Process of Cultural Retooling. Academy of Management Journal, 56(3), 683-710. doi: 10.5465/amj.2010.0492
Rudmin, F. (2003). Acculturation: Advances in theory, measurement, and applied research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(6), 751-753. doi: 10.1177/0022022103254206
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










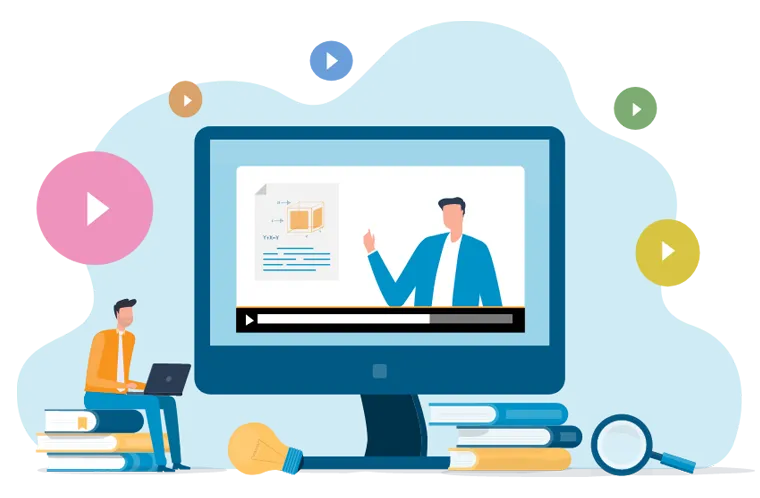 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての