連載・コラム
国際経営研究の現場から 第14回
企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 公開日:2017/06/19
- 更新日:2025/04/15

「グローバル化のために英語を企業の公用語にする。社内文書もすべて英語で作成し、会議は英語で行う」
「管理職の登用条件にTOEICを組み込む。これからは全管理職が英語を使いこなす必要がある」
企業活動がますます国際化するなかで、「英語」 が注目を集めている。企業が国境を越えて活動すると、必然的に母語が異なる人たちと関わる必要が発生するためだ。英語はビジネスを行う上での公用語になり、英語が自由に使えることを管理職に求める企業は急速に増えた。求人市場でも、「 英語で海外の人材と渡り合えること」は、人材要件として存在感を増している。
ただ、 今日の英語力に対する注目の高まりは、歴史を振り返えると比較的新しい現象だ。日本企業が本格的に国際展開を始めたのは1980年代であり、90年代の初頭にはすでに、アメリカ、欧州、日本が海外直接投資の三極(The Triad)であることは、国際的な常識になっていた(United Nations,1991)。しかし、日本本社の管理職も含めて英語を話せることの必要性が広く指摘されるようになったのは、筆者が認識している限り2000年代の後半以降である。何がこうした変化の要因になったのだろうか。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
なぜ英語が重要なのか
それは、国際ビジネス、国際競争のモードの変化にある。
古典的な海外進出のモデルは、本国で生み出した技術や製品、サービスを海外に持ち出し、販売、提供する、あるいは現地で生産する、というものだ。基本的には「市場開拓」または、「コスト削減」が海外展開の目的となる(Dunning,2001)。これに対して、昨今の国際競争は、進出先の需要を捉え、現地でイノベーションを行うとともに、その成果を本国、あるいは他の拠点に展開すること、また、そのために現地の人材を活用することが重要な位置を占めつつある<これらの議論については、「リバースイノベーション」(Govindarajan & Trimble, 2012)、 「メタナショナル経営」(Doz, Santos & Williamson, 2001)を参照されたい>。このことは、日本で知識を生み出して送り出すだけでなく、海外拠点から日本に知識を還流する、という流れを生み出す。
このトレンドを更に推し進めたのが、統括機能の国際移転だ。
世界で最先端の市場が日本ではない場合、情報速度が遅くなる日本よりも、最先端の市場に拠点を置こう、という発想だ。また、税制や産業集積などの観点から、統括機能を特定の国や都市においた方がよい、という判断を行う企業もあるだろう。こうした動きは、「技術やノウハウを生み出す」「意思決定をする」機能が、日本から海外に移り、更には、一社のなかでも世界に分散することにつながる。
かつては進出先のそれぞれの国で、ある程度独立してビジネスを行うことが主流だったが、グローバル化、インターネット化のために、ある国で行った施策が他の国の市場に与える影響を考えざるをえないのが現状である。
例えば、デジタルカメラは、国を越えて商品の転売が簡単に行えるため、ある国で値引き販売を行うと、その商品があっという間に他の国に流れ、周辺国での市場価格の低下につながってしまう。そのため、価格政策をはじめとしたマーケティング政策を、グローバルで調整することが必須になる。
生産過程でも、バリューチェーンが複数国にまたがることは常識になった。例えばNAFTA(北米自由貿易協定)のおかげで、平均的な自動車生産の過程では、部品が7回以上、カナダ、アメリカ、メキシコの国境を行き来しているという。こうなると、生産調整や品質管理など、さまざまな活動を、拠点間でコーディネートする必要がある。
これらすべての動きは、知識や情報の流れが、「(日本)本社→海外拠点」というシンプルなトップダウン型 から 、「海外拠点→(日本)本社」「海外拠点⇔海外拠点」という流れも含む、複雑なネットワーク型に変化することにつながる。そのため、 意思決定のために海外の拠点と頻繁にコミュニケーションを取ることが、一部の人の仕事から、多くの人の仕事になっていく(もちろん、こうした変化は全ての企業のあらゆる部門で生じるわけではない。しかし、大きな傾向として、こうした変化が起きている、ということが今回の論点である)。
こうした変化が生じる前、海外拠点の人材と頻繁にコミュニケーションを取る必要があったのは、海外拠点の幹部や管理職として赴任する人や、本社で海外拠点を統括する人などに限られていた。かつてよく見られた、「海外事業部門」が独立して、いわゆる通常の事業部門とは別扱いになっている、という組織構造は、まさに、こうした状況の産物である。
これに対して、上記のような変化の結果、開発、生産、マーケティング、それを支える人事や財務、経営企画などのあらゆる機能部門で、海外の拠点と本社の間で双方向のコミュニケーションを取り、グローバルとローカルの事情を鑑みつつ、意思決定や知識創造を行うことが必要になった。そのため、もはや「海外のことは海外事業部門の人が考えればいい」というのは現実的ではない。
こうした動きのなかで、「英語=ビジネス国際語」への変化が急速に進んだと考えられる。
海外拠点間のやり取りを円滑に行う上では、赴任者だけでなく、現地の管理職も、他の拠点の人材とコミュニケーションできることが重要になる。こうなると、世界共通の言語を現地の従業員にも話してもらう必要がある。更にいえば、統括機能を本国以外に移した場合は、その拠点でもともとの本社所在地の言語を公用語にするのは効率が悪い。現地で採用する人材が、必ずしも本社所在地の言語(日本企業の場合は日本語)を流暢に話せるとは限らないためだ。こうしたことが、英語が母国語ではない国の多国籍企業の間で、「本社所在地の言語=公用語」から「英語=公用語」 への変化が急速に進むことにつながった。
また、従来であれば、本社にいるのは本社所在地出身の人材ばかりであった。しかし、本社から海外拠点、海外拠点から本社への知識移転を促進するために、本社に海外拠点の人材を逆赴任させることが、過去20年で大幅に増えた(Harzing, Pudelko & Reiche, 2015)。こうなると、本社のなかにおいても、英語を使わなければ、という動きにつながる。
このことは、日本企業に重要な示唆がある。筆者が見聞きしている限りでは、中国に関しては日本語が話せる人材が比較的多いこと、また、日本人が総じて英語を苦手としていることから、日本語を中国拠点の公用語にしているケースが多い。結果として、日本語を流暢に話せる、日本企業に勤める中国人の労働市場が確立している。しかし、この方針は、中国市場を想定した経営を行う上では十分だが、中国と他の国の間で拠点間の連携を進める上では問題となりうる。実際、ある日系商社の海外人事責任者から、次世代リーダーの登用の条件として、「中国語と日本語ができればいい、と従来は考えていたが、間違いだった」「日本語、中国語に加えて英語も使えないと、結局、国際人材としては活躍できない。現地のビジネスを考えると、中国語は必須だが、国際的に大きな仕事を仕掛けるには日本語と英語の両方がいる」と、聞いたことがある 。
つまり、言語政策は、事業構造の未来像と密接につながっている。日本と海外の間で、どのような活動を行っていくかを想定し、それを踏まえた言語政策を考える必要があるのだ。そして、「言葉も話せるし、仕事もできて、なおかつ自社にも合う」人材を、世界各国で確保するのには時間がかかる。 今、投資を始めても、こうした条件を満たす人材が確保できるのは数年後かもしれない。そう考えると、「現状、本社はまだまだ日本語でやっていても大丈夫」な状態であっても、「英語を公用語にして、強制的に本社の人材の英語力を高める」という方針に、一定の合理性があることが分かる。また、「日本語人材を確保できるから、この国では日本語を公用語にしよう」という意思決定が、目の前では確実に事業運営をやりやすくしてくれる一方で、実は将来の禍根につながるかもしれない、ということも示唆される。
本社人材の英語力と、海外拠点の経営現地化には、密接な関係がある
更に、「なぜ日本の本社の人材においても英語力が重要なのか」という問題について、もう少し掘り下げてみたい。上述のとおり、国際経営上、本社と現地拠点の間で、知識や情報をやり取りすることは非常に重要である。そして、言語はその媒介になる。特に技術やノウハウなど、業務に関わる知識の移転には、現場レベルまで巻き込んだ コミュニケーションが必要になることが多い。そのため、現地の管理職、本社の管理職の間で共通の言語で会話できることが非常に重要になる。
本社の管理職や一般メンバーが英語を自由に操ることができ、また、現地法人の幹部や管理職、一般メンバーも同様だとすれば、何が起きるだろうか? この状況では、英語を共通語として、本社と海外拠点の間の幹部、管理職の間で頻繁にコミュニケーションを取ることが可能になる。定例会議だけでなく、日常的にチャットやメール、電話などで、有機的に海外拠点と本社がつながって仕事を進めることができる。この点で、アメリカやイギリスなど、英語が本社所在地の母国語である多国籍企業は優位にある。
ただし、海外拠点の人材が英語を流暢に操れない場合は、話が別である。例えば、Peltokorpi and Yamao (2016)らは、「海外拠点の管理職が企業公用語(=英語であることが多い)を流暢に使いこなせるほど、当該拠点で生み出されたナレッジが、本社に還流される傾向が強い」ことを示している。逆にいえば、現地拠点の管理職が公用語を流暢に操れない場合、知識還流が妨げられる、ということだ。
もちろん、本社の管理職の語学力にも同じことがあてはまると考えられる。つまり、本社の管理職が「企業公用語」を流暢に扱えない場合も、知識還流が妨げられる可能性がある。
こうした場合、コミュニケーションの「架け橋」になる人が必要になる(Harzing, Koster & Magner, 2011)。本社から海外拠点への赴任者はその「架け橋」としては最適である。本社所在地の言語(=日本語)と、公用語(=英語)の能力を持ち、現地に身を置くことで現地のマーケットやオペレーションの状況、現地で生み出されたノウハウの価値を把握し、なおかつそれを本社の人々に伝えることができるからだ。
このことは、海外拠点における人材登用に示唆がある。 仮に、英語が企業としての公用語だとしよう。そして、ある拠点の現地人材の中間管理職のなかに、「英語を自由に操れ、なおかつ自社の理念や価値観を十分に理解し、体得し、仕事上でもリーダーシップや専門性を発揮している」人がいる、という状況を考えてみたい 。本来であれば、この人は、将来の現地拠点の幹部候補として、積極的に責任ある仕事を任せ、 いずれは登用していきたい人材だと考えられる。特に、「 海外拠点内で完結する仕事だけでなく、本社とのやり取りが発生する仕事を任せる」ことが視野に入るだろう。こうした仕事は、拠点を越えた広い視野を得られると共に、本社の考え方への理解が進み、人脈も広がるため、将来の幹部候補を育てるには最適だ。
しかし、彼ら、彼女らが密接にコンタクトを取る必要がある本社の幹部や管理職は、必ずしも英語を自由に操れる人たちばかりではないとしたらどうだろうか(筆者が知る限り、海外経営上の公用語は英語だが、本社は主に日本語で運営されており、本社の幹部や管理職には英語に苦手意識がある方がかなりの数、存在する、という企業は珍しくない)。このような場合、本社と関わる仕事のなかには、どうしても日本語が必要な場面が出てくる可能性が高い。そうなると、こうした仕事を現地の中間管理職に任せることは難しくなってしまう。更に、本社からの赴任者を引き上げ、完全に現地の人材に幹部ポジションを任せることは、本社の視点からすれば、不安が残る。
つまり、本社の人材の英語力不足が、海外拠点の人材を育成、登用していくことの妨げになり得るのである。もちろん、人材の育成、登用に関わる意思決定は、多様な要素を考慮するものであり、言語だけが障害になるわけではない。しかし、仕事を任せる、登用するといった場面で、(無意識かもしれないが)本社と拠点の間でのコミュニケーションがうまくいくだろうか? という不安が積み重なり、現地化を妨げている、ということは十分に考えられる。実際、 筆者が現在行っている国際比較研究からは、「 ビジネスパーソンの平均的な英語力」が低い国に本社がある企業では、「海外拠点における本社からの赴任者比率」が高いという傾向が明らかになっている。
こう考えると、本社の人材の英語力を高めることが、間接的に海外拠点での幹部の現地化につながる可能性がある。また、逆にいえば、本社の人材が必ずしも英語を自由に操れるわけではない状況で、海外拠点の幹部の現地化だけを進めることには無理がある、とも考えられるのだ。
とはいえ、「全員が英語を自由に操れる」という状況は現実味がない。日本人が英語を苦手としていることはよく知られているが、他国の人々は皆、まったく何の問題もなく英語を母国語と同じように扱えるのかといえば、そういうわけではない。そのような限界があるなかで、現実に仕事をどう回していくのか、コミュニケーションをどう円滑にしていくのか、ということが問題になる。次回は、こうした点に注目して、「言語の壁をどう乗り越えるのか」について更に掘り下げよう。
参考文献
Doz, Y., Santos, J., & Williamson, P. J. 2001. From Global to Metanational: How Companies Win in the Knowledge Economy: Harvard Business Press.
Dunning, J. H. 2001. The Eclectic (Oli) Paradigm of International Production: Past, Present and Future. International Journal of the Economics of Business, 8(2): 173-190.
Govindarajan, V. & Trimble, C. 2012. Reverse Innovation: Create Far from Home, Win Everywhere. MA: Harvard Business Press.
Harzing, A.-W., Koster, K., & Magner, U. 2011. Babel in Business: The Language Barrier and Its Solutions in the Hq-Subsidiary Relationship. Journal of World Business, 46(3): 279-287.
Harzing, A.-W., Pudelko, M., & Reiche, B. S. 2015. The Bridging Role of Expatriates and Inpatriates in Knowledge Transfer in Multinational Corporations. Human Resource Management.
Peltokorpi, V. & Yamao, S. 2016. Corporate Language Proficiency in Reverse Knowledge Transfer: A Moderated Mediation Model of Shared Vision and Communication Frequency. Journal of World Business, 52: 404-416.
United Nations. 1991. World Investment Report 1991 - the Triad in Foreign Direct Investment. In C. O. T. Corporations (Ed.). New York.
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
次回連載:『国際経営研究の現場から 第15回 言葉の違いにどのように対処するか~ Language Barriers in International Business ~』
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










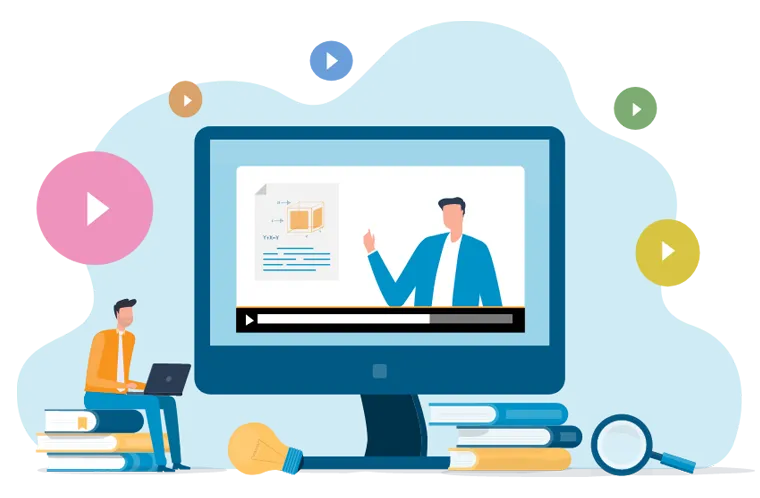 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての