連載・コラム
マネジメント人材育成ブック【5】経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
優れた経営幹部は 十分に信頼を獲得してから改革する
- 公開日:2018/10/15
- 更新日:2025/07/30

近年、私たちが行ったマネジメント(に関する)研究を6つのテーマでまとめ直した『マネジメント人材育成ブック』より、第5章は、「経営幹部が就任後に行うべきこと」として、「経営幹部の就任後行動の研究」の成果を中心にお知らせします。
はじめに、架空の会社・X食品の新任営業マネジャー(加藤洋介)と、社内の誰かが対話する「ストーリー」がついています。
それぞれの章の研究成果を受けた内容となっておりますので、本文の導入として気軽にお読みください。
また、メルマガ会員の方は『マネジメント人材育成ブック』全体のPDFをダウンロードいただけます。ご興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。
- マネジメント人材育成ブック【6】経営者への道(卓越した経営者の学びのプロセス研究)
- 卓越した経営者は 日々の鍛錬からも学んでいる
- マネジメント人材育成ブック【5】経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
- 優れた経営幹部は 十分に信頼を獲得してから改革する
- マネジメント人材育成ブック【4】女性マネジャーの特徴(マネジメントの男女差研究)
- 女性マネジャーは より「部下」をよく見ている
- マネジメント人材育成ブック【3】成果をあげるミドル・マネジャーとは(ミドル・マネジャー研究・これからのミドル・マネジャー研究)
- 成果をあげるミドル・マネジャーは「持論」をもっている
- マネジメント人材育成ブック【2】経験から学ぶ(経験学習論・経験デザイン研究)
- 修羅場を経験してから しっかり内省すれば一皮むける
- マネジメント人材育成ブック【1】マネジャーになる(マネジャーへのトランジション研究)
- 新任マネジャーのほとんどが トランジションに苦労している
第5話 新任マネジャー、事業部長と話す

田中「どうだった?」
加藤「田中部長、永杉事業部長は本当に優秀な方なのでしょうか?」
田中「というと?」
加藤「面談の間、ニコニコ笑って僕の話を聞いているばかりで、気の利いたアドバイスなんて一つもなかったですよ。人の良い親戚のおじさんみたいな感じだったんですが。」
田中「それはきっと、加藤や部署のことを知りたかったからだ。」
加藤「え?」
田中「もっと言えば、加藤と仲良くなりたかったからだな。」
加藤「どういうことですか?」
田中「どうもこうもない。言った通りだ。永杉さんは、この部署に来て2カ月。加藤は1年半。この部署のことをより知っているのは?」
加藤「僕です。」
田中「だから、この部署の先輩として、加藤にいろいろと教えてほしかったんだよ。」
加藤「確かに、この部署のことは根掘り葉掘り聞かれたので、いろいろと答えました。」
田中「大丈夫、永杉さんは優秀だよ。」
加藤「へえ~。まだよくわかりません。」
田中「部署のことを深く知らないで、いきなり改革策を打ち出す上司をどう思う?」
加藤「信用できませんね。」
田中「部署のメンバーの性格をよく知らないで、その人に合っていない指示を出す上司は?」
加藤「嫌ですね。」
田中「そうだろう? だからまず、永杉さんは加藤や僕たちのことをよく知ろうとしているんだよ。」
加藤「なるほど。」
田中「ここからは僕の推測だけれど、永杉さんはすでにこの部署の課題をだいたい見極めていると思う。何をどう改革すればいいかもたぶんわかっているはずだ。でも、少なくともあと数カ月は抜本的な改革策を打ち出さないだろう。細かい改善はすると思うけどね。」
加藤「それはちょっと遅くないですか?」
田中「そんなことはない。ところで加藤、何か会議に誘われたりしなかったか?」
加藤「あ、そういえば、これから2週間に一度くらい、定期的にランチミーティングをしようと言われました。」
田中「それはおそらく、加藤をこの部署のキーパーソンの1人だと見たということだろう。」
加藤「え?」
田中「この部署で誰と仲良くなって、誰に仕事をお願いすればよいか、永杉さんにはわかったんだ。」
加藤「それが僕。嬉しいな。」
田中「永杉さんのお眼鏡にかなったんだから、喜ぶべきことだろう。でも、その分大変だぞ。きっと数カ月後、加藤は随分忙しくなるよ。長期休暇を取るなら、その前にとっておいた方がいい。」
加藤「そんなにですか?」
田中「そうだよ。永杉さんは、ここに来る前に所属していたグループ会社では取締役で、その会社を徹底的に改革してきた敏腕の経営幹部だ。ああ見えて、本気になったら恐いんだからな。」
加藤「そ、そんな風には全然思えなかったんですが。」
田中「人は見かけによらないものなんだ。加藤、マネジャーの力を磨きたいなら、もっと細かな人物観察ができるようになった方がいいぞ。」

新組織をいきなり任されて 独りで苦労することが多い「経営幹部」を応援したい
プレイヤーから課長に昇格する際は、もともとプレイヤーとして所属していた職場のマネジャーとなるケースが少なくありません。しかしその後は、未経験の部署・職場をマネジメントする機会が出てきます。部長、事業部長と職位が上がるに従って、新組織の立ち上げ、既存組織の立て直し、グループ会社の再建などを任される立場になってきます。また最近は、外部から経営幹部として入社する経営幹部が増えています。いくら優秀な方でも、未知の組織をマネジメントするのは簡単ではありません。事実、私たちは、マネジメントに苦労している経営幹部をこれまでに数多く見てきました。しかし、日本企業にはいまだに「リーダーは一人で決断するもの」と考える風潮があります。欧米では一般的なエグゼクティブ・コーチも、ようやく広まりだしたのが現状です。日本の経営幹部の多くは相談相手がおらず、独り悩みを抱えているのです。
私たちが、そうした経営幹部を応援したいと始めたのが「経営幹部の就任後行動の研究」です。経営幹部の赴任初期の組織立ち上げプロセスに絞って、どういったマネジメント行動がよいのかを探求してきました。
私たちはまず、先行研究の「相互作用によるリーダーシップ論」に注目しました。これは、リーダーシップをリーダーとフォロワーの相互作用として捉えるアプローチで、リーダーがフォロワーに及ぼす影響と同じくらい、フォロワーによるリーダーシップ受容を重んじる見方です。特に参考になったのが、リーダーシップ発揮の過程を、リーダー・フォロワー間の信頼蓄積プロセスと捉えたホランダーの「特異性―信頼理論」です。この理論では、リーダーは集団の規範に忠実である「同調性」を示すことでフォロワーの信頼を獲得していきます。同時に、自らの能力で組織の目標達成に貢献する「有能性」を示すことでも信頼を蓄積していくのです。そして、「同調性」と「有能性」によってフォロワーに十分に認められて、はじめてリーダーはフォロワーから変革行動を期待されるのです。
私たちは定性調査(図表1)を行うにあたって、このホランダーの理論をベースに「仮説モデル(図表2)」を構築しました。このモデルのポイントは、同調性と有能性のバランスです。同調性と有能性は相反するもので、受け入れられようとするばかりだと有能だと思われませんし、自分の能力を誇示してばかりではなかなかメンバーから認められません。そこで定性調査では、経営幹部たちがこの2つをどのように両立させながら信頼を獲得していくのか、そして、この仮説モデルがどの程度正しいのかにフォーカスを当てました。
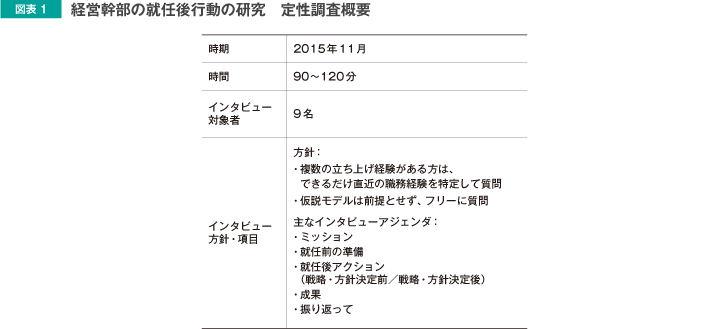
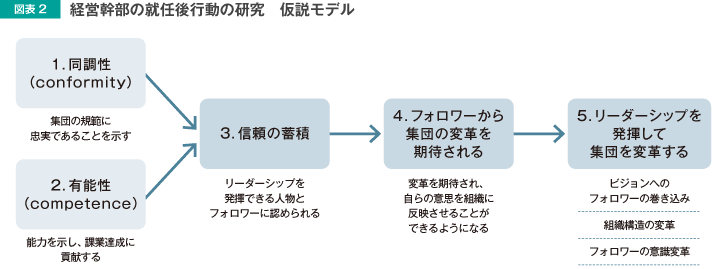

組織・メンバーから十分に信頼を得た上で 本質的な改革を進めるのが鉄則
2015年11月、私たちは9名の事業責任者経験者に90分から120分のインタビューを行いました。この定性調査の成果を結論からお伝えすると、おおむね仮説モデルのとおりだったのですが、1点、私たちの予測と違う点がありました。それは、事業責任者の方々が就任当初、「有能性」よりも「同調性」を示す行為に重点を置いていたことでした。新たに赴任した事業責任者には、早く成果をあげなければならないというプレッシャーがありますから、序盤から、その手腕を組織内の従業員や人事、上位の役員あるいはベンチャーキャピタルに見せて、どんどん改革を進めているのではないかと予測していました。つまり、早期に「有能性」を示しているだろうと考えていたのです。しかし、実際にインタビューしてみると、有能性を示す行動よりも、「同調性」に重きを置いた行動の話をよく聞きました。有能性を示す機会が少ないわけではないのですが、そうしたときも同調性を優先させていました。なぜなら、不必要に有能性を誇示しても、組織内の従業員からの信頼を得られず、かえって反発を招く可能性があることが、彼らにはわかっていたからです。
就任当初、9名全員が部長・課長をはじめとする従業員にインタビューを行っていました。この「従業員インタビュー」で、事業責任者たちはメンバーの入社動機や在社理由を聞くとともに、企業・組織の歴史や文化について細かく質問しています。これは、一人ひとりに関心があることを示すだけでなく、企業・組織理解を深める上で意味のある行為です。つまり、従業員インタビューを通して、事業責任者たちは同調性を示すと同時に、有能性のベースとなる情報を手に入れていたのです。また同時に、自分の力になってくれそうなキーパーソンを探していた事業責任者も多くいました。
そして、就任2~3カ月後には、全員が従業員・顧客・ビジネスパートナーへのインタビューなどで獲得した情報をもとに、多様なセグメント軸から分析を行い、組織課題を明確に設定していました。しかし、そこですぐに手を打った事業責任者は経営再建を任されていた1名だけで、他の8名は、就任半年以内は抜本的な改革施策を一切行いませんでした。ではその間、いったい彼らは何をしていたのでしょうか。ある事業責任者は、従業員の意志を問い、自発性を高めるワークショップを企画し、実行していました。賞与の支給、エアコンの設置、人事制度のマイナーチェンジなどの小さな課題を解決することで、従業員の心を掴んでいる事業責任者も見られました。就任3カ月後に、意図的に当たりさわりのない方針を発表し、様子を見た事業責任者もいました。そしてその間、全員が従業員との定期的なコミュニケーションを大切にしていました。
つまり、事業責任者は少なくとも半年間、しっかりと同調性を示した上で、はじめて本格的な組織変革に手をつけていたのです。事業責任者は、その変革実行のタイミングを注意深く見ていました。ある事業責任者は、マネジャー同士のコミュニケーションが増える、メンバーが自発的に動くようになるといったチーム内のポジティブな反応・動きが増えてきたところで、すかさず手を打っていました。他にも、キックオフスピーチに「いいですね」というフィードバックが多くあった、斜に構えていたメンバーが前向きになったなど、事業責任者たちは組織の変革を期待されるフェーズに移ってきたことを敏感に察知しています。
しかし、この段階まできても、多くの方が慎重に注意深く動いています。ほぼ全員が、まずは確実に成果が見込める対策から進めていました。例えば、営業活動の管理を徹底するといった個別機能の改革・改善です。あるいは、自らビジネスパートナーと交渉して大幅なコストダウンにつなげるなど、自らの手で確実に生みだせる成果から始める事業責任者もいました。こうした施策を重ねた上で、初めてクロスファンクションで取り組む本質的な組織改革に取り組んでいたのです。抜本的な改革に着手するまで、就任から1年くらいかかっている事業責任者も珍しくありませんでした。
♦PDF版のご案内
第5章では他に「部長へのトラジション支援の取り組み」についてもお伝えしています。
▼▽第5章の全体を読みたい方はメルマガご登録の上、PDF版をダウンロードしてください▼▽
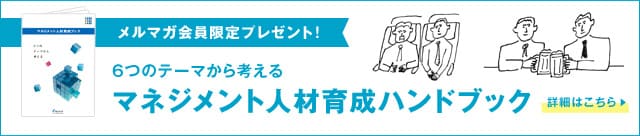
経営層向けの研修をご検討の方は、経営層研修特集ページをご覧ください。
- マネジメント人材育成ブック【6】経営者への道(卓越した経営者の学びのプロセス研究)
- 卓越した経営者は 日々の鍛錬からも学んでいる
- マネジメント人材育成ブック【5】経営幹部が就任後に行うべきこと(経営幹部の就任後行動の研究など)
- 優れた経営幹部は 十分に信頼を獲得してから改革する
- マネジメント人材育成ブック【4】女性マネジャーの特徴(マネジメントの男女差研究)
- 女性マネジャーは より「部下」をよく見ている
- マネジメント人材育成ブック【3】成果をあげるミドル・マネジャーとは(ミドル・マネジャー研究・これからのミドル・マネジャー研究)
- 成果をあげるミドル・マネジャーは「持論」をもっている
- マネジメント人材育成ブック【2】経験から学ぶ(経験学習論・経験デザイン研究)
- 修羅場を経験してから しっかり内省すれば一皮むける
- マネジメント人材育成ブック【1】マネジャーになる(マネジャーへのトランジション研究)
- 新任マネジャーのほとんどが トランジションに苦労している
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)













