連載・コラム
連続小説 真のリーダーへの道 第6回
「出向して、新規事業を興す!?」
- 公開日:2017/11/13
- 更新日:2024/03/27

リーダーの成長には、「仕事経験から学ぶこと」が最も重要であるといわれています。
企業は自社のリーダー育成のために、リーダーの成長に必要な経験を明らかにし、そしてその経験を網羅的に積めるよう、ポジションや仕事・役割を、意図的にローテーションさせていくことが有効です。私たちはこれを「成長経験デザイン」と呼んでいます。
リーダーに必要な経験は各社さまざまで、特定するのは至難の業です。そこで弊社では、先行研究やインタビュー、これまでの支援事例などから、リーダーの成長を促す8つの経験を抽出しました(下図参照)。
この連載小説では、架空のリーダー佐々木の成長ストーリーをたどりながら、それぞれが具体的にどのような経験で、それによって何を学び、どのようにリーダーシップを形成していくのか、1つずつ紹介していきます。
第6回は、「ヒト・モノ・カネをマネジメントする経験」です。
※「成長経験デザイン」について詳しく知りたい方は、>>>特設ページ<<<をご覧ください
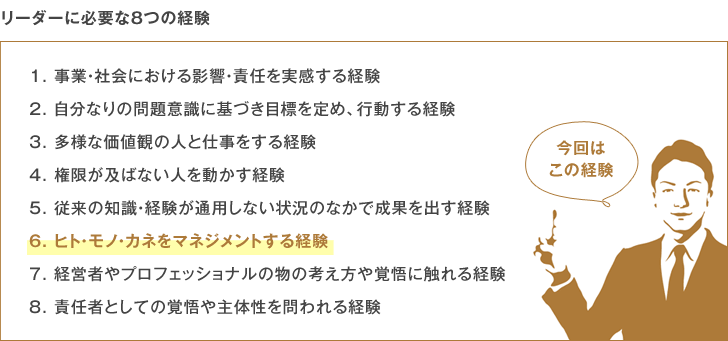
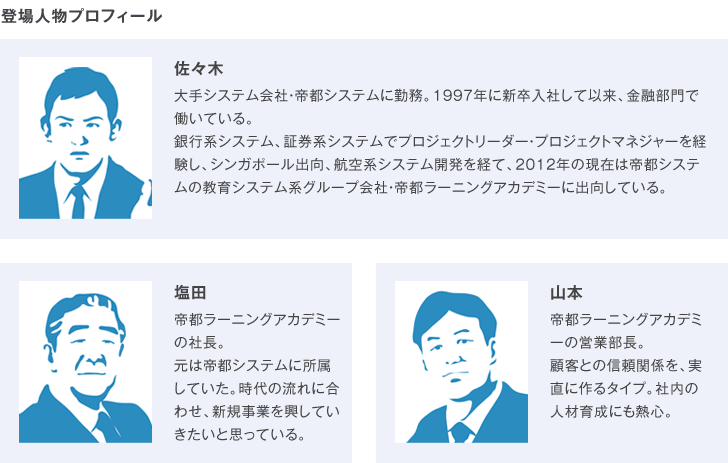
攻めのマネジメントは初めてだった
「まさか、自分がマーケティングの会議に出て、“ペルソナ”なんて言葉を使う日が来るとは……」。佐々木は会議室の窓辺でコーヒーを飲みながら、不思議に思った。佐々木は、航空系システム部門のシステム開発プロジェクト(第5回)を終わらせた後、今度はグループ会社・帝都ラーニングアカデミーの経営企画部に異動となっていた。上司からは「出世コースだ。頑張れよ」と送り出された。確かに帝都システムでは、幹部候補になると一度はグループ会社に出向するケースが多いのは知っていた。おそらく佐々木もその一人になったのだろう。ただ、佐々木自身はあくまでも現場でシステム開発に携わっていたい意向が強く、気持ちは複雑だった。現場で第一線に立ち続けるべきか、出世して経営を担っていくべきか……、自分のなかで答えが出ないまま、帝都ラーニングアカデミーに通う日々は始まった。
帝都ラーニングアカデミーに来た初日、塩田社長から伝えられたのは「新規事業立ち上げチームのリーダーとして新しい事業を立ち上げてほしい」という言葉だった。帝都ラーニングアカデミーはもともと帝都システムの教育研修子会社としてスタートしたが、現在は研修プログラムを他社に販売するビジネスも順調だった。そこで更に、クラウドを利用した新たなeラーニングサービスの開発を進めていたのだ。佐々木が任されたのは、このサービスを売り出し、ビジネスを軌道に乗せることだった。
佐々木はシステム開発のプロジェクトマネジャーとして、これまでにヒト・モノ・カネのマネジメントを何度も行ってきたが、新規事業を立ち上げる仕事はそれらとはずいぶん違った。例えば、佐々木は経営について、きちんと学んだことはなかった。P/LやB/Sの読み方を理解するのがせいぜいで、経営戦略の立案方法や営業・マーケティングについては、ほとんど知らないも同然だった。キャッシュフローの感覚や、経営マネジメントに関する法的知識にも疎かった。システム開発プロジェクトのマネジメントはいわば「守りのマネジメント」で、攻めに転じる必要がなかった。そのため、佐々木はメンバーのアサインメントやモチベーション管理、スケジュール管理、予算管理といったことには強くなっていたが、ビジネスを拡大していくためのマネジメントには携わったことがなかったのだ。これはまったく新たなチャレンジだった。
チャレンジには失敗がつきものだ
佐々木はまず、帝都ラーニングアカデミーの営業部長・山本の力を借りた。自分だけで営業戦略やマーケティング戦略を立てられるとは到底思えなかったからだ。山本たち営業部のメンバーとタッグを組みながら、佐々木は営業・マーケティングの方針を打ち立て、直販営業・代理店営業・プロダクトマーケティングのチームをそれぞれつくっていった。システム開発プロジェクトのように最初から大きな予算が与えられているわけではないので、短期・長期の売上目標に基づいて、少しずつ組織を大きくしていくようにした。最初のうちは、山本たちに同行してもらいながら、佐々木自身も営業に回った。今までの佐々木は、営業を少し軽く見ている部分があった。実際に手を動かしているのはエンジニアである、という自負がそうさせている部分も多分にあったが、佐々木は考えを改めた。自ら何社もの顧客を訪問するなかで、営業がいなければ、そもそもエンジニアの仕事は成り立たないのだと痛感した。

一方、システム開発の方は、自分が見すぎないように注意した。すでに基本的なeラーニングシステムやプログラムはできあがっていたが、お客様の要望に応じてカスタマイズする要望があったり、継続的なサービス改善の必要があったりしたので、小さなシステム開発プロジェクトは随時いくつも動いていた。こうしたプロジェクトに関して、佐々木は極力、口を出さないようにした。今の自分はエンジニアではないからだ。それよりも、営業・マーケティング・システムエンジニアが互いに連携を取りやすい組織づくり・体制づくりに腐心した。また、主要顧客や鍵となる代理店と深くコミュニケーションを取って、営業のタネを見つけ、営業・マーケティング戦略を調整することに力を入れた。そして、佐々木は新たなeラーニングサービスを次々に生みだしていった。
途中、失敗や間違いはたくさんあった。さまざまな関係者から注意を受けたり、山本からたしなめられたりすることも珍しくなかった。しかし、佐々木はそのたびに、塩田に励まされた。「チャレンジには失敗がつきものだ。まだ形のないものを創るんだ。それぐらいでめげていてどうする」と、厳しくも温かい激励を受けた。できないことは、できるようにすればよいのだ。佐々木は失敗を繰り返しながら、少しずつ攻めのマネジメントを覚えていった。
かける眼鏡が変わってきた
佐々木が帝都ラーニングアカデミーに来て2年近く経った頃、eラーニングシステム事業部は総勢30名を超えていた。サービスが増えるに従って、顧客の業界・業種も広がりを見せ、今では大手企業からベンチャー企業まで、500社以上の顧客が何らかのサービスを利用していた。営業チーム・マーケティングチーム・エンジニアチームも基本的な形が整い、初期に入ったメンバーは目に見えるほどの成長を遂げていた。売上と経費のバランスも悪くなく、多少の利益も出ていた。あとはビジネスを拡大していけばよい、というところで、佐々木は帝都システムに戻ることになった。
しかし、以前と異なり、佐々木は、帝都システム全体の経営課題や、組織のあり方について、自然と意識が向くようになっていた。いわば「経営」という新しい眼鏡を手に入れたようだった。自分自身が、帝都システムの経営に対して、どのような価値を発揮できるだろうか。佐々木はそんなことに思いを馳せるようになっていた。そして、その課題を解決するのは、自分たちリーダークラスであるということも、あらためて感じていた。
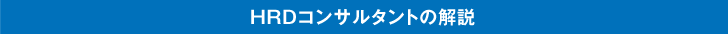

連載第6回目のテーマは「ヒト・モノ・カネをマネジメントする経験」です。
この経験は、ヒト・モノ・カネの裁量権を持ち、全体最適を考えた上で意思決定・実行を担う経験です。前回、航空部門に異動となった佐々木が、今度は、グループ会社に出向となります。
そこで佐々木は、経営企画部の新規事業担当として奮闘し、事業成果をあげるに至りました。
では、この経験がリーダー育成にとってなぜ有効なのかを考えていきます。
ヒト・モノ・カネをマネジメントすることは、いわゆるマネジメント、リーダー職としての当然の職務です。この職務を全うするには、ヒトに対して働きかけ動かすこと、カネを理解するための財務知識、マーケティングの視点、デリバリーを設計する力…等々、広範な力が求められ、鍛えられ、経営的な視点と感覚を得る機会となりえます。それだけでも十分意味のある経験と言えるかもしれません。しかし、この経験において最も重要なのは、ヒト・モノ・カネに責任を持った上で、決断し、実行するということです。
今回、佐々木は、成長軌道にあるグループ会社で新規事業の戦略を練り、決断、実行するという前向きな仕事に取り組みましたが、実際に経営幹部の方々にインタビューをさせて頂くと、事業の撤退やグループ会社の清算など、非常に厳しい場面に直面されているケースも多くあります。その中で、従業員の生活と事業合理性の狭間に立たされ非常に厳しい決断をし、最前線で実行するということを経験し、経営者、リーダーとしての覚悟や姿勢を獲得されています。
また、出向の場合には、親会社から離れて初めて問題や課題がよく見えてきたという声も多く聞かれます。これもまた大きな学びと言えるでしょう。
今回は、グループ会社への出向というケースを取り上げました。前述のとおり、当然、「ヒト・モノ・カネをマネジメントする」という機会は他にもあります。全社的な横断プロジェクトの責任者なども代表例でしょう。しかし、企業の状況によっては、必ずしもそうした機会を潤沢に用意できるとは限りません。特に、組織がフラット化し職務権限も変化していく中で、ヒト・モノ・カネ、特にヒトをマネジメントする機会が限られている企業もあるでしょう。
限られた機会をどのような人材に提供していくか、そして、そこでどのように成長してもらえるとよいのか、これらを組織的に考えていくことがますます重要になってきています。
今回は以上です。本連載も、残すはあと2回となりました。次回はいよいよ、「経営者・実力者の物の考え方や覚悟に触れる経験」です。佐々木は、重大な火消し案件に直面。いよいよクライマックスを迎えます。ご期待ください。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

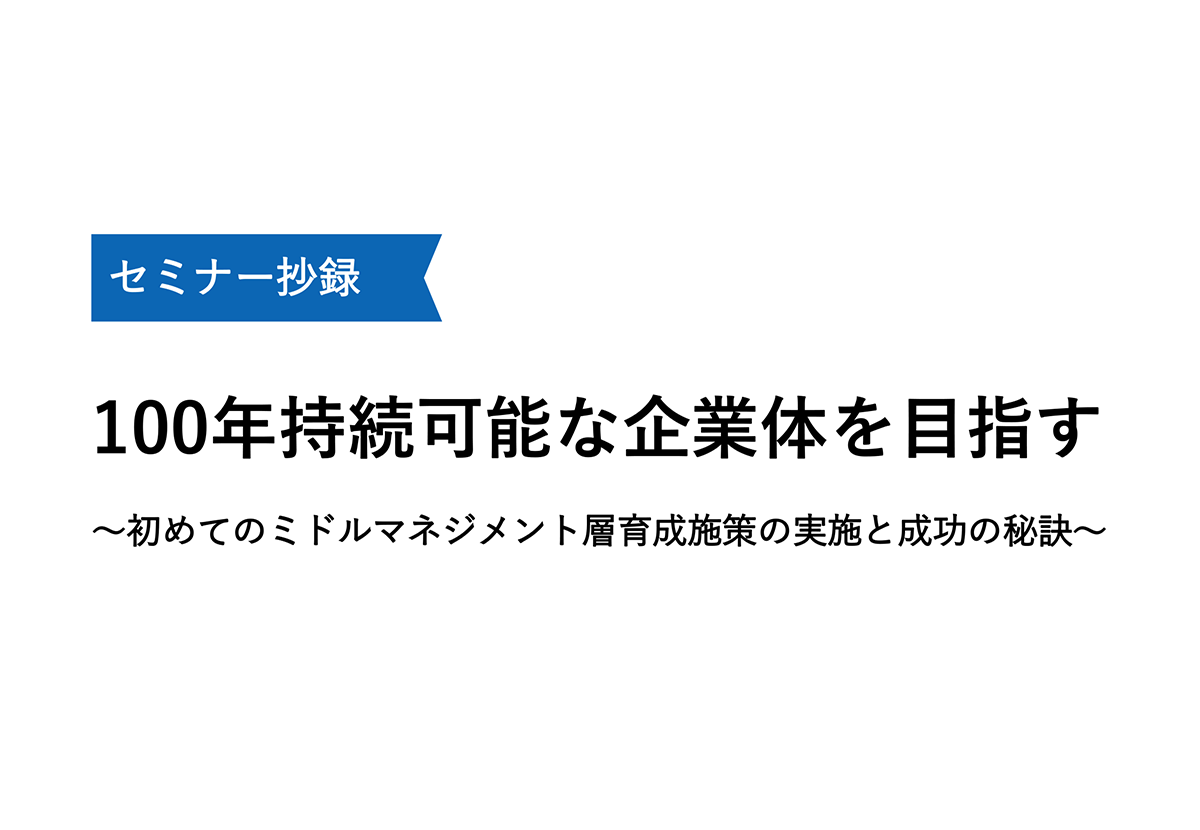









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての