連載・コラム
国際経営研究の現場から 第15回
言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 公開日:2017/08/28
- 更新日:2025/04/15

前回は、「グローバル公用語としての英語」に焦点を合わせて、なぜ英語が重要視されるようになったのか、そして、企業内での公用語について、どのように考え、人材を確保していくかが、事業活動の未来像と密接に関わっていることについて考察した。
今回は、英語が公用語であるとしても、母国語が違う、なおかつ、必ずしも皆が公用語(である英語)を流暢に話せるわけではないということが、業務や組織運営にどのように影響するのか、そして、それに対してどのように対処すればいいのか、について検討する。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
「言語」はただのコミュニケーションの道具ではない
組織やそこで働く個人に対して言語が与える影響について考える上で重要な点は、「言語」はただのコミュニケーションの道具ではないということだ。どのような言葉で考え、話すかということは、個人のアイデンティティに密接に関わってくる。
アイデンティティとは、簡単にいいかえると「自分は何者なのか」ということである。そして、アイデンティティを構成する重要な要素の1つに、「自分をどんな集団のメンバーだと考え、感じているか」ということがある 。現代の社会においては、一人の個人は複数の集団に属しているため、個人のアイデンティティも、おのずと複数の組織への帰属意識を含むものになる。
私自身を例にすれば、私は「日本人」であり、「関西人」であり、「リクルートOB」であり、「LSEの学生」である、といったふうに、複数の集団への帰属が私のアイデンティティを構成している、といえるだろう。
こうした、集団への帰属をもとにしたアイデンティティは、自己と集団を同一視することにつながる(Ashforth, Harrison & Corley, 2008)。例えば、自分が強い帰属意識を持つ集団について批判されると、自分がけなされたように感じて、ついついムッとしてしまうというのは、まさに集団への心理的な同一化の結果といえるだろう。
言語と アイデンティティのつながりとしての例を挙げるとするならば、日本語のなかの方言についての意識だろう 。
例えば、私は関西出身だが、東京での勤務が長いため、仕事の際には通常、標準語に近い言葉で話している。しかし、関西に帰った際に、つい東京っぽい言葉で話してしまうと「関西人なのに関西に溶け込めてない」気持ちになるし、友人からは「東京に魂売ったんか(笑)」とからかわれたりする。冷静に考えてみれば、方言ひとつで大げさな話なのだが、関西弁で話すということは、関西人であるという私の自己認識や、友人たちとの間に存在する関西人としての同郷意識に密接に関わっているのだ (この例は、首都圏出身の方にはちょっと分かりにくいかもしれないが、首都圏以外の方には共感していただけるのではないだろうか)。
2000年代後半から楽天など、いくつかの企業で導入された「英語を社内公用語化する」という施策が、社会的にさまざまな物議をかもしたのはこのためではないか、という指摘がある(佐藤, 2015)。
「日本の会社だと思って働いてきたのに、突然、これからは英語が公用語だと言われた」ということを、「日本語が否定された」と感じ、さらに、日本語話者としての自分のアイデンティティが脅かされたように感じてしまう、というわけだ。なおかつ、「英語が公用語である会社」の中で、「英語があまり話せない自分」は一人前の組織メンバーとして扱われなくなるのではないか、というふうに、「組織メンバーとしてのアイデンティティ」も脅かされるといったと考えられる 。
実際、英語の公用語化を行ったフランス企業の調査から、Neeley (2013)は、英語非ネイティブの従業員が、社内での(主観的な)立場の低下を経験したこと、更には、(英語の公用語化によって結果的に優位な立場に立った)ネイティブスピーカーに対する不信感や怒りを感じていたことを報告している。ここからは、言語が心理的な影響を個人に及ぼすことがよく見て取れる。
個人が話す言語と、その流暢さは、個人と周囲の関係性にも影響する。人間は、同じアイデンティティを共有していると感じる相手のことは、無意識に「身内」として好意的に扱う傾向が、日本に限らず、欧米でもある(Tajfel, 1978)。 海外で日本語を話す外国人に会うと、なんとなく身近に感じ、気を許してしまう、といった経験はないだろうか?上記のとおり、何語を話すかはアイデンティティにつながっており、そのことが、「身内」意識にもつながるのだ。日本企業の海外拠点では、日本人赴任者同士でばかり日本語で話をしていて、現地従業員に同じ情報が伝わってこない、といった不満を現地管理職の方から聞くことはめずらしくないが、こうした「身内」意識がコミュニケーションの断層の一因になっているのではないか、と考えられる。
また、自分の言語力に自信がないと、ついついコミュニケーションに消極的になる 、という傾向も見られる。上記のNeeley (2013)によると、自分の英語力に自信のない場合、 言いたいことをうまく言えないのではないかという不安から、ネイティブスピーカーを交えた会議で自分の言いたいことを抑え込んだり、そもそも、ネイティブスピーカーとの会議に出席するのを避けたりする、という傾向が見られたと報告している 。
このように、言語はただのコミュニケーションの道具ではなく、個人のアイデンティティや個人間の関係性に関わってくるものだという点は、言語をめぐる問題を考える上で、非常に重要な点である。
どう母国語の違いに対処するか
このように、英語が公用語になったからといって、皆が同じように流暢に話せるわけではない。日本人に限らず、母国語ではない言語で話している以上、(完璧なバイリンガルでもない限り)言いたいことをすべて上手に言えるわけではないし、ネイティブスピーカーの発言を100%理解できるわけでもない、と考えるのが妥当だろう。
さて、このようななかで、具体的に業務上、どのような配慮を行うことが重要なのだろうか。本稿では、この点に関して、2つの研究をご紹介したい。まず、Aichhorn and Puck (2017)は、オーストラリアの多国籍企業での調査をもとに、以下のような対応が有効に働いている、と報告している
・公式言語にかかわらず、相手の母国語に気を使う。メールや会話のなかで、ちょっとしたフレーズを相手の母国語で表現することで、相手との間の心理的な距離を縮め、信頼関係を築く
・言語をシンプル化する。 単語や表現の選択(ことわざなど、非ネイティブに分かりにくい表現を使わない)、文法の選択(単純な構文で話す)、スピード(ゆっくり話す)や発音(くっきり話す)などに気を使う。特にネイティブスピーカーが非ネイティブと話をする際に重要
・意図を互いに確認し合う。同じ母国語の人同士で話している時に比べて、よりクリアにかつ、詳細に自分の考えを表現するように心がける。また、図やグラフで言語を補完したり、相手の文脈にあてはめた例を使ったりすることで、共通理解が生まれやすいように工夫する。
これらの対応の背景には、単に言語力に限界があるために、どうやって意思疎通をうまく図るか、という対応を超えた配慮がある点が特に興味深い。例えば、2点目は、一見すると意思疎通のための対策に見えるが、実は、それだけではない。この研究に協力したマネジャー(英語ネイティブ)によれば、「ネイティブスピーカーの話している調子で、非ネイティブのメンバーに話したりしたら、一気に心理的な壁をつくってしまう。それは絶対に避けなければいけない」と話している。単に伝わるか伝わらないかという点を超えて、どういう印象を与えるかまで考えているのだ。
私がとある企業のロンドンの拠点で過去に行った調査を振り返ってみても、日本人赴任者、現地管理職両方に、こうした工夫を意図的に行っている方と、かなり無頓着な方の両方がいる、という傾向が見られた。そして、総じて、こうした配慮を行っている赴任者の方は、現地メンバーのマネジメントがうまくいっており、また、こうした配慮を行っている現地管理職の方は、日本人赴任者からの信任を得ていた。
こうした配慮は、どちらかといえばスキルに当たるものであり、必要性を理解し、意図的に練習すれば、誰にでもある程度はできるようになるものだと考えられる。そういう意味では赴任者に対するトレーニングとして、単に英語を教えるだけでなく、このように相手に配慮したコミュニケーションの手法を教える、ということが有効かもしれない。
2つ目の研究は、 バーチャルでのコミュニケーションに関する研究である。Tenzer and Pudelko (2016)は、さまざまな言語を母国語とする人たちからなるグローバル・バーチャル・チーム(異なる拠点からのメンバーが、遠隔で一緒にプロジェクトなどに取り組むチーム)での、コミュニケーション手段の選択について研究を行い、興味深い結果を報告している。
グローバル・バーチャル・チームでは、距離が離れているため、さまざまなコミュニケーション手段が用いられる。例えば、eメールやチャット、電話会議やテレビ会議、共有のデータストレージなどだ。
こうした手段のなかでは電話会議やテレビ会議は、参加者が一堂に会して即時に コミュニケーションを取ることができ、また、口調や声のトーン、顔の表情やボディランゲージなど非言語の情報も伝わるため、「濃い」コミュニケーション手段だと考えられる。一方、メールやチャットは、それと比べれば文字情報だけであり、電話会議やテレビ会議と比べれば情報量が少なく、なおかつ、必ずしも同時に参加者が一堂に会する必要がない、散発的な「薄い」コミュニケーションの手段、と見なせるだろう。
グローバル・バーチャル・チームのようなプロジェクト型で問題解決を行うチームでは、参加者間で意見の違いを解消し、合意を形成する、また、新しいアイディアを出し合い、発想を刺激し合うといった双方向性がもとめられる場面が多々発生する。その点から上記の2種類のコミュニケーション手段を比較すると、一般的には、こうした目的を果たす上では、テレビ会議や電話会議のような「濃い」手段の方が適していると考えられる。
しかし、Tenzerらの研究によれば、その企業の公用語がネイティブではない人たちが参加する場合は、必ずしもそうではないようなのだ。
上で述べたとおり、非ネイティブの話者は、自分の考えをきちんと表現できるだろうかという不安を抱えている。そうした人たちにとっては、テレビ会議や電話会議のような即時性がもとめられるコミュニケーション手段は、あまり望ましくない。キャッチボールのようなやり取りのなかで、相手も即対応してくるため、自分の考えをまとめて話す必要があるからだ。結果的に、「濃い」コミュニケーション手段を使うと、 ネイティブや言語力に自信がある人の意見は出るものの、そうではない人たちが黙ってしまい、結果的に双方向のコミュニケーションで合意を形成したり、発想を刺激し合ったりという目的が達成できなくなってしまう。
Tenzerらの研究では、非ネイティブの話者にとっては、メールやチャットのような「薄い」コミュニケーション手段の方が、むしろ、自分の考えを落ち着いてまとめられるため、意見を表明しやすい手段であるということが明らかになった。そのため、「薄い」手段の方が、むしろ「濃い」コミュニケーションになるという一見矛盾した結果になるのだ。
この研究からいえることは、コミュニケーション手段の選択においては、単純にどのようなトピックかということだけでなく、参加するメンバーの言語能力にも配慮する必要があるということだ。仮に、日本人同士のコミュニケーションであれば電話会議やテレビ会議が適している場合でも、さまざまな母国語の人たちを交えて行う場合も、同じようとは限らない。むしろ、メールでじっくりと考えを関係者の間で交換するような形の方がいいかもしれない。
昨今は、電話会議やテレビ会議をはじめとして、様々なコミュニケーション手段が利用できる企業が増えてきているが、どの手段を用いるか、ということを意識的に判断することで、拠点を超えたコミュニケーションの質、効率を高めることができる可能性があるのだ。
参考文献
Aichhorn, N. & Puck, J. 2017. Bridging the Language Gap in Multinational Companies: Language Strategies and the Notion of Company-Speak. Journal of World Business, 52(3): 386-403.
Ashforth, B. E., Harrison, S. H. & Corley, K. G. 2008. Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions. Journal of Management, 34(3): 325-374.
Neeley, T. B. 2013. Language Matters: Status Loss and Achieved Status Distinctions in Global Organizations. Organization Science, 24(2): 476-497.
Tajfel, H. 1978. Social Categorization, Social Identity and Social Comparison. In H. Tajfel (Ed.), Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations: 61-76. London: Academic Press.
Tenzer, H. & Pudelko, M. 2016. Media Choice in Multilingual Virtual Teams. Journal of International Business Studies, 47(4): 427-452.
佐藤, 智恵; ハーバードの留学生が思わず涙する「楽天の英語公用語化」の授業; ダイヤモンド オンライン
http://diamond.jp/articles/-/80734
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










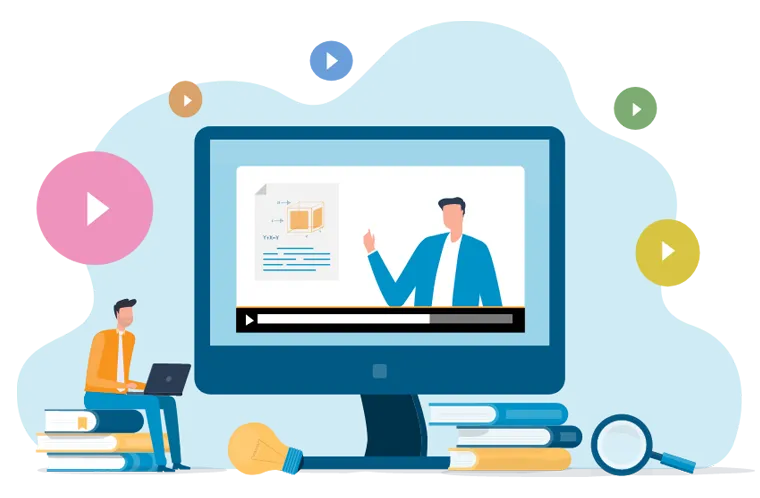 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で