連載・コラム
国際経営研究の現場から 第7回
人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 公開日:2015/06/24
- 更新日:2025/04/15

多国籍企業は、文化や制度が異なる多様な国々でビジネスを行っているため、それらの違いに配慮することが必要である。一方で、 国を越えて、1つの企業としての一貫性を保つ必要も同時に存在する。 この 「現地への適応」と「グローバルでの統合」という2つのプレッシャーにどう向き合うか、ということが国際経営の本質の1つといってもいいだろう。今回は、国際人事に関する研究をもとに、人事施策における2つのプレッシャーとの向き合い方について考えてみたい。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
現地適応 vs. グローバル統合
国際経営においては、「現地への適応」と「グローバルでの統合」というのは古くて新しい議論である。進出先の各市場に特有のニーズに応える上では、各拠点で独立した意思決定を行い、適応を行うことが重要となる。一方、経営資源を最適配置したり、規模の生産性を追求したりする上では、中央集権的に意思決定を行い、各拠点での活動をコントロールしていく、グローバル統合が必要になる。
この2軸の観点から、多国籍企業の戦略および組織の特徴を類型化したBartlett and Ghoshal (1989)のフレームワーク(図表01)は、日本でもビジネスパーソンの間で比較的知られているのではないだろうか。この枠組みは、現地にある程度の権限を委ねつつも、経営の根幹は本社でコントロールをするInternational モデル、世界の意思決定を中央集権的に行うGlobalモデル、各地に権限を委ね、全体としては緩やかな連合体として経営を行うMultidomesticモデル、そして、世界に分散する機能がネットワークとして有機的につながり、部分の強みを全体に活かすことを志向するTransnationalモデルの4つから構成される。
図表01 Bartlett and Ghoshal (1999)による多国籍企業の類型
による多国籍企業の類型.gif)
Bartlett とGhoshalは、複雑で激しい競争環境においては、効率性、個別対応、そしてそれぞれの拠点間での学習、という3つの要素をすべて兼ね備えるTransnationalモデルが主流になるだろうと主張した。しかし、 Transnationalモデルの企業は実際にはほとんど存在しないのではないか、という指摘も同時に存在する点には注意が必要である。権限を分散しつつ、それぞれが有機的につながるというのは、概念としては美しいが、 実行するのは難しい。 本稿では、紙幅の関係上、これ以上の議論は行わないが、 現実的には、「現地への適応」か「グローバルでの統合」のいずれかにウェイトをおいた経営が行われているのが実情なのかもしれない。
さて、では人事においてはどうだろうか。Schuler, Dowling, and De Cieri (1993)は、多国籍企業が各国にさまざまな機能を配置し、各国で異なる環境で活動している 以上、人事は、「各拠点の拠点戦略に基づく、 現地環境のなかでの円滑な運営」と「そうした異なる各拠点を1つにつなぎ合わせること」に貢献する必要があるとしている 。拠点により戦略が異なる以上、各拠点の人事施策も異なっていて当然である。また、 前々回、前回に議論したとおり、労働市場のあり方や、有効なリーダーシップスタイルが国によって異なる以上、そうした違いを踏まえ、各地の環境に合わせた人事施策を行っていくことが必要になる 。一方で、1つの組織としての一貫性を維持しようとすれば、拠点間での人の異動(本社から海外現地拠点への海外赴任や、逆に現地拠点から本社への逆出向など)や、共通の幹部教育プログラムなどによって、人のつながりや共通の考え方を作っていくことも必要になる。こうした点で、「現地への適応」と「グローバルでの統合」は人事においてもやはり重要な観点だと考えられるのである。
何を現地化し、何をグローバルで統合するのか? この問いは、日本企業のみならず、多国籍企業における国際人事を考える上では中核的な論点である。そこが定まらないことには、本社のグローバル人事を担う部門の役割も定まらないし、本社と海外現地拠点の人事の連携やつながりをどのように考えていくかについても、方針が定まらない。 では、どのような要因に考慮して、考えていけばよいのだろうか。
国際人事における「現地への適応」
財務や生産、研究開発など、ほかの機能分野と比べると、人事は相対的に見て「現地への適応」の傾向が高い機能であることが知られている。例えば、Rosenzweig (1994)はアメリカ企業の海外法人に調査を行い、さまざまな機能部門の施策が「本社に近い」か「現地企業に近い」かを聞いている。そこから分かったのは、人事部門では、ほかの機能部門と比べて「現地企業に近い」ケースがかなり多く、逆に、財務部門などは、本社に近いケースが多いということであった。同じ管理部門でも、大きな違いが見られたのである。
では、こうした「現地への適応」が必要な理由は何だろうか? まず最初に考えられる要因は、前回も議論した文化の違いである。Schuler and Rogovsky (1998)は、文化によって好まれる報酬制度に違いがあることを示している。例えば、アメリカやイギリスのように、個人主義の社会においては個人の成果によって報酬が決まる制度(いわゆる成果主義)が好まれる、また、日本のように不確実性への耐性が低い社会では、給与が大きく変動するのではなく、安定的なことが好まれる、といったことが分かっている。このように、現地の人々の価値観に合った制度の方が、現地の人に頑張って働いてもらいやすい。このことは、人事における「現地への適応」の重要性の大きな要因であると考えられる。
また、もう1つのポイントは「制度化」の観点である。現地の企業において一般的に広く行われている施策は、「当たり前」のものになる。そして、そうした制度から逸脱することは「正当性に欠ける」ことだとみなされがちなのである。Zaheer (1995)は、多国籍企業が、現地の制度環境と異なる施策を持ち込むことで負うハンディキャップのことを「liabilities of foreignness(外国的であることの負債)」と呼んでいる(ただし、Zaheerの議論は人事に限らない)。「欧米流のやり方は日本になじまない」といった意見は、まさにliabilities of foreignnessを象徴するものだといえるだろう。
例えば、日本においては、新卒一括採用を行い、給与がある程度安定的で、雇用が守られることが「当たり前」だとみなされる傾向が強い。 逆に、そうした施策から逸脱すると、奇異の目で見られがちである。そのため、こうした壁を乗り越えるには、 海外から来た企業であっても、日本の慣行に合わせて人事施策を作っていく方が良い、ということになる。その方が、日本の「当たり前」に慣れた人材から見て、軋轢が生じにくいのである。ただし、もちろん、全員が一律に反応するわけではない。例えば、外資系企業のなかには必ずしもそうした日本的な慣行には従わない企業が存在するが、そうした企業を好む人たちも日本人のなかには存在することは、皆さんご存じのとおりである。むしろ、外資系企業の方が「グローバルスタンダード」であるがゆえに、より正当性があるとみなす人々もいるだろう。
また、制度という観点では 、現地の雇用法令への準拠も重要である。例えば、解雇に関する法律は国によって大きく異なる。日本では解雇が難しいことは皆さんご存じのとおりだが、同じヨーロッパの国の間でも、イギリスとフランスでは、後者の方が、はるかに労働者保護が厳しく、解雇が難しい(Eyraud, Marsden, & Silverstre, 1990)。また、保険や年金などの制度も各国で異なっているし、外国人雇用に関するビザの規定などもさまざまである。
人事機能は現地の人材を対象にするものであるだけに、こうした文化や制度の影響を強く受けやすいと考えられる。もちろん、財務部門も現地の法制度に合わせる必要は少なからずあるだろう(文化の影響はあまり考えにくいが)。しかし、 拠点を越えて財務データを一貫して管理することの経営上の重要性を考えれば、外部の環境に合わせることよりも、むしろ、内部で処理を一貫させることが優先されるのは、自然なことのように思われる 。それに比べ、人事施策を世界的に一貫させる必要性は、そうはいっても限られる、というのが国際経営研究における伝統的な見方である。
国際人事における「グローバル統合」
前節では、一般論としての人事における「現地への適応」の重要性を議論してきた。しかし、当然ながら、現地適応とグローバル統合の相対的なウェイトは、企業によって異なる。Scullion and Starkey (2000)は、事業運営上の中央集権的なコントロールが重要なほど、本社人事がもつ影響力が大きい、ということを示している。こうした企業では、本社人事が主導する形での管理職育成やサクセションプランニング(幹部の後継者候補の選抜と育成計画の立案・実行)がより幅広く行われ、また、実際の幹部人材の配置や給与水準の決定にも本社が関与することが多い。
また、時系列で見て、相対的に人事施策のグローバル統合の重要性が高まっている、と指摘する研究も見られる。例えば、Evans, Puick, and Barsoux (2002)は、さまざまな企業において、従来と比べて事業上の統合の必要性が高まっており、その結果として、(従来、現地適応が重視されてきた)人事においても、統合の必要性が高まっている、と指摘している。
さて、では、具体的にはどのような領域で、人事施策の統合化が進んでいるのだろうか? 第一に考え付くのは、上述のとおりサクセションプランニングや幹部の配置、報酬などの領域である。Burbach and Royle (2010)らは、こうしたいわゆる、タレントマネジメントの領域において、グローバルに共通のプロセスや基準、さらにそれを支える横断的なITシステムが導入されつつある、ということを指摘している。この領域は比較的、必要性が分かりやすい。幹部が共通言語、共通の考え方をもち、互いに顔見知りであることは、柔軟な連携や調整を行っていく上では不可欠だからだ。事業運営上のニーズに直結した人事統合化施策だといえる。筆者が見聞きしている限り、日本企業においても、この動きは共通であるようだ。 従来、本社人事は国内の人事施策を統括し、現地のことは現地に任せるという、分権的な人事管理が一般的であった。しかし、外国人管理職を登用し、幹部層の多様性を高めていこうという動きのなかで、世界共通の管理職教育の仕組みを導入したり、世界横断的にサクセションプランニングを導入したり、といった取り組みも広まりつつある。
ただし、これ以外の領域でもさまざまな領域で、グローバル統合化の事例は見られる。例えば、Fichter, Helfen, and Sydow (2011)は、 国際的な労働組合の連合からのプレッシャーを受けて、労働環境に関する基準をグローバルに展開している多国籍企業の事例を報告している。各国によって安全衛生基準など労働環境の基準は大きく異なる。総じて、先進国と比べ途上国の方がそうした基準は緩く、コストを考えれば、現地基準で現場を運営した方が効率的である。また、自社内でそうした緩い基準を利用しないにしても、現地基準で操業している現地企業にアウトソーシングを行うことで、コスト優位を得ることができる。しかし、多国籍企業のこうした動きに対抗して、労働組合が国際的に連合し、 プレッシャーをかける動きが出ているのである。
また、Sippola and Smale (2007)は、ダイバーシティマネジメントに関する方針や施策がグローバルに展開されている事例を報告している。この研究で興味深い点は、国によって多様性のあり方が異なる(移民が多く、そもそも労働者の多様性が高い国もあれば、全くそうではない国もある)ことが、そうした施策の展開の妨げになっている点である。やはり、幹部のタレントマネジメントのように、グローバルに拠点を越えて共通化することの必要性が分かりやすい領域と、より現場に近く、個別事情への配慮が必要な領域の違いがあることが読み取れる。
これらの事例から考えると、人事施策のグローバル統合を考える上では、大きく3つの要素を見ていく必要があるといえそうだ。1つ目は、戦略上、事業運営上のニーズである。Globalモデルにせよ、Transnationalモデルにせよ、統合の重要性が高い場合には、なんらかの形で人事面でも統合が必要になる。従来の日本企業においては、白木(2006)が指摘するように、各国に赴任する日本人が共通の仕組みで管理され、現地の人材は現地ごと、という形での統合が一般的であった 。しかし、現地の人材を登用した上で、グローバルに統合した経営を行おうとすれば、現地の人材も含めた人事施策の統合が必要となってくる( 一方で、Multidomesticモデルを適用し、各地に合わせた経営を行う場合、人事統合の必要性は限られる)。企業のなかでも、こうした性格が大きく異なる事業がある場合には、それぞれで人事のアプローチを変えることも必要かもしれない。
2つ目は、 グローバルな外圧の存在である。上述のように、労働環境に関しては各国の制度に準拠するだけでなく、国や地域を越えて 「望ましい」労働環境を提供することが多国籍企業の社会的責任だとみなされるようになってきている。国連が主導するグローバルコンパクト(人権、労働、環境、腐敗防止の4領域についての行動原則)への参加なども、こうした動きの1つといえるだろう。こうした、国を越えたプレッシャーが存在する領域では、人事施策のグローバル統合が必要になる。いわば、グローバルなCSR(企業社会責任)施策としての統合である。
そして、3つ目は、個別環境への配慮の必要性の程度である。人事施策のなかでも、現地の文化や制度の影響が強い領域と、自社の思想や基準を展開しやすい領域がある。 幹部の登用や配置は、相対的には後者に当てはまるだろう。現地の文化の影響が強い領域でグローバル統合を進めることは、必要以上の軋轢を生むことにつながるかもしれない。言い換えれば、グローバル統合だけを考えることには無理があり、現地適応とのバランスを考える必要がある、ということになる。
「現地適応」と「グローバル統合」のバランスを誰が取るのか
これまでの議論を整理したのが図表02である。文化的差異と制度的差異が、現地への適応の必要性を生む一方、事業上の統合の必要性や、国際的な圧力の存在が、グローバル統合の必要性を生む。そして、人事のなかでも領域により、これらの影響の強さは異なると考えられる。
図表02 人事における現地適応とグローバル統合に影響する要因

そして、ここで重要なのは、これらの要素は固定的ではないということだ。各国の文化が短期で変化することは考えにくいが、制度環境はより短い期間で変わりうる。特に、新興国においてはさまざまな法令の改革によって、制度環境が変化することはよく見られる。 一方で、事業上の統合の必要性や、国際的な圧力の存在も、時期によって変化するものと考えられる。
このことは、グローバル人事の体制を一度作れば終わりではなく、内外の環境の変化を踏まえ、現地適応とグローバル統合のバランスを取り直すことが求められるということを示唆している。特に、各国に任せる形で分権型の人事を行っている際には、内外環境の変化への適応は比較的分かりやすい(各国の人事が、各国の制度の変化に合わせて対応すれば良い)。しかし、現地適応とグローバル統合の両者の要素を併せ持って人事を運営していく場合には、より話が複雑になってくる。グローバルを統括する本社人事と、現地の変化を掴んでいる現地人事の間でコミュニケーションをとり、施策を見直し、展開していく必要があるからだ。
こうした調整をうまく進めるためには、本社人事と、現地人事の間での相互交流を通じた共通言語づくりや信頼構築、また、日々の コミュニケーションの密度を高めるためのインフラ構築といった取り組みが必要になると考えられる。一部の企業で行われている、グローバルに人事関係者を集めた会議の定期的な開催、海外法人から本社への人事担当者の逆出向、また、本社人事の現地法人の訪問などは、グローバルな人事基盤を作っていく上で有効だろう。また、拠点間でのテレビ会議などの、コミュニケーション基盤の導入も同様だ。さらに、英語にせよ日本語にせよ、コミュニケーションの標準言語について、一定の 能力を本社、各地の人事がもつことも必要になると思われる。
最後に
今回は、人事の現地適応とグローバル統合について考えてきた。人事はほかの部門と比べ、現地に適応することの重要性が伝統的には高い部門である。しかし、事業の統合や、国際的な圧力などの影響から、グローバルに人事施策を統合しようという動きが、広く見られるようになってきている。このように、現地適応からグローバル統合に向けて力点を動かしていく際には、現地人事と本社人事の間での、共通言語づくり、信頼関係づくり、そして日々のコミュニケーションを円滑にするためのインフラづくりが重要となる。言い換えれば、グローバルな人事のネットワークの組織能力を再構築することが必要になる。そして、日本企業において最大の壁となりそうなのが言語である。日本語ができる人事を世界中に確保するのは難しいことを考えると、英語が日本の人事において必修言語となる日は近いのかもしれない。
REFERENCES
Bartlett, C. A., & Ghoshal, S. 1989. Managing Across Borders: The Transnational Solution. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Burbach, R., & Royle, T. 2010. Talent on demand? Talent management in the German and Irish subsidiaries of a US multinational corporation. Personnel Review, 39(4) : 414-431. doi: 10.1108/00483481011045399
Evans, P., Puick, V., & Barsoux, J.-L. 2002. The global challenge, frameworks for international human resource management New York: McGraw-Hill.
Eyraud, F., Marsden, D., & Silverstre, J.-J. 1990. Occupational and internal labour markets in Britain and France. International Labour Review, 129(4) : 501-517.
Fichter, M., Helfen, M., & Sydow, J. 2011. Employment relations in global production networks: Initiating transfer of practices via union involvement. Human Relations, 64(4) : 599-622. doi: 10.1177/0018726710396245
Rosenzweig, P. M. 1994. Management practices in US affiliates of foreign-owned firms: Are “they” just like “Us”? The International Executive, 36(4) : 393-410.
Schuler, R. S., Dowling, P. J., & De Cieri, H. 1993. An Integrative Framework of Strategic International Human-Resource Management. Journal of Management, 19(2) : 419-459. doi: 10.1177/014920639301900209
Schuler, R. S., & Rogovsky, N. 1998. Understanding Compensation Practice Variations across Firms: The impact of National Culture. Journal of International Business Studies, 29(1) : 159-177.
Scullion, H., & Starkey, K. 2000. In search of the changing role of the corporate human resource function in the international firm. International Journal of Human Resource Management, 11(6) : 1061-1081.
白木三秀 2006. 『国際人的資源管理の比較分析「多国籍内部労働市場」の視点から』(有斐閣)
Sippola, A., & Smale, A. 2007. The global integration of diversity management: a longitudinal case study. International Journal of Human Resource Management, 18(11) : 1895-1916. doi: 10.1080/09585190701638101
Zaheer, S. 1995. Overcoming the Liability of Foreginness. Academy of Management Journal, 38(2) : 341-363. doi: 10.2307/256683
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










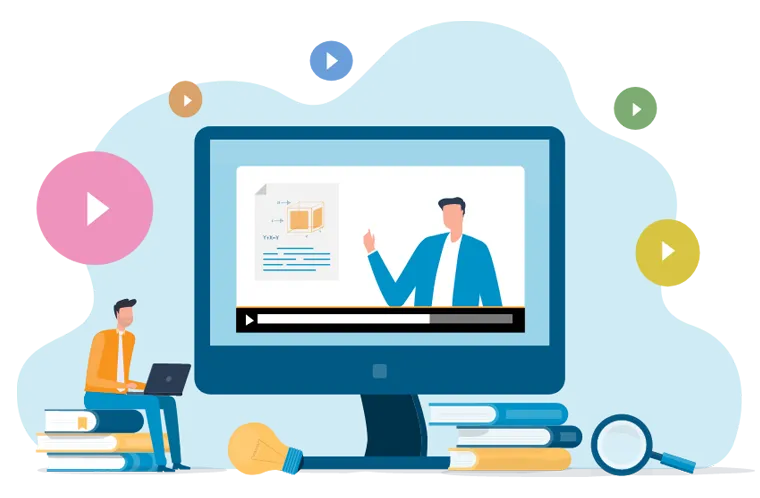 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての