連載・コラム
国際経営研究の現場から 第3回(前編)
AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 公開日:2014/07/23
- 更新日:2025/04/15

今回は、これまでの2回の連載のスタイルを少し変更し、2014年6月21日~26日に開催された2つの学会、AJBS (Association of Japanese Business Studies/日本ビジネス研究学会)および、 AIB (Academy of International Business/国際ビジネス学会)についてご報告する。まず、前編では前者についてご報告する。後者についてのレポートと合わせてご覧いただきたい。
さて、まず簡単にAJBS(日本ビジネス研究学会)についてご紹介すると、その名のとおり、日本および日本企業に関する研究にフォーカスした学会である。90年代に日本企業が世界的に注目を集めた時期に設立され、今年で設立27年となる。
筆者は2012年より本学会に出席しており、今回で3回目となる。AIB(国際ビジネス学会)が世界中から国際ビジネスについて研究する研究者が集まるかなり大きな学会(参加者は1000人を超える)であるのと比べ、AJBSの参加者は90人に満たず、毎回参加している顔見知りの研究者が多い。例年、AIBの開催前に同じ都市で開催されることとなっているため、必ずしも日本で毎回開催される訳ではなく、ワシントンD.C. (2012年)、イスタンブール(2013年)を経て、今年はバンクーバーでの開催となった。
本レポートでは、筆者が参加したセッションのなかから、日本で人材マネジメントに関わる皆さんに示唆があると思われるポイントをご紹介したい。
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
国際経営における立地選択と、都市の魅力
バンクーバーと言われて、読者の皆さんは何を思い出されるだろうか? スポーツに関心のある方は、冬季オリンピックを思い出されるかもしれない(ソチの一つ前、2010年の冬季オリンピックはバンクーバーで開催された)。また、海に面していながらも山や森林等が近隣にあるという自然の豊かさから、世界でも有数の住みやすい都市としての評価も高い。しかし、ビジネスという点では、バンクーバーについてはあまりイメージが湧かない方が多いのではなかろうか。
しかし、バンクーバーは実は、ソフトウェアおよびコンピューターでの映像処理に関する世界的な産業集積地(クラスター)という側面をもっている。本学会の冒頭では、この現象に焦点を当て、現地に拠点を置くバンダイナムコおよびDeNAの現地拠点の幹部、また、ブリティッシュコロンビア州(バンクーバーが所属する行政区分)の企業誘致責任者を招いてのパネルディスカッションが行われた。もちろん、議論のポイントは、何がそうした企業をバンクーバーに引き寄せるのか? ということである。

各パネリストからの話を筆者なりに要約すると、(1)地方自治体からの税金面も含めた有形無形のさまざまなサポート、(2)高レベルの教育を受けた専門的スキルをもつ人材の豊富さ、(3)ヨーロッパとアジアの中間に位置し、アメリカ国内にも豊富なアクセスをもつ地理的、交通面での優位性、といったあたりが、どうやらポイントのようであった。
特に、ここでは(2)に注目したい。ソフトウェア開発やコンピューターグラフィックスの処理等は、確かに専門的なスキルを要する産業である。所謂製造拠点の誘致の際には、どちらかというと人件費の安さがポイントになりそうだが、こうした知的集約度の高い拠点を誘致する上ではそれは当てはまらない。必要なスキルを持つ人材がいなければ仕事が成り立たないためだ。
産業クラスターの研究は90年代以降盛んに行われてきた(シリコンバレーのIT集積が分かりやすいが、バイオやテキスタイル等、さまざまな産業のクラスターが存在する)。産業クラスターの形成には、関連業界の企業が集まることだけではなく、高等教育・研究機関が存在することも大きな役割を果たすことが知られている。企業との共同研究や、関連する知識・スキルを学んだ人材の輩出といった点で、地域における知識蓄積に寄与するのである。
バンクーバーもその例に漏れず、ある大学には、携帯電話やタブレット等のモバイル機器上でのソフトウェアおよび、サービス提供に特化した学位を取得できるコースが十数種類あるという。そうした機関を通じて、専門的なスキルを身につけた人材が豊富に供給されていることが、産業誘致上、大きな魅力となっているということであった。また、前述のとおり、バンクーバーはその住みやすい環境から、高度なスキルをもつ人材を、北米のみならず、世界中から引きつける魅力がある(実際に、街を歩いていると驚くほどアジア系の人をよく見かける)。さらに、(1)にも関わるが、就労許可の申請が大幅に簡素化されており、企業が人を動かしやすい、という点も魅力だとのことであった。
この話を聞いていて感じたのは、M&Aの買収先の評価の時点から人事が関わることの必要性が指摘されて久しいが、海外展開にも同じことがいえるのではないか? ということだ。もちろん、すべてのケースに人事が関わる必要は必ずしもないかもしれない。しかし、特に、知識依存型のハイスキルな人材を必要とする機能-例えば研究開発-を国際化していく際には、特に重要になるのではないだろうか。
多国籍企業の拠点の立地選択に関わる観点は多岐にわたる。多くの場合、税制上の優遇措置や、交通上の利便性、さまざまなオペレーションコスト、また市場へのアクセスのしやすさ、といった要素が、主要な論点になるだろう。そうした観点ももちろん重要である。しかし、我々人事に関わる立場からすれば、現地の労働市場が供給できる人材の質、また、コストといった観点も同時に重要である。進出先の労働市場に、現地の拠点が必要とするタイプの人材、特に質の高い人材が潤沢にいるか、また、日本やその他の国から人材を派遣することが相対的に行いやすいかどうか、といった点は明らかにその後の拠点の運営に影響するからだ。人材供給については、もちろん、自社内で育成することも1つの選択肢である。しかし、市場で潤沢な供給があるケースの方が、より有効に人材を拠点に蓄積していきやすいのも、事実だろう。また、人材の移動に関しては、赴任者を送り込む上で厳しい制約が存在する国も多く存在する。
国際的に、国家間、都市間で人材獲得、人材育成の競争が行われていることは、国際人事のコストや成果にも関わってくる。自社が必要としている人材は、世界のどこに存在するのか? 今後、ますますそうした議論が、国際人事には求められるようになっていくのではないだろうか。
言語ポリシーと知識移転
今回のAJBSでは、「言語」が国際経営に与える影響に関する研究がいくつか発表された。最近のJournal of International Business Studies(JIBS:国際経営に関するトップクラスの学会誌)でも、言語が国際経営において果たす役割についての特集が掲載されていたし、併催のAIBにおいても言語に焦点を当てたセッションが多く開かれており、この分野は国際経営研究の新しいトレンドといえそうである。改めて考えてみると、日本企業の人事の方から、組織をグローバル化していく上でのチャレンジとして、言語、特に英語力に関する問題意識を伺う機会は多い。国際言語である英語を母国語とするアメリカ企業やイギリス企業よりも、世界的に見て英語を苦手とする人が多い日本の企業にとってこそ、このトピックの重要性は高いのではないだろうか。
今回は、北陸先端科学技術大学院大学のVesa Peltokorpi准教授から、言語に関する研究が2つ発表された。そのうちの1つ、「海外拠点における言語ポリシー」と「現地法人から本社への逆知識移転」に関する研究をここでは報告させていただきたい。
一部の例外を除き、本社の所在地の言語(日本企業の場合は日本語)と、海外進出先の人材の母国語(例えばアメリカに進出した場合は英語)は異なる。その結果、多くの国に展開している多国籍企業のなかには、さまざまな言語を母国語とする従業員が存在することとなる。そのため、多国籍企業においては「世界横断で社内コミュニケーションに用いる言語」が決まっていることが一般的である(公式な場合もあれば、非公式に事実上、というケースもあるだろう)。また、複数の言語が同時並行で使われている場合も、少なからず存在する。日本企業の場合、筆者が見聞きする限り、英語を国際経営上の標準言語としているものの、日本人赴任者と本社の間では日本語が多用されており、日本語も事実上の標準言語になっているケースも多い。
Peltokorpi准教授の研究は、日本に進出している外資系多国籍企業の「現地法人」を対象にしたものだ。これら現地法人のなかには、多国籍企業としての標準言語(殆どの場合は英語)を話せることを採用の条件にしたり、また、入社後にトレーニングを提供したりして、標準言語を現地の人材にも徹底する施策を展開している企業が存在する。一方で、日本人は上述のとおり英語を苦手とする人が多いため、敢えてそうした形で英語力を問うことを行っていない拠点もあるようだ。こうした「言語関連のHR施策の実施状況」が、どの程度、「(日本国内の)現地法人から本社への知識移転」に影響を与えるかに着目したのが、今回の報告である。
知識移転は通常、2つの方向で起きる。本社からの技術やノウハウを現地法人に展開していく、「本社→現地法人」の知識移転と、現地法人が現地の市場の状況について収集した情報や、現地で開発されたノウハウ、技術等を本社に還流していく、「現地法人→本社」の知識移転だ。本研究の焦点は、後者である。こうした「現地法人→本社」の知識移転は、世界の多様性に素早く適応し、多様性をイノベーションの源泉として活かしていく、という観点で重要性が指摘されている。国際経営において、重要な組織能力の1つである。
この両者の関係が研究の焦点であるが、多くの読者の皆さんはすでに察しがついておられるのではないだろうか。そう、在日現地法人において、英語を重視した採用や教育が行われている会社ほど、「現地法人→本社」の知識移転が活発になされている、ということである。当たり前、に思えるかもしれないが、こうしたことを定量的に明らかにした研究はおそらく初めてだろう。
このことが日本企業に対して示唆することは、大きく2つある。まず、現地法人での採用において、日本語力を要件として求める、また、入社後に日本語の教育を行うことは、特に本社との知識の共有が重要な業務において、ポジティブな影響があると思われる、ということだ。もちろん、日本語を採用条件とすることは、採用時に考慮対象とできる人材のプールを狭めてしまうため、ネガティブな影響も十分に存在する。しかし、ここで敢えて指摘しておきたい点は、日本で営業している外資系企業にとっても、程度の差こそあれ同じようなことが起きているはずだ、ということだ。英語で業務の会話がこなせるレベルの語学力を日本で求めると、採用できる人材のプールは格段に狭くなる。それでもなお、こうした施策がポジティブな影響をもつ、という点は、注目に値する。現地の労働市場における日本語人材の供給量や、職務上の必要性を考慮する必要はあるものの、一考の価値はあるのではないだろうか。
もう1点は、本社の日本人の英語力についてである。日本の多国籍企業では、(ごく一部の国にのみ進出しているケースを除いて)殆どの企業で英語を標準言語にしているのではないだろうか。ただし、それは日本社内を除いて、である。本社においても英語を標準言語にし、幹部層も含めて英語をコミュニケーションに使うことを求めているケースはごく少数だろう。本研究の結果から示唆されるのは、赴任者だけでなく、現地とのやり取りが発生するであろう、本社のさまざまな部門、階層の人材の英語力を高めるような人事施策が、本社から現地法人への知識移転を促進するのではないか? ということだ(勿論、この予測が正しいかどうかは今後の研究が必要である)。
言語については、冒頭でも述べたとおり、AIBでもいくつか面白い研究が報告されていた。興味のある方は、AIBのレポートも、併せてご覧いただきたい。
日本の新卒労働市場における企業選択
最後に、South Australia大学のYanadori氏、大阪大学の関口教授、Yamaguchi氏らによる、日本の労働市場の構造に関する研究について紹介したい。本連載の趣旨である、国際経営研究という範囲からは少し離れるが、日本の新卒労働市場における企業選択の行われ方と、その結果として各企業が獲得する「人材の質」について定量的に分析した、斬新な研究である
本研究では、「サンデー毎日」に毎年発表される大学別の各企業への就職人数のデータと、ベネッセから発表されている大学入試難易度のデータを基に、各企業が新たに採用した人材群の「質」を定量化している。より難度の高い大学からの卒業生がたくさん入っている企業ほど、「よい質の人材群」を調達した、と見なすということだ。この手法自体、議論の余地があること(例えば、大学での教育の質が無視されている)は、発表を行った関口教授自身も言及されていたが、とはいえ、「人材の質」を定量化すること自体が難しいことを考えれば、かなり面白い試みである。

この方法を用いて、さまざまな年度に各社が獲得した「人材の質」に関するデータを定量化した上で、本研究では、「業界」としての特徴(業界全体としての成長度合いや、安定性)と、「企業」としての特徴(業界内でのシェアや相対的な業績の良さ)が、「人材の質」にどのように影響しているか、を分析している。ここから明らかになったのは、「業界」としての成長度合いや安定性が、結果として各企業が獲得する人材の質に大きな影響を与えており、「企業」レベルの特徴は非常に限られる、ということであった。言い換えれば、学生の多くはまずは業界というレベルで志望先を選択し、そのなかでの企業の違いについては、あまり大きな興味を払っていない(本人が意識しているかどうかはともかくとして、そのように行動・判断をしている)ということだ。
特に筆者が興味深く感じたのは、「業界の安定性」が新卒採用における企業選択にかなり強く影響する、ということだ。業績が上下に激しく振れるような業界は、たとえ成長傾向にあるとしても、なかなか人気を集めにくい、ということを意味する。これは日本の文化として「不確実性を好まない」傾向があることともマッチしており、面白い結果といえるだろう。新しい産業に本格的に人材が流入していきにくい、という、新卒に限らず日本の労働市場で広く見られる傾向を反映しているようにも思われる。
逆に言えば、こうした文化や制度が異なる国の大学生は、日本の大学生とは異なる企業選択をしているかもしれない、ということでもある。実際、セッションに参加していたアメリカの研究者は、経験則的にはアメリカの大学生は業界ではなく、個々の企業としての知名度や競争力により関心を払っているように感じる、とコメントを述べていた。業界別の特徴が大きな役割を果たすのは、日本固有の現象なのかもしれない。
日本以外の地域で新卒採用を行う日本企業も徐々に増えていることを考えると、こうした、各国固有の労働市場の特徴を明らかにしていくことは、国際人事にとっても重要なことだと思われる。日本とは異なる文化、制度をもつ国では、企業選択の基準も自ずと異なり、だとすれば、有効な採用施策も異なる、ということになる。国内と同じような基準で現地法人の採用を考えることはできない、ということだ。
終わりに
本レポートでは、AJBSのセッションのなかから、都市の競争力、言語と知識移転、日本の新卒労働市場における企業選択、という3つのテーマについて共有させていただいた。期せずして、いずれも人材の獲得に関わるテーマとなった。人材が企業の競争力の源泉として重要な役割を果たす、ということを考えれば、国際経営において、人材獲得の問題は無視できない観点である。今後も継続的に議論を深めていきたい。
PROFILE
吉川 克彦(よしかわ かつひこ)氏
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 客員研究員
1998年リクルート入社。
コンサルタントとして、経営理念浸透、ダイバーシティ推進、戦略的HRM等の領域で、国内大手企業の課題解決の支援に従事。
英London School of Economicsにて修士(マネジメント)取得。
現在は同校にて博士課程に所属する傍ら、リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所客員研究員を務める。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
次回連載:『国際経営研究の現場から 第3回(後編) AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告』
- 国際経営研究の現場から 第15回
- 言葉の違いへの対処 ~ Language Barriers in International Business ~
- 国際経営研究の現場から 第14回
- 企業公用語としての英語 ~English as a corporate language ~
- 国際経営研究の現場から 第13回
- 国際経営における女性の活躍 ~Women in International Business~
- 国際経営研究の現場から 第12回
- 複数の文化を生きる「バイ/マルチカルチュラル」な人たち
- 国際経営研究の現場から 第11回
- 自ら海外に飛び出し、現地で就職する人々
- 国際経営研究の現場から 第10回
- 「境界を超える」個人とその効用
- 国際経営研究の現場から 第9回
- テロリズム、紛争と国際ビジネス 〜危険にどう対処するか〜
- 国際経営研究の現場から 第8回
- 「遠くの親類より近くの他人」は正しいか?〜国際経営における距離〜
- 国際経営研究の現場から 第7回
- 人事施策を統合するのか、それとも現地化するのか
- 国際経営研究の現場から 第6回
- 文化・制度の違いとリーダーシップ
- 国際経営研究の現場から 第5回
- 制度の多様性〜「ゲームのルール」の国際的な違い〜
- 国際経営研究の現場から 第4回
- 海外赴任における適応
- 国際経営研究の現場から 第3回(前編)
- AJBS(日本ビジネス研究学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第3回(後編)
- AIB(国際ビジネス学会) 2014 Conference 参加報告
- 国際経営研究の現場から 第2回
- 自分を何者と捉えるか?〜グローバル組織におけるアイデンティフィケーション〜
- 国際経営研究の現場から 第1回
- なぜ、日本企業では“組織の国際化”が進まないのか
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










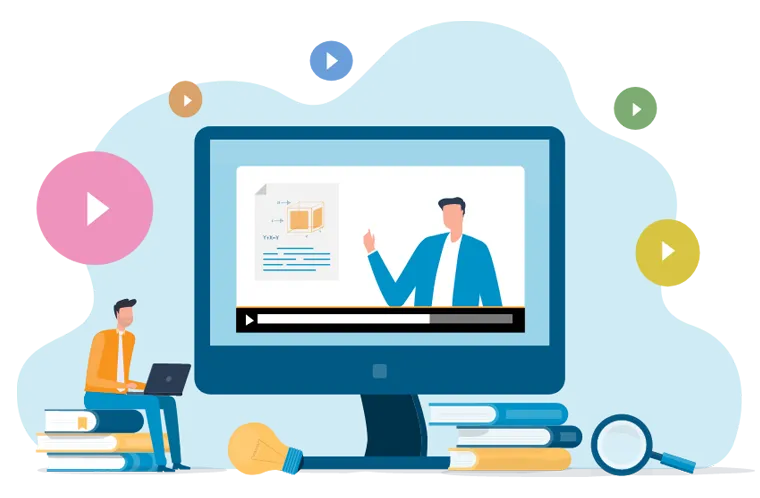 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての