用語集
内発的動機付けとは? 重要な理由やメリット・デメリットについて解説
- 公開日:2014/05/07
- 更新日:2025/06/25
社員の成長を促し、やる気を引き出す方法として、外部の報酬や評価に頼らず、個人の内側から湧き上がる意欲を育むことは、長期的な成果と満足度向上につながるとされています。
本記事では内発的動機付けについて以下の点を中心にご紹介します。
・内発的動機付けとは
・内発的動機付けが重要な理由
・内発的動機付けのメリット・デメリット
内発的動機付けについて理解するためにも参考にしていただけると幸いです。ぜひ最後までお読みください。
目標管理制度をうまく機能させる
「評価フィードバック力を高めるマネジメント研修 | FCMP」
内発的動機付けとは
内発的動機付けとは、内面に湧き起こった興味や関心、意欲によって動機付けられている状態のことです。この動機付けの要因は、金銭や食べ物、名誉など、外から与えられる外的報酬に基づかないものを指します。社会心理学者のデシによれば、内発的動機付けには有能感と自己決定感が強く影響するそうです。つまり、人は仕事をするなかで「能力を発揮できている」という感覚があるとき、また「自分自身で目的を定め、計画を立て、実行している」という感覚があるときに、内発的な動機を得やすいといえます。
外発的動機付けとの違い
内発的動機と外発的動機の違いは、その源泉が内面にあるか外部にあるかという点にあります。内発的動機とは、自分の興味や好奇心、やりがいを感じることが行動の原動力となるものです。例えば、趣味で読書をしたり、自分のスキルを向上させるために勉強する行為が挙げられます。一方、外発的動機は、報酬や評価、懲罰など外部からの働きかけに基づくものです。「お金をもらえるから働く」や「叱られないように作業をこなす」などがその例です。
内発的動機は、モチベーションが持続しやすく、自主性や創造性を高める効果があります。しかし、形成には時間がかかり、短期的な成果を求めるには向いていません。一方、外発的動機は即効性があり、関心が薄い人の行動を促すのに適していますが、効果が長続きしにくいという欠点があります。
このように、内発的動機は長期的な成長や継続性を重視し、外発的動機は短期的な成果や即効性を求める際に活用されます。それぞれの特徴を理解し、場面に応じて使い分けることが重要です。
内発的動機付けが重要な理由
ここでは内発的動機付けが重要な理由を解説します。
生産性を向上させる
内発的動機付けが重要な理由の1つに、生産性の向上が挙げられます。人が自らの興味や意欲に基づいて行動すると、仕事への没頭度が高まり、自然と効率的に業務を進められるようになるとされています。内発的動機付けがある人は、単に与えられた仕事をこなすだけでなく、課題を自発的に見つけ、解決策を考える意識が強くなる傾向があります。このような姿勢は、個々の行動量や集中力を高め、結果として組織全体の生産性を押し上げる要因となります。
また、内発的動機付けが高い状態では、創造的なアイディアが生まれやすく、問題解決や業務改善の際に新たな視点を提供することが可能とされています。例えば、仕事に対する熱意や興味が高い人は、従来の方法にとらわれず、より効率的なプロセスを提案することがあります。これにより、組織の活性化や成長にもつながります。
特に労働人口が減少し、効率的な働き方が求められる現代では、内発的動機付けを育むことがますます重要です。一人ひとりが主体的に行動できる環境を整えることで、持続的な生産性向上が期待できます。
多様な働き方に対応できる
内発的動機付けが重要な理由の2つ目に、多様な働き方への対応が挙げられます。現代では、フリーランスやリモートワークなど、働き方の選択肢が増え、従業員が自身に合ったスタイルを選べる環境が整いつつあります。この変化により、報酬や昇進などの外発的な動機だけではモチベーションを維持しにくい状況が増えています。そのため、内発的動機付けが重要視されるようになっています。
内発的動機付けは、自分にとって意味のある仕事ややりがいを見出す力となり得ます。このようなモチベーションを持つことで、自律的かつ柔軟に働けるため、個々の働き手が環境に左右されずに成果を出せるようになります。例えば、テレワークの環境でも、仕事に対する意欲が高い人は自己管理能力を発揮し、業務を効率的に進めることが可能とされています。
また、企業にとっても、内発的動機付けを引き出せる環境を整備することは、有能な人材を長期的に維持するうえで重要です。多様な価値観に対応できる職場を実現することが、組織の成長に寄与すると考えられています。
離職率を下げる
内発的動機付けが重要な理由の3つ目に、離職率を下げる効果があります。内発的動機付けにより、従業員が仕事を通じてやりがいや達成感を得られるようになると、職場の雰囲気がよくなり、連帯感や協力意識が高まるとされています。これにより、目標達成に向けて互いに支え合う環境が生まれ、「この職場で働き続けたい」と感じる人が増えると期待できます。
現代では、終身雇用制度の崩壊や転職のハードルが下がったことから、外発的動機だけに頼った働き方では、待遇がよい企業に人材が流れるリスクが高まります。そのため、「この職場だからこそ得られる経験がある」と思える環境を整えることが、優秀な人材の定着につながります。
内発的動機付けは、外部の報酬や評価だけでは補えない「仕事の意味」を従業員が感じる基盤となります。このような職場環境を築くことで、離職率を低下させ、長期的な組織の安定と成長が期待できるでしょう。
内発的動機付けのメリット
内発的動機付けのメリットを2点紹介します。
長期的にモチベーションを維持できる
内発的動機付けのメリットの1つとして、長期的にモチベーションを維持しやすい点が挙げられます。これは、個人の興味や価値観に基づく動機が行動の源になっているためです。外部からの報酬や強制に依存せず、心から「やりたい」と思える状態が続くことで、困難な課題にも粘り強く取り組めるとされています。
例えば、自己成長や新しいスキルの習得を目指す際、内発的動機は学習への意欲を高め、達成感を得るプロセスを楽しむ姿勢を支えます。このようなやる気は、短期的な成果を求める場面だけでなく、長期的な取り組みにも適しているといわれています。
また、内発的動機付けによる行動は、本人の心理的な安定感を高めると考えられています。興味を持ったことを追求する過程がポジティブな影響をもたらし、学びや挑戦を継続する力を後押しする可能性があるでしょう。このように、内発的動機付けは、持続性の高いモチベーションの維持に役立つとされています。
仕事の満足感・幸福感を向上させる
内発的動機付けのメリットの2つ目に、仕事の満足感や幸福感の向上が挙げられます。これは、自分自身の興味や価値観に基づいて行動することで、仕事そのものを楽しめる可能性が高まるためです。例えば、自分が取り組みたいと感じる業務に熱中すると、達成した際に外的な報酬に頼らない深い満足感を得られるとされています。
このような感情は、達成感や自己効力感を生み出し、次の挑戦への意欲を高めると考えられています。また、行動そのものに喜びを感じることができれば、日々の仕事に対するポジティブな姿勢が養われ、結果として幸福感の向上につながる可能性があるでしょう。
さらに、内発的動機付けに基づく満足感は、外的報酬の有無にかかわらず持続的に得られる点が特徴です。このことは、長期的に安定したモチベーションを保つうえでも重要とされています。個人の仕事に対する満足感を高めることで、全体の働く環境にもよい影響が期待できるでしょう。
内発的動機付けのデメリット
次に内発的動機付けのデメリットを3点紹介します。
動機付けされるまでに時間がかかる
内発的動機付けには多くのメリットがありますが、一方で動機付けされるまでに時間がかかるというデメリットも存在します。内発的動機付けは、個人が自身の興味や価値観を発見し、それを行動の原動力とするプロセスを必要とします。そのため、即効性が求められる場面や短期間で成果を出す必要がある場合には不向きとされています。
例えば、緊急性の高い課題や短期的な目標を達成する場面では、報酬や評価を用いた外発的動機付けの方がスピーディーに行動を促すと考えられています。一方、内発的動機付けが十分に育まれるには時間がかかるため、急な変化や結果を求められる場合には対応が難しい場合があるでしょう。
さらに、外発的動機から内発的動機へ移行するには、本人が行動の意義を見出すプロセスが必要とされます。この移行には時間がかかることが多く、組織やプロジェクト全体のスケジュールに影響を与える可能性もあります。こうした点から、内発的動機付けの活用には場面に応じた慎重な判断が求められるとされています。
標準化が難しい
内発的動機付けのデメリットの2つ目に、標準化が難しいという点が挙げられます。内発的動機は、個人の価値観や興味、関心に依存するため、全員に一律で適用することが難しいとされています。このため、企業が従業員の内発的動機を引き出すには、個別にヒアリングを行い、それぞれに合った対応をする必要があるでしょう。
さらに、個人の興味や関心には偏りが生じることがあり、組織全体で必要とされるスキルや知識が不均衡になる可能性も指摘されています。例えば、ある分野には強い関心を示す一方で、ほかの業務に対してはモチベーションが低い場合、業務配分や能力開発のバランスを保つことが課題になると考えられます。
また、内発的動機付けが効果を発揮しない従業員もいるかもしれません。そのため、外発的動機と組み合わせて、それぞれの従業員に合った手法を模索することが必要です。こうした対応には時間や労力がかかるため、組織全体で一貫性を持たせることが難しい点がデメリットといえるでしょう。
外部からのコントロールが難しい
内発的動機付けのデメリットの3つ目は、外部からのコントロールが難しいという点です。内発的動機は、個人の興味や価値観に基づくものであるため、外部から直接的に働きかけて高めることが難しいとされています。例えば、指示や命令によって動機を高めようとすると、結果的に外発的動機付けへとシフトし、自発的な意欲を損ねる可能性があるでしょう。
また、内発的動機は個人ごとに異なるため、組織全体で一律の方針を打ち出す際には、個々のモチベーションとのズレが生じることがあります。このようなズレは、組織の目標達成に対する貢献度に差を生む原因となると考えられます。さらに、内発的動機が強い人ほど、自分の興味を優先する傾向があり、組織の方針と一致しない場合には協調性や柔軟性を欠く場面が出てくるかもしれません。
こうした課題に対処するには、個々の自発的な行動を引き出す環境を整えることが重要とされています。例えば、目標設定や評価のプロセスの際に、個人の価値観や関心に配慮することで、組織としての一体感を保ちながら、内発的動機を促す取り組みが期待されます。
内発的動機付けを促す方法
最後に内発的動機付けを促す方法を5つ解説します。
有能感を高める
内発的動機付けを促す方法の1つに、「有能感を高めること」があります。有能感とは、自分の能力や成果が認められていると感じることで得られる感覚を指します。この感覚を高めることで、仕事に対するモチベーションを維持しやすくなるとされています。
有能感を高めるためには、従業員の成果を積極的に認めることが重要です。具体的には、上司が定期的に仕事の進捗や成果を評価し、適切なタイミングで褒めることが効果的と考えられます。直接の褒め言葉に加え、社内での表彰制度などを活用することで、従業員が自分の努力が組織にとって価値があると実感しやすくなるでしょう。
さらに、短期的なゴールを設定し、成功体験を積ませる方法も有効とされています。高すぎる目標は達成までの道のりが長くなり、途なかで挫折を招く可能性があります。そのため、達成しやすいミニゴールを設定し、目標をクリアするたびに自信を積み上げることで、内発的なモチベーションを育むことが期待できます。
このような取り組みにより、従業員が仕事に対してやりがいや達成感を感じやすくなるでしょう。
自立性・自己決定力を高める
内発的動機付けを促す方法の2つ目に、「自立性・自己決定力を高めること」があります。
自分自身で意思決定を行う経験は、個人の内発的動機を引き出すきっかけとなるとされています。意思決定には一定のストレスが伴うものの、自分の選択が仕事や結果に反映される実感が得られるため、モチベーションの向上が期待できるでしょう。
具体的な方法としては、部下やチームメンバーに裁量を持たせ、意思決定の場を提供することが挙げられます。例えば、業務改善に関する問いかけを行い、「どうやったらこの課題を解決できると思う?」と意見を求めることで、自ら考える機会を増やすことができます。
このような取り組みは、単に上司の指示に従うだけでは得られない満足感や達成感をもたらすとされています。
さらに、少し高いレベルの目標を本人に設定させる方法も効果的といわれています。自分で目標を立て、それを達成する過程で成長を実感できれば、次の目標設定に対する意欲も高まるでしょう。このように、自立性を高めることで、外発的動機付けから内発的動機付けへの移行を促すことが期待されます。
職場のチームワークを向上させる
内発的動機付けを促す方法の3つ目として、「職場のチームワークを向上させる取り組みが挙げられます。チーム内での信頼関係が強まると、職場の雰囲気がよくなり、互いに相談しやすい環境が整うとされています。このような環境では、従業員が自分の意見を表現しやすくなるため、内発的なモチベーションが高まりやすいでしょう。
具体的な方法として、課題解決に向けたブレストミーティングの実施や、社員同士の交流を深める研修の開催が効果的とされています。
また、仕事以外の場でチームの親睦を深めるためにレクリエーションを取り入れることも推奨されています。例えば、ゲームや軽いスポーツを行うことで、普段の業務では得られないリラックスした雰囲気が生まれ、自然なコミュニケーションの機会が増えるでしょう。
こうした取り組みを通じて、チーム全体のつながりが強化されると、従業員が組織への帰属意識を持ちやすくなり、個々の内発的動機付けを高めることにつながるとされています。結果的に、仕事に対する意欲が向上し、業務の質の向上が期待できるでしょう。
定期的にフィードバックを行う
内発的動機付けを促す方法の4つ目としては、「定期的なフィードバックの実施」が挙げられます。フィードバックは、従業員が自分の取り組みや成果を認めてもらい、さらに成長の方向性を見出すための重要な機会とされています。なかでも、よかった点を具体的に伝えることは、相手の満足感ややる気を引き出すきっかけになるでしょう。
例えば、「〇〇の取り組みが素晴らしかったです。これを生かしてさらに〇〇を意識すると、もっとよい結果が期待できると思います」などの具体的なコメントは、改善点を伝えつつ前向きな印象を与えるといわれています。
一方で、叱責や否定的な表現ばかりが続くと、従業員が「怒られないために行動する」という外発的動機付けに偏る可能性があるため注意が必要です。
また、フィードバックの頻度も重要とされています。定期的に行うことで、従業員が自身の進捗を確認しやすくなり、自分の努力が認められていると感じやすくなるでしょう。このプロセスが内発的動機付けの向上につながるとされています。
フィードバックは事実に基づき、相手の成功体験を引き出すような形で行うことで、仕事への意欲を持続させる効果が期待されます。
マネジャーのメンバーへの姿勢・関わり方が問われる象徴的な場面である“評価フィードバック面談”を題材にして、育成マネジメントの実践的な知恵・原則を身につける
評価フィードバック力を高めるマネジメント研修
適材適所を考慮する
内発的動機付けを促す方法の5つ目に、「適材適所を考慮する」ことが挙げられます。
人それぞれの得意分野や適性を理解し、それを生かした業務配分を行うことで、従業員がやりがいを感じやすくなり、モチベーション向上が期待されるでしょう。適性に合った業務に取り組むと、自信を持って業務を遂行しやすくなり、ストレスの軽減にもつながるとされています。
例えば、日常的に部下の仕事ぶりを観察し、定期的に面談を行うことで、それぞれの強みや関心を把握することが重要です。得意分野を任せるだけでなく、適性を考慮して新たな挑戦の機会を与えることで、成長意欲を引き出せる可能性があります。
ただし、適材適所を実現する際には、業務配分の理由を丁寧に説明し、従業員が納得できるようにすることも必要です。配慮が欠けると不満や誤解が生じる場合があるため、適切なサポート体制を整えることが大切とされています。
このように、個人の特性を考慮した配置や業務内容の割り振りは、従業員が主体的に仕事に取り組む環境づくりにつながるでしょう。
おわりに
ここまで内発的動機付けについてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。
- 内発的動機付けとは、個人の内面から生じる興味や好奇心を源とし、自分の意思で行動することで長期的な継続性や集中力を高める概念である
- 内発的動機付けは、生産性向上、多様な働き方への対応、離職率低下などを通じて、個人と組織の成長を支える重要な要因である
- 内発的動機付けは、長期的なモチベーションや満足感を高めるが、標準化や外部からのコントロールが難しく、即効性に欠ける面もある
内発的動機付けは、社員のやる気や満足度を高め、長期的な成長を支える重要な要素です。一人ひとりの内発的動機を引き出す取り組みは、組織全体の活性化にもつながるでしょう。本記事でご紹介した内容が、皆さんの職場での育成のヒントになれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
関連するサービス
Service
おすすめの
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

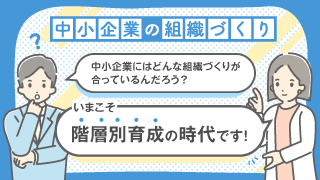
















 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての