特集
職場におけるマッチョイズム
男性性の高い組織について考える研究トピック
- 公開日:2025/07/07
- 更新日:2025/07/07

機関誌RMS Message78号では、「職場におけるマッチョイズムの功罪」というテーマで特集を組んだ。本稿では、先行研究のレビューとして、職場における「男性性」を競う文化(Masculinity Contest Culture:MCC)とは何かや、この文化がもたらす可能性のあるネガティブな影響について紹介する。また、この問題を考察する際に有用であると思われる視点として、(1)組織文化の影響をよりダイナミックに捉えるための「規範」、(2)男性性の特徴がデフォルトになっていることの弊害、(3)競争を心理学的に捉えるモデルについて取り上げる。
男性性の高い組織について考える視点
組織にはさまざまな問題が存在するが、セクシュアル・ハラスメントの研究で知られるBerdahlが、ハラスメントという事象にとどまらず、組織が男性性を多くもつことの問題点を指摘している*1。組織における「男性性」とは、積極的に競争し、他者を支配しようとする傾向とされている*2。組織が男性性、つまり男らしさを重視するようになると、職場は男らしさを競う場となり、仕事量の多さや長時間勤務を誇示したり*3、逆に自分に都合の良い手抜きをしたり*4、理不尽なリスクを背負ったり*5するようになると論じている。
男性性の高い組織は、高度成長期の日本企業の職場のように見えなくもない。その後、働き方改革が推進され、ハラスメントの対策が推進されつつある現在の日本において、組織における男性性の影響とはどのようなものだろうか。メディアで取り上げられるニュースを見ていると、日本の職場においても、同様の問題はまだ残っているように思われる。
本稿では、まずBerdahlを中心として行われている、組織における男性性の有害な点に着目した研究を紹介する。ただしこの視点での研究は新しく、一般化されるほどの実証研究の蓄積がないことから、この問題を考察する際に有用であると思われる他の視点からの研究もいくつか紹介する。具体的には、(1)組織文化の影響をよりダイナミックに捉えるための「規範」、(2)男性性の特徴がデフォルトになっていることの弊害、(3)競争を心理学的に捉えるモデルについてである。最後に、これらの視点から改めて組織における男らしさの競争が行きすぎる理由について考察する。
職場における男性性を競う文化
社会学の研究者によれば、ジェンダーは、人種や社会階級と同様に、個人、対人関係、集団のそれぞれのレベルで作用し、社会階層を生み出している*6。つまり、男らしさや女らしさは、生物学的な特徴というよりも、社会的に創られ、再生産された結果であり、男性的な男性は女性(あるいは男性的でない男性)よりも高い地位、大きな権力や特権をもつようになったと考えられている。
男らしさの定義は時代や場所によって変わる部分もあるが、不変的な要素もある。男らしさとは、優位な立場に立つことによって獲得され、達成されるものである。女らしさが与えられた特性として捉えられる傾向があるのに対し、男らしさは獲得しなければならないとされる*7。男らしさは社会的に獲得されるため、他者の評価に左右されるし、感傷的な感情を表に出したり、職を失ったりすることで、簡単に失われてしまう。
Berdahlらは、有害な男性性は「男性性を競う文化(Masculinity Contest Culture:MCC)」のもとで存在するとしている*1。MCCは有毒なリーダーシップ、いじめ、ハラスメントなどの組織の機能不全に関連し、女性だけでなく男性にとっても、幸福度の低下など望ましくない個人的な結果をもたらす。
MCCは次の4つの下位次元からなる。「弱さを見せない」は、迷いや心配がなく、過ちを認めない堂々とした自信につながる一方で、優しく女性的な感情を抑制する。「力強さとスタミナ」は、休憩なしで長時間働くなど持久力とスタミナがあることで、職場で尊敬され地位を得る。「仕事第一主義」は、家庭の事情などの個人的な要因が仕事に干渉することを容認せず、休憩や休暇をとらないことで、組織の中心になる。「食うか食われるか」は、職場を勝者が敗者を支配し搾取する場、戦いの場として特徴付ける。
ある警察組織を対象とした実証的研究では、MCCが高いと組織におけるインクルージョンや心理的安全性のレベルが低くなっている。加えて、個人のレベルでは、MCCのもとでは、仕事への不満や離職意向は上がり、心理的幸福が低下していた*8。
MCCの影響は、その文化をどう受け取るかの個人差によっても異なる。同僚が自分よりもMCCを強く支持していると思う人は、仕事の満足度や仕事へのコミットメント、さらに精神的健康が低下し、配偶者やパートナーとの関係葛藤が増加することが報告されている*9。仕事は成人の生活の大きな部分を占めるため、MCCは個人の全般的な精神的・身体的健康へのネガティブな影響がある。
男性性への脅威が、MCCに関連する行動をどのように動機付けるのかの検討を行った研究では、性格テストで女性的なスコアを獲得したと言われた男性参加者は、男性的なスコアを獲得したと言われた男性参加者よりも、より多くの性差別的発言を相手の男性に向けて行った*10。さらにこのような傾向は、参加者が女性的だと言われたことをネガティブに感じるほど強まったことから、脅威に直面して自分の男性性を再確認したいという欲求が高まることが、攻撃性につながったと考えられる。
男らしさを競う規範
MCCは男らしさを競う組織文化であるが、これが組織メンバーに有害な影響を及ぼす可能性について述べた。心理学における文化に関する研究の多くは、国や地域のレベルで行われており、そこでは主に価値観の差が扱われてきた。ところが残念ながら、職場行動における多くの重要な国際的差異は、価値観とはあまり相関しないし*11、価値観によって予測できる行動は限定的であるとの指摘もある*12。そこで、企業組織における特定の行動や態度を検討する際に有用なものとして、「規範」に着目する。
アメリカ合衆国の文化心理学の研究で著名なMorrisら*13は、中国やシンガポールの研究者と共同で、文化のダイナミズムを説明するために、規範が行動に及ぼす影響についてのモデルを提案している(図表1)。
<図表1>規範の要素と主な関連性の統合モデル
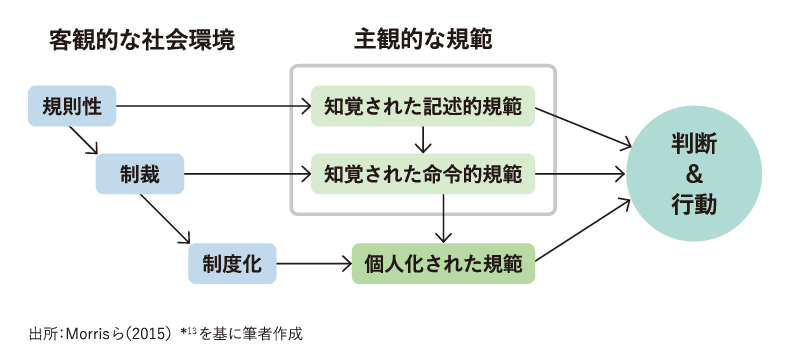
規範は、社会環境の客観的特徴を通して、特定される。最も基本的なレベルでは、規範は、集団の信念や行動に広く見られる「規則性」のなかに存在する。私たちは、一般に観察される行動や信念に従うことで、周囲とのコミュニケーションを円滑に行い、社会に適応する。社会環境で何がうまくいくかを経験することで、私たちのデフォルト(標準)と期待が形成される。社会環境のもう1つの特徴は「制裁」で、承認される行動か否かに応じて、報酬と罰を与えるものである。例えば、管理職は承認される行動をとる部下を高く評価することで、報いる。3つ目の社会環境の特徴は、「制度化」である。いくつかのパターンや慣習は、社会的に承認されるか否かにかかわらず、ルールとして扱われるようになる。例えば、交通のルールは最初、慣習として始まったが、時が経つにつれて法律として定められるようになった。
モデルでは、社会環境の特徴を通して、人は主観的な規範を認識するようになることが示されている。主観的規範には2種類あり、「記述的規範」は多くの人々がとる行動によって示され、その状況における適切な行動であると知覚することに基づく。「命令的規範」は、多くの人々によって、適切・不適切が一義的に知覚される。いずれも社会的に望ましい行為という点で、従うべきものである。規則性は知覚された記述的規範として、制裁は知覚された命令的規範として、そして制度化は人々の内面化に拍車をかけ、「個人化された規範」となる。
組織文化という大きな枠組でなく、特定場面の行動に着目することで、周囲が好ましいと思う行動がどのように集団内で拡散・維持されるかを考えることが容易になる。
男性性デフォルト(masculine default)
男性が多数を占める分野や職業における女性の地位改善に多くの企業が取り組んでいる。アメリカ合衆国は日本よりもその点でずっと先に行っているように思う。しかし、取り組みは十分な成果を上げられないことも多い。取り組みを成功させるために、男性性デフォルトと呼ばれる文化的バイアスを認識する必要がある*14。
男性性デフォルトとは、ある文化的側面が、男性の性役割に関連する特性や行動を、標準的で正当なもの、あるいは必要なものとして評価したり、みなしたりする場合に存在する。デフォルトと類似する概念に規範がある。規範は、行動を導く社会的に認められたパターンや基準である*13。規範はデフォルトでもあるが、デフォルトは行動以外のものを含むため、より広い概念とされる。例えば男性が多数を占める企業や職場において、組織文化の複数のレベル(個人、相互作用、組織方針など)でデフォルトは存在している。そして、男性性デフォルトを特定し、それに対抗する方法を考えることは、女性の参画を促進することに役立つと考えられる。
デフォルトの存在は、組織におけるモットーや重視されるアイディアなどに目を向けると、認識しやすい。図表2は、男性性と女性性の特徴をまとめたものであるが、自組織のどういった側面にこれらの特徴があてはまるかを考えてみることが、1つの方法として提案されている*14。ちなみにこの表にまとめられた特徴は現在のアメリカ合衆国におけるものであって、文化や時代によって変化するものであることに注意が必要である。また、図表2に示された男性性の特徴それ自体は決してネガティブなものではなく、ネガティブに影響する可能性のある文脈(例えば、女性活躍推進、メンタルヘルス)においてのみ、対抗策が必要なものである。
<図表2>アメリカ合衆国における男性性と女性性の特徴の典型例
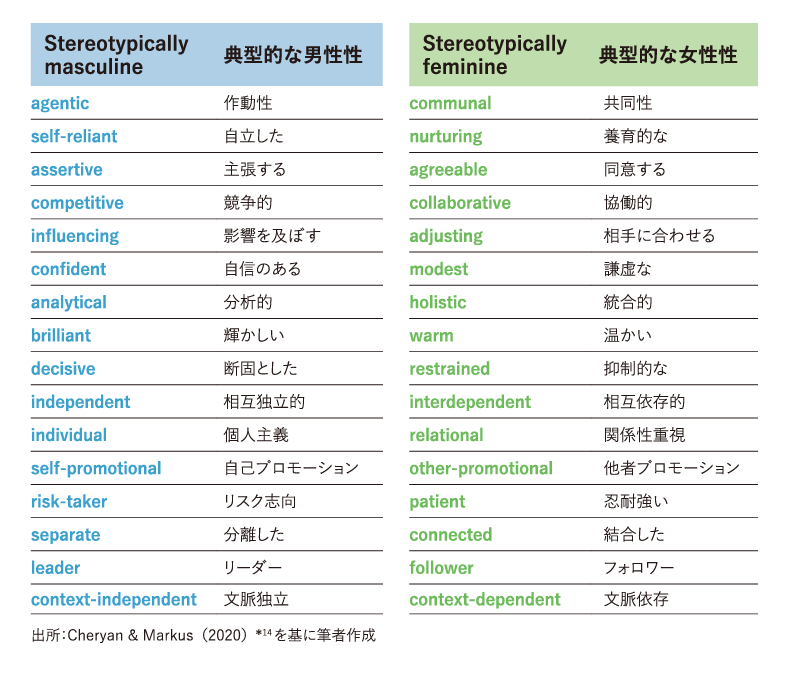
男性性デフォルトは女性活躍推進の文脈で提案された概念であるが、男性性が組織に及ぼす他の有害な影響を特定する際にも役立つ考え方である。デフォルトである以上、当然のように組織のなかにあるものであって、そのままだと意識することが難しい。既存の考え方やあり方について、なぜこうでなくてはいけないのか、という素朴な視点をもつこと、そのためには組織外からの意見や視点を取り入れることが求められる。
組織のなかの競争を考える
私たちは、人と自分を比較して、競争することがある。例えば、組織で同期と比較して自分の昇進が早い、遅いといったことに関心があり、負けたくないと思うことがあるかもしれない。他者との比較によって自己を評価する社会的比較は、競争行動の重要な源である。社会的比較理論*15によれば、私たちは他者の成果に追いつき、さらにその先に行こうとする欲求をもっているが、その結果、さまざまな競争的態度や行動が生じる。
人の社会的行動のうち、協力行動については心理学の研究が多くあるものの、競争行動については、相対的に研究が少ない。そこで、Garciaらは*16、社会的比較を理論的ベースに、競争行動を促進する個人要因と状況要因に着目したモデルを提案した(図表3)。
<図表3>競争の社会的比較モデル:個人要因と状況要因の内外の関係
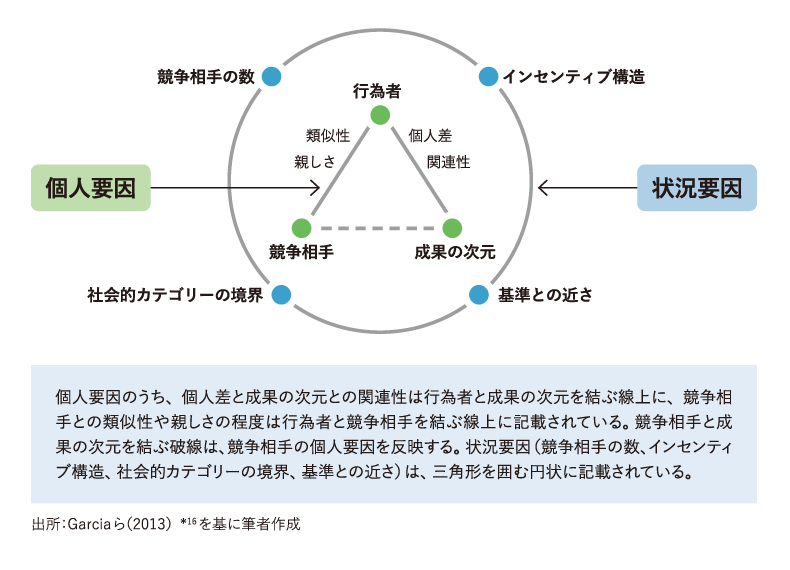
個人要因とは、成果の次元との関連性、競争相手との類似性、競争相手との親しさ、さらに一般的な社会的比較に関連するさまざまな個人差変数などで、競争の個人差となる。例えば次元の関連性について、初期の研究では、最初の言語課題が自分の知能に関連していると考えた参加者の方が、最初の課題が知能に無関係だと考えた参加者よりも、その後の交渉課題において、最初の言語課題の成績が自分よりも少し良かったと知らされた実験協力者に対して、より競争的に行動した*17。つまり自分に関連すると感じる課題において、より競争的になったのである。また、自分と似た相手や親しい相手の場合に、より社会的比較が促進され、競争的になることも示されている*18。
一方、状況要因とは社会的比較に影響を及ぼす状況の違いであり、同じ状況下の個人に対して、一般的な影響を与える。重要な状況要因として、競争の結果得られるインセンティブの構造がある。インセンティブへの期待が高いほど、比較に対する意識や競争心が高まる可能性がある。あるいは、一方の利益が他方の損失となる「ゼロサム」状況は、他者との比較への関心と競争心を高める*19。また、例えばランキング1位との近さなど基準との近さ、競争相手の数、相手が社会的カテゴリー内かカテゴリー外か、などがある。基準と近いほど、競争相手の数は少なくなるほど、相手が社会的カテゴリー外の人ほど、競争的になる。
これまで紹介した考え方を用いて、日本企業において男らしさの競争が行きすぎる理由を考えてみる。これまでの日本企業は、組織内メンバーの多様性が低く、しかも組織外とのメンバーの入れ替えが少ない。仕事の仕方も固定しており、それを踏襲する。このような状況では、組織内にさまざまな固定した規範ができることが予測できる。そしてその規範は、「この場面ではこうふるまうことが一般的である」との記述的な規範から、やがて「この場面ではこうふるまうべきである」との命令的な規範として認識されることになる。また、日本企業が成功を経験した際の組織の中心は男性であったため、男性性のデフォルトが存在することになる。加えて、周囲の組織メンバーと自分には類似する点が多く、昇進のインセンティブが1つの基準で決まること(失敗せず、会社の期待する結果を出しつづけること)は、組織内での競争心を高めることに寄与しそうである。
*1 Berdahl, J. L., Cooper, M., Glick, P., Livingston, R. W., & Williams, J. C. (2018). Work as a masculinity contest. Journal of Social Issues, 74(3), 422-448.
*2 Kupers, T. A. (2005). Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in prison. Journal of Clinical Psychology, 61(6), 713-724.
*3 Blair-Loy, M. (2005). Competing devotions: Career and family among women executives. Harvard University Press.
*4 Roth, L. M. (2006). Selling women short: Gender and money on Wall Street. Princeton, NJ: Princeton University Press.
*5 Iacuone, D. (2005). “Real men are tough guys”: Hegemonic masculinity and safety in the construction industry. The Journal of Men’s Studies, 13(2), 247-266.
*6 Risman, B. J., & Davis, G. (2013). From sex roles to gender structure. Current Sociology, 61(5-6), 733-755.
*7 Vandello, J. A., Bosson, J. K., Cohen, D., Burnaford, R. M., & Weaver, J. R. (2008). Precarious manhood. Journal of Personality and Social Psychology, 95(6), 1325-39.
*8 Rawski, S. L., & Workman-Stark, A. L. (2018). Masculinity contest cultures in policing organizations and recommendations for training interventions. Journal of Social Issues, 74(3), 607-627.
*9 Munsch, C. L., Weaver, J. R., Bosson, J. K., & O’Connor, L. T. (2018). Everybody but me: Pluralistic ignorance and the masculinity contest. Journal of Social Issues, 74(3), 551-578.
*10 Alonso, N. (2018). Playing to win: Male-male sex-based harassment and the masculinity contest. Journal of Social Issues, 74(3), 477-499.
*11 Kirkman, B. L., Lowe, K. B., & Gibson, C. B. (2006). A quarter century of culture’s consequences: A review of empirical research incorporating Hofstede’s cultural values framework. Journal of International Business Studies, 37, 285-320.
*12 Leung, K., & Morris, M. W. (2014). Values, schemas, and norms in the culture behavior nexus: A situated dynamics framework. Journal of International Business Studies, 46(1), 1-23.
*13 Morris, M. W., Hong, Y. Y., Chiu, C. Y., & Liu, Z. (2015). Normology: Integrating insights about social norms to understand cultural dynamics. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 129, 1-13.
*14 Cheryan, S., & Markus, H. R. (2020). Masculine defaults: Identifying and mitigating hidden cultural biases. Psychological Review, 127(6), 1022-1052.
*15 Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.
*16 Garcia, S. M., Tor, A., & Schiff, T. M. (2013). The psychology of competition: A social comparison perspective. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 634-650.
*17 Hoffman, P. J., Festinger, L., & Lawrence, D. H. (1954). Tendencies toward group comparability in competitive bargaining. Human Relations, 7(2), 141-159.
*18 Kilduff, G. J., Elfenbein, H. A., & Staw, B. M. (2010). The psychology of rivalry: A relationally dependent analysis of competition. Academy of Management Journal, 53(5), 943-969.
*19 Mittone, L., & Savadori, L. (2009). The scarcity bias. Applied Psychology, 58(3), 453-468.
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.78 特集1「職場におけるマッチョイズムの功罪」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
関連する研究テーマ
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
今城 志保
1988年リクルート入社。ニューヨーク大学で産業組織心理学を学び修士を取得。研究開発部門で、能力や個人特性のアセスメント開発や構造化面接の設計・研究に携わる。2013年、東京大学から社会心理学で博士号を取得。現在は面接評価などの個人のアセスメントのほか、経験学習、高齢者就労、職場の心理的安全性など、多岐にわたる研究に従事。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)












