- 公開日:2022/07/11
- 更新日:2024/05/16

環境が変われば、人事への期待や役割も変わっていく。
本稿では、人事を取り巻く環境と人事の役割の歴史について、研究・調査をもとにひもといていきながら、「現場を支える人事」について考察する材料の1つとしたい。
背景
弊社機関誌RMS Messageでは、2010年に人事の役割に関する特集を行った*1。そこでは、企業を取り巻く環境が人材マネジメントに影響し、それに伴い、人事への期待や役割も変わっていくということを扱った。企業外部の環境を「国内人口の減少」「高齢化」「価値観の多様化」と置き、そのような環境下においては、従業員の個々人の思いや自律的で持続可能なキャリア形成が重要で、経営と働く人との間での信頼醸成、チームビルディングなどのソフトイシューを扱うことが人事には求められると提唱した。また、働きがいやプライドをもたせ、個々人が知恵を出し合い、より創造的な職場を形成させていくことが人事の役割であると述べた。
現在も2010年と比べて、企業の外部環境は大きくは変わらないが、外部環境が人事に影響を与えている度合いが高まっていると感じる。例えば、14歳以下人口は、1990年から2030年の40年で半減していく*2が、その影響は表面化している。人材採用やリテンションに関して、それまで苦労が少なかった大企業でも人事課題として浮上している。
同様に、現在の人事課題である、シニア(アフターミドル*3)世代の活躍促進、エンゲージメント・ウェルビーイング向上、心理的安全性の重視、キャリア自律や働き方改革促進にも、「国内人口の減少」「高齢化」「価値観の多様化」の影響を受けている。
2010年時点で扱わなかった環境要因であるが、今後の人事の役割を考える際に大事な環境要因は「技術の発展」と「人的資本への注目」である。
「技術の発展」は、ビジネスそのものと共にHRテックのように人材マネジメントの手法に影響を与える。流通業界のeコマース、金融業界のフィンテック、自動車業界のCASEなどのように、ビジネスモデルの変革が起こり、それに従って、専門人材の採用、異動、再教育、組織文化の革新が人事課題になってくる。また、HRテックという点では、その技術が分かる人材を人事部門へ配属、採用、あるいは育成していくことが求められる。
加えて、米国証券取引委員会が上場企業に対して、人的資本に関する情報開示を義務付けたことをきっかけに、人的資本の開示が世界的な潮流になってきている。「自社の人的資本を把握すること」「それがどのように企業価値に貢献しているのかを分析すること」「人的資本を適切に活用するためにできること」「人的資本を増強していくこと」が企業人事の課題になっていく。
人事を取り巻く環境が変われば、人事の役割も変わっていく。ここでは、まず人事を取り巻く環境とそれに対応する人事の役割の歴史を、最初に見ていきたい。
人事を取り巻く環境と人事の役割の歴史
明治元(1868)年、最初の大企業である横須賀造船所では、すでに600人の労働者を擁しており、その後、近代化と共に大きくなっていった。同造船所は、徳川幕府がフランスから支援を受けて設立したもので、のちに新政府が引き継いでいる。日本史上初めての近代的な工場であり、試行錯誤しながら、独自の制度を構築していったが、そのなかには、長期雇用、年功序列賃金、企業内訓練、集団主義などの日本的労働慣行の原型がすでに揃っていた*4。
明治の時代(1868~1912年)から大正の時代(1912~1926年)を通して、日本は、急速に近代化していったわけであるが、この時期は、近代経営を確立した時期でもあり、日本企業に人事部門が広がっていった時代でもあった*5。その後、1950年代は労働運動が高揚していく時代であるが、そのような運動に対応するために、人事部は会社のなかでの影響力を高めていった。1970年代以降は、労働運動への対応という側面は低下していったが、終身雇用、ゼネラリスト育成、ローテーション人事などの日本独自の経営手法の発展に伴い、本社での個別人事管理の必要性が高まった。その流れのなかで、日本企業の人事部の多くは強い権力と影響力をもっていった*6。
米国企業の人事部と比較して、日本企業の人事部は、配置転換に対して強い影響力をもっている*7。職能内あるいは事業部内での人事異動は、ラインの管理職の意向が反映されるが、職能や事業部を超える異動や全社単位でのローテーション人事は人事部が関与する。なぜなら、ラインの管理職では、全社のことや他事業のことは分からず、本社人事部が関与せざるを得ない状況だからである。そのために、本社人事が社員個別の情報をもっていることが必要で、多くのスタッフを抱えることで、その要望に応えてきた。スタッフ数の多さそのものが会社への影響力を高めてきたという要素もある。
加えて、昇進・昇格制度や給与制度が、社外労働市場より社内要因(年次、年功、業績評価)を重視していたため、職能間、事業部間で不公平にならないという観点から本社人事の関与は大きかった。
しかしながら、バブル経済崩壊後の1990年代不況期に入ると、日本の強い人事が批判の対象になっていった。八代(1998)は「人事部不要論」を展開し、人事がもっている人事権を弱め、個人が主体的に自らの異動や転進などのキャリアを選択できるようにすべきと主張した*8。同時期、金融機関の倒産も相次ぎ、人そのものも過剰であったこともあり、人事部の役割を再考する機運は高まった。
また、1990年代の終わりから2000年代にかけて、日本企業は、日本型経営からグローバルスタンダードへ舵を切る。職能資格制度から成果主義制度への転換を図り、人件費を流動化できるように非正規社員の比率を高めていった。同時に、人事もその役割を再構築する議論が活発になってきた。その際にクローズアップされてきた概念が戦略人事である。
戦略人事論
ハーバード・ビジネススクールにおいて、1981年にMBA必修科目に「ヒューマン・リソース・マネジメント(HRM)」が開設された。同校では必修科目の新設はめったにあることではないが、1970年代後半の日本企業躍進の鍵としてのHRMが注目され、米国のビジネスリーダー輩出スクールの同校で取り扱うことになった*9。
同校の戦略人事のモデルでは、事業戦略や組織の内外の環境がHRM戦略と結びついていることを表している。また、米国の伝統的な価値観である、従業員の統制をベースにしたマネジメント観ではなく、従業員のコミットメントと自律性を強調するマネジメント観をベースにしている。さらに、HRMの複数の施策間での適合を重視したモデルになっている。そのモデルでは、HRMの概念的な枠組みを提供しており、今日の戦略的人事を考える際の基礎になっている(図表1)。
<図表1>HRMの概念的枠組み(ハーバード・モデル)
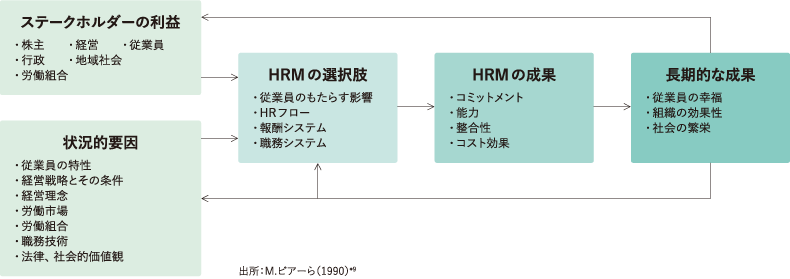
このモデルを見てみると、HRM施策が社内外の環境や経営戦略にも影響を及ぼしている枠組みになっており、経営戦略がHRM施策に影響を与える一方で、HRM施策が経営戦略に影響を与えると考えられる。つまり、HRM施策を行った結果、企業の構成員や技術や風土が形成される。その構成員や技術や風土は、その企業のリソースであり、競合優位性の源泉である。そのリソースを活用して経営戦略を形成していくことは、合理的でもある。戦略論のリソース・ベースド・ビュー(RBV)に通じている。
RBVは、経営戦略問題に関して、企業外の市場ではなく*10、企業内の問題に注目しているという意味で、HRM施策との関係性は強い。ライトら*11は、RBVと戦略的HRMの間の関係性を「人的資本プール」「従業員の行動」「人的管理施策」の3つの領域を提示して整理している(図表2)。「人的管理施策」によって「人的資本」や「従業員の行動」を促進することができる。そのようにして形成された「人的資本」と人的資本を有した従業員が「行動」することで、持続可能で模倣困難な競争優位を築けるというモデルである。戦略的人事を考える際には、頻繁に引用されるモデルの1つである。
<図表2>戦略的HRMの基本的要素
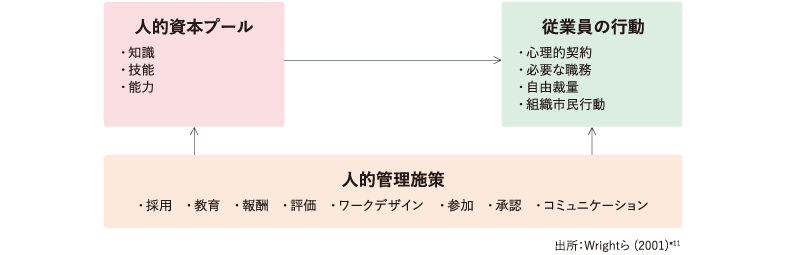
そのような米国で起こった戦略人事の動きを日本の人事にも取り入れようとしたときに、最も影響を与えた考え方が、以下のウルリッチの4つの役割モデルである*12。
(1)戦略パートナー(戦略とHRMを結びつける)、(2)管理エキスパート(採用、教育、制度設計などを通じて効率的な経営を実現する)、(3)従業員チャンピオン(従業員からの貢献を引き出す)、(4)変革エージェント(変革を設計し実行していく)。この4つの複合的な役割は、人事部門だけが行うのではなく、経営者や現場のマネジャーや従業員あるいは外部コンサルタントと分担していく、とウルリッチは述べている。
人事の役割の実態
ウルリッチの4つの役割モデルを参考に、弊社で図表3のような役割を定義して*13、「どのような役割を重視しているのか」491名の人事への調査を2021年に行った(「人材マネジメント実態調査」)*14。結果は、図表4のとおりである。
<図表3>人事の4つの役割
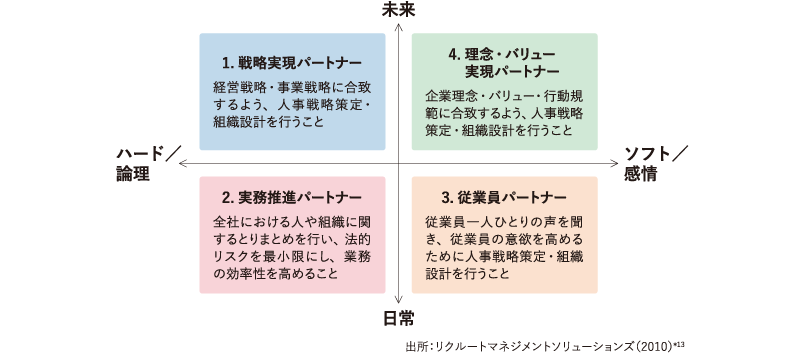
<図表4>現在と5年後の一番重視する人事の役割〈単一回答/n=491/%〉
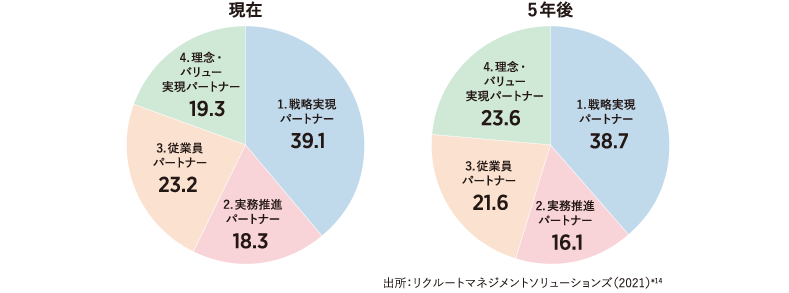
現在一番重視するものとして最も多く選択されたのは「1.戦略実現パートナー」(39.1%)だった。次に多いのが「3.従業員パートナー」(23.2%)で、「4.理念・バリュー実現パートナー」(19.3%)、「2.実務推進パートナー」(18.3%)については、大きな差がなく回答が分かれた。5年後についても、現在と同様に「1.戦略実現パートナー」(38.7%)が最も多く選択されている状況に変わりないが、次に多く選択されているのが「4.理念・バリュー実現パートナー」(23.6%)となっていた。
実は、同様の調査を2010年にも行っている*13。その調査でも「1.戦略実現パートナー」(61.7%)が人事の役割として最も多く選択されているが、2010年から2021年にかけて、61.7%から39.1%へ割合が減少していることが分かる。一方で、「3.従業員パートナー」の選択率が2010年には5.7%だったのが、2021年には23.2%へ大きく増加している。人口減少に伴う人材不足の影響と共に、競争優位の源泉として人の存在が改めてクローズアップされていることが推察されるデータになっている。
2021年の調査では、人事の役割・貢献に関して、自由に記述してもらっている。結果を見てみると、「会社としての考え方・やり方の変更を頻繁に行う。制度を守るのではなく、活動しやすいように制度を変えていく。前例を一度疑い、見直していく」というようなコメントに代表されるように、「変化対応」していくことが人事に求められているといったコメントが最も多かった。
また、コロナ禍ということもあり、テレワークや働き方に関連したコメントも多く、コミュニケーション、組織としての求心力、評価の仕組みの見直しなどについての言及が散見された。さらに、モチベーションや働きがいに関しても具体的な言及が複数見られ、「従業員パートナー」としての役割を裏付けるものになっている。
別の調査を見てみよう。
前述したように、かつて人事は会社のなかでの影響力が大きかった。現在はどうだろうか。一般社員の人事管理上の権限関係について、上林・平野ら(2019)は、10個の質問を使って調査している*15。その調査によると、人事部門の権限が大きいものは、「労使間協定の締結」(72.7%*16)、「社員の賃上げ・賞与原資の決定」(62.4%)、「昇進・昇格者の枠の決定」(45.3%)。逆に、人事部門の権限が小さいものは、「部門内での異動」(11.9%)、「部門内の教育訓練計画」(15.4%)、「部門内の人員計画」(16.2%)である。全社的な調整が必要なものは、人事部の意向が強く反映される。しかしながら、個別の企業に注目すると、現場の意向が強い企業も少なくないという状況であり、多様化してきているといえる。
人事の役割に関して、過去の研究や調査をレビューして分かることは、
1 人・組織能力の巧拙が競争優位を決めるという文脈で、人事では、事業の戦略実行支援が重視されてきている
2 日本企業においては、本社機能が強い人事から現場へ分権化されてきている
3 国内の人口減、人材不足感が高まる環境のなか、従業員に寄り添うことがより求められている
の3つである。
前述したように、働き方改革、人生100年時代への対応、エンゲージメント向上、A&R*17対応、DX人材の採用と育成、HRテック対応、人的資本に関する情報開示ということを考えていくと、企業のなかでの人事機能は、増大し複雑化しているといえる。しかしながら、その機能は、人事部門だけが行うわけではない。ラインの管理職、従業員、あるいは外部パートナーなどで分業するものである。そして、そのことは1980年代にHRMを戦略的に行う必要性を説いたハーバード・モデルでも、ウルリッチの4つの役割のなかでも指摘している話である。
例えば、変革エージェントという役割について、人事部門3割、現場マネジャー4割、外部コンサルタント3割という割合が示されている*11。これはそのとおりにやることを推奨しているわけではなく、自社の状況に合わせて変化するものであるということが前提である。現場を支える人事として、何を本社の人事として行うのか、現場マネジャーへ分権化していくものは何か、外部パートナーに任せていくものは何か、増加する役割に対して、グレートリセットの時代、改めて考え直す機会であるといえるだろう。
*1 リクルートマネジメントソリューションズ(2010)RMS Message vol.22 特集「人事の役割3.0」.
*2 14歳以下人口1990年2249万人、2030年1204万人(予測)(総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」)。
*3 RMS Message vol.62(2021)にて提唱したリクルートマネジメントソリューションズによる造語。ミドルからシニアへの移行期であるおおよそ50代~60代前半の世代を指す。
*4 ロナルド・P・ドーア(1993)『イギリスの工場・日本の工場-労使関係の比較社会学(上・下)』山之内 靖・永易浩一訳 筑摩書房.
*5 トマス・C・スミス(1995)『日本社会史における伝統と創造-工業化の内在的諸要因1750-1920年』大島真理夫訳 ミネルヴァ書房. 山下充(2008)「人事部」仁田道夫・久本憲夫編『日本的雇用システム』ナカニシヤ出版.
*6 サンフォード・M・ジャコービィ(2005)『日本の人事部・アメリカの人事部-日本企業のコーポレート・ガバナンスと雇用関係』鈴木良始・伊藤健市・堀 龍二訳 東洋経済新報社.
*7 平野光俊(2011)2009年の日本の人事部-その役割は変わったのか.日本労働研究雑
誌, (606),62-78.
*8 八代尚宏(1998)『人事部はもういらない』講談社.
*9 M.ビアー、B.スペクター、P.R.ローレンス、D.Q.ミルズ、R.E.ウォルトン(1990)『ハーバードで教える人材戦略』梅津祐良・水谷栄二訳 生産性出版.
*10 市場に注目しているのは、ポジショニング・ベースド・ビュー。
*11 Wright, P. M., Dunford, B. B. & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of management, 27(6), 701-721.
*12 デイビッド・ウルリッチ(1997)『MBAの人材戦略』梅津祐良訳 日本能率協会マネジメントセンター.
*13 リクルートマネジメントソリューションズ(2010)「人材マネジメント実態調査2010」からの考察.
*14 リクルートマネジメントソリューションズ(2021)「人材マネジメント実態調査2021」【後編】変化の時代の人事の役割・貢献に対する思いとは.
*15 上林憲雄・平野光俊編著(2019)『日本の人事システム-その伝統と革新』同文舘出版.
*16 数字は「人事部が決定する」「人事部の意向がより尊重される」を合算した値である。
*17 人材の採用(Attraction:引きつけ)と定着させること(Retention:引きとめ)の略語。
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.66 特集1「現場を支える人事」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
執筆者
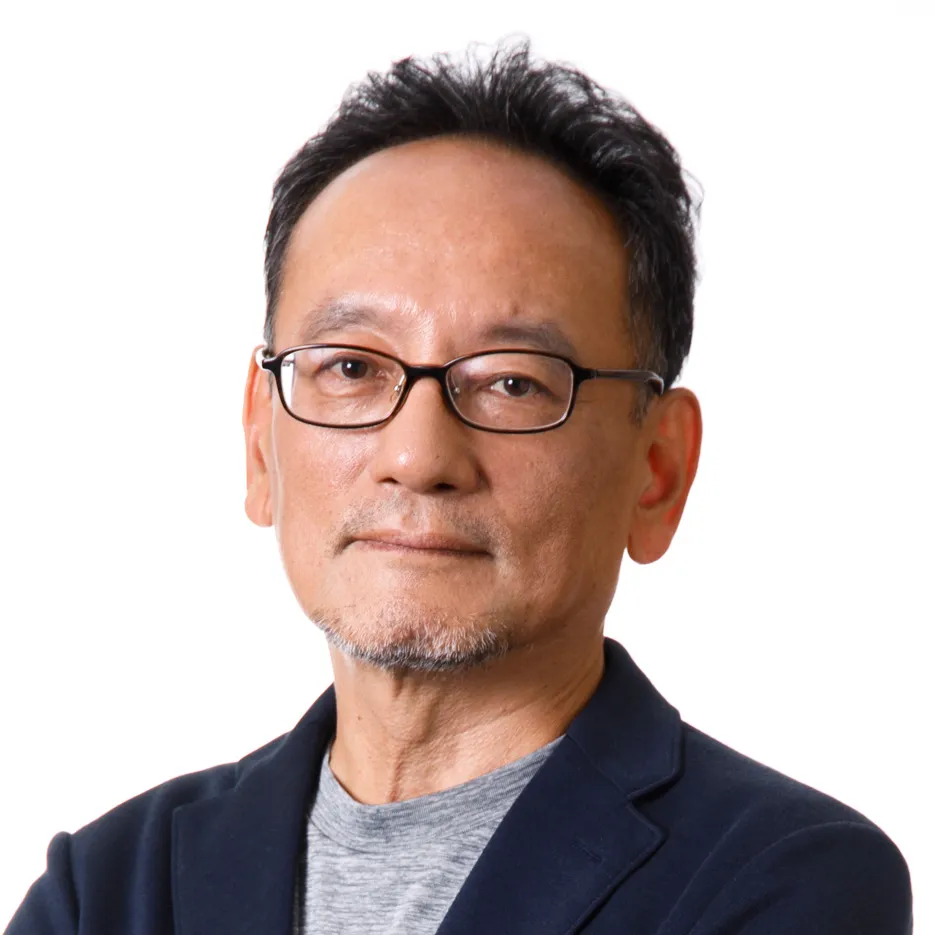
技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
古野 庸一
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社
南カリフォルニア大学でMBA取得
キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事
2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


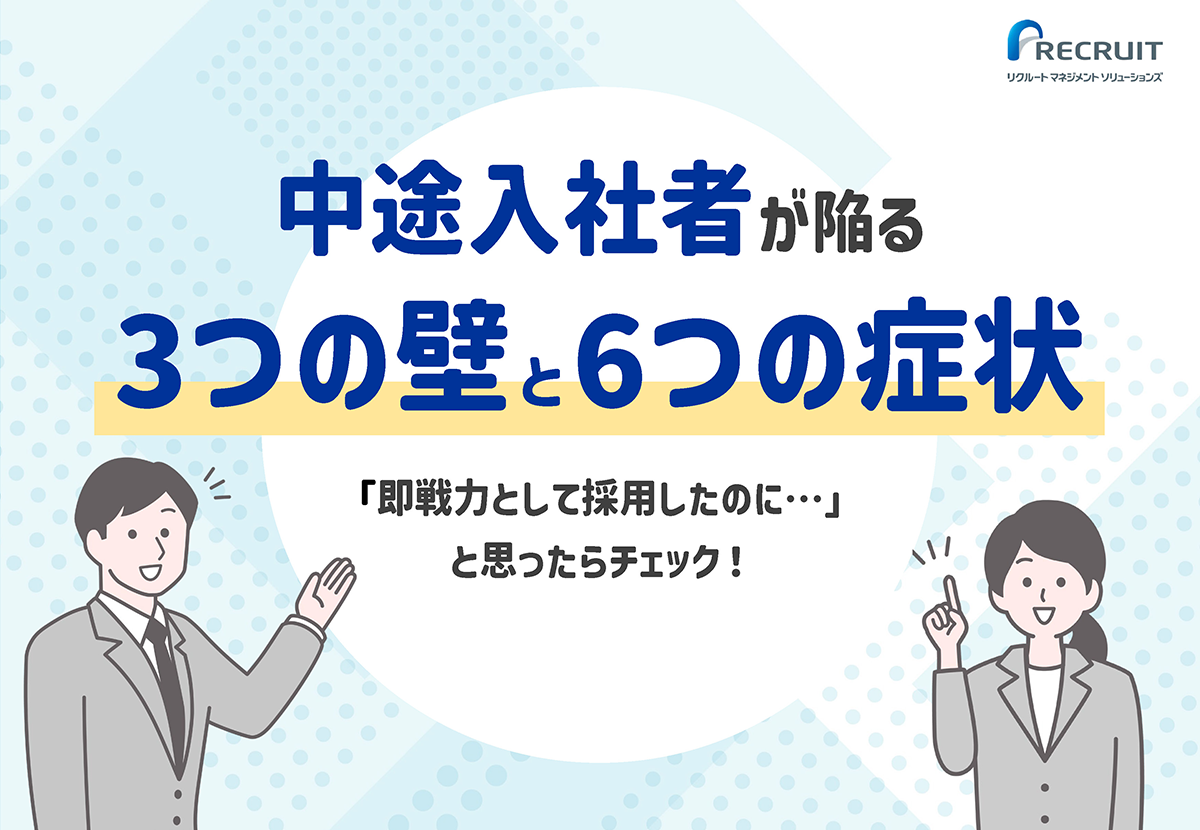
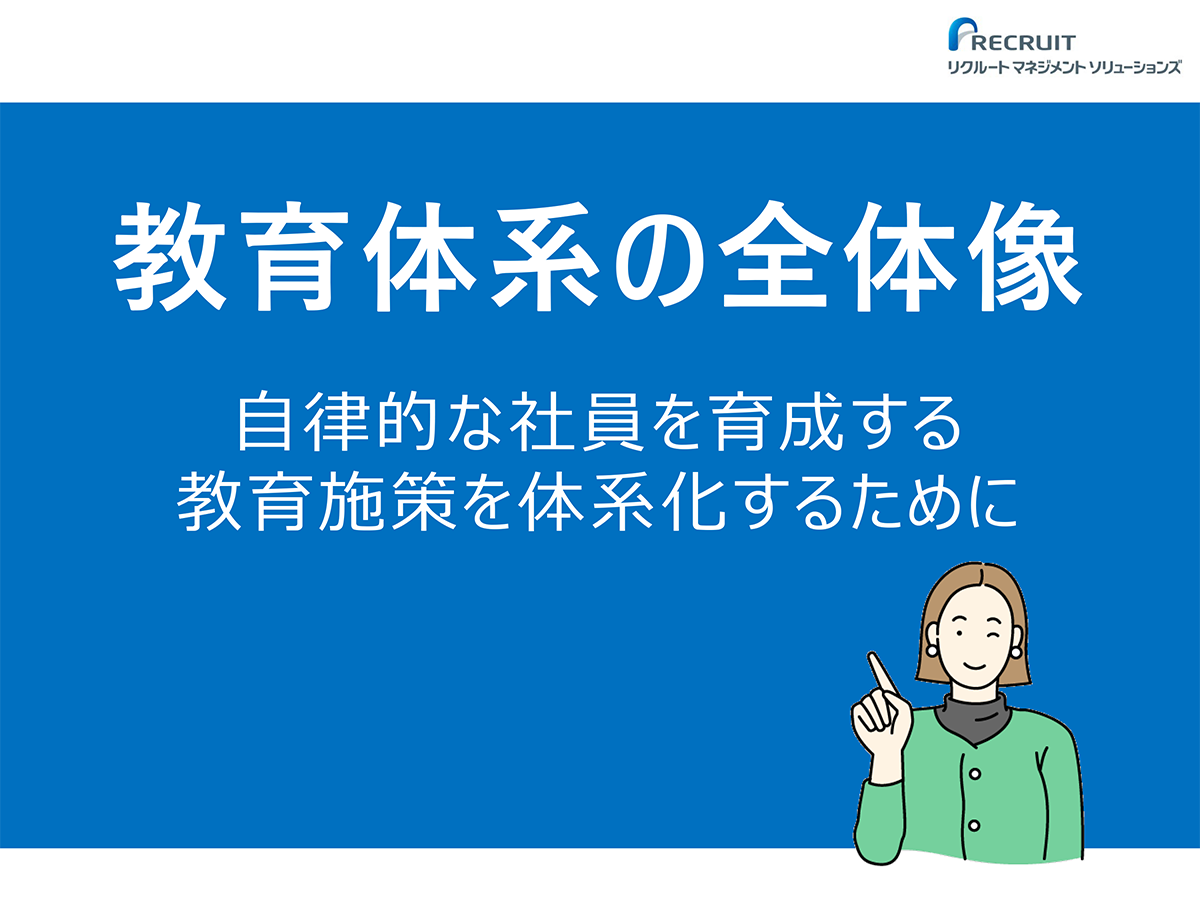
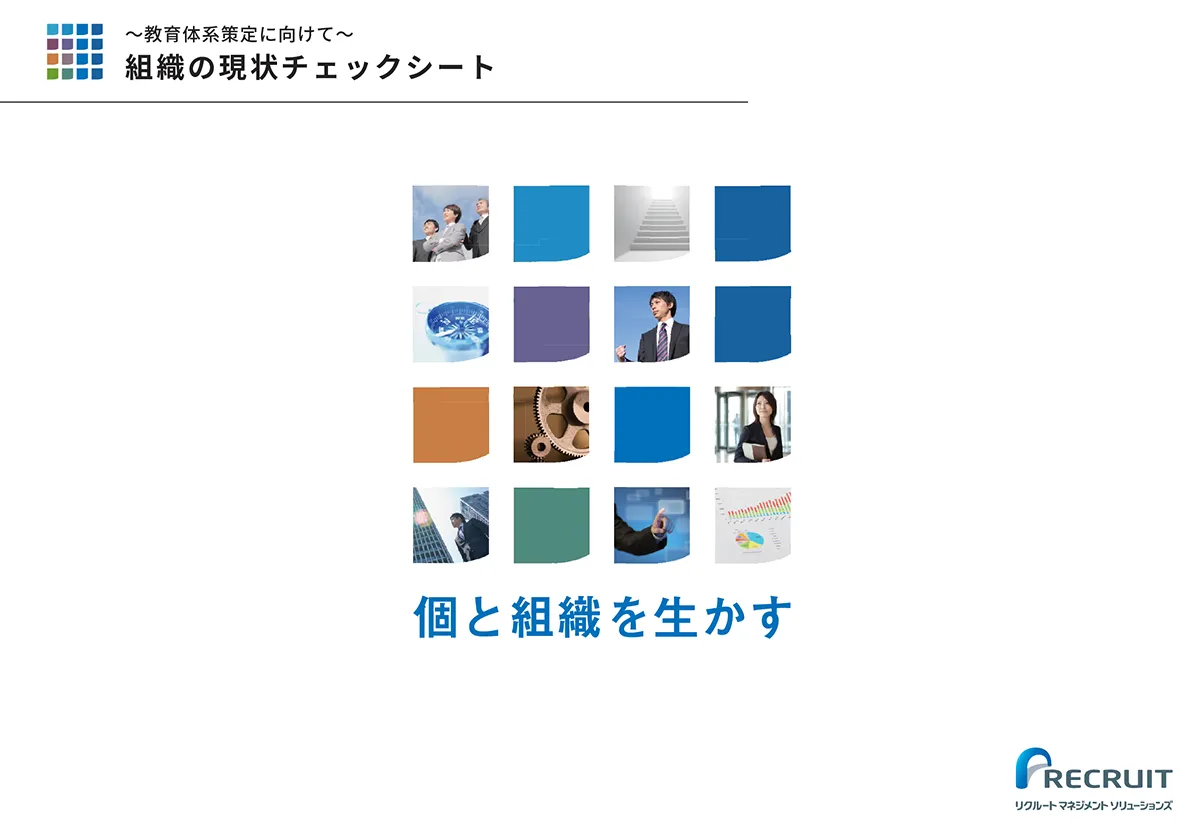









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての