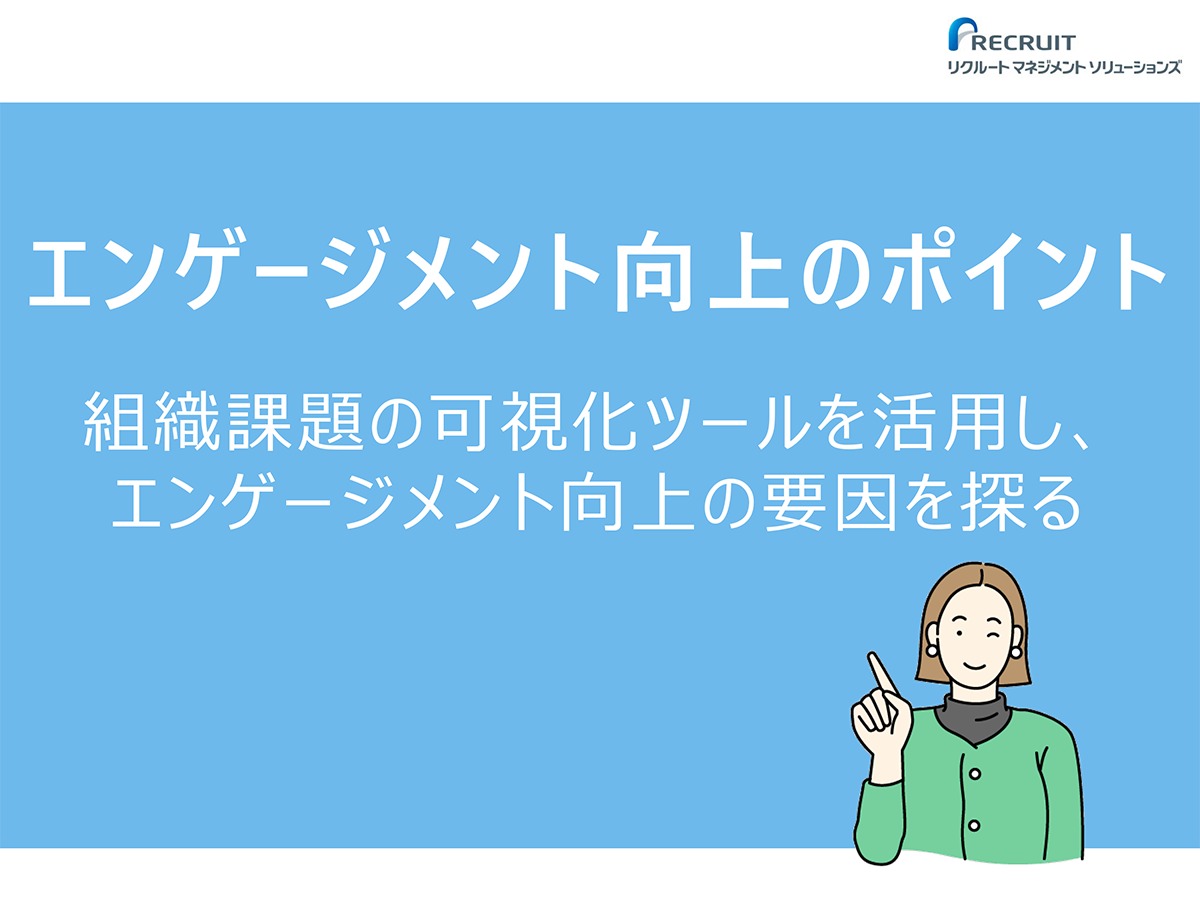特集
社外活動が仕事に及ぼす影響とは
ワーク・ライフのポジティブな関係性
- 公開日:2018/10/05
- 更新日:2024/05/16

かつて、仕事以外の時間は、「余暇」とみなされていた。今日では、労働時間が生活時間に占める割合は高く、核家族や共働き家庭においてケア責任を担う労働者が増え、もはや仕事外の領域は単純に「余暇」としてくくることができなくなった。ワークとライフの関係性についての研究は、そのような背景から、今日まで盛んに行われている。本稿では、主にキャリア論や経営学の領域における、仕事と仕事外の領域の関係性についての研究を概観する。
- 目次
- 1.「ワーク」は「ライフ」の一要素
- 2. 日本の労働者のワーク・ライフ
- 3. ワーク・ライフ研究はネガティブ面からポジティブ面へ
- 4. ポジティブ・スピルオーバー
- 5. 私的活動は仕事への熱意を奪わない
- 6. 多様な人の ワーク・ライフ
- 7. 多重役割とアイデンティティ
- 8. 組織開発への展開、管理職のワーク・ライフ
1.「ワーク」は「ライフ」の一要素
何が「ワーク」に含まれるかは比較的分かりやすい。では「ライフ」には何が含まれるだろうか。
ライフ・キャリア・レインボーという概念がある。キャリア研究の発展に貢献したドナルド・E・スーパーが、1950年代に発表した理論の1つである。スーパーによれば、人は人生において、「子」「学生」「余暇を楽しむ人」「市民」「労働者」「家庭人」「その他」といった複数の役割を担う。それぞれの役割に割く時間的・心理的エネルギーの重みづけは、人生の時期によって変化していく(図表1)。人が多重な役割を担っている事実に光を当てただけでなく、その構成割合が時間の経過に応じて変化するという観点を提示したことは、スーパーの大きな貢献といえる。
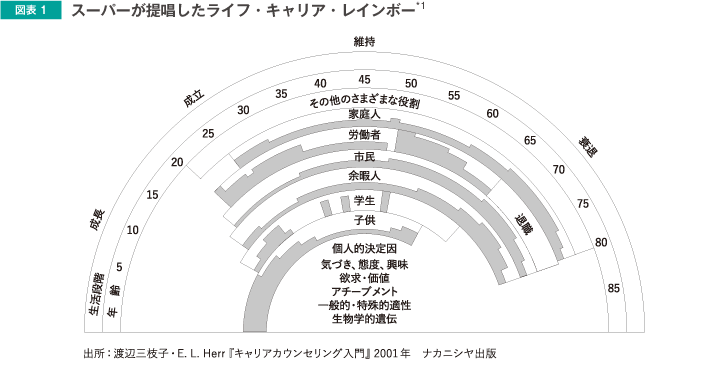
もう1つの重要な指摘は、人が複数の役割を引き受け、演じる経験を通じて、価値観の発達を遂げるという人間観を示したことである。社会を支え、社会に支えられて生きていく人間という生物においては、引き受ける社会的役割を自在に取捨選択することが難しい面がある。一つひとつの役割は、それを担う人の人格を規定するものではない。しかし、役割を演じることでその人に内面化される価値観もあり、1人の人のなかに複数の視点が育まれることも多い。
ライフ・キャリア・レインボーという、社会との相互作用や時間の経過を考慮にいれた世界観から見れば、「労働者」という役割、あるいは「ワーク」の領域は、人が人生において担う複数の役割の1つにすぎない。そして、人が「労働者」の役割をいかに演じるかということは、その人が他の役割を通じて遂げる価値観の発達に大いに影響を受けると考えられる。
2. 日本の労働者のワーク・ライフ
欧米諸国において、核家族化、ケア労働に従事する従業員の増加トレンドは、ワーク・ライフの関係性を見直す契機として認識されている。しかし、そのような環境は、少子高齢化が世界に先んじて進む日本においてこそ顕在化している*2。全世帯に占める核家族の割合は半数を超え、婚姻率の低下や世帯主の高齢化などから単身世帯が約3割を占める(2017年時点)*3。共働き世帯の数は1990年代半ばに専業主婦世帯数と逆転し、2017年時点では専業主婦世帯のほぼ倍に達している(図表2)。若い世代の減少と並行して、要介護認定者の数は増加の一途であり、今後は夫婦共働き世帯や単身世帯において、家事を担いつつ、育児や介護といったケア労働に従事する従業員の増加が見込まれる。
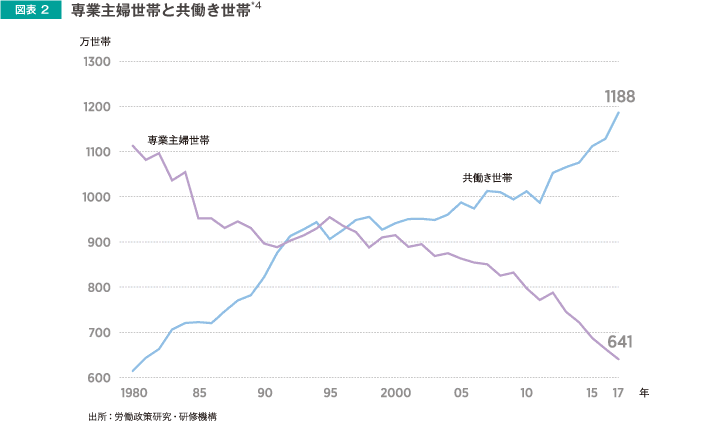
親世代を頼れない核家族の子育ては、パートナー同士が協力しなければ成り立たない。兄弟姉妹の少ない現代では、性別や婚姻の有無に限らず、老親の介護の主体者となる人が増える。誰もが、「家庭人」として「子供」として、ケア役割を担う当事者となり、「労働者」の時間でライフのほとんどが埋まっていては社会がもたない。
労働者自身にも、「働きすぎ」の自覚が見られる。内閣府の調査によると、希望就労時間が現実と合致しない人の割合は、1日の労働時間が10時間未満である労働者の約6割、10時間以上の労働者の約7割に上る(図表3)。働きすぎ社会への自覚は、1970年代から顕在化しており、「労働の人間化(QWL:Quality of Work Life)」「ディースントワーク(適度な労働)」といった運動が行われてきた*6。近年も、厚生労働省が男性育休を啓発した「イクメン」プロジェクト、NPO法人ファザーリング・ジャパンなどが発信する「イクボス」(部下の家庭役割を支援する上司)、中央大学ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プロジェクトによるワーク・ライフ・バランス(WLB)管理職への提言など、労働者の生活時間・家庭役割への配慮を企業のマネジメントに求める運動が見られる。
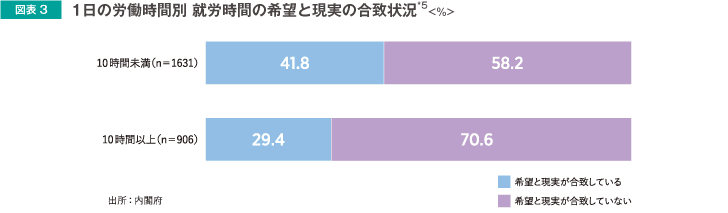
このように、ワーク・ライフの関係性に関する議論は、家庭におけるケア役割の負担増を中心とする、時間再配分の問題として関心を増してきた。しかし、生産年齢人口が減少の一途をたどり、ICTの普及や世論の成熟が進むなか、在宅勤務やフレックスタイム制度などの適用者も増加する可能性が高い。1日のうちにも、ワークとライフの切り替えスイッチがONとOFFを繰り返すような環境下では、仕事と仕事外の線引きがより曖昧になっていくことが予想される。今後は、時間配分の観点にとどまらず、ワークとライフのポジティブな関係性とはどのようなものか、という議論へと発展していくことが考えられる。
3. ワーク・ライフ研究はネガティブ面からポジティブ面へ
「仕事外」の活動の存在感が増し、ワーク・ライフ研究が盛んになった経緯はすでに述べた。当初は、仕事における役割と家庭における役割の間のネガティブな側面が、「葛藤(conflict)」という概念を用いて盛んに研究され、主に「時間」「ストレス」「行動・価値観」などの側面において、役割間の葛藤が生じることが明らかになった。ネガティブ面への認知が浸透すると、次第に研究上の関心がポジティブ面に注がれるようになり、複数の役割間の調和や相乗効果の研究が1990年代の終わりから2000年代にかけて増えていく*7。
ネガティブ面からポジティブ面への視点の転換は、時間の有限さとは異なり、心的エネルギーや能力の源泉は必ずしも有限ではなく、ワークとライフは補い合う可能性をもつという気づきからもたらされた*8。裏を返すとそれまでは、ライフは、ワークに従事する時間とコミットメントを奪うものと考えられてきた。しかし、数々の研究成果が、複数の役割をもつことが、特定の役割における心理的にネガティブな影響を軽減することや、仕事外の役割に熱心に打ち込むことでエネルギーの総量が増えたり、仕事にも還元されたりすることを示している。
4. ポジティブ・スピルオーバー
ワークとライフのポジティブな関係性については、「エンリッチメント」「ポジティブ・スピルオーバー」といった概念によって研究が積み重ねられている。「エンリッチメント」は、一方の役割で経験したことが他方の役割における生活の質を高めることと定義される*9。「ポジティブ・スピルオーバー」は、一方の役割から他方の役割にスピルオーバー=“流出する”もののうち、ポジティブなものを指す。いずれも、仕事と家庭役割の関係に着目した実証研究が多い。
カールソンらによれば、仕事役割から家庭役割へ(Work to Family)は、能力開発(スキルや視野の広がり)、情緒(良い気分)に加えて資源(金銭的・心理的)が、家庭役割から仕事役割へ(Family to Work)は、能力開発、情緒に加えて能率(手際の良さや集中)が流入する*10。ポールマンらは、ポジティブ・スピルオーバーを促進する職務要因、個人要因、職場要因の3つを整理している(図表4)*11。自律性や工夫が求められる職務や、自己概念や情緒の安定、周囲の支援がある場合などに、仕事と家庭役割の間に良い相互影響が起こる。また、ポジティブ・スピルオーバーは、個人の生活の質的向上のみならず、職務満足や組織コミットメント、組織に貢献する役割外行動である組織市民行動などを促し、組織貢献の観点から良い結果をもたらすことが明らかにされている。
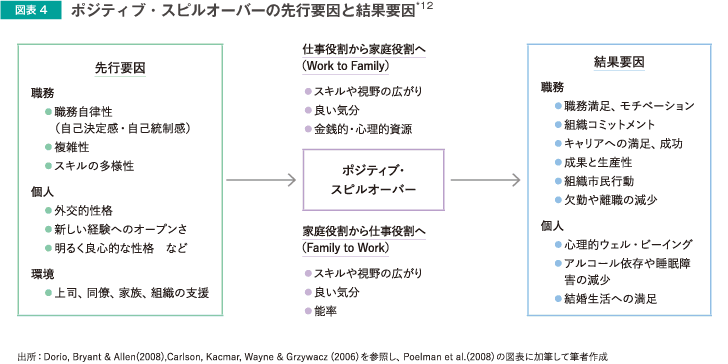
5. 私的活動は仕事への熱意を奪わない
仕事役割へのポジティブ・スピルオーバー、エンリッチメントは、私的活動一般においても成立すると考えられる。アリスとオドリスコールは、家庭役割とその他の私的活動を比較しながら、仕事役割との関係性を検証した。彼らによれば、家庭役割であれ私的活動であれ、投入時間が長い人ほど役割間の葛藤が高まるということはなく、一方、仕事外の役割に情熱を傾けている人ほど、仕事役割との間のエンリッチメントが高い傾向が見出された。仕事外の役割への献身は、仕事に傾ける資源や熱意を奪うものではなく、むしろ仕事とのエンリッチメントをもたらすことが示唆されている*13。
個人内のエンリッチメント感覚が検証される一方で、働き方の柔軟化や長期休暇などの制度利用がキャリアに悪影響を及ぼすという調査もあり、その因果関係は安定して検出されない。理由として指摘されるのが、組織の規範や上司の色眼鏡に左右されるということである。具体的には、WLB施策の利用が、仕事への「献身」を判定する「シグナル」として、組織や上司にどのように解釈されるかによる*14。長時間労働が献身のシグナルとみなされる場合には、個人は制度利用を控えることが多い。また、仕事への献身が薄いというレッテルが貼られた環境では、キャリア上の成果は表れにくいだろう。昇進などキャリア開発の道が閉ざされることを恐れて制度利用が進まないとの指摘は、国を問わず共通である。
仕事への献身のシグナルとしてみなされやすいことに加え、性別に関連した役割規範によって制度が利用されないことも多い。英国で、男性の育児休業が取得されない理由を検証したバーネットとハイドは、金銭的コスト、制度の利便性の不足と並んで、父親の長期離職に職場が支援的でないと感じること、さらに、女性の側がより長い期間休職すべきというジェンダー規範がパートナー間にもあることをその理由として分析している*15。
6. 多様な人の ワーク・ライフ
研究のみならず、企業の想定する「ライフ」が、主に子育てに関するケア役割に限られる場合は多い。しかし、ライフは個人内だけでなく、個人間においても多様である。育児と仕事の両立を支援する「ファミリー・フレンドリー」の施策のみでWLBがメッセージされる場合には、制度の利用機会やニーズが従業員間で異なることになる。
すべての人が「バランス」を望むわけではないために、ケア責任を負わない従業員からの「ファミリー・フレンドリー・バックラッシュ(反動・批判)」が起こる、という指摘がなされることがある。しかし、実際に聞き取り調査を行うと、養育する子どもが家族にいない管理職や専門職にもWLBのポリシーを支持する人は多く、バックラッシュの根拠は薄いとの研究もある*16。それによれば、組織における公平さや公正さは、キャリア開発や昇進の機会などを含めて判断されることから、柔軟な働き方を中心としたファミリー・フレンドリー施策が単独で不公平感につながるとは限らない。問題は、一部の社員の業務負荷軽減が、他の社員に過負荷としてしわ寄せがいく場合に生じる。柔軟な働き方が育児などに限定されず、自分にも制度利用の権利があると感じられることが重要だという。また、世代間の違いや時代の変化も指摘される。仕事における自由や柔軟な働き方を、若い世代ほど重視するとの指摘もあるが*17、社会全体で見ても、仕事の中心性は低下している。日本放送協会が5年ごとに実施している「日本人の意識」調査では、1988年に逆転して以降、余暇絶対・優先の考えが、仕事絶対・優先の考えを上回っている(図表5)。
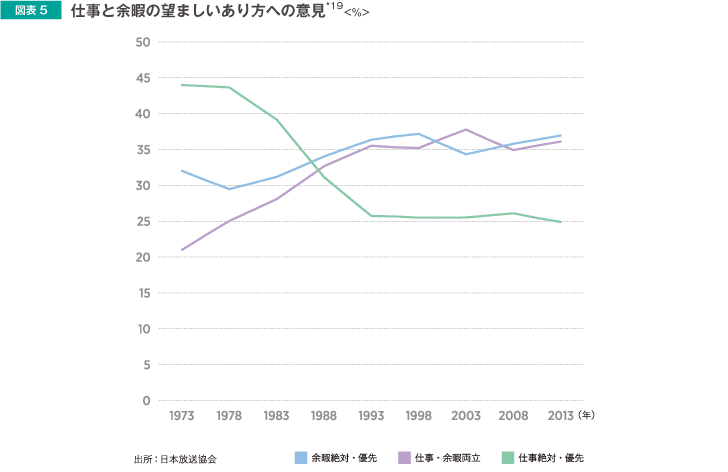
つまり、ライフは多様であるが、ライフを「尊重」されることへのニーズは広く共有されている。カーチマイヤーの研究によれば、カナダの管理職221名の組織コミットメントに対して、選択できる働き方などライフを「尊重」する会社の方針や施策は正の影響を与えた。一方、職場でレクリエーションを行うなど、ライフをワークへ「統合」するような施策は影響を及ぼさず、公私を明確に分けてほしいとする「分離」のメッセージは負の影響を与えたという*18。
7. 多重役割とアイデンティティ
何者として何のために働くかという、仕事の意味や仕事上のアイデンティティの明確化は、仕事上の成果や個人のウェル・ビーイングにつながるポジティブな要素であるが、ワーク・ライフの環境はそれらにも影響を与える。
複数の役割間の境界は、くっきりとしていることもあれば、かなり曖昧な場合もある。前者では、役割間の線引きが容易であるが、気持ちや考え方の切り替えが難しくなる。後者の場合は、切り替えに悩むことは少ないが、線引きが難しくなる*20。近年の職場環境では、コンプライアンスや労働時間短縮の観点などから、仕事外の要素が職場から排除される一方、在宅勤務などによって生活空間との区別が曖昧になる場面も増えており、ワーク・ライフの境界はますます複雑化している。また、仕事の意味づけや仕事上のアイデンティティは、他者からの期待に応えたり、理解されやすいものが選択されやすく、他者との関係性に大きく影響される。ワークとライフを単純に区別できない環境は、他者との関係を複雑化し、仕事の意味を語る難しさを増す。
しかし、そのことは同時に、変革と創造の好機ともなる。何者として何のために働くかという、仕事にまつわる「物語」は、従来、固定的な集団内に向けて閉じがちであった。ワーク・ライフの境界が曖昧になることは、「物語」のフィールドや語りかける相手を多様化することを通じて、「物語」に新しいバリエーションを加える材料や機会を増やす。個人にとっては、同じ仕事に就いたままでも、より納得感や発展性のある意味を見出しやすくなる可能性がある。
企業は、働く意味が見失われたり個人化しやすい環境を認識し、職場における対話の機会をもつ必要性を認識すべきである。仕事の意味についての対話は、モチベーションの維持・向上のみならず、仕事に新たな発想や変革を取り入れることにつながることも考えられる。
8. 組織開発への展開、管理職のワーク・ライフ
従業員のワーク・ライフの関係性が良いものになるために、支援的な組織文化や上司の関与の重要さを指摘する研究は多い。しかし、多くの組織にとって、ライフに十分な時間や意識を向けることを肯定することは、伝統的な働き方と価値観に疑問を投げかけることであり、組織開発を伴う変革となる。
働き方の変化と組織変革の関係を論じた研究は少ない。ルイス*21によれば、ファミリー・フレンドリー施策の浸透への壁は2つあり、1つは、ライフの役割に正当な「資格」が与えられるかどうか。家族の介護を理由に、会議の時間を調整してほしいというような要望を職場で口にできるかというような規範である。もう1つは、「時間」に対する半ば無意識の前提、生産性やコミットメントが労働時間との関係でどのように語られるかということである。「資格」と「時間」に関する文化は、(1)社会的文脈のレベル(2)組織メンバーに半ば無意識に共有されている価値前提のレベル(3)組織が成果創出のために意識的に形成するレベル、の3層にまたがって形成されているという。法改正や保育所の整備などの社会制度面の変化は(1)のレベルの文化を変え、組織内でライフの役割が議論される「資格」を得るために必要である。しかし、組織変革を完全に進めるには十分ではなく、仕事の本質や理想の従業員像といったより深層の(2)の価値前提のレベル、(3)の組織成果のための合理的選択のレベルが組織内で問い直される必要がある。
(2)(3)のレベルの変革のために重要なのは、より見えにくい男性の家庭役割を可視化すること、そして、ワークとライフの役割を同程度に優先することが組織成果をもたらすという因果関係を証明することだという。役割間の優先度の偏りはストレスを助長する環境となるため、「同程度」の優先度が職場で合意されることが重要である。ルイスはここで、ワーク・ライフの関心と組織開発の接続に成功したゼロックス社の事例分析をした論文を紹介している。マネジャーが関与しつつ職場で個々人のワーク・ライフの問題を話し合ったところ、問題の根は個人の対処の巧拙ではなく、環境が生み出す構造的な問題であるとの認識が共有された。興味深いのは、これが構造的な問題解釈の訓練となり、職場における成果創出の構造理解を促進し、有効な能力や時間の使い方、無用なストレス要因などが可視化され、成果創出に向けた仕事の変革が促されたことである*22。
ワーク・ライフの関係性は、従業員自身だけでなく、仕事や職場にも良い影響を及ぼし得ることが分かってきている。しかしそのポジティブな関係性を実現し続けるには、仕事の本質についての理解を促すような組織開発が必要である。組織的な内省を促し、組織文化を変えていくのは、現場のリーダーたる管理職である。しかし、管理職自身のワーク・ライフ・エンリッチメントの実情も、組織開発への影響もほとんど理解されていない。それらを解明していくことが、表面的なワーク・ライフの葛藤の解消ではなく、職場全体での本質的な問題解決につながるのではないか。
*1 渡辺三枝子・Herr,E.L.(p.7)(2001)『キャリアカウンセリング入門』,ナカニシヤ出版
*2 内閣府「平成29年版高齢社会白書」
*3 厚生労働省「平成29年国民生活基礎調査」
*4 http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html
*5 内閣府「平成26年ワーク・ライフ・バランスに関する個人・企業調査」
*6 菊野一雄(2009)「「労働の人間化(QWL)運動」再考:その歴史的位置と意味の再検討」『三田商学研究』51(6), 13-24.慶應義塾大学出版会.
*7 藤本哲史(2011)「仕事と私的生活のポジティブな関係性」『日本労働研究雑誌』606, 118. 独立行政法人労働政策研究・研修機構; Geurts, S. A., & Demerouti, E. (2003). Work/non-work interface: A review of theories and findings. The handbook of work and health psychology, 2, 279-312.; Poelmans, S., Stepanova, O., & Masuda, A. (2008). Positive spillover between personal and professional life: Definitions, antecedents, consequences, and strategies. In Handbook of work-family integration, 141-156.
*8 Friedman, S. D., Christensen, P., & DeGroot, J. (1998). Work and life: The end of the zero-sum game. Harvard business review, 76, 119-130.; Geurts & Demerouti(2003).
*9 Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. (2006). When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of management review, 31(1), 72-92.
*10 Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Wayne, J. H., & Grzywacz, J. G. (2006). Measuring the positive side of the work-family interface: Development and validation of a work-family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 68(1), 131-164.
*11 Poelman et al.(2008).
*12 Poelman et al.(2008), Dorio, J. M., Bryant, R. H., & Allen, T. D. (2008). Work-related outcomes of the work-family interface: Why organizations should care. In Handbook of work-family integration (pp. 157-176).; Carlson, Kacmar, Wayne & Grzywacz (2006)より
*13 Allis, P., & O'Driscoll, M. (2008). Positive effects of nonwork-to-work facilitation on well-being in work, family and personal domains. Journal of Managerial Psychology, 23(3), 273-291.
*14 Bourdeau,S, Ollier-Malaterre, A, & Houlfort, N.(2018).Not All Work-life Policies Are Created Equal: Career Consequences of Using Enabling versus Enclosing Work-life Policies
*15 Barnett, R. C., & Hyde, J. S. (2001). Women, men, work, and family: An expansionist theory. American psychologist, 56(10), 781.
*16 Wilkinson, K., Tomlinson, J., & Gardiner, J. (2018). The perceived fairness of work-life balance policies: A UK case study of solo‐living managers and professionals without children. Human Resource Management Journal, 28(2), 325-339.
*17 Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit. Journal of managerial psychology, 23(8), 891-906.; Bal, P. M., & De Lange, A. H. (2015). From flexibility human resource management to employee engagement and perceived job performance across the lifespan: A multisample study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(1), 126-154.
*18 Kirchmeyer, C. (1995). Managing the work-nonwork boundary: An assessment of organizational responses. Human Relations, 48(5), 515-536.
*19 日本放送協会「日本人の意識」調査(2013)より
*20 Ashforth, Kreiner & Fugate(2000).
*21 Lewis, S. (1997). ‘Family friendly’employment policies: A route to changing organizational culture or playing about at the margins?. Gender, Work & Organization, 4(1), 13-23.
*22 Fletcher, J., & Rapoport, R. (1996). Work-family issues as a catalyst for organizational change. The Work-Family Challenge: Rethinking Employment, 142-158.
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.51 特集1「ミドルマネジャーのワーク・ライフ・エンリッチメント」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
関連ページとして「働き方改革」についてまとめた記事をご用意しています。こちらもぜひご覧ください。
>「働き方改革」とは? いまさら聞けない基本から、今後のトレンドまで
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
客員研究員
藤澤 理恵
リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。
“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。
経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)