- 公開日:2022/11/21
- 更新日:2024/05/16

「個人選択型HRM」とは、従業員が自律的・自己選択的に、仕事・働き方・キャリアに関する選択を行う機会を増やす制度やマネジメントのことを指します。9月14日に開催した組織行動研究所セミナーでは、第1部として、弊社・組織行動研究所が実施した「個人選択型HRMに関する実態調査2022」(企業調査)「個人選択型HRMと個人選択感に関する意識調査」(個人調査)の結果をご報告し、個人にとって魅力的であり、かつ組織にとっても有益な「個人選択型HRM」のあり方についてお話ししました。また第2部では、2022年版「日本における『働きがいのある会社』ランキング ベスト100」大規模部門第3位のレバレジーズ株式会社執行役員 藤本直也氏をお迎えして、社員の自己選択を尊重するユニークなHRMの取り組みについて伺いました。以下、第1部、第2部、それぞれについて内容をご紹介します。
第1部 個人選択型HRMとは
講師プロフィール
古野庸一 リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 所長

1987年株式会社リクルートに入社。キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、リクルートワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事。2009年より現職。著書に『「働く」ことについての本当に大切なこと』(白桃書房)、『「いい会社」とは何か』(講談社現代新書、共著)、『リーダーになる極意』(PHP研究所)、『日本型リーダーの研究』(日経ビジネス人文庫)、訳書に『ハイ・フライヤー 次世代リーダーの育成法』(プレジデント社、共訳)など。
個人選択型HRMのある組織の方が働きがいがある
日本企業では今、「個人選択型HRM」の取り組みが進んでいます。個人選択型HRMとは、従業員が自律的・自己選択的に、仕事・働き方・キャリアに関する選択を行う機会を増やす制度やマネジメントのことを指します。具体的には、配属先を特定した採用、自己申告制度、社内公募制度、フレックスタイム制度、在宅勤務制度、短時間勤務制度、限定正社員、副業・兼業許可、選択型の能力開発制度、キャリア相談制度などの施策があります。
個人の能力、経験、志向は多様です。その多様な個性を組み合わせて、組織としての能力を高めていく必要があります。しかしながら、個々人に合わせた仕事やキャリアや働き方をすべて組織主導で用意することは効率的ではありません。そこで、個人が自ら選択できる施策の導入が必要とされている、という側面があります。さらにいえば、個人のエンゲージメントを高めるためにも、個人が自律的に働くためにも、組織がイノベーションを推進するためにも、土台となる制度が個人選択型である必要があります。
心理学者のアルバート・バンデューラ氏は、「自己効力感」の重要性を主張しています。彼によれば、「人は、そもそも主体的に行動するもの」です。私たちは、自分の目標を選択し、目標に向けて計画して現在の行動を選択し、時々の状況に応じて対処し、行動の結果のフィードバックを受けて次へ備える生きものなのです。個人選択型は、根本的に私たちに適している、というわけです。その証拠に、63の国と地域の調査で、人生における選択や自律性の程度が高い地域ほど主観的幸福度が高いことが分かっています(※1)。また、コントロール感(選択感)をもっていると認知することは、仕事の満足感やパフォーマンスにつながっています(※2)。
私たちの調査でも、自律的なキャリア形成をしたい人は81.7%と多数に上ります(※3)。また、「本人の希望ができるだけ尊重される配置」や「自分の希望に応じ、特定のスキルや知識を学べる研修」など、個人選択型HRM施策が行われている組織の方が、「働きがい」に対して肯定的に答える人が明らかに多いことも分かっています(図表1)。
※1 Fischer, R., & Boer, D. (2011). What is more important for national well-being: money or autonomy? A meta-analysis of well-being, burnout, and anxiety across 63 societies. Journal of personality and social psychology, 101(1), 164-184.
※2 Spector, P. E. (1986). Perceived control by employees: A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work. Human relations, 39(11), 1005-1016.
※3 リクルートマネジメントソリューションズ(2021)「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」
<図表1>人材マネジメント施策の有無と働きがいの関係
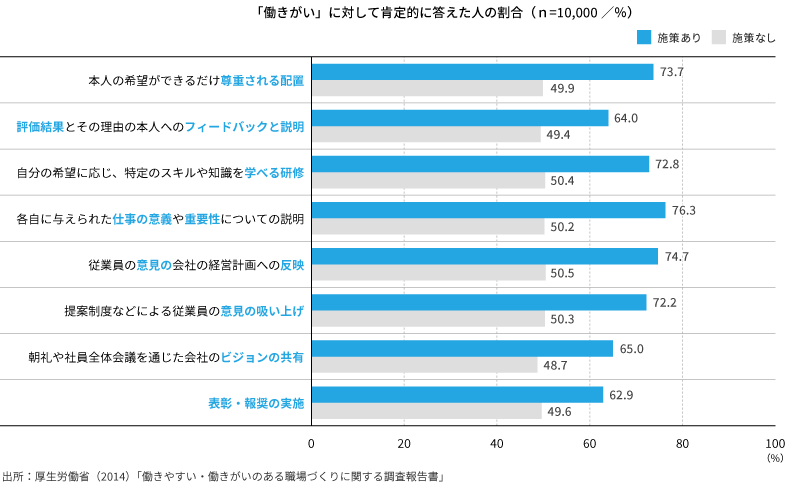
「副業・兼業」に対する企業の不安は杞憂?
以上を踏まえて、私たちの2種類の調査の成果をご紹介します。2022年に行った企業調査「個人選択型HRMに関する実態調査2022」と、個人調査「個人選択型HRMと個人選択感に関する意識調査」です(図表2)。
<図表2>調査概要
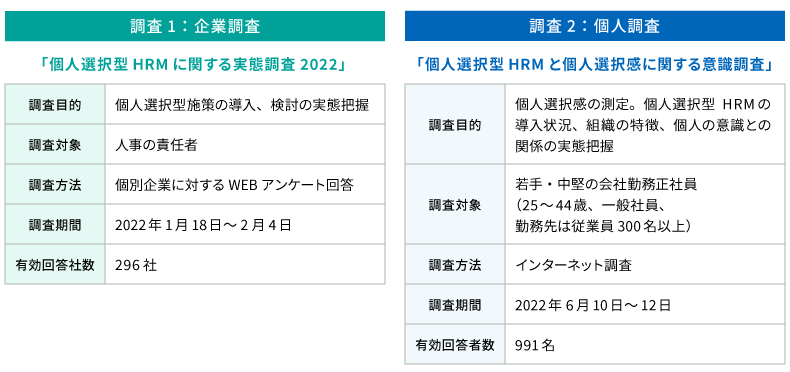
まず、調査1の企業調査をご紹介します。「個人選択型HRM施策の導入・活用状況」(図表3)を見ると、「10.テレワーク・在宅勤務制度」「19.目標管理制度」は9割程度、「2.自己申告制度」「11.フレックスタイム制」「20.上司とのキャリア相談」は7割程度、「1.配属先の職種や事業などを特定した採用(職種別採用)」「3.手挙げ研修」は6割程度が導入しており、個人選択型HRMが一定程度進んでいることが分かります。しかし一方で、「9.社内FA制度」の導入は1割程度と、ほとんど進んでいません。
「16.副業・兼業の許可」と「23.メンターやカウンセラーとのキャリア相談」は、導入している企業はそれぞれ25.0%と39.2%、そして導入検討率が24.7%と29.1%であり、これから増えていくことが予想されます。
「2.自己申告制度」と「20.上司とのキャリア相談」は、導入率は高いものの活用が十分に進んでいません。自己申告制度は、経営側としては人事異動を戦略的に行えないという不安があると同時に、制度をつくっても社員がなかなか手を挙げてくれないという悩みを抱えています。上司とのキャリア相談は、上司・部下の双方に内容・方法への戸惑いがあるようです。日本企業の個人選択型HRM施策の導入はまだ道半ばです。
<図表3>個人選択型HRM施策の導入・活用状況
貴社における以下の施策への取り組み状況をお答えください。<単一回答/n=296/%>
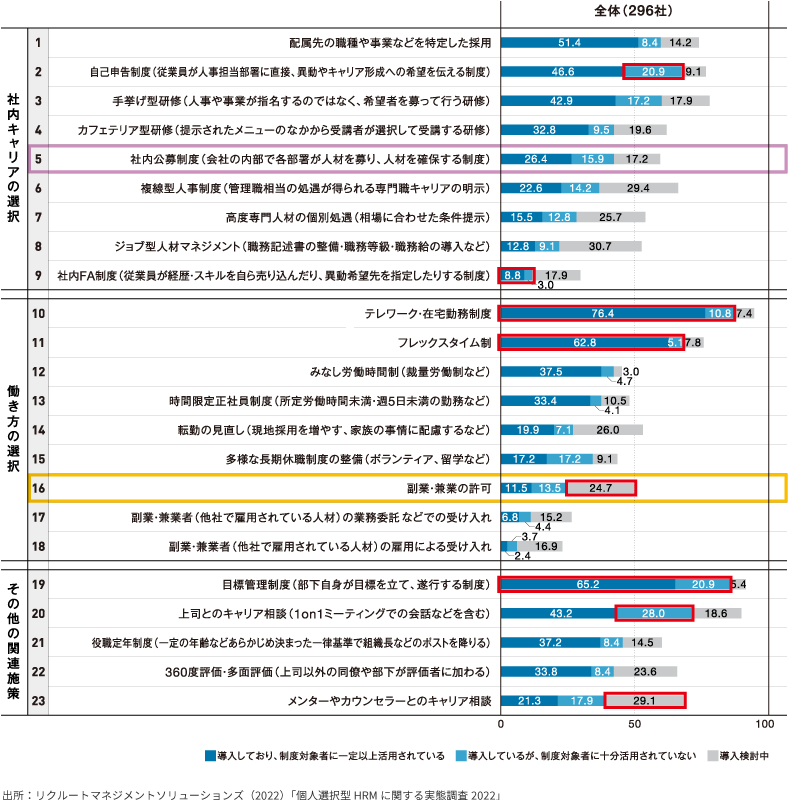
「社内公募制度」は、導入後に普及している企業とそうでない企業に差があります。私たちの調査では、普及のポイントは「募集ポジションを限定していない」「上司の拒否権はない」の2つである、という結果が出ました(図表4)。この2点をしっかり押えている企業では、社内公募制度活用が促進されていると考えられます。
<図表4>社内公募制度の運用実態
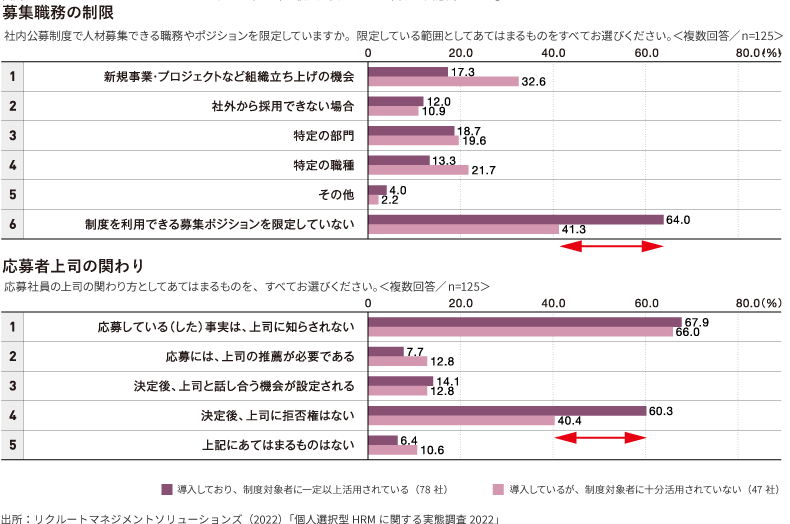
「副業・兼業の許可」については、導入していない企業が不安に思っている理由のほとんどが杞憂にすぎないと思われます。実際に導入した企業は、それらの理由を課題と捉えていないことが多いのです(図表5)。杞憂の壁を乗り越え、副業・兼業をポジティブに検討してみることをお勧めします。
<図表5>副業・兼業の導入企業と非導入企業の課題認識の差
導入しない理由:社内公募制度を導入していない理由として、あてはまるものをすべてお選びください。<複数回答/n=109>
導入企業の課題認識:社内公募制度の運用上の問題点・課題として、あてはまるものをすべてお選びください。<複数回答/n=125>
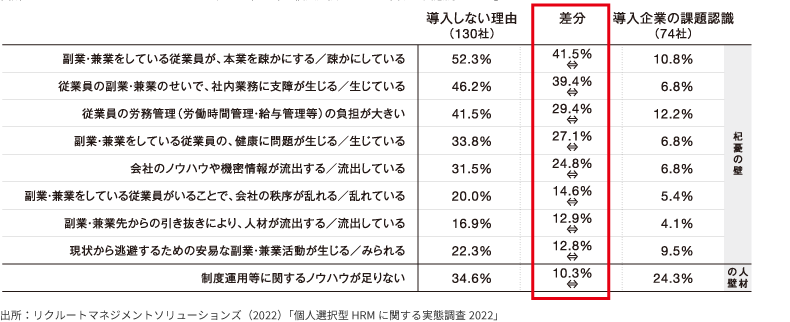
最後に、異動・配置ポリシーと組織能力の関係について紹介します(図表6)。私たちの分析結果では、個人選択中心タイプは離職率が下がり、多様な人材に活躍機会を与える傾向があることが分かりました。一方の選抜・底上げ・個人選択併用タイプは、変革実行力・現場力・求心力を高めることが明らかになりました。
<図表6>異動・配置ポリシーと組織能力の関係
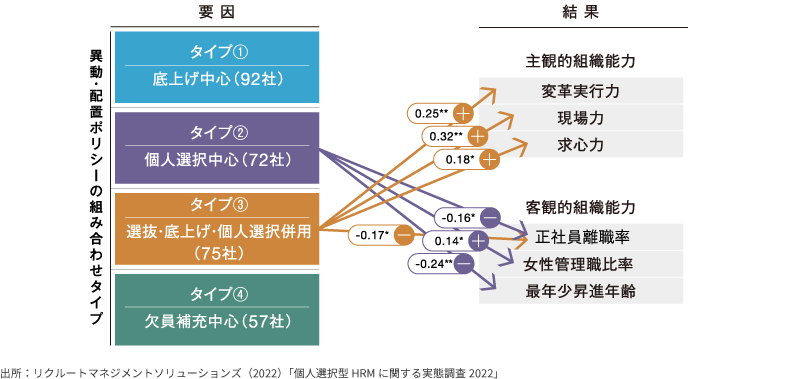
社内異動制度に自ら手を挙げる機会があると、たとえ不採用でも選択感は高まる
続いて調査2の個人調査の結果をご紹介します。個人選択感の実態(図表7)を見ると、働く個人の約6割が自分の仕事、働き方、キャリアを自分で選択していると感じています。また5~6割の人が、自分の希望が尊重されていると感じ、自分の将来展望をポジティブに捉えています。
<図表7>個人選択感の実態
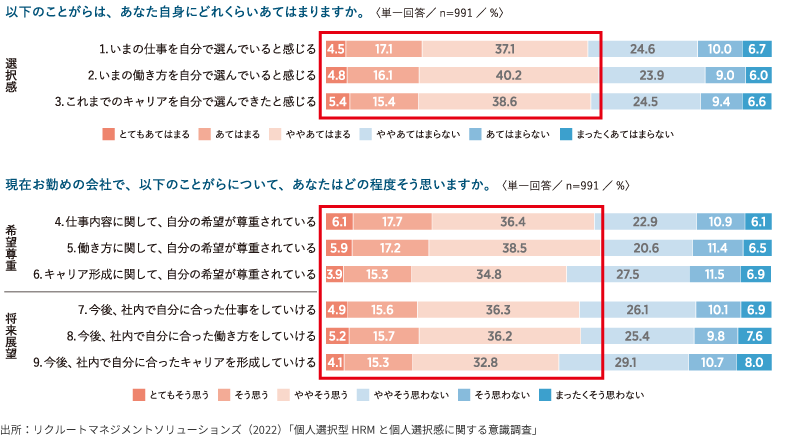
図表8から分かるのは、個人選択型HRM施策の導入と選択感がおおむね相関していることです。選択感を高めるという視点から見ても、個人選択型HRMを進めることが大切なのです。社内異動制度に絞ってお話しすると、当然ですが、自ら手を挙げた納得感のある異動は個人選択感を高めます。面白いのは、手を挙げて不採用だったとしても、選択感が高いということです(図表9)。異動の成否というより、自ら手を挙げる機会があることが選択感を高めるポイントのようです。
<図表8>個人選択型HRM施策の導入と選択感の関係
現在の会社で導入されている制度や仕組みについて、あるものをすべてお選びください。<複数回答/n=991>
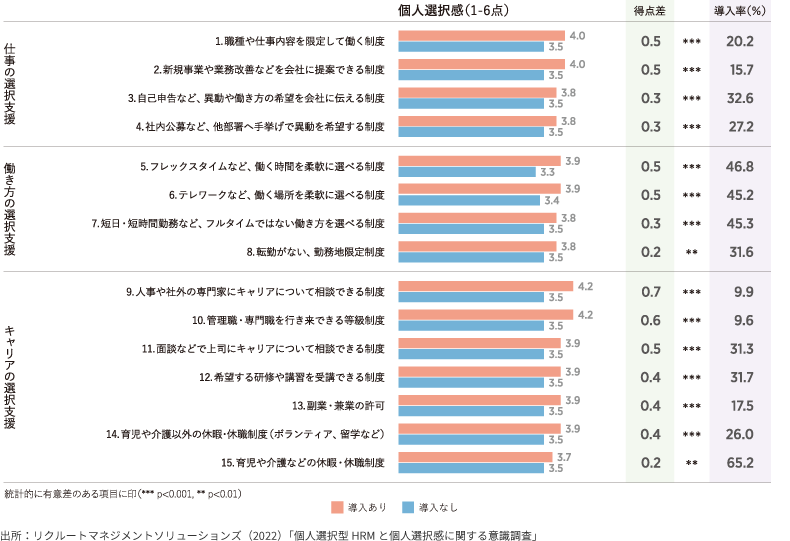
<図表9>異動経験と選択感の関係
現在お勤めの会社での人事異動に関する以下の経験のうち、あてはまるものをすべてお選びください。<複数回答/n=991>
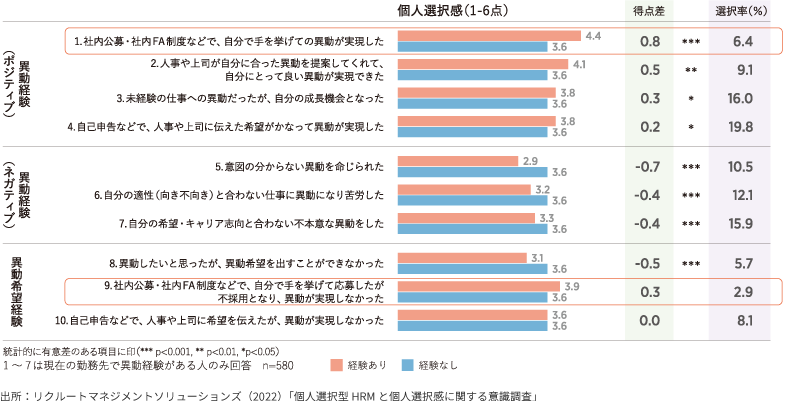
また、組織の特徴として「学習指向の評価」がある(チャレンジを評価して、育成の観点でフィードバックしてくれる)組織、「他部署・経営情報の開示」がある組織、「ライフ・キャリア重視」の組織では、個人の選択感が高まることが分かりました(図表10)。そして、個人選択型HRM施策導入数が多いほど選択感は高まること、選択感が高まれば、「人生・生活満足」「組織コミットメント」が高まり、「離職意識」が低減することも明らかになりました(図表11)。
<図表10>組織の特徴と選択感の関係
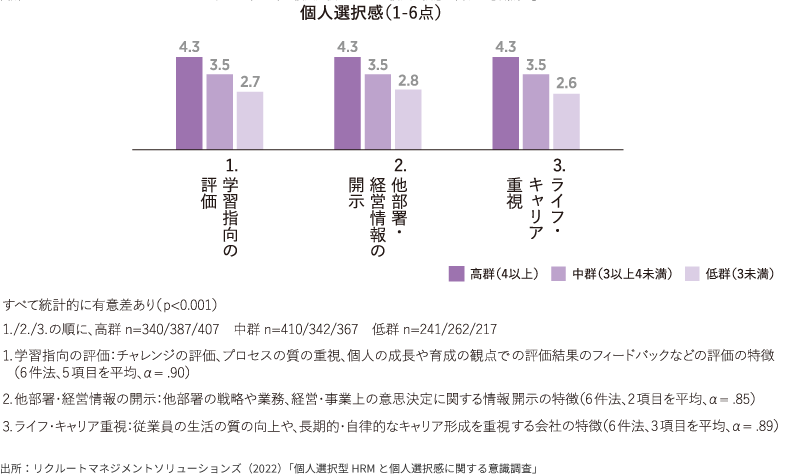
<図表11>組織の特徴、個人選択感、個人の意識の関係
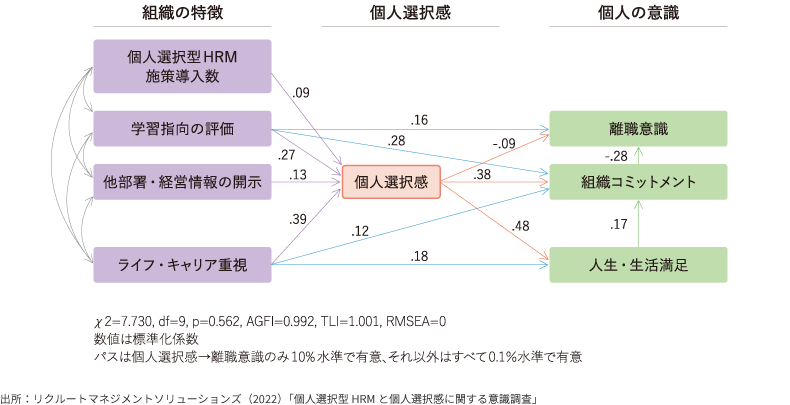
ただ一方で、個人選択型HRMには注意も必要です。なぜなら、自律的・主体的なキャリア形成にストレスや息苦しさを感じている人が約65%も存在するからです(図表12)。単に個人選択の幅を広げるだけでなく、個人が選択する際のサポートを充実させること(異動時の社内情報提供、キャリア相談など)、個人選択と組織主導を併用すること(特に次世代リーダー育成や教育研修などの場合)、個人選択型HRMを流動的な実験と位置づけて個人側の既得権益にしないことが大切です。
<図表12>自律的・主体的なキャリア形成のストレス・息苦しさ
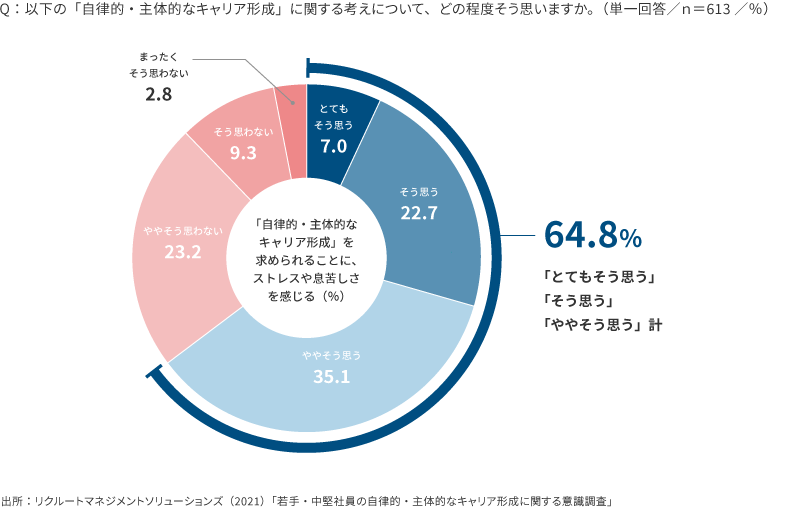
第2部 事例紹介 レバレジーズ
講師プロフィール
藤本直也氏 レバレジーズ株式会社 執行役員

1991年生まれ。兵庫県加古川市出身。大阪大学工学部卒業。2014年新卒入社。マーケティング部、新規事業の責任者、レバテックの経営企画を担当した後、25歳でレバレジーズ史上初の執行役員に就任。就任後は人事責任者、新規事業の統括を経て、現在は経営企画室長。2018~2019年度に、中央大学で新規事業、マーケティングについての非常勤講師を務めた。
「職務内容・キャリア・上司を選択できること」を極めて重視している
レバレジーズの藤本と申します。古野さんのお話を受けて、私は自社の個人選択型HRMの事例をご紹介します。私たちレバレジーズは、「レバテック」「看護のお仕事」をはじめとして、医療、介護・福祉、IT、人材や電力など、多様な領域で事業展開を行っています。2005年に創業し、18期目で年商800億円規模の会社になりました。2023年度には年商1000億円超えのメガベンチャーを目指しています。国内だけでなく、海外4カ国も含めて40事業を展開しており、正社員数は1400名(2022年4月)で、男女比は1:1です。正社員数は3年で約2倍の成長率となっています。インハウス型の経営を行っており、社内職種の選択肢が幅広いことが働きやすさにつながっています。
なお、私たちはGreat Place to Work® Institute Japan(GPTWジャパン)が発表する2022年「日本における『働きがいのある会社』ランキング ベスト100」において大規模部門3位、サブランキングにおいても女性ランキングの大規模部門1位、若手ランキングの大規模部門1位と、高い評価を受けました(図表13)。
<図表13>「働きがいのある会社」ランキング ベスト100(2022)で高い評価
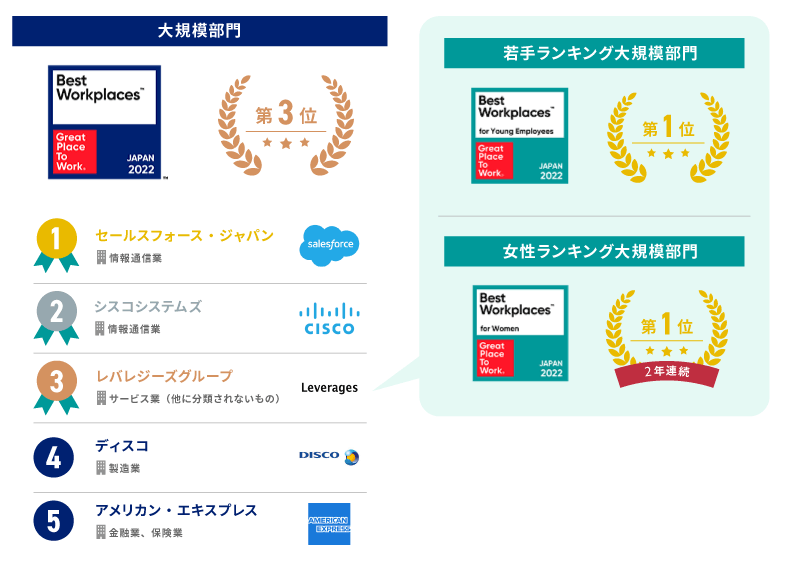
では、私たちがどのような個人選択型HRM施策を進めているかをご紹介します。結論から言えば、レバレジーズでは「動機づけ要因」の向上に向けた個人選択型HRMを行っていくことが最重要である、と考えています。動機づけ要因とは、職務満足を生む要因のことで、主に達成感・承認・仕事そのものなどを指します。対義語は、職務不満足を生む「衛生要因」で、会社の方針・労働条件・人間関係などのことです。
より具体的に言えば、私たちは個人が「職務内容・仕事上のキャリア・上司を選択できること」を極めて重視しています。なぜなら、これら3つの選択の自由が、動機づけ、モチベーション向上につながるからです。
そのうえで、「会社・事業のWillと個人のWillを一致させること」にも力を入れています。私たちの企業理念は、「顧客の創造を通じて、関係者全員の幸福を追求し、各個人の成長を促す」です。当然ながら、社員は重要な関係者です。その社員の幸福を追求するためには、社員一人ひとりのWillを大事にすることが欠かせません。個人のWillの重視は、働きがいの向上、成長実感、パフォーマンス向上、離職の減少にもつながると考えています。そのために、レバレジーズには絶対的な辞令が存在しません。
ただ一方で、私たちには「自由と責任」の文化もあります。「自由=個人のWillの裏には、責任=会社のWillがある」と捉える社風なのです。社員には、個人がやりたいことを選択する以上は、責任をもってやり遂げてほしいと伝えています。この自由と責任のカルチャーが、事業におけるアジリティを高め、戦略と実行の精度を上げています(図表14)。
<図表14>企業理念とカルチャー
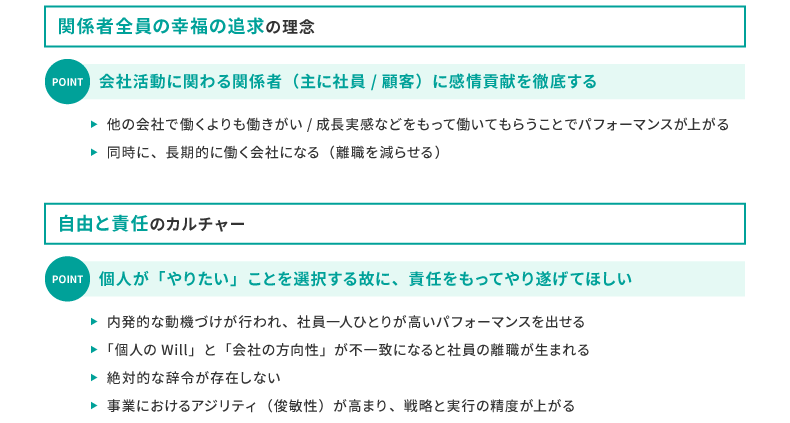
ミッションマネジメントの徹底が個人選択を最大化する近道
次に、個人選択型HRMの実践についてお伝えします。私たちは、採用から入社後までの一貫した個人選択型HRM施策を大事にしています。なかでも、採用・オンボーディングの初期段階が8割と言っても過言ではないと考えています。キャリア選択に前向きな社員を採用することがすべてのスタートとなるからです。採用時には、採用基準を徹底し、職種別採用を行い、選考段階におけるキャリア教育を徹底しています。そうすることで、候補者に個人のWillを明確にして入社してもらい、前向きに自分でキャリアを選択することを習慣化してもらっています(図表15)。
<図表15>主な採用施策
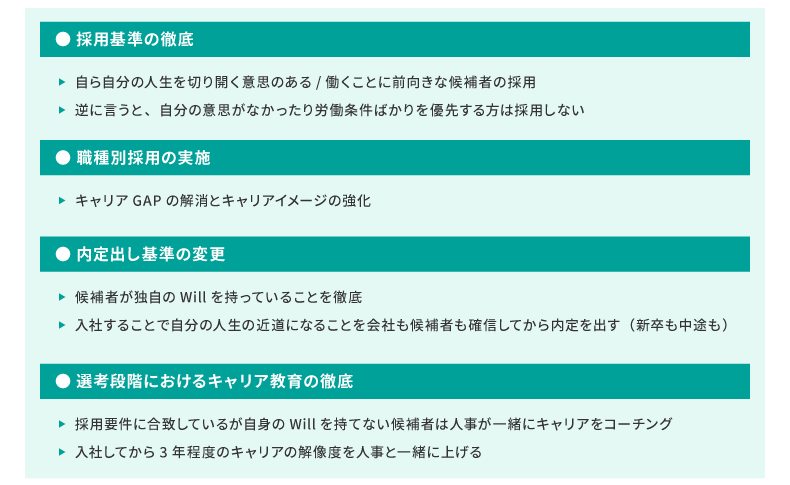
入社後は、社内公募求人サイト、事業部交換留学制度、急募公募ポジションイベント(新規事業コンテストなど)などを通して、社内の選択肢に興味をもってもらい、個人選択を促しています。また、個人選択をスムーズにするために、個人のWillを応援する文化の醸成と、個人の選択時の障壁を下げるための施策も行っています。具体的には、公募フローの整備、職種変更時の基準明確化、1on1の徹底、組織サーベイの徹底などです(図表16)。
<図表16>主な入社後施策
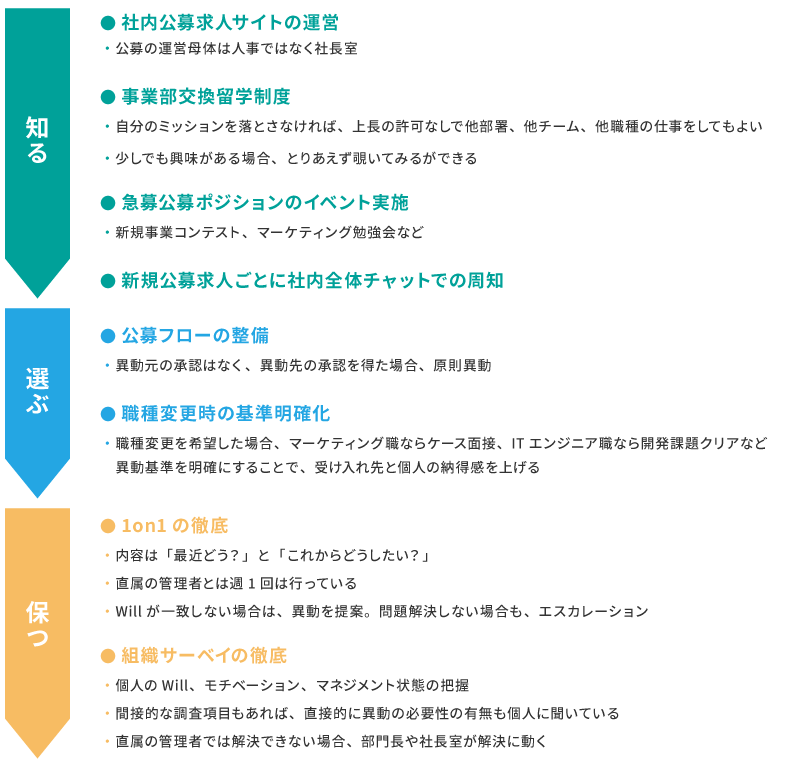
個人的には、ミッションマネジメントの徹底が、会社のWillと個人のWillの一致度を高め、個人選択感を最大化する近道だと感じています。個人のWillと事業軸のWillと機能軸のWillの合致点に、個人のミッションを用意するのです(図表17)。具体的には、メンバーとマネジャーが1on1でメンバー自身のミッション案と事業戦略をすり合わせて、メンバーのミッションを定めます。その際、必要に応じて、ミッション実行に必要なポジション・権限を用意します。その後は3カ月に1度、ミッションローリングを継続的に実施しています。
<図表17>ミッションマネジメントの理想
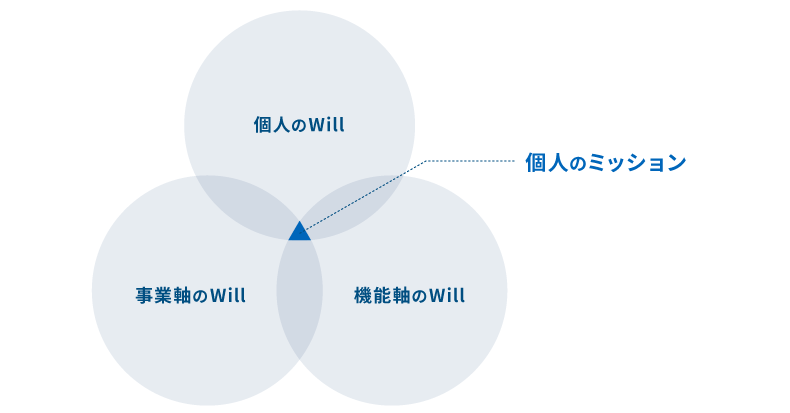
私たちは、以上のような実践に取り組んでいます。最も注意しているのは、「動機づけ要因の向上」や「会社のWillと個人のWillの一致」という目的をぶれさせないことです。
【text:米川 青馬】
まとめ
実施した調査によると、選択の自由があると感じる方が、人生・生活満足度と組織コミットメントは高まり、離職は減る。しかしながら、選択の自由を多くすると個人がわがままを言いだすのではないかと経営側は心配になる。個人選択型HRMを進めているレバレジーズの事例を聞いてみると、そのような懸念を払拭する経営を行っていることが分かる。つまり、個人のWillを尊重しつつも企業側のWillとのすり合わせを丁寧に行っている。そうすることで、個人側のモチベーションを高めつつ、個人の持ち味を経営に生かし、企業側がやりたいことを実現している。
施策面ではそのようなことを行っているが、ベースには社員の方々を「大人扱い」していると、藤本さんの話を聞きながら、感じた。相手を大人と思えば、相手を尊重し、相手の意向を大切にする。だから、無理やりな異動や仕事のアサインはない。社員は社員で、大人であれば、甘えられないし、自分勝手なわがままは言えない。自由と責任がセットである。
企業において、個人選択型HRM施策が増えていくことは、社会において大人が増えていくことになる。成熟した社会という観点で、それはそれで好ましいと思われる。
【組織行動研究所 所長 古野庸一】
この記事で引用した調査
「個人選択型HRMに関する実態調査2022」(企業調査)
「個人選択型HRMと個人選択感に関する意識調査」(個人調査)
関連する記事
RMS Message vol.67 特集1 個人選択型HRMのこれから(2022年8月発行)
レバレジーズ「企業の成長には俊敏性が必須 社員のWill尊重による自由と働きがいが鍵」
バックナンバー
アフターミドルの可能性を拓く~ポストオフ・トランジションを促進するには~(2022年6月開催)
キャリア自律施策の展開~なぜキャリア自律が進まないのか~(2022年3月開催)
自律とエンゲージメントを促進するために 変わるマネジャーの役割(2021年12月開催)
コロナ禍で注目される自律的な働き方とエンゲージメント(2021年9月開催)
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



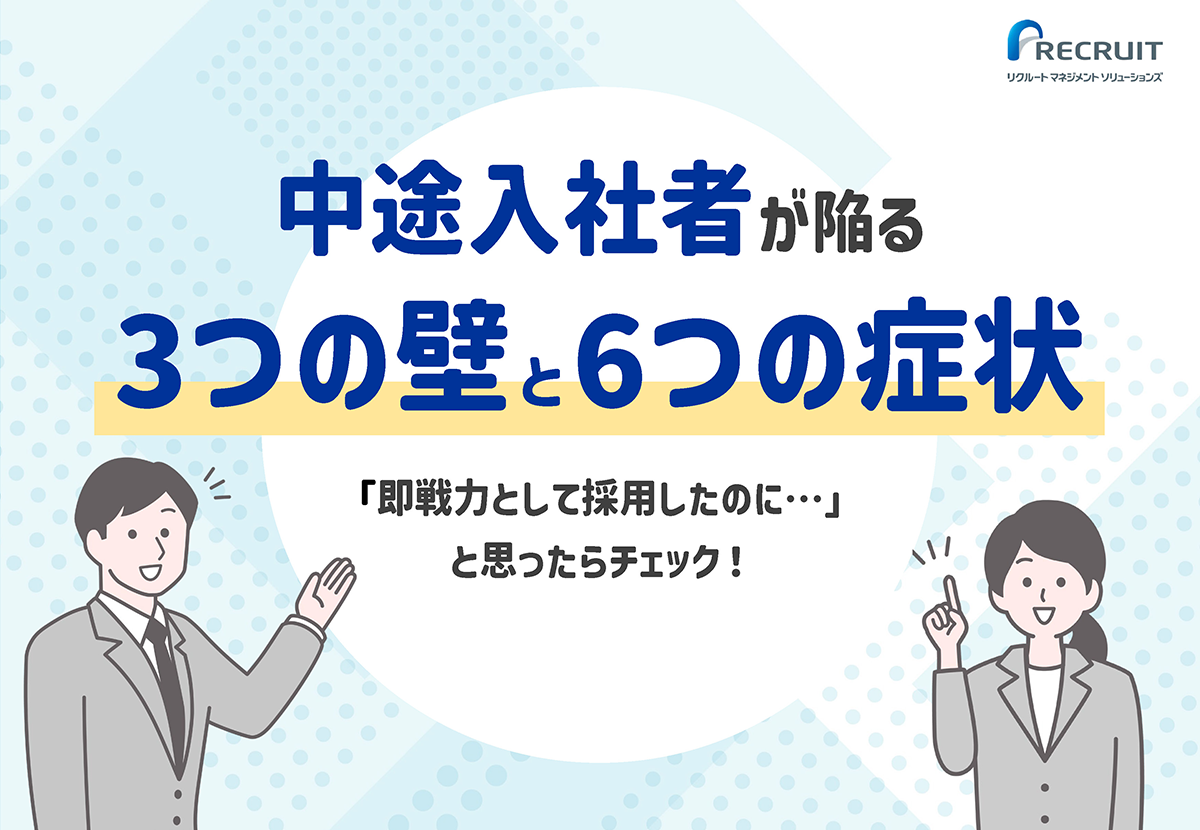
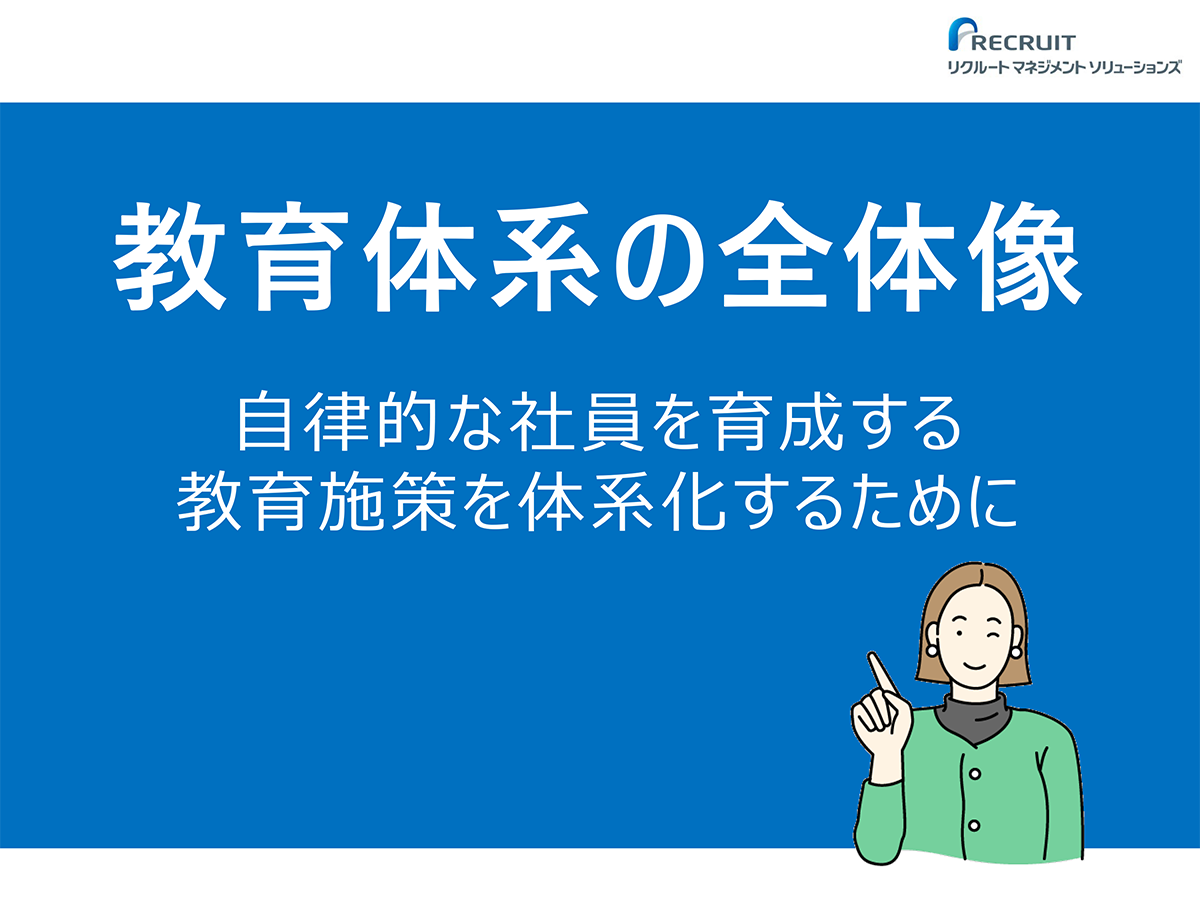









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての