連載・コラム
マネジャー座談会「リモート時代のマネジャーの役割」第1回
リモート時代にマネジャーが直面している課題とは
- 公開日:2020/11/16
- 更新日:2024/11/25

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、多くの企業では、想定外のスピードでテレワーク(リモートワーク、在宅勤務)への移行が進んだ。各職場ではこの数カ月、業務のあり方の急激な変化による不安や不便を解消すべく、マネジャーを中心として試行錯誤を重ねてきただろう。しかし、それぞれの職場で実際にどのような課題に直面し、それをどう克服しようとしているかについては、なかなか実態が見えづらい。
そこで、今回、さまざまな職場で働く30~40代のマネジャー16名にお集まりいただき、「テレワークが常態化するなかでマネジャーとしてどのような課題に直面しているか?」「この環境下でマネジャーが本来の役割に集中するためには何が必要か?」についてオンライン座談会を行った。これから3回にわたり、座談会の内容とそこから再考したリモート時代のマネジャーの役割について、レポートする。
(マネジャー座談会運営事務局:藤澤理恵、佐藤裕子、藤村直子、石橋慶)
参加者の概要とテレワークの導入状況
座談会は、2020年8月27日(5名参加)、9月2日(5名参加)、9月7日(6名参加)に開催した。参加者の主なプロフィールは図表1のとおりで、業種も管轄する部署の仕事内容も多様な16名となった。所属企業の業績へのコロナ禍の影響はさまざまで、生活様式や働き方の変化にともなって需要が右肩上がりの職場がある一方、新規受注が停滞し業務の量や質が低下していたり、戦略の見直しを余儀なくされていたりといった職場もあった。
<図表1>参加者の主なプロフィール
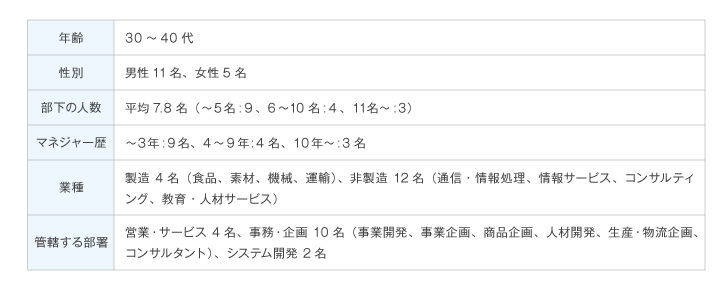
今回は、テレワーク経験があることを条件に参加者を募っており、座談会の開催時点で全員がテレワークを継続中だった。16名とも、テレワークの準備はしていたが未導入だった、あるいは部分的にテレワークを進め始めていたところで、緊急事態宣言前後に一気にフルリモートに転換したという。9月末の段階でも、13名は部下がほぼフルリモート、10名はマネジャー本人もフルリモートを続けている(図表2)。
<図表2>職場のテレワーク実態
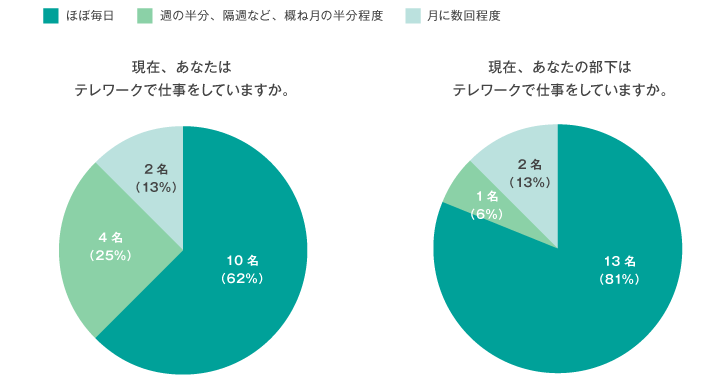
開発系なのでゆくゆくはリモート化を考えていたが、3月末にまさかのタイミングで準備なく一気にフルリモートに。8月には在宅勤務制度も人事で整備され、本格的にフルリモート体制になっている。(教育・人材サービス/システム開発)
緊急事態宣言中は社員の9割が出社しなかったが、どうしても顔を合わさないとやりづらい仕事もあり、今はそれぞれ月に数回くらい出社している。(運輸/生産・物流企画)
4月に着任して7月ぐらいまで部下3人に一度も会ったことがないという状況で、7月に1回集まったがそれ以来また会ってない。(情報サービス/人材開発)
座談会前半では、このようにテレワークが進展したことで、マネジメントや職場にどのような変化があったのか、マネジャーとしてどのような課題に直面しているかを、ざっくばらんに意見交換した。
マネジャーとしての課題の感じ方はさまざまで、システム開発やコンサルティングなど独立性や専門性の高い仕事が多い職場やベテラン中心の職場を担当するマネジャーからは、思ったより問題なくテレワークに移行できたという声も少なくなかったが、異動者が多い職場や、新人・若手中心の職場、営業の職場を担当するマネジャーは、いろいろな面で困難を感じている傾向があった。また、課題がある一方で、このコロナ禍で一気に押し寄せたテレワーク化がもたらした副産物をポジティブに捉える声も多数聞かれた。
テレワークの進展がもたらしたポジティブな変化
テレワークの進展は、課題だけではなく移動時間の低減などいくつものポジティブな変化をもたらしたが、今回の参加者からは、主に以下の3点が聞かれた。
・会議関係での忖度がなくなった
・社内の交流が広がった
・働き方の意識改革が進んだ
1.会議関係での忖度がなくなった
普段から多くの会議に忙殺されてきたマネジャーにとって、会議が効率化されるのは大きなメリットである。これまで多くの人がムダだと思いながらも、忖度により変えられなかった会議のあり方が一気に変わったという。
役員会議とか査定会議といった緊張感の高い会議もリモートになったのは大きい。権限のある人と顔を合わせて圧を感じるというストレスがなくなり、資料と会話に集中できるようになった。(情報サービス/事業企画)
3年ぐらい前からリモートで話ができる状態にあったにもかかわらず、役員に15分説明するために1時間かけて出向くようなムダがあった。今は、リモートでお願いしますと一言で言えるし、むしろ上役からリモートでいいよと言ってくれる状況。行かなきゃいけないものだというお互いの暗黙の了解があったが、もしかすると相手もいいよと思っていたかもしれないと気づいた。(運輸/生産・物流企画)
2.社内の交流が広がった
出社して人と会う機会が減ったことで、かえって、お互いの孤立を防ぎ、人とつながろうという動きが、草の根的な形で発生しているという例が多く話された。場所はオンライン上であり、働く場所にとらわれず、これまで接点のなかった他部署、他拠点の人との交流が広がり、視野を広げた学びの場にもなっている。
社内の人と話をする機会がないのを心配して、グルメ、旅行、映画というような、テーマ別のチャットルームを作って盛り上げていこうというようなチームができ、逆に今まで接点がなかったほかの拠点の人と話をする機会が増えたのはよかった。(情報サービス/営業・サービス)
少し前に始めていた社内のオンライン勉強会の参加者が一気に増えた。テーマは各自でエントリーし、心理的安全性を大事にして全員平等にニックネームで呼び合う形式で、夜に非公式でやっている。スーパー営業担当の話を研究員が聞いたり、技術系の話に別の部署の人が気軽に参加したりできている。(食品/事業開発)
3.働き方の意識改革が進んだ
会社や部署による差が見られるところではあるが、数年かけて進んでいた働き方改革について、成果を出せば働き方は自由でも仕事は回るということを、経験的に実感する人が増えたという声が聞かれた。
これまでは上司の承認が必要だったが、2月の末ぐらいから承認なしで全員原則テレワークになった。自分もメンバーも含めて全く抵抗感はなく、基本すごくいい。数週間前に出た従業員満足度の結果は、働き方回りについては相当高い数字が出ていて、成果を出せば働き方は自由でいいよねという考えに変わってきている人が多いと感じる。(情報サービス/事業企画)
業務マネジメントで直面している課題
直面している課題についてはどのような話がなされただろうか。マネジャーの仕事は大きく業務のマネジメントと部下のマネジメントからなるが、業務のマネジメントで直面している課題として多く聞かれたのは、以下4点だった。
・新しい信頼関係を築くのが難しい「新体制の立ち上げ問題」
・インフォーマルな会話から生まれるものがある「ちょっといい?問題」
・新しいものを生み出す会話がやりにくい「ホワイトボード問題」
・微妙な機微がつかめない「顧客の懐に入れない問題」
1.新しい信頼関係を築くのが難しい「新体制の立ち上げ問題」
緊急事態宣言が4月だったこともあり、参加者のなかでも、自身の異動、部下の異動や入社、組織合併や再編にともない、新しい体制や信頼関係を築く必要に迫られるなかでフルリモートに突入した人が多数いた。関係性ができる前に、お互いの仕事の考え方や進め方をすり合わせていくのはそもそも難しい。これを対面の機会が限られた状況で行うのは非常に難しく悩ましいということで、意見は一致していた。
自分は4月から新しい組織に異動で、部下も何名か、地域間異動も含めて異動者だった。自分のマネジメントの考え方として、営業組織におけるメンバー間の関係性の質を担保する密なコミュニケーションをいかに確保するか、職場関係の安全・安心というのをどのようにつくるかを心がけていたので、集まって話すことを完全に封じられたなかでの立ち上げというのは非常に難しいと感じた。(情報サービス/営業・サービス)
この4月に会社統合をして、別の会社の人が新しく10人ぐらい入った。仕事のやり方を極力統合していきたいが、本来なら対面でできる人間関係づくりがリモートだとなかなか難しく、苦労している。(素材/生産・物流企画)
プロジェクトベースで、都度、人が替わっていくスタイルで、コロナ発生後も何回かチームが変わるという体験はしている。新しく会うメンバーは何人もいるので、コミュニケーションの難しさはコロナ禍になってからよく感じている。(コンサルティング/コンサルタント)
7月に海外から帰国し新しいチームに着任して、メンバーにも異動者がいる。対面のコミュニケーションがないままチームとして信頼関係を構築していくのが今非常に今難しい。週次で出社してミーティングやランチをすることで一応仲良くはなれたかなと思うが、任せておいてちゃんとアウトプットを出してくれるのかまだまだ信じきれていないところ。(通信・情報処理/商品企画)
2.インフォーマルな会話から生まれるものがある「ちょっといい?問題」
既存の枠にとらわれない新しいアイディアは、周辺的なもの、異質なものから生まれる。場所を共にして長時間過ごすなかで生じる何気ない会話がそのきっかけになっていたことを、失ってあらためて実感しているという。オンライン上で雑談を引き起こすための工夫がされているものの、思うように機能していない模様だ。
雑談がないというのが、実はかなり大きいと思う。定期的に出社してお互い見えるところで仕事をする日を作ったが、そのときポロッと誰かが言った一言が実はすごく重要で、そこからワーッと緊急の会議を動かして物事が進んだことがあった。一番失われているのはそういうものかなと最近思う。(通信・情報処理/システム開発)
新規事業をやっていくなかでは、チームを超えた雑談から、「ああ、そういうアイディアがあるよね」とか「そういったソリューション、確かに面白いよね」というのが出てくるので、それがなくなったのは困っている。(教育・人材サービス/事業開発)
チャットツールで雑談チャンネルを作ってみたが、やっぱりなかなかうまくいかなくて、雑談チャンネルは決まった人しか書き込まなくて廃れてしまった。(通信・情報処理/システム開発)
3.新しいものを生み出す会話がやりにくい「ホワイトボード問題」
企画職を中心に盛り上がったのは、「ホワイトボード問題」だ。抽象的な議論、ブレスト段階の議論、行きつ戻りつ具体策を探る議論など、ホワイトボードを囲んでお互いのイメージをすり合わせてきたが、それがオンラインでできるツールがないという。手書き資料OKを方針とし、議論の質とスピードを確保しようとしているといった工夫も披露された。
ホワイトボードを使った抽象的な議論ができないのが課題として大きい。テキストと会話での構造的なアウトプットができないとどんどん置いていかれてしまうし、言葉の定義のニュアンスや理解が難しくて手戻りになるというケースが結構あると感じている。リモートはすごくいいが、100%だとこの点でちょっとしんどいと思っている。(情報サービス/事業企画)
プロダクトのバリューを定めていくとか、ミッション・ビジョンを決めていくというところの、議論のしづらさは、リモートになって少し出てきている。(教育・人材サービス/事業開発)
全員が違う母体から専門領域をもって集まっている部署で、ちょっとした会話をすることでお互いの情報をやり取りしながらものを作っている。在宅だとそのちょっとした会話ができないことにみんなストレスを感じていて。対面だとちょっとした会話でできていたのが全部電話して、パワーポイントに書いて送ることになると時間もかかる。今は結局、会社に集まってきてしまっているのが現状。(運輸/生産・物流企画)

対策例
手書きOKでスピード重視
部内の資料においては手書きを全部OKにした。パワーポイントでまとめなくていいので、ノートに書いて画面で見せたり送ったりで早く話ができる。相手が部長くらいまでなら、資料のクオリティが落ちるのはごめんなさい、で通すように言っている。(情報サービス/事業企画)
ホワイトボードを使いたい場面は2つあって、最初に前提の確認をしたいときと、話を進めるために認識をそろえながら新たな案を書き込んでいくとき。前提の確認については、チャットなりメールなりで箇条書きにして条件を整理しつつ、電話で会話することが多い。問題は後者で、前提を確認し方針を打ち合わせても、アウトプットが期待どおりにならないときは、もう一度、本当に細かく、ちょっとじゃあ今書くねということで手書きのものを画面に写してみたり、パワポに殴り書きしたものを共有したりでやっている。が、ホワイトボートのときよりスピードは非常に落ちている。(情報サービス/事業企画)
4.微妙な機微がつかめない「顧客の懐に入れない問題」
法人営業職のマネジャーが全員口をそろえたのは、「顧客の懐に入れない問題」だ。商談の成立にはお互いの能力や誠意を見極める必要があり、交渉には微妙な駆け引きもある。対面の商談や会食が十分に行えないなかで本当に困っているという。部下には強要できないが、相手さえよければ自分は会うようにしているという人もいれば、この際発想を変え、オンラインだからこその強みを生かした営業スタイルへの転換に目を向けているという声も聞かれた。
お客さんとダイレクトのコミュニケーションをしていないと微妙な機微は分からない。どういう反応がくるかというのがその言葉とか顔だけじゃなく、雰囲気から感じ取るというのが結構大事。それに合わせてプレゼンなり提案なりをしているので、本当に困っている。(機械/営業・サービス)
これまで接待がかなり重要な位置づけだったが、非常に難しくなったこともあり、やっぱり顧客とのコミュニケーションに課題があるという認識。空気を読んだり、機微を読み取ったりというのがほぼできなくなって、本当にやりづらい。より対人コミュニケーションに神経を使う必要があるなと思う。(情報サービス/営業・サービス)
営業職としては、やっぱり顧客にぐっと入り込むというところが難しくて。顧客関係性をどうやってつくっていくかが、実質的に難しい部分。それを自分の部下とどう乗り越えていくのかというところにまだ解がなくて、今後の提案活動が本当にうまくいくのかどうか不透明。(情報サービス/営業・サービス)

対策例
できる限り対面する
今、出社することは義務ではなく、選択できる権利という状況になっているため、メンバーに出社を強制するということは基本的に不可能だが、営業に関しては、自分は会ってもいいという人にはどんどん会いに行っている。(情報サービス/営業・サービス)
別の営業スタイルに目を向ける
なかなかアポイントメントが取れないお客様も、オンラインだったらいいよだとか、出張だと1~2日かかり、今までアプローチできなかったところに逆にアプローチできるだとか。これまで出張でそれぞれ忙しくてできていなかった、プレゼンテーション前のリハーサルや資料共有などは、チャットやオンラインの打ち合わせで今まで以上にコミュニケーションを取って質を上げている。(機械/営業・サービス)
今事業を起こしているアフリカは対面の文化。実際に会うことができないため、顧客拡大は遅れている。それなら広げるのではなく、絞った相手とより深く関わることでイノベーションを目指そうという、今までにない動きを始めた。(食品/事業開発)
「ホワイトボード問題」や「顧客の懐に入れない問題」については、参加者から実践的な工夫や発想の転換がいくつか出され、なるほど、やってみますなどと盛り上がった。一方、「新体制の立ち上げ問題」「ちょっといい?問題」についてはこれといった解決策が出されず対策の難しさを感じさせられた。今後、早急に解決の糸口を探していくべきテーマだと思われる。
部下マネジメントで直面している課題
一方、部下のマネジメントについてはどうだろうか。コロナ禍、フルリモートが部下の心身に与える影響については、多くのマネジャーが最も懸念したところだろう。今回の参加者も部下とのコミュニケーションを増やす、相談しやすい雰囲気をつくる、などの行動を取っていた。そんななかでも苦慮している問題として次の3点があった。
・オンライン向けの表情しか見えない「新規参入者のコンディション把握問題」
・一緒に仕事をして学ばせてきたが …… 「背中を見せられない問題」
・意識して動きを見せることが必要に「アウトプットへの意識改革問題」
1.オンライン向けの表情しか見えない「新規参入者のコンディション把握問題」
懸念してケアしているにもかかわらず、やはり新入社員や若手の異動者や転職者に、不調を訴える人が出てきてしまったケースが複数あった。新規参入者は、人事やマネジャーだけではなく、周囲の関係者との関わりのなかで、組織の文化や文脈に馴染み、居場所を見つけていく。オンラインで1対1になりがちな関係を、どう広げていくかを考えて突破口を開こうとしている例もあった。
新卒が配属されたが、現場の言葉やテンションの変化に気づくことができず、メンタル不調で退職してしまった。(情報サービス/営業・サービス)
同僚の部下だが、コンサルタントに転職してきたばかりで、いきなりリモートに入った若手が1カ月で調子を崩してしまった。定期的にコミュニケーションを取っていたが、それでも会わないとちょっとした相談ができないし、マネジャーも気づかない。(コンサルティング/コンサルタント)
土地勘のないところに4月から異動で来た若手がいて、周りに誰も知り合いがいない状態。これまでオフィスに行ったのは1回だけで、ずっとワンルームの家に1人でいるという状況なので、マネジャーとして気にして声をかけるようにしている。(情報サービス/事業企画)
マネジャーが忙しそうで相談しにくいと言われ、相談しやすい雰囲気はどうすれば出るのだろうと悩んでいる。(情報サービス/事業開発)

対策例
相談しやすい職場や上司
何でも言えるような、心理的安全な環境を作れるように、お互いの特徴がわかるサーベイを実施して共有している。「この人はこういうタイプなんだ」というのが分かってくると発言の意図も見えてくるし、フラットに物事を言えるようになる。(教育・人材サービス/事業開発)
リモートになって相談しやすい佇まいとはどうあるべきか、がマネジャーにさらに問われていると思う。必ずその人の名前を呼ぶとか、発言に対してしっかり反応するとか、意見してくれたことには謝意を示すとかにはこだわっている。(コンサルティング/コンサルタント)
2.一緒に仕事をして学ばせてきたが …… 「背中を見せられない問題」
これまでのOJTでは、一緒に仕事をするなかで背中を見せて、その仕事で何を大事にすべきか、どのように行動すればいいのかを伝えてきた。また、部下が誰とどういうやり取りをしているのか、横目に見てタイムリーにフィードバックすることができた。それができないなか、どうやって部下の能力を引き上げていくのかについて、自分はこう考えている、といういくつかの考えが熱心に取り交わされた。
他部署と1人で調整できるようなスキルについて、オフィスにいると後ろや隣でどういう仕事をしているか、どのような会話をしているかが見えるので、さっきのミーティングのあの発言は良かったといった声がけの積み重ねで成長させられるが、今はどういうやり取りをしているのか全く見えないのが悩み。営業組織であればリモートで同席すれば少なくともセールストークは多分まねできると思うが、社内打ち合わせに教育目的だけで同席するのもどうかと。(素材/生産・物流企画)
打ち合わせに一緒に行って上司と終わった後に話すことができれば、進むべき方向やどのくらい大事な仕事かという温度感も伝わるが、それがない。やってみせるということができず、時間ないからこちらであとはやっておくから、みたいなことがこれまでもいくつか出てきている。(通信・情報処理/商品企画)

対策例
方針づくりを重視
方針づくりというのは非常に重視して時間を割いている。この作業はこういう方針でいつまでにこういうアウトプット、できればプラスアルファでここまでいきたいというのを割と情熱を持ってメンバーには説明するようにしている。資料の絵とか文字数で伝わるように努力している。(通信・情報処理/商品企画)
伸ばすべき部分を絞って戦力化
何でも背中を見せるしかないというのは、現状把握から問題解決までの一連のプロセスの何ができていないかをこちらが把握できていないことからくると思う。彼・彼女は今ここまでできている、ここはできなくて、今期伸ばすのはこの部分というのを上層部とも合意して、そこについては裁量を与えたり徹底的に伴走したり1on1で集中的に扱ったりして、基本的には育てるというよりは業務遂行に必要な戦力まで早く引き上げることを考えている。(情報サービス/事業企画)
3.意識して動きを見せることが必要に「アウトプットへの意識改革問題」
いかに早く、精度高いアウトプットをして、どんどんみんなにぶつけてディスカッションして物事を進めていくかというところが大事だが、放っておいてもちゃんとアウトプットを出してくれるのかというとまだまだ十分ではない。リモートでは、本人が自覚して、アウトプットをアピールしていく必要が高まっているが、その価値観を理解して意識してもらうのが結構難しくて、苦労している。(通信・情報処理/商品企画)
対面のミーティングは苦手だから、で済んでいたような方も、オンラインになると話してもらわないといけない。ほかの部署から、聞いているか聞いていないか分からない、というようなネガティブなフィードバックが増えている。(教育・人材開発/システム開発)
在宅ワークが当たり前になると、コミュニケーション能力が高い人の方が重用される。よりアウトプットが問われる時代。メンバーも言語化力を磨いたり、アウトプットしたりできるようにならないといけない。(コンサルティング/コンサルタント)

対策例
意識を変えてもらう
リアクションやアウトプットが普段から苦手なメンバーも多いが、性格だからではなくて、スキルとして必要なんだと、メンバーともコミュニケーションし始めたところ。(教育・人材開発/システム開発)
カジュアルな場で慣れてもらう
ITエンジニアの特徴かもしれないが、オンラインで会議をやっても発言がなかったりする。気軽にといってもどうしても堅苦しくなるので、少人数でオフィシャルではなくカジュアルに話せそうな場をつくるようにしている。(コンサルティング/コンサルタント)
以上、部下マネジメントの課題は、部下それぞれの意識やスキル、置かれている環境によって個別に判断や支援を要するものが多く、マネジャーとしてどこまで対応していくべきものなのかも悩ましいという声も聞かれたが、各問題の対策として語られたような、方針を明確にする、部下同士の学び合いを促進する、マネジャーの役割を明確にするといった組織的なアプローチは、マネジャーの負荷が高くなりすぎないための有効な方向性かと思われた。
座談会後半は、さらに話を深め、こうした課題に直面するなかで、マネジャーとしての時間の使い方がどう変わったかについて伺った。
マネジメントスタイルの変革についてはこちらの特集で詳しくご紹介しています。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
研究員
佐藤 裕子
リクルートにて、法人向けのアセスメント系研修の企画・開発、Webラーニングコンテンツの企画・開発などに携わる。その後、公開型セミナー事業の企画・開発などを経て、2014年より現職。研修での学びを職場で活用すること(転移)、社会人の自律的な学び/リスキリング、経験学習と持論形成、などに関する研究や、機関誌RMS Messageの企画・編集などに携わる。

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
客員研究員
藤澤 理恵
リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。
“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。
経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)














 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で