導入事例
エンゲージメントスコア大躍進を支えるハードとソフトの組織改革。インサイズのデータで課題設定・施策改善サイクルを加速
ヤマハロボティクス株式会社(旧:ヤマハロボティクスホールディングス株式会社)

- 公開日:2025/07/22
- 更新日:2025/07/22
事例概要
背景・課題
2019年に設立された持ち株会社であるヤマハロボティクスホールディングスには、ヤマハ発動機、新川、アピックヤマダ、PFAの4社のメンバー、さらには中途入社者が集まっていました。それぞれのバックグラウンドの違いから1つの会社として一体感を醸成することに苦慮していました。上司と部下の「関係の質」が最大の課題ではないかと考え、職場改善の第一歩として「1on1」を導入し、上司・部下の関係の質を高めることにしました。
検討プロセス・実行施策
インサイズは、1on1コミュニケーションの支援だけでなく、施策のPDCAサイクルを回すのに役立っています。インサイズの分析結果を活用することで、社員が抱えている課題がコミュニケーションで改善できるソフト面のものなのか、人事・経営として取り組むべきハード面のものなのかが明らかになり、より的確に対応できるようになりました。抜群の使いやすさ、記名制サーベイで個々の現状を明らかにできる点、高頻度に実施できる点もありがたいです。
成果・今後の取り組み
インサイズや1on1だけの影響ではありませんが、エンゲージメントスコアは年々上昇してきました。2024年度には、エンゲージメントスコアの実績値と改善度の2軸において、ヤマハ発動機グループ国内トップクラスのスコアを記録しました。社員の皆さんが「長く働きたいと思える会社」になってきたことは間違いないと思います。コミュニケーションの土壌が整った結果、現場からも組織改善アイディアが出るようになりました。
背景・課題
異なるバックグラウンドのメンバーが集うなか、共通言語もなく信頼関係の構築が課題だった

森田:私たちヤマハロボティクス株式会社は、ヤマハ発動機を親会社として、ヤマハロボティクスホールディングス、新川、アピックヤマダ、PFAの4社合併によって、2025年7月に誕生した会社です。新川、アピックヤマダ、PFAの3社は、半導体後工程プロセスの各種製造装置や水晶デバイスやカメラモジュール用製造装置に強みを持っています。
この強みにヤマハ発動機の表面実装工程や産業用ロボットのソリューションを加えて、ワンストップのロボティクスソリューションを提供しています。
川上:当社には、先述の4社のメンバーが集まっています。当然ながら、4社の文化はそれぞれ異なり、共通言語もありませんでした。出自の違うメンバーに対してはお互いに遠慮してしまう側面もあり、本音でのコミュニケーションがなかなかできず、信頼関係構築や一体感の醸成に課題がありました。設立間もない組織であったこともあり、この会社でどのようにキャリアを築いていくかもイメージしにくい状況にありました。正直に言うと、インサイズを導入した2022年時点では、私自身この会社に長くいることは想像できなかったし、同じように感じていた社員は少なくなかったと思っています。一言で言えば、エンゲージメントが低い状態にあったのです。
2022年に、ヤマハ発動機から出向してきた森田が新たな上司となりました。実のところ、最初はかなり警戒していました。彼が何をミッションとしてこの会社にやってきたのか、当時、会社から特に説明もなく、皆が「あの人は一体何者!?」と不安に感じている状態でした。現在の私と森田には、1on1が不要なほどの深い信頼関係がありますが、当時は今とは全く違う状況でした。

森田:私が出向してきた当初は、川上に限らず、多くの社員がこのような感じでした。上司のいないところでヒソヒソ話をする風景をよく目にしました。上層部から与えられるタスクに十分に納得して働いている社員は多くなかったと思います。
私は、上司と部下の「関係の質」が低いことが要因の1つであり、改善の基礎になる部分だと考えました。ダニエル・キム氏が提唱した「成功の循環」モデルによれば、関係の質が高くなると、思考の質が高まり、行動の質が高まり、結果の質が高まる好循環が生まれますが、関係の質が低くなると、思考の質も行動の質も結果の質も下がる悪循環が生まれるといいます。本当にそのとおりで、関係の質が十分でないことで、うまくいっていなかった部分が大きかったと思います。そこで私たちは、職場改善の第一歩として1on1を導入し、上司・部下の関係の質を高めることにしました。
検討プロセス・実行施策
コミュニケーションで改善できるソフト面の課題なのか、人事・経営として取り組むべきハード面の課題なのかが分かる
森田:2022年、1on1を新たに実施するにあたって、さまざまな支援ツールを検討し、そのなかからインサイズを選びました。
1on1支援ツールにインサイズを選んだ理由はいくつかあります。1つ目の理由は、インサイズが上司・部下の1on1コミュニケーションの改善につながる点です。実際、私たちは上司の皆さんから、「インサイズのデータは助かる」という声を多く耳にしてきました。なぜなら、上司はインサイズのデータを見れば、部下がどのような性格タイプでどういった考えを持っているのか、上司として1on1でどう接したらよいのかが分かるからです。こういったことを現場目線で部下の状況に合わせてしっかり示してくれる点が、インサイズを高く評価したポイントでした。私たちは4社の混合チームで、最近は中途入社者も増えており、上司が人となりをまだよく知らない部下が少なくありません。インサイズのデータは、特にそうした部下と1on1をするときに役立つのです。
2つ目の理由は、ツールの「使いやすさ」や「見やすさ」が抜群に良く、しかも現状に満足せずに改善を続けてくれていることです。とにかく誰でも分かりやすく、扱いやすいのです。
3つ目の理由はサーベイが「記名制」であり、一人ひとりの現状をさまざまな点から明らかにできる点です。上司も人事も「元気がなさそう」と感覚的に見立てることはできますが、データに基づいて可視化されると、答え合わせになりますし認識のギャップに気づく機会にもなります。

川上:例えば、ワークメンタリティ診断の結果がパッとひと目で分かりやすく表示されるのが嬉しいです。可視化されることで直感的に理解できます。しかも、その結果となっている理由を分析したレポートが作成されるので、とても参考になります。
窮々・悶々※の理由のなかには、人間関係や職務上の不満など上司が介入できる問題と、待遇面の不満など上司だけでは対応が難しい問題があります。これらの問題解決のアプローチはケースバイケースです。前者の人間関係や職務上の不満については、基本的には上司に部下のフォローを行ってもらいますが、場合によっては人事が介入することもあります。ときには社長や上層部を巻き込むことも考えなくてはなりません。後者の不満に関しては、組織全体で取り組む必要があります。
インサイズの情報をもとに課題を洗い出すと共に、それがコミュニケーションで改善できるソフト面の課題なのか、人事・経営として取り組むべきハード面の課題なのかを選別し、より的確に対応できるようになったのもプラスです。
森田:実施頻度を自由に設定できる点もありがたいです。年1回のエンゲージメントサーベイよりも高頻度に実施でき、取り組んだ施策が響いているかどうかを確認できるので、PDCAを回すのに非常に役立ちます。私たちは、2024年からは目標管理面談に合わせて、インサイズを年3回実施しています。年1回のエンゲージメントサーベイと年3回のインサイズで、そのつど組織課題を把握し、課題解決を重ねてきました。
会社への理解を深め、愛着を育むための新たな取り組み
森田:私たちは1on1とインサイズ以外にも、組織改善の取り組みを行っています。2023年から川上が中心となって、経営メッセージやグループでのトピックスなどを社内に広めるために「WEB社内報」を創刊しました。2024年には、若手社員や中途社員を対象に、業界に関する基礎知識向上を目的とした「グループ基礎研修」も導入しました。社員の皆さんの自己成長や、自分たちが働く会社への理解度を高めて愛着を持ってもらうきっかけになればいいと考え、実施した施策です。それ以外にも、福利厚生制度などの刷新にも力を入れてきました。

川上:2023年に本社オフィスが拡張され、拠点としての存在感が増したことも社内に良い影響を及ぼしていると思います。それまでは、本社でありながらヤマハロゴもないため、眺望は良いのですが、「ここが自分達の職場・ベース」だと感じられる環境では全くなく、かりそめの住まいといった感じでした。
そこでオフィス設計にあたっては、機能面だけではなく情緒的側面も意識し、エントランスに存在感のあるヤマハロゴのオブジェを設置しました。それ以外にも社内報のロゴを壁にあしらったり、壁一面の大きな世界地図に海外拠点をプロットしたりと、社員が「ここが自分たちのベース」だと感じられるオフィスにすることを重視しました。
オフィスが拡張されたことで、2024年度には会社の創立を祝う「Yamaha Day」のイベントとしてオープンハウスを初開催しました。社員が本社オフィスに家族を連れてきてもよい1日です。元々ヤマハ発動機グループではない会社が集まった成り立ちから、社員の多くはこれまでヤマハブランドと触れ合う機会があまりありませんでした。そこで初開催のオープンハウスでは、ヤマハ発動機の部活動を前身とするサッカーチーム「ジュビロ磐田」やラグビーチーム「静岡ブルーレヴズ」に協力を仰ぎ、過去の試合映像や歴代ユニフォーム、実際にプロの公式戦で使用されるボールを展示したり、その他にもヤマハ発動機の電動バイクを展示したりしました。ヤマハグッズを景品としたビンゴ大会では子供たちの楽しそうな姿がとても印象に残っています。社員だけではなく、大切なご家族の皆さんと一緒に楽しむことができる大変貴重で有意義なイベントでした。こうした取り組みも、会社への愛着を高めるうえで一役買っているのではないかなと思っています。
成果・今後の取り組み
エンゲージメントスコアと改善度のランキングでヤマハ発動機グループ国内1位に

森田:インサイズや1on1だけの影響ではありませんが、ヤマハロボティクスホールディングスのエンゲージメントサーベイは、2022年度の59ポイントから、2023年度の63ポイント、2024年度の74ポイントと年々上昇してきました。
2024年度には、エンゲージメントスコアと改善度の2軸で計測したランキングにおいて、ヤマハ発動機グループで国内トップレベルになりました。特に「心理的安全性(87ポイント・前年比14ポイントアップ)」「コミュニケーション(71ポイント・前年比10ポイントアップ)」「会社戦略との結びつき(72ポイント・前年比12ポイントアップ)」の3項目が、2023年度から大きく改善しました。もちろん、上司・部下の関係の質も順調に高まっています。

川上:さらに「会社に誇りを持てる」という項目も高まりました。基礎研修や社内報によって経営メッセージが浸透し、経営ゴールに対する納得感が増している結果かもしれません。「長く働きたいと思える会社」になってきたことは間違いありません。
それから、継続的な1on1によってコミュニケーションの土壌が整った結果、現場からも組織改善のアイディアが出てくるようになりました。例えば、現場発で「クロス1on1」のアイディアが生まれ、実際に現場で行われています。グローバル社員が自ら提案した「英会話カフェ」も定期的に開催されています。
上司と部下の関係の質は、思考の質・行動の質・結果の質を左右する
森田:今年7月に発足したヤマハロボティクス全社にも、インサイズを活用したいと考えています。ただ、人事が現場に押しつけてしまうと、「やらされ感」が出てしまいます。それでは意味がありません。私たちの取り組みを社内に共有し、興味を持ってくれた部署から導入していく予定です。現場の気持ちは大事にしたいですから、まずは「やってみたい」と思ってもらえるように働きかけたいです。
川上:世の中には、「ツール(インサイズ)など使わなくても、部下の状態は分かっている」という自信を持つ上司も多いと思います。そうした上司の皆さんには、一度インサイズを使って、答え合わせをしてみてほしいです。仮に、部下全員が予想通りの結果だったとしても、部下のメンタリティや性格タイプを自分以外の目でチェックすることには意味があります。それに、インサイズのデータを蓄積することにも価値があるはずです。もちろん、1人でも想定外に窮々・悶々の部下がいれば、インサイズを導入した意味があるでしょう。

森田:「上司と部下の関係の質が、本当にそこまで重要なのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、私の経験上、関係の質を高めることには大きな効果があります。なぜなら、関係の質が悪いまま、部下にタスクを与えると「やらされ感」が芽生えてしまい、責任感やエンゲージメントが高まらないからです。
また、会社の目指すゴールや会社からの期待などを理解できず、将来のビジョンも描きにくいからです。関係の質は、本当に思考の質・行動の質・結果の質を左右するのです。
エンゲージメントを高めるためには、まず上司と部下が腹を割って話せる関係になることが欠かせません。インサイズはその信頼関係を築く際に有効なツールです。
※「窮々・悶々」:インサイズで可視化される5段階のワークメンタリティの呼称。「窮々」とは、余裕を持てず、自分を見失ってしまっている状態を表す。「悶々」とは、不安や不満を外に出せず、自分の内に抱え込んでしまっている状態を表す。
取材日:2025/04/08
企業紹介

ヤマハロボティクス株式会社(旧:ヤマハロボティクスホールディングス株式会社)
ヤマハ発動機株式会社を親会社とし、ヤマハロボティクスホールディングス株式会社、株式会社新川、アピックヤマダ株式会社、株式会社PFAの4社合併によって、2025年7月に誕生した。表面実装機・産業用ロボットのヤマハ発動機、ボンダの新川、モールドのアピックヤマダ、各種自動機のPFAの各社技術を統合し、“半導体後工程におけるTurn-Keyプロバイダー”として、お客様の期待を超えるトータルソリューションの提供を目指している。「ロボティクスで感動を手のひらに」をミッションに、最高のロボティクス技術を結集し、お客様が描いた未来を、より早く、より自由な方法で実現するための製品・サービスを提供する。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
関連するサービス
◆ サーベイを活用したマネジメント支援ツール「インサイズ」
関連する
無料セミナー
Online seminar
関連する無料動画セミナー
Movie seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)






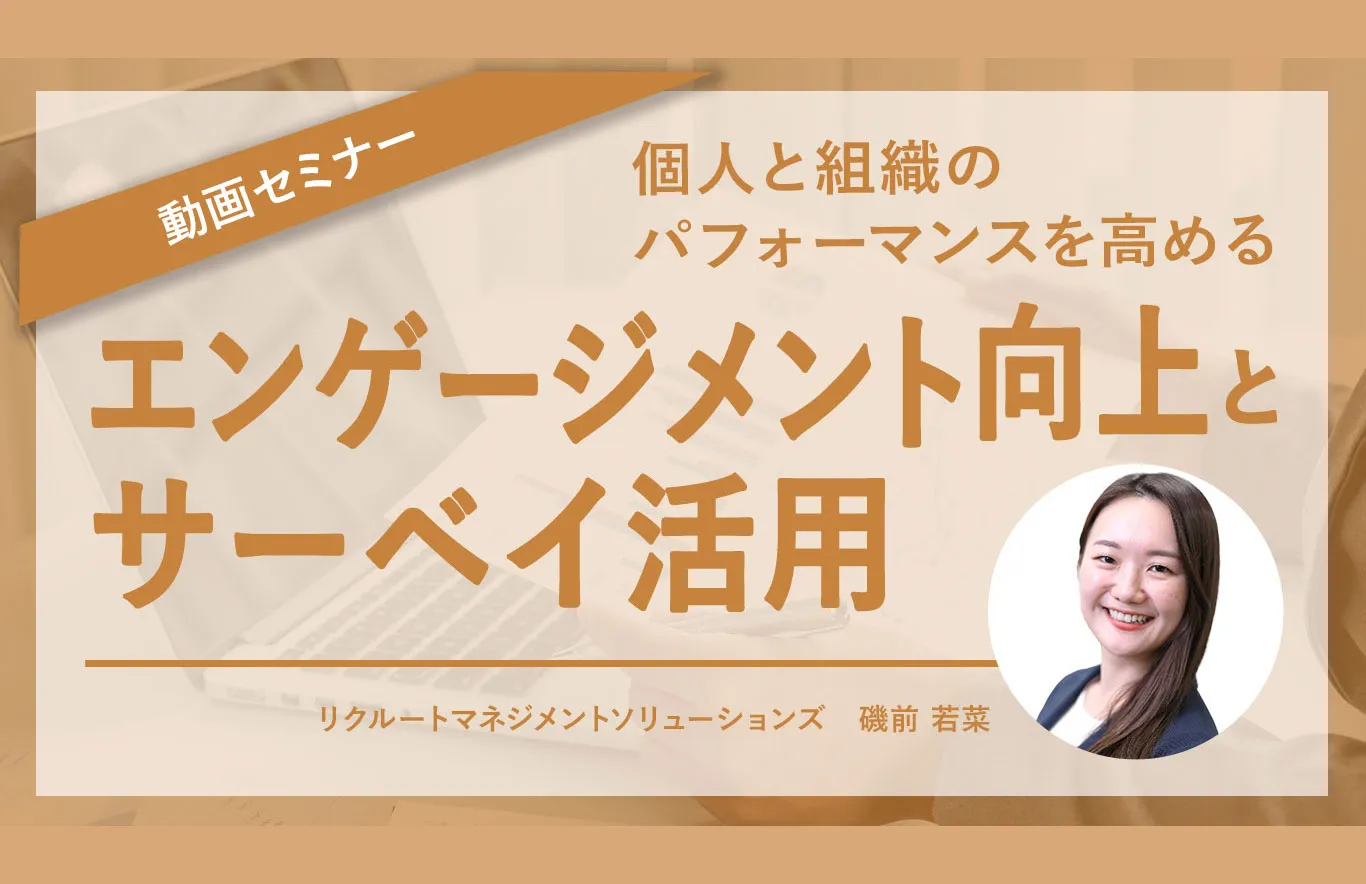
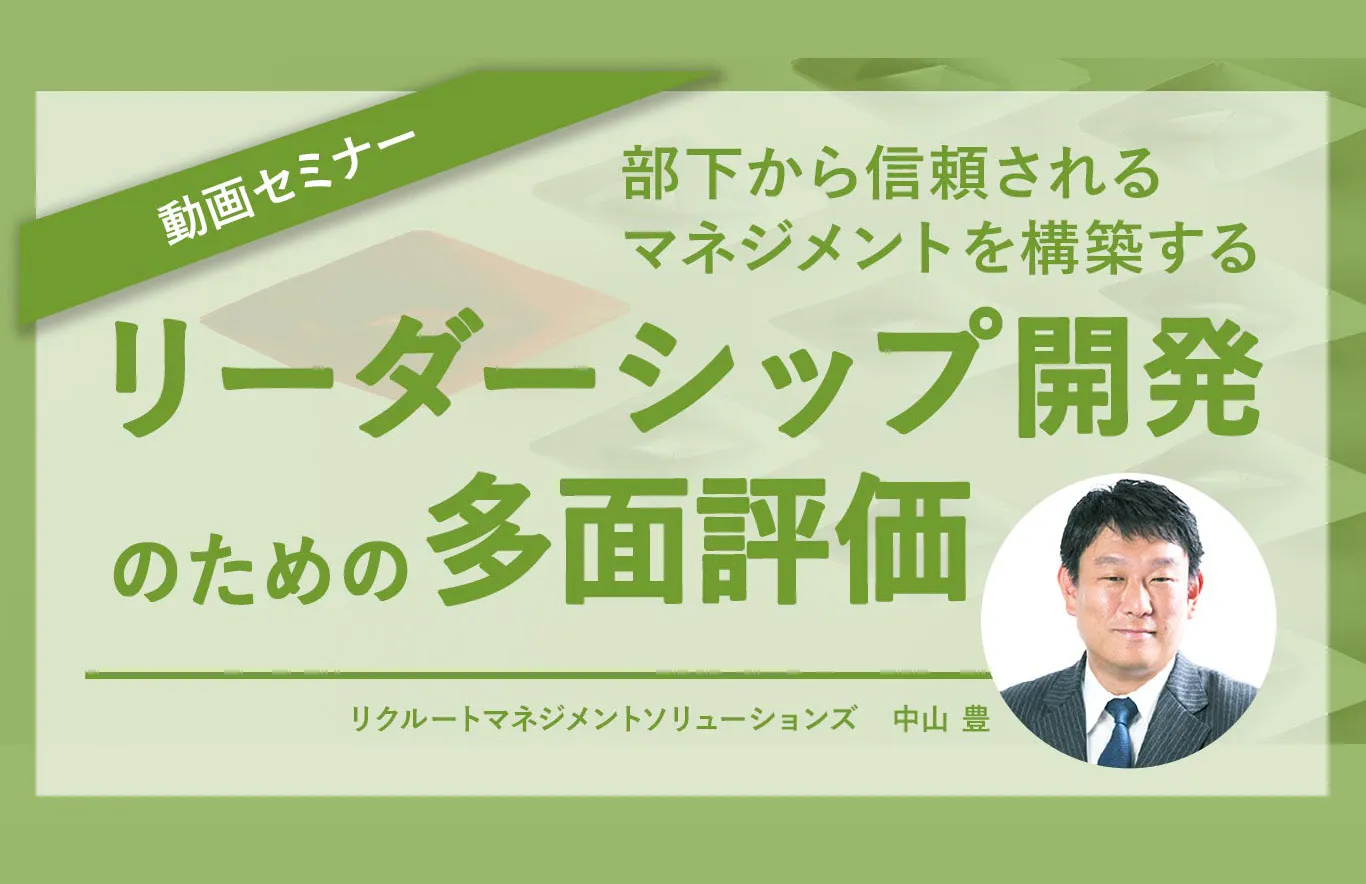









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で