導入事例
新入社員を入社6年で自立したリーダーに育てる
株式会社日立製作所

- 公開日:2013/01/16
- 更新日:2024/11/18
事例概要
背景・課題
小規模プロジェクトの増加に対応するために新人・若手育成プログラムを見直し、できるだけ多くの自立した人材を早期育成する必要がありました。
検討プロセス・実行施策
6年間で自立した人材を育てる唯一無二の育成プログラムをつくり、事務局の日常的な関わりや、研修前後のフォローなど、研修だけで終わらせない工夫も行いました。
成果・今後の取り組み
6年目で小規模のプロジェクトを任せられるような人材が育ってきました。研修は回を重ねるにつれ、職場のリレーションも太くなり、上司の関わりも大きくなっています。
背景・課題
プロジェクトを任せられる「自立した若手」を育てたい

私たち金融システム事業部を含む、当社金融システム部門は、主に大手銀行や保険・証券・取引所で利用される金融システムソリューションを提供しているSE・営業・開発・スタッフから構成される部門です。
時代の最新技術を駆使し、信頼性の高いシステムで経済の大動脈を支えてきたという自負があります。かつては、金融系の大手顧客にホストコンピューターを導入・運用するという、数百人単位の大規模プロジェクトがメイン。社員は同じ顧客を何年も担当し続けるというのが基本的な開発スタイルでした。
ところが1990年代後半になると、金融業界、とりわけ都銀の統合・再編がはじまりました。そして、端末やネットワークが進化した2000年代には、システムの小型化・分散化が進み、大規模プロジェクトから小規模・短期間のプロジェクトへと、顧客から求められる業務そのものが大きく変わりました。
例えばプロジェクトマネジャーでいえば、かつては大規模プロジェクトのスーパープロジェクトマネジャーが数人いればよかったのが、今では小規模プロジェクトのプロジェクトマネジャーが多数必要になったのです。しかしながら、これまでのやり方を変えることは簡単ではありませんでした。
しかも、2000年以降のプロジェクト数の増加にともない、新卒採用人数も増加していったため、新人の指導役も不足していました。その上、大規模プロジェクトの場合、新人は現場で先輩から指導を受けることができましたが、小規模プロジェクトでは一人ひとりに高いスキルが求められるため、現場でのんびり学ばせる時間の余裕もありません。
また、会社として技術や知識などを学ぶ研修は豊富でしたが、仕事に取り組む姿勢や困難への向き合い方、人との関わり方などのヒューマンスキルの部分は、基本的に職場でのOJTに委ねていました。よって、早くから現場に入り自ら動ける「自立した人材」を生み出すために、金融システム部門全体として、社員が仕事に取り組む「姿勢・スタンス」を身につけさせる機会を新たに設ける必要があったのです。
ソリューションプランナーの声
知識や技術ではなく人にフォーカスし、マネジメントの土台作りを行う
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 担当ソリューションプランナー
金融システム事業部を取り巻く環境や事業課題、人材育成などについて徹底的にヒアリングを行い、事業推進本部長をはじめとするみなさまと何度も何度も議論を重ねました。その中で見えてきたのは、プロジェクトの小規模化への対応において、「相手のニーズを汲み取りきれない」「あと一歩深く踏み込めない」など、技術・知識以外の課題が見えてきました。そのため、まずはビジネスパーソンとしての基礎・土台作りを目指し、仕事に取り組む「姿勢・スタンス」に重きを置くこととなったのです。
このように、私たちは集めた情報をもとに、科学的に、実証的に、育成プロセスを明らかにし、課題解決につながるフレームをご提供しています。そして、事業課題にお客様とともに取り組み、事業推進の一助となるだけでなく、効果を定着させていくことが我々の使命です。
検討プロセス・実行施策
人材育成のコンセプトを明確化し、パートナーとしっかり合意する

効果的な教育施策を実施するためには、まず我々の置かれた状況を関わる人たちに知ってもらう必要があります。
そのため、私たちはまず研修のパートナーであるリクルートに対して、我々金融システム部門全体の目標や想い、当時のビジネス環境などについて徹底的な理解をお願いし、同じ視点で課題に向き合ってもらえるように働きかけました。
月に何度もトレーナーと打ち合わせの機会を設けていましたし、ソリューションプランナーとはそれこそ毎週のようにすり合わせを行いましたね。
それともう一つ、私たちが重要だと考えていたのが、社員に「金融システム部門に来て良かった」と思ってもらえるような、特別な研修にすること。不特定多数に応用できるような研修ではなく、金融システム部門に特化した唯一無二の育成体系にしたかったのです。
そうしたテーマのもとに話し合いを重ねて生まれたのが、「自分を取り巻くステークホルダーが有言・無言で示す期待や、求められる成果を認識し、自分が貢献すべき領域(役割)を自ら設定、何をすべきかを自分で考えて実行できる人」という人材育成コンセプトです。
また一例として、6年間で「10名規模のメンバーを率いるプロジェクトマネジャーを育てる」という、より現場に落とし込んだ目標も生まれました。
いい意味で口うるさく面倒見がいい、選りすぐりの社員に企画・運営を任せる
一般的に、たとえ小規模であっても、6年間でプロジェクトマネジャーを任せられるような自立した人材を育てるのは、かなり急ピッチと言えます。2004年から研修を実施してきた中で、その実現には質の高い研修を提供するだけでなく、運営事務局と受講者との日常的な関わりが重要であることが見えてきました。
そのため2010年度から、施策の効果をより高めるために、金融システム部門での経験が豊富で、なおかつ面倒見のいい社員を研修の企画・運営スタッフに任命しました。いい意味で口うるさく、時には新人・若手を叱り、時には勇気づけることができるような、頼もしいメンバーです。
育成プログラムは、入社1年目から6年目までの社員が対象となります。1~2年目は仕事の基本と、困難を乗り越えるヒントを習得することで自立する準備を行い、3~4年目は周囲の期待を知り、自分の貢献領域を決め、5~6年目にはリーダーシップを点検し、周囲にそれを発揮していくというステップで研修を実施しています。
事前課題や事後課題の提出、上司との面談による実践支援など、研修の前後も事務局が細かくフォロー。また、研修初日の朝一番と研修の最後に、企画・運営スタッフから研修の意義やそこにかける想い、若手への期待など、受講者へメッセージを送ることで、研修そのものと、その後の動機づけにも努めました。
さらには、研修の興奮が冷めてしまう、研修後1.5カ月時点でアンケートをとり、内容のリマインドをかけて定着度合いを確かめるなど、研修を実施する過程で生まれた工夫もあります。
トレーナーの声
年々たくましくなる受講者の成長を見るのが、何よりの楽しみです
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 担当トレーナー
この一連の施策は、2004年からのトップの強い意志と、事務局の受講者一人ひとりの成長を見守る熱い思いの賜物です。お客様の熱意を意気に感じて、受講者の特性・個性を鑑み「こんなところでつまづくであろう」ことを予測し、トレーナーとして効果的なアドバイスができるよう研修に臨んでおります。
毎年の受講者の成長ぶりが、手に取るようにわかることも楽しみの一つです。営業部門に所属するある受講者は、1年目の研修では、グループ討議でなかなか発言できず、「不器用で営業には向かないのでは・・・」と心配しましたが、職場と研修で磨かれて、3年目、4年目になるにつれて、徐々にたくましくなり、研修でも堂々と発言をし、仕事も前向きに取り組むようになったようです。
6年目研修となると、選抜ということもあり他社の管理者を上回る人材となってる受講者もいるくらいで、成長スピードの速さに本当に驚かされます。新人だった受講者が諸先輩の励ましと研修での気づきを得て、困難を乗り越え、年々たくましくなる姿を見届けられるのは、トレーナー冥利につきます。
成果・今後の取り組み
「同じ研修は一つとしてない」 それがリクルートとの共通認識

2004年に育成プログラムをスタートして8年。当初の目標通り、6年間でプロジェクトマネジャーを任せられるような自立した社員は増えてきました。一方で、2009年ごろから見えてきた新しい課題も。
新入社員の特性や、ビジネス環境が変わってきたのです。
これまでも「同じ研修は一つとしてない」というリクルートとの共通認識のもと、研修内容は随時見直してきましたが、新人の変化を踏まえ、2011年からは社員の“自立”にフォーカスし、内容を大きく変えました。
一例をあげると、研修は先ほど申し上げた大きく3つのステップに分かれていますが、特に新入社員研修において、最初の2年の「自立する準備」という目標を達成するまでの道のりを、やや丁寧にしました。
ただし、厳しさを弱めたわけではありません。内容を現在の金融システム部門のビジネスシーンに合うものに進化させ、研修を受け終えた後にそれぞれの社員が、厳しさの中にも達成感を得ることができたり、何かしらの課題を持ち帰ることができるようにしたかったのです。
もちろん、研修の改善にゴールはないので、これからも実施するたびに新しい課題を見つけて、それを改善していくことになります。
研修は先輩・後輩の「共通体験」 今や金融システム部門の伝統に
この自立した人材を育成する「金融ビジネスコンピテンシー研修」は、今や当社金融システム部門に欠かせないものになっています。当社には職種を問わず入社2年目の終わりに、事業部長の前で発表する研修員論文という制度があります。
発表の直前にはその上司も泊まり込みで指導するほどの一大イベントなのですが、金融ビジネスコンピテンシー研修もそれに匹敵する重要な行事だと社員は捉えているようです。
その証拠に、以前は研修のために職場を離れることを良く思わない上司・先輩もいましたが、今では「行ってこい」と快く送り出してくれるようになりました。また、多くの社員がその厳しさに面食らう新人導入研修が、先輩・後輩の共通体験として話のネタになるということもあるようです。
金融ビジネスコンピテンシー研修はこれからも続くわけですから、これを体験する社員の割合も当然ながら増えていきます。これにより、研修と職場のリレーションもより太くなりますし、上司の関わりも大きくなるでしょう。
受講者が職場に戻ってから上司や先輩のフォローがあれば、その成果もさらに色濃いものになるはずです。これらは最初から意図していたことではありませんが、今では金融ビジネスコンピテンシー研修は、金融システム部門全体の数年後に前向きな変化を起こすことを期待される取り組みとなっています。
関連記事
【事例】 「職場ぐるみで新人を育てるOJTを目指して」株式会社荏原製作所
【特集】 「ゆとり世代の新入社員は何を求めているのか?」2012年新入社員意識調査
【コラム】 「新人若手育成のアタリマエを変えよう」
受講者の声

研修を受けるたびに悩みを解決するヒントを発見
株式会社日立製作所 金融システム事業部 事業推進本部 システム統括部 河地 崇之 様
私は入社して6年目で、ちょうど金融ビジネスコンピテンシー研修をすべて受講し終えたところです。入社時から受けてきた研修をふり返って思うのは、研修を受けるたびに自分が抱えている悩みを解決するためのヒントが見つかったということです。たとえば、入社3年目に設計担当からSEに変わったとき。
当時の私は、設計の知識には自信があるのに、SEとしては新人という立場にギャップを抱いており、チーム内でどのような立ち居振る舞いをすべきか悩んでいました。そんなとき、周囲の期待と自分の役割をすり合わせる中堅社員研修を通じて、上司や同僚から自分が何を求められているのかを理解し、それを行動指針とすることができたのです。
さらに、直近のリーダーシップ開発研修では、受講者同士がお互いの行動をフィードバックし合うことで、リーダーとして成長するためのヒントを見つけることもできました。どの研修も頭の中で理解するだけでなく、「明日からこうしよう」と具体的な行動に落とし込める実践的な内容だったので、ありがたかったですね。
取材日:2013/01/16
企業紹介
株式会社日立製作所
関連するサービス
Service
関連する
無料セミナー
Online seminar
関連する無料動画セミナー
Movie seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)





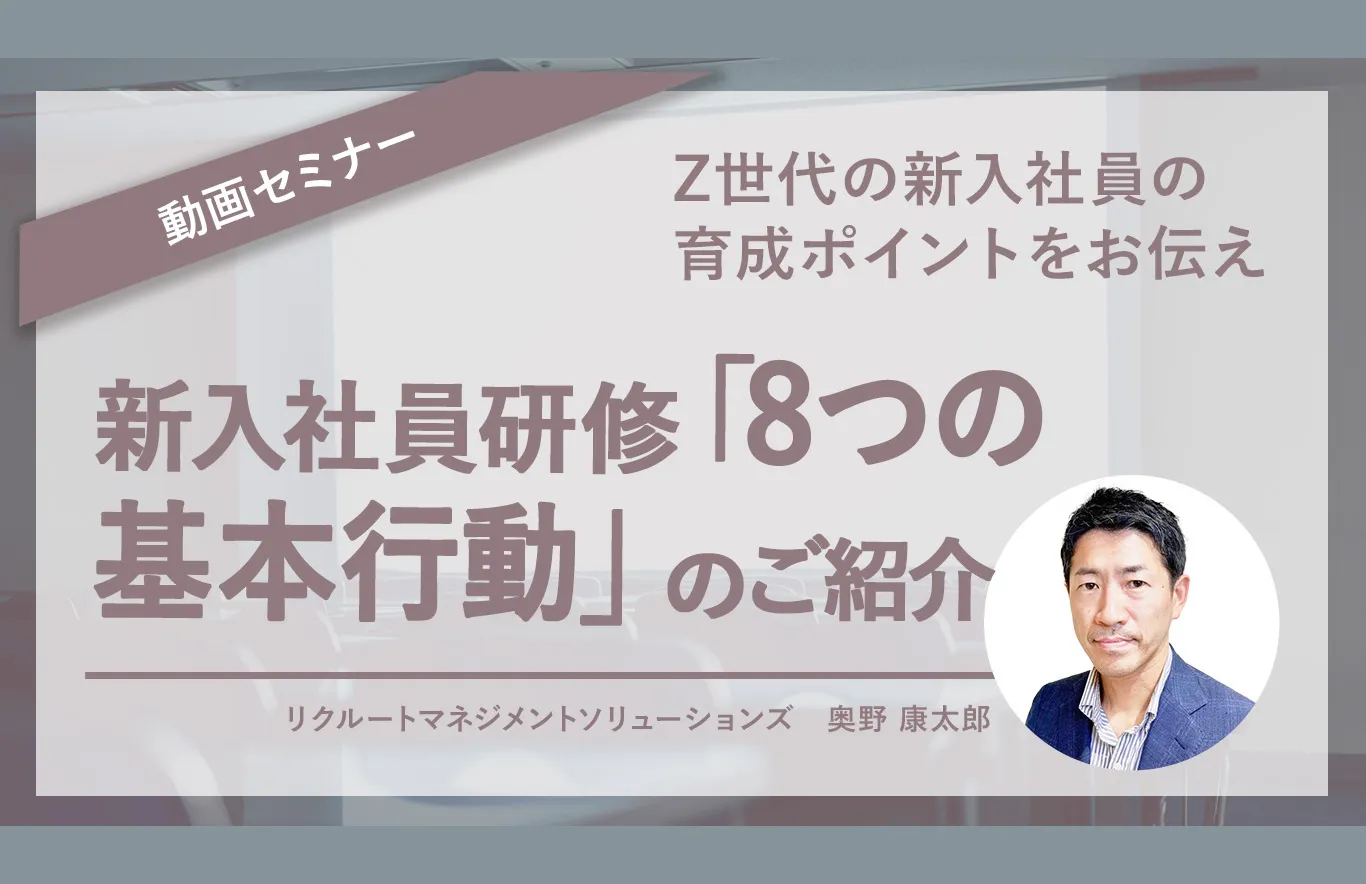
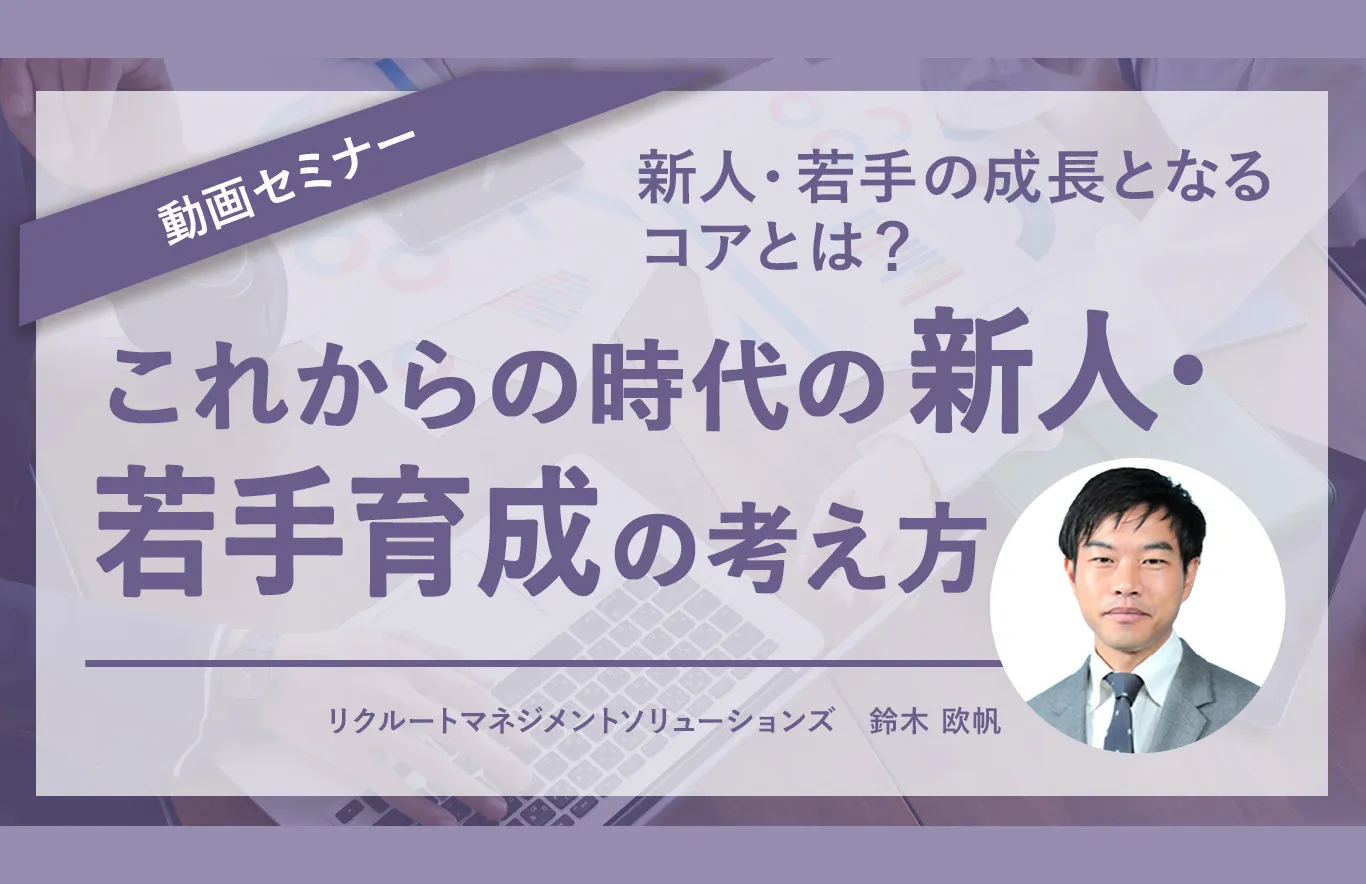
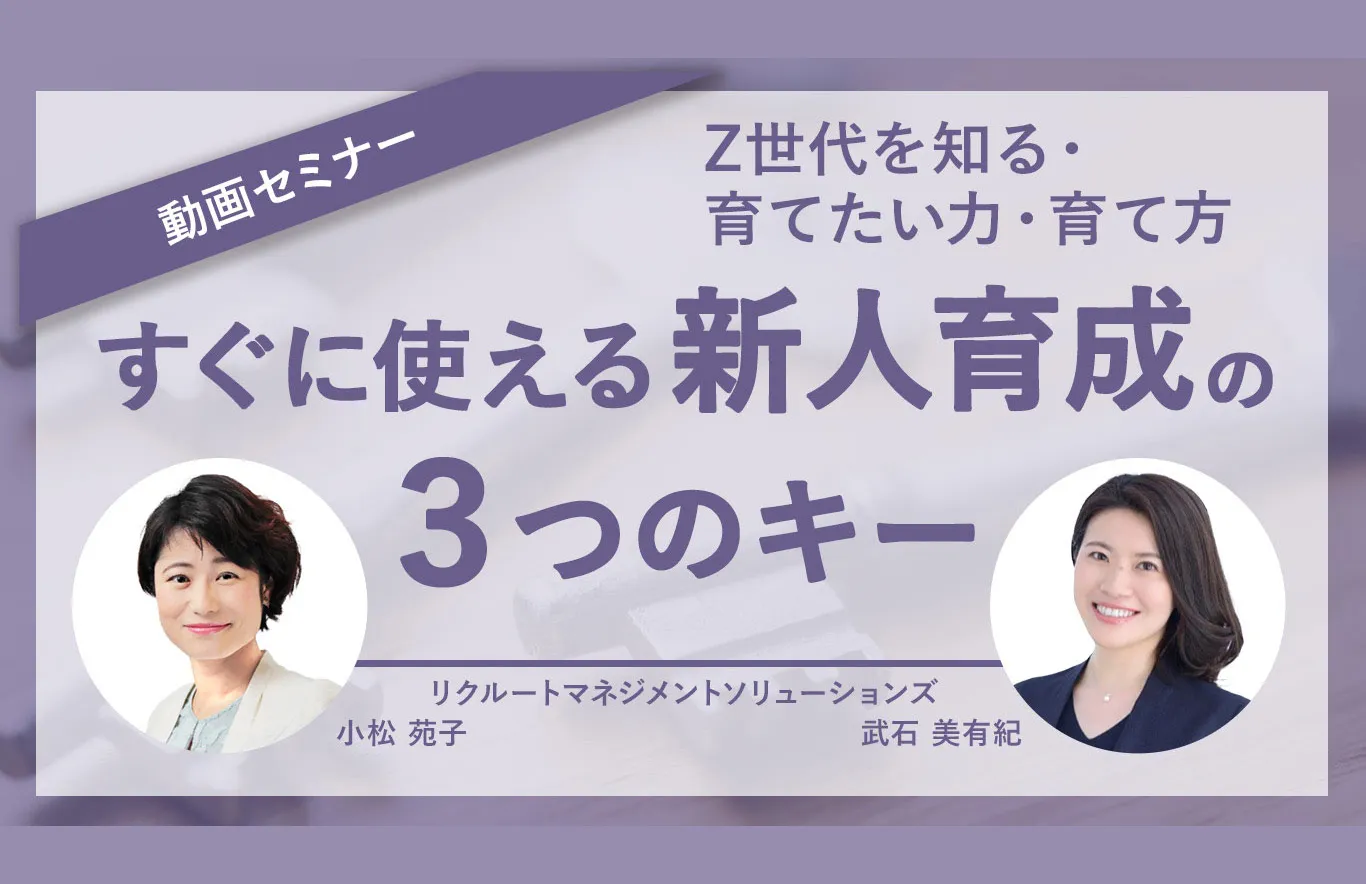









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての