インタビュー
オンライン緊急座談会 アフターコロナの「働く」とは何か?
ステイホームで増えた「働き方の選択肢」を、私たちは生かしていけるだろうか
- 公開日:2020/07/27
- 更新日:2024/03/22

新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言によって、一時的にせよ、私たちの働き方は大きく変わった。そのことが、「働く」について何を問い直し、何を浮き彫りにしたのか。新型コロナウイルス感染症対策の先にある「働く」の未来とは何か。「新型コロナウイルス感染症の流行への対応が、就労者の心理・行動に与える影響」について共同調査を行った江夏幾多郎氏、高尾義明氏、リクルートワークス研究所所長の奥本英宏氏と、弊社組織行動研究所所長の古野庸一で、2020年5月22日にオンライン緊急座談会を行った。その内容を紹介する。
座談会登壇者
江夏幾多郎氏(神戸大学 経済経営研究所 准教授)
高尾義明氏(東京都立大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 教授)
奥本英宏氏(リクルートワークス研究所 所長)
古野庸一(リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 所長)
当たり前が当たり前でなくなった世界
古野:正直にいって、この数カ月、幻想の世界にいるような感じがしています。目に見えないウイルスによって、現代社会がこれほど翻弄されるとは思ってもみませんでした。数世紀前と同じように都市封鎖をしなければならないなどとは想像もしませんでした。その一方で、中国や韓国はスマートフォンの位置情報を利用した感染追跡システムを導入しており、先進性には感心しますが、行動監視社会に恐怖を感じる部分もあります。
新型コロナ禍の数カ月を経て、今どのようなことを考えていますか?江夏:当たり前だと思っていたことの多くが当たり前ではなかったのだ、と気づく日々でした。例えば、これまで街を歩くときにはぶつからないようにすれば十分でしたが、今は常に1~2メートルの距離を意識しながら歩かなくてはなりません。これはある意味で新しく興味深い現象ですが、生活する上ではけっこうなストレスです。
また、オンライン会議システムは、神戸にいても東京など遠くにいる皆さんと簡単にコミュニケーションできて便利ですが、2時間も話すとぐったり疲れます。オンライン会議には大きな可能性を感じますが、私はまだ対応しきれていません。こうやってさまざまな場面でストレスを感じつつ、変化に適応しようとしてきた数カ月でした。
奥本:最近よく考えているのは、アフターコロナの「ニューノーマルとは何か?」ということです。江夏先生のおっしゃるとおり、今私たちは2メートルのソーシャルディスタンスを意識しながら生活しています。他方、こうしたオンライン会議では、画面越しに30センチくらいの至近距離で話し合っています。
これは、人が生来もっている個体距離(※)からすると、2メートルはずいぶん遠いし、画面越しの30センチは近い。私たちは、いつもより遠いことにも近いことにも強い違和感を覚えながら暮らしているわけです。何でも「できたからいいじゃん」というわけではなく、この違和感を大事にしながら、あらためて日常に混ぜ直した「ニューノーマル」が必要ではないかと感じています。
※個体距離……相手の表情が読み取れる空間、親しい人と会話する距離感
高尾:今回の共同調査で分かったことの1つは、「新型コロナ対応が従来あった格差を再生産している」ということです(※)。例えば、リモートワークを行える方々は、新型コロナ対応から受ける影響が比較的小さいのですが、リモートワークを行えない方々は少なからぬ影響を受けています。今後、こうした格差がさらに広がる恐れがある。ニューノーマルを考える際には、こうした格差も踏まえなくてはならないと思います。
※関連する主張は、共同調査第2報の方で、より積極的に行っている
第1報「新型コロナウイルス感染症の流行への対応が、就労者の心理・行動に与える影響 」
第2報「新型コロナウイルス流行下で就労者や企業が経験する変化-デモグラフィック要因の影響-」
江夏:私は、ニューノーマルをはっきりと定義すべきではないのではないか、と感じています。別の言い方をすると、「ノーマルの自明性がないことがニューノーマルではないか」と思っているのです。
社会学者ニクラス・ルーマンの説明を借りると、世界はあまりにも複雑であり、私たちは何らかのルールや認知上のショートカットによってその複雑性を縮減しなければ生きていけません。社会は、経済・法・芸術・科学・政治・マスメディアなどの分化システムを使って、その複雑性を縮減するシステムです。平たくいうと、そうしたシステムに乗っかってこそ「分かったつもり=ノーマル」で生きていけるわけで、そしてそうした生き方自体はこれからも変わらないわけですが、既存の方法の耐用年数がますます短くなり、「分かったつもり=ノーマル」であるための方法を常に再構築しないといけません。しかも、再構築のための間違いない観点を政府や有識者が出してくれるわけではなく、とはいえインターネット空間の情報は膨大で、往々にして矛盾しています。誰かのノーマルに頼れない、自分のノーマルを否定しながら、しかし何かしら再構築しないといけない、という不安定な状況こそがニューノーマルではないでしょうか。
奥本:この数カ月、さまざまな場所で「まずやってみよう」という行動が増えてきたように見えます。例えば、リモートワークがよいかどうかを分析したり考えたりしている場合ではないから、とりあえず始めてみて、そこで起きた問題に対応していったらリモートワークが割とうまくいった、という形のチャレンジがいろいろな領域で見られました。ニューノーマルは、モデルを固定的に定めにいくのではなく、このようなチャレンジをさらに積み重ねていく上に現れてくるものではないかと思っています。

私たちはリモートワークという新しい幸せな働き方を知ってしまった
古野:リモートワークに関してはどのように捉えていますか?高尾:まず当然のことですが、リモートワークが実施可能な事業・職種とそうでない事業・職種の差があります。それとは別に、大企業と中小企業の差も見られます。2月時点では企業規模とリモートワークの利用率には明確な関連がありませんでしたが、4月には大企業のリモートワーク利用率が急速に高まりました。おそらく多くの大企業は、以前からリモートワークに必要な設備や体制を整えていたのでしょう。そして、緊急事態宣言発令で一斉に実施し始めたのだと考えられます。
また、役職なしの方々は、もともと役職者よりもリモートワーク利用率が低かったのですが、新型コロナ対応以降、その差がますます広がっています。組織の末端にいるほど、リモートワークしにくい実態があります。
奥本:正規・非正規の間にもリモートワーク利用率の差があります。派遣会社にヒアリングしたところ、やはり派遣社員の利用率は正社員よりも低いのです。ただ、今回のコロナ危機をきっかけに、導入に後ろ向きだった派遣社員のリモートワークが大幅に増えたことは大きな成果でした。新しい派遣就業のスタイルが生まれる可能性を秘めています。
古野:一方、私たちの調査(※)では、リモートワークしている方々の生活満足度は高まっています。先生方の共同調査でも、就労者の幸福感は決して低くありませんでした(「どちらかといえば幸福」41.11%、「非常に幸福」7.22%)。他のさまざまな調査を見ても、特に通勤がなくなったことで生活満足度が高まっているのは明らかだと思います。
※「一般社員2040名、管理職618名に聞く テレワーク緊急実態調査」
【前編】温かく明快なコミュニケーションで、誰も孤立させないテレワークを
【後編】テレワークがあぶりだすマネジャー依存の限界と、自律・協働志向組織への転換
江夏:つまり、多くの就労者は「リモートワークという新しい幸せな働き方」を知ってしまったということですね。職場に行く必要がないのに満員電車に乗るなど、やっていられないと感じているビジネスパーソンは多いでしょう。リモートワークによって生産性が落ちたり就労時間が長くなったりするという報告もありますが、それはリモートワークの使い方の問題であって、リモートワークそのものの問題ではないことが、我々の調査(特に第1報)でも示されています。今後、企業がそれをどう捉えるかが問われていると思います。以前と同じように全員を通勤させる「オールドノーマル」に戻るのは難しいのではないかと思うのですが、皆さんはどう思いますか?奥本:そのとおりだと思います。私自身が組織長として特に今考えているのは、オンライン会議と対面会議の使い分けです。オンライン会議のどこに限界があり、どのようなときは対面会議の方がよいのか。そのポイントと理由を明確にして、メンバーと認識を共有する必要があります。例えば、感情と思考を同時に動かしたり、思考の発散を促すような会議、ビジョンを考えたり、ブレストしたりする会議は対面の方が向いています。今後はそのことをメンバーにも理解してもらい、オンライン会議と対面会議を上手に振り分けなくてはならないと感じています。
一方で、2019年にリクルートワークス研究所で「働く人のリレーション調査」を行って分かったのは、職場の心理的安全性が崩れると、リレーションが提供する価値のうち、「成長」と「展望」はあまり変わらないのですが、「安心」と「喜び」が極端に減ることです。つまり、リモートワークが増えることで心理的安全性が崩れるなら、働く上での「安心」や「喜び」が減ることになります。「安心」や「喜び」の経営的価値をはっきり説明できないと、会社が従業員に出社する合理性を説得できなくなる日が来るかもしれません。
古野:リモートワークが心地よいタイプと、1人で働くのが寂しいと感じるタイプの両方がいることにも配慮する必要がありそうです。というのは、私たちの調査で分かったこととして、リモートワークが増えてから、多くのマネジャーが画面越しに何とかして部下とコミュニケーションを取ろうと頑張っているのですが、それを喜ぶ部下もいれば、うっとうしいと感じている部下もいるのです。リアルでは、部下がどう感じているのか分かりやすいですが、リモートワーク下では、部下の状況が分かりづらく、マネジメントは明らかに難しくなっています。
江夏:リモートワークに温かさがないわけではありません。今回の共同調査でも、オンラインで集まって志を共にする関係性から活力をいただきました。オンライン会議で、むしろ相手のプライベートが良い意味で感じられるケースもあります。リモートワーク下での上手なチームマネジメント、心理的安全性を高められるマネジメント手法もあり得るのではないでしょうか。
奥本:危機下ではリモートワークが目的になっていますが、新型コロナが収束したら、いずれにしてもリモートワークをあらためて手段の1つと位置づけ、どう活用するかを考える必要があるのだと思います。
江夏:つまり、「リモートか通勤か」ではなくて、「リモートも通勤も」になればいい。リモートワークが選択肢の1つになればよいのですね。


揺らぎの先に、つくりたい未来
高尾:そこで私が気になるのは、社員育成です。特に若手社員を育成する際には、彼・彼女らが「コミュニティ・オブ・プラクティス(実践のコミュニティ・COP〈※〉)」に入るプロセスが欠かせないと思うのです。COPを培いやすいのは、やはりリアルな職場ではないでしょうか。
※実践のコミュニティ(COP:Communities Of Practice)
実践共同体ともいう。ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーが示した用語で、コミュニティ(例えば会社)への参加は、そのコミュニティが共有している社会的実践において、さまざまな役割を担い行為することを通じて、文脈に埋め込まれた知識やスキルを徐々に習得すると同時に、集団の成員としてのアイデンティティを学んでいくプロセスであることを示した。古野:おっしゃるとおりだと思います。知識の獲得とオンラインでの学びは相性がいいけれど、コミュニティ形成はリアルな研修の方がよいと思われます。ただ、今後はオンライン上のCOPの可能性を追求して、リアルとオンラインを上手に使い分けながらコミュニティを形成できるとも感じています。
そのこととも関連するのですが、私は今、テレワークの平等性や民主性がどう影響するのか気になっています。従来の職場では、役職者の席が、それと分かるように配置されていたり、机や椅子が少し大きかったりします。また、会議では、役職順に席が決まっていることも多く、その序列に意味がありました。しかし、テレワークであれば、地位を表す机や椅子はなく、会議だと序列もなく、参加者の画面は皆同じ大きさです。役職者だからといって画面が大きくなったりしません。ゆえに、若手からすれば、発言の機会が多くなる可能性があります。しかし、経営陣や役職者には、ネガティブな印象をもっている方が多いような気がします。リアルな会議であればオーラを発揮できるけど、オンラインでは、どうもうまくいかない。そのことが面白くなくて、オンライン会議をやめることにならないか心配です。
江夏:違う見方をすると、これは役員・部課長の役割や、ジョブの意味をあらためて考える良いきっかけなのかもしれません。リモートワークが普及した結果、部長は別に必要ないのでは、といったことになっていく可能性もおおいにあります。
奥本:私もまったく同じことを感じています。オンライン会議では人間関係が本当にフラットですから、オンライン会議がデフォルトになったら、ポジションパワーよりもパーソナルパワーが重視されるのは明らかです。マネジャーであっても、必要な能力・スキルがなければ会議に呼ばれないケースが増えるでしょう。
もう1つ、オンライン会議が画期的なのは、情報シェアが格段にやりやすくなったことです。私のチームでは従来、月次の情報共有会は研究員だけで行っていました。会議室のキャパシティや時間拘束などを考えると、研究員に絞るのが最も都合が良かったのです。しかし、オンライン会議なら会場のキャパシティは関係ありませんし、あとで録画を見るのも簡単です。そこで現在は、アシスタントやアソシエイトにもオンライン情報共有会を公開しており、彼・彼女たちも喜んで参加しています。こうした情報のフラット化も、組織構造を大きく変える可能性があると思います。
古野:先日、300名規模のあるグローバル企業が、世界中に住んでいる社員全員が参加できるオンラインミーティングを、コロナをきっかけに隔週で開くようになったという話を聞きました。そこでは、役員から新人までの全員が同じ情報を共有し、意見交換するようになったのです。そうした新たな試みには可能性を感じます。
江夏:経営層は社員を動機づける、つまり「刺さる」ビジョンやミッション、経営計画、方針を打ち出して、現場がそれを受けて、試行錯誤しながらビジネスを形にしていく。そして、ある程度の形ができたら、経営陣の承認を取って市場に展開する。リモートワークとオンライン会議によって、むしろそうした柔軟な組織づくりができるようになるのかもしれません。
高尾:この前も古野さんとお話ししましたけれど(※)、日本的な「ミドル・アップダウン・マネジメント」がアップデートした形で実現できるかもしれない、ということですね。
※「自分なりの意志で上や周りを動かせるマネジャーになろう」(高尾氏インタビュー記事)
奥本:ただ一方で、大企業のオンライン会議では、一番偉い人が抜けないと、誰も抜けられないというケースもあるようです。より良いミドル・アップダウン型経営を実現するには、経営陣も従業員も変わらなくてはならないでしょう。
古野:終了時間が迫ってきました。最後に一言お願いします。
高尾:皆さんとお話しして、リモートワークが当たり前になることで、マネジャーの力がますます重要になってきていることを再認識しました。私はビジネススクールの教員でもあるので、リモートワーク時代のマネジメント教育をより真剣に考えなくてはならないと感じています。
江夏:在宅勤務に強い潜在的ニーズがあることは、実はここ10年、15年ほど、ずっと分かっていたことです。企業は、出産・育児・介護やワークライフバランスの文脈でそのニーズに小出しで対応しつつ、大きなニーズへの取り組みは後回しにしてきたのが現実です。つまり今、日本企業は10年、15年分のツケをまとめて払っている、と見ることもできるわけです。そのことを認識しながら、長い目線で新時代の組織構造やコミュニケーション構造を形づくる時期に入ったのだと思います。
奥本:今回の新型コロナ対応で最も重要なのは、やはり「働き方の選択肢が増えた」ことだと思います。大事なのは、ステイホームで増えた選択肢を今後もそのまま残すことです。せっかく増えた選択肢を狭めてはならないと思います。
古野:個人的には、通勤ラッシュを撲滅したいという思いが強くあります。通勤電車の混雑率が半分になれば、仕事もプライベートもより充実するのではないか、と思うのです。

【text:米川青馬】

座談会を終えて
すべての仕事がリモートでできるわけではありませんが、かなりの仕事が在宅でできることが分かってしまったのが、緊急事態宣言下の学びでした。慣れないので、ストレスを感じることもありますが、徐々に適応していくと思われます。
働くにあたって、必ずしも職場に行かなくてもいいということであれば、住む場所の自由度は高まり、家族との関係性は変化していきます。実際、郊外やリゾートに住むことを検討している人はこの数カ月で増えています。
お客様との会話もリモートでできるということであれば、オフィスは都会の一等地である必要はありませんし、必要以上に広くなくてもいいでしょう。オフィスに集まって仕事をする意味、意義、効用について、あらためて議論していく必要がありそうです。
オンラインで会議を行うことが前提であれば、会議体の自由度は高まり、会議の進め方も変化していくと思われます。会社全体のコミュニケーションのあり方を、ゼロベースで考える機会と捉えた方がいいでしょう。
もちろん、実践共同体での学びやちょっとした相談、偶然の出会いなどは、リモートワークでは難しいかもしれません。しかし、リモートでできる仕事と対面で行う方がいい仕事の峻別は、進んでいくでしょう。そのことは、私たちの働き方の選択肢を増やし、より豊かに働けるようになることを意味します。そして、豊かに働くことができる組織が選ばれていくでしょう。
この座談会を通して、そういうことを、あらためて考えました。
皆さんは、いかがでしょうか。
【組織行動研究所 所長 古野庸一】
PROFILE
江夏 幾多郎(えなつ いくたろう)氏
神戸大学 経済経営研究所 准教授
2003年一橋大学商学部卒業。2005年神戸大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。2008年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得満期退学。同年名古屋大学大学院経済学研究科講師。2011年より名古屋大学大学院経済学研究科准教授。2019年9月より現職。著書に『人事評価の「曖昧」と「納得」』(NHK出版新書)、『人事管理』(共著・有斐閣)などがある。
高尾 義明(たかお よしあき)氏
東京都立大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 教授
1991年京都大学教育学部教育社会学科卒業。大手素材メーカーを経て、京都大学大学院経済学研究科修士課程、同博士課程修了。2009年4月より現職。専門は経営組織論・組織行動論。著書に『はじめての経営組織論』(有斐閣)、『組織と自発性』(白桃書房)、『経営理念の浸透』(共著・有斐閣)などがある。
奥本 英宏(おくもと ひでひろ)氏
リクルートワークス研究所 所長
1992年立教大学社会学部卒業。同年株式会社人事測定研究所(現 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)入社。採用・若手育成事業のビジネスユニット長、人材開発・組織開発事業部長を歴任。2011年10月には、株式会社リクルート ソリューションカンパニー カンパニー長、株式会社リクルートマネジメントソリューションズ代表取締役社長に就任。企業の人事制度、人材評価、人材開発、組織開発全般のソリューションに従事。2018年4月よりリクルートワークス研究所に参画、2020年4月より現職。
古野 庸一(ふるの よういち)
リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 所長
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社。南カリフォルニア大学でMBA取得。キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事。2009年より現職。著書に『「働く」ことについての本当に大切なこと』(白桃書房)、『「いい会社」とは何か』(講談社現代新書)、『日本型リーダーの研究』(日経ビジネス人文庫)、訳書に『ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法』(モーガン・マッコール著、プレジデント社)などがある。
※記事の内容および所属等は取材時点(2020年5月22日)のものとなります。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

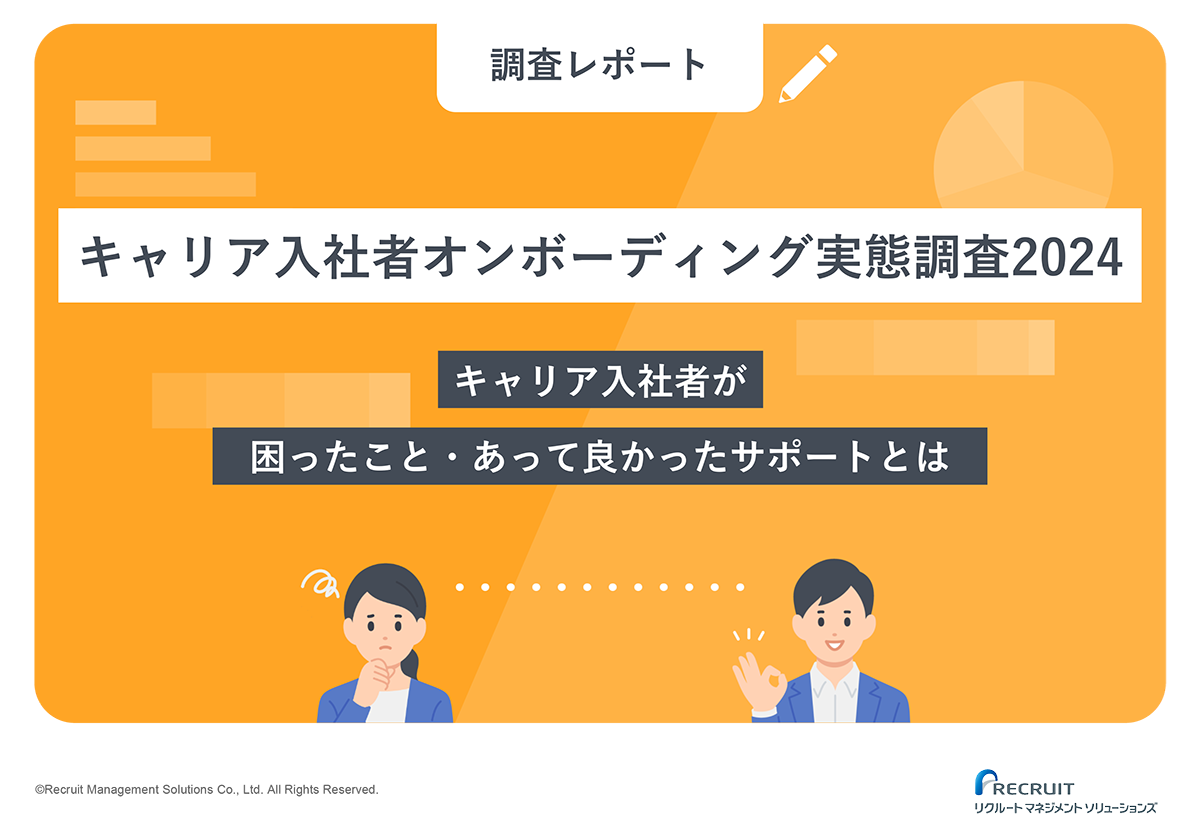












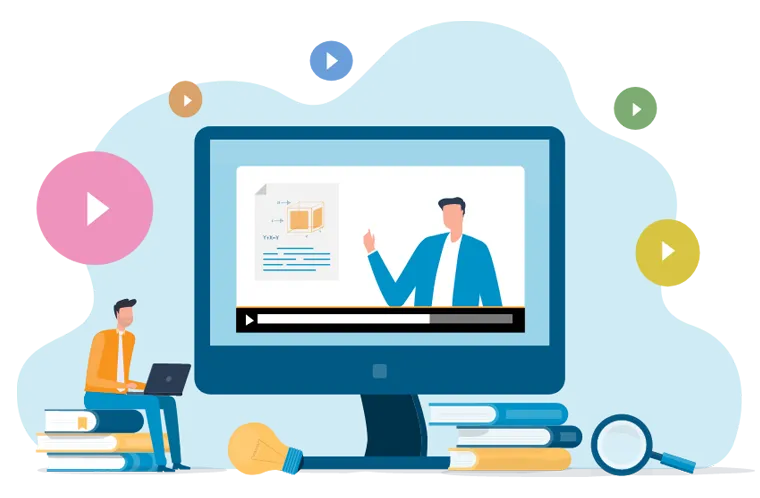 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての