特集
中途入社者の適応支援のポイント
中途入社者のオンボーディングと組織適応─実証的研究を踏まえた現状把握の重要性
- 公開日:2025/07/22
- 更新日:2025/07/22

事業環境が大きく変化するなか、中途採用を強化する動きが加速している。
一方、これまで新卒採用を主体としてきた企業側に、中途入社者の受け入れ・育成に関するノウハウは少なく、現場で混乱が生じているケースも多い。中途入社者の適応を支援するために何がポイントとなるのかについて、実証的なデータを踏まえて考えてみたい。
- 目次
- 経営にとっての重要性を増す中途採用
- 中途入社者の受け入れと組織適応の難しさ
- 中途入社者の組織適応の理解に向けて ~弊社における研究結果のご紹介
- 研究で得られた知見の現実場面への適用 ~中途入社者の適応状況をサーベイで把握する
- 中途入社者のジャーニーマップを描く
- 中途入社者ならではの適応の難しさの理解がすべての出発点
経営にとっての重要性を増す中途採用
事業のグローバル化、サービスのデジタル化、サステナブルな社会への適合、内部統制・コンプライアンスの強化など事業変革の必要に迫られるなか、近年、大手企業において就労経験者を対象とする中途採用(キャリア採用)を大幅に増加させる動きが生まれている。製造業や金融業界では、ここ3~4年の間に採用した人数が、新卒採用より中途採用の方が多いという企業も少なくない。不足した人材の単なる補充ではなく、事業変革や価値創造のために必須となる人材を確保するという重要な役割を、中途採用が担うようになりつつある。
中途入社者の受け入れと組織適応の難しさ
大手企業を中心に採用数を拡大しつつある中途採用だが、その受け入れや入社後の組織適応については、必ずしもうまくいっていない状況がある。中途入社者が短期間で離職してしまったり、配属先の組織における適応がうまくいっていないなど、現場で生じている状況に不安を抱える人事の方も多い。
中途入社者の組織適応が難しい理由として、まず挙げられるのは現場における受け入れの実績が少ないことである。これまでは新卒採用が人材調達の主軸であったために、中途入社者の受け入れ・育成については現場にも、人事にも十分なノウハウが存在しないことが多い。中途入社者は“即戦力”なので、支援やフォローは必要ないという誤った考えをもつ上司や職場も多く、中途入社者にどのように関わり、何をどの程度支援していけばよいのかを受け入れ側が十分に理解できていないという問題がある。
また、中途入社者の組織適応を難しくしているもう1つの理由として、我が国に特有の中途採用の特徴がある。ジョブ型の人的資源管理を基盤とする欧米とは異なり、日本の場合には、中途採用においても採用時に求められる経験・知識・スキルは必ずしも厳格な要件としては適用されず、中途採用でありながらも入社後の“伸びしろ”(ポテンシャル)を重視して採用するというケースが多く見られる。中途入社者は、入社後に周囲から「即戦力」を期待されることが多いが、実際には前職の経験やスキルをそのまますぐに仕事に生かせるわけではなく、さまざまなことを一から学ばなければならない環境のなかで、同時に早期の成果発揮が求められるという板挟みの状況に陥りやすい。前職の経験を入社後に生かせる程度は人によってさまざまだが、ポテンシャルを重視して採用された人材の場合は特にこの壁にぶつかりやすいため、中途入社者の適応を支援していく上ではこの「経験/未経験の程度」を考慮に入れておくことが大切である。
中途入社者の組織適応の理解に向けて ~弊社における研究結果のご紹介
受け入れに苦慮している企業の現場に経験・ノウハウが少ないのと同様に、アカデミックな領域においても、中途入社者のオンボーディングや組織適応に関する研究は、この分野の第一人者である甲南大学の尾形教授の研究など一部に限られており、知見がまだ十分には蓄積されていないのが現状である。中途入社者のオンボーディングを円滑に進め、組織適応を促進していくためには、今後この領域における研究を幅広く行い、現場での実践を重ねることで、中途入社者がいかにして組織に適応していくのか、そのプロセスや構造を明らかにしていくことが重要になるだろう。
そこで以下では、弊社が中途入社者を対象に2023年に実施した調査データを用いて行った研究結果*を取り上げ、中途入社者の組織適応に関して得られた知見とモデルを紹介する。この研究は、前述した「経験/未経験の程度」の違いによって、中途入社者を「A専門性重視型採用者」と「Bポテンシャル重視型採用者」の2つに区分し、それぞれの組織適応の状況にどのような違いが見られるかを調べたものである。
1.調査データ
2023年8月にインターネット調査により収集した1038名のデータを用いる。データの属性は、図表1のとおりである。
<図表1>調査データの属性の内訳
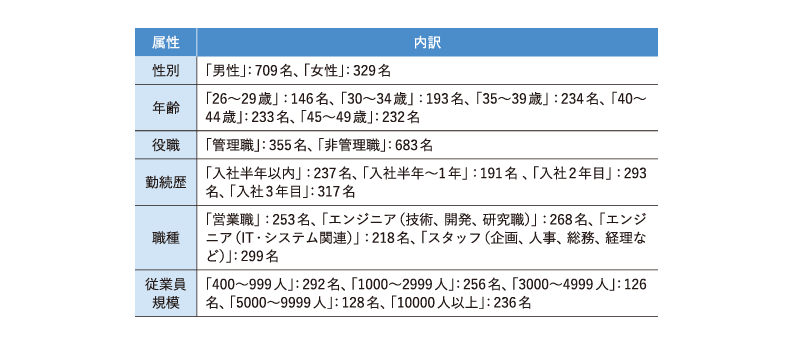
2.分析に用いた要素
組織適応の結果を捉える指標
組織適応の結果は、「短期的な結果指標」と「中長期的な結果指標」の2つに分けて把握することができる。「短期的な結果指標」は、「成長実感」「職務遂行への自信」「認められている実感」「役割の明確さ」の4つで構成される。これらは適応が進むなかで比較的早いタイミングで高まっていくことが想定される要素である。一方「中長期的な結果指標」は、「勤続意思」「ワーク・エンゲージメント」「組織推奨意向」の3つで構成される。これらは良好な状態が実現されるまでに比較的長い期間を要することが想定される要素である。
組織適応を促進する要因
組織適応を促す要因として、「上司の関わり」「職場の風土」「本人のプロアクティブ行動」「本人のプロアクティブな性格特性」の4つを取り上げる。中途入社者が組織に適応し、仕事で成果をあげていく上で上司の支援やサポートは非常に重要であり、またプロパーの従業員とは異なる能力・スキル・価値観をもつメンバーを柔軟に受け入れようとする前向きな職場風土も、適応を促進することが予想される。一方、組織に適応していこうとする中途入社者自身の積極的な行動(プロアクティブ行動)や、そうした前向きな行動をもたらしやすい性格特性(プロアクティブな性格特性)も適応にプラスに働くことが想定される。
採用時の企業からの期待に基づく区分
採用された際に企業から受けていた期待が、「A:前職で身につけた専門領域における高度な知識・スキル・経験を直接的に生かして即戦力で活躍すること」「B:前職で身につけた知識・スキル・経験を直接的に生かすというよりは、これまでの社会人経験をベースにして、入社後に新たな知識・スキル・経験を学びながら活躍すること」のどちらに近いかを本人に選択させ、2つのタイプに区分した。対象者の内訳は「A専門性重視型採用者」が565名、「Bポテンシャル重視型採用者」が473名となった。
3.分析の結果
分析1
組織適応の結果の比較
図表2は、AB両群における組織適応結果の平均値を比較したものである。これを見ると、B群(ポテンシャル重視型)は、A群(専門性重視型)に比べて「職務遂行への自信」「認められている実感」「ワーク・エンゲージメント」の得点が有意に低くなっている。新たな組織への適応は、B群(ポテンシャル重視型)にとってより困難であることが分かる。
<図表2>AB両群における組織適応結果の比較
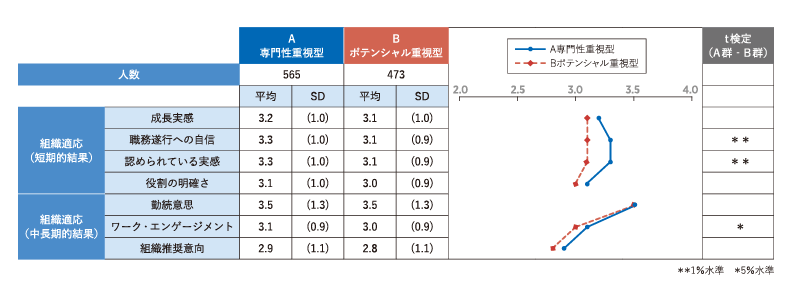
組織適応の短期的結果
組織適応の短期的結果の平均値を入社歴別に比較すると(図表3)、AB両群共に時期を追うごとに短期的な適応が次第に高まっていくことが分かる。このことは、中途入社者の組織適応の進展の状況を捉える上で、「仕事を通じて成長している実感をもてているか」「自らの職務遂行能力に自信をもてているか」「周囲から認められている実感をもてているか」「自分に求められている役割を明確に認識できているか」という点に注目することが有効だということを示している。
<図表3>組織適応の短期的結果の入社歴別比較
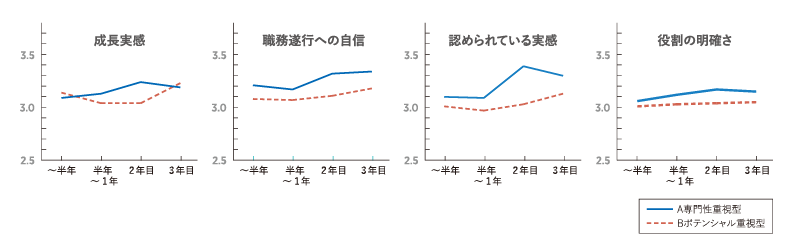
組織適応の中長期的結果
図表4は、組織適応の中長期的結果の平均値を入社歴別に比較したものである。これを見ると、A群では時期による変動があまり見られないのに対して、B群では入社後半年から2年目にかけて得点が一度低下し、その後上昇するという「J字」を描いている。このことは、A群は入社後比較的早いタイミングで一定水準の組織適応がなされるのに対し、B群は入社後かなり長期にわたって適応が困難な状態が続き、2年目以降になってやっと適応した状態に至るということを示している。中途入社者の組織適応を捉える上では、比較的単調に上昇しやすい短期的指標に目を向けるだけでは十分ではなく、条件によっては長期的な「J字」を描くこともある「勤続意思」「ワーク・エンゲージメント」「組織推奨意向」という、中長期的指標にも注目することが必要だといえる。
<図表4>組織適応の中長期的結果の入社歴別比較
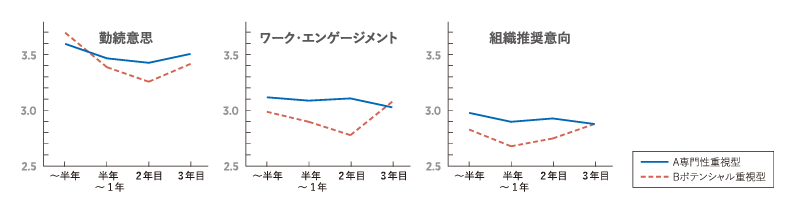
分析2
中途入社者の組織適応を捉えるモデル
図表5は、組織適応の促進要因が短期的結果を経由して中長期的結果をもたらすという因果関係を表現したモデルである。多母集団同時分析の結果が一定の適合度を示したことから、下記のモデルを想定することは妥当であることが示された。このことは、「上司の関わり」「職場の風土」「本人のプロアクティブ行動」「本人のプロアクティブな性格特性」という4つの要因が、中途入社者の組織適応には重要であることを表している。なかでも「上司の関わり」は、短期的適応に直接的な効果を与えているだけでなく、職場風土の形成や本人のプロアクティブ行動の促進を通じた間接的な影響も同時に与えており、中途入社者の組織適応を考える際に非常に重要な要素であるということが分かる。
<図表5>中途入社者の組織適応を表すモデル(多母集団同時分析)
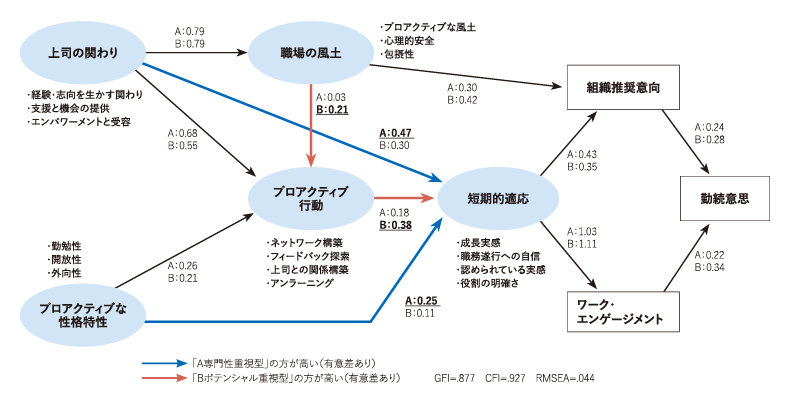
また、図表5におけるパスの係数に注目すると、「本人のプロアクティブ行動」が短期的適応に与える影響、および「職場の風土」が「本人のプロアクティブ行動」に与える影響は、A群よりもB群の方が大きかった。このことは、B群の組織適応にとって、自ら働きかけて上司や周囲との関係を深めたり、社内のネットワークを広げていく行動(プロアクティブ行動)が重要であること、また本人がそうした行動をとる上で職場の受容的・支援的な風土が重要であることを示している。
一方A群では、「上司の関わり」と「プロアクティブな性格特性」が「プロアクティブ行動」を経由せずに直接的に短期的適応に与える影響が、B群に比べて大きかった。このことは、A群にとって「プロアクティブ行動」の重要性が相対的に低いこと、また業務遂行に直接的に関連するような上司からの支援や、仕事の成果に結びつきやすい本人の特性(例えば新しいことへの挑戦心や粘り強さなど)が短期的適応に与える影響が大きいことを示唆している。
研究で得られた知見の現実場面への適用 ~中途入社者の適応状況をサーベイで把握する
以下では、今回紹介させていただいた調査研究の結果を、実際の中途入社者のオンボーディングや適応支援に向けてどのように生かしていくことができるかについて説明する。
上記の研究で得られた知見を踏まえて、弊社では中途入社者の組織適応の状況を把握するための標準的なフレームと調査項目のセット、およびリファレンスデータを用意している。図表6は、「中途入社者向けオンボーディングサーベイ」のフレーム構成である。大きく、オンボーディング・組織適応に関する「結果」を捉える指標、「プロセス」を捉える指標、適応を促進する要素が適切に機能しているかを捉える指標、オンボーディングをめぐる環境に関する項目で構成されている。このサーベイを用いることによって、自社の中途入社者のオンボーディング・組織適応の進展状況を、他社における一般的な水準との比較で評価したり、適応支援上の課題がどこに存在するかを把握することが可能となる。
<図表6>「中途入社者向けオンボーディングサーベイ」のフレーム構成
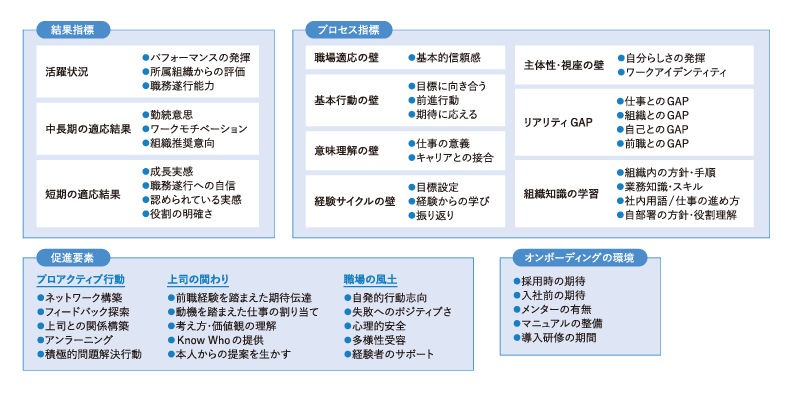
中途入社者のジャーニーマップを描く
中途入社者が組織に適応するまでに要する期間や、適応の途上で壁にぶつかるタイミングは企業によって差があり、「ある会社ではこの時期にこうした壁につまずきやすい」という傾向の違いが見られる。そのため、図表7のような「ジャーニーマップ」を作成し、自社のオンボーディング・組織適応の特徴を事前に整理しておくことが望ましい。中途入社者の組織適応の進行状況を曲線で表したこの図を見れば、「どのタイミングで、どのような支援が必要になるか」ということが予測できるため、適応支援に関わる施策の内容や時期について検討する際の有効な手がかりとなる。
<図表7>中途入社者のジャーニーマップ
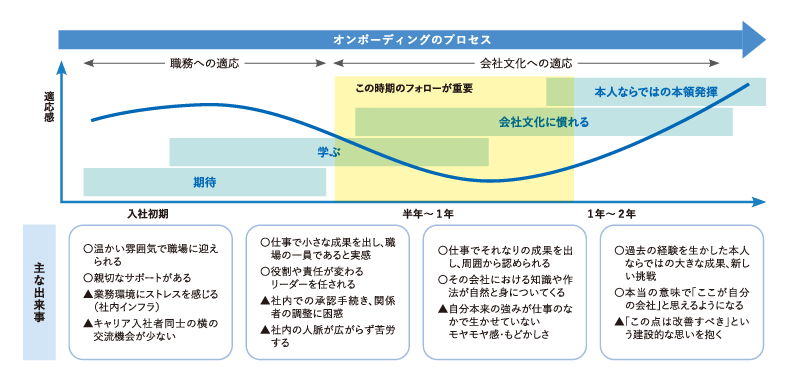
中途入社者ならではの適応の難しさの理解がすべての出発点
一般に中途入社者を受け入れる職場の上司やメンバーは、「中途入社者なのだから経験もあるし、放っておいても自分でなんとかするだろう」と思ってしまいがちであるが、中途入社者の組織適応には、新卒入社者とはまた異なる難しさがある。前職で身につけたスキルや能力をそのまますぐに仕事に生かせるわけではなく、ポテンシャル重視で採用されたB群の中途入社者であれば一層難しい。専門性を重視して採用されたA群の場合も、これまでの経験を仕事により生かしやすいというアドバンテージをもつとはいえ、その会社ならではの仕事の進め方、判断の仕方、社内のルールや社内用語を理解・習得するまでには相当の時間がかかる。仕事を進める上で不可欠な社内の人脈やネットワークを有していないことも大きなハンディキャップであり、周囲が「もう入社して半年も経つので大丈夫だろう」と思っている時期に、実は本人が適応上の大きな壁にぶつかって悩んでいるということも多い。
大切なことは、中途入社者が直面するこのような中途入社者ならではの悩みや難しさを、職場の上司やメンバーがきちんと理解し、それを踏まえて適切な支援・フォローを行うことである。中途入社者が置かれた状況について周囲が正しく理解できていれば、「本人のことをもっと深く知りたい、適切な支援を行いたい」という気持ちも生まれやすくなるし、ただ単に「自社のやり方に従え」というスタンスではなく、「自社にはない知識や経験」をもつ人材として、中途入社者ならではの強みを引き出そうとする関わりも生じやすくなる。このため、社内でサーベイ調査を実施した上でジャーニーマップを作成し、得られた情報を「受け入れマニュアル」の形にまとめて、現場の上司に配布しているという企業も多い。中途入社者のオンボーディング・組織適応を支援する体制を整えていくための第一歩として、現状の正確な把握から着手することを皆様にお勧めしたい。
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.78 特集2「中途入社者のオンボーディングと組織適応」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
関連するインタビュー記事
オンボーディングを強化して中途採用者に選ばれる会社になろう
甲南大学 経営学部 教授 尾形真実哉氏
関連する研究テーマ
執筆者

技術開発統括部
研究本部
主任研究員
内藤 淳
1989年、東京大学文学部社会心理学専修課程卒業後、リクルートに入社。1994年、人事測定研究所に転籍。以来、法人向けの心理アセスメント、組織診断ツールの研究開発および各種人事データの解析に携わる。2014年より、立教大学現代心理学部兼任講師。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)









