特集
オーバーマネジメント(過剰管理)を考える3つの観点
オーバーマネジメントの要因とその弊害
- 公開日:2024/07/12
- 更新日:2024/07/12

オーバーマネジメントに関して、古くからその弊害は指摘されている。それにもかかわらず、現在に至るまで、管理は過剰になっていると感じる。オーバーマネジメントがなぜ起こってくるのか、また、どういう弊害があるのか改めてひもといてみる。
- 目次
- マネジメント論:統制と解放の歴史
- ネガティビティ・バイアス:ゼロリスク思考による管理強化
- アカウンタビリティとメトリックスの広がり
- 部下への権限委譲が進まないマイクロマネジメント
- 必要なマネジメントも過剰になれば弊害も
マネジメント論:統制と解放の歴史
弊社組織行動研究所で、持続的成長企業の研究を行った*1。その研究のなかで、中長期にわたって高業績企業と低業績企業の比較を行い、低業績の特徴を調査した。低業績企業の特徴を見てみると、「会議を通すための内向きの仕事が多い」「形式的で本質的な議論がされていないという場面が多い」「誰のためにもならない仕事が多い」「人事制度やコンプライアンス上の制約が多い」というものがあった。それらの特徴を一言で言うと、「過剰管理」つまり「オーバーマネジメント」であった。
弊誌59号(2020年)の調査では、84.1%の会社員が「自律的に働きたい」と考えている*2。この数字が意味することは、「8割以上の人は他人から指図されて働きたいわけではない」、つまり「管理されたくない」と思っている。しかしながら、同調査では、自律的に働きたいと考えている人の半数程度が「上司や会社から、自律的に働くことを阻まれている」と感じている。多くの社員は自律的に働きたいと思っている一方で、会社から邪魔をされていると感じているのである。そこでもオーバーマネジメントの存在が見え隠れする。
世界のトップシンカー50に選ばれ、日本を代表する経営学者の野中郁次郎氏は、日本の国際競争力低下の背景には、「オーバープランニング(過剰計画)」「オーバーコンプライアンス(過剰規制)」「オーバーアナリシス(過剰分析)」の3つがある*3と指摘している。「過剰計画」「過剰規制」「過剰分析」の3つに「過剰測定」を加えて、ここではオーバーマネジメント(過剰管理)と定義する。
企業組織におけるマネジメントは、本来、混沌とした組織をまとめ、生産性を高めるための手法として、発達してきた。1人では達成できないことを組織で行うことによって、より大きな成果を得ることができるようになったのもマネジメントのおかげである。
統制と解放という観点で、図表1に主なマネジメント論についてまとめている。
<図表1>統制と解放に関する主なマネジメント論
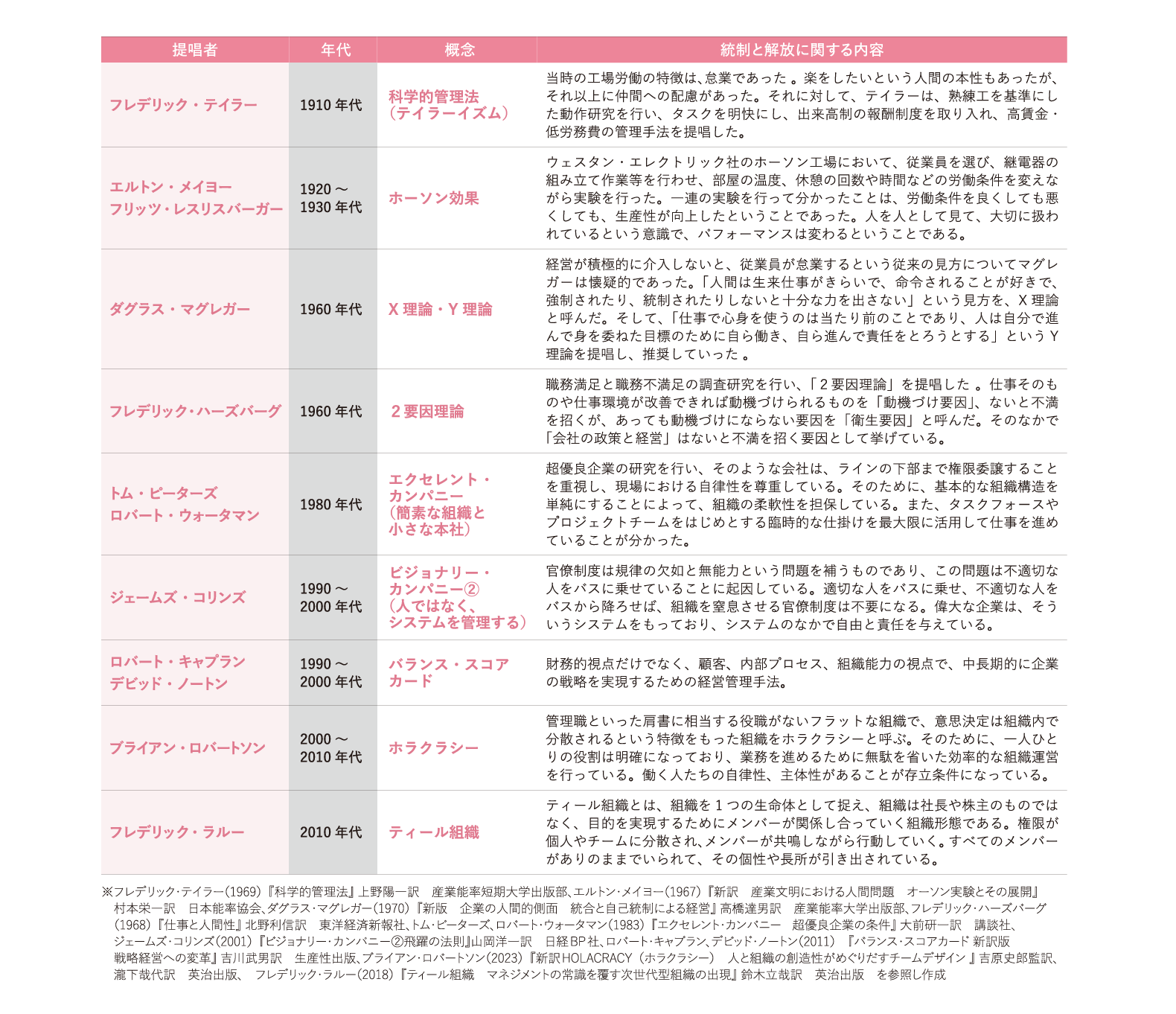
100年以上前に、フレデリック・テイラーは、より高い生産性を上げるための方法論を提唱し、多くの企業で実践していった。ある意味、統制のマネジメントである。一方で、その手法に対して、人間性の疎外を生むもの、資本家の搾取の武器だという批判もあり、その後、新しいマネジメント論が展開されていった。統制に対して解放のマネジメント論である。近年では、上司の指示を待つのではなく、自律的に仕事を進めていくティール組織やホラクラシーなどが注目を浴びており、次世代型の組織として、その導入を試みる企業も増えている。
100年前から現在に至るまで、人を統制するのではなく、解放していくことを提唱しているマネジメント論は多いのにもかかわらず、管理統制マネジメントは粛々と進められているように思える。コンプライアンスは強化され、手続きやルールは増え、株主や社会に対する説明責任を果たすためにさまざまな報告書が作られる。
業績を上げる上で大切だと思われる、従業員の自主性やモチベーションを犠牲にしてまで、経営はなぜ管理を強化しようとしているのか。
「ネガティビティ・バイアス」「アカウンタビリティとメトリックス」、そして「マイクロマネジメント」という観点で、ひもといていく。
なお、マネジメントという概念には、会社の経営のことを指す場合と上司・部下間でのマネジメントのように使われることがある。このレビューでは、両方とも視野に入れている。
ネガティビティ・バイアス:ゼロリスク思考による管理強化
人は得することよりも損失を回避することの方がより重大だと感じる傾向がある。ネガティビティ・バイアスと呼ばれる、この傾向は多くの研究で支持されている*4。コイントスをして「表が出たら100ドル払う。裏が出たら150ドルもらえる」というギャンブルをやるかどうかという実験を行ったとき、期待値はプラスにもかかわらず、多数の人がそのギャンブルを行わないと回答する。多くの実験結果によると、人は損失の2倍程度の利得がないとギャンブルを行わない*5。つまり、人は得をするよりも損をすることが嫌なのである。それは人の進化の歴史を考えると、納得がいく。目の前にある、好機よりも脅威に対して鋭敏に反応した方が生き残る可能性が高かったということである。
企業の場合、ネガティブなことといえば、不正や不祥事による信頼の失墜である。経営者としては、最も避けたいことである。それゆえに、不正や不祥事が起こらないような管理体制を作る。制度やルールを充実させる。何か非難を受けても言い訳ができる準備をする。リスク対策である。ネガティビティ、つまり不安や恐怖や心配は、制度やルールが強化される要因になる。
それでもリスクはゼロにならない。ビジネスを行っていれば、人為的なミスは起きるし、想定外の出来事も起こる。ゼロに近づけようとすればするほど、管理はさらに強化される方向に動き、オーバーマネジメントになる。
アカウンタビリティとメトリックスの広がり
企業経営を行っていると、経営者は自分たちが行っていることを説明しなければならない。特に、上場している場合には、不特定多数の株主や投資家に対して、財務諸表と監査報告書を含む有価証券報告書を作成・開示することが義務づけられている。さらには、企業は株主だけでなく、環境問題に代表されるように、社会的責任も求められており、CSR報告書や環境報告書の作成・開示というものまで必要になってきている。
いわゆる「アカウンタビリティ」が企業経営に求められているわけだが、その歴史は古く、古代アテネ民主制に起源をもつとされている*6。日本においては、戦後から国会にて使われるようになったのだが、「説明責任」という訳語を含めて国会議事録での出現回数を数えてみると、昭和の時代にはわずか7件、平成の最初の10年間で183件、平成10年から22年で2810件と急増している*7。
企業経営においても、2000年代に入ってから、会計不正、偽装工作、消費期限の改ざんなどの企業不祥事が多発し、社会に対してきちんと説明することが求められたこともあり、アカウンタビリティという言葉が使われ始めた。対株主、対社会だけではなく、社内においても部下が上司に対して、あるいは取締役会や経営会議での説明の際にも使われるようになった。そのような説明責任であるが、分かりやすく説明するためには、その成果を数値化して示すために測定(メトリックス)することも求められるようになった*8。
実際、測定して数値化すると説明はしやすくなる。投資の判断に使えるし、自分たちが投資した理由を株主に説明しやすくなる。そのため、メトリックスは、アカウンタビリティが広がるのと同じように広がっていった。
ただ、説明責任を果たすための報告書づくりや指標づくり、成果の測定には、相応のコストがかかっている。オーバーマネジメントにつながる。
部下への権限委譲が進まないマイクロマネジメント
初めて管理職に就いた際の、陥りやすい問題の1つとして、「部下への権限委譲が進まない」ことがある*9。権限委譲が進まなくて、仕事のやり方を細かく指示し、メンバーそれぞれの進捗状況を高頻度で報告させるということを行う。人を通じて成果を出すのが管理職の仕事だからこそ、メンバーがきちんと成果を出すのかどうか心配であり、つい口を出してしまう。メンバーのレディネスレベルが低ければ、指示が細かい方が効果的ではあるが、メンバーの経験が豊富になれば、メンバーの自主性に任せていった方が、成果があがる。優秀な管理職であれば、メンバーの状況を見ながら、自分のスタイルを調整する*10。
問題は、メンバーに任せていった方がいい状況であったとしても、つい口出ししてしまう管理職である。そのようなマイクロマネジャーは、過剰に監視を行い、数字を好み、メンバーからの報告を高頻度で求める。早朝から深夜まで長時間働き、メンバーにも同じことを求め、休暇中にも連絡をとりたがる。間違いを嫌い、メンバーのミスを過度に追及し、説教をして、メンバーが二度とミスしないように矯正を行おうとする*11。
そのような管理職のなかには、環境をコントロールしたがり、目的のためなら手段を選ばないマキャベリズムやサイコパシー傾向をもっており、目的のためにメンバーを「使う」という思想をもつ人も多い*12。そして環境をコントロールしようとする傾向は、経営側から見ると、頼もしく見え、管理職に選ばれやすい*13。
そのような個人特性はなかったとしても、昇進するにしたがって、コントロールしたがる傾向が強まる。メンバーの役割や仕事や目的を決める権限をもっていて、メンバーを査定する権限をもっていると勘違いするようになり、メンバーに対して必要以上に権力を行使する傾向が増すのである*14。
つまり、コントロールしたがる傾向がある人が管理職に昇進しやすく、そうでない人も昇進するにしたがって、その権力を必要以上に行使する傾向をもつようになるということである。
「ネガティビティ・バイアス」「アカウンタビリティとメトリックス」「マイクロマネジメント」の観点から、企業経営を行う際に、オーバーマネジメントに陥る要素を述べた。3つの観点は、つながっている。損をしたくないという本性から、何か起こったときでも説明ができるようなルールや制度を整え、言い訳づくりを行う。そのようなルールを作って従業員をコントロールできるように、コントロールがうまい人たちを管理職に昇進させていき、結果、企業経営はオーバーコントロール傾向になる。
必要なマネジメントも過剰になれば弊害も
改めて、オーバーマネジメントの弊害をまとめる。
利得を得るよりも損失を回避するネガティビティ・バイアスは、企業経営にとってメリットはある。不祥事を予防することで、企業の信頼失墜を避けることができる。問題は、そのやりすぎである。実際にはほとんど起こり得ないことであっても、確率無視で、起こり得る最悪のケースを極端に恐れる。あるいは、起こっても許容できるリスクに対して過敏になって、規制を厳しくしてしまう。結果、得られたであろう便益や不必要なコストに関心が向かないことがよくある*15。
「何かあったらどうするのだ」という組織風土は、リスク回避傾向に陥る。投資をしてもリターンが見えない新しい事業や商品に対して不寛容になり、必要以上に、そのリターンを保証するような証拠を求めるようになる。そこに、アカウンタビリティ(説明責任)とメトリックスが絡まってくる。説明をするための資料づくりばかりが仕事になり、新しいビジネス開発が進まない。測定できることは限られている。企業は新しい価値を創造して、収益を稼いでいくのだが、これまでにない商品やビジネスは、やってみないと分からない部分も大きい。測定しにくい分野である。測定できるように、緻密なマーケティングを行い、緻密な売上計画を作るとなると、そのことにパワーが割かれて、肝心な新しい商品を作るのがおろそかになる。
「それは本当に儲かるのか」と経営者は問う。重箱の隅をつつくようになる。儲かるような計画を作成していくことになる。その商品やビジネスにとって、肯定的に見えるデータばかりを探して、プレゼンテーションするということが多くなる。そういうことが重なっていくと、新しい大胆なビジネスを開発していくことは面倒になっていく。長期的な目標はなおざりにして、短期目標が重視される。測定可能なものにばかり注目すると、改ざんや不正の温床になる*8。
測定がしやすい報酬システムは、創造性に対するマイナス影響、不正、短期的な目標へのシフト、そしてアンダーマイニング効果(内発的動機づけの低減)につながることが確認されている*16。従業員は数値のために働くようになり、本来あった職業倫理は忘れ去られる*8。正確な評価をするための報告が多くなり、管理職は、部下の一挙手一投足を見ていなければならなくなり、管理負担は増える。
マイクロマネジメントは、メンバーの自主性、主体性、創造性を減衰させる。メンバーは萎縮し、自分で判断することを放棄し、やる気を失い、場合によってはメンタル不調をきたすようになる。相互の信頼感を壊し、長期的には組織の生産性を下げ、欠勤率や離職率を高めるようになる*11。
組織を動かすためには、マネジメントは必要である。リスク社会*17であり、先行きが不透明で何が起こるか分からない時代、経営としては、不安を払しょくするためにマネジメント強化を行っていきたい。ただ、マネジメントを強化すればするほど、現場のやる気は下がり、疲弊感が増し、業務効率は下がることも事実である。自社なりの適正なマネジメントというものを改めて議論すべき時が来ている。
*1 リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所(2010)『日本の持続的成長企業 「優良+長寿」の企業研究』東洋経済新報社.
*2 リクルートマネジメントソリューションズ(2020)自律的に働くことに関する実態調査.RMS Message Vol.59
*3 経営アカデミー(2021)日本変革へ「見抜く力」養成~野中郁次郎名誉学長・沼上幹学長が対談
*4 Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of general psychology, 5(4), 323-370.
*5 Novemsky, N., & Kahneman, D. (2005). The boundaries of loss aversion. Journal of Marketing Research, 42(2), 119-128.
*6 Day, P., & Klein, R. (1987). Accountabilities: Five public services. London: Tavistock.
*7 山本清(2013)『アカウンタビリティを考える どうして「説明責任」になったのか』NTT出版.
*8 ジェリー・ミュラー著、松本裕訳(2019)『測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?』みすず書房.
*9 小方真・嶋村伸明・橋本ひろみ(2010)「日本企業におけるトランジション(職位の移行)に関する研究 課長・部長・事業部長を中心に」『経営行動科学学会第13回年次大会:発表論文集』
*10 ポール・ハーシー、デューイ・ジョンソン、ケネス・ブランチャード著、山本成二、山本あづさ訳(2000)『入門から応用へ 行動科学の展開【新版】 人的資源の活用』生産性出版.
*11 White Jr., R. D. (2010). The micromanagement disease: Symptoms, diagnosis, and cure. Public Personnel Management, 39(1), 71-76.
*12 Babiak, P., Neumann, C. S., & Hare, R. D. (2010). Corporate psychopathy: Talking the walk. Behavioral sciences & the law, 28(2), 174-193.
*13 ケヴィン・ダットン著、小林由香利訳(2013)『サイコパス 秘められた能力』NHK出版.
*14 Padilla, A., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2007). The toxic triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive environments. The leadership quarterly, 18(3), 176-194.
*15 キャス・サンティーン著、角松生史・内野美穂監訳(2015)『恐怖の法則 予防原則を超えて』勁草書房.
*16 Dan Cable and Freek Vermeulen(2016). Stop Paying Executives for Performance. Harvard Business Review.
*17 ウルリッヒ・ベック著、島村賢一訳(2003)『世界リスク社会論 テロ、戦争、自然破壊』平凡社.
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.74 特集1「オーバーマネジメント─管理しすぎを考える」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
執筆者
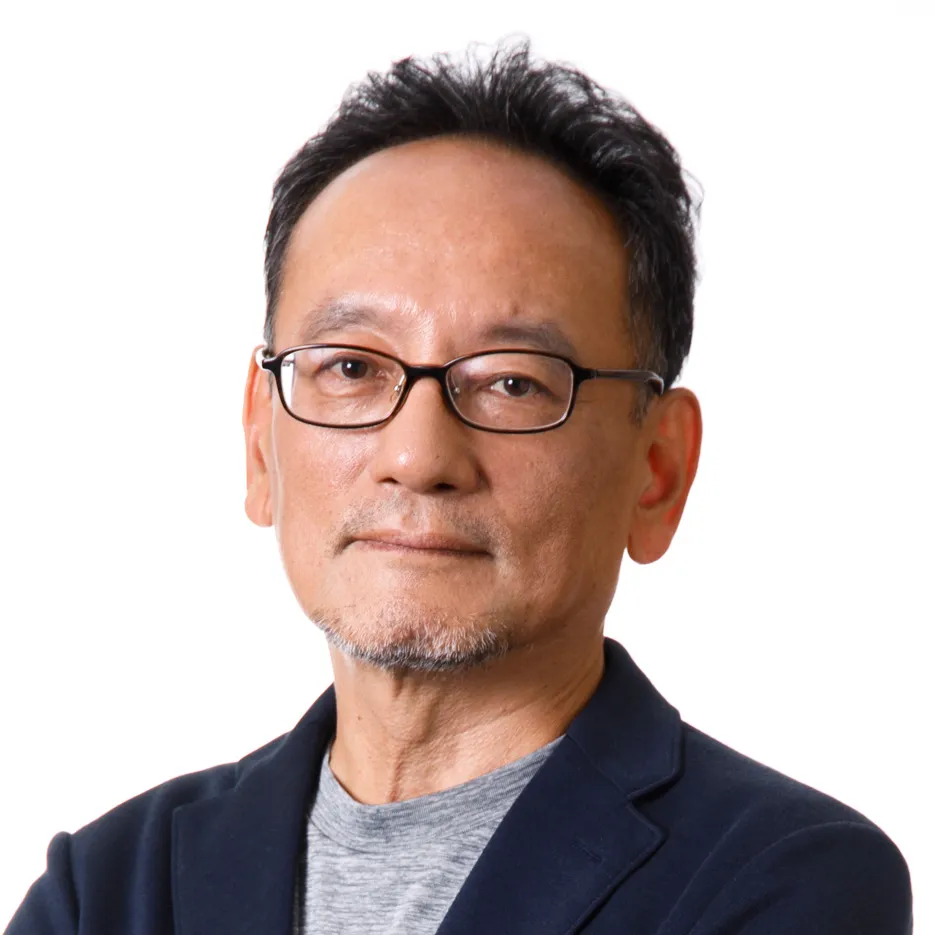
技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
古野 庸一
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社
南カリフォルニア大学でMBA取得
キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事
2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



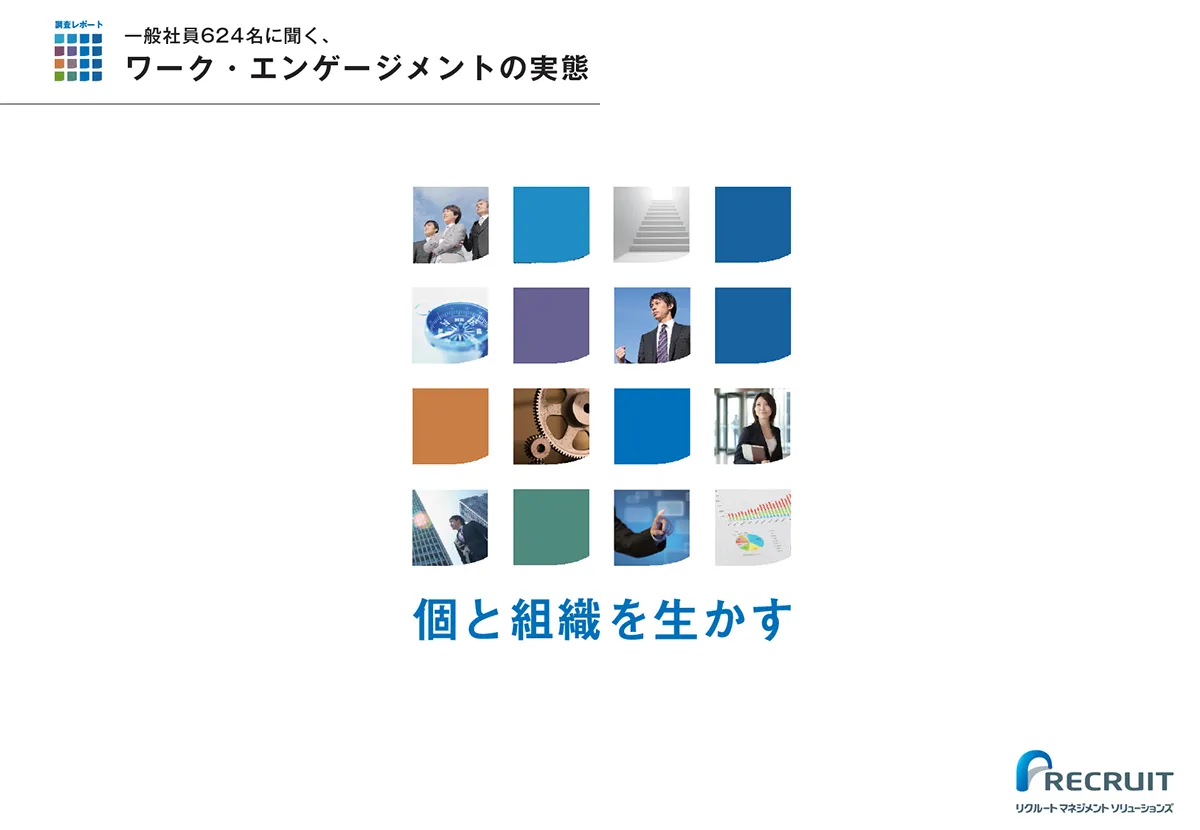
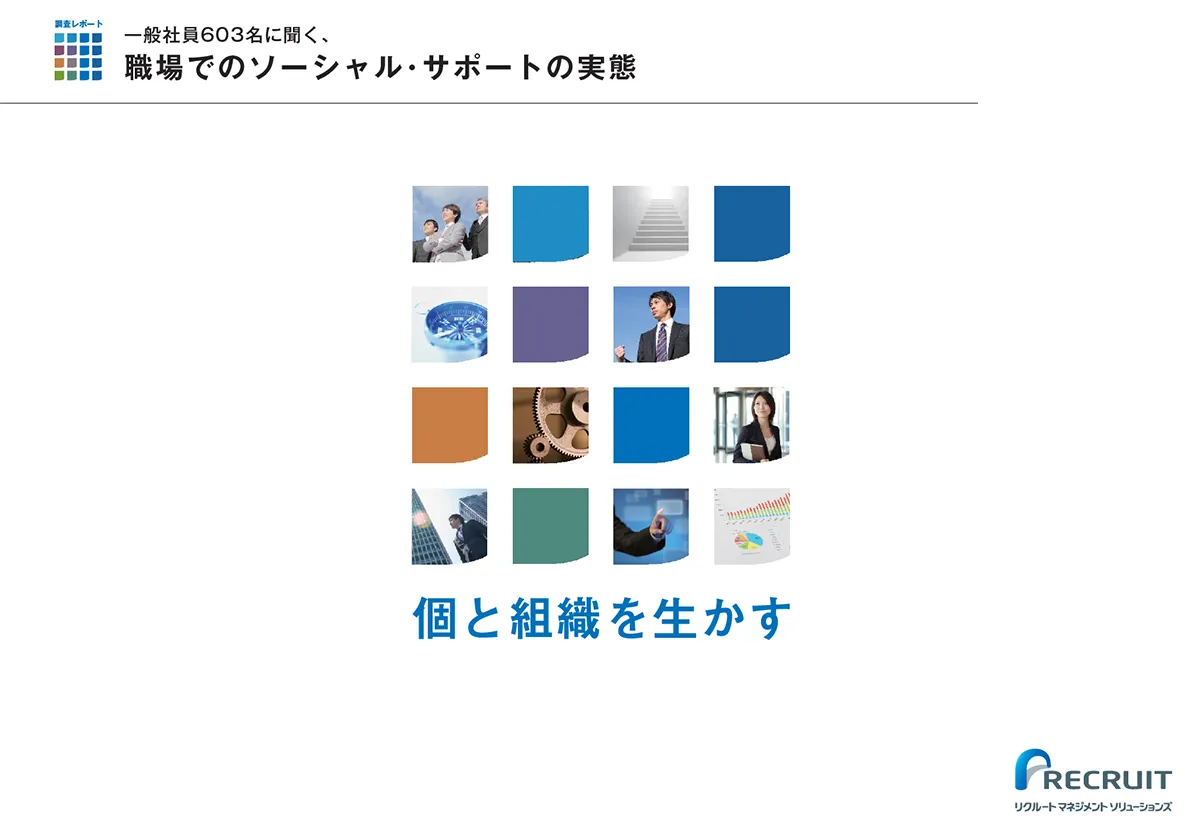









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての