特集
知っておきたい3つの視点
変化の時代における「学び」の理論
- 公開日:2019/10/10
- 更新日:2024/04/06

社会が速いスピードで多様化・複雑化する今日、学ぶこと、学び続けることへの関心がかつてないほどに高まっている。本稿では、変化の時代に求められる企業人の「学び」を理解する助けになるような概念や理論を、「他者と共にある学び」「実践のなかにある学び」「コミュニティを変革していく学び」の3つの視点から紹介したい。
- 目次
- 学びの理論の変遷
- 教室の学習からよく生きるための学びへ
- 1人の学びから「他者と共にある学び」へ
- まだ自分でないものを演じることで「箱」の外に出る学び
- 「実践のなかにある学び」経験に学ぶプロセス
- 状況に埋め込まれた学習
- 「コミュニティを変革していく学び」状況論の限界
- コミュニティの活動が拡張していく「越境」
- 前提を問い直す学び
- 変革的な組織学習
- 「楽しさ・愉しさ」が人を「学び」に参加させる
- 他者へのかかわりに踏み出すこと
- 結びに代えて
学びの理論の変遷
「学び」についての科学的探究は、20世紀初頭の、個人の行動の変化に着目する「行動主義心理学」に始まったとされる。1950年代には、頭のなかで起こっている情報処理に関心を向ける「認知主義心理学」へ、さらにそれらの行き詰まりから、1980年代にはより広い視野をもつ「認知科学」、そして「状況論」へと展開した*1*2。
学びに関する研究のこのような変遷・拡張は、研究関心や対象の移り変わりであり、研究フィールドの移り変わりでもある。研究関心や対象は、行動のコントロールから、学習者の能力、そして教育者がいかに教えるかへ、そして実践現場における学び手の学び方へと移り変わってきた。研究のフィールドは、実験室から教育現場、あらゆる実践の現場へと広がった。
近年では、比較的安定したコミュニティやその実践への適応プロセスのみならず、多様な他者やコミュニティ間の接触がそれらを変化させていくダイナミクスが活発に議論されている。「拡張的学習理論」や「パフォーマンス心理学」はそのような例といえるだろう(図表1)。
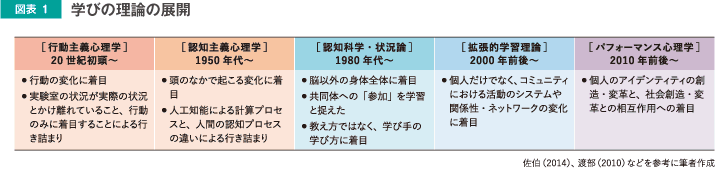
教室の学習からよく生きるための学びへ
学び研究のフィールドが実践に向かうのは、単に応用のためではない。松下(2010)は、学習目標を設定し、そこへ学習者をより効率的に到達させようとする「学習」は、近代に特有の学びのスタイルであると指摘している。「学習」は、学びの対象を、目標に対する到達度として指標化・測定可能なものに限定する。そのようにして知識や技術を学習することは、それらが成立する前提となっている社会のルールや構造を強化する側面がある*3。
しかし、複雑性と変化の速度を増す今日の社会において、私たちはむしろ、既存のルールを変えていく必要がある。また、現代に生きる私たちは、より多様な個人の可能性を開花させることを望んでいる。
佐伯や松下は、近代的な狭義の「学習」と対比し、人や社会がより良くなっていくという方向性を含む語として「学び」という言葉を用いている。本稿もそのような語感を頼りに「学び」の理論をレビューしていく。より良い、ということの意味は一義に決まらないが、本稿では、問題や制約を乗り越え続けていくといった動的なイメージで捉えたい。
変化の時代に求められる「学び」を考えるという目的から、本稿では、認知科学や状況論と呼ばれるアプローチの周辺にある理論を紹介していく。
なお、本稿は、次のような限定的な範囲をカバーするレビューとなる。
・大人を対象とする
・学校や公的な教育機関での学びではなく、実践や経験からの学びについて扱う
・今後求められるであろう、変化を創造する学びに焦点を絞り「他者と共にある学び」「実践のなかにある学び」「コミュニティを変革していく学び」の3つの視点から紹介する
1人の学びから「他者と共にある学び」へ
20世紀初めに活躍、38歳の若さで没し「心理学のモーツァルト」とも称されるレフ・ヴィゴツキーは、認知科学の裾野を広げた1人とされる。それまで個人の内部で起こる働きに注目しがちであった学びや発達の研究関心を、他者との関係性や相互作用に向けさせた。
ヴィゴツキーの提案した著名な概念に、「発達の最近接領域」がある。例えば言語を習得していく段階の幼児は、身近な人が使っている言葉のうち、自分が今使いこなせるよりも少しだけ難しいものを選択的に模倣するという。そのような、まだ1人ではできないことと、他者の助けがあればできることとの差分が、「発達の最近接領域」である(図表2)。
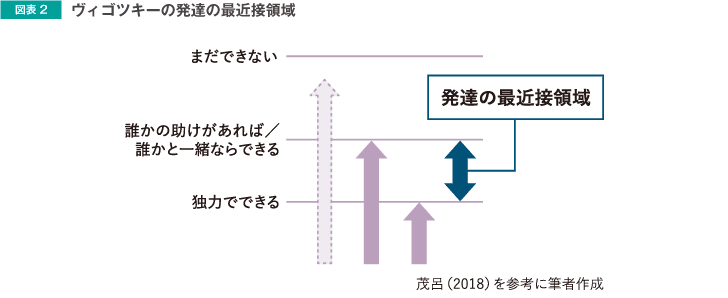
茂呂(2018)は、「発達の最近接領域」は、在ること(being)と成ること(becoming)が同居する人間ならではの学びであるとし、このような他者と共にある学びは、幼児の発達に限らず、子どもや青年、大人や高齢者にも広く通用すると指摘する。つまり、人は他者の助けを受けて、できることの限界を突破していく。そして、成長に関わる他者も、その人を動機づけ、変化に立ち会うことで、新しい関係性や在り方を育んでいく。
このような理論化は、発達の中途にある人が「何をまだできないか」ということよりも、「これから何ができるようになっていくか/何になっていくか」に関心を向ける点で、大きな転換を含んでいる*4。
まだ自分でないものを演じることで「箱」の外に出る学び
ヴィゴツキーの心理学を発展させ、ロイス・ホルツマンらのグループは、今の自分ではないものに「なってみる(performing)」ことのできる、遊び心の許される環境が、人の在り方と関係性をより良いものに発展させていくことを論じている。彼らの理論と実践は「パフォーマンス心理学」として日本でも紹介されている*5。
ホルツマンは、遊びのなかで普段とは違う活動の姿を見せることを「頭1つの背伸び」と呼ぶ。それは大人においては、豊富な経験が現実を見る目を狭める「箱」から出て、「箱なしに」ものを考えるための1つの方法となる。しかし遊び心が許される空間は、子どもにおいてさえ学齢期以降、ましてや職場では失われてしまうことが多い。アメリカでは、職場にパフォーマンス(なってみる、演じてみること)を取り戻そうと、インプロ(即興)ゲームや演劇などを取り入れたコンサルティング企業が多数存在するという*4。
「実践のなかにある学び」経験に学ぶプロセス
このように、学びの研究は、実験室や教室から実践のなかへ、教え方ではなく学び手の学び方、学ぶプロセスへと向かっていった。
学びのプロセスとして有名なものには、コルブが唱えた「経験学習サイクル」(図表3)や、野中・竹内の「SECIモデル」がある。これらのモデルは多くの実務家の直感に訴えるところが大いにあるが、こうしたプロセスが実際に段階的に生じ、いかに連関していくのか、理論的、実証的な根拠が明確でないとの批判もある*6。
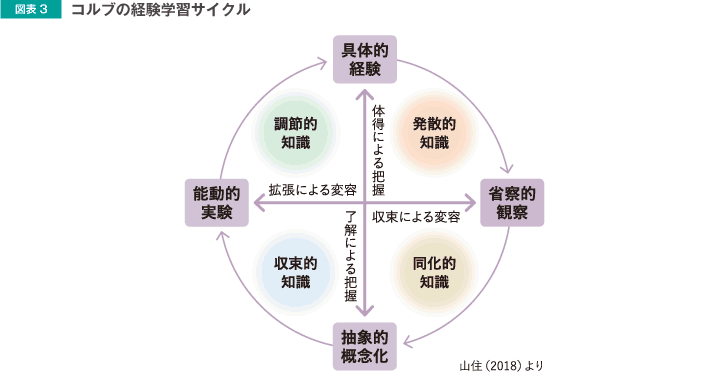
状況に埋め込まれた学習
学びのプロセスやメカニズムに着目する研究のうち、ヴィゴツキーの心理学の影響を受けながら、職場の実践に関心を向けた理論的系譜が、「状況論的学習理論」である。頭のなかに知識を蓄積することで個人が変化するといった教室的な学習観を批判し、何らかのより良いものを生み出す「実践」に参加するなかでの、「学びあい」の重要性を強調した*1。
状況論的学習理論は、さまざまな職業における徒弟制を研究した、文化人類学者であるジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーによって生み出された。仕事や趣味の集団は、実践を共有する人たちの共同体、つまり「実践共同体(community of practice)」であり、そこで何が知識となりスキルとして機能するかは、状況に埋め込まれて(situated)いる*7。実践共同体への新規参入者が、実践活動に十全に参加できるようになることを学習プロセスと捉えた。
実践における学びとは、単純な「知識の増加」ではなく、「今までと違う自分へとアイデンティティが変化していくこと」、そして「実践共同体における自分の位置が変化し、より良く実践に参加できること」が並行して生じるプロセスであることに意識を向けさせた、画期的な理論であった*8。
「コミュニティを変革していく学び」状況論の限界
学習とは「参加」であると見抜いた状況論は画期的なものであったが、いくつか不足している観点もある。特定のコミュニティへの実践に参加することが自明視されており、参加する動機や情動が重視されていないこと。そして、コミュニティの立派な一員となることを目標とする「学習」的側面が前面となり、コミュニティの活動がより良く変化したり、変革されたりする側面を十分に論じていないことなどである*9*10。
人や社会がより良くなっていく「学び」において、変化や変革は欠かせないと考えられる。しかし、生まれたときから何かしらのコミュニティに参加し、適応し続ける側面を強くもつ人間にとって、「変革」の側面はいかにして可能になるのだろうか。
コミュニティの活動が拡張していく「越境」
フィンランドの教育学者ユーリア・エンゲストロームらは、多様な他者やコミュニティと接し、協働して、さまざまな考えに触れることで、個人ではなく活動のシステムが変化し、新しい考えや活動を生み出していくプロセスを解明し、仕事や教育の現場の実践に役立てている。
活動理論という理論的系譜のなかで生み出された彼らの学習理論は、「拡張的学習理論」と呼ばれる。
エンゲストロームが提唱した概念のうち、「越境」は、日本でも近年、注目度が高い。越境において生じる学びは、水平方向の学びであるとされ、いわゆる熟達を表す垂直方向の学びと対比される(図表4)。
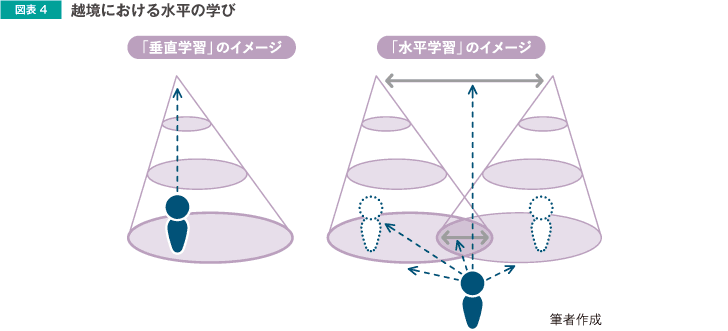
垂直方向の熟達は、あるコミュニティのなかですでに共有されている知識や技術をよりうまく、速く使えるようになるような学びであり、そのマインドセットは学習目標が明確な教室の学びに近い。一方、越境における水平学習は、「境界」の外にある異質なコミュニティや他者との協働を通して、それまでの学習目標、つまり何を学び、目指したいかが揺さぶられる学びである。それまでの「アタリマエ」の感覚が問い直され、異質なものと自分の領域を隔ててきた「境界」の存在も曖昧になっていく*11。このような変化が、結果的にコミュニティにおける関係性や活動、そして個人の在り方や振る舞いを変革していく。
前提を問い直す学び
拡張的学習理論は、前提を問い直すことが、コミュニティの変革につながることを伝えている。個人やコミュニティに「何ができて、どのように変わっていけるか」ということは、ヒトやモノやコトに助けられたり阻害されたりする、つまり「媒介されている」というヴィゴツキーのアイディアがその根底にあるのだが、関係性における矛盾や苦痛を克服していくというグレゴリー・ベイトソンやミハイル・バフチンの思想にも大きく影響を受けている*6。
どのような社会や活動のシステムにも、物事をよく進める面と、誰かに不便や苦痛を強いる面が生まれてしまうものだ。個人では解決できない社会の本質的なジレンマを表出させ解消するポイントとして、バフチンは「多声性」、つまりあらゆるグループや階層にある人の声を取り入れながら活動していくことを指摘している。
変革的な組織学習
このような、前提を見直す学習は、企業などの組織を学習の主体と見立てる「組織学習」においても論じられてきたテーマである。
クリス・アージリスは、組織がすでに使用している考え方や行動の前提を見直すか、見直さないか、ということによって、組織の学習を2種類に分けた。組織がすでにもっている考え方や枠組みのなかで、改善を行うことを「シングルループ学習」、前提そのものを問い直し変更する組織変革を「ダブルループ学習」と呼んだ(図表5)*12。
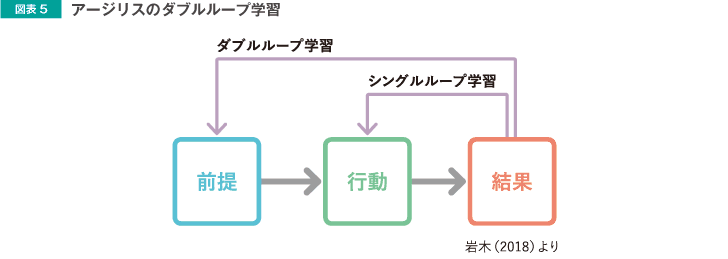
アージリスのダブルループ学習を行う方法を具体的にしたのが、ピーター・センゲが描いた「学習する組織」のモデルである。組織やチームが学習能力を向上させるためには、志の育成、共創的な会話の展開、複雑性の理解が必要だとしている。
「楽しさ・愉しさ」が人を「学び」に参加させる
近年、変革的な学習の文脈と結びつけて語られるのが「感情」への注目だ。今年度のATD2019国際大会においても、Self-compassion(自己への慈しみ)、Empathy(共感)、Vulnerability(弱みをさらけ出せる勇気)、Psychologicalsafety(心理的安全性)など、自己や他者の感情に関わるキーワードが頻出した。詳しくは、ATD2019参加報告レポートを参照されたい。
前述のように、バフチンのいう「多声性」が変革の鍵であるとすれば、耳を澄まして引き出すべき声なき声は、現状に過剰適応している自身のなかにもある。
「弱さ」を語り始めることのできる環境は、より良い社会を目指す変革により多くの人を参加させる、動機形成のメカニズムの1つの手がかりといえよう。
手がかりとなるもう1つの「感情」が、「楽しさ・愉しさ」である。佐伯(2014)は、インターネットの創設期に新しい社会を模索した人々が、イヴァン・イリイチの著書『コンヴィヴィアリティのための道具』(2015年、筑摩書房)を熟読していたことに触れ、学んだり新しいものを創り出したりする動機の根源に、コンヴィヴィアリティ=「共愉(共に楽しみあう)」的学習共同体があると指摘している*1。
またエンゲストロームも、拡張的学習の発生の仕方や広がり方を、同時代に別の場所で同じような活動が多発的に起こる「野火」的活動、中心のないゆるやかなつながりや活動に無報酬で参加し貢献し合う「菌根」的ネットワークといったメタファー(喩え)で表現している。今の社会にある前提に抑圧されている声に耳を傾け、より良い在り方や関係性を求める変革的な活動は、「楽しさ・愉しさ」を中心にすることで可能となり、個の自発性を尊重しながらの連帯によって始まり、拡散していく。
他者へのかかわりに踏み出すこと
ここにおいて、「コミュニティを変革する学び」は「他者と共にある学び」へと還ることになる。佐伯(2014)は、人間を「共愉的」な存在とみなして「かかわる」ことが、人が学びに参加する動機を理解する鍵だと言う。自己や他者を、喜びや悲しみといった情動をもつ存在とみなし、こちらのかかわり次第で相手との関係性は変化するとみなし、共に体験する愉しさやうれしさを求めているとみなす。そのようなかかわりに踏み出すことから、より良いコミュニティが生まれ、自分にできることも増えて、より良い自分になっていけるようになるのである。
結びに代えて
本稿では、変化の時代に知っておきたい学習理論について大胆に選択的にレビューした。学びの研究領域は広大であり、触れることのできなかった理論や研究成果がたくさんある。例えば、大人の学びという観点から見れば「成人学習理論」などもその1つだろう。それらの議論はまた別の機会に譲りたい。
*1 佐伯胖(2014). そもそも「学ぶ」とはどういうことか:正統的周辺参加論の前と後. 組織科学, 48(2), 38-49.
*2 佐伯胖監修・渡部信一編(2010). 『「学び」の認知科学事典』. 大修館書店 序章 渡部信一 「学び」探求の俯瞰図
*3 ――1章 松下良平 学ぶことの二つの系譜
*4 青山征彦・茂呂雄二編(2018). 『スタンダード学習心理学』. サイエンス社 第1章 茂呂雄二 人間の学習
*9 ――第3章 広瀬拓海 学習と社会
*8 ――第4章 青山征彦 仕事場の学習
*12 ――コラム(1) 岩木穣 組織の学習
*5 香川秀太・有元典文・茂呂雄二編(2019). 『パフォーマンス心理学入門』. 新曜社
*10 ――4章 太田礼穂 状況論からパフォーマンス心理学へ
*6 ユーリア・エンゲストローム著・山住勝広監訳(2018). 『拡張的学習の挑戦と可能性』. 新曜社
*7 ジーン・レイヴ、エティエンヌ・ウェンガー著・佐伯胖訳(1993). 『状況に埋め込まれた学習』. 産業図書
*11 香川秀太・青山征彦編(2015). 『越境する対話と学び』. 新曜社
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.55 特集1「職場の学びはどう変わるか」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
客員研究員
藤澤 理恵
リクルートマネジメントソリューションズ組織行動研究所主任研究員、東京都立大学経済経営学部助教を経て、青山学院大学経営学部准教授。博士(経営学)。当社組織行動研究所客員研究員。
“ビジネス”と”ソーシャル”のあいだの「越境」、仕事を自らリ・デザインする「ジョブ・クラフティング」、「HRM(人的資源管理)の柔軟性」などをテーマに研究を行っている。
経営行動科学学会第18回JAAS AWARD奨励研究賞(2021年)・第25回大会優秀賞(2022年)、人材育成学会2020年度奨励賞。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










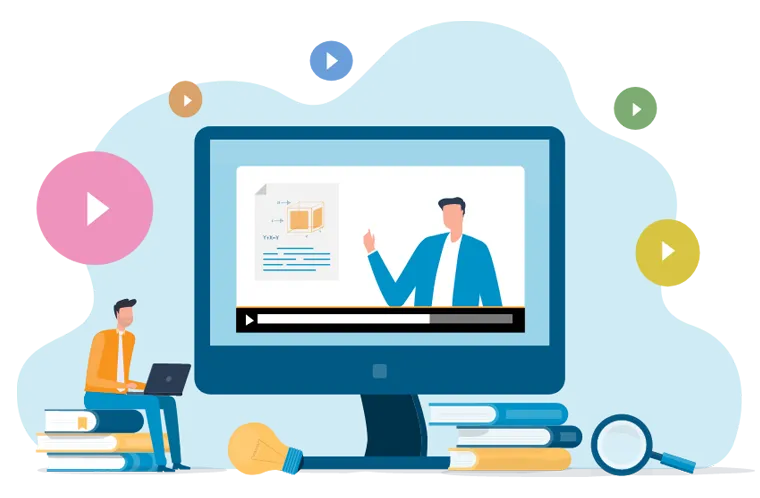 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての