特集
新人教育の目的と進め方|OJTの役割やメリット・課題を徹底解説
- 公開日:2008/03/26
- 更新日:2025/12/01

近年、新卒採用が難しくなっていることや、新人・若手の離職率が高まっていることにともない、弊社にも新卒の育成担当に関する相談が多く寄せられています。なかでも、「育成担当はつけたものの、現場で機能していない」「育成担当制度をつくったけれど、現場で運用できずに形骸化してしまった」「新人と育成担当の価値観にギャップがあって育成がうまくいっていない」といったお悩みが多くなっています。
企業人の能力のうち70%以上は「職場での経験」、すなわちOJT(On-the-Job Training)を通じて開発されるといわれています。新人育成においても、職場で仕事を通じて育てていくことは極めて重要なことと考えられます。そこで今回は、多くの企業で今になってなぜ「OJTリーダー制度」が見直されているのかといった現状と、これからの新人育成のあり方について考えていきたいと思います。
※ここでは、育成担当・メンター等の新人の育成担当をOJTリーダーと呼びます。
- 目次
- 新人教育とは?
- 新人が直面しやすい4つの壁と克服ポイント
- 新人と職場を取り巻く現状
- 新人教育の主な手法(OJT・Off-JT・eラーニング)
- 各社の取り組み状況と起こりがちな問題
- OJTリーダー制度をうまく進める3つのポイント
- 新人教育に力を入れるメリット
- 新人教育でよくある失敗と改善策
- 新人育成をきっかけとして職場の育成力を向上させる
新人教育とは?

新人教育とは、新しく入った社員が会社の業務や文化に迅速に適応し、効果的に業務を遂行できるようにするための一連のトレーニングや指導を指します。新人教育は、企業の長期的な成長や成功において不可欠なプロセスであり、社員が組織の一員として確実にスタートを切るための基盤を築く役割を果たします。
新人教育の目的
新人教育の主な目的は、新入社員が会社の業務内容やビジョン、ミッションを理解し、自らの役割を明確に認識することです。これにより、新入社員は業務に対する理解を深め、自信を持って仕事に取り組むことができるようになります。また、組織の一員としての意識を高め、チームワークやコミュニケーションスキルの向上を図ることも重要な目的の1つです。新人教育は、単なるスキル習得にとどまらず、企業文化を伝え、社員が組織の価値観を共有することで、より強固な組織づくりにも寄与します。また、学習という側面以外にも、組織に馴染んで働きやすくしていくための関わりであるということも重要なポイントです。
新人教育の重要性
新人教育は、企業にとっても新入社員にとっても極めて重要です。適切な新人教育を行うことで、新入社員の早期戦力化が実現し、業務の効率化や生産性の向上が期待されます。また、新入社員が早い段階で会社に対する信頼感や帰属意識を持つことができるため、社員の定着率向上にも繋がります。さらに、新人教育を通じて、会社の価値観や目標を共有することで、組織全体の一体感を強化し、持続可能な成長を目指す企業文化の形成が可能となります。
〈関連コラム〉
「今」の新入社員育成のヒント
新入社員の早期立ち上げを後押しする「8つの基本行動研修」とは? 実際の研修模様も紹介
新人が直面しやすい4つの壁と克服ポイント
新人・若手社員は仕事に取り組むなかで4つの壁に直面しやすい傾向があります。
能力や意欲が足りないからではなく、困難を乗り越えた経験が少ないために、行動が停滞してしまうケースが多いためです。
1.自信喪失
新人は社会人になったばかりでできないことがあるのが当たり前なのですが、できないことが多いと「自分には力がない」と感じて自信を失いやすくなります。
この段階では、「成果」よりも「経験から何を学んだか」に焦点を合わせる関わりが効果的です。
▼ポイント
- 成果よりも、経験の意味や学びを一緒に振り返る
- 成功・失敗を問わず、行動したこと自体を評価する
- 「挑戦する姿勢」を認め、次の行動を後押しする
経験そのものに価値があると本人が理解できれば、前向きな行動意欲が高まります。
2. 職場との信頼関係が築けない
上司や先輩との関係が築けないと、気づきや学びが深まらず、孤立感を抱きやすくなります。
多くの新人は「相談すると迷惑ではないか」と考えがちです。教育担当者が率先して声をかけ、安心して相談できる関係づくりを意識しましょう。
▼ポイント
- 新人が抱きやすい思い込み(例:「迷惑では?」)を言語化して一緒に整理する
- 360度サーベイなどで多角的なフィードバック機会を設ける
- 期待や役割を直接伝え、相互理解を深める
誤った思い込みを外すサポートを行うことで、信頼関係が強まり、学びの機会が増えます。
3. 仕事の意味・価値を見出せない
仕事の目的や背景が理解できないままでは、意欲が低下しやすくなります。
教育担当者としては、日々の業務のなかで「成長実感」を得られるようサポートすることが大切です。
▼ポイント
- 日々の変化やできるようになったことを一緒に振り返る
- 小さな成果も共有・承認し、達成感を言語化させる
- 担当業務が組織の目的とどう関わっているかを説明する
「小さな成功体験」を積み重ねる機会をつくることで、仕事の意味を実感しやすくなります。
4. 自力でやり切れない
困難に直面したとき、最後までやり遂げられずに達成感を得られない新人も少なくありません。
教育担当者は「結果だけでなくプロセスを評価する姿勢」を持つことが重要です。
▼ポイント
- 取り組みの途中経過を定期的に共有させる
- 成果に至らなくても、工夫や努力を認めて言語化する
- 未完了の取り組みを次の挑戦に繋げるフォローを行う
過程を認めてもらえる経験が、自信と次の挑戦に繋がります。
新人と職場を取り巻く現状
現在、新人と職場を取り巻く環境はどのようになっているのでしょうか。以下の3つの観点から解説していきます。
- 新人の採用難度の高まりと早期離職の増加
- 新人に対する早期戦力化のプレッシャー
- 新人育成の協力を引き出しにくい職場の状況
新人の採用難度の高まりと早期離職の増加
ご存じのとおり、近年の求人総数はバブル期を超え、求人倍率は2倍を超えています。さらに、大学卒業後に進学する割合が増加していることや、この年代の人口そのものが減少していることを考えると、各社の求める人材の獲得競争は熾烈な状態にあるといえます。
人材の流動化が進むなかで、「第二新卒」という言葉も生まれました。今や大卒者の3人に1人は3年以内に離職するという実態があります。これから活躍してもらいたいと思うこの時期に新人・若手が離職してしまうのは残念なことでもありますし、経営的なリスクであるともいえます。
この傾向には、若手の仕事観の変化も大きく影響しています。「自分自身が意義を感じられる仕事か」「その仕事を通じて成長できていると感じられるか」「入社後の教育体系や職場での新人の支援体制が整っているか」を重要視する学生が増え、入社後の体制をきちんとつくり上げることが企業にとっての採用ブランドにも繋がっています。
このように、多くの企業が求める人材獲得と定着は困難を極めています。それは企業が大事にしたい価値観を継承することを難しくさせ、ひいては企業の成長に大きな影響を与えることになります。
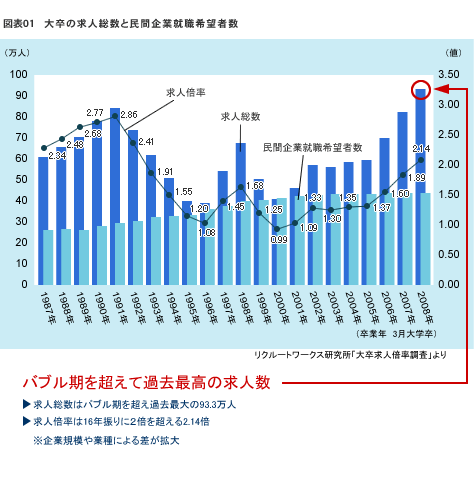
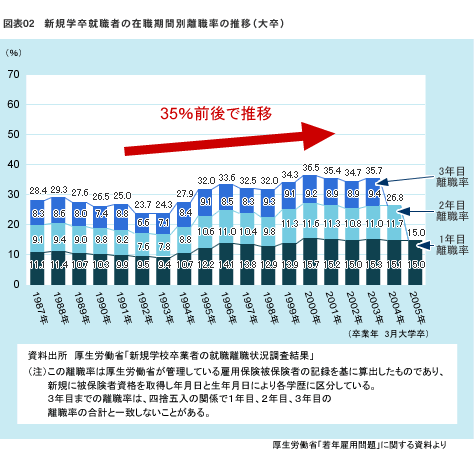
新人に対する早期戦力化のプレッシャー
こういった現状のなかで、「できる限り早く戦力化してほしい」ということが今の新人への期待です。以前は、5年程度で一人前になってほしいという時間のなかで、新人は新人にふさわしい仕事の役割を担い、一喜一憂しながら成功体験を積み重ねてじっくりと成長することができていました。しかし、今は3年で一人前、早い企業であれば1年で一人前になるという期待のもとに、失敗が許されない仕事をこなさなくてはならない状況にある新人が多く存在します。そのため、本人の資質や努力だけでは成果をなかなか上げられないという事態が起こっています。
新人育成の協力を引き出しにくい職場の状況
しかしながら、職場の協力体制は必ずしも十分ではありません。
「失われた10年」という言葉をよく耳にしますが、バブル崩壊以降、多くの企業が極端な成果主義にシフトし長期的な観点で人を育てることを怠り、さらには採用数を控えたため、そもそも人を育てる機会が減少してしまいました。そのため、現在のマネジャー層にあたる人はもちろんのこと、OJTリーダーに任命される20代後半から30代前半の若手・中堅社員のなかには、育成された経験も育成した経験もほとんど持たずに、自分1人で頑張ってきたと感じている人が多く存在します。
育てられた経験のほとんどない人が初めての人材育成を手探りで行うことは難しく、「なぜ今になって自分が新人を育成しなくてはならないのか」という声が出ることもあります。OJTリーダーに任命されるのは、多くが現場の中核を担っている業務負荷の高い人たちです。そんな彼らが手間のかかる割に成果が見えづらい人材育成に仕事の優先順位を上げて取り組むには、相当の覚悟と自分自身による意味づけが必要となるでしょう。
さらに、職場の環境も新人育成を困難にしているといえます。かつては、先輩社員は電話で顧客と話をし、手書きで企画書を作成していました。しかし、現在ではパソコンを使う頻度が高くなり、新人から見れば、先輩社員が何をして仕事の成果を上げているのかが分かりにくい状況にあるといえます。また、業務が細切れであることが多く、先輩と一緒に同じ仕事を担う機会も減っているため、先輩社員を手本にして真似しながら学ぶことも難しくなっています。
〈関連コラム〉
VUCA × Well-being 時代のニューノーマル
Z世代の新人・若手の育て方・生かし方
新人教育の主な手法(OJT・Off-JT・eラーニング)

新人教育には、さまざまな手法が活用され、それぞれの手法が持つ特性によって新入社員の成長を支援します。企業によっては、複数の手法を組み合わせて効果的な教育プログラムを構築しています。ここでは、代表的な3つの手法であるOJT(職場内研修)、Off-JT(職場外研修)、そしてeラーニングについて説明します。
OJT(職場内研修)
OJTとは、「On-the-Job Training」の略で、職場内で行われる実地研修を指します。新入社員が実際の業務を通じて、仕事の流れや必要なスキルを身につける手法です。OJTの特徴は、リアルタイムでのフィードバックが可能であることです。上司や先輩社員から直接指導を受けることで、新入社員は業務のポイントや注意点をその場で学び、即座に改善することができます。
また、OJTは業務の流れを理解するだけでなく、企業文化や職場の雰囲気を肌で感じることができるため、新入社員が職場に馴染むうえでも重要な役割を果たします。ただし、指導者の能力や研修の質が新入社員の成長に大きく影響するため、OJTを成功させるには計画的かつ体系的なプログラム設計が必要です。
Off-JT(職場外研修)
Off-JTは、職場外で行われる研修を指します。新入社員が通常の業務を離れて、研修施設やセミナーなどで集中的に学ぶ機会を提供する手法です。Off-JTの利点は、業務から離れて専門的な知識やスキルを習得できる点にあります。講師による体系的な講義やワークショップを通じて、新入社員は深い理解を得ることができ、業務に直接関連する知識だけでなく、広範なビジネススキルやコミュニケーション能力を向上させることが可能です。
また、他部署の社員や他社の新入社員と交流する機会もあるため、異なる視点や考え方を学ぶことができ、視野を広げる機会にもなります。ただし、Off-JTは業務から離れて行うため、学んだ内容を実務にどう適用するかを考えるフォローアップが重要です。
Off-JTにおけるeラーニングの活用
eラーニングは、インターネットを利用してオンラインで行われる学習方法です。近年、急速に普及している手法で、時間や場所にとらわれず、自分のペースで学習を進めることができる点が魅力です。eラーニングの特徴として、新入社員一人ひとりが個別に進捗を管理できるため、自己学習の習慣を身につけやすい点が挙げられます。
また、テキストや動画、クイズなど多彩なコンテンツが提供されるため、学習内容を視覚的に理解しやすくなっています。さらに、最新の情報や技術が反映された教材を用いることで、業務に直結する知識を効果的に習得できる点もメリットです。しかし、自己管理能力が求められるため、eラーニングを効果的に活用するには、新入社員のモチベーションを維持するための仕組みやサポートが重要です。
各社の取り組み状況と起こりがちな問題
ここで、何社かのOJTリーダー制度における取り組みについてご紹介したいと思います。
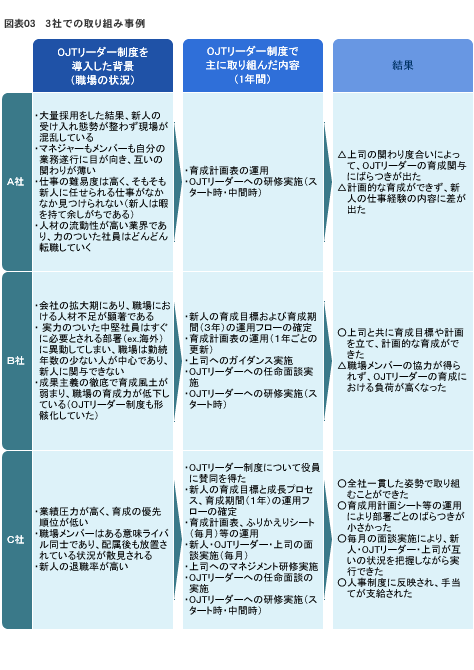
上記3社に共通した職場の問題は、上司、職場メンバーが新人を育てることに対して、優先度を上げることができていないということでした。こうした状況は多くの企業で起こりがちであり、OJTリーダー制度自体は以前から存在していても、現場が本気にならないために形骸化しているという問題があります。また、OJTリーダー制度で取り組んだ内容と結果を見ると、以下のような問題がOJTリーダー制度の実行を困難にしているといえます。
<企業で起こりがちな問題>
1.職場ごとにバラバラな育成をしている
- 会社としての育成目標・成長プロセスが不明確である
- 計画的な育成の仕組みがない
2.職場の育成に関するコミットが低い
- 上司の育成への意識が低い
- 職場メンバーの協力が得られない
- OJTリーダー自身がやらされ感で行っている
3.現場任せになっている
- 育成に対して、経営陣のコミットが得られていない
- 育成を評価対象に組み込むことができていない
- 職場で人を育成するという風土が失われている
OJTリーダー制度をうまく進める3つのポイント
前のセクションでOJTリーダー制度の際に企業で起こりがちな問題について紹介しました。ここでは、OJTリーダー制度をうまく機能させるポイントを解説します。
1.全社で一貫性のある育成を行う
そもそも新人育成は全社の取り組みとなります。そのため、各部署がバラバラな育成を行うのではなく、全社でどのように新人を育てていきたいのか、育成計画や育成方針が一致している必要があります。特に、新人の「育成目標」を明確にし、さらには職場の上司やOJTリーダーにとって目安となる「新人の成長プロセス」が明示されると、職場では取り組みやすくなります。
また、長丁場の取り組みでもあるため、具体的な実施計画やそれに伴う育成用計画シートも重要な役割を果たします。最初に実施計画を立てるだけでなく、節目でOJTリーダーや新人が振り返ることができる育成用計画シートが伴って初めて新人の成長度合いを確認でき、上司やOJTリーダーは計画的に育成を進めることができます。
2.職場ぐるみで育成を行う
OJTリーダー制度を運用すると、OJTリーダーに新人育成を任せっきりにしてしまう職場が多く見受けられます。しかし、上司には新人の育成責任があることはもちろん、OJTリーダーに任命される中堅社員の業務負荷も高いことや、新人と異なる業務を持っている場合もあります。そのため、あらためて上司の育成へのコミットを確認すると共に、上司からOJTリーダーに対して期待する役割をしっかりと伝えておくことがまず必要となります。さらには、上司が新人の育成目標や育成方針を職場メンバーと共有する機会を持ち、職場メンバーの協力を引き出すことも重要です。こうした土壌があって初めて、OJTリーダーは自分の役割を担う構えができ、主体的に取り組むことができます。
新人にとっても、意欲的に仕事に取り組むためには、まずその職場にいて安心できることが大切です。そう考えると、職場全体で新人育成をしていく場をつくることが大事であり、そういった職場を醸成していくための取り組みを上司やOJTリーダーが率先して行うことが期待されています。
3.OJTリーダーの実行を支援する体制を整える
会社(経営)が短期業績ばかりに目を向け、育成に関する優先順位が低いと、たとえ職場全体で新人育成を行っていこうとしても継続することは困難です。全社で推進していくという強い意志を経営陣が示すことで、現場は迷いなく前進することができます。そのためには、経営陣(特にトップ)を巻き込み、節目節目で考えを発信していただくことが大切です。また、人事制度にOJTリーダーの役割や報酬を盛り込むことや、人事評価に反映させていくことも有効です。最後に、現場で困った時に相談できる場が確保され、他のOJTリーダーたちと情報共有できる仕組みをつくっていく支援組織があることもOJTリーダーにとっては強い味方となります。
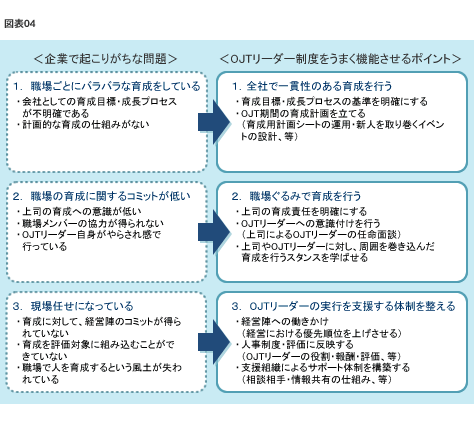
新人教育に力を入れるメリット
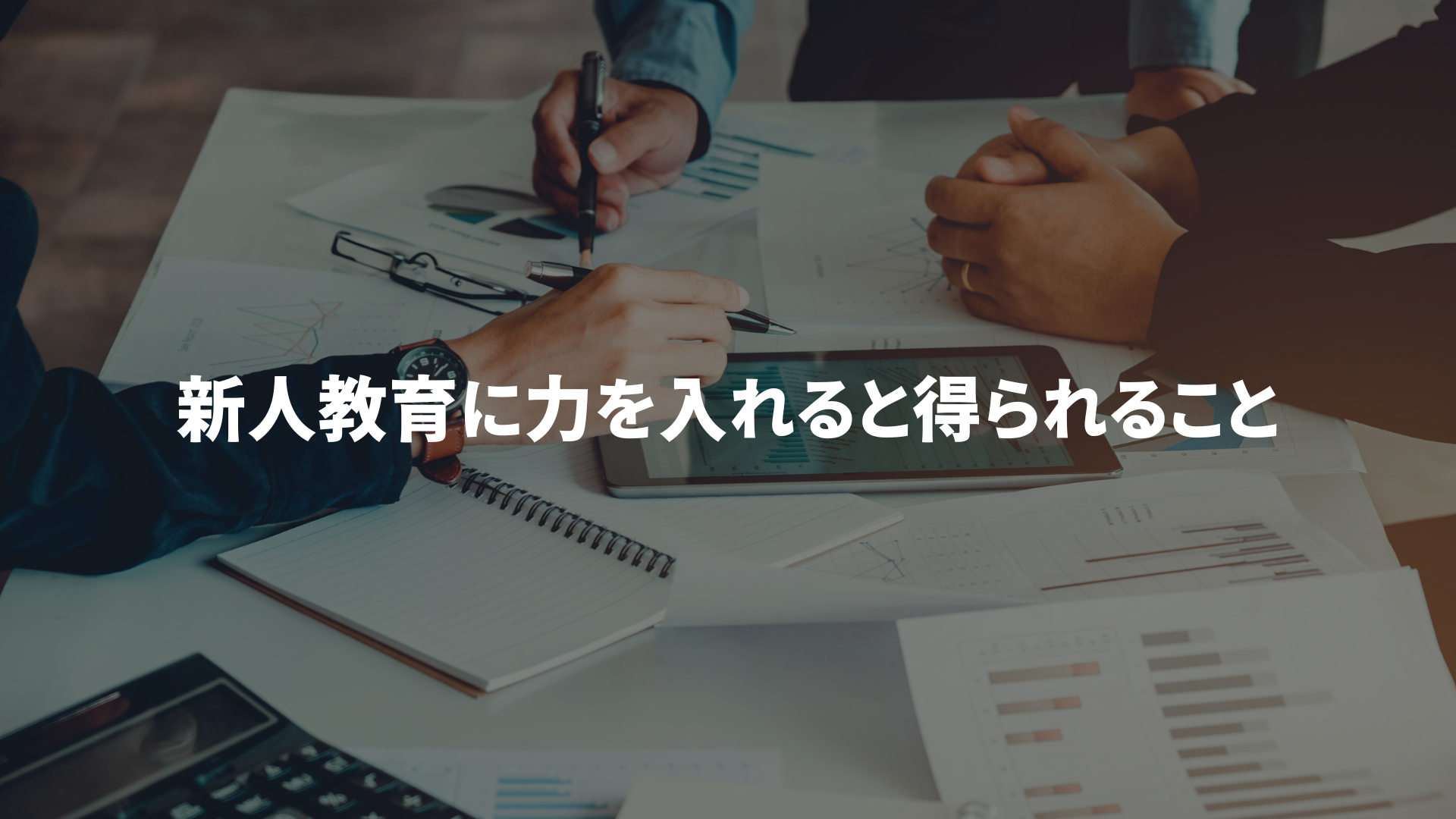
新人教育は企業にとって重要なプロセスであり、力を入れることにはさまざまなメリットがあります。適切な新人教育を行うことで、企業全体の生産性向上や離職率の低減、さらに教育担当者や新入社員自身の成長に繋がる効果があります。ここでは、新人教育に力を入れるメリットを4つの観点から詳しく説明します。
各個人の生産性が向上する
新人教育に力を入れると得られることの1つは、各個人の生産性が向上することです。新入社員が業務内容を理解し、必要なスキルを習得することで、業務を効率的に遂行できるようになります。特に、職場内研修(OJT)を通じて実際の業務を経験することで、業務に必要な知識や技術を身につけることができ、早い段階で即戦力となることが期待されます。また、新人教育を通じて、社員一人ひとりが自分の役割を明確に理解し、自信を持って業務に取り組むことができるようになるため、全体としての生産性向上にも寄与します。
離職率を減少させられる
新人教育は、離職率の低減にも大きな効果を発揮します。新入社員が早い段階で業務に慣れ、会社の文化や価値観を理解することで、職場に対する適応がスムーズになり、長期的に会社にとどまる意欲が高まります。特に、組織内でのサポート体制が充実していると、新入社員は困難な状況に直面しても安心して相談できる環境が整っていると感じるため、離職のリスクが減少します。さらに、新人教育を通じて、会社に対する信頼感や帰属意識が強化されることで、社員のエンゲージメントが向上し、結果的に離職率の低減に繋がります。
教育担当者が成長する
新人教育は、新入社員だけでなく、教育担当者にとっても大きな成長の機会となります。教育担当者は、新入社員に対して知識やスキルを教える過程で、自身の業務に対する理解を深め、コミュニケーション能力や指導力を向上させることができます。また、新入社員からの質問や意見を受けることで、新たな視点や考え方に触れ、自分自身の成長にも繋がります。教育担当者が積極的に指導に取り組むことで、職場全体の知識の共有やスキルアップが促進され、組織全体の成長にも貢献します。
新入社員のモチベーションが向上する
新人教育を通じて新入社員のモチベーションが向上することも、重要なメリットの1つです。新入社員が会社のビジョンや目標を理解し、自分の役割に対する意義を感じることで、仕事に対する意欲が高まります。特に、職場外研修(Off-JT)やe-ラーニングを通じて自己成長を実感できる環境が整っていると、新入社員は自分自身のスキルアップやキャリアの成長に対して前向きな姿勢を持ちやすくなります。また、上司や先輩からのサポートを受けながら学び続けることで、新入社員は自己効力感を高め、自信を持って業務に取り組むことができるようになります。結果として、新入社員が高いモチベーションを維持し、積極的に業務に取り組むことで、企業全体の活力も向上します。
新人教育でよくある失敗と改善策
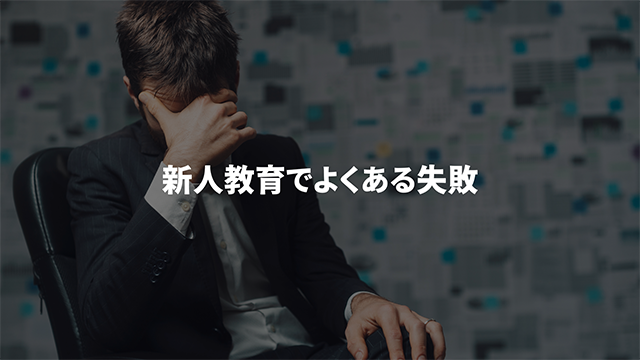
新人教育は企業の成長に欠かせない重要なプロセスですが、その実施においていくつかの共通する失敗があります。これらの失敗を回避するためには、事前の計画と継続的な改善が求められます。以下に、新人教育でよく見られる失敗について解説します。
各部署によって新人教育の内容や質がバラバラ
企業内の各部署で新人教育を行う際に、教育内容や質が統一されていないケースがよく見られます。これは、部署ごとに異なる教育方針や担当者のスキル差によるもので、新入社員にとって一貫性のない教育は混乱を招く原因となります。結果として、同じ企業内であっても部署ごとにスキルや知識の差が生じ、業務効率や協力体制に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした問題を防ぐためには、企業全体で統一した教育プログラムを設計し、各部署においても一定の基準を保つことが重要です。
教育担当者へのサポート不足
新人教育を担当する社員に対するサポートが不十分であることも、よくある失敗の1つです。教育担当者が新入社員の指導に専念できるように、十分なリソースや時間を提供することが必要ですが、これが欠けていると教育の質が低下するリスクがあります。また、教育担当者自身も成長し続けるための研修やフィードバックが欠かせません。担当者への適切なサポートがない場合、新入社員への教育が効果的に行われず、全体的な新人教育の成功率が低下することになります。
毎年同じ内容で教育を行う
新人教育の内容が毎年同じであることも、企業が陥りやすい失敗です。時代や業界の変化に伴い、求められるスキルや知識は絶えず進化していますが、これに対応しないまま過去の教育プログラムを繰り返すことで、時代遅れの教育となり、新入社員が実際の業務に対応できなくなる可能性があります。したがって、新人教育のプログラムは定期的に見直しを行い、最新のトレンドや技術に適応した内容にアップデートすることが求められます。
〈関連コラム〉
「新入社員8つの基本行動研修」リニューアル背景
Z世代の新入社員の早期育成に向けてどんな工夫をしたのか?
新人育成をきっかけとして職場の育成力を向上させる
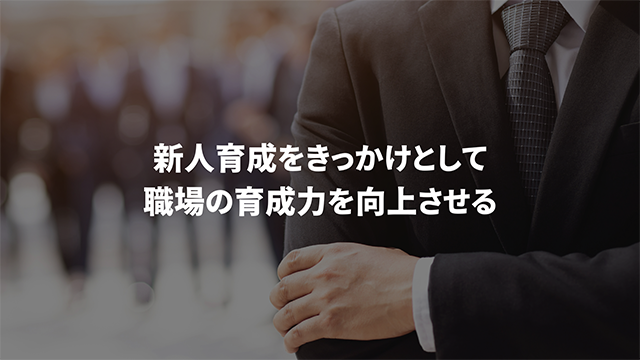
新人教育は単なる新入社員の教育にとどまらず、職場全体の育成力を向上させる絶好の機会でもあります。新人教育を通じて、企業は業務内容や文化の共有を行うだけでなく、教育担当者のスキルアップや教育体制の見直しを促進できます。これにより、全社員が共通の価値観や知識を持つことが可能となり、組織全体の一体感が強化されます。また、育成力の向上は、新入社員だけでなく既存社員にも良い影響を与え、業務の効率化や社員の定着率向上に繋がります。新人育成を成功させることは、長期的には企業全体の成長や競争力強化にも大きく寄与するものです。育成力を高めることは、企業の持続的な成長を支える基盤づくりであり、そのためには新人教育の質を向上させ、常に進化し続けることが重要です。
新入社員向けの研修をご検討の方は、新入社員研修特集ページをご覧ください。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




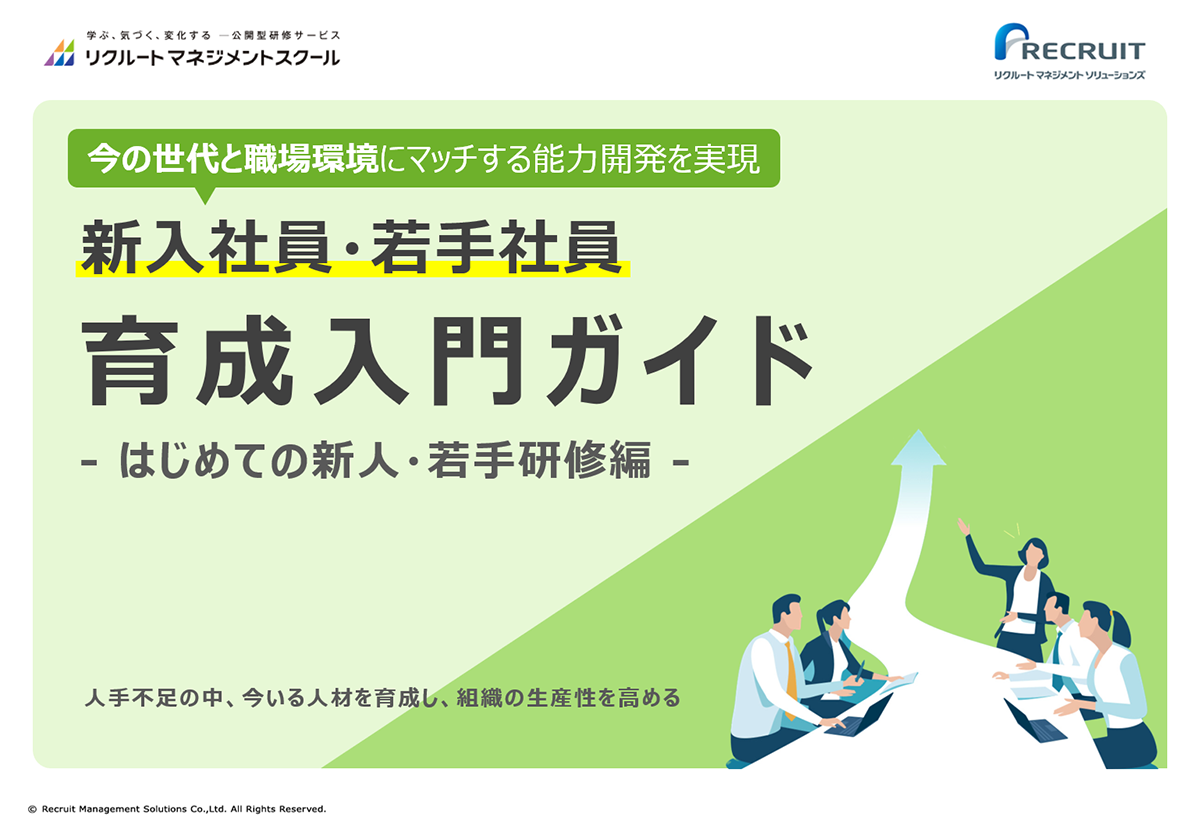









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で
メルマガ会員登録で