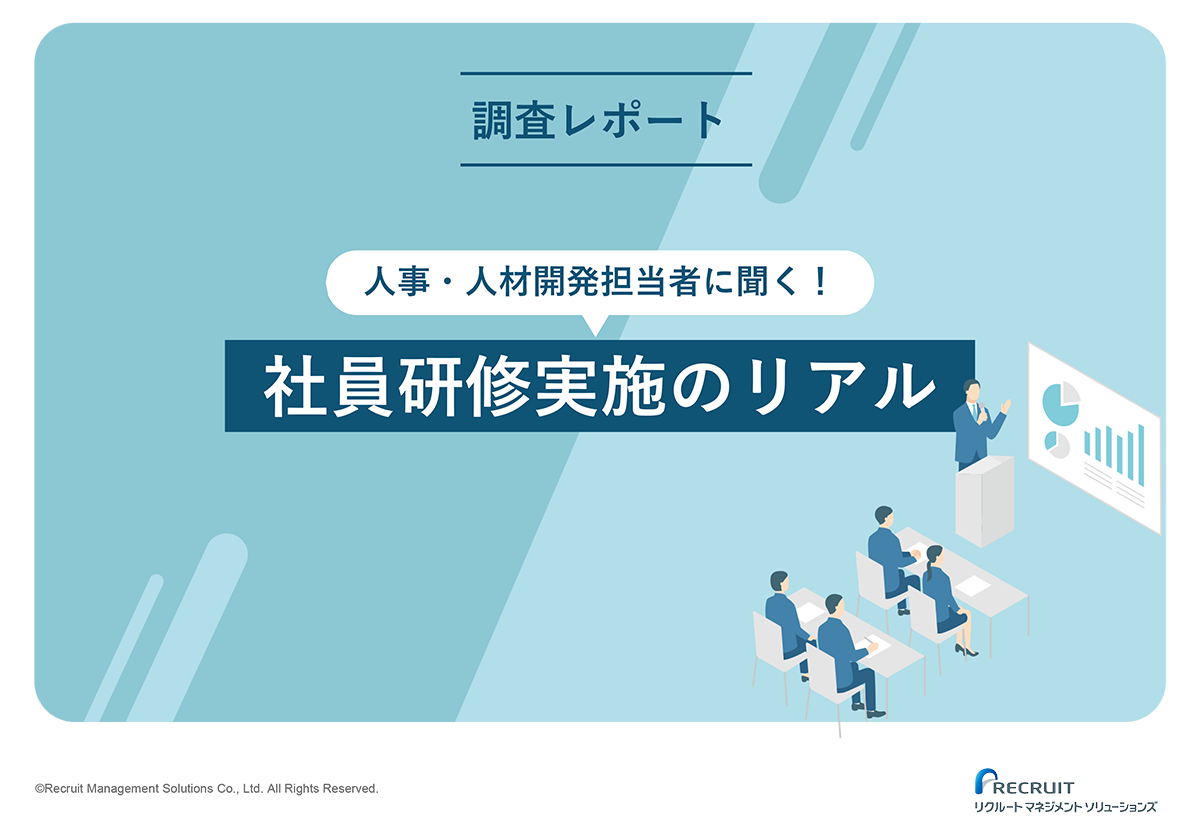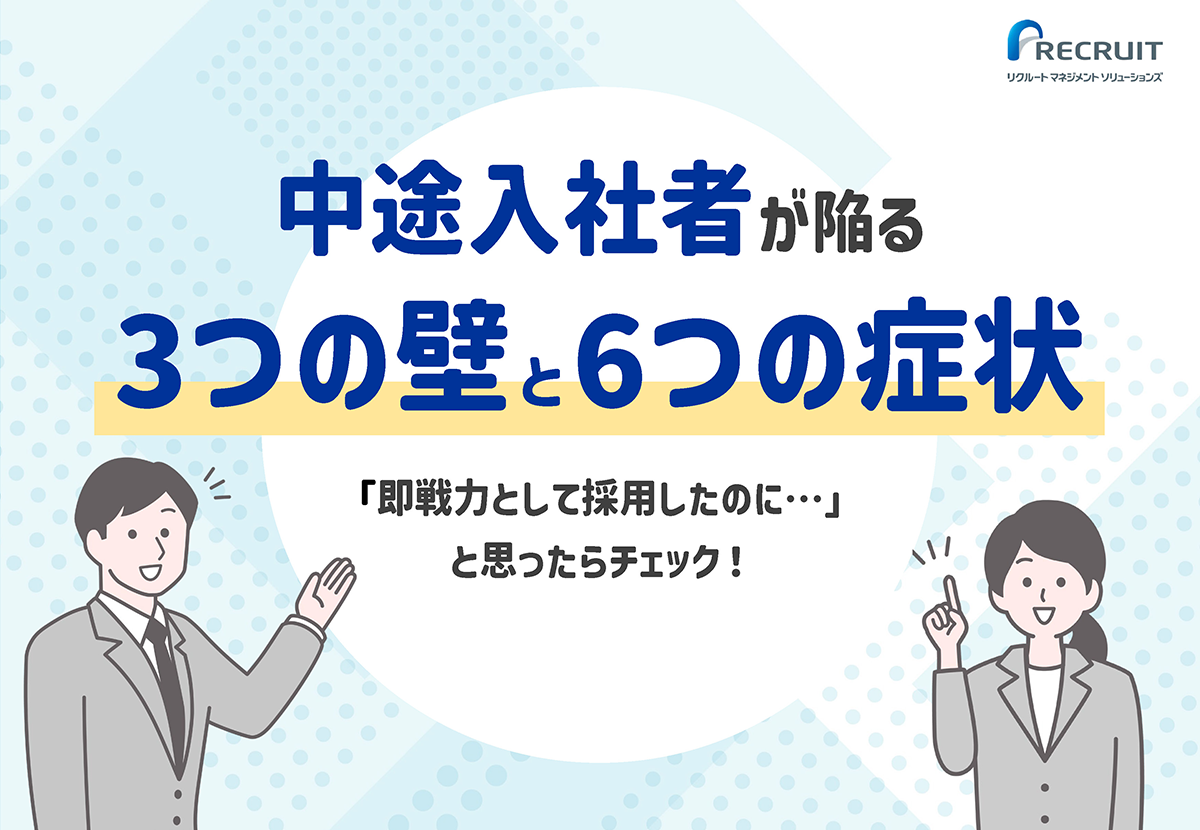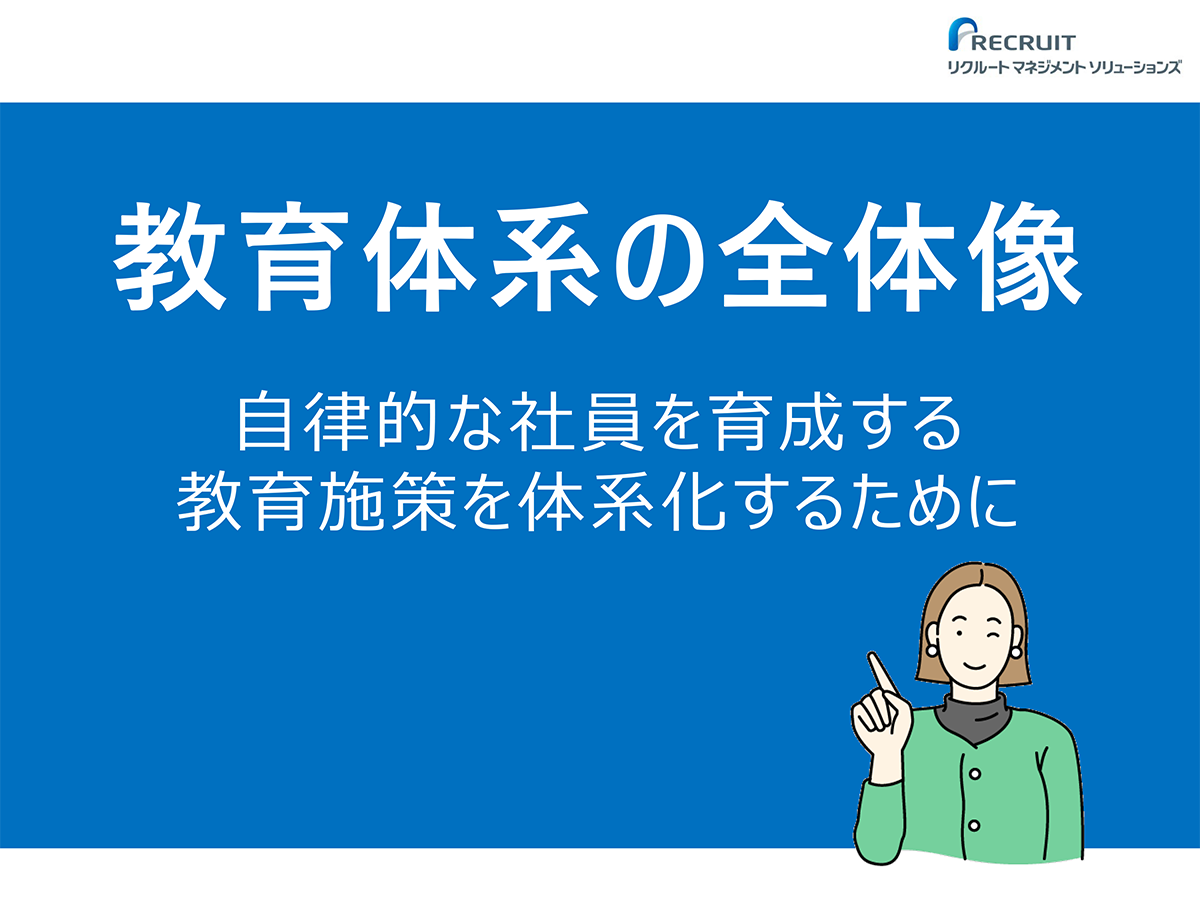連載・コラム
人的資本経営の実現に向けたエビデンス・ベースドHRM 第1回 座談会1
エビデンスを使いこなすには対話とストーリーが欠かせない
- 公開日:2023/06/26
- 更新日:2026/01/07

人事が取り組むべき新しいテーマとして、「人的資本経営の推進」、その実現に向けた「事実や根拠に基づいた人材マネジメント(エビデンス・ベースドHRM)」の重要性が高まっている。人材マネジメントに有効なエビデンスにはどのようなものがあるか、得られたエビデンスを経営や現場の課題解決に生かすとはどういうことか。3回にわたり、ご紹介していく。
第1回 経営視点から見たエビデンス・ベースドHRMの意義
エビデンスを使いこなすには対話とストーリーが欠かせない 座談会 旭化成・キリンホールディングス・富士通
第2回 ピープルアナリスト×HRBPの本音
人事データの戦略的蓄積がHRBPと事業現場の対話を生み出す 座談会 日本電気・LINE
第3回 人事の対話を豊かにするエビデンス・ベースドHRM
リクルートマネジメントソリューションズ HAT Lab所長 入江崇介
第1回では、3社の人事責任者にお集まりいただき、経営視点から見たエビデンス・ベースドHRMの意義について伺った。
座談会登壇者
● 旭化成株式会社 人事部 人財・組織開発室 室長 三橋 明弘 氏(写真右)
● キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 坪井 純子 氏(写真中央)
● 富士通株式会社 Employee Success本部 Engagement & Growth統括部 統括部長 佐竹 秀彦 氏(写真左)
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.70
特集1「エビデンス・ベースドHRM─対話する人事」より抜粋・一部修正したものです。
-----------------------------------------------------------------------------------------
◆『「人的資本開示義務化に関する実態調査」の分析結果』など人事お役立ち資料も無料配布中!
資料一覧はこちらから
-----------------------------------------------------------------------------------------
- 目次
- エビデンス・ベースドHRMへの取り組み
- 「手段のみの検証」から「目的に即した検証」へ
- 対話が乏しいとエンゲージメントも下がる
- 幅広い異動によって人材戦略が人材育成に
- データやエビデンスの価値を決するのは信念
エビデンス・ベースドHRMへの取り組み
――エビデンス・ベースドHRMは耳慣れない言葉かもしれません。エビデンス・ベースド・メディスン、つまり根拠に基づく医療という言葉があるように、HRMにも依拠すべきエビデンスが必要ではないか、という意味が込められています。最初に、この概念に対する基本的な考え、もしくは御社での実践例を教えてください。
坪井:キーとなるポイントを3つ考えています。まず1つ目は、最初にストーリーがあるということです。人材戦略と経営戦略は密接に結びつく必要があります。例えば将来の経営課題に対し、どんな人材がどの程度必要か。これらのストーリーを可視化、構造化する上で重要なのがエビデンスです。もう1つは、対話による戦略の進化です。昨今は投資家や従業員をはじめ、さまざまなステークホルダーから人材に関するデータの開示が求められます。それを積極的に実施し、対話を繰り返しながら、PDCAのサイクルを回していく必要があり、そこで共通言語となるのがエビデンスです。3つ目は、これは私がマーケティング出身であるがゆえの持論かもしれませんが、平均値では何も見えないということ。年代によるギャップも大きいですし、ダイバーシティを推進するなか、平均値は本当の意味のエビデンスにならないのではないでしょうか。
佐竹:現在、富士通ではまさにデータドリブン経営を推進しています。人的資本経営が叫ばれるなか、人事面でもデータの見える化や分析に鋭意取り組んでいるところです。
三橋:弊社でも人的資本の強みを可視化するために、データがますます重要になってきています。それから、先ほどの坪井さんの話にかぶせると、社員に向けてのストーリーも重要になっています。上からの押し付けではない、自律的キャリア形成を推進していくためには、人材育成のストーリーを変えなければならない。会社が「学んでください」と言ってもうまくいかない。人材育成にもマーケティングの知識が必須になってきています。
「手段のみの検証」から「目的に即した検証」へ

佐竹:弊社ではUdemyという社外のオンライン学習システムを導入し、国内8万人の社員のうち、手挙げ制で、2万5000人が学んでいます。これに対し、2つのデータドリブン施策が重要だと考えています。1つは経営層に対するもので、学習者と非学習者とで、エンゲージメントの値にどのような差があるのかを報告しています。一方の社員に対しては、学習者の方が非学習者よりも昇進が早い、といったデータを示しています。
坪井:経営と従業員がWIN-WINの関係でないと、持続性のある施策にはなりませんから、それは大切なことですね。私たちはイコールパートナーという言葉でそれを表現しています。
またすべての戦略・施策は価値創造につながらなければ意味がない。ある研修をやったとして、それが将来の価値創造にどうつながっていくのか。すぐには見えないけれど、見えるようにする努力を人事は積み重ねなければならない。
佐竹:それを「脱・手段のみの検証」とわれわれは呼んでいます。セミナーやイベントをやり、参加人数を数え、アンケートをとって終わりでは意味がないと。経営に対してどんなインパクトを生んだのか、「目的に即した検証」が必須なんです。
エンゲージメントの数字が前より上がったから万歳、ではなく、それが離職率の低下や生産性の向上につながり、顧客に対する提案力がアップし業績につながるというプロセスをデータで示せたら最高ですが、なかなか難しい。
三橋:われわれも研修の効果検証のため、受講者にはアンケートをとっていたんですが、彼らが学んだことを実務で活用し成果を上げているのかという点は未解明でしたので、そこを見るよう変えようとしています。例えば、組織開発に役立つように、対話のスキルを学ぶマネジャー向けの研修があります。受講者と非受講者合わせて2000名近くを対象に、研修後の職場メンバーとの対話の有無や有用性について調査したところ、受講者は非受講者に比べ、対話の実施率が高いことが検証できました。有用性に関しては両者で顕著な差は見られませんでしたが、それは、研修によって対話の有用性に対する受講者の期待値が高まったからではないか、と考察しています。
対話が乏しいとエンゲージメントも下がる
――対話というキーワードが出てきました。データを使うことで、対話の質はどのように変わりましたか。
坪井:弊社の社長は「エンゲージメントの値は経営の鏡」と言っており、10年ほど前からサーベイを行ってきました。エンゲージメントの全体値はもちろん、何と何の相関が高いのか、何が上がれば何が上がるのか、そういった分析を行いながら、部門ごとにブレークダウンし、組織ごとのリーダーがメンバーと対話するようにしています。
三橋:われわれは人材戦略の上で「終身成長」という言葉を使っています。若手だろうがシニアだろうが、全員それを目指すと。うちもエンゲージメントサーベイを行っており、その値を分かりやすく社員の“活力”という指標にしています。一方で、組織行動論の先生と一緒に、「成長につながる行動」を指標化し、社外にも公開しています。統計的に見ると、エンゲージメントと成長につながる行動との間には相当強い相関があることが分かっています。
活力は、先ほどの対話との相関も強い。メンバーとの対話がなかったグループと、対話を実施したグループとでは活力の値に有意な差がありました。
――対話の頻度を高める方がいいということでしょうか。
三橋:そのとおりです。ただし、とりあえず対話しておこうという意識をマネジャーがもつと、良くない。
坪井:対話の量と質ですね。キリンは、現在はまずは量を増やすことに注力している段階かもしれませんが、質も重要ですね。
佐竹:対話といえば、うちが力を入れているのが上司とメンバーとの1on1です。取り組みの当初、1on1を有益だと感じている程度とその人のエンゲージメントの値は、見事な相関関係にありました。そこで皆の背中を押すために、さまざまな施策を行った結果、実施率は上がったものの、エンゲージメントの値が上がらなくなってしまった。やれと言われてやる社員は増えたものの、それこそ質に問題があったのでしょう。
三橋:コロナ禍になり、うちでも、コミュニケーションがとりにくくなったこともあり、全社に1on1を入れようという議論があったのです。ただし、トライアルを実施し、分析したところ、マネジャーのやらされ感が強いまま導入してもうまくいかないことが分かり、全社一律での導入は見送りました。
幅広い異動によって人材戦略が人材育成に
――冒頭に坪井さんがおっしゃったように、人材戦略と経営戦略は密接な関係にあり、互いに連携しなければならない。その要として、エビデンスが機能するのではないかと。キリンの場合、両者の関係はどのようになっていますでしょうか。

坪井:キリングループはビールを祖業としていますが、40年前に医薬に参入しました。現在は食や医薬など既存事業の多様化・発展にとどまらず、ヘルスサイエンスへ事業を拡大し、グループ全体を大きく変革させようとしています。事業がトランスフォームするなかで、これまでにない能力が求められ、リスキリングも必要ですし、新しい人材を採用することも必要になる。つまり、足元での経営の実行力を高めるために、人材戦略も変革が必要だということです。またさらに、これだけ将来が見えない時代ですから、どんな人材がいれば将来の経営の選択肢を狭めずにいられるかという観点も重要です。将来への投資です。キリンではそのキーワードを専門性と多様性と置いています。終身雇用制が前提でなくなり、日本の労働市場は大きく変わってきています。だからこそ、外でも通用する専門性を磨く一方で、多様な視点や価値観を身につけてほしい。
キリンでは、お酒から医薬まで、事業が幅広いので、グループ内で多様な経験を積むことができる。例えば、ビール事業のエンジニアが医薬のエンジニアに異動するケースやその逆も含め、多々あります。つまり軸をもちながらキャリアが広がり成長できる。このように人材戦略が人材育成につながることを目指しています。
佐竹:今年からスタートした新しい中期経営計画では最初に2030年のありたい姿を描き、それからバックキャスティングで2025年の中期目標を立てるやり方をとりました。それに基づき、事業のあり方と人材戦略を考えたというわけです。これまでの人員計画は数ありきになりがちだったのを、例えば対クライアントサービスを伸ばそうと思った場合、ある資格をもった人材がどれくらい必要で、それを社内で調達するのか、異動させるのか、あるいは外から獲得するのかをきちんと計画立てて行っているところです。
三橋:われわれはGDP(Green、Digital、People)という3つの変革を中期的な経営課題に掲げています。Peopleでいうと、中途採用の活発化を図り、専門性を上げていくために高度専門職という制度を導入し、社内外で活躍できる人材の育成に注力しています。多様性はうちの武器でもあり、その多様性から生まれる共創力の強化も大きな課題になっています。
坪井:個々人の内なる多様性と、活発な異動によって生まれる組織としての多様性、その両方が良い意味で循環するのが重要だと思います。さらに、多様性の実現が価値創造につながらないと意味がありません。キャリアの採用率や女性採用率が高いことはもちろん大事ですが、そこで止まっては駄目なんです。時間はかかりますが、多様性がどんな価値やイノベーションを生むのかをステークホルダーにきちんと説明する必要があると思います。
佐竹:データドリブン経営がいいのは、まさにそこができるからだと思います。新しい施策や制度というものは、できたときは目的が明確なのに、時間が経ち、担当者が変わると、得てして形骸化してしまう。データドリブン経営は都度、目的をはっきりさせていきますから、仕事のレベルや生産性は必ずアップすると思います。
データやエビデンスの価値を決するのは信念
――この時代、あらゆる会社が変革を迫られており、既存の強みと新しく取り組む事業をどう融合していくのか、非常に難しい問題を各社が抱えていると認識しています。知の深化と知の探索という言葉で表される「両利きの経営」が1つの解だとは思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
坪井:基本は両利きだと思います。先ほどもお話ししたように、祖業はビールでしたが、40年前に医薬に進出しました。ビール会社がなぜ医薬に、とよく聞かれますが、ビールと医薬には発酵バイオ技術という共通項があるんです。まったく新しい事業に取り組んでいるというよりは、既存の強みをより発展させ、新しい価値を生み出し続けることを目指しているのです。
――そうしたなか、人材戦略のコアとして人間性の尊重を置いている。
坪井:キリンの醸造哲学に「生への畏敬」という言葉があります。ビールの発酵を担う酵母、そして原料である大麦やホップは生物であり、そうした生物の可能性を無限に引き出すことでおいしいビールを作っていくという考えです。生きとし生けるものをリスペクトする教え。まして人間も生物ですから無限の可能性をもっているはずで、それを引き出す環境を整えるのが会社の役割だという教えが、キリンのDNAのなかに含まれているのです。

三橋:弊社は創業100年を迎えました。社員を人的資本として捉えた場合、強みが3つあります。誠実性、多様性、風通しのいい風土、です。ただこれだけでは物足りない。最近経営陣が言っているのがA-Spirit、野心的な意欲や進取の気風といったものです。以前われわれは野武士集団と呼ばれていた時期もあり、その精神が薄れているのではないかという危機感があるんです。
佐竹:富士通も高度成長期、野武士集団と呼ばれていた時期がありました。それがバブル崩壊後、景気が低迷し、経営やコストの見える化が叫ばれ、社員の活力が弱まっていった。かつての元気を取り戻すため、いろいろな仕掛けを模索しなければならなくなったのが今だと思うんです。
――富士通という会社のパーパスを実現する経営ということですか。
佐竹:違うんです。社員一人ひとりのマイパーパスの実現を支援する経営なんです。IT企業からDX企業に変わろうと盛んに言っているのですが、それに合わせて各自のパーパスを明確にしようと。どんな目的をもって富士通で働きたいかをもう一度考えてもらう。その上で、マネジャーには、組織のビジョンと、各自のパーパスから由来するキャリアプランとがうまく重なり合うようなコミュニケーションをメンバーととってくれるよう、お願いしています。……エビデンス・ベースドの話から大分離れた気がしますが。
――いえ、つながっていると思います。社員や株主と、何をどう話すか。そのときにきちんとした根拠や証拠があると説得力やストーリーが生まれてくるという話が続いていると思っています。
三橋:パーパスの話もそこに落ち着くんですね。うちでも、50歳になった社員に、キャリア面談で旭化成に入った動機を尋ねることがあり、その上で、定年までの今後15年間、自分がやりたいことと会社が求めていることをどうバランスさせていくかを考えてもらう。これもパーパス経営の一形態ではないかと思いました。
佐竹:データやエビデンスの価値を最後に決するのは信念だと思うんです。業績とエンゲージメントの因果関係を証明するのは難しい。業績がいい会社にいればエンゲージメントが高いのは当然で、その値が高い社員がいるから業績が高まるかどうかはよく分からない。ただ、社員がやる気をもって仕事に熱中することがマイナスであるはずがない、という信念や信仰に近いものをトップがもってくれるかどうかは大きいと思います。
【text:荻野 進介 photo:伊藤 誠】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.70 特集1「エビデンス・ベースドHRM─対話する人事」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)