連載・コラム
1on1ミーティング・次の一手
1on1ミーティングを形骸化させないために「経験学習サイクル」を回そう
- 公開日:2021/07/05
- 更新日:2026/02/19

昨今、管理職と部下の1on1ミーティングを導入する企業が増えています。それにともない、「1on1ミーティングによって、上司・部下の関係性が良くなった」という声もよく耳にするようになりました。一方で、「1on1ミーティングが形骸化してきた」という新たな問題を抱える企業も出てきています。なぜ1on1ミーティングは形骸化してしまうのでしょうか。また、それを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
- 目次
- 1on1ミーティング導入半年後の悩みが増えている
- なぜ1on1ミーティングが形骸化するのか
- ポイントは「省察」と「概念化」
- 「何を振り返るか」を提示して、動画レベルの具体的な振り返りを促そう
- 心理的安全性をベースに「抽象化」を支援し、部下の持論を補強しよう
- 根底にあるスタンスは「強みや兆しへの着眼」
1on1ミーティング導入半年後の悩みが増えている
これまで1on1に関して、「1on1ミーティング導入時に陥りがちなポイントと会話例」と「テレワーク環境下における、1on1ミーティングの必要性とは」の2つのコラムを公開してきました。前者では1on1ミーティングの基本的な背景・目的・効果的な進め方について、後者ではテレワーク環境下での1on1ミーティングの必要性やポイントについて、詳しくご紹介しています。以上の2つのコラムと重複する点もありますが、本稿では、1on1ミーティングを形骸化させないためにはどうしたらよいかというテーマで、ポイントを詳しく解説していきます。
コロナ禍という状況の変化もあり、1on1ミーティングを導入する企業はますます増えています。ところが、1on1ミーティングを導入して半年が経つと、以下のようなお悩みを抱えることが多いようです。
<図表1>1on1ミーティングの導入後半年以降にお伺いする悩み
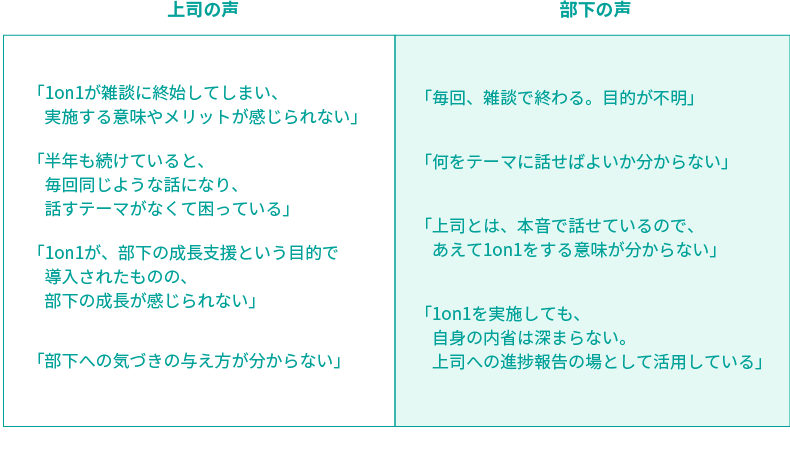
このような声が挙がっている企業では、簡単に言えば、1on1ミーティングのマンネリ化、「形骸化」が起こりつつあります。こうした状況で1on1ミーティングを続けても、十分な成果は得られません。
なぜ1on1ミーティングが形骸化するのか
なぜ1on1ミーティングの形骸化が起こるのでしょうか。理由を考える際に重要なのが、1on1ミーティングには5つのレベルが存在する、ということです。
<図表2>1on1ミーティングの5つのレベル
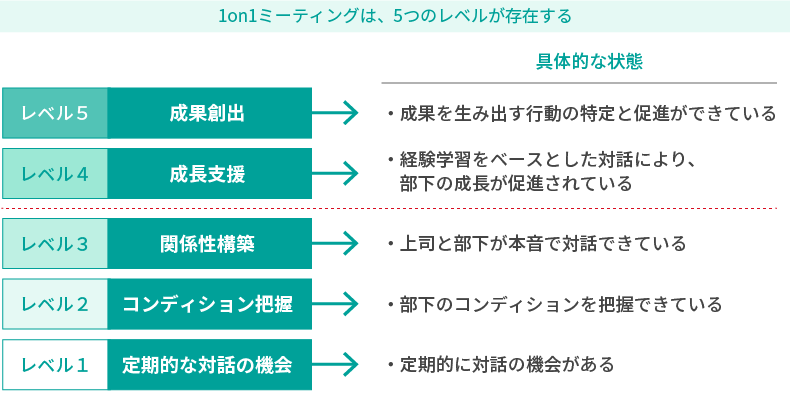
形骸化が起こっているのは、レベル3「関係性構築」にある企業です。このレベルでは、上司と部下が本音で対話できています。上司は、研修などを受けて1on1ミーティングの基本的な意義や手法を理解しており、部下の本音を上手に引き出せています。一見すると、悪くない状態です。
しかし、いったん本音で対話できると、図表1のお悩みにもあったとおり、継続的に対話する意味やメリットが次第に感じられなくなっていきます。そのため、レベル3にとどまったままだと、既存メンバーとの1on1ミーティングは、時間が経つにつれて形式的なものになっていくのです。最終的に、上司は、既存メンバーとの1on1ミーティングにあまり時間を割かなくなり、新メンバーとだけ関係性を築くことを目的とした1on1ミーティングをするようになってしまうでしょう。これが、1on1ミーティングが形骸化するメカニズムです。
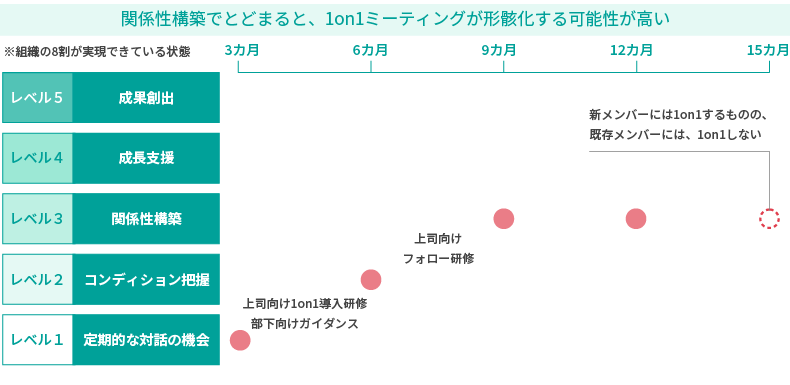
ポイントは「省察」と「概念化」
では、どうしたら形骸化を防げるのでしょうか。一言で言えば、「経験学習サイクル」を回して、レベル4「成長支援」やレベル5「成果創出」へと、1on1ミーティングのレベルを高めていけばよいのです。
<図表4>経験学習サイクル
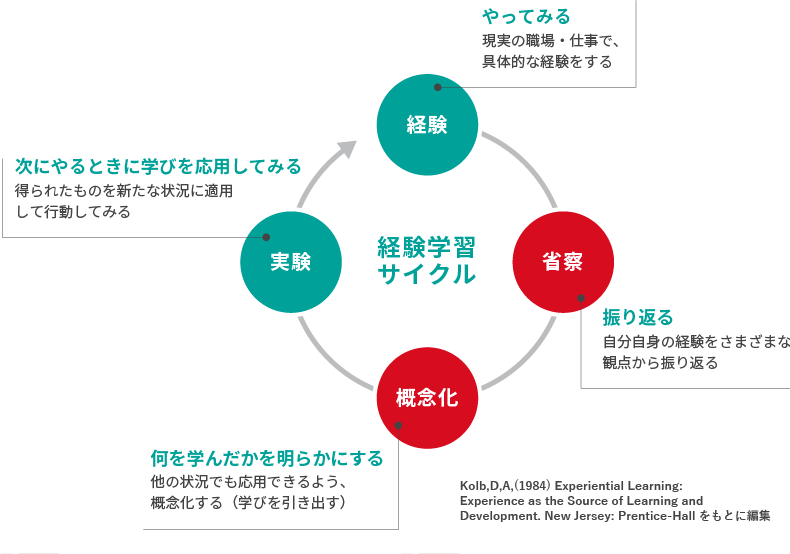
経験学習とは、自らの業務経験を振り返ることで学びを深める学習のことです。経験学習を最大化するには、「経験→省察→概念化→実験」の経験学習サイクルを回すのが最も効果的だと言いわれています。
1on1ミーティングにおける経験学習サイクルにおいては、特に「省察」と「概念化」がポイントになると考えています。日々の業務に追われながら、経験学習サイクルを部下が1人で回しつづけるのは容易ではありません。そこで、上司が1on1ミーティングの場で、部下の業務振り返りを促したり、何を学んだかを共に明らかにしていったりするのです。こうして省察や概念化をサポートすると、部下は学びを応用した「実験」をやりやすくなります。それが、部下の成長支援・成果創出につながっていくのです。経験学習サイクルは、回せば回すほど効果が高まります。部下の振り返りを促し、共に概念化を進めることができれば、効果的な1on1ミーティングとなるでしょう。
ただし、経験学習サイクルを回す関わり方は、上司にとっても決して簡単なことではありません。特に、上司が投げかける問いの質が部下の経験学習の質を決めるため、上司は問いの作り方をよく知っておく必要があります。
「何を振り返るか」を提示して、動画レベルの具体的な振り返りを促そう
「省察」とは、自分自身の経験を多様な観点から振り返ることです。省察には、自身の成功要因を知って再現性を高めたり、同じ過ちや失敗を繰り返さないようにしたりする効果があります。つまり、部下が振り返りの習慣をつけると、成功を増やすと同時に、失敗を繰り返さないようになっていくのです。
上司が1on1ミーティングで部下の省察を促す際には、「何を振り返るか」と「どのくらい振り返るか」を示すことが大切です。なぜなら、第一に、部下はどこに着眼して、何を振り返ればよいかが分からないケースが多いからです。第二に、どのくらい内省すればよいかを分かっていないケースがほとんどです。省察には2つの壁があるのです。
<図表5>省察の2つの壁
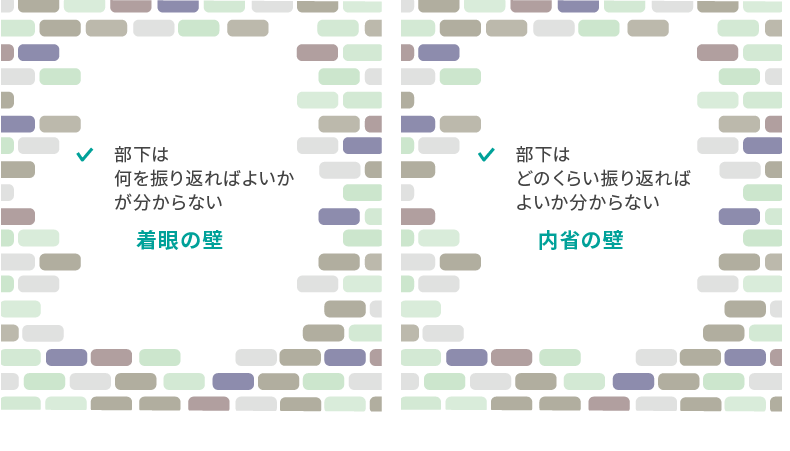
「何を振り返るか」という着眼の壁に対して、最も有効な方法の1つは、何に照らして振り返るかを事前に設定することです。期初の目標設定面談やキャリア面談などで、「今期は○○の能力を高めていきましょう」もしくは「今期は、△△を能力開発のテーマに置きましょう」といった形で、振り返りの軸を事前に設定しておくのです。そのうえで、期中の1on1ミーティングで、事前に設定した軸に沿って振り返りの対話をしていくと、次第に、部下は自分でも何を振り返ればよいかが見えるようになっていくでしょう。
もう一つの有効な方法は、うまくいったことや成功事例に焦点を当てることです。例えば、プロジェクトが成功したときには、「なぜうまくいったと思いますか?」と質問するのです。人は、失敗したことに焦点を当て、反省という名の振り返りをよくする傾向にあります。一方、うまくいったことは自分にとっては当たり前のことを当たり前にしたまでなので、あえて振り返らないことが多いのです。上司のサポートによって成功要因が明確になれば、部下は成功確率を高められるでしょう。また、成功事例をめぐる対話が、さらに良い方法を思いつくヒントになる可能性もあります。
次は、内省の壁の乗り越え方です。内省の壁を越えるには、上司が部下の話を動画としてイメージできるほど具体的に振り返ることが必要です。営業事例なら、自分やお客様がどのような言葉を使ったのか、自分の言葉に対して、お客様の表情はどうだったのか、といったことを細かくヒアリングするのです。イメージが豊かになるほど、部下の振り返りと内省の質が高まっていくはずです。
リモートワークでは、上司が部下の仕事ぶりを間近で見ることができません。業務プロセスをできるだけ具体的に振り返ってもらうことは、リモートワーク下での部下の仕事ぶりを知るうえでも大切なことです。
心理的安全性をベースに「抽象化」を支援し、部下の持論を補強しよう
省察が終わったら、次は「概念化」です。概念化とは、省察を踏まえて、自分が経験から得た学びを言葉にすること、何を学んだかを明らかにすることです。言い換えれば、持論を考えることです。そのため、概念化は持論化と捉えることもできます。概念化がうまくいけば、他の状況でも自分なりに応用できるようになります。それだけではなく、ナレッジとしてチームや組織に共有することも可能になります。
上司が1on1ミーティングで部下の概念化をサポートする際のポイントは、「心理的安全性を確保すること」「抽象化を支援すること」「補強する理論を提示すること」の3点です。これらがポイントとなる理由としては、第一に、部下1人では持論をなかなか言語化できないからです。第二に、裏づけとなる理論がない限り、そう簡単には持論に自信を持てないからです。概念化には、「言語化の壁」と「自信の壁」の2つがあるのです。
<図表6>概念化の2つの壁
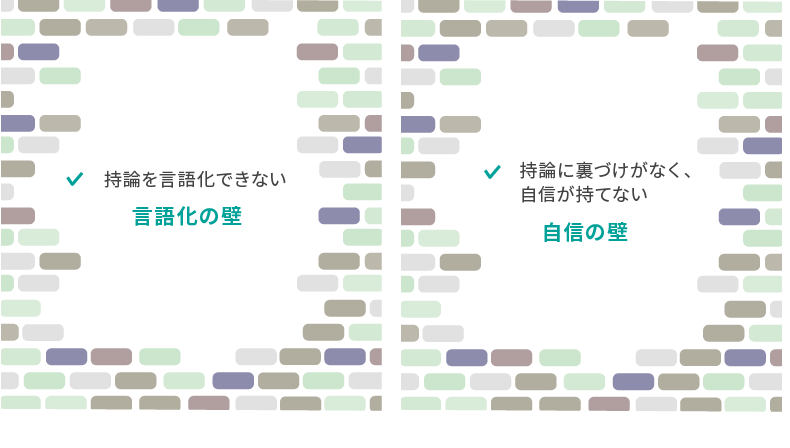
概念化は、1on1ミーティングのレベル3「関係性構築」をある程度満たしてから行いましょう。なぜなら概念化には、部下の「心理的安全性」が不可欠だからです。部下の持論は、上司の流儀とは反するものもあるかもしれません。また、部下が的を射ていない持論を持ち出す可能性も十分にあります。部下が上司にそうしたことを話すのは勇気が要ることです。部下が何でも安心して話せる関係性がなければ、上司は概念化をサポートできないのです。上司の方は、たとえ部下の考え方が自分と違ったとしても受け入れるだけの度量を持つ必要があります。要点を押さえられていない発言をしたときにも、頭ごなしに否定するのではなく、まずは部下の発言を許容したうえで、対話を重ねていく姿勢が大切です。
心理的安全性が確保できたら、部下の経験の抽象化を支援していきましょう。成功事例の核心的な要因を明確にして、抽象的な言葉に昇華させていくのです。「この経験で学んだことの核心は何ですか?」という問いや、「この成功事例で特に大切だと感じたことは何ですか?」という問いを活用して、具体から抽象への移行を意識しましょう。
抽象化が終わったら、次は、部下の持論を補強する理論を提示することを目指しましょう。世のなかには、経営学や心理学などの学問分野に、科学的研究によって検証された理論が数多くあります。また、それとは別に、業界セオリー・ビジネス定石・格言などもいろいろとあります。上司がこうしたことを率先して学びながら、部下の持論を補強していくのです。そうすることで、部下は持論に自信を持てるようになるでしょう。また、持論の再解釈などもできるようになる可能性があります。つまり、概念化のサポートにあたっては、上司は理論・定石・格言などを幅広く勉強しておく必要があるのです。
なお、持論は、状況や時代によって変化すべきものです。実際、昭和の持論が令和に役立つかといえば、怪しいものが多いはずです。持論は定期的に見直した方がよいのです。持論を見直す際には、既存の目的や前提そのものを疑って、それらも含めた軌道修正を行う「ダブル・ループ学習」が効果的です。部下の持論が古くなったと感じたら、上司は部下の持論そのものを疑って、持論を改変したり、新たな持論を生み出したりする方向に持っていく必要があります。
根底にあるスタンスは「強みや兆しへの着眼」
まとめると、省察・概念化のポイントは以下のようになります。
<図表7>省察・概念化のポイント
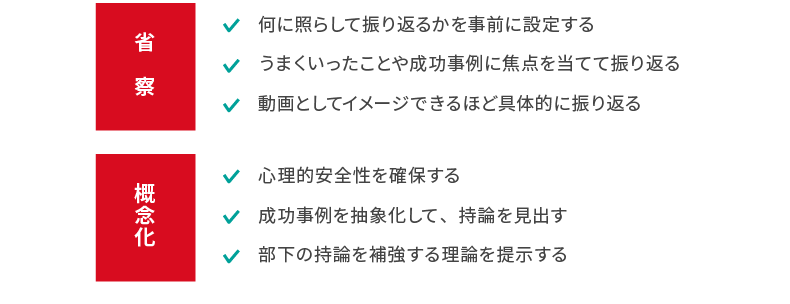
最後に、経験学習サイクルを回して、1on1ミーティングをレベル4「成長支援」やレベル5「成果創出」に高めていくうえで、最も重要なスタンスをお伝えします。それは、弱みや課題への着眼ではなく、「強みや兆しへの着眼」に重心を置くことです。いつも部下の強みや変化の兆しに着眼するスタンスを根底に持つことが、部下の成長を後押しし、部下の成果を高めることにつながっていくのです。
経験学習サイクルを回すための1on1ミーティングについて、こちらの無料オンラインセミナーでもお伝えしています。セミナーでは1on1ミーティングの実例もご紹介していますのでぜひお気軽にご参加ください。
関連する無料セミナー
■無料オンラインセミナー
今話題の1on1ミーティングはどのように導入され活用されているのか
また、1on1ミーティングのありがちな例と、改善パターンを記載したトーク例をご用意しています 。
(ダウンロードにはメルマガ会員無料登録が必要です)
1on1ミーティングの効果的な実施に向けて、少しでもお役に立てれば幸いです。
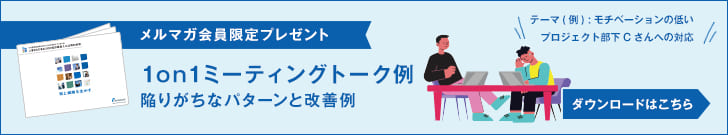
リクルートマネジメントソリューションズでは、1on1ミーティングを導入される企業様に向けて導入サポートやコーチングワークショップなどのサービスもご提供しています。
下記よりお問い合わせください。
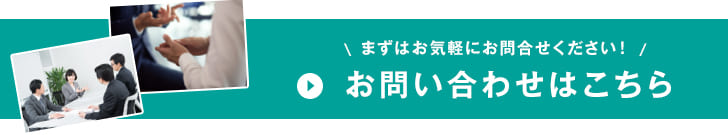
関連するサービス
■ 管理職向け1on1スキル研修
執筆者

サービス統括部
HRDサービス共創部
パーソナルディベロップメントグループ
シニアソリューションアーキテクト
星野 翔次
ベンチャー企業・商社勤務を経て、2013年に現在の株式会社リクルートに入社。 管理職として、部下がパフォーマンスを最大限発揮できるコミュニケーションを追求。 最近では、コーチングサービスを提供する部門にて、部長職の育成やコミュニケーション変革に携わっている。民間企業や官公庁、教育機関等、延べ300組織を支援。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)













