導入事例
ありたい姿を目指して、ジョブ型とメンバーシップ型の中間型人材マネジメントシステム「ジョブグループ」を導入
農林中央金庫

- 公開日:2024/10/21
- 更新日:2024/10/21
事例概要
背景・課題
2019年頃から、創立100周年の節目となる2023年に向けて、人材マネジメントを大きく見直す動きが始まりました。より柔軟かつスピーディーにミッションを遂行できる集団に変わることが欠かせなかったからです。目玉となった施策は、ジョブ型とメンバーシップ型の中間型の人材マネジメントシステム「ジョブグループ」の新規導入でした。これまでゼネラリスト志向で、メンバーシップ型の人事制度だった私たちが、一足飛びにジョブ型の人事制度に移行し、実効性を担保するのは難しいため、このシステムは現在の私たちに最適だと考えたのです。
検討プロセス・実行施策
人材マネジメント改正のポイントは、「専門性」「自律性」の2つのコンセプトを定めたことです。最初は「ジョブ型」を検討していましたが、導入がより容易で、専門性・自律性を高める効果もあるジョブグループの存在を知り、導入を決断しました。現場の協力を得ながらグループを設定し、グループ単位で専門性を言語化したうえで、グループジョブディスクリプションを作成しました。職員は、これらのグループジョブディスクリプションに基づいて、専門性を醸成していくこととなります。
成果・今後の取り組み
職員が自分の専門性やキャリアパスを再考する機会は確実に増えています。しかし結局は、ジョブグループが組織の成長につながることが肝要です。そのため専門性を定義し、可視化することで、よりデータドリブンな運用を図りながら、マネジャーたちがジョブグループを最大限に活用し、適正な評価や人材育成につなげるための支援を続けます。
背景・課題
人材マネジメント改正の一環として、「ジョブグループ」の導入を決断

五十嵐:私たち農林中央金庫は、JAバンク・JFマリンバンク・JForestグループの全国機関として農林水産業をしっかりと支えていくと同時に、国内有数の機関投資家としてグローバルな投資活動による安定収益の確保に努めています。1923年(大正12年)に設立された組織で、2023年に創立100周年を迎えました。
2019年頃から、この100周年を機に人材マネジメントを大きく見直す動きが始まりました。私たちは今、さらなる成長・発展に向けて、ビジネスの多角化・多様化に取り組んでいます。理事長を筆頭に経営層は、ビジネスの多角化・多様化を成功させるためには、組織をよりフラットに変革し、必要に応じてプロジェクトを組みながら、より柔軟かつスピーディーにミッションを遂行できる集団に変わることが欠かせない、という強い想いを抱いていました。そのためには、新たな人材マネジメント手法を取り入れる必要があったのです。
そこで、経営層と私たち人事部は、2020~2022年に全体コンセプトを検討し、どのような人材マネジメントのシステム・制度を導入するかを決めました。その後、2022年のトライアルを経て、2023~2024年に新システム・新制度を段階的に導入し、人材マネジメント改正を行いました。リクルートマネジメントソリューションズには、2020年から人材マネジメントに関するアドバイスコンサルティングをお願いして、2024年の新システム・新制度の導入まで一貫して伴走してもらいました。
今回の人材マネジメント改正では、キャリア・等級・評価・報酬・働き方改革・シニア・年金と全方位で変革を進めましたが、最も大きな目玉は、ジョブ型とメンバーシップ型の中間型の人材マネジメントシステム「ジョブグループ」の新規導入でした。リクルートマネジメントソリューションズの提案のもと、経営層と熟議したうえで導入を決断しました。これまでゼネラリスト志向で、メンバーシップ型の人事制度だった私たちが、一足飛びにジョブ型の人事制度に移行し、実効性を担保するのは難しいため、このシステムは現在の私たちに最適だと考えたのです。
検討プロセス・実行施策
自律的に専門性を醸成し、キャリア形成できるよう、職員一人ひとりがジョブグループを自ら選ぶ仕組みに

𠮷羽:議論をスタートした頃は、人材マネジメント改正の具体的な形が見えていませんでした。そこで私たちは、リクルートマネジメントソリューションズのコンサルタントと共に理事長インタビューを行ったうえで、経営会議で経営層と対話を重ねて、最初に「ありたい姿」を言語化しました。次に、ビジネスと組織の「現状」を再確認しました。
そして、現状からありたい姿に近づくために「現時点で最適な人材マネジメントとは何か」を、地に足をつけて議論したのです。その結果、2021年には、ジョブグループも含めて人材マネジメント改正の大枠が見えてきました。
五十嵐:特にポイントだったのが、「専門性」「自律性」の2つのコンセプトを定めたことです。今回の人材マネジメント改正によって、職員一人ひとりが自律的に専門性を醸成しキャリア形成できる場をつくり、農林中央金庫内外で活躍できる人材を形成していくこと。また、職員の専門性と自律性を高めるために、各種制度構築や育成・リスキリング支援(学び直し支援)を実施すること。この方針を決めたことで、すべてが具体的になっていきました。
人材マネジメントのあり方について、最初は専門性と自律性を高める効果のある「ジョブ型」の導入を検討していました。しかし、私たちは長らくメンバーシップ型を続けてきた会社ですから、いきなりジョブ型を導入しても十分に機能しない可能性があります。そのときリクルートマネジメントソリューションズのコンサルタントから、ジョブ型とメンバーシップ型の中間に「ジョブグループ」という新しい人材マネジメントシステムがあると教えてもらいました。私たちは、これなら導入がジョブ型より容易で、専門性・自律性を高める効果もあると考え、経営層の同意を得て導入を決めました。
𠮷羽:ジョブグループとは、例えば私たちの場合なら、投資ビジネスを担い、中長期的に安定した収益の確保を目指す「GIグループ」、食農ビジネスを担い、ステークホルダーの価値創造と金庫・系統収益の向上を目指す「食農グループ」、リスク管理を担い、適切なリスクテイクや業務運営を促す「リスク管理グループ」など、業務を通じてどのような価値を提供するかといった観点でジョブグループをいくつか設定し、さらにそのグループごとに機能別・グレード別に必要な専門性をグループジョブディスクリプションとして定義した人材マネジメントシステムです。私たちは、職員が入庫後、さまざまな経験を積みながら、どのジョブグループに登録するかを考え、若手から中堅となるタイミングでジョブグループを自ら選んで登録する仕組みにしました。それ以降は、一人ひとりがさまざまなプロジェクトや業務に携わりながら、登録したジョブグループ内で専門性を自律的に磨いていくのです。
現場の協力を得て、議論を重ねながらグループジョブディスクリプションを作成

久野:ジョブグループごとに、さらに機能別・グレード別に専門性を言語化し、グループジョブディスクリプションを作成していく際には、現場の協力が欠かせません。ジョブグループの導入を決めてから、私たちは経営層だけでなく、各本部・ユニットの部長らとも議論を重ね、グループジョブディスクリプションの内容を徐々に固めていきました。
グループジョブディスクリプションの定義が難しいのは、どの現場にも、言語化されていない業務・スキル・知識がいくつもあるからです。また、一つひとつの業務やスキルがどのくらいのレベルの高さなのか、専門性をどこで区切るのか、といったことも明確でなく、人によって意見が異なることがよくあります。そこで私たちは、各現場と話し合いながら、それぞれの業務・スキル・知識の言語化を進めていきました。これは職員が専門性やキャリアを考えるうえで間違いなくプラスになっています。
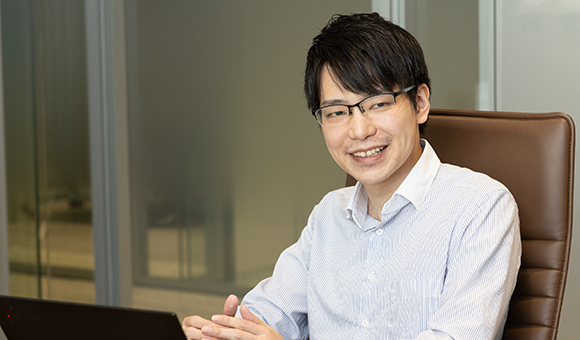
村澤:付け加えると、ジョブグループはそれだけでは十分に機能しません。特に重要なのが、若手から中堅にステップアップしていく職員がジョブグループを主体的に選ぶサポートをすることです。そこで私たちは、今回の人材マネジメント改正で「インターン制度」「職務・ポスト公募制度」「コースチャレンジプログラム」を新たに導入しました。
「インターン制度」は、入庫から数年後の若手職員が、各グループの業務を数週間経験できる制度です。また「職務・ポスト公募制度」は、若手職員に限らず、職員が次に従事する職務・ポストを自ら選択できる制度です。そして、「コースチャレンジプログラム」は、コースと呼ばれる職種を変更し、キャリアの幅を広げていくための制度です。若手職員に社内にどのような仕事があり、自分がどのように活躍できるのかをより深く知ってもらうと共に、すべての職員が自律的なキャリア形成を行っていくためには、こうした支援も大切です。
成果・今後の取り組み
ジョブグループが組織の成長につながる運用をしていきたい

五十嵐:今回の人材マネジメント改正の大半は2023年から適用を開始しましたが、ジョブグループは2024年度から開始しました。導入前の準備や周知などに多くの時間が必要だったからです。今はまだジョブグループを導入したばかりなので、具体的な成果が分かる段階ではありません(※取材時は2024年7月)。
久野:ジョブグループに対する社内の反応はさまざまで、「専門性を磨けて嬉しい」「キャリア形成について考えるきっかけになった」といったポジティブな声がありました。一方で、「“自律性”を押し出すと、好きな業務を自由に選べると極端な解釈がなされないか」「ジョブグループで“プロ”を重視しすぎるあまり、他グループへの理解の希薄化や、事業ごとの横連携の不足につながらないか」といった不安の声も届いています。私たちは研修機会などを定期的に設けて、ジョブグループの真意を粘り強く伝え、職員のみなさんの不安をできる限り払拭していく努力が肝要だと考えています。
𠮷羽:ジョブグループについて、単に本部・ユニットで区分するのではなく、業務を通じてどのような価値を提供するかといった観点で設定している点はポイントの1つです。例えば、「リスク管理グループ」には、本店のリスク管理部署における業務だけでなく、リテールビジネスや投資ビジネスといった別のビジネスにかかる関連業務も含まれます。これは、リスク管理を担い、適切なリスクテイクや業務運営を促すという価値の提供を担っているのは、本店のリスク管理部署だけではないからです。
ジョブグループを導入したことで、今後はさまざまなビジネスの経験を積みながらも、「リスク管理」にかかる専門性を磨いていくといった明確な意識を持ちながらキャリアパスを歩めるようになりました。他のグループでも同様のことが起こっており、職員が自分の専門性やキャリアパスを再考する機会は確実に増えています。
久野:組織視点でいえば、ジョブグループという新しい仕組みを導入したことは、採用にも有利に働くはずです。また、ジョブグループの考え方は、「この部署の、この専門性しか磨かない」といった極端な専門性やジョブ型の捉え方を抑制し、組織の「タコつぼ化リスクの軽減」にも役立つと考えています。
村澤:私たちは、人材マネジメント改正に合わせて人事システムも刷新し、人事データの活用にも力を入れています。人材マネジメントと事業戦略が紐づき、組織の成長につながることが何よりも大切であり、今回専門性を定義し、可視化したことで、よりデータドリブンな運用を図っていくことができると考えています。
五十嵐:各ジョブグループの担当者たちは、すでに「担当グループを人気のジョブグループにしたい」という想いを抱いています。彼らやマネジャーたちがジョブグループの仕組みを最大限に活用し、よりよい評価や人材育成につなげていけるようになれば、ジョブグループは自然と事業に寄与し、定着していくはずです。私たちは、そのためのサポートを惜しまずに続けていきます。
コンサルタントの声

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
コンサルタント
森本伊織
農林中央金庫様でのジョブグループ導入のポイントは 、経営層・人事部との十分なすり合わせと現場の協力があり、一体となって変革を進められたことです。
長い時間をかけて制度改定を検討するなかで、各事業領域の所管役員の方々からさまざまな意見が出ました。多様な視点での懸念点を洗い出したうえで総合的に物事を考え、現実的な選択をしながら丁寧に積み重ねていく議論に、新たなことへ挑戦しながらも着実に形にしていく緻密な企業風土を感じ、我々も経営の考えを人事と共有したうえで設計に取り組めました。
加えて、各現場の出身者として現場をよく知る人事の方が多く、今回の制度改定によって現場がどう感じるのかを考え、現場視点を持って定期的にヒアリングの機会や説明会を設けたり、フォローを行ったりしたこともポイントです。現場との丁寧なコミュニケーションが、新たな仕組みの導入を後押しする制度設計につながっていると考えます。
さらに農林中央金庫様には、よい変化を捉えるだけでなく、現場から上がる不安の声も受け止めて、積極的にフォロー施策を行う姿勢も見られました。
今後も運用面でのご相談にお応えし、また制度改定が必要になった際にはよいものを創り上げるパートナーとして支援できるよう、精進してまいります。
取材日:2024/07/22
企業紹介

農林中央金庫
農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を基盤とする全国金融機関として、JA(農協)、JF(漁協)、JForest(森組)など会員のみなさまのために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資するという重要な社会的役割を担っている。この役割を果たすため、JA(農協)、JF(漁協)、JForest(森組)などからの出資や、JAバンク、JFマリンバンクの安定的な資金調達基盤を背景に、会員や農林水産業者、農林水産業に関連する企業などへの貸出を行うと共に、国内外で多様な投融資を行い、資金の効率的な運用を図ることにより、会員のみなさまへの安定的な収益還元に努めている。
関連するコンテンツ

- コンサルティング
関連する
無料セミナー
Online seminar
関連する無料動画セミナー
Movie seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)




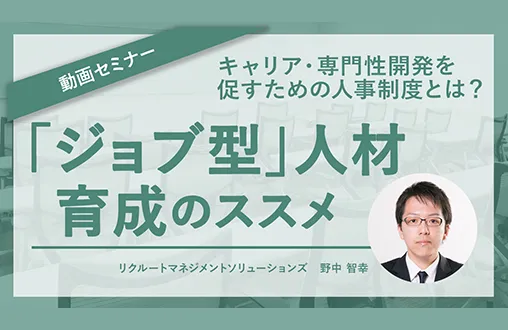
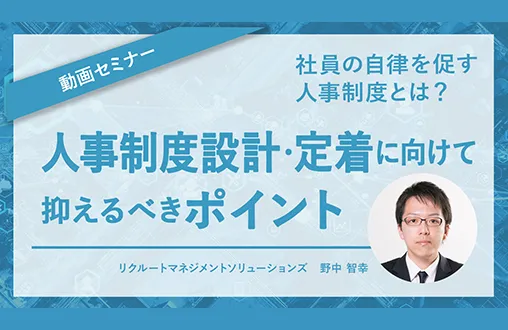
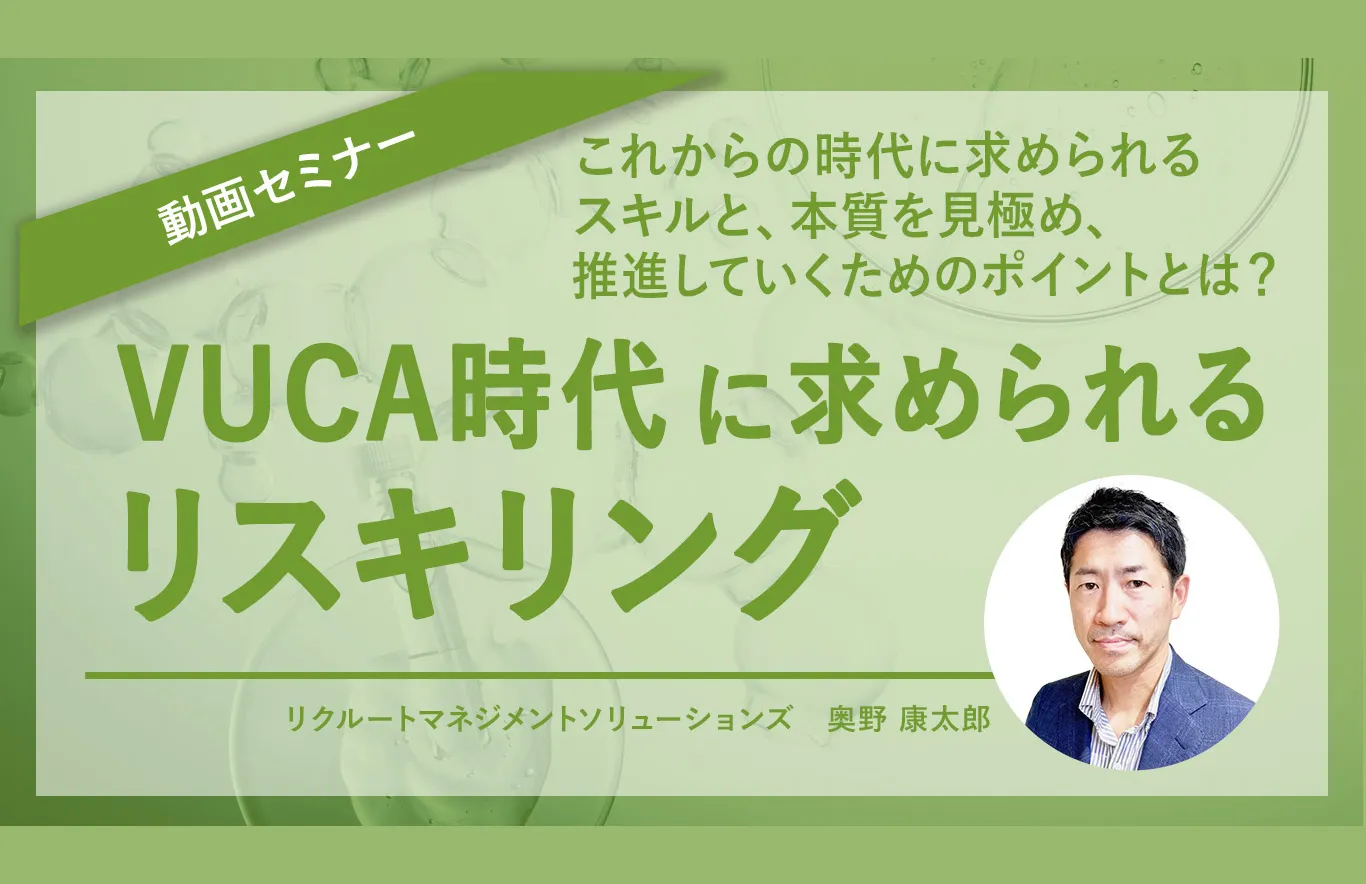
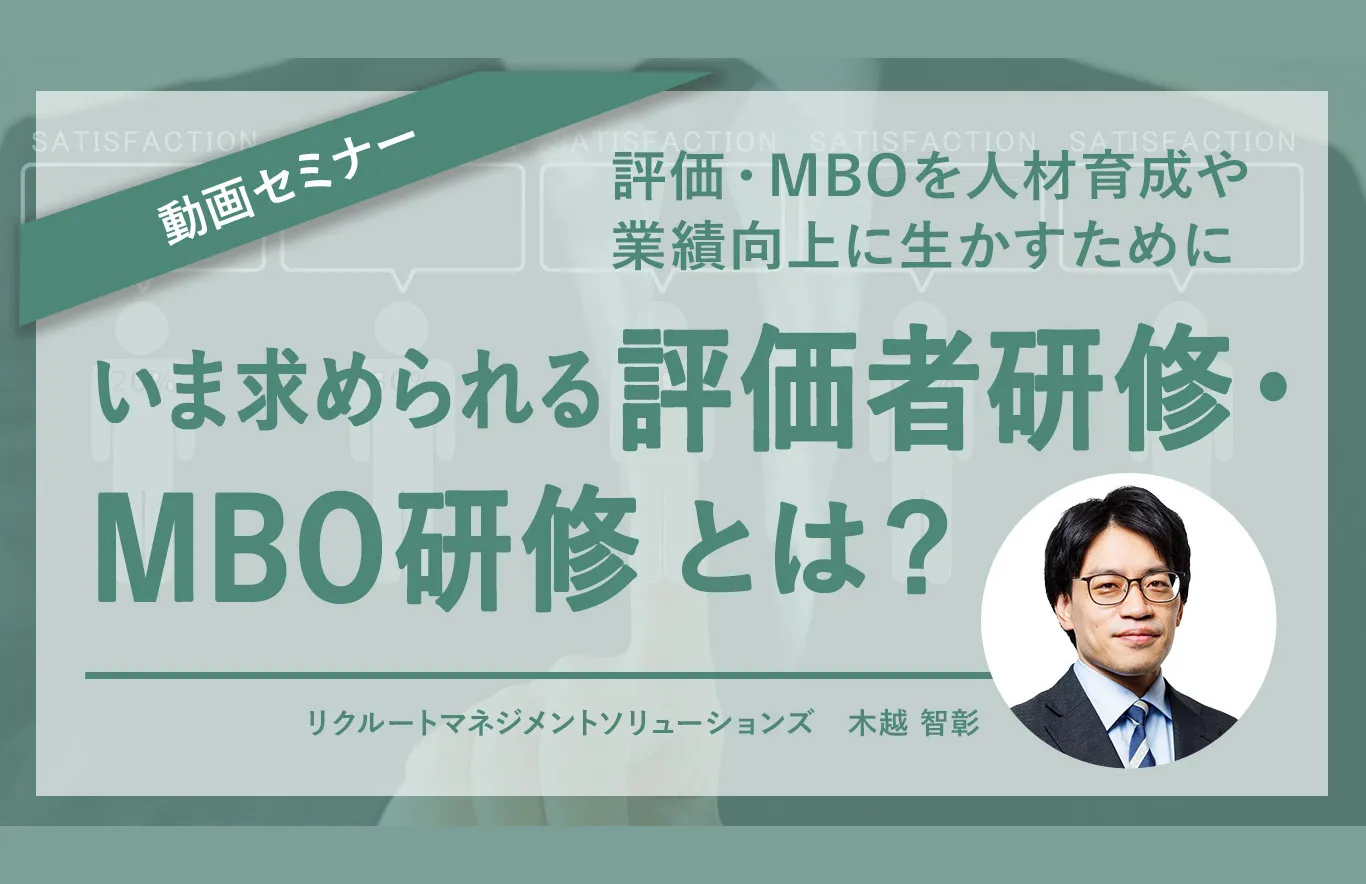









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての