インタビュー
社会を変えるリーダー
社会変革推進財団(SIIF) 常務理事 工藤七子氏
- 公開日:2024/10/28
- 更新日:2024/10/28

このたび新しい一万円札の顔となった渋沢栄一は、「日本資本主義の父」と呼ばれ、生涯で500社もの企業を立ち上げたといわれる。
その渋沢は、事業をする上で、社会貢献や人々の幸せの実現といった公益を追求しながら、同時に利益を上げていくという「道徳経済合一」という理念を唱えていた。
今回取り上げる工藤七子氏はまさに「道徳経済合一」を投資の面から強化しようとしている。
SIIFが取り組んでいることとは
インパクト投資という言葉が身近なものになりつつある。岸田政権下では2022年6月に発表された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」で取り上げられ、2024年3月には金融庁がインパクト投資に関する基本的指針を取りまとめた。
それは財務上の収益に加え、社会的・環境的な変化や効果(=インパクト)を同時に生み出すことを目的とした投資行動のこと。2000年代に欧米で広がった概念であり、日本での普及の第一人者と呼ばれているのが、社会変革推進財団(Japan Social Innovation and Investment Foundation、以下SIIF シーフ)常務理事の工藤七子氏である。
「われわれの取り組みは、地上戦と空中戦に分かれます」と工藤氏が説明する。
地上戦とは、インパクト投資の事例を自ら作ることだ。具体的には、自身が投資家となり、社会課題の解決を目指すスタートアップに投資したり、そうした企業に投資するファンドを作ったりする。一方、空中戦とは、インパクト投資に関する調査研究や政策提言の実行、投資家同士のネットワークや学びの場づくりを意味する。
前者に関し、現在注力する支援先は、ヘルスケア、機会格差、地域活性化の3つの分野に分けられ、NPOを含め、合計47団体ある。
具体例として、まずヘルスケア分野では、糖尿病の治療や禁煙の支援を薬ではなく、スマホのアプリで行うCureAppだ。機会格差の分野では、この7月に投資が決まったAiCANがある。2027年までに子ども虐待ゼロを謳い、児童相談所と市区町村の児童虐待対応部署向けにDX(デジタルトランスフォーメーション)事業を展開している。地域活性化分野では、岡山県西粟倉村に本社があり、滋賀県高島市、北海道厚真町、鹿児島県錦江町にも拠点を持つエーゼログループ。ここは、「未来の里山」の実現に役立つ事業を自然資本領域、社会資本領域、経済資本領域で行っている。
工藤氏いわく「インパクトは意図して生み出すことが重要です。そのためにはインパクトを計測し、さらに大きなインパクトが生まれるよう、経営を改善しなければなりません」。
その指標にはどのようなものがあるのか。「ケースによって千差万別です。健康分野では糖尿病の症状を表す数値が有名ですし、教育分野でよく使われるのが子どもの自己肯定感の数値です。介護分野では日常生活自立度という指標があります。われわれ投資家が具体的な指標を投資先に提案し、実際に用いられることもあります」
インパクト投資は2007年に生まれた
インパクト投資という言葉はアメリカのロックフェラー財団主導の国際会議で2007年に生まれた。当時は各国の諸団体が社会貢献を名目にアフリカの途上国への支援を行っていたが、例えば古着を無償で送る試みを続ければ続けるほど、現地のアパレル企業が駆逐されてしまう。「そうではなく、市場メカニズムが駆動するような開発援助を行うことが重要だと多くの人が気づき始め、そのなかから現地企業への投融資をきちんとやっていこうという一派が生まれた。それがインパクト投資の第一世代です」
その後、2008年にリーマンショックが起き、世界の金融業界が激震に見舞われ、金融パーソンが転職市場に溢れ出た。「彼ら自身のなかで倫理的な揺り戻しがあり、その多くがインパクト投資の世界に向かったのです」
ESG投資は随分前からいわれてきたが、インパクト投資はどこが違うのか。「ESG投資とは、E(環境)、S(社会)、G(企業統治)を考慮することで、リスク調整後のリターンを高くするという仮説に基づいたもの。目的はあくまでリターン増なんです。インパクト投資は社会課題の解決自体を目的に置き、そのインパクトを測る指標までもつ、というところが違いますが、いい意味で、最近は両者が接近し、統合されつつあります」
工藤氏の考えるインパクトの概念は、投資家だけのものではない。「チェーンストアが自社の店舗で働いている全従業員の家族の状態を調べ、相対的貧困状態に陥っている従業員の育成に力を入れ、昇給を図ることもインパクトを追求する行動だといえます。あらゆる経済活動のなかに、ネガティブなインパクトを減らしポジティブなインパクトを増やす仕掛けを組み込んでいく。われわれはそのためのエコシステムを作りたいんです」
SIIFの調査によると、日本のインパクト投資の市場規模(投資残高)は2016年度の調査結果では337億円だったが、2023年度調査報告書では11兆5414億円と、この7年間で342倍に伸びている。工藤氏はこれをどう見るか。「われわれの実感でいうと、投資先の変化は目覚ましいものがあります。一方で、世の中を変えるに至っているかといえば、道半ばです。例えば、身の回りで女性活躍がこんなにも叫ばれているのに、2023年の日本のジェンダーギャップ指数は世界125位と過去最低でした」
紆余曲折のキャリアを経て
工藤氏は社会への関心が深い両親の下で育つ。その影響で憧れの人は日本初の国連難民高等弁務官になった緒方貞子氏、憧れの仕事は国連職員だった。大学時代は長期休暇になるとカンボジアやベトナムの農村を訪問した。
国連職員になるには、3年間の社会人経験と修士号が必須だ。どうせなら近い仕事をと、国際協力機構(JICA)や国際協力銀行(JBIC)を受けるも不採用。2005年、商社に入社する。配属先はアパレルや食糧などを扱うコンシューマサービス事業本部だった。「私がやりたかったのはアフリカでの水道事業で、まったく関心のない分野でした。それでもしつこく言い続けていたら、上司から君の希望に最も近いのはここだと、不動産投資部への異動を打診され、移りました」
仕事だからと、投資の勉強に邁進する。同時に、巨額の金が国境を越えて動く様子を目の当たりにした。「金融資本主義の異常性を垣間見、こうしたシステムが変わらないと、アフリカで水道を引いても意味がないと思い知りました」
2009年、商社を退社し、米国の大学院に2年間、留学する。途上国支援を志望していたが、途上国で何をしたいのかが明確ではなかった。そのうち、途上国の企業への投資を行うアキュメンファンドという組織の存在を知る。「これこそが、私がやりたいことと、やってきたことが重なる分野かもしれないと思いました。大学院1年目が終わった後のインターン先もアキュメンファンドのパキスタン事務所に3カ月行きました」
大学院修了後、念願の国連を受けるが不採用。英米のファンドにも、アフリカのベンチャーにも応募したが駄目だった。これは日本に帰らざるを得ないと思い、受けたのが日本財団だった。
試験には小論文があり、日本財団がインパクト投資ファンドを設立すべきだという内容を書いた。7名の理事が居並ぶ3次面接で「論文の内容を説明してください」と言われ、そのとおりにすると、皆がぽかんとしている。それもそのはず、日本財団は福祉団体などに助成金を支給する法人であり、投資とはまったく縁がない。
そんななか、「僕もそれをやりたかったんだよ」という声が上がる。7名の理事の1人で、現在はSIIFの理事長を務める大野修一氏。この一言で採用が決まったようなものだった。2011年のことで、工藤氏は29歳になっていた。
日本財団に入職後は水を得た魚のように積極的に動いた。2013年には、社会課題解決に取り組む事業者に対し、資金提供と経営支援を行う日本初のベンチャーフィランソロピーファンド「日本ベンチャー・フィランソロピー基金(JVPF)」設立の中心メンバーとなる。2014年にはイギリスのキャメロン首相(当時)の呼びかけで発足した「G8社会的インパクト投資タスクフォース(後にGSGに改称)」に外務省の依頼で出席し、その後、同タスクフォースの日本国内諮問委員会を設立した。
こうして、インパクト投資の機運を盛り上げた“張本人”が取り組まないわけにはいかない。そこで、2017年4月、日本財団内にあり、工藤氏が室長を務めていた社会的投資推進室を独立させる形で、社会的投資推進財団(現SIIF)が設立され、工藤氏は常務理事に就任する。
SIIFには現在、業務委託などを含め、約30名の職員が働いている。「立ち上げのときから、組織のミッションと重なったライフミッションをもつ個人が集まる自律分散型の集団にしたいと思っていました。放っておいても気になっちゃう、追求しちゃう、身体が動いちゃうという人たちですね。メンバー7、8名だった初期の頃はそれでよかったんですが、30名となると、組織としてのレベルアップが必要になってきます。今は個人のライフミッションを大切にしながら組織としての求心力も向上させることが課題で、目標管理を今年初めて取り入れました」
工藤氏自身は論理や数字を駆使する“投資家”というより、朗らかでさっぱりした、コミュニケーション力溢れる女性だ。日本の投資文化を変えるべく、今日も奔走していることだろう。
【text:荻野 進介 photo:山﨑 祥和】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.75 連載「Message from TOP 社会を変えるリーダー」より転載・一部修正したものである。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
工藤 七子(くどう ななこ)氏
一般財団法人社会変革推進財団(SIIF) 常務理事
千葉県出身。2005年東京都立大学卒業後、三井物産に入社。2009年に退社し米クラーク
大学大学院国際開発学部に留学、2011年修了、日本財団に入職し、2017年4月より現職。
家族と共に島根県雲南市と東京との二拠点生活を送っている。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

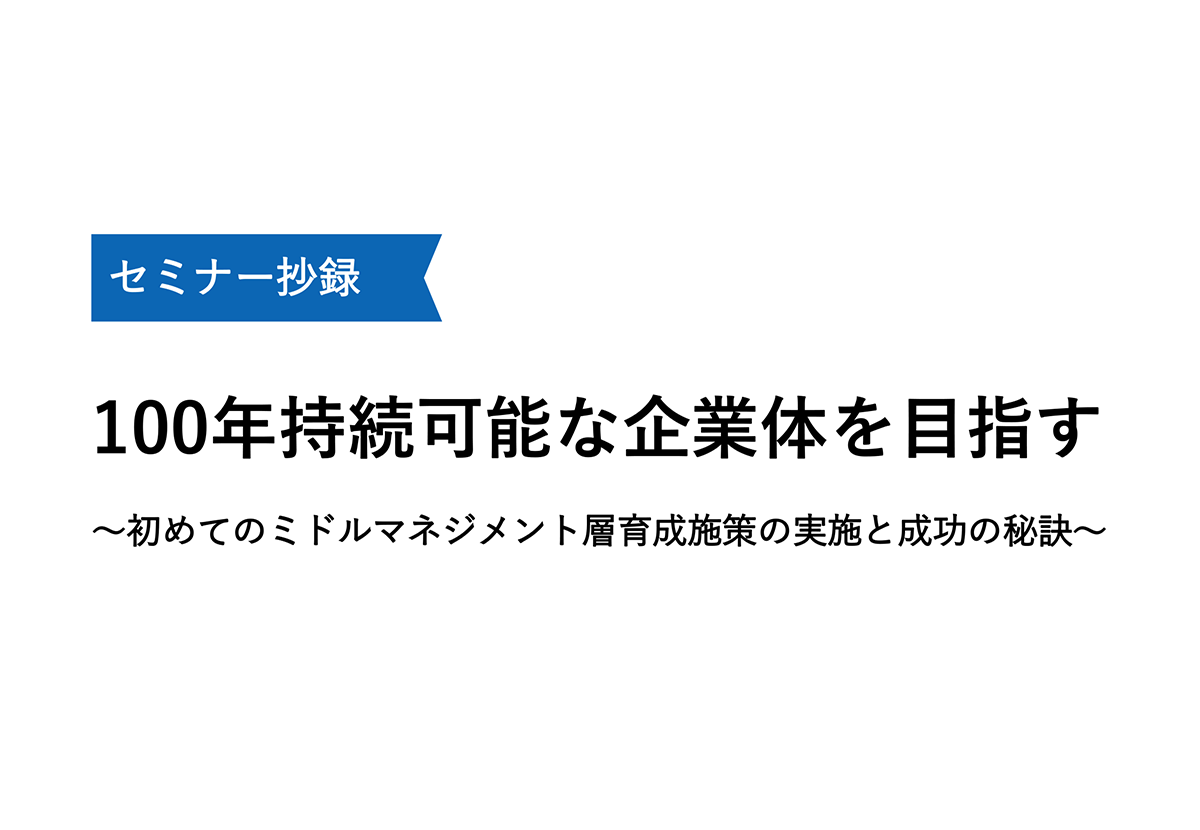









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての