インタビュー
昭和女子大学 本多 ハワード 素子氏
「過組織症候群」が社員の思考を停止させ大事件を引き起こす
- 公開日:2024/07/01
- 更新日:2024/07/01

昭和女子大学 人間社会学部心理学科 准教授の本多ハワード素子氏は、「過組織症候群(メガホリズム)」という概念を使い、個人と集団の心理の視点から、大事件を引き起こした企業の事例を研究している。過組織症候群は、マネジャーの「マイクロマネジメント」とも関係しているという。詳しく伺った。
- 目次
- 組織に過組織症候群が広まると腐敗や不正が起きやすくなる
- 日本企業の組織特殊的な人材育成が過組織症候群も育てている
- 過組織症候群の組織ではマイクロマネジメントが増える
- マネジャーの倫理性は経営状態に影響を受けやすい
- 時間と気持ちの余裕が過組織症候群の予防につながる
組織に過組織症候群が広まると腐敗や不正が起きやすくなる
私は2010年、佐藤眞一氏と共に『メガホリズム組織に巣食う原罪』(CCCメディアハウス)を上梓しました。私たちが明らかにしたのは、組織が引き起こす大事件には、何らかの形で「過組織症候群」が絡んでいる、ということです。本書では、事例としてリーマン・ショックや年金不正、列車事故、食品偽装、贈収賄事件などの不祥事を取り上げました。私たちは、これらに過組織症候群が関係していると考えています。
過組織症候群とは、「組織と個人がもとからもっている認識や行動の歪みが合致することで生じる病気」のことです。過組織症候群にかかると、個人は自分の所属する組織集団があたかも自分にとっての全世界のような錯覚に陥ってしまいます。思考停止が生じて、たとえ自組織が常識から乖離して逸脱しても、犯罪的な行為に手を染めても、奇妙さに気づかなくなります。組織に過度に適応して完全に取り込まれてしまうことから、過組織症候群と呼んでいます。
組織内に過組織症候群が広まると、組織全体が内向き・上向きになり、狭く短期的な「われわれ」意識に過度にとらわれて、腐敗や不正、隠蔽などが起きやすくなります。リーマン・ショックなどの大事件の背景にも同様な病気があると考えています。
日本企業の組織特殊的な人材育成が過組織症候群も育てている
過組織症候群は、世界中のどのような組織でも起こる可能性があります。事例で紹介した企業がそうであったように、社員の誰もがトップや上司の指示に従って夜遅くまで馬車馬のように働き続ける組織には、すぐに過組織症候群が蔓延します。つまり、経営層が社員たちを忙しくさせて考える余裕を奪い、自尊心を失わせて、何も考えずに上層部と内部だけを見て一生懸命働けばよいのだ、という行動規範や組織文化を作ってしまえば、社員は簡単にコントロールされるのです。
日本企業は、なかでも過組織症候群が広まりやすい環境にあります。日本企業では職業アイデンティティを築きにくく、多くの人は組織アイデンティティを拠り所にしているからです。自分という個人の職業をあまり意識せず、所属組織だけが働く上でのアイデンティティに強く影響します。
経済学者の岩井克人氏は、『会社はだれのものか』(平凡社)のなかで、日本的経営は、1つの組織にのみ有効な知識や能力をもった「組織特殊的人的資産」の育成のために、大変有効に働いてきた経営システムだった、と述べています。日本企業の組織特殊的な人材が、過組織症候群にかかりやすいのは当然のことでしょう。日本企業では、組織特殊的人的資産の育成が採用時から始まります。多くの日本企業は潜在性という曖昧な基準での新卒者の採用を好みます。集団の一員として価値観を共有できる人、自分たちの組織に合う人を優先して新卒で採用し、自社の価値観を植え付けていきます。もしもその価値観が社会から乖離している場合、入社時から過組織症候群の芽が出てきます。
過組織症候群の組織ではマイクロマネジメントが増える
過組織症候群の組織では、リーダーシップやマネジメントにも問題が生じることがよくあります。その一例が「マイクロマネジメント」です。マイクロマネジメントとは、部下の能力を信じず、仕事を任せずに、細分化したタスクを厳しく管理するマネジメントや、タスクを担う個人を過剰に細かく管理したがるマネジメントのことです。
マイクロマネジメントの要因の1つが「コントロール飢餓」です。ケイト・メレディスは、人とのやり取りを通して心に肯定的なコントロールがあれば、エンパワーメント、安定、人とのつながりを得ることができること、一方で、心のコントロールが不足すれば、失望、混乱、孤独を防ぐための、神経質なコントロール方法に陥ると指摘しています。内向き・上向きで余裕のない組織で、上層部の言うとおりの結果を、と強く思いすぎるマネジャーが、効率性や速度を少しでも高めようと部下への過剰なコントロールに陥るのもその例です。さらに、マネジャーのスキルが低かったり、視野が狭かったり、マネジャーが心配性で自信がなかったり、逆に自信過剰だったり、あるいは部下がマネジャーを過信しても、マイクロマネジメントが生じるのです。
マイクロマネジメントのもとで、部下はますます考えなくなり、タスクをこなすだけの存在になっていきます。チームもより窮屈になり、柔軟性や魅力や変化適応力を失います。そうして過組織症候群も重症化していきます。
マネジャーの倫理性は経営状態に影響を受けやすい
マイクロマネジメントとは対照的な考え方として、オーセンティック・リーダーシップ、サーバント・リーダーシップなどの「倫理的リーダーシップ」が注目を集めています。
もちろん、倫理的リーダーシップがいつも実践できれば理想的です。しかし、現実はそう簡単ではありません。松井賚夫氏、角山剛氏らの研究では、倫理意識は経営状態によって左右されやすく、マネジャーの倫理性が個人特性や資質よりも経営や組織の状況に強く影響を受けやすいことを示しました。どのようなときも揺るがない倫理観をもつマネジャーを育てるのは、おそらく難しいでしょう。
むしろ、優れたマネジャーも間違えるものと考える方が現実的です。倫理的だったマネジャーも、追い込まれた状況になれば、マイクロマネジメントに走り、部下に暴言を吐く「アビューシブ(侮辱的)リーダーシップ」をとるようになるかもしれません。人間とはそのように状況にうまく適応していく存在でもあるからです。
時間と気持ちの余裕が過組織症候群の予防につながる
以上を踏まえて、個人が過組織症候群にならないようにする方法を提案します。決して難しいことではありません。まず、一人ひとりが「時間と気持ちの余裕」をもつことが大切です。睡眠時間を確保し、外に出て散歩をしたりして、そのときの自分の感覚をよく味わいます。社外の人たちと話しましょう。子育てや動物との触れ合いもよいです。そうやって社会の常識やさまざまな価値観に触れ、自分なりの思考力や価値観を維持することが、過組織症候群を予防します。組織の一員であると同時に、個人として、また、社会の一員として考える力が大切です。
もちろん一方で、組織側は何らかの健康な基準や軸をもつ必要があります。組織が健全な考えや常識をきちんと備えていさえすれば、過組織症候群は広まらないのですから。
過組織症候群は、誰にでも起こり得ることです。組織生活があなたの全世界になっていないか、生活スタイルを一度見直してみてください。自分に過組織症候群の気配があると感じたら、ぜひ時間と気持ちの余裕を取り戻してください。
【text:米川 青馬 photo:平山 諭】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.74 特集1「オーバーマネジメント─管理しすぎを考える」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
本多 ハワード 素子(ほんだ はわーど もとこ)氏
昭和女子大学 人間社会学部 心理学科 准教授
2003年日本女子大学大学院人間社会研究科修了。IT企業で働いた後、法政大学キャリアデザイン学部兼任教員などを経て2017年より現職。専門は産業組織心理学。著書に『メガホリズム』(共著・CCCメディアハウス)、『内部告発のマネジメント』(共著・新曜社)などがある。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



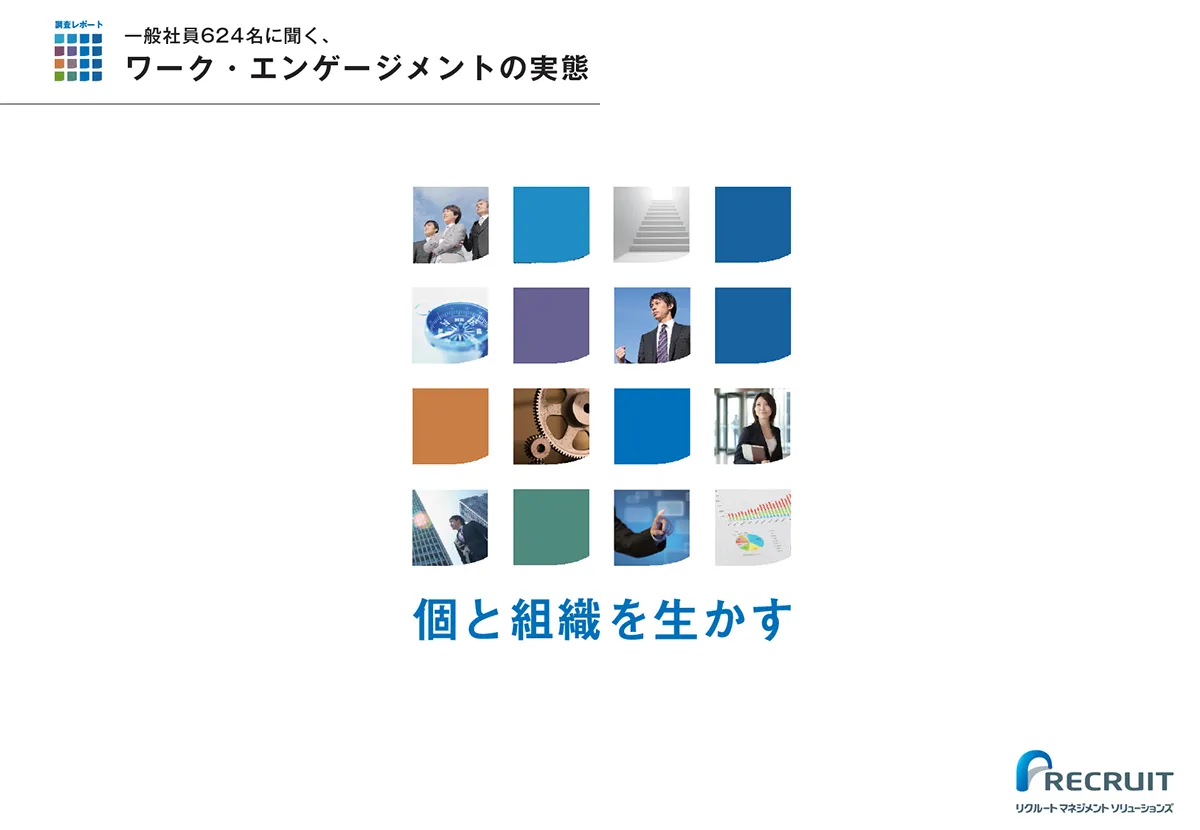
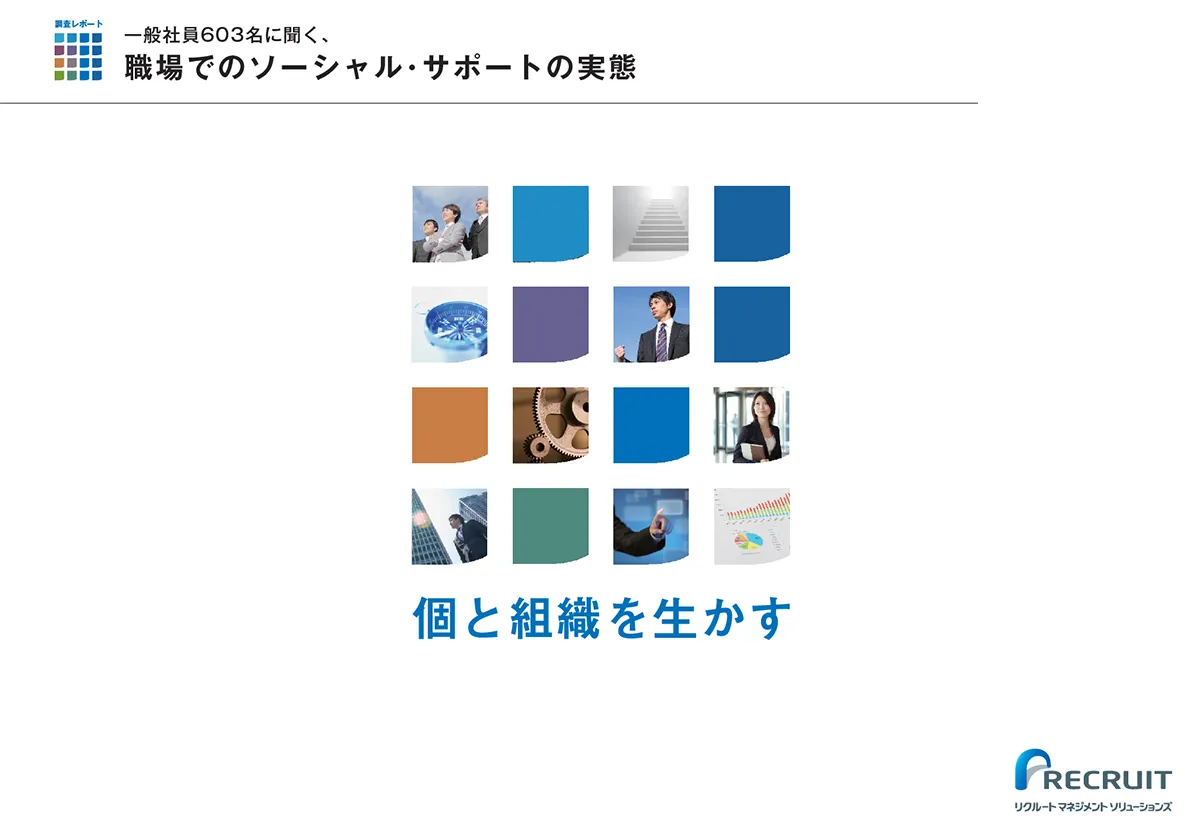









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての