- 公開日:2023/04/10
- 更新日:2024/05/16

個人や組織は、社会ネットワークにどのように埋め込まれており、社会ネットワークからどのような影響を受けているのだろうか。それを調べているのが「社会的埋め込み」の研究だ。ネットワーク組織論を研究する犬塚篤氏に、社会的埋め込み研究について詳しく伺った。
- 目次
- ネットワークのあり方には、大きく2つの種類がある
- 関係的埋め込みと構造的埋め込みのハイブリッドが必要だ
- 構造的埋め込みの支援策で有効なのは「越境」や「副業」だ
- テレワーク時代の新人育成は新たな人事課題になるだろう
ネットワークのあり方には、大きく2つの種類がある
社会的埋め込みの研究には、何度も繰り返し一緒に仕事をしていて関係性が安定している、信頼関係のあるつながりに埋め込まれたことを指す「関係的埋め込み」と、その人がいなくなるとビジネスやプロジェクトや物事が動かなくなるような構造に埋め込まれたことを指す「構造的埋め込み」という、大きく2つの理論的立場が存在します。
関係的埋め込みとは、密で閉鎖されたネットワーク構造のなかに組み込まれた状態をいいます。暗黙知を伝達したり、仕事の効率性・生産性を高めたり、スムーズにコンセンサスをとったりするときには、関係的埋め込みが役立ちます。ただ一方で、関係的埋め込みからはイノベーションは起きにくい、といわれています。
構造的埋め込みとは、疎で開放されたネットワーク構造をもつことの利点を強調する立場です。特に、集団間の結合が弱くなっている部分に橋を架ける関係(仲介者になる機会)に注目します。簡単にいえば、集団間・組織間・部門間などをつなぐ「なくなると困る組織・人・ポジション」のことです。企業レベルでいえば、その1社のビジネスが止まると、ある製品やサービス自体を提供できなくなることがあります。このような存在を構造的空隙に囲まれている、あるいは「構造的に埋め込まれた存在」といいます。個人レベルでも、やはり同じように構造的に埋め込まれている人がいると考えられます。
構造的に埋め込まれた人は、多様なつながりから獲得した種々の知識を組み合わせることで、新たな価値を創造できるといわれています。つまり、イノベーションは多くの場合、構造的埋め込みから生じると考えられるのです。
なお、関係的埋め込みを強い紐帯、構造的埋め込みを弱い紐帯と対応させることがありますが、これらは別の概念と捉えた方がよいでしょう。強い紐帯を有していても、構造的に埋め込まれることは十分に可能だからです。
関係的埋め込みと構造的埋め込みのハイブリッドが必要だ
結論からいえば、私は、これからの企業では組織も個人も、関係的埋め込みと構造的埋め込みの2つのネットワークのあり方を上手にハイブリッドさせる必要がある、と考えています。
例えば、私のような研究者は、大学内では関係的に埋め込まれている必要があります。大学の先生方や職員のみなさんと日常的に仲良くしなければ、仕事の生産性は上がらないでしょう。
しかし、研究のアイディアは、たまに会う学外の研究者や企業のみなさんから新たな知を獲得したり、刺激を受けたりして生まれることが多いのが事実です。そうした人たちこそが、イノベーションの種を運んできてくれるのです。私が学外のネットワークで構造的に埋め込まれていなければ、イノベーションを生み出せる可能性は小さくなってしまうでしょう。
そう考えると、私たち研究者は、関係的埋め込みと構造的埋め込みのどちらも大切にしなければ、良い成果を上げることができません。企業でも同じではないでしょうか。優秀なビジネスパーソンはみなさん、仲の良い密な関係と、オープンで疎な関係の両方を大事にしているはずです。
ただし、どちらをより重視すべきかは、状況によって異なります。変化が少なく定型的な業務を行う人や組織は、関係的埋め込みだけに注目すれば足りるかもしれません。一方で、イノベーションを求められている組織や個人は、構造的埋め込みも十分に意識することが欠かせません。
なお、研究開発組織などには、外部情報を収集して組織内にもたらす「ゲートキーパー」や、ゲートキーパーがもたらした情報を組織内に翻訳して伝える「トランスフォーマー」が存在することがあります。これらの人たちが組織内のハブに位置付けられることで、組織が関係的埋め込みと構造的埋め込みのハイブリッドを実現できる可能性があります。
構造的埋め込みの支援策で有効なのは「越境」や「副業」だ
コロナ禍を契機として、バーチャル・ネットワークを使ったコミュニケーションが普及しました。これは、社会的埋め込みを考える上で大きな変化です。
私は、大学構内で働く頻度が減り、自宅で働く日が増えました。同時に、コロナ禍で出張が禁じられたことを契機に、バーチャル・ネットワークを通じて、海外や遠隔地の研究者と対話することが当たり前になりました。これまでめったに会えなかった学外の人たちから刺激を受けるチャンスに恵まれるようになったわけです。その結果、研究成果を出せるようになったかといえば、必ずしも理論通りでない気もしますが、コロナ禍以前よりも関係的埋め込みの重要度が下がり、構造的埋め込みの必要性が高まった、と感じています。多くの企業でも同様の変化が起こっているはずです。
私は、この変化が悪いことだとは思っていません。なぜなら、現代社会ではイノベーション創出が強く求められており、それには構造的埋め込みがポイントになるからです。
企業が従業員の構造的埋め込みを支援する上で有効なのは、「越境」や「副業」など、従業員が社外に出ることを許すことです。業種の枠を超え、社外の方々と触れ合う機会を設けるのも効果的でしょう。昔ながらの「ジョブローテーション」も、社内ネットワークを薄く広く構築することで、社内での構造的埋め込みの獲得に一役買う可能性があります。
テレワーク時代の新人育成は新たな人事課題になるだろう
こうした変化の一方で、新たな課題も引き起こされようとしています。私が第一に気になっているのは「新人のキャリア形成問題」です。従来の成功パターンは、若い頃は所属する組織・チーム内の関係的埋め込みを大事にしながら仕事を学び、経験を積むと共に構造的埋め込みの比重を高め、外に向けて実力を発揮する、という流れでした。
ところが、テレワークが広まると、新人時代にチーム内の関係的埋め込みを作るチャンスを十分に得られない可能性があります。私が心配しているのは、キャリア形成の土台となる関係的埋め込みを作らないまま、果たして生涯にわたる実力をつけていけるのだろうか、イノベーションを重視するあまり、関係的埋め込みをないがしろにしてよいのだろうかということです。テレワーク時代の新人育成は、新たな人事課題になるでしょう。
また、組織内の関係的埋め込みが弱まってしまうと、いざというときに一致団結できない組織、助け合いが起きない組織になってしまうのではないか、という危惧もあります。チームワークに重きを置いてきた日本企業の社風が変質する可能性もあるでしょう。その変化をよしとするかどうか、各社が考えるタイミングなのかもしれません。
【text:米川 青馬 photo:平山 諭】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.69 特集1「つながり」を再考する より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
犬塚 篤(いぬづか あつし)氏
名古屋大学大学院 経済学研究科 教授
大手電子機器メーカーを経て大学院へ。在学中に知識綜合研究所を創設。2004年北陸先端科学技術大学院大学修了。東京大学特任准教授、岡山大学大学院准教授、名古屋大学大学院准教授などを経て2016年より現職。専門は経営組織論、経営戦略論、サービスマネジメント。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



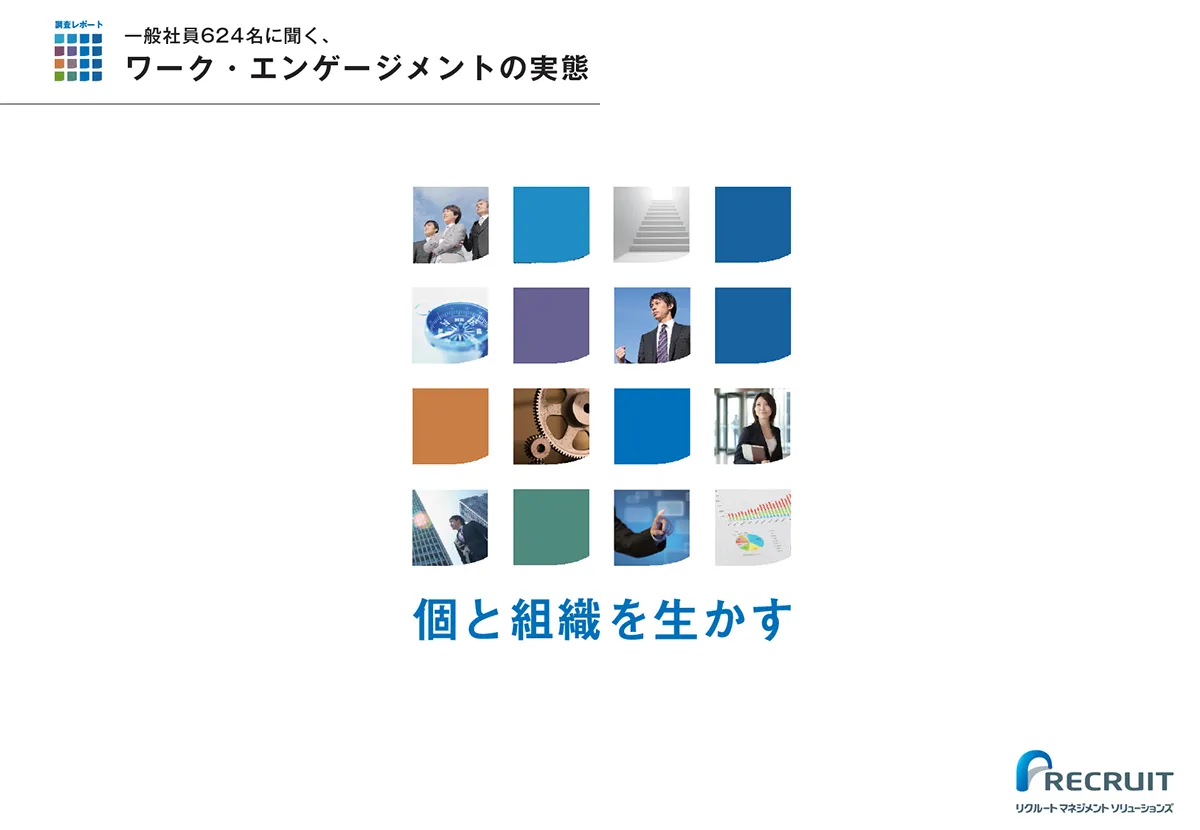
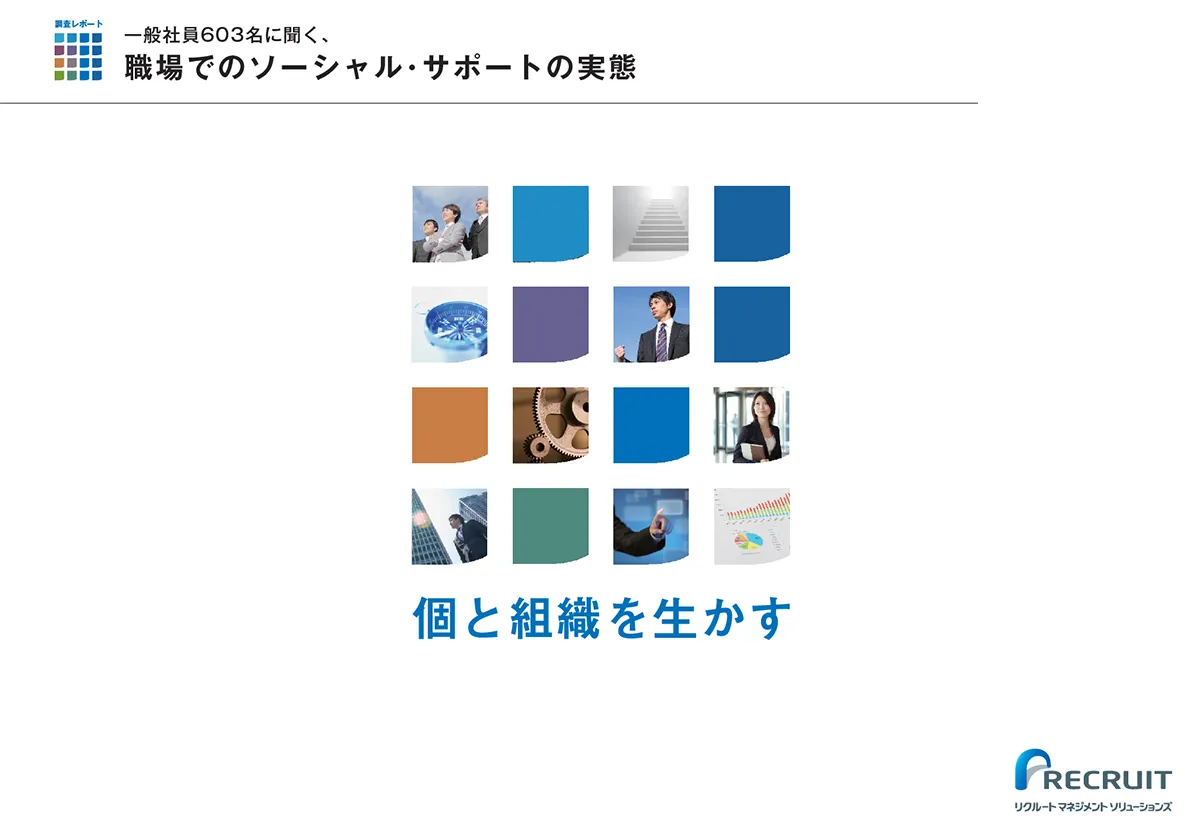









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての