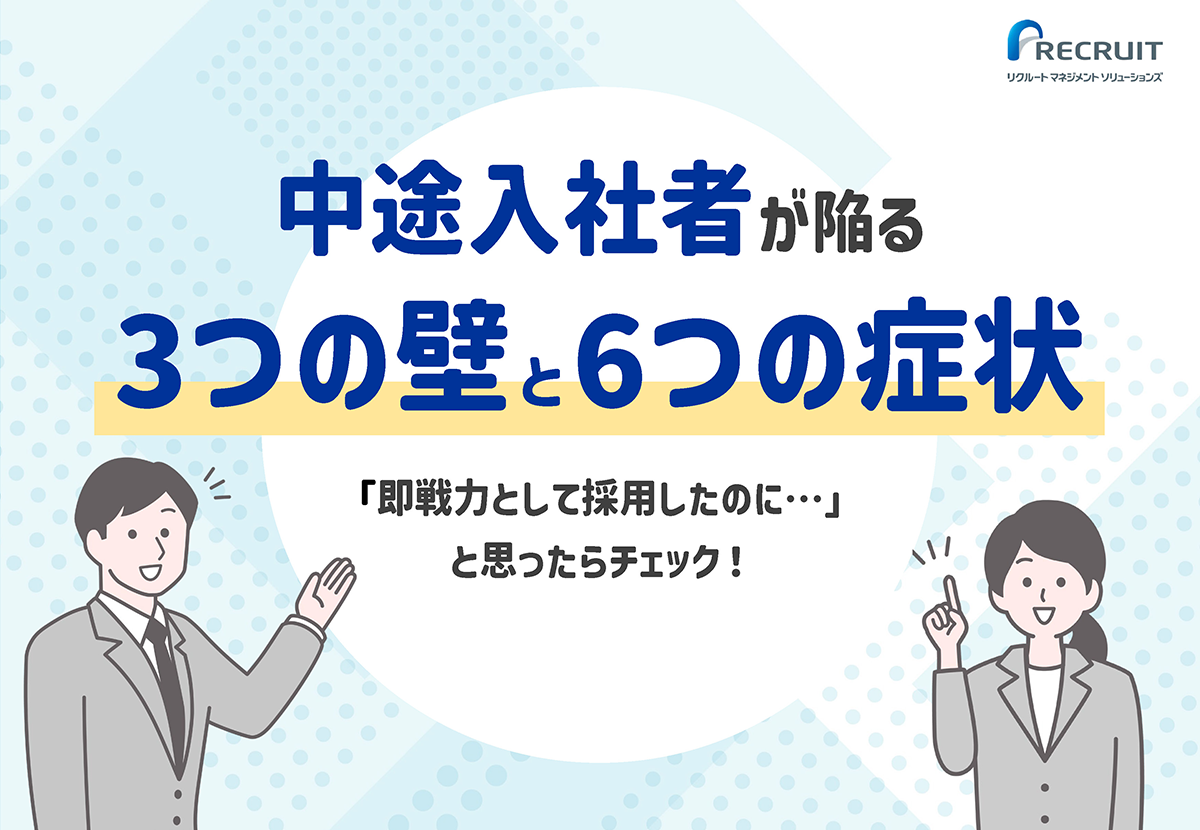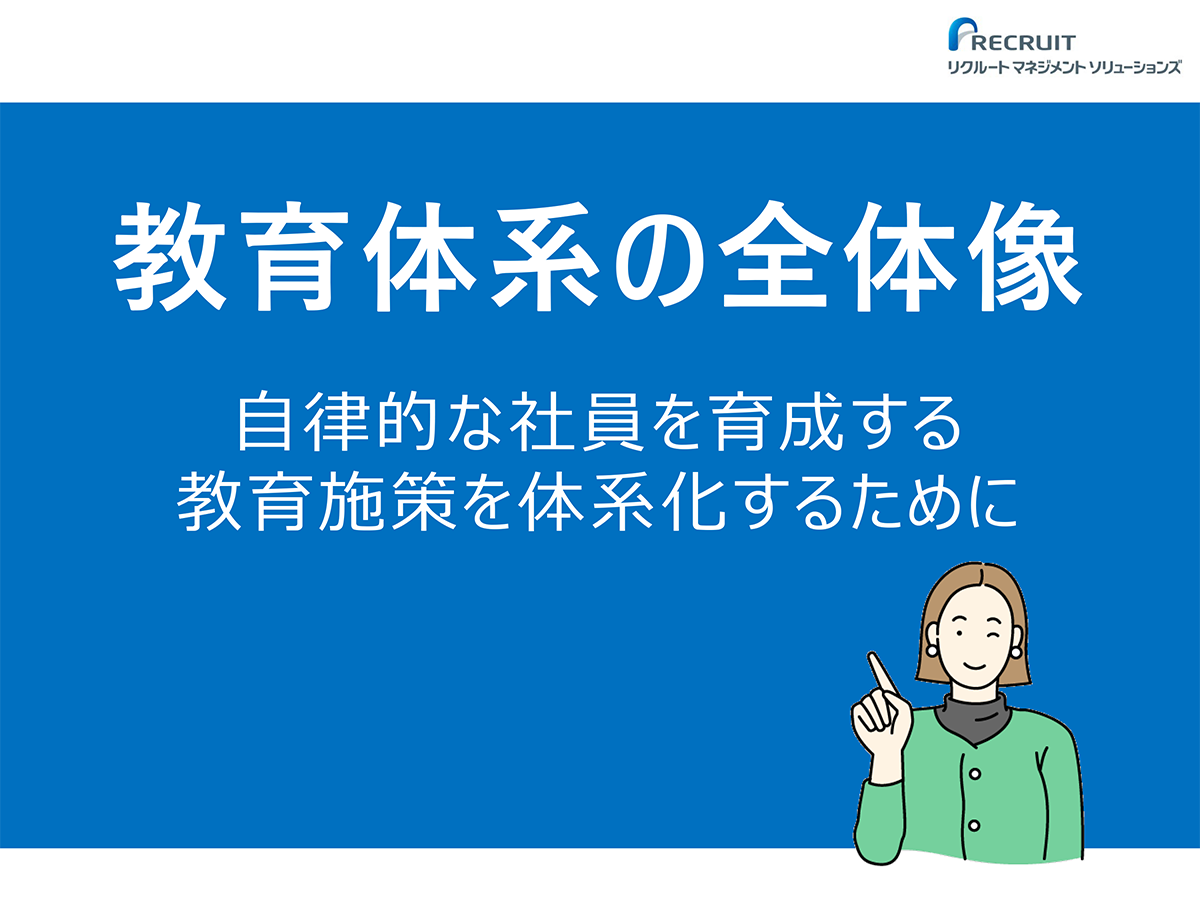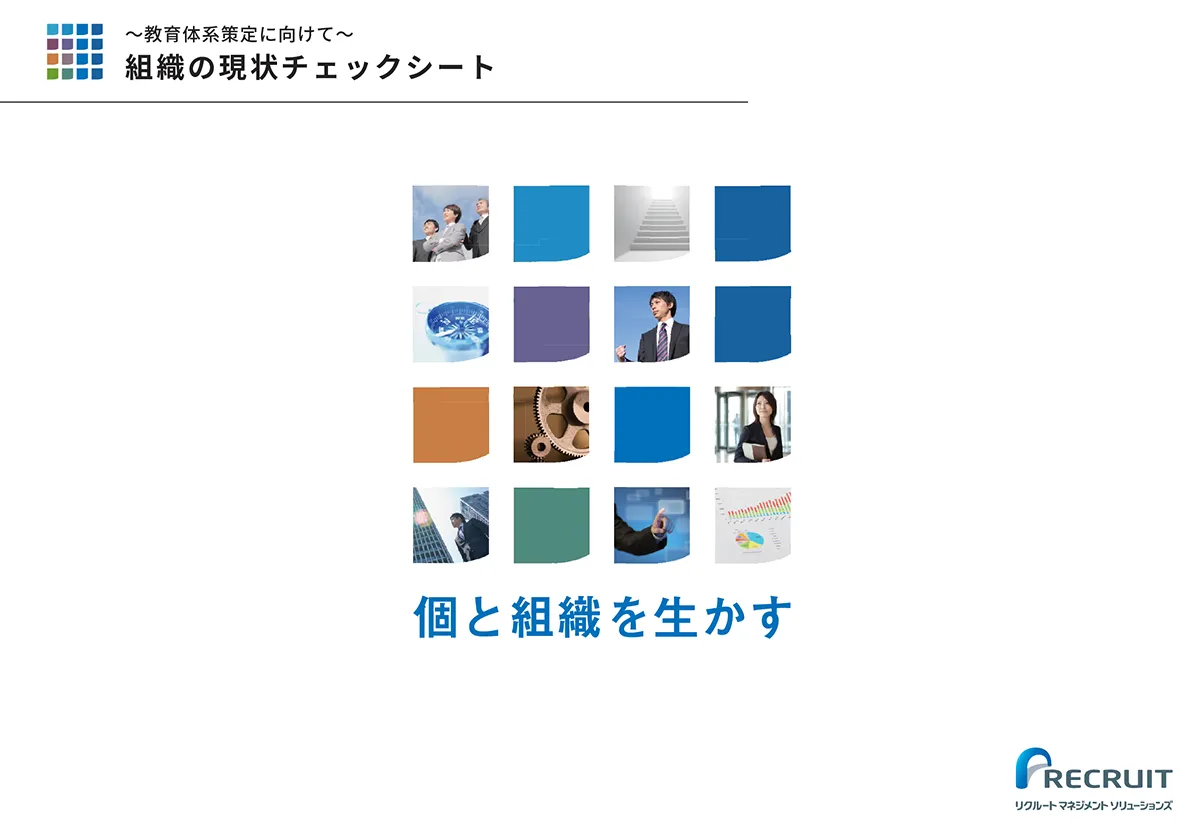- 公開日:2022/06/27
- 更新日:2024/05/16
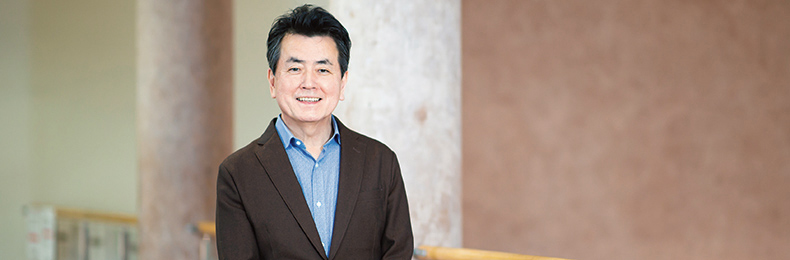
日本企業の人事部は、これまでどのように現場を支えてきたのか。今後はどのように現場に働きかければよいのだろうか。企業の人事部長経験をもつ人的資源管理の専門家であり、長年にわたり人事の役割について研究を続けてきた大手前大学 学長 現代社会学部 教授の平野光俊氏に、日本型人事システムの進化と、今後の人事部の役割について詳しく伺った。
- 目次
- 人事部の活動には3つの補完性が要求される
- 役割等級制度は人事権をライン管理職に移譲するとよい
- 個別化された能力開発には粘着的人事情報が欠かせない
- 人を大切にして人をよく知り人を生かす
- 従業員のウェルビーイングを高めるアプローチが重要だ
人事部の活動には3つの補完性が要求される
前提として、人事部の活動というのは独立したものではなく、さまざまなシステムの補完性が要求されます。大きく3種類の補完性があります。1つ目は「制度的補完性」で、法律など企業外の環境変化に対応する動きをとる必要があります。2つ目は「企業内補完性」で、戦略・人材・組織・人事管理の4つのシステムを補完する動きが求められます。
3つ目は「人事管理の編成の補完性」です。人事管理は、縦軸「人事管理活動の抽象度(人事の基本的価値観・人事方針・人事規則・人事プロセス)」と横軸「人事管理の活動領域(職務設計・報酬・配置など)」で補完性が要求されるのです。今回紹介する研究では、社員格付け制度と人事部の役割の補完的関係に着目しています。なかでも人事部の人事権と人事情報を集める程度という2つの変数について、補完的関係の変化を見ていきました。
役割等級制度は人事権をライン管理職に移譲するとよい
伝統的な日本企業の人事部は、「強い人事部」です。異動、キャリア開発、経営者選抜、企業戦略策定に強く関与する人事部です。なぜそんな力があるかといえば、人事権と人事情報の両方が人事部に集中しているからです。
強い人事部の背景には、終身雇用保障と職能資格制度があります。終身雇用を前提に職能資格制度のもとで幅広い異動を頻繁に行い、社内で必要な技能を総合的に身につけたゼネラリストを長期視点で育成するのが、伝統的日本企業です。
このシステムを運用するにあたっては、人事部が強い人事権をもち、異動やキャリア開発を集中的に管理した方が機能します。その際、人事部が従業員をよく知ることが欠かせませんから、強い人事部は人事情報を丹念に集めています。
対して最近の日本企業では、伝統的な職能資格制度だけではなく、「職務等級制度」やハイブリッド型の「役割等級制度」を導入する企業も増えており、現在は3つが混在しています。
また、終身雇用保障に代わって「エンプロイヤビリティ保障」を重視する企業も多くなりました。エンプロイヤビリティ保障とは、企業が従業員の雇用される能力を保障する雇用関係のことです。終身雇用・定期昇給・安定賃金の保障はなく、キャリア競争力を高める仕事機会の提供がインセンティブです。
今回の研究で分かったことの1つは、次のことです。職能資格制度のもとでは、人事権が人事部に集中している方が従業員の働きがいを高めます。一方で、役割等級制度のもとでは、ライン管理職が人事権をもっていた方が従業員の働きがいを高めるのです。つまり、今の日本には、「職能資格制度+人事権の人事部集中」と「役割等級制度+人事権のライン分権化」という2つの補完的な組み合わせがあるのです。
各職務については、当然人事部よりもライン管理職の方が詳しいですから、職務重視の役割等級制度では、ライン管理職が配置や異動を決めた方がよいのです。職能資格制度から役割等級制度に移行する企業は、人事権をライン管理職に移譲した方がうまくいきます。実際、多くの人事部が人事権のライン分権化を実行しています。
個別化された能力開発には粘着的人事情報が欠かせない
さらに私は、もう1つの事実を発見しました。「日本企業の人事部は、人事権をライン分権化した後も、相変わらず人事情報を蓄積しつづけている」ことです。
特に、人事部は、私が「粘着的人事情報」と呼ぶものを手間ひまかけて収集しています。粘着的人事情報とは、本人への面談や周囲への聞き取りをしなければ得られない定性的情報のことです。例えば、人となり、新しい職務において活躍する可能性、キャリア志向やキャリア目標、潜在的能力などの情報です。
粘着的人事情報を獲得するには、従業員との信頼関係を作ったり、インタビューを解読したり、人事自身の洞察力を高めたりするコストがかかります。日本企業の人事部はわざわざそうしたコストをかけてでも、引き続き粘着的人事情報を集めているのです。人事権をライン管理職に移譲したら人事情報は要らなくなりそうなものですが、そう考えていないのです。
実は、そこには「エンプロイヤビリティ・パラドックス」の問題があります。エンプロイヤビリティ保障が従業員の汎用的専門能力を向上させ、転職可能性を高めてしまう矛盾です。企業はエンプロイヤビリティ保障を導入したいのですが、そうすると優秀人材に転職されるリスクが高まるのです。企業は、この問題を何とか解決して、エンプロイメンタビリティ(社員から働きつづけたいと評価される魅力)を高めたいと考えています。
有力な解決方法が「個別化された能力開発」です。人事部とライン管理職が協力して、従業員一人ひとりの成長機会となる職務と教育訓練の場を提供し、個別最適の能力開発を促す取り組みです。私たちの研究では、「エンプロイヤビリティ保障は従業員の働きがいを下げるが、エンプロイヤビリティ保障と個別化された能力開発を組み合わせると、むしろ従業員の働きがいは高まる」ことが分かりました。多くの人は魅力的な仕事と成長のチャンスがある会社で働きつづけたいのです。
人事部が粘着的人事情報の収集を続けているのはこのためです。個別化された能力開発を実現するには、従業員一人ひとりをよく知る必要があります。粘着的人事情報は、エンプロイメンタビリティを高めるために欠かせないのです。さまざまなコストをかけるだけの価値があるのです。
人を大切にして人をよく知り人を生かす
つまり、役割等級制度を採用する企業の人事部の多くは、実は完全なライン分権化をしていないのです。人事部には、全体最適視点や人の専門家としての人間洞察力があります。そうした能力を発揮してライン管理職のパートナーとして、粘着的人事情報を収集して、個別化された能力開発を実現しているのです。
私は、役割等級制度と個別化された能力開発を組み合わせた人事システムを「進化型人事システム」と呼んでいます。進化型人事システムの特徴は、「人を大切にして、人をよく知り、人を生かす」ことです。エンプロイメンタビリティの高い組織を作ることを目指す人事システムです。
従業員のウェルビーイングを高めるアプローチが重要だ
以上に加えて、人事の皆さんは「人間モデルの変化」にも留意する必要があります。
エドガー・H・シャインは、経営学の人間モデルの変遷を4段階に整理しました。最初に生まれたのは、成果に至る行動や発揮された能力に連動して給料やボーナスが変動することにより、人が動機づけられると考える「経済人モデル」です。2つ目に、人は集団に所属していることから安心や喜びを得る社会的存在だと捉える「社会人モデル」が登場しました。3つ目に現れたのは、自ら自分を動機づけることができることに目を向けた「自己実現人モデル」です。
4つ目に、シャイン自身が「複雑人モデル」を提唱しました。シャインは、人間のもつ動機は多様で一筋縄ではいかない、十人十色であることをしっかり認識すべきだ、と考えたのです。とはいえ、これまで人間モデルは、経済人モデル、社会人モデル、自己実現人モデルの3つに大きく集約できる、と考えられてきました。
ただ、私は最近、ここに新たなモデルが追加されたと考えています。それは、神戸大学の鈴木竜太教授が提起する「生活人モデル」です。従業員を、生活する人としても見る必要が出てきたのです。これからの人事部は、生活人モデルに則り、従業員の「ウェルビーイング」を高めるアプローチをとることが求められます。生活を含めたウェルビーイングの向上が、従業員の働きがいや定着率を高めることが分かってきたからです。
従業員のウェルビーイング向上のためには、一人ひとりの生活・プライベートに関する粘着的人事情報も集めることが大切です。また、ワーク・エンゲージメントを高めると仕事時間を増やすため、家庭時間を圧縮する可能性がある、といったことにも気を配る必要があります。
人事はもともと人間への深い洞察や哲学が求められる仕事ですが、今後の人事の皆さんには、これまで以上に「人間対人間」として従業員一人ひとりと向き合う姿勢、より深く人間を洞察する力が求められるでしょう。
【text:米川 青馬 photo:角田 貴美】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.66 特集1「現場を支える人事」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
平野 光俊(ひらの みつとし)氏
大手前大学 学長 現代社会学部 教授
神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。ジャスコ(現イオン)にて人事部長、人事教育部長を歴任後、神戸大学教授、大阪商業大学教授を経て大手前大学副学長。2022年4月より現職。神戸大学名誉教授。主要著作は『日本型人事管理―進化型の発生プロセスと機能性』(中央経済社)。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)