インタビュー
静岡大学 学術院 橋本 剛氏
職場での援助要請が難しいのはなぜか
- 公開日:2019/06/24
- 更新日:2024/03/27

「助けてほしい」と言う「援助要請」が援助を必要とするメンバーにとって難しいことが、職場のソーシャル・サポートを滞らせる要因の1つとなっている。なぜ、そうなってしまうのか。どうしたら解決するのか。社会心理学の側面から「援助要請」を研究する橋本剛氏に伺った。
- 目次
- 貢献感の低いメンバーほど援助要請しにくくなる
- ギブアンドテイクを求める組織ゆえに援助要請しにくいことも
- 遠慮ストラテジーと遠慮しないストラテジーの衝突
- フリーライダーを抱える余裕と曖昧さもある程度は必要
貢献感の低いメンバーほど援助要請しにくくなる
日本社会は全体的傾向として、「援助要請」を抑制しがち、つまり「遠慮」しがちです。周囲の顔色を窺い、言いたいことを言わず、波風を立てないよう、互いに忖度しながら行動する傾向があります。そこには、「人様に迷惑をかけてはいけない」「周囲の足を引っ張ってはいけない」という意識があると思われます。あからさまに助けを求めると波風を立て、周囲の迷惑にもなりかねないため、あまり好まれないのです。こうした文化の下で、援助要請を遠慮してしまうのは自然でしょう。
そこで日本社会では、援助のニーズを抱えている本人が声を発しなくても、周りが気を使って助けるような行動が好まれます。なかでも、本人すら助けてもらったと気づかないような形でのさりげない援助は、非常にありがたいものです。例えば、日本社会で効果的なソーシャル・サポートの方法の1つは、「悩みを抱える人と同じ悩みを抱えているかのように振る舞うこと」です。Aさんが分からないことがあって悩んでいると察知したら、Bさんは、自分自身が悩んでいるふりをして、上司や先輩に「●●が分からないのですが、どうしたらよいのですか?」と質問するのです。そうすれば、Aさんは周囲に悩みを知られることなく(実はBさんは気づいているのですが)、問題を解決できます。これが、Aさんにとって精神衛生上望ましい援助方法の1つです。
良くも悪くも、日本はこうした社会であり、日本で暮らせば多かれ少なかれ、このようなことを日常的に体験しているのではないでしょうか。
この点、アメリカは対照的です。アメリカでは、必要なら主体的かつ明確に「助けてほしい」と援助を求めるべきであり、それに応えるかもまた相手の主体的な判断次第、という考え方が主流なので、援助要請を抑制することは日本ほど多くありません。また、「自分のせいで周囲の足を引っ張ってはいけない」という意識も日本ほどではありません。日本では、自分が得すると誰かが損する、というゼロサム的感覚があるのに対して、アメリカでは、自分の幸せを追い求めることがみんなの幸せにもつながる、という感覚があるようです。
ただし、日本人であれば、誰もが同じように遠慮しがちなのかといえば、もちろんそうでもありません。私の研究によれば、日本人でも「貢献感」の強さによって、援助要請傾向に違いがあるようです。簡単に言えば、「周囲に貢献していると思う(貢献感が高い)」ほど、援助要請傾向が高く、「周囲の役に立っていないと思う(貢献感が低い)」ほど、援助要請傾向は低くなるのです。
これを企業組織にあてはめて考えると、優れた成果を出している社員は、周囲に「ちょっと助けてよ」「協力して」などと言いやすいけれど、そうでない社員ほど、周囲に助けてほしい、協力してほしいと言いにくくなってしまうということです。
なぜかと言うと、先ほどもお話ししたとおり、日本人の多くは「周囲の足を引っ張ってはいけない」という意識が強いからです。自分は普段から組織に貢献していると思っていれば、多少援助要請をしても周囲は大目に見てくれるだろうと思えるでしょう。しかし、自分が組織の役に立っていないと感じている場合、そこでさらに援助要請をすれば、さらに仲間の足を引っ張ってしまうと思い、助けを求めるのを躊躇してしまうわけです。
それでも、新人・若手であれば、経験不足ゆえに援助要請がある程度まで正当化されますから、貢献感が低くても、援助要請しやすいかもしれません。その意味で最も援助要請をしにくいのは、十分に成果を出せていない中堅以上でしょう。
ギブアンドテイクを求める組織ゆえに援助要請しにくいことも
さらに、そこにもう1つの要素が関わってきます。「互恵性規範」です。互恵性規範とは、分かりやすく言うと、「ギブアンドテイクを重視する傾向」のことです。例えば、互恵性規範が強い人は、「誰かに助けてもらったら、必ずお返しをしないといけない」と思います。また、年齢や在籍期間などに関係なく、成果に応じて報酬をシビアに変える組織は、短期的スパンでの互恵性規範が強い組織といえます。近年は、日本にも短期的互恵性規範の強い組織が増えているのではないでしょうか。
そして、互恵性規範には、貢献感と援助要請の正の関連を増幅する効果があります。つまり、何ごとにもギブアンドテイクを求める傾向の強い組織、成果に応じて報酬をシビアに変えるような組織だと、貢献感の低いメンバーはさらに援助要請しにくくなります。逆に短期的な互恵性規範が弱い組織では、貢献感の低いメンバーでも援助要請をしやすくなるかもしれません。
遠慮ストラテジーと遠慮しないストラテジーの衝突
援助要請、貢献感、互恵性規範がこうした関係であることは、これまで日本社会で主流であった「遠慮ストラテジー」が、現代社会では有効性を失いつつあることとも無関係ではないでしょう。
遠慮ストラテジーとは、短期的には遠慮をして自分が割を食ってでも他者に配慮し、長期的には他者から好ましい評価を得よう、受け入れてもらおうとする戦略です。日本では長い間、農村部でも都市部でも、遠慮ストラテジーが主流でした。
ところが、最近はアメリカ的な「遠慮しないストラテジー」、つまり、他人の迷惑などを気にするよりも、自分の権利を主張していく戦略が、徐々に広まっています。その結果、援助要請がしやすくなる側面もありますが、例えばクレーマーの増加など、過剰な主張にまつわる問題も生じます。遠慮しないことで自分は楽になりますが、その分、他者がどこかで割を食うことになります。
今後はおそらく日本でも、グローバルスタンダードである遠慮しないストラテジーがますます一般的になるでしょう。しかし、日本社会全体がそう簡単に変わるとも思えません。当分は、遠慮ストラテジーと遠慮しないストラテジーが混ざり合った状態が続くのではないでしょうか。両者のストラテジーの衝突によって、さまざまな混乱や問題が起こるでしょう。
フリーライダーを抱える余裕と曖昧さもある程度は必要
こうした状況で、今私たちは援助要請について、どのように考え、どう対処していけばよいのでしょうか。当然ながら、絶対的な答えがあるわけではありませんが、私の思うところをいくつか述べたいと思います。
組織内の遠慮を減らし、援助要請やソーシャル・サポートを活性化するには、まずは組織の互恵性規範を弱めて、「フリーライダーになってしまうことをある程度は許容する余裕と曖昧さ」が必要なのかもしれません。今は成果を上げていないメンバー、さほど戦力にならないメンバーであっても、彼らもまた仲間の一員であると積極的に受け入れること自体、組織がサポーティブであることの一側面ともいえるでしょう。
また、経営者や上司などのリーダーが、自らの弱さを見せるというのも、時には有効かもしれません。上位にいる者が弱みを見せ、部下に助けを求めるモデルが示せれば、立場や勢力にこだわらない援助要請やソーシャル・サポートが活発になっていくのではないでしょうか。
ビジネスライクに考えれば、成果を出せないメンバー、必要性が不明瞭なメンバーは切り捨てるという判断が正当なのかもしれません。短期的な互恵性規範が強い組織では、そうしたフリーライダーは、排除するのが合理的と見なされるでしょう。厳しいビジネス環境で生き残るためには、どのような会社でも、そうした面を完全になくすことはできないだろうと思います。
しかし一方で、不本意ながらフリーライダー的な立場となってしまう人々への対応は、現代日本のような格差社会・高齢社会では、特に重要な社会問題の1つとなるようにも思われます。フリーライダーと見なされることを恐れて小さくなっている人々に、どのように向き合うのか。それもまた、その企業や組織が何を目指しているのか、社会に発するメッセージの1つとなるでしょう。
ただし、フリーライダーには、本当に弱い存在である「やむを得ないフリーライダー」と、弱い存在を装う「確信犯的なフリーライダー」がいるとも考えられます。私がここまで語ってきたのは、やむを得ないフリーライダーのことです。確信犯的なフリーライダーは、話が違ってくるかもしれません。しかし、その両者を見極めるのは容易でなく、これはなかなか難しい問題です。
私は、単純に援助要請が増えればよいと思っているわけではありません。援助要請が必要以上に増えることは、それはそれで問題だと思います。もっと言えば、援助要請という枠組自体にも問題があるかもしれません。援助という言葉の響きは表面的には良いのですが、その裏に「強い者が弱い者を助ける」という意味合いを含むことも少なくありません。援助要請は、時には否応なく力関係をあらわにしてしまうのです。もっと気楽に、必要であれば細かいことを気にせず助け合うのが当たり前、という雰囲気を作るには何が必要なのか、さらに考えていきたいと思います。
【text:米川青馬】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.54 特集1「職場におけるソーシャル・サポート 希薄化する人間関係にどう向き合うか」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
橋本 剛(はしもと たけし)氏
静岡大学 学術院 人文社会科学領域人文社会科学部 社会学科 教授
1999年名古屋大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程後期課程修了。愛知産業大学経営学部専任講師、静岡大学人文学部准教授を経て現職。専門分野は社会心理学。著書に『ストレスと対人関係』(ナカニシヤ出版)、『大学生のためのソーシャルスキル』(サイエンス社)などがある。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



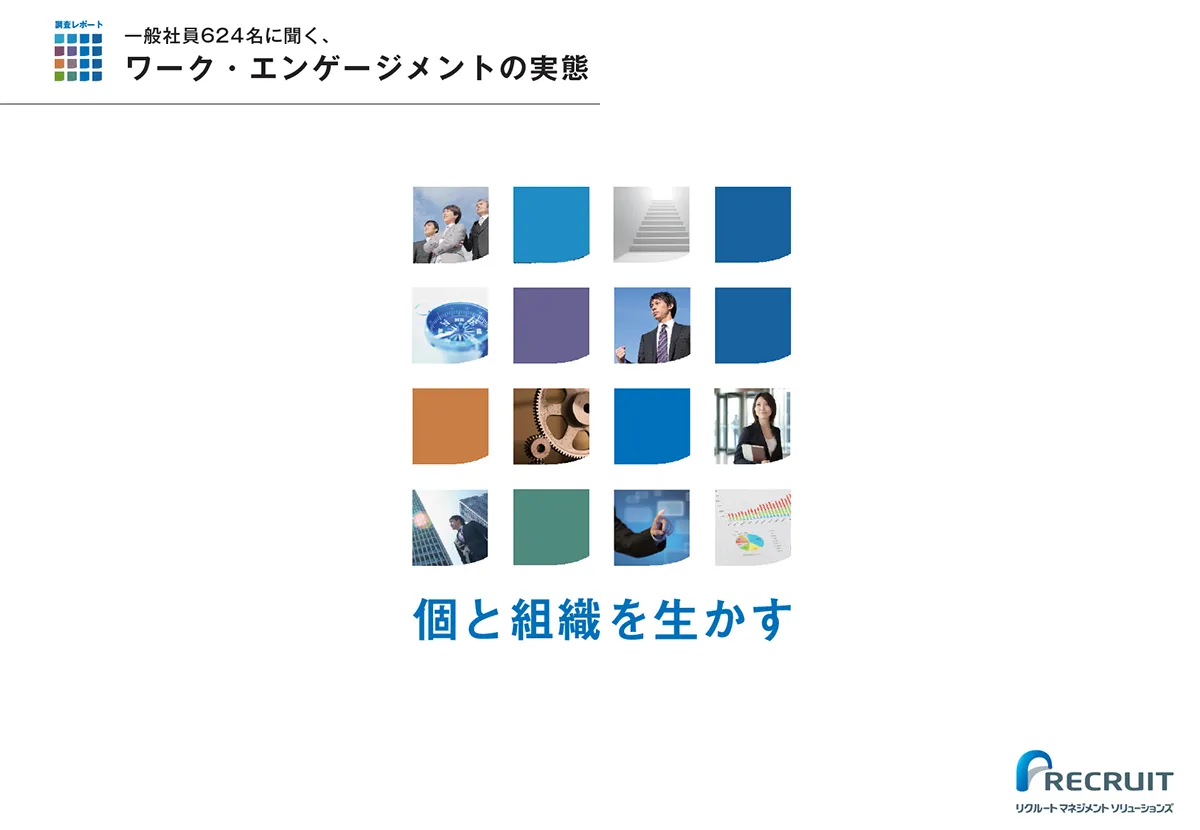
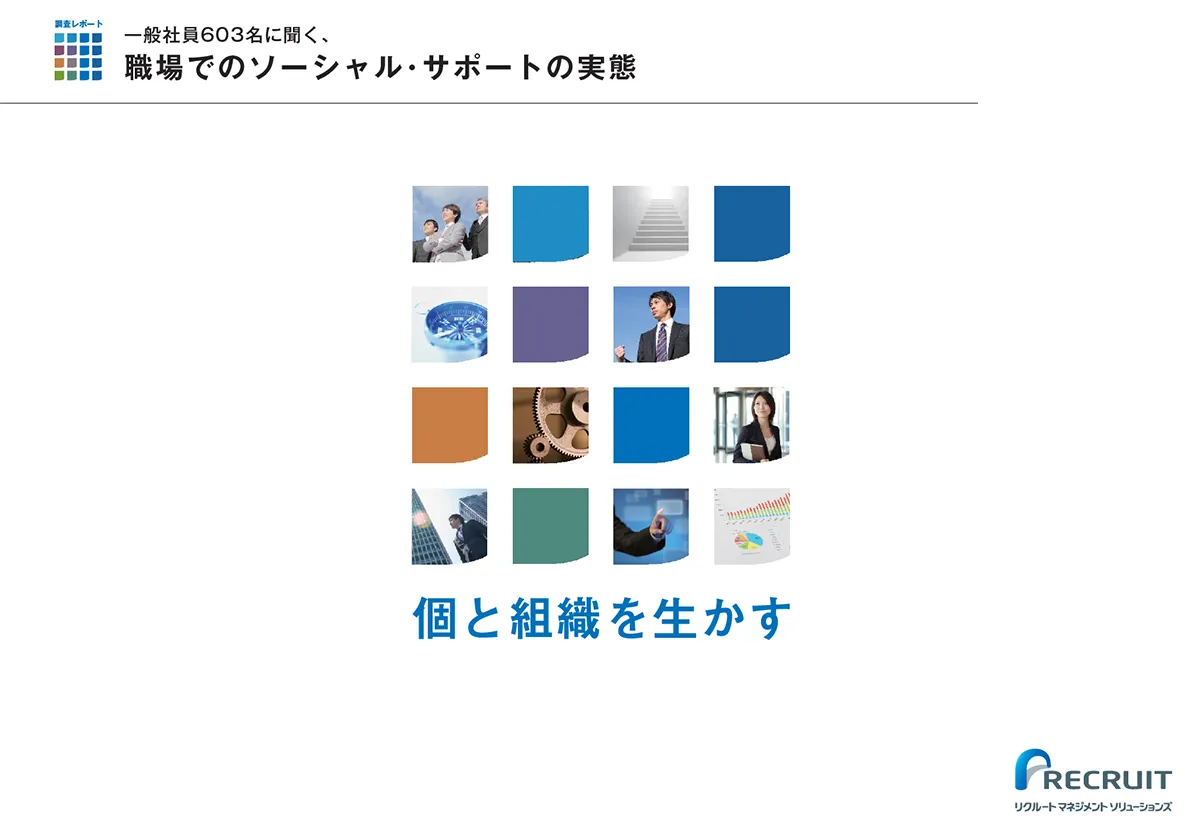









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての