インタビュー
早稲田大学商学学術院 清水 洋氏
オープン・イノベーションの歴史的背景と日本の課題
- 公開日:2019/03/18
- 更新日:2024/03/26

オープン・イノベーションには、どのような歴史的背景があるのか。世界ではどういった取り組みが行われているのか。なぜ今日本で流行しているのか。オープン・イノベーションのコツはどこにあるのか。早稲田大学商学学術院教授の清水洋氏に伺った。
オープン・イノベーションは系列システムの延長線上にある
2012年、一橋大学イノベーション研究センターは、オランダの化学会社・DSMと共にオープン・イノベーションのコンソーシアムを日本で立ち上げました。DSMは、世界的にいち早くオープン・イノベーションに取り組んだ会社の1つです。オープン・イノベーションは2003年にチェスブ ロウが提唱した概念ですが、彼が参考にした会社の1つがDSMでした。
SMなどの先進事例を調べていくうちに分かってきたのは、オープン・イノベーションの流れは1980年代から始まっているということです。
その頃、経営学では「アウトソーシング」「コラボレーション」「コアコンピタンス」「選択と集中」「make or buy」といったキーワードが注目されました。これらに共通するのは、「今の企業は経営資源を自社内に溜めすぎだから、社内の経営資源を絞り込んで不必要な経営資源を外に出し、その代わりに外部の力をうまく利用しましょう」というメッセージです。1980年代にこうした流れが生じたのは、アメリカに次のような変化があったからです。
アメリカでは、「垂直統合型組織」が歴史的によく見られてきました。例えば、紡績・紡織業なら、糸紡ぎも織物づくりも、巨大企業がすべてを行うのが普通でした。それどころか、企業は水平方向にもさらにくっついてコングロマリットとなっていました。対して産業革命時代のイギリスでは、糸の太さごとに小さな専門商社が存在し、紡績・紡織業者は製造に特化していました。
この違いの源は、制度整備と経済成長の関係にあります。19世紀後半から20世紀のアメリカは、経済成長のスピードが速く、商法・知的財産法・規格統一といった制度の整備が十分に追いつきませんでした。そのため、取引先の探索・交渉・監督などにかかる時間や労力、すなわち「取引コスト」が高く、自社で内製した方が効率的でした。反対に産業革命時代のイギリス経済は、制度が整備されていたため、取引コストが低くビジネスが垂直分化していたのです。
ところが、アメリカでも1980年代には制度が整ってきました。これにより取引費用が低下、加えて輸送機能が充実し、コンピュータが発達したこともあって、垂直分化が進んだのです。例えば、メーカーは独自の販売チャネルや小売網を放棄・縮小して製造に特化するようになりました。また、コングロマリットが解体され、ベンチャー企業の支援が盛んになりました。
この流れを後押ししたのが、実は日本企業でした。1990年代、日本の製造業が世界的な成功を収めた一因として、「系列」が注目されました。日本企業は系列企業の集団的な生産体制によって、垂直統合型のアメリカ企業との競争で優位に立ったのです。それを見て、欧米の企業が垂直統合を改めた面もあるのです。なお、オープン・イノベーションは、系列を一歩推し進め、系列を超えて外部を探索する動きと見ることもできます。つまり、日本企業の学んだ欧米企業を、さらにもう一歩進化させたものが逆輸入されてきたといえます。
オープン・イノベーションは社会課題解決に欠かせない
ところで、オープン・イノベーションがなぜ今これほど流行しているかといえば、その一因は、「社会課題解決」にあります。社会課題が複雑化しており、既存事業だけではなかなか解決できなくなってきています。社会課題を解決するためには、さまざまなステークホルダーと一緒に取り組むオープン・イノベーションのプロセスが欠かせないのです。
もう1つの要因は、「補完財」にあります。補完財とは、パンとジャムのように相互補完して価値を発揮するものです。製品・サービスの新奇性が高い場合、往々にして補完財の開発が追いつきません。それを、オープン・イノベーションで行うケースがあるのです。最たる例がアメリカの自動車産業で、T型フォードなどが爆発的に売れる一方で、道路という補完財が十分に整備されていなかった1900年代初め、業界関係者たちは自ら協会を立ち上げ、道路建設を進めました。今も大陸を横断するリンカーン・ハイウェイが、その代表です。
自社のコアコンピタンスを明確にすることが第一歩
これからオープン・イノベーションを進める企業には、補完財の開発から始めることをお勧めします。補完財のオープン・イノベーション戦略なら、日本でも比較的進めやすいはずです。
そのときに重要なのは、「自社製品・サービスをボトルネックにする戦略」です。補完財のレベルを高めることで、自社製品・サービスをボトルネックにすると、顧客がその製品・サービスの進化に価値を感じてくれるからです。事例を1つ紹介します。以前、GEがジェットエンジン用のブラケッ ト(取付具)のデザイン案をクラウド上で公募しました(3Dプリンティング・デザイン・クエスト)。世界中から設計図が集まり、インドネシアのエンジニアが最高評価を受けて賞金を得ています。このブラケットはジェットエンジンの補完財ですが、開発が難しく、優れた製品が市場にありませんでした。つまりこの時点のボトルネックはブラケットであり、そのままいくとブラケットがボトルネックになってしまい、相対的にGEのジェットエンジン本体の設計の重要性が低くなる恐れがありました。そこでGEは最高評価のデザイン案を公表し、ブラケットをコモディティ化することで、ボトルネックをジェットエンジンに換えたのです。そうして「ジェットエンジンの進化が鍵」という状況にしておけば、GEは新製品を出すたびに注目してもらえるというわけです。
この補完財のオープン・イノベーション戦略の第一歩は、自社の経営資源を棚卸しして、コアコンピタンスを明確にすることです。そうすれば、何をボトルネックにすべきか、何をオープン・イノベーションで開発すべきかが見えてくるはずです。また、設計と生産を切り離す、社内組織を整理する、既存取引先との付き合いを変えるといった意思決定もしやすくなるはずです。
最後に大きな話をすると、アメリカでは基礎研究は大学で行い、開発研究は企業が行うという分業体制ができつつあります(図表1)。日本も同様の体制をとって、企業が基礎研究の比率を減らせれば、より柔軟にコアコンピタンスにフォーカスできるようになるでしょう。また、スピンアウトやスピンオフを増やして、労働市場の流動性を高めることも重要です。オープン・イノベーションを増やすには、こうして日本全体で体制や仕組みを変えていく必要もあります。
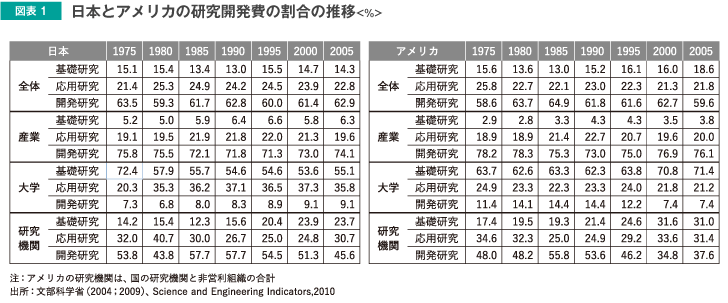
【text :米川青馬】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.53 特集1「オープン・イノベーションの歴史的背景と日本の課題 補完財のオープン・イノベーションから始めてみては」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は2019年4月1日時点のものとなります。
PROFILE
清水 洋(しみず ひろし)氏
早稲田大学商学学術院 教授
2007年ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス・アンド・ポリティカルサイエンスPh.D(経済史)取得。アイントホーヘン工科大学研究員、一橋大学イノベーション研究センター准教授などを経て2018年2018年より一橋大学大学院経営管理研究科イノベーション研究センター教授に就任。2019年4月より現職。著書に『オープン・イノベーションのマネジメント』(共著・有斐閣)などがある。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)









