インタビュー
一橋大学 野中 郁次郎氏
相互主観を醸成しながらスクラムを組んで進め
- 公開日:2018/05/28
- 更新日:2024/03/26
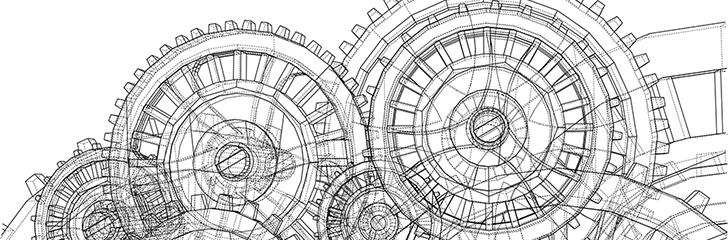
暗黙知と形式知の相互転換を核とする知識創造理論は日本発の経営理論として世界的にも知られている。その提唱者、野中郁次郎氏に、イノベーションが続々と起こり、社員全員が働き甲斐を感じ、いきいきと仕事に向かえるような企業組織のあり方を語ってもらった。
「俊敏なスクラム」とは
これからの組織を考える際の重要なキーワードの1つが「スクラム」だと私は思います。ラグビーでフォワードが肩を組んで押し合う、あのスクラムのことです。
洋の東西を問わず、現在、企業においてはそれぞれが専門と担当領域をきっちり分けながら、分業制で仕事を進めるというやり方が主流になっていますが、スクラムはそれとは逆で、それぞれが専門と担当をもちながらも、緩やかに連携し、関係性を深めながら、機動的に仕事を進めていくスタイルを指します。
前者が担当する業務を終えたらそれで終わりになるリレー型とすれば、スクラムは互いが皿の上で少しずつ重なり合う刺身型といえるでしょう。
このスクラムが最も普及しているのが、ソフトウェア開発の現場で、それは特に「アジャイル(俊敏な)・スクラム」と名付けられています。
1990年代半ばまでのソフトウェア開発はプロジェクトの工程を明確に分割し、前工程で作られた成果物に基づき、後工程の開発を順次進めていくやり方でした。まさにリレー型です。
それに対し、アジャイル・スクラムでは少人数の開発チームが専門性を生かしながら互いに協力し、決められた時間内で機動的な開発を行います。一度決まった計画も絶対視せず、臨機応変な変更を加えます。時には2人がペアになり、同じパソコンを共有しながら、プログラミングすることもあります。
このアジャイル・スクラム、実はその原点は私が書いた論文にありました。正確には、かつての日本企業にあったというべきでしょう。
私が竹内弘高さんと執筆し、1986年に『ハーバード・ビジネス・レビュー』に掲載された日本企業の新製品開発に関する論文がそれです。富士ゼロックスやホンダ、キヤノンといった日本の先進企業で行われていた製品開発は各フェーズが緩やかに連結され、重複部分がある状態で伸縮自在に進行していました。
われわれはそれを「ラグビーアプローチ」と名付け、本論の冒頭に、「スクラムを組んで進め」という言葉を置きました。
イノベーションの速度を上げるにはどうしたらいいか、という問題意識をもっていたジェフ・サザーランドというアメリカ人のコンサルタントが、たまたまこの論文を読み、そこから着想を得て、アジャイル・スクラムを考案したのです。
チームを組んで機動力を発揮していくことは、日本企業の得意技だった。それが今は劣化してしまいました。なぜでしょうか。
サイエンスよりアートを
バブル崩壊後の失われた20年で、アメリカ流の経営に過剰適応し、オーバー・プランニング(過剰計画)、オーバー・アナリシス(過剰分析)、オーバー・コンプライアンス(過剰法令遵守)の3大疾病にかかってしまった結果だと思います。
その背景にあるのが「経営はサイエンスである」という考え方であり、その典型がROE(自己資本利益率)経営です。ROEは「投資に対する利回り」ですから、その値を高めると株主は喜びます。
ROEの向上は利益を増やすことで実現できますが、借入金の増大、自社株買い、社員の解雇、研究開発費の削減などによる自己資本の減損によっても値を高めることができます。それは顧客や社員にとってはもちろん、経営の健全性という意味でも問題があります。
そうしたリスクを考えず、数値さえ高めればいい、とやみくもにROE経営を推進すると取り返しのつかないことになりかねません。
サイエンスを追求していくと、企業の存在価値は最大貨幣価値の実現となってしまいますが、果たしてそれでいいのでしょうか。私は、貨幣の向こうにある公共善の実現こそが企業が追求すべき最大価値だと考えています。そうだとすれば、企業経営にはアートの部分が不可欠となります。善はサイエンスが取り扱う領域の外にあるものだからです。
日本企業はそうしたサイエンス過剰を改めアートの部分を取り戻すと共に、スクラムをすべての仕事に適用するようなプロジェクトベースの自律分散的な組織体に移行していくべきでしょう。
仲間に対する「共感」が鍵を握る
スクラムを行うにあたっては、仲間に対する共感が醸成されていなければなりません。それは主観的で身体的な暗黙知が共有され、「自分たちは同じ感情や価値観をもっている」という感覚のことで、現象学でいうところの「相互主観」です。メンバー一人ひとりが自分の主観を保持する一方で、他のメンバーと共同で築き上げる「われわれの主観」のことです。
組織における知識創造は、一人称の個人の主観を受け止める仲間がいて、対話によってそれを二人称の相互主観に作り上げ、さらにそれを組織内で客観的に共有する共同主観へと成長させるプロセスをたどります。その結果、個人、集団、組織が一体となって、ビジョンやミッションを追求することができるようになります。その最も重要な基盤が相互主観、つまり仲間への共感なのです。
その共感経営を組織的に行っている企業が、ワイガヤで有名なホンダです。ホンダジェットの開発においても、クロスファンクショナルなチームを編成して、徹底的に議論を重ねることによって画期的なイノベーションを実現しました。
同じような試みとしては、京セラのコンパがあります。上司と部下、同僚同士が畳の上に車座になって座り、時には肘をぶつけ合いながら、鍋をつつき、酒を酌み交わします。手酌はエゴイズムの象徴として厳禁で、他人に徹底して注ぎまくれ、そうしたら、他人がお前に注いでくれるだろう、そう教えられます。そこでは、時には名誉会長の稲盛和夫さんが加わりながら、今の仕事のことはもちろん、キャリアや私生活、人間のあるべき生き方まで、毎回、さまざまなテーマで議論が繰り広げられます。
このコンパにせよ、ワイガヤにせよ、表面的な議論に終始しがちなブレーンストーミングとは決定的に異なります。それは人間と人間との真剣な対話の場であり、そこから、同じ組織に属する人間としての仲間への共感が芽生えてくるのです。
今こそアメリカ企業に学べ
この共感経営という意味では、シリコンバレーを中心としたアメリカの先進企業の試みが注目に値します。
例えば従業員の幸福度と業績の関係に着目、幸福度の改善と向上を目指し、自社の成長を促進させるチーフ・ハピネス・オフィサー(CHO)を置く企業が増えています。その幸福度は社員同士の共感意識と緊密に関係しているでしょう。
また、動画通信サービスのネットフリックスは、(1)一人前の大人だけを雇用し、報い、裁量を与える、(2)成果に関してありのままを話す、(3)優れたチームを作るのはマネジャーの仕事だ、(4)企業文化を形成するのはリーダーの仕事だ、(5)優れた人事はまずビジネスパーソンやイノベーターのように考える。人事として考えるのは最後である、という5つの理念に従って人材マネジメントを行い、急成長を遂げました。チームや文化を重視することは、共感経営の第一歩です。この理念は、日本の企業人事にとっても大いに参考になる内容だと思います。
アメリカの伝統的企業のGE(ゼネラル・エレクトリック)が2年ほど前に、有名な人材評価の仕組みの運用を取り止めました。年2回、業績結果とバリュー発揮度の2軸のレベルをそれぞれ3段階に分けてできる9ブロックに社員を順位付けする例の仕組みです。
その背景には、巨艦GEの文化を変革しITベンチャーのような機動力をもたせたいというトップの意向がありました。年2回しか行われない、杓子定規的な相対評価は社員の間に溝を生むだけだ、と考えたのでしょう。今では上司と部下が日常業務のなかで、「君はよくやった」「もっとこうした方がいい」という会話を当たり前のように交わしているようです。
われわれが30年前、ジャパン・アズ・ナンバーワンといわれて浮かれていたとき、アメリカ企業はわれわれの優れた点を学び、虎視眈々と逆転する機会をねらっていました。今度はわれわれが学ぶ番でしょう。できるはずですよ。スクラム重視の共感経営はわれわれが元々やっていたことですから。
【text :荻野進介】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.50 50号特別企画「個と組織を生かす 人材マネジメントのこれまでとこれから」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
野中 郁次郎(のなか いくじろう)氏
一橋大学 名誉教授
1935年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学経営大学院にてPh.D. 取得。知識創造理論の提唱者でありナレッジマネジメントの世界的権威。2008年5月5日のウォールストリートジャーナル「最も影響力のあるビジネス思索家トップ20」でアジアから唯一選出された。『失敗の本質』(共著、ダイヤモンド社)、『知識創造企業』(共著、東洋経済新報社)など著書多数。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての