インタビュー
早稲田大学 村瀬 俊朗氏
心理的安全性の高低を決めるのはまずリーダー
- 公開日:2018/01/15
- 更新日:2024/05/16

人間が恐怖や不安に打ち勝ち、新しい出来事に挑戦するには心のよりどころが必要になる。心理学では「セキュアベース(安全基地)」という。幼児にとっては母親がまさにそれにあたる。組織における心理的安全性も「安全基地が確保された状態」といえるかもしれない。アメリカでリーダーシップとチームワークの研究を行ってきた早稲田大学の村瀬准教授に話を伺った。
- 目次
- 心理的安全性は shared cognition(認知共有)から生まれる
- 余計なことはするな 上司の一言が現場を壊した
- 日本とアメリカで文化の違いが存在する
- 心理的安全性を高めるには人間同士が触れ合える場を
心理的安全性は shared cognition(認知共有)から生まれる
組織がうまく機能するためには、メンバーが思いや価値観、考え方を共有していなければなりません。その共有されたものが組織の文化に、マナーに、そして仕事の作法に転換します。そうした共有がうまく行われている組織ほどパフォーマンスがよくなります。組織心理学でいうところのshared cognition(認知共有)です。
サッカーの試合を想像してみてください。ボールを保持した選手が「あそこに蹴るぞ」というコミュニケーションをとらなくても、空いたスペースにボールを蹴り出し、阿吽の呼吸で、いつの間にか走ってきた味方にパスがつながるチームほど、多くの得点が期待できます。あいつがボールを持ったら、空いているスペースへの球出しを真っ先に考えるはずだ、という先読み、すなわち考え方の共有ができているのです。
心理的安全性も、そうした共有の結果、生まれてくるものだといえます。「こんなことを言ってもいいはずだ」「 こんな振る舞いをしても非難されないだろう」。そんな価値観が共有されているからこそ、メンバーが自分の考えを自由に吐露し、時にはリスクを冒してまでも、新しいことにチャレンジできるのです。
余計なことはするな 上司の一言が現場を壊した
イノベーションやクリエイティビティは上意下達のトップダウン組織からは生まれにくいもの。言葉を換えれば、それは心理的安全性の低い組織といえます。そうではなく、若手が活発に発言し、「私はこう考える」「自分はこうしたい」というアイディアを具申できる組織ほど、イノベーションが生まれやすいのです。
心理的安全性が低いと逆の不都合も起きます。
アメリカの航空会社の従業員調査の分析をお手伝いしたことがあります。複数の客室乗務員からこういう“愚痴”が上がっていました。機内でトラブルに見舞われ困っていた乗客を助けたところ、客からは大いに感謝されたのに、後で上司に呼ばれ、「なぜ余計なことをしたのだ 」と怒鳴られ、こってり油を絞られたというのです。
彼女たちは異口同音にこう述べていました。「頭にきて、それ以来、ルールブックにしか従わなくなりました」と。
これは上司の措置が心理的安全性を損なった例です。それまでは客室乗務員がルールブックにとらわれず、客のためによかれと思う行為を自分の裁量で行っていました。客にとっても「乗り心地のいい」航空会社だったでしょう。
それがルールブックにのっとった味気ないサービスに変わってしまいました。客室乗務員の意識もルールブック絶対になり、その改善を考える意識や、重大な事故につながる機内の些細な変化を察知する目も曇ってしまったかもしれません。
心理的安全性が低下すると、会社のブランドを毀損しかねないのです。実際、アメリカでは、心理的安全性の高さが現場の思わぬ事故を防ぐのに役立つという研究結果もあるくらいです。
日本とアメリカで文化の違いが存在する
心理的安全性を醸成するのはまさにリーダーの役割です。鍵を握るのは日常の行動です。若手が何か意見を言うと、「分かりもしないのに、何言ってんだ」「経験者でないと分からないんだよ」と切り捨てていたら、いざ会議となり、「忌憚のない意見を聞かせてくれ」と発言を促しても、皆貝のように押し黙るだけです。自分がいつも正しいと考え、下が何を言っても聞く耳をもたない。そういう人物がリーダーの組織は心理的安全性が最低レベルにあるといえます。
「俺はこう思うんだけど、君たちの意見を聞かせてほしい」。そんな会話ができる者こそリーダーになるべきでしょう。
ただ、会議の活性化に関しては文化の違いという問題が横たわります。アメリカで長く生活し研究を行ってきた私から見れば、年齢や性別を問わず、誰もが活発に発言するという文化が日本の組織には根付いていません。
目上の人を敬い、1歳でも年上の人は「先輩」、教師を「先生」とみなす儒教的文化があるから、会議では若手がどうしても萎縮してしまうのです。
その点 、アメリカは違います。いつ、いかなる場面においても自分の意見をもち、表明すべきだと、幼少の頃から教えられます。学校ではクラスにいる40人全員が自分の意見を述べますが、その多くは「優れた意見」ではなかったりします。
一方の日本は、40人のうち意見を表明するのは10人ですが、よく考え抜かれた 「優れた意見」のことが多い。どちらにも良い面、悪い面があるのです。
ただ、そんなアメリカでも昨今、心理的安全性の確保が改めて重要になっています。特にグローバル企業にあてはまります。言語や文化の壁を越え世界中から優秀な人材を集めても、心理的安全性が低ければ、イノベーションやクリエイティビティが生まれないからです。そればかりではなく、早期退職も起こり得ます。逆に高ければイノベーションが実現し、優秀な人材が長くいついてくれます。そういう評判が新たな人材を惹きつけることにも役立つでしょう。
心理的安全性を高めるには人間同士が触れ合える場を
心理的安全性が高い職場を作るには仕事を離れたパーソナルな付き合いの場を設けることも重要です。飲み会やホームパーティなどです。心理的安全性が確保されているということは、「この人にはこんなことを言っても大丈夫だ」という信頼感を抱いていることを意味します。お酒が入ってリラックスすれば胸襟を開き、本音の話が出るでしょうし、家族との会話や言動などから、その人の意外な一面が見え、いままでとは別の面からその人を見られるかもしれません。そうなると、「嫌だな」と思っていたことも許せるようになる可能性があります。信頼感が増すと、多少の欠点も目に入らなくなるからです。
このところ、一時中断していた社内運動会を復活させる日本企業が増えているようです。そうした活動も心理的安全性を高める手段になります。
この問題を深く考えていくと、実は「リーダーシップのありか」という問題に突き当たります。優れたリーダーシップが発揮された組織を作るのは、実はリーダーだけの責任ではありません。
リーダーも1人の人間です。欠点はありますし、ミスもします。それをカバーするのは部下の役割です。リーダーシップは上司から派生されるものではありますが、部下はそれを支え、健全なものに修正していかなければなりません。
リーダーは自分を支えてくれる部下に感謝し、頼りにします。折に触れて発言を求め、部下も期待に応えようとするでしょう。そうなると「これぞわがチームだ」とメンバー全員が思うような組織ができあがります。それこそ、心理的安全性が確保された組織といえます。
【text :荻野進介】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.48 特集1「組織の成果や学びにつながる心理的安全性のあり方」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
村瀬 俊朗(むらせ としお)氏
早稲田大学 商学部 准教授
1997年、日本の高校を卒業後、渡米。2011年、中央フロリダ大学で博士号取得。ノースウェスタン大学およびジョージア工科大学で博士研究員(ポスドク)をつとめた後、シカゴにあるリバラルアーツ系のルーズベルト大学で教鞭をとる。2017年9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



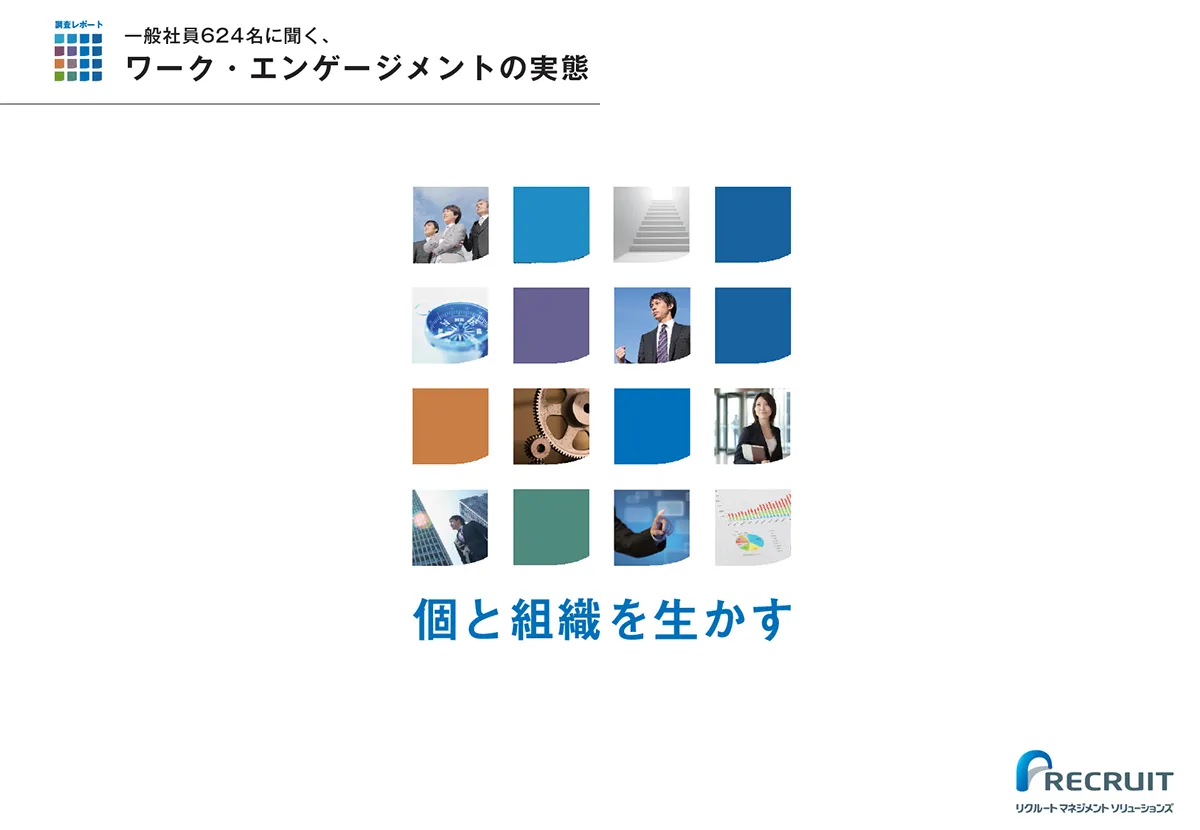
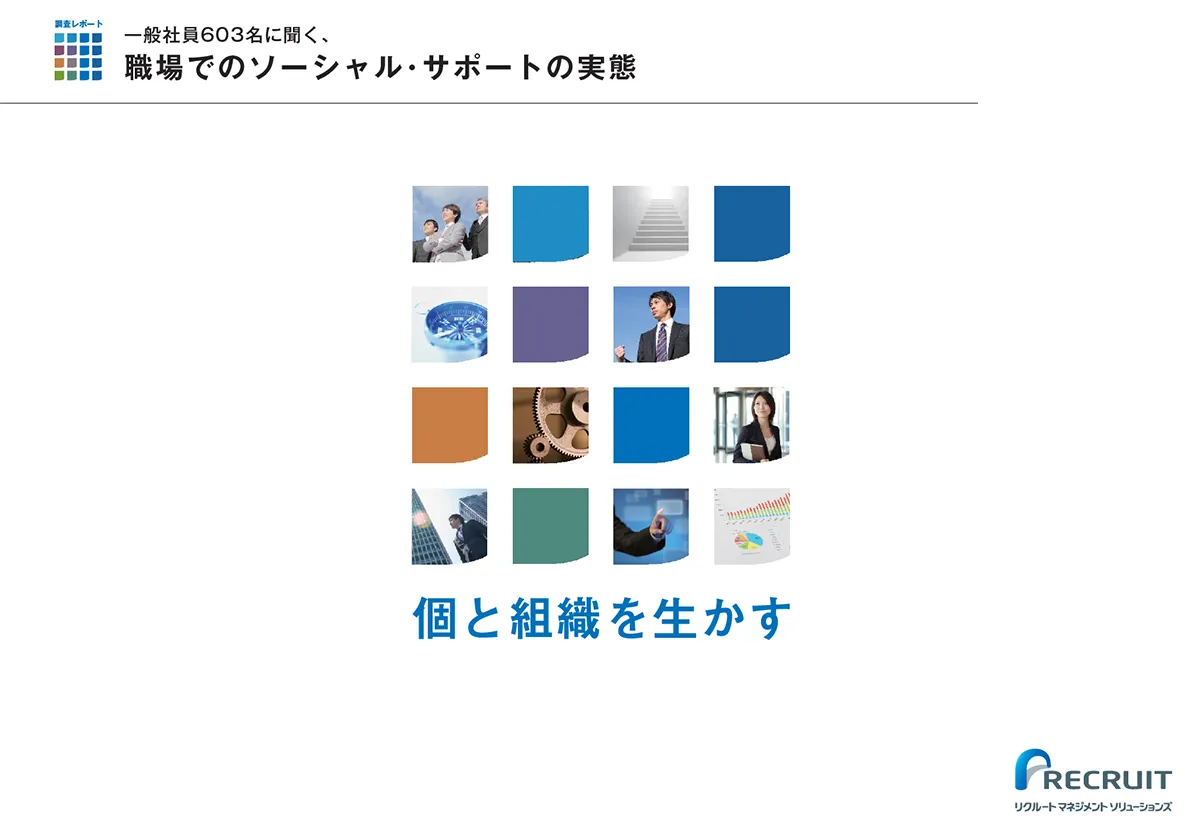









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての