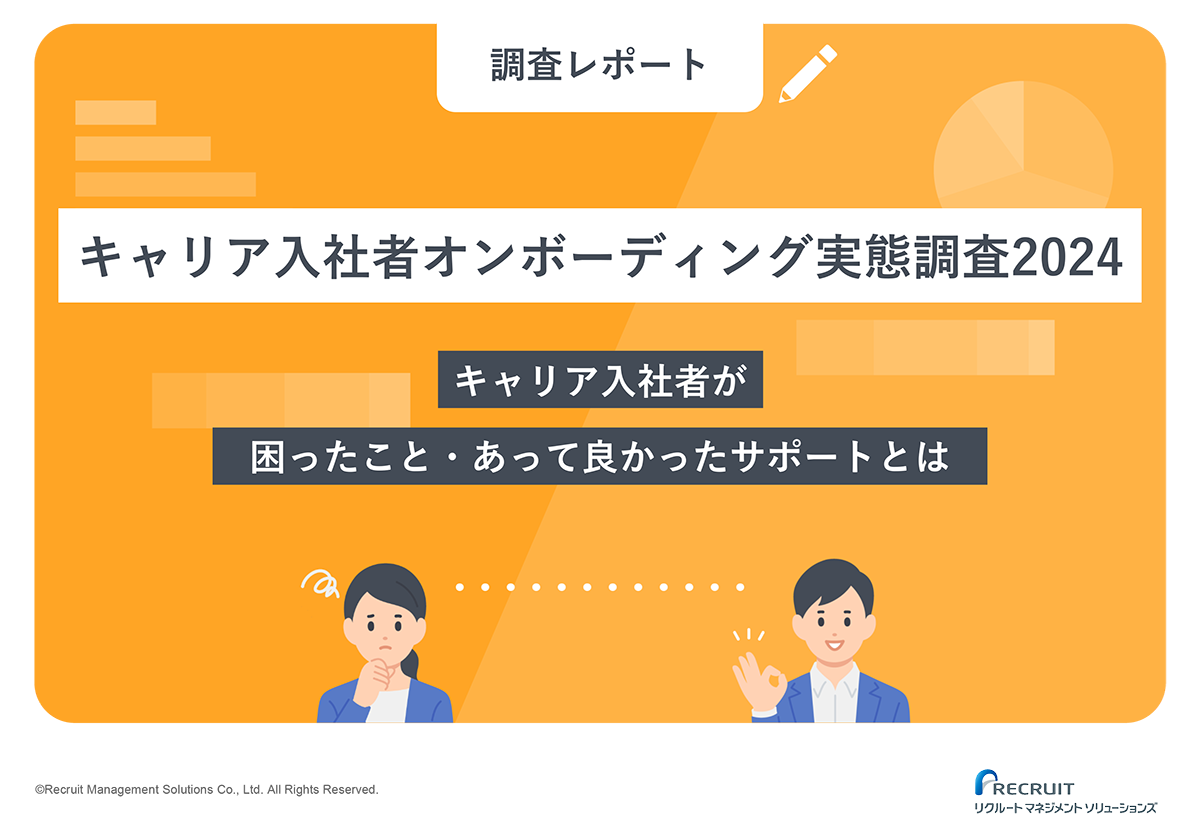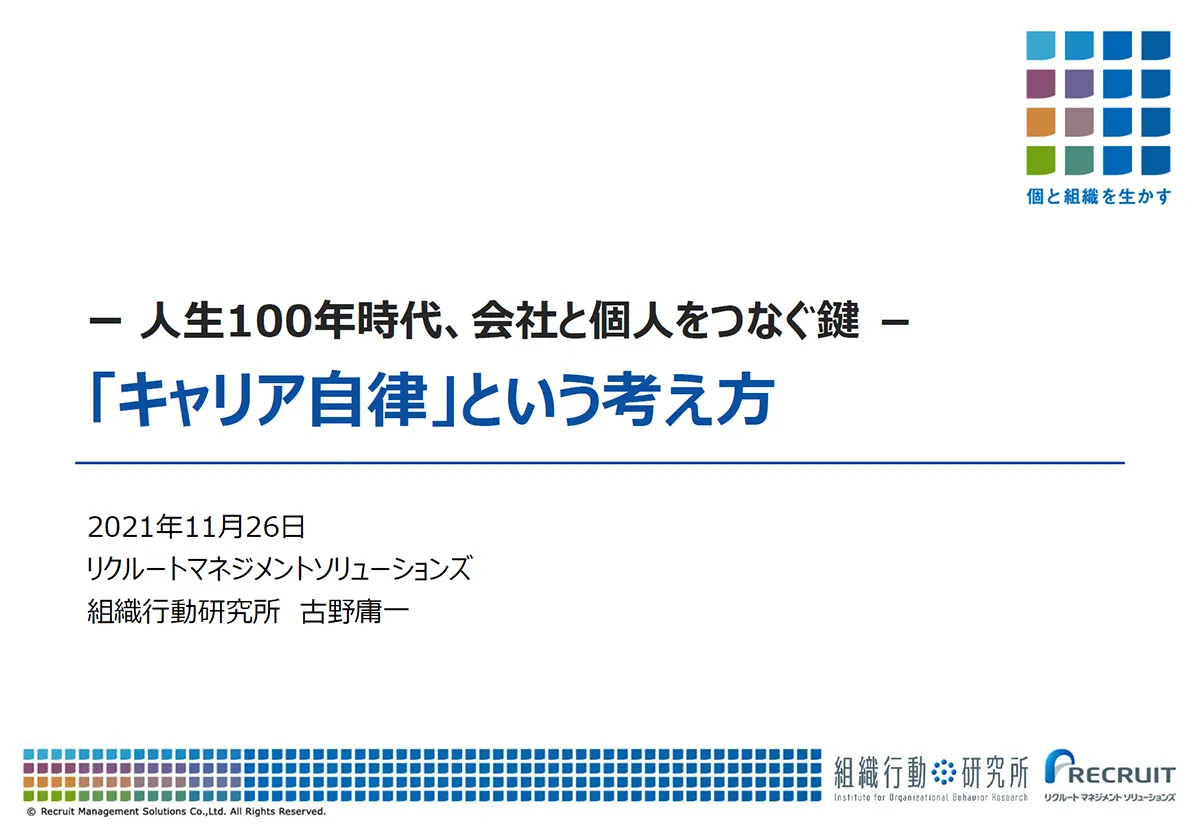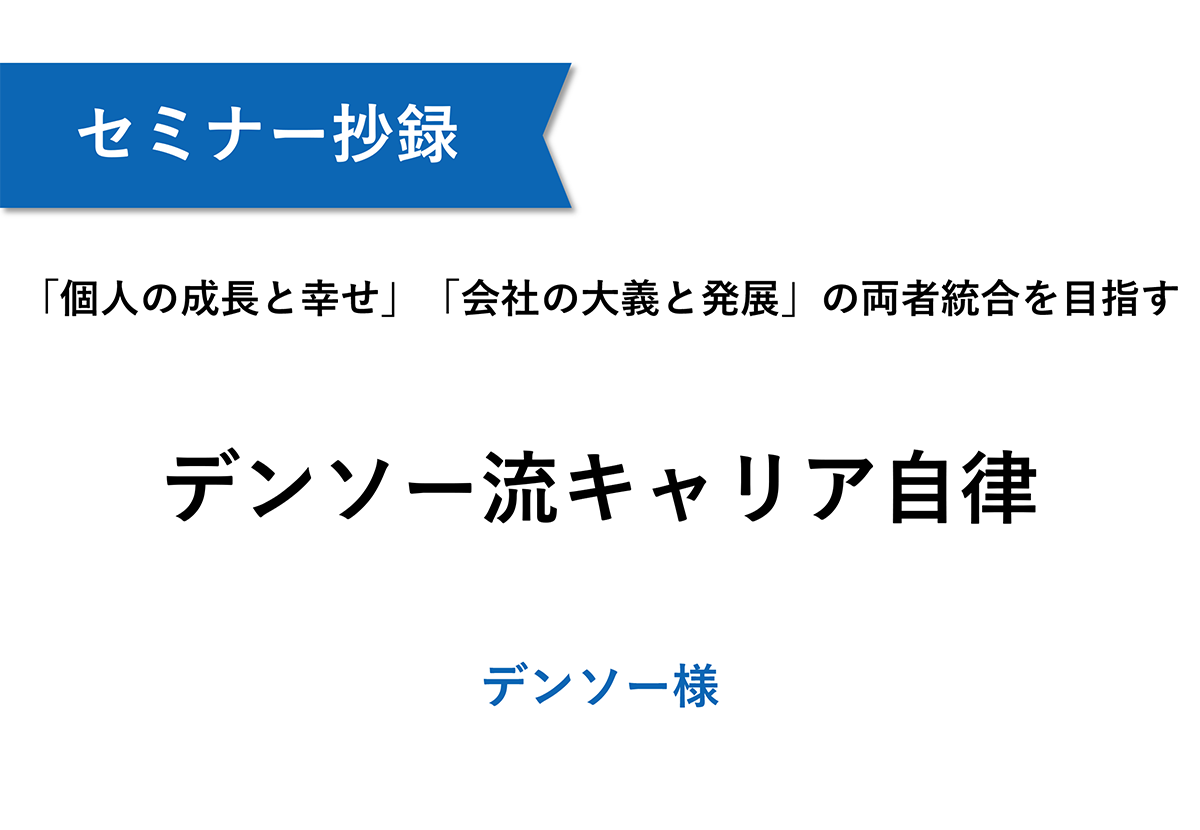インタビュー
東京学芸大学 浅野 智彦氏
働く私は私の一部 「自分」を自由に使い分ける時代
- 公開日:2017/09/15
- 更新日:2024/03/22

自分は何者か。特に若い頃などは、この問題に頭を悩ますこともあるだろう。アメリカの心理学者エリク・エリクソンが唱えたアイデンティティ(自我同一性)の問題だ。それはどうやったら確立できるのか。社会の変化がどう影響するのか。最近の動向を交えなから、東京学芸大学の浅野智彦教授に語ってもらった。
結婚と就職によってアイデンティティが確立
エリクソンがアイデンティティの概念を提唱したのは1960年代で、当時のアメリカでは多くの若者が公民権運動やベトナム反戦運動といった激しい政治活動に身を投じ、社会問題となっていました。彼はそうした現象の背後に、青年期に特有の「自分探し」という試行錯誤があると考えました。
アイデンティティは個人と社会の接点に成立します。自己認識だけではなく、社会における自分の居場所をきちんと確保できなければ確立できません。それはどんな場合なのでしょうか。
1つは結婚です。配偶者を得て子供を作り、家族を形成することを通じて、自分が何者かという答えが得られるというわけです。
もう1つが就職です。一生ものと思えるような仕事に就き、自己の力を思う存分、そこに投入することで、自分らしさを認識でき、安定した自己を獲得できるわけです。
ドイツ出身でユダヤ系のエリクソンは子供の頃は母親の不倫に悩み、大学を中退して各地を放浪し、ナチスの迫害を逃れてアメリカに移民したという経歴の持ち主です。そのアメリカは、同じようなヨーロッパからの移民で成立した国です。
そこに価値観を揺るがすような運動が起こり、自分は何者なのか、という問いに若者が向き合い始めました。1960年代のアメリカでアイデンティティの概念が唱えられ、人口に膾炙(かいしゃ)していった背景にそういう事情があります。
逆にいえば、価値観が普遍で、多くの人が1つのコミュニティで一生を終えた時代は問題にならなかったはずです。住む場所も就く仕事も、もしかしたら婚姻相手も決まっていたわけですから。
日本の場合、コミュニティが揺らぎ、離脱者が大量に生まれたのが同じ1960年代の高度成長期でした。地方から集団就職で大量の若者が都会に出てきました。彼らを包摂しようと、企業は年功賃金や手厚い福利厚生などで職場を“第二の村”化し、「ここが居場所だ」と彼らが感じられるようにしたのです。
社外でも若者たちのグループ活動が盛んで、合同ハイク、歌声喫茶といった場も人気でした。そこで出会った男女が結婚して家庭を築き、子供をもうけました。家族と仕事という2つの生きがいを手にしていたわけですから、自分は何者かというアイデンティティ問題に悩むことはまずありませんでした。
1978年に『モラトリアム人間の時代』という本が出版され、ベストセラーになります。モラトリアムは「アイデンティティ確立のための試行錯誤期間」を指し、同じくエリクソンが唱えた概念です。日本ではこのモラトリアムの方がメジャーになったのも、そんな事情が背景にあったからだと思います。
1990年代後半からアイデンティティが危機に
様子が変わり始めたのはバブル崩壊を経た1990年代後半からです。若者が自分の存在に不確かさを覚え始め、「自分探し」という言葉が流行りました。
企業の姿勢が大きく変わったからです。業績悪化に苦しんだ企業は人件費を減らし、1960年代に顕著だった「包摂の動き」を一変させ、その対象となる社員を絞るようになりました。1995年に日本経営者団体連合(当時)が発表した「新時代の『日本的経営』」が典型的な考え方です。正社員の数を減らし、非正規社員や専門人材を増やす雇用ポートフォリオの推進が提唱されました。
その結果、正社員になれない若者が増えました。お金がないわけですから結婚にも踏み切れない。一生ものの仕事も配偶者も見つからず、エリクソンがいうアイデンティティを確立できない若者が増えているのが今です。これはアメリカをはじめ、先進諸社会共通の現象です。
自分の居場所だと実感できる職場を確保できても、長くいられる保証はない。結婚できて子供が生まれても、すぐ離婚するかもしれない。エリクソンのアイデンティティは青年期に限った課題ですが、われわれが生きている現代社会は変化が激しく、それこそ青年期が生涯続くような状態になっており、自分とは何者かという問題は結婚と就職を主軸にしたエリクソン理論だけでは捉えられなくなっています。
複数の自分をもつ多元的自己が当たり前に
実際、アイデンティティはもっと多元的になっています。
1980年代の後半から、Aさんとは恋愛のこと、Bさんとは勉強のこと、Cさんとは趣味の話といったように、友人のタイプに応じ別の顔を見せる若者が増えてきました。
その背景にあるのが、消費社会の成熟による価値観の多様化です。分かりやすくいえば、学校のクラスがまとまりを失い、趣味の仲間が集うクラス横断のグループの方が活性化するような状況が起こってきました。
さらに1990年代にかけて、携帯やメールといったパーソナルメディアが普及し、同じ中学出身、同じ高校出身、同じクラス同士、同じサークル同士、バイト仲間といったように、複数のネットワークに所属しながら、別の顔を使い分ける学生が当たり前になってきました。
その下の世代は、フェイスブックやラインといった、パーソナル機能が一層強化されたメディアを駆使するSNS世代ですから、その傾向がさらに高まっています。
そうした多元的自己を駆使して大学までやってきた若者が就職した途端、職場だけの顔になるのは無理でしょう。「働いている私だけが本当の私じゃない」と思っているはずです。職場以外にも、別の自分の顔を見せる場があるわけです。その場は趣味のサークルかもしれないし、ボランティア団体かもしれません。
企業側も包摂の姿勢をますます弱め、社員の副業を大っぴらに認める動きも出てきました。
私は学生によく言うんです。働くことは生活の一部であり、職場はそのための場所にすぎないから、別の場面で通用する顔を複数もっていた方がいいよ、と。
職場にしか生き甲斐がない人間は労働者としても弱い。それよりは活躍の場を複数もった自立的な人間のほうが思考も柔軟で、いざという場合、頼りになるのではないでしょうか。企業も積極的に働きかけ、社員が多元的な自己をもてるようにするべきです。
【text :荻野進介】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.47 特集1「職場での「自分らしさ」を考える」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
PROFILE
浅野 智彦(あさのともひこ)氏
東京学芸大学 教育学部 教授
1964年生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。専門は社会学(自己論、アイデンティティ論、物語論)。著書『「若者」とは誰か』(河出書房新社)、『趣味縁からはじまる社会参加』(岩波書店)、『自己への物語的接近』(勁草書房)など。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)