インタビュー
日本経済大学大学院 古川久敬氏
評価のスタートは仕事の意義と価値の意識化
- 公開日:2017/05/15
- 更新日:2024/03/22

これまでに経験のない新規の課題に取り組む状況が増えていることから、継続反復型だけでなく新規挑戦型のモチベーションをも促し、組織や従業員の成長と成果につなげていく評価が求められるという。リーダーシップとチームマネジメント、モチベーションを専門とする古川久敬氏に伺った。
- 目次
- 給与は多くなるほどに重要度は頭打ち 達成感や成長感は得るほど重要性が増大
- 部下のモチベーション向上・維持には 取り組む仕事の意義の「意識化」が必須
- モチベーションには2つの種類がある プロアクティブが必須になっている
給与は多くなるほどに重要度は頭打ち 達成感や成長感は得るほど重要性が増大
経済的報酬の個人格差を謳う評価制度や、結果の良否評価に偏った結果主義の評価制度では、モチベーションを高めることは難しい。
報酬のもっている特性、そして評価と連動している「目標管理制度」を、その本質をよく理解した上で活用することで、新規挑戦型(proactive)のモチベーションも高めることができます。
まずは報酬とモチベーションの関係から考えましょう。報酬には経済的報酬と心理的報酬の2種類があります。いずれも、それが納得できる形で得られるとうれしい。そしてモチベーションにつながります。
しかし、両者の間に、気づいておくべき違いが2つあります。1つは、経済的報酬=給与に対する納得感(公正感)は総じて低いということです。どの企業でも、自分の役割や職責に比して、給与をもらえていない、不公正、不満と感じている従業員の割合は多い。私たちが“不足”の方に敏感であることによります。
もう1つは、給与は一定程度以上もらうと、その重要度は頭打ちして、納得感や満足感との関連は弱くなります。他方、達成感、承認、成長感などの心理的報酬は、得るほどに重要度が高まり、さらにもっと欲しくなることが実証されています。
かつて、ハーズバーグは、給与のように不足が気になるものを「衛生要因」、達成感、承認、成長感のように多いほど意欲につながるものを「動機づけ要因」と呼びましたが、やはり慧眼といえます。
つまり、評価制度をもとに、給与の多寡を操作すれば従業員のモチベーションをコントロールできるわけではないということです。可能な限り、公正感や納得感を伴う給与を用意した上で、達成感、承認、成長感を実感させる機会をもたせられるかが、モチベーションマネジメントの鍵です。
経済的報酬の頭打ち効果を補填する上で、心理的報酬の充足は、大きな効力をもっています。
部下のモチベーション向上・維持には 取り組む仕事の意義の「意識化」が必須
それと関連して、「目標管理制度」を、結果評価と処遇の制度と思い込んでいる人は多い。大きな誤解です。結果評価と処遇はもちろん重要なことですが、効果的なモチベーションマネジメントという点からは、中核ではありません。
仕事への取り組みには3つの段階があります。すなわち、(1)よしやるぞ、やってみようの「着手」(取り組み始める)段階。(2)続けよう、粘ろう、我慢と辛抱の「中途」段階。時間の上ではこれが一番長い。そして、(3)やってよかった、次もまた、次こその「完了・結果」段階です。
結果評価と処遇は、これら3段階の最後の段階にしか関係していません。モチベーションマネジメントからすると、それに先立つ着手段階と中途段階はとても重要です。どんなことがあっても、結果は、着手と中途の後です。また着手と中途段階をおろそかにして、期待する結果は出ません。
心理的報酬(達成感、承認、成長感など)の芽は、仕事の着手段階において、自らが取り組む仕事の「意義、意味、価値」を意識化することで膨らみます。意義、意味、価値を感じられる仕事こそが、働きがいのある仕事に他なりません。
取り組む仕事が、(1)同僚や職場、会社にとって、(2)顧客や社会にとって、併せて(3)自分自身の成長にとって、意義があり、価値をもたらすと感じられるものであれば、誰もがやりがいを感じられます。自分のアイデンティティーともなり、「よしやるぞ」のモチベーションを生みます。
職場や会社、顧客や社会だけの意義では、長続きできない。他方、自分のためだけの意義では独りよがりになる。三者を満たせるのが理想です。
着手段階で「意識化」するのは、意義や価値だけではありません。どういう成果を出すのか、どう取り組むのか(方法とシナリオ)も含まれ、そして実行に移す。その後に、結果が出る。これら一連の意識化をすんなりと自分でできる人もいれば、難しい人もいます。後者には、上司の問いかけやコーチングが必要で、それはとても効果があります。
こうして、「目標管理制度」は、結果の評価や処遇の制度でもある以上に、「意識化」によって働きがいを刺激し、KP(キーパフォーマンス)を明確にし、心理的報酬(達成感、承認、成長感など)を得る機会を増やす。ここに本質があります。
モチベーションには2つの種類がある プロアクティブが必須になっている
モチベーションには、継続反復型(reactive)と新規挑戦型(proactive)の2種類があります。両者は基本的には独立したものです。
多くの人が気づいているように、今日、いずれの組織でも、これまでに経験のない(未経験)課題への取り組みが増え、同時に、それを他との新たな連携と協働のなかで進めるようになっています。
そのために、マネジメントに問われることが3つあります。第1は、上司自身も未経験の課題に携わることが多くなっている。それ故に、自分が部下よりも何事においても精通し、優れているという状況ではなくなっていることを理解しておく必要があります。
第2は、未経験のことなので、経験による学習(経験知)が蓄積されてはおらず、確たる計画は立たない。それ故に、仮説をもとにした「実験」の着手が必要で、proactiveな(予測を立ててチャレンジしていく)モチベーションが必須です。そのためにも、前述のように、着手段階で、取り組む仕事の「意義や価値」の意識化と共に、目指す成果、取り組み方略(方法とシナリオ)を意識化し、実行することが重要になる。そうした「実験」に積極的に取り組む様子、および「実験」の成否にかかわりなく、そのプロセスから学習する姿勢は、もちろん高い評価の対象となります。
第3は、部下との間、あるいは連携を必要とする他部門(他部署)との間で、面談やミーティングを通して、経営理念や課題、部門や職場の目標を確認し、「共に見るもの」(創り出す価値など)を、意識化し、言語化して設定できることです。これにより、相互間に壁や溝があったとしても、それを緩和させ、乗り越えた感じをもてるようになります。
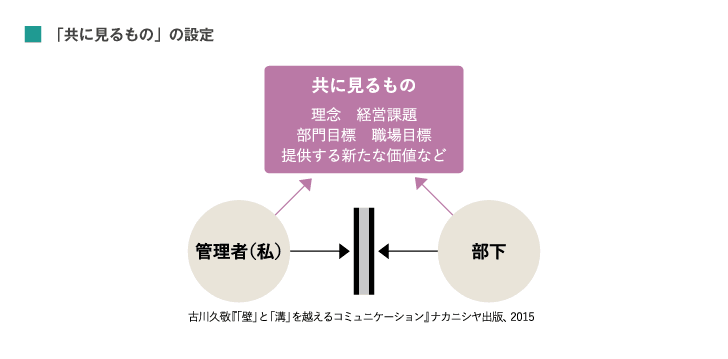
【text :米川青馬】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.45 特集1「心理学からみる人事評価」より抜粋・一部修正したものです。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属・役職等は取材時点のものとなります。
PROFILE
古川久敬(ふるかわひさたか)氏
日本経済大学大学院 経営学研究科 教授
九州大学名誉教授。九州大学大学院教育学研究科修士課程修了。教育学博士。鉄道労働科学研究所主任研究員、ニューヨーク州立大学ビンガムトン校経営管理学部客員研究員、九州大学大学院人間環境学研究院教授などを経て現職。専門は組織行動、人的資源管理、組織心理学。『「壁」と 「溝」を越えるコミュニケーション』(2015年 ナカニシヤ出版)など著書多数。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


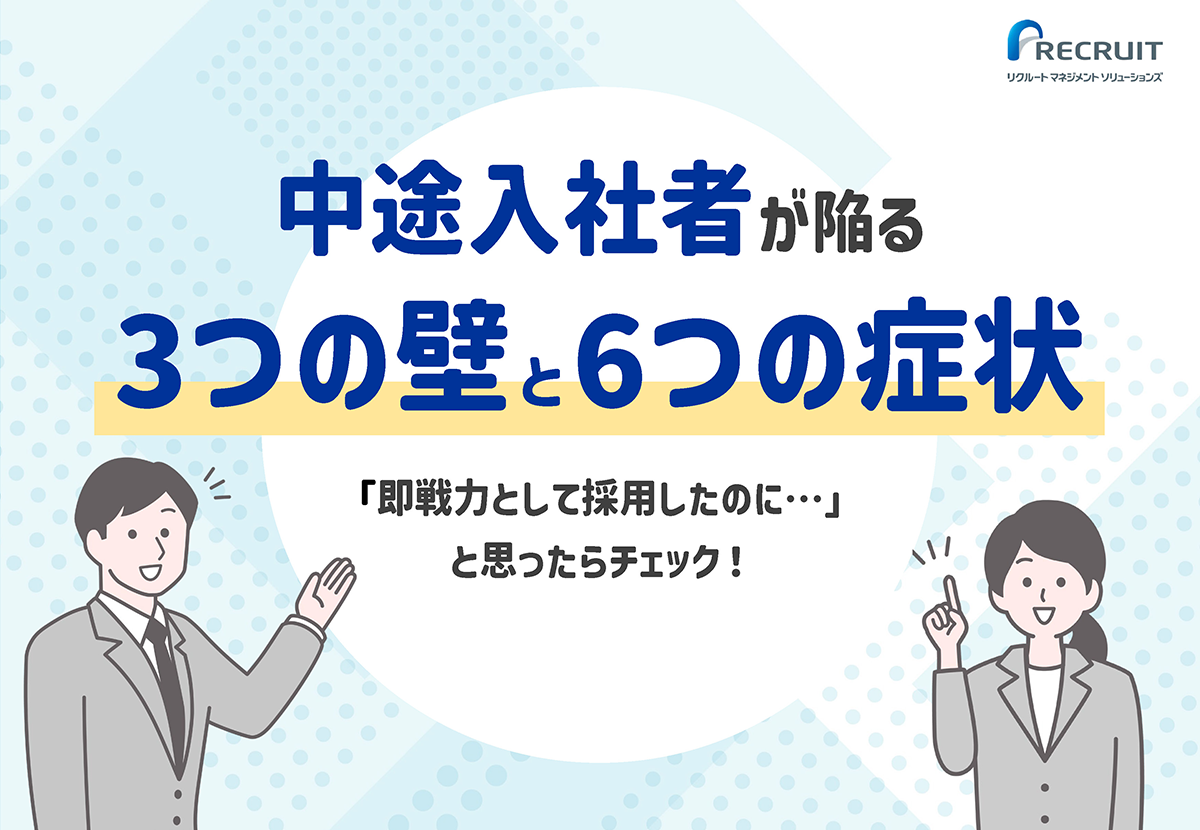
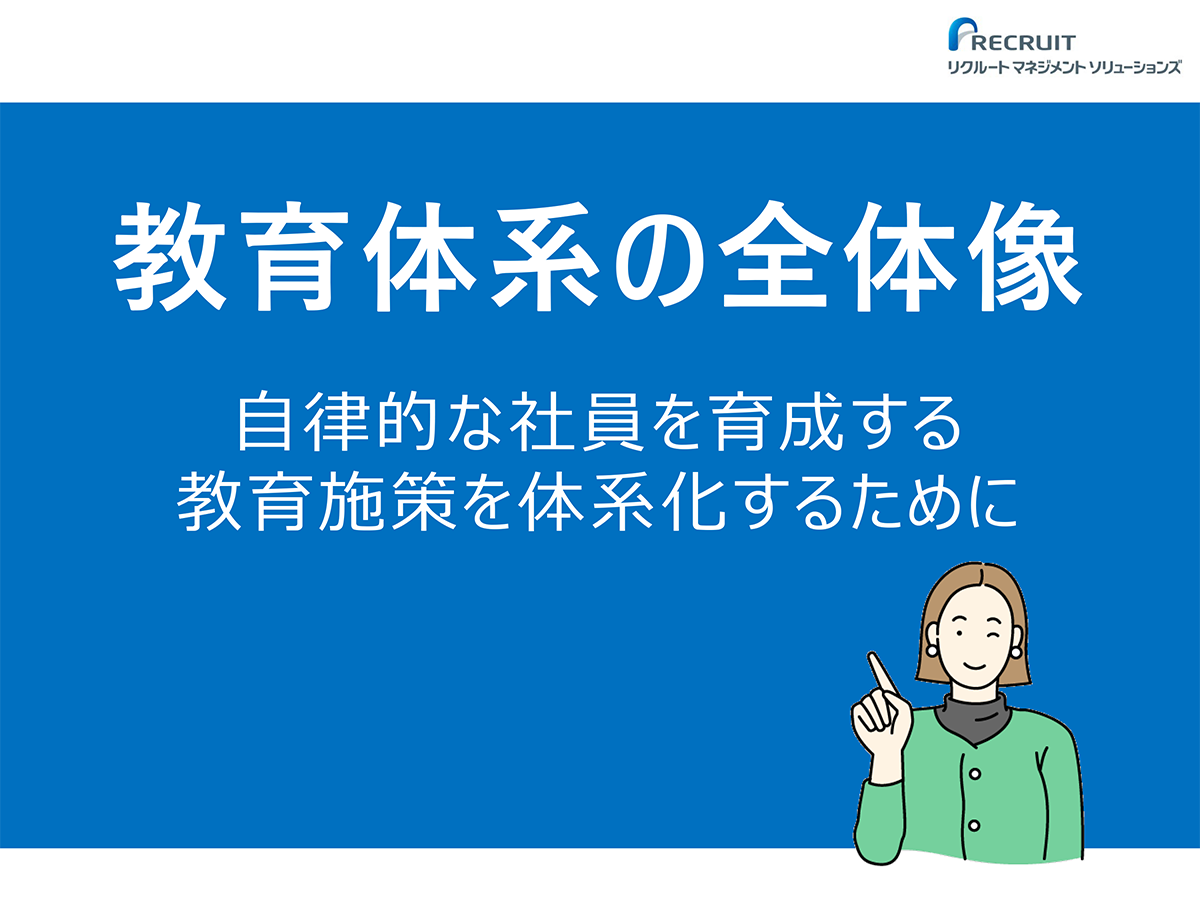
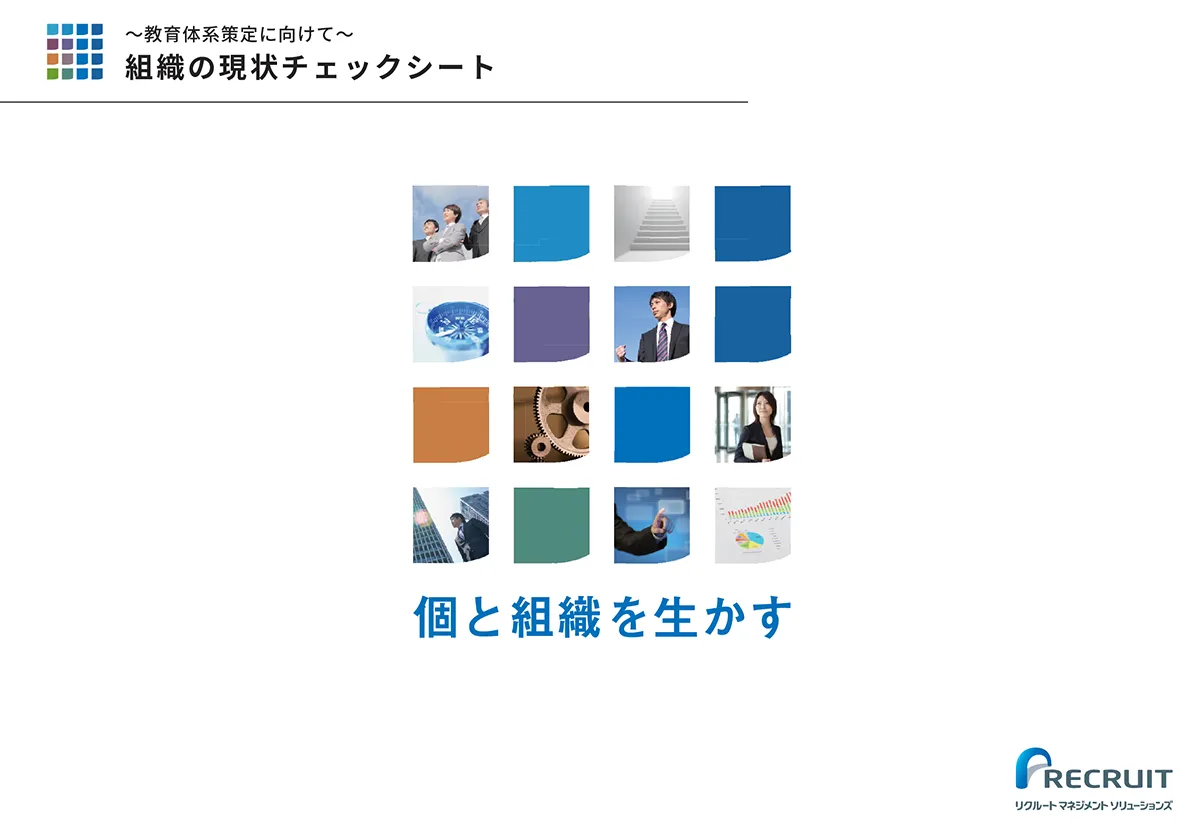









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての