インタビュー
慶應義塾大学 中室牧子氏
子どもへの教育投資のタイミングは?
- 公開日:2016/11/21
- 更新日:2024/03/22
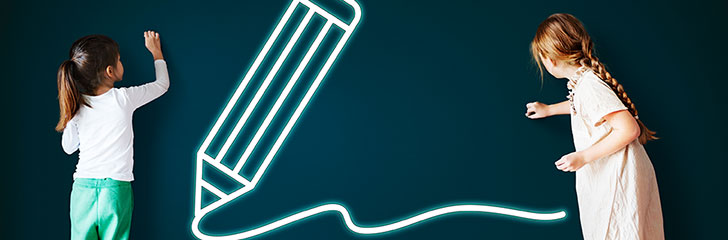
国や社会にとって、これからを担う子どもへの教育投資は、重要な課題である。
少子化、グローバル化など、わが国を取り巻く危機的状況を回避するための教育投資はどうあるべきか、文部科学省を中心に議論が進んでいる。限られた予算のなかで、誰にどのような教育を行うのが効果的か。教育経済学の研究成果と今後の取り組みをご紹介しよう。
4歳のときの100円が60年後には300倍に
教育経済学でよく用いられる概念の1つに「教育の収益率」なるものがある。経済学では教育を「投資」と考えるので、教育への投資リターンを計測するのである。文部科学省の調査によると、子どもを公立学校に通わせている保護者は中学校3年生のとき、すなわち高校受験の直前に最も多くの学習費をかけている。しかもそのほとんどが学習塾などの学校外活動費だ。しかし、教育経済学の研究蓄積によると、最も教育への投資リターンが高いのは、中学校3年生のときではなく、子どもが小学校に入学する前であることが示されている(図表1)。
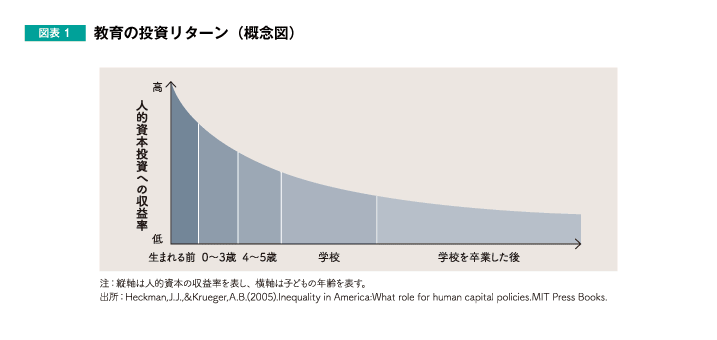
この図からも明らかなように、教育の投資リターンは、子どもの年齢が小さいうちほど高く、その後は低下の一途を辿る。この概念図の根拠となるのが、ノーベル経済学賞を受賞したシカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授による「ペリー幼稚園プログラム」の効果測定である。ペリー幼稚園プログラムは、ミシガン州のある地域で貧困層の3~4歳の子どもを対象に質の高い就学前教育を提供するために政府の支援を受けて1960年代から開始された。
このプログラムは、正確に効果を測定するため、ペリー幼稚園に通う子どもと通わない子どもをランダムに振り分け、両方に対して約40年間追跡調査が行われた。ヘックマン教授の研究で明らかになったことは、図表2のとおり、 6歳時点のIQや19歳時点の高校卒業率や27歳時点の持ち家率、40歳時点の所得などは、ペリー幼稚園に通う子どもの方が通わなかった子どもに比べて高かった。一方、生活保護の受給率や犯罪率などは低かったので、質の高い就学前教育がもたらした教育の社会的収益率はかなり高いということが明らかになったのである。ヘックマン教授の推計では、4歳のときに国が投資した100円が65歳のときに6000円から3万円になって社会に還元されるということになる。
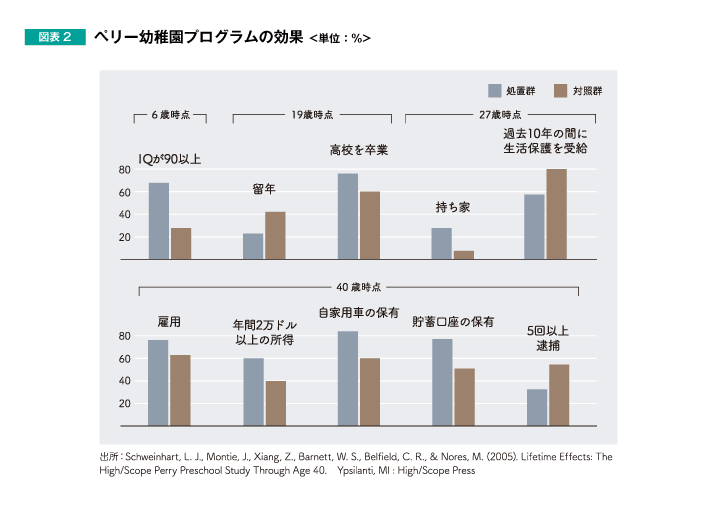
本稿では、こうした米国における研究成果から日本が学ぶべきことを整理したい。第1に、日本では、就学前教育が重要であるというコンセンサスが全くないということだ。冒頭のデータにも示されたとおり、家計は受験の前に学習塾などへの支出を増加させるような投資を行っているし、最近の待機児童問題の深刻さから見ても、国が就学前児童に積極的に投資をしているとは到底思えない。現在、わが国の政府による年間1人当たり支出は、就学前の子どもに対しては100万円以下にもかかわらず、100歳の老人に対して500万円が分配されているという推計もある。
また、現在就学期の子どもの相対的貧困率は6人に1人となる高水準に達しているが、最近の日本財団の「子どもの貧困の社会的損失」推計によると、このまま子どもの貧困を放置すると最も保守的な推計でも、社会が被る経済的損失は約2.9兆円、政府の財政負担は1.1兆円増加することが明らかになっている。そもそもペリー幼稚園プログラムも、貧困の世代間連鎖を断ち切ることを目標の1つとして設計され、就学前教育の拡充を図ることがその有力な方法であることを示している。
第2に、米国では、ペリー幼稚園プログラムのような追跡調査が多く行われ、教育の「効果」が正確に計測されているという点である(米国の追跡調査で最長のものはすでに70年に達している)。わが国ではたびたび「教育の効果はすぐ出ない」と指摘されながらも、同一個人を長期間追跡するという調査を行ってこなかったがために、「いつ」の「どのような」教育の投資リターンが高いのか、にこたえられるだけのデータが存在していない。
長期的な追跡調査が日本でも始まる
しかし、最近ようやくこうした問題に改善の兆しが見えてきた。1つは日本財団が子どもの貧困の連鎖を断ち切ることを目標に、小学校低学年以下の子どもを対象にした教育支援に50億円を拠出することを発表したのだ。このサービスの第1号拠点は、埼玉県戸田市で展開されるという。埼玉県では、昨年から子どもの認知能力、非認知能力を計測する優れた追跡調査を独自に実施しており(「埼玉県学力・学習状況調査」)、この2つが合わされば、まさに日本版ペリー幼稚園プログラムが始動するというわけである。私も研究者の1人として、この効果測定に参画するつもりだ。
米国で1960年代にはすでに実施されていた試みを、日本で開始するまでに50年を要したという事実には愕然とせざるを得ないが、こうした試みをゼロから立ち上げる関係者の努力を考えれば、この研究におけるあらたな発見がペリー幼稚園プログラムのような「知的公共財」として、社会に貢献することを願うのは私ばかりではなかろう。
※本稿は、弊社機関誌RMS Message vol.43連載「<寄稿> 中室牧子の“エビデンスベーストが教育を変える”」より転載・一部修正したものである。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
PROFILE
中室牧子(なかむろまきこ)氏
慶應義塾大学 総合政策学部 准教授
1998年慶應義塾大学卒業。米ニューヨーク市のコロンビア大学で学ぶ(MPA、Ph.D.)。専門は、経済学の理論や手法を用いて教育を分析する「教育経済学」。日本銀行や世界銀行での実務経験がある。主著に『「学力」の経済学』(ディスカヴァー・トウエンティワン)など。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



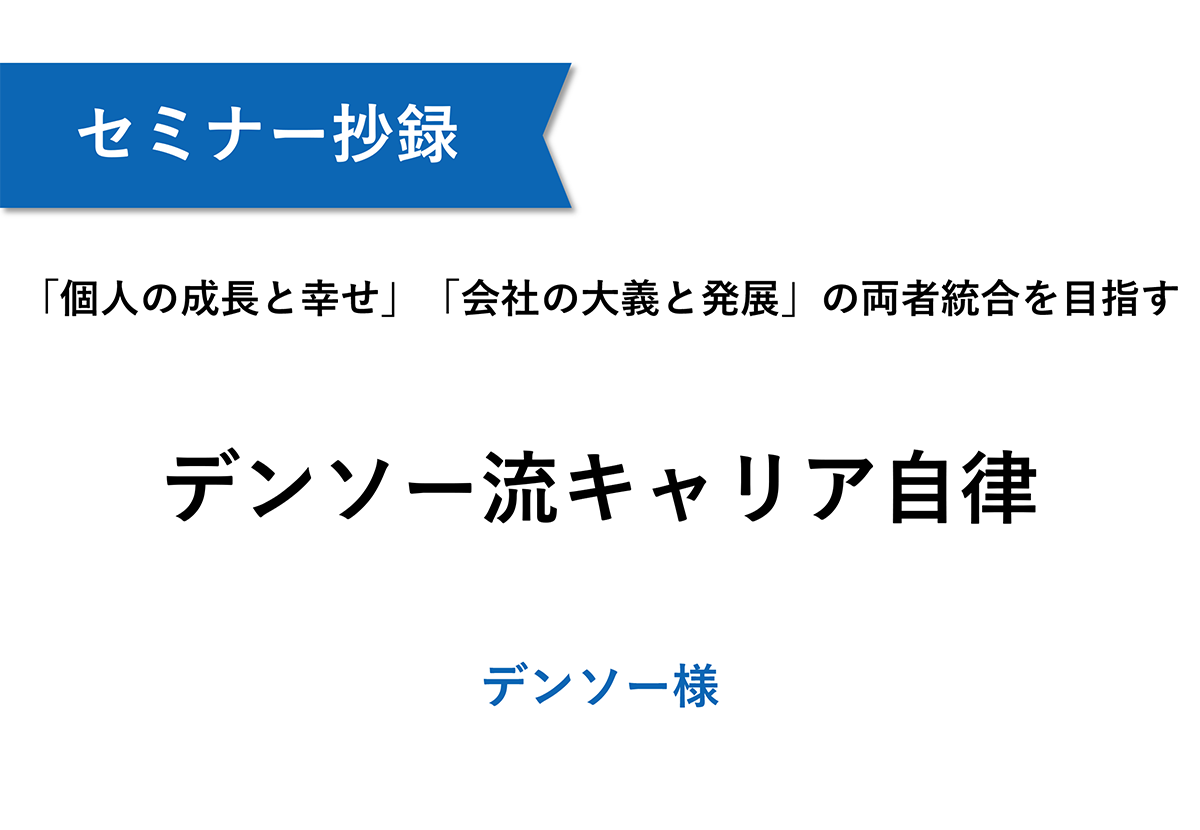









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての