- 公開日:2022/08/05
- 更新日:2024/05/16

2020年1月の国内での新型コロナウイルス発生をきっかけに、仕事と学習のリモート化が大きく進展した。これにより、会社員の仕事に関する学びには、どのような変化があっただろうか。この調査では、コロナ禍前と比較して、勤務形態が「出社ワーク中心」から「テレワーク中心」へと変化した会社員を対象に、自身の仕事に関する学びの実態や変化についてたずねた。なお、この調査では「学び」について、知識やスキルの習得だけでなく、職場での経験や対人関係からの学びなども含めて、広く捉えている。
- 目次
- 仕事と学習のリモート化が学習に与える「プラス」と「マイナス」の影響
- 1. テレワーク中心になったことで、「仕事に関する学びの満足度」「仕事に関する新しい学びの有無」はどのように変化したか
- 2. 学習資源としての「仕事に関する学びに使える時間」「対人ネットワーク」「学習機会」はどのように変化したか
仕事と学習のリモート化が学習に与える「プラス」と「マイナス」の影響
国土交通省(2022)*1によると、2021年11月時点における雇用型テレワーカーの割合は27.0%で、最初の緊急事態宣言時の一過性の増加は落ち着いたものの、コロナ禍前(2019年)の14.8%と比べて、12.2ポイント増となっている。テレワークによる「通勤時間が減った」「自分や家族のための時間を取りやすくなった」といった時間的な余裕の増加は、もっと学びたいと考える社会人の「仕事が忙しく時間が取れない」「プライベートが忙しく時間が取れない」という悩み*2を解消し、学びにとってプラスの影響を与える可能性がある。一方、テレワークにより、「同僚と、お互いの仕事の進捗を気にかけ、助け合う機会」「雑談や思いつきレベルのアイディアの共有」などのコミュニケーションが減ったと感じる人は少なくない*3。これらは、職場での学びにマイナスの影響を与える可能性がある。
仕事のリモート化と同時に、会社員の学習機会のリモート化も進展した。パーソル総合研究所(2021)*4によると、2020年にオンライン集合研修の実施を増やした企業は75.0%であり、さまざまな研修でオンライン形式が採用されていることが分かる。また、各種のセミナーや勉強会は、オンライン開催が主流になってきている。こうした学習機会の対面からリモートへの変化は、会社員の学びに、プラスとマイナスのどちらにも影響する可能性がある。
*1 国土交通省(2022)「令和3年度 テレワーク人口実態調査」
*2 リクルートキャリア (2019)「人生100年時代に働きながら学ぶこと」実態調査
*3 リクルートマネジメントソリューションズ(2020)「テレワーク緊急実態調査」
*4 パーソル総合研究所(2021)「コロナ禍における研修のオンライン化に関する調査」
以上のように、仕事と学習のリモート化が学習に与える「プラス」と「マイナス」両面の影響が想定されるなか、この調査では、コロナ禍前と比較して、勤務形態が「出社ワーク中心」から「テレワーク中心」へと変化した会社員を対象に、下記を検証した。
1. テレワーク中心になったことで、「仕事に関する学びの満足度」「仕事に関する新しい学びの有無」はどのように変化したか
2. 学習資源としての「仕事に関する学びに使える時間」「対人ネットワーク」「学習機会」はどのように変化したか
調査時期は2022年2月で、コロナ禍前から同じ会社で勤務しており、テレワークの頻度が、週または月の半分以上に増えた(以前は半分以下)832人(従業員規模300名以上の会社勤務、大卒・大学院卒)から回答を得た。今回は、職種特性によりテレワークの実施率が低い販売・サービス職は調査対象外としている(図表1)。
<図表1> 調査概要「会社員の自律的な学びに関する実態調査」
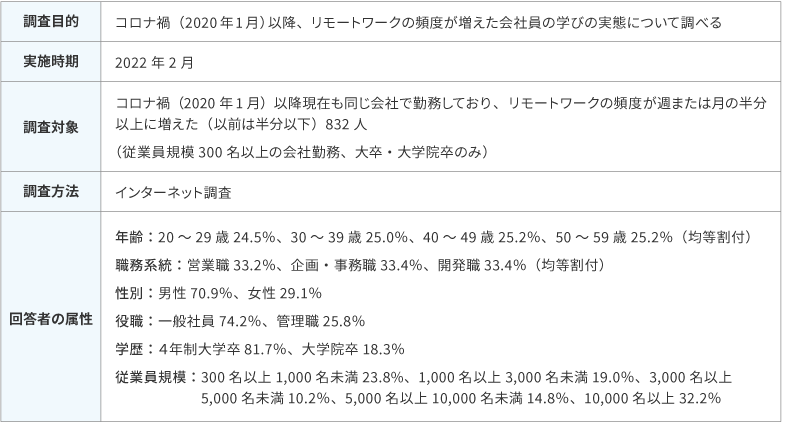
1. テレワーク中心になったことで、「仕事に関する学びの満足度」「仕事に関する新しい学びの有無」はどのように変化したか
「仕事に関する学びの満足度」は、高くなった4割、変わらない4割
まず、過去1年の仕事に関する学びについて、コロナ禍前(テレワークが今ほどなかったころ)と比べて、満足度がどのように変化したかをたずねた(図表2)。最も多いのは「あまり変わらない」で約4割(42.4%)、次いで多いのは「どちらかといえば高くなった」の約3割(31.9%)である。「高くなった」「どちらかといえば高くなった」の計が43.4%なのに対し、「低くなった」「どちらかといえば低くなった」の計は14.3%であり、仕事に関する学びの満足度は、低くなった人が少数派で、変わらないか高くなった人が多数派だった。
<図表2>仕事に関する学びの満足度の変化 (単一回答/n=832/%)
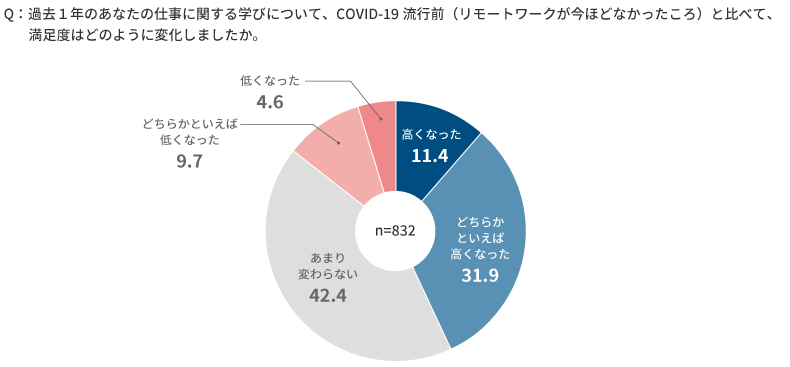
過去1年で仕事に関する新しい学びを得た割合は、以前よりやや増加傾向
次に、過去1年で、仕事に関する新しい学びがあったか、についてたずねた。コロナ禍前の2019年調査*5と比べたのが図表3である。なお、2019年調査は、本調査の対象に揃えて集計しなおしている。
「現在携わっている仕事に直結する学び」は、「あった」「どちらかといえばあった」が、2019年調査では62.5%に対し、2022年調査は64.5%で、有意な差は見られない。一方、「中長期的に自分のキャリア形成に役立つ学び」については、「あった」「どちらかといえばあった」が、2019年調査の43.8%に対し、2022年調査は54.9%と有意に多かった。2019年調査ではテレワークを行っている程度によって条件付けしておらず、明確な比較はできないものの、2022年調査で「テレワーク中心」の働き方をしている人が、過去1年で仕事に関する新しい学びを得た割合は、中長期的な学びを中心に、以前の調査に比べてやや増加傾向にあるようである。
※図表中の%の値は小数第2位で四捨五入しているため、本文に記載の合計の数値が図中の数値を足した値と一致しない場合がある。
*5 リクルートマネジメントソリューションズ(2019)「職場での個人の学びに関する実態調査」
<図表3>過去1年の新しい学びの有無 (単一回答/n=832/%)
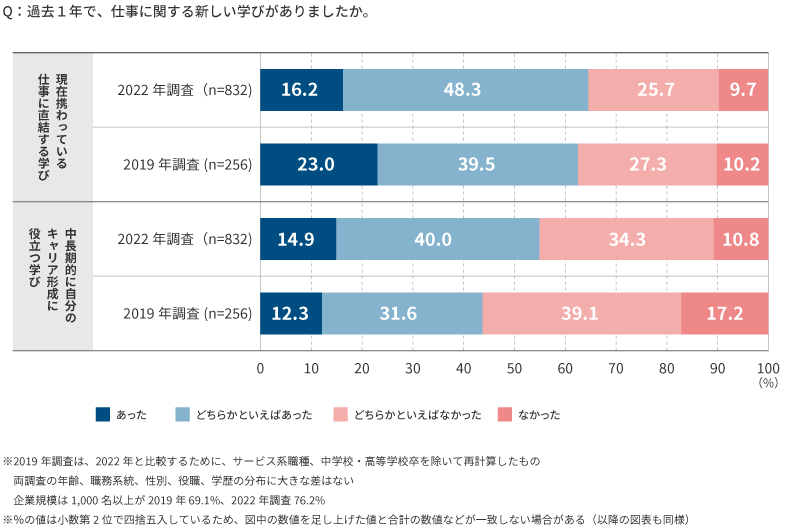
2. 学習資源としての「仕事に関する学びに使える時間」「対人ネットワーク」「学習機会」はどのように変化したか
学びを促進する資源となる、「仕事に関する学びに使える時間」「対人ネットワーク(社内)(社外)」「学習機会」は、リモート化でどのように変化しただろうか。
仕事に関する学びに使える時間は約半数が増加、対人ネットワークは約半数が減少
図表4のとおり、「仕事に関する学びに使える時間」「対人ネットワーク(社内)(社外)」は、いずれも「あまり変わらない」が最も多いが、「仕事に関する学びに使える時間」については、「減った」「どちらかといえば減った」が5.4%と極めて少なく、「増えた」「どちらかといえば増えた」が48.5%と約半数に迫った。一方、「対人ネットワーク(社内)(社外)」は共に、「増えた」「どちらかといえば増えた」が15%前後と少なく、「減った」「どちらかといえば減った」が45%前後と多かった。
<図表4>学びの資源(仕事に関する学びに使える時間・対人ネットワーク)の変化 (単一回答/n=832/%)
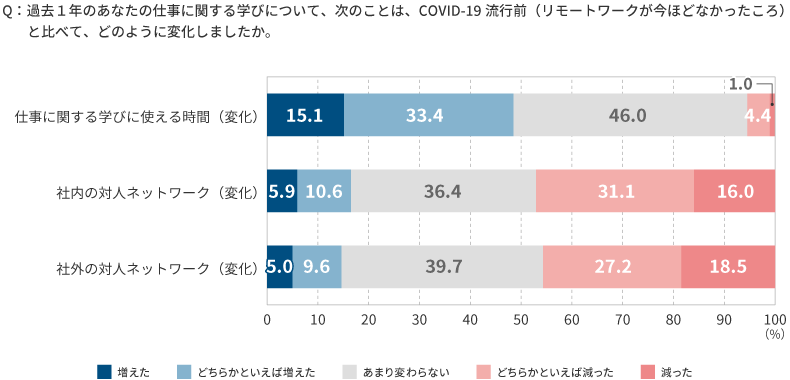
学びの機会は減少よりも増加の傾向。特に社外の学習機会が増加
学習機会は、まず、「社外」「会社」「上司・職場」に関する10の学習機会について、「過去1年において経験したものは何か」をたずねた(図表5)。過去1年で経験したという回答が多いのは「上司と部下の間の1on1ミーティング(41.5%)」「社員対象の研修(35.3%)」「上司や同僚からの業務支援やフィードバック(30.8%)」で、3~4割の人が経験している。一方、少なかったのは「社外の社会人向けの専門教育プログラム(7.6%)」「副業、ボランティアなど社外活動(10.9%)」だった。
<図表5>学びの資源(学習機会)の実態(複数回答/n=832/%)
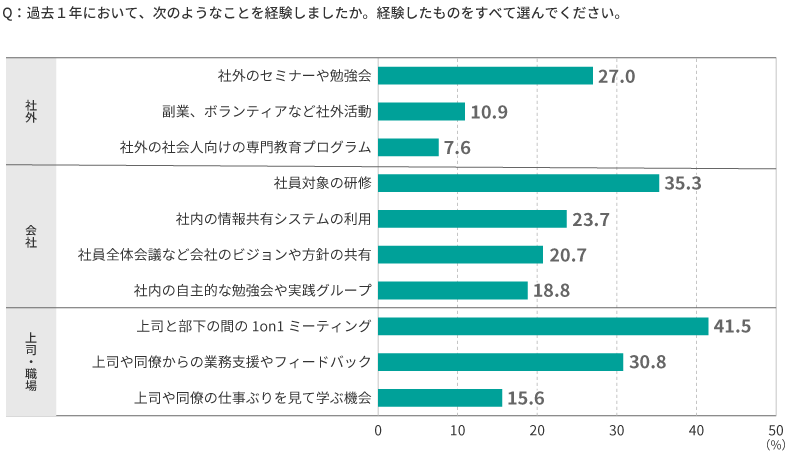
これらの機会は、リモート前と比べてどのように変化したのだろうか。「(経験したものについて)その機会は以前と比べてどのように変化したか」をたずねた結果が図表6である。
<図表6>学びの資源(学習機会)の変化(単一回答/%)
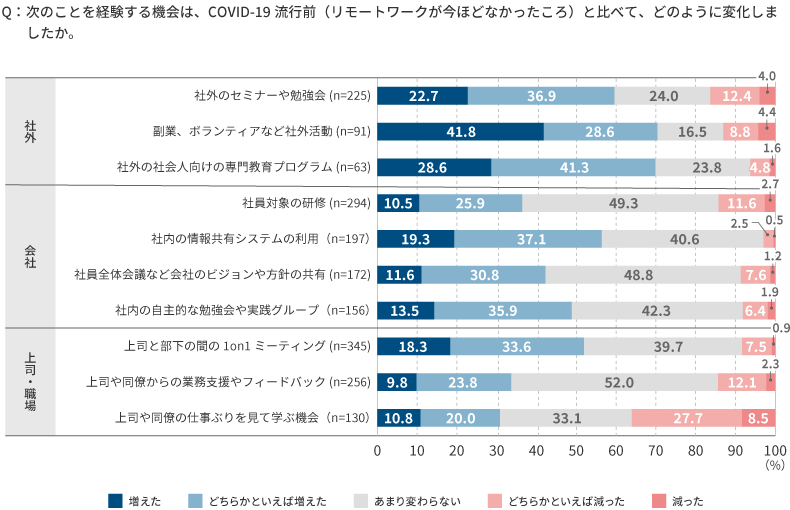
それぞれの学習機会が、以前と比べてどのように変化したかをたずねた(「5.増えた」~「1.減った」の5段階)結果で、「増えた」「どちらかといえば増えた」の計が特に多かったのは、「副業、ボランティアなど社外活動(70.3%)」「社外の社会人向けの専門教育プログラム(69.8%)」「社外のセミナーや勉強会(59.6%)」と、社外の学習機会だった。具体的な内容や増えた背景についての自由記述では、「通勤など仕事のための時間が減り、自由に使える時間が増えたため、通信制大学に入学し卒業を目指して学習中(20代開発系)」「在宅勤務で日中の時間調整がしやすくなったため、2カ月に1回程度、組織改革についてのセミナーに参加(50代企画事務系)」「オンライン開催で参加しやすくなり、月に1度程度、社外のビジネスセミナーに参加している(30代営業系)」など、テレワークで仕事に関する学びに使える時間が増えたこと、オンライン化で手軽に社外の学習機会を活用できていることがうかがえる。
逆に、「増えた」「どちらかといえば増えた」の計が少なかったのは、職場での学習機会にあたる「上司や同僚の仕事ぶりを見て学ぶ機会(30.8%)」「上司や同僚からの業務支援やフィードバック(33.6%)」だった。「電話で1対1で話す機会が増え、周りを気にすることなく話せる。業務に関することや仕事の仕方についてフィードバックをもらうことが増えた(30代開発系)」「上司の管理職の研修などがオンラインに切り替わり現場へ関わる時間が増えたため、上司の営業同行が増えた(20代営業系)」など、テレワークや学びのオンライン化がこうした機会を増やしたケースもあったことが分かるが、その割合は少なかった。
「増えた」「どちらかといえば増えた」機会が1つ以上あった人は383名(46.0%)、「減った」「どちらかといえば減った」機会が1つ以上あった人は140名(16.8%)だった。また、機会が増えたものが減ったものより多かった人は343名(41.2%)、減ったものが増えたものより多かった人が91名(10.9%)、同数の人が398名(47.8%)で、リモート下での学びの機会は、減少より増加の傾向であるようだ。
図表7では、図表5と図表6の結果をマトリクスにした。横軸は「経験度(過去1年に経験した割合)」、縦軸は、機会の「増加度(『5.増えた』 『4.どちらかといえば増えた』」の割合)」を示している。経験度も増加度も高いのは「上司と部下の間の1on1ミーティング」「社外のセミナーや勉強会」で、リモート化に後押しされて増加し、最も経験しやすい学びの機会であるといえよう。経験度は低いが増加度が高い、経験した人は少ないながら、以前より機会が増えたのは「副業、ボランティアなど社外活動」「社外の社会人向けの専門教育プログラム」「社内の情報共有システムの利用」「社内の自主的な勉強会や実践グループ」「社員全体会議など会社のビジョンや方針の共有」だった。今後、より増加する可能性がある。
一方、「社員対象の研修」「上司や同僚からの業務支援やフィードバック」は、経験した人は多いが、機会が増えたと答えた人は少ない。これらは「あまり変わらない」の回答が多く、リモート化の影響をあまり受けていない。リモート化の影響をあまり受けていないのは、「上司や同僚の仕事ぶりを見て学ぶ機会」で、「減った」「どちらかといえば減った」という回答が他に比べて多かった。
<図表7>学びの資源(学習機会)の経験度と増加度(単一回答/n=832/%)
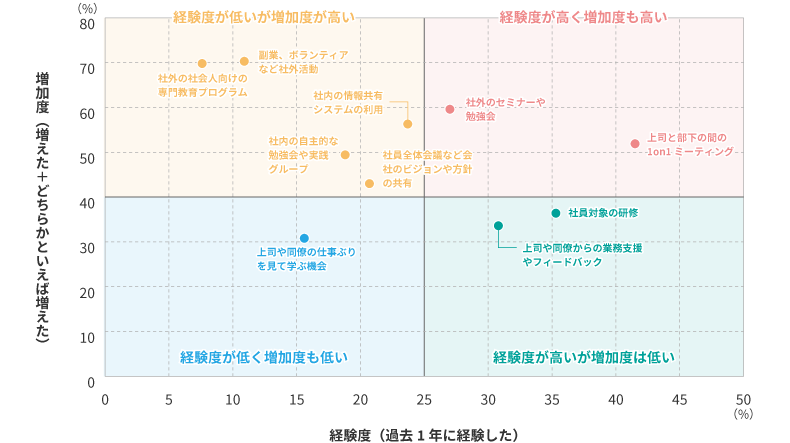
以上から、
・「仕事に関する学びに使える時間」は、減少した人より増加した人が多い
・「対人ネットワーク(社内)(社外)」は、増加した人より減少した人が多い
・「学習機会」は、減少した人より増加した人が多い
ことが確認できた。
仕事に関する学びに使える時間や学習機会の増加は、学びを促進している
これらの学びの資源の変化は、学びの程度にそれぞれどのような影響を及ぼしているのだろうか。図表3で紹介した「現在携わっている仕事に直結する学び」「中長期的に自分のキャリア形成に役立つ学び」の程度への影響を確認したところ(図表8)、「仕事に関する学びに使える時間の増加」「学習機会の増加」は、いずれの学びに対しても、有意な関係が見られた。また「社外の対人ネットワークの増加」は「中長期的に自分のキャリア形成に役立つ学び」に対してのみ、やや有意の関係が見られた。今回の調査では、「仕事に関する学びに使える時間」「学習機会」は減少した人より増加した人が大幅に多いこと、「対人ネットワーク(社内)(社外)」は増加した人より減少した人が大幅に多いことが示されたが、学びの程度に対して、「仕事に関する学びに使える時間」「学習機会」の増加は、「対人ネットワーク(社内)(社外)」の減少より強い影響を与え、結果的にリモート下での学びを維持・促進したと推測される。「中長期的に自分のキャリア形成に役立つ学び」に対する「社外の対人ネットワーク」の減少が与える影響は、今後懸念されるところだが、リモート化以外の要因である外出や会食の規制が緩和されることで状況が変わってくると思われる。
<図表8>学習資源の変化と学びの程度(重回帰分析/n=832)
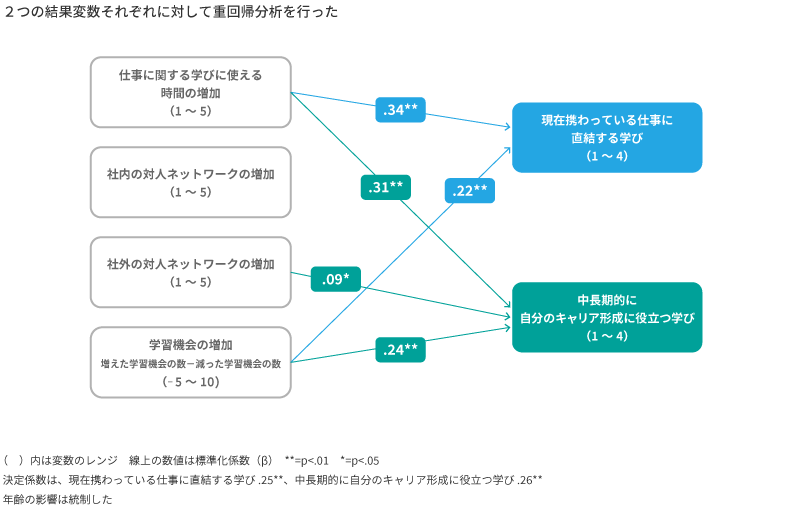
今回の調査は、現時点から以前との変化の主観的な認知をたずねたものが多く、また、複雑な学びのメカニズムの一端を調査したにすぎない。そのため、限定的な解釈にはとどまるが、少なくともデータからは、リモート化によって会社員の仕事に関する学びが低下するという仮説を支持する結果は見当たらず、以前と同等か向上していることを示していると考えられる。仕事と学びのリモート化はテクノロジーの進歩や人々の意識の変化にともない、さらに様相を変えていくだろう。会社員の学びの変化については、今後も継続的に調査・検討していきたい。
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
研究員
佐藤 裕子
リクルートにて、法人向けのアセスメント系研修の企画・開発、Webラーニングコンテンツの企画・開発などに携わる。その後、公開型セミナー事業の企画・開発などを経て、2014年より現職。研修での学びを職場で活用すること(転移)、社会人の自律的な学び/リスキリング、経験学習と持論形成、などに関する研究や、機関誌RMS Messageの企画・編集などに携わる。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



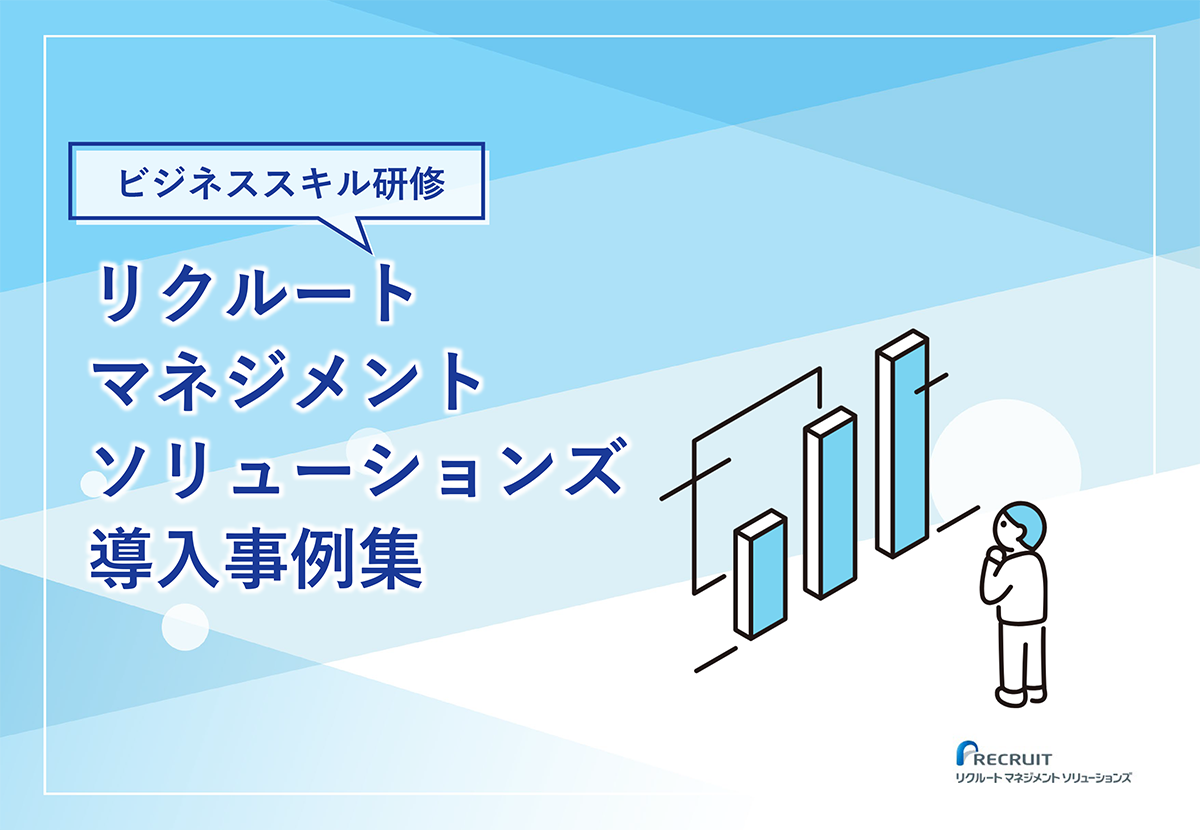










 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての