特集
3つの壁を乗り越えるためのヒント
なぜ経営人材育成は行き詰まってしまうのか
- 公開日:2018/02/05
- 更新日:2024/03/25

経営人材育成は長い間人事の重要課題として上位に挙がっているテーマである。それにもかかわらず、「経営人材を順調に確保・育成できている」と認識している企業は未だに多くはない(「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成ガイドライン(2017年3月経済産業省)」では37.6%)。
過去、さまざまな文献などで、経営人材育成の基本的なプロセスとポイントは示されてきた。またGEやP&Gといった企業事例が、リーダー育成のベストプラクティスとして共有されている。それでもなぜ、経営人材育成は人事の重要課題であり続けるのだろうか。
本稿では、まず経営人材育成の基本的なプロセスを概観した上で、経営人材育成の推進を阻むものを「3つの壁」として整理し、その要因を考察する。その上で、人事起点で経営人材育成を進めるためのヒントをお伝えしたいと思う。
- 目次
- 経営人材育成の基本的なプロセスとポイント
- 「分かっちゃいるけど、やりきれない」経営人材育成
- 第一の壁 育成対象を「選抜」できない
- 第二の壁 意図的な「異動・配置」ができない
- 第三の壁 育った人材を「早期登用」できない
- 「3つの壁」を乗り越えるには経営者のコミットメントが必要
- 人事起点で経営人材育成を進めることはできる
- 3つの壁を乗り越えるために人事ができること
- おわりに
経営人材育成の基本的なプロセスとポイント
なかなか成果が出ない経営人材育成だが、基本的なプロセスとポイントは明確だ(図表1)。
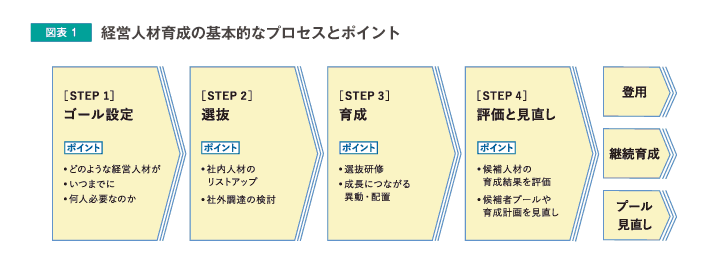
第1のステップは、ゴール設定である。自社の目指すビジョンや経営戦略に照らして、「どのような経営人材が」「いつまでに「」何人必要なのか」といった5W1Hを明確にしなければならない。例えば、海外でのM&Aによって成長することを決めている企業の経営者は、海外を飛び回りタフな交渉をする必要があり、体力があることが必須だ。そのため、新入社員から候補者を選抜し、若い経営者を輩出しようとする傾向がある。
第2のステップは、候補となる人材の選抜である。全社共通の基準を用いて人材の評価を行い、候補者をリストアップする。もし社内に十分な候補者が見当たらない場合には、社外からの人材調達(中途採用)も考えなくてはならないだろう。
第3のステップは、候補人材の育成だ。手段としては選抜研修が行われることが多い。従来はマーケティングやアカウンティングといった経営に必要となるリテラシーを学ぶことが多かったが、ここ数年は単なるお勉強で終わらせず、実際に事業上の課題を設定したり新たなビジネスを構想するといった実践型の研修が主流となっている。また、研修実施だけで終わらせず、チャレンジングなプロジェクトへのアサインメントや他部門・他事業へのローテーション、海外現地法人への出向といった、候補者の成長につながる異動・配置を継続して行うことが重要である。ちなみに、異なる事業や地域への異動・配置、職種転換は、人材の環境適応力や学習能力を見極めるという「ロードテスト」の意味合いも兼ねている。
第4のステップは、育成結果の評価と候補者プールの見直しだ。定期的に候補者の変化をモニタリングし、登用や候補者の入れ替えを判断する。 PDCAサイクルのCheckとActionに相当する部分であり、やりっぱなしにならないためにもこのステップは不可欠である。
「分かっちゃいるけど、やりきれない」経営人材育成
プロセス自体はさほど複雑なものではない。しかし実際には、これらのステップをきっちりと踏むことができている企業は意外と少ないのではないか。プロセスの一部分しか実施していなかったり、プロセス上のどこかで行き詰まったりしている場合が多いように思う。「分かっちゃいるけど、やりきれない」……経営人材育成における“Knowing- Doing Gap(知識と行動のギャップ)”である。人事の現場からの話を聞いていると、その理由が構造的に見えてくる。そのうち代表的なものを「育成を阻む3つの壁」として以下でご紹介する。
第一の壁 育成対象を「選抜」できない
経営人材育成を実施する場合、まず育成の対象を決める、すなわち人材を選抜することが必要だ。しかしながら、そもそも社員のなかから一部の社員を「選抜」すること自体ができない(したくない)という悩みを聞くことがある。特に、若手からの早期選抜には及び腰となりがちである。背景には、日本企業に特有の新卒一括採用や遅い昇進といった人事施策に代表される、横並びを尊重する風土がある。そのため、育成においても「選抜」をすること自体に強い抵抗や反発が生まれる。選抜されない社員のモチベーションに過度に配慮し、「選抜」自体に足踏みをしてしまう。場合によっては、「平等」を旗印にこれまで全社一律の制度やルールを適用することを生業としてきた人事自体が選抜をよしとしない、といったケースもある。似た話としては、選抜研修はするものの、「受講者にエリート意識をもたせたくない」という理由から、研修の目的や受講者への期待を曖昧にすることがある。呼ばれた受講者は何のために研修に参加するのかも分からず、なかなかモチベーションが上がらないという本末転倒の事態が起きる。
第二の壁 意図的な「異動・配置」ができない
この壁の前で止まっている企業は非常に多い(図表2)。限られた拘束時間と現場が割り切ってくれれば、社員を選抜研修に呼ぶことはできる。しかし、「異動・配置」となると話は別だ。経営人材候補として選抜される人材というのは、各部門のエース級の人材であることが多い。そのような人材を育成の観点で異動させるとなると、現場からの反発は避けられない。現場にとっては戦力ダウンにつながるからである。もちろん、将来が期待される人材の成長にとって、いろいろな事業や機能を経験することのメリットを理解しないわけではない。しかし、業績達成の責任を担っている各部門からすれば、希少であるエース人材を他部門に出す人事は簡単に飲めるものではない。結果、人材の異動は「総論賛成、各論反対」で進まない。
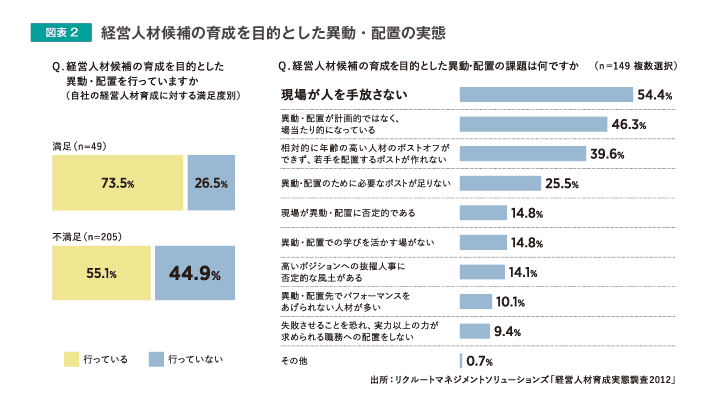
第三の壁 育った人材を「早期登用」できない
候補者が順調に育ったとしよう。次は、会社にとって重要なポストに登用していくフェーズとなる。しかし、ここにも壁がある。まず、年功序列の風土である。候補者の準備が整っていても、「若い」「年齢順からするとウェイティングリストの下の方」ということで、結局早期登用が進まない。年下の上司に対する抵抗感もある。役職定年制度が導入されている場合は一定期間で交替していくものの、順送りの登用がなされがちである。
また、成長著しい企業であれば、それに伴って組織が大きくなり、従ってポスト数も増加するが、成熟期や衰退期にさしかかった企業では、ポスト数には限りがある。そうなると、ポストオフが必要となるが、降格を前提としないとすると、ポストオフを機能させるためには、シニアマネジャー級の専門職制度が機能していることが前提になる。言い換えると、マネジメント以外でも生きる道を作っておく必要がある。しかし、ゼネラリスト育成に主眼が置かれてきた日本企業において、そのように育てられたシニアマネジャーは非常に少なく、ポストオフに踏み切ることができないケースも散見される。
「3つの壁」を乗り越えるには経営者のコミットメントが必要
以上、経営人材育成を阻む「3つの壁」をそれぞれ見てきた。壁の根っこにあるのは、日本企業に従来からあった人事慣行や「出る杭を打つ」風土が、(特に早期選抜を伴った)経営人材育成にそぐわない、ということである。特に、第一の壁(選抜できない)と第三の壁(早期登用できない)はこの日本特有の慣行や風土の影響が大きい。「過去のやり方にこだわり続ける」のは、知識と行動が一致しない原因の1つとされている。
もう1つ、経営人材育成の実行を難しくしているもの、それは「不確実性」である。経営人材育成には「将来の」活躍を期待した先行投資の面がある。若いうちから選抜しようとすればするほど、経営人材としてのポテンシャルを見極めることは難しい。本当にその人材のポテンシャルに賭けていいのかどうか分からないなかで、現場の反発があっても異動やローテーションをすべきか。そもそも、「VUCAの時代」(VUCA=Volatility〈変動性〉、Uncertainty〈不確実性〉、Complexity〈複雑性〉、 Ambiguity〈曖昧性〉)といわれるように環境変化が激しい昨今、一度決めた経営人材像が10年後も通用するものなのかどうかも分からない。ここに難しさがある。これは、組織のなかからイノベーションを起こそうというときに直面する難しさと本質的には同じである。つまり、「不確実性が高いなかで資源動員をする」という決断をしなくてはならない。
企業風土や価値観とのコンフリクトを超えて、また不確実性があるなかで資源動員の意思決定をするのは経営者の役割である。そもそも、将来の経営者を育てるのは現在の経営者の責務であり、人事に一任して経営者は報告を聞くだけでは、うまくいくはずもないだろう。さらに、経営者自身が多くの時間を経営人材育成に費やすことで、その重要性が社内にも伝播していく。「経営人材育成を成功させるためには、経営者のコミットメントが必要」だといわれる(図表3)のはこのためである。
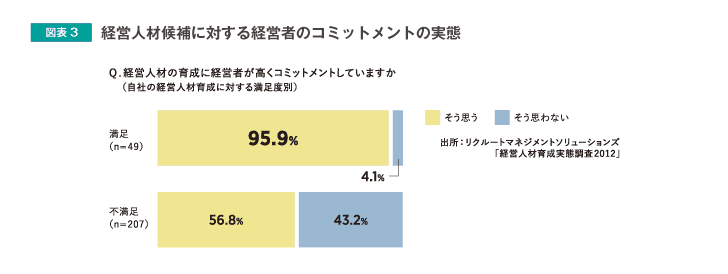
人事起点で経営人材育成を進めることはできる
経営人材育成には経営者のコミットメントが不可欠なのだが、かといって人事は受け身で待っている必要はない。ある企業の人事マネジャーは、グローバル化・テクノロジーの進歩のなか、現経営層が経営判断をしていては勝ち残ることができないと考え、膨大な事実に立脚した提言を経営層に対して行った。退職も覚悟で現経営層にNOを突きつけたのだ。その必死の訴えが認められ、戦略的な経営人材育成を進めた結果、いまでは経営層のほとんどが入れ替わっている。極端な例だと思われるかもしれないが、この例から伝わるのは、人事から経営者を動かし、経営人材育成を進めることもできるという事実だ。
ここからは、自社の経営人材育成に強い課題感をもち、変えていきたいと考えている方、特に人事担当の皆さまに向けて、先の3つの壁を乗り越えるためのヒントをお伝えしたい。
3つの壁を乗り越えるために人事ができること
(1)外部の視点を取り入れ
風土や価値観からくる反発や懸念を払拭する
知識を行動に変えるための1つのポイントとして、「何をどうやってするのか」という行動そのものよりもまず「なぜそうするのか」といった行動の裏にある哲学を理解すること、がある。
第一の壁と第三の壁を作り出しているのは新卒一括採用、横並び人事、年功序列の風土であると書いた。まず、「なぜ」これまでの慣行や風土とのコンフリクトを起こしてでも経営人材育成を進める必要があるのか、自社にとっての経営人材育成の必要性やあり方について経営と人事が徹底的に議論する必要がある。
その際のポイントは、自社の基準に染まりきっていない人の視点を取り入れることである。自社の基準が前提として染み込んでいる人のみで議論をしても、デメリットや懸念点が先に立つものだ。取材でお話を伺った日立総合経営研修所の迫田氏によると、日立製作所では、グローバルメンバーを含めたバーチャルチームで大変革を成し遂げている(企業事例)。また、外部から来た役員や顧問の提言によって初めて経営人材育成を本格的にスタートする企業は少なくない。多様な視点やある種の「外圧」をうまく使うことで、前提に凝り固まらないフラットな議論を進めることができる。
また、実際に施策を進めてみると、懸念していたよりもデメリットは大きくなかった、ということもある。昨今、「管理職になりたくない」という人が増えているという調査もある。だとすると、「選抜されなかった人のデモチベーション」よりも、「選抜された人のモチベーションや意欲、覚悟をいかに引き出すか」の方を考えるべきではないだろうか。
(2)人材開発委員会を主導し
全社で経営人材を育てる意識を醸成する
第二の壁を乗り越えるには全社視点・中長期の視点での育成検討が必要になる。そこで人材開発委員会(人事委員会、タレントレビューなどとも呼ばれる)の 導入が欠かせない。委員会メンバーを各事業の責任者で構成することで、個別事業の利害を超えて、全社視点で必要な育成施策を話し合うことを可能にする。そこで人事は、お飾りの委員会ではなく意味ある委員会を運営するために果たせる役割がある。
まず、人事の大事な役割としては、人材開発委員会のファシリテーターである。委員会メンバーが事実に基づいて議論をしているかをチェックし、印象論で議論がなされていたり議論がかみ合っていない場合には軌道修正する。また議論が発散するだけでなく収束しているか、候補者一人ひとりの今後の育成方針について結論を出しているかをチェックする。
次に、人材開発委員会に参加する経営陣に、議論対象となる候補者についての多面的な情報を提供する。ありがちなのが、自部門以外の候補者について、「実はほとんど知らない」という状態である。これではまともな議論は成立しない。人事評価の結果にとどまらず、360度サーベイの結果やアセスメントデータなど複数の定量データを用意する。さらに、定性的な情報や一次情報を得ることも必要だ。例えば、人事が現場に赴いて候補者の日常的な評判や噂を収集する。日産自動車の「キャリアコーチ」は、社内を動き回り、将来の経営者候補となり得る優秀な人材を発掘するのが役目だ。また、候補者向けの選抜研修を経営陣がオブザーブして直接自分の目で候補者を見る、といったことも有効である。
加えて、自社の経営人材の成長に資する経験について棚卸しをし、その情報も人材開発委員会に提供する。個人の育成課題について議論ができたとしても、その課題を克服するためのアサインメントや配置のアイディアが乏しければ打ち手に行き詰まる。人材情報だけではなく成長機会の情報を人事が収集して提供することで、人材開発委員会では候補者の育成方針の確認にとどまらず、方針に応じた具体的なアサインメントまで議論することができる。例えば、ある企業では、リージョン(地域)ごとに「タレント・ダイレクター」という役割があり、自らのリージョン内におけるアサインメントの機会を発掘するという機能を担っていた。
どの会社にも、経営陣になるための登竜門的なポジションは存在するものだが、限られた花形ポジションだけが経営人材の成長に資するポジションであると決めてかかる必要はない。むしろ、傍流だとみなされていた関連会社などに意外な成長機会があるかもしれない。規模は小さくても、ビジネス全体を見ることができる立場に立つことは有益である。また、ポストありきではなく、プロジェクトにアサインすることで得られる成長機会もある。かつての日産自動車におけるクロスファンクショナルチームは、リーダー育成のねらいもあった。また、KDDIの「役員補佐制度」(社長をはじめとする5名の役員に男女1名ずつ役員補佐がつき、経営の意思形成過程を知り、全社的・中長期的な視点を養う)や、サムスン電子の「地域専門家制度」(3年目以上の社員を世界中の各地域に1年間派遣する)のように、社員に必要な経験をさせるための制度を設けるというやり方もある。このように、自社における成長経験が明らかになれば、それを踏まえて意図的にタフアサインメントの機会を作り出すという発想もできる。
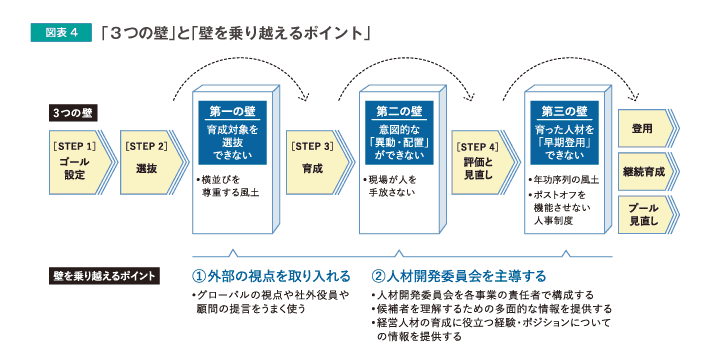
おわりに
以上、経営人材育成がなかなか進んでいない状況を「分かっちゃいるけど、やりきれない」と表現して、その要因を考察してきた。ただ、こう言っては元も子もないが、阻害要因や「壁」に目を向けて分かった気になるのではなく、いかに愚直に行動するかに尽きるともいえる。取材した日立製作所でも、グループ会社で40代の社長誕生という大胆な人事が実現したのは、人事が各所に根回しをして合意をとりつけるなど、まさに泥臭く行動した結果であった。
「成功事例を探すだけで何もしないのはもうやめて、そろそろ動き出そう」と思われている人事担当の皆さまにとって、少しでも本特集が参考になれば幸いである。
【text:ソリューション統括部 ビジネスフロンティア部 ソリューショングループ 主任研究員 岩下広武 研究員 高橋真寿美】
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.48 特集2「なぜ経営人材育成は行き詰ってしまうのか」より抜粋・一部修正したものである。
本特集の関連記事や、RMS Messageのバックナンバーはこちら。
※記事の内容および所属は掲載時点のものとなります。
おすすめコラム
Column
関連するお役立ち資料
Download
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)

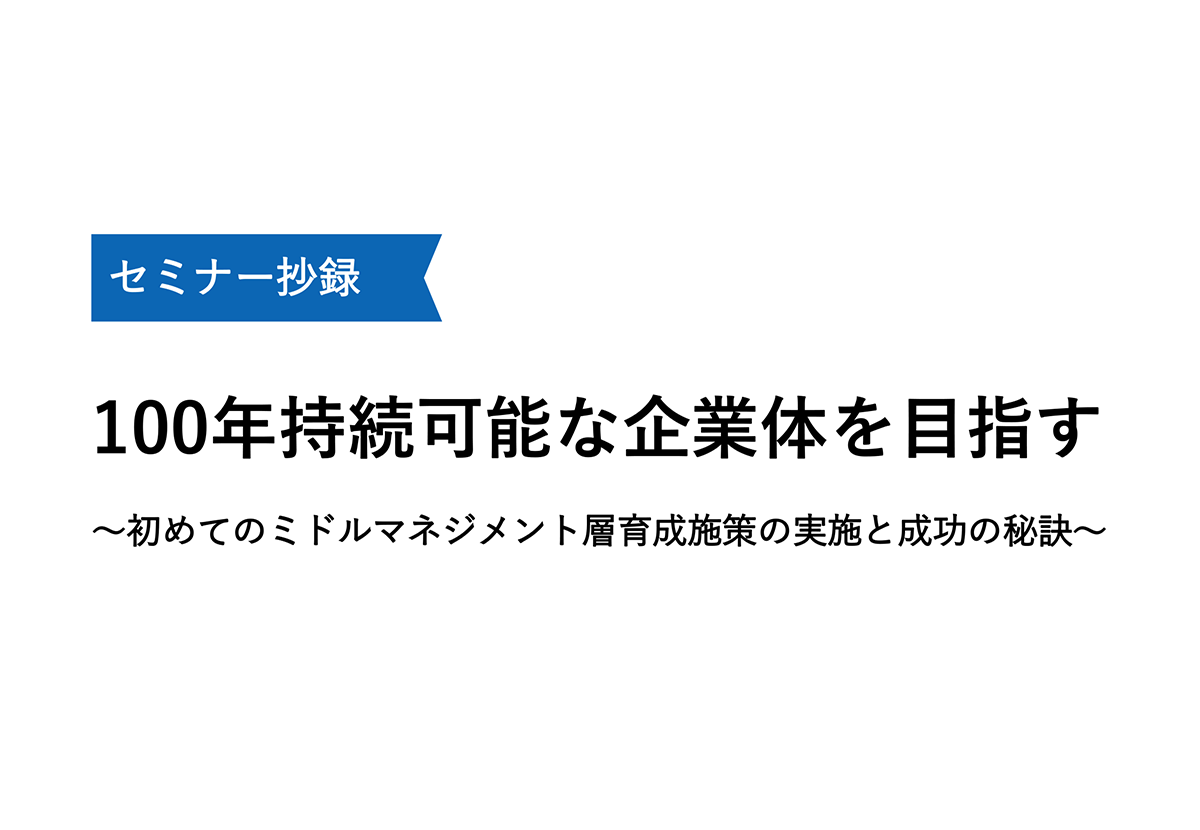









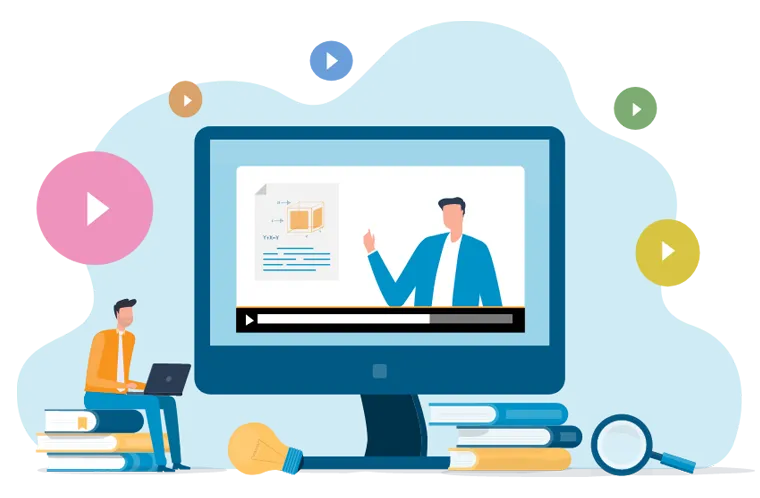 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての