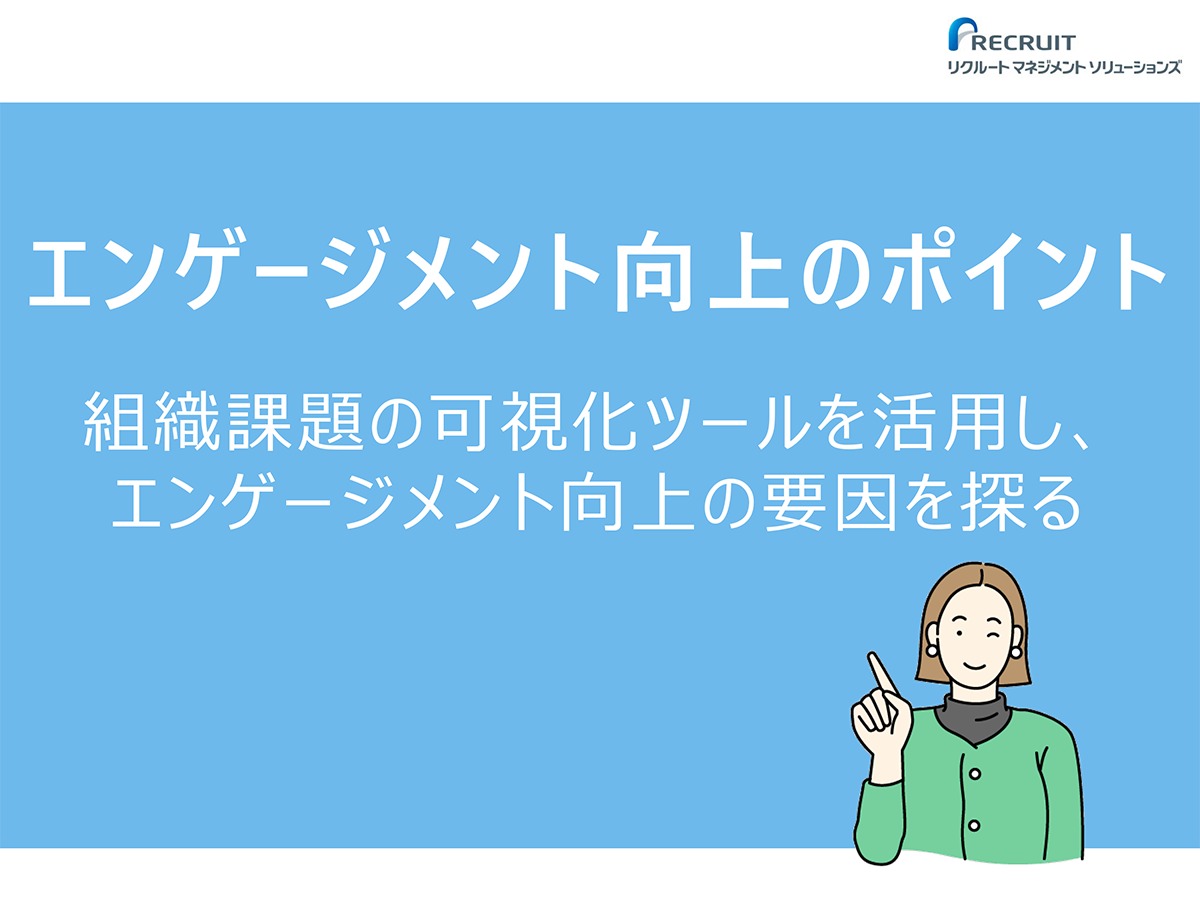特集
長時間労働の要因とは何か
日本人の長時間労働をめぐる法律とその要因に関する研究
- 公開日:2017/08/07
- 更新日:2024/04/06

労働時間に関する法規制は、社会の変化と共に修正を重ねている。 ここでは、労働法の推移を概観すると共に、日本人の長時間労働の実態とその要因に関する研究をレビューしていく。
労働時間の規制に関する法律の推移
労働市場が完全な状態であれば、労働時間の規制はいらないというのが経済学の通説になっている。つまり、労働に関する情報が適正に開示され、労働者がより良い労働条件を求めて、自由に移動できるのであれば、長時間労働を強いる企業には自然と人が集まらなくなり、そのような企業は淘汰されるので、規制は必要ないと考えられる。
あるいは、労働者が、自らの健康状態を考え、適正だと思われる労働時間を設定し、それを雇用主に受け入れてもらい、合意のもとでの労働契約がなされていれば、規制する必要はなさそうである。雇用主にとっても労働者の健康を害してまで働かせることは、長期的な損失につながることになる。そのことを鑑みれば、労働時間をわざわざ法律によって定める必要はない。
しかし、実際には、労働市場は不完全であり、労働者は自由に移動することは難しい。また、労働者は、自らの健康状態を客観的に把握できないことは十分にあり得ることを勘案すると、雇用主と労働者とそして社会全体の利益のために労働時間の規制は望ましいと考えられてきた。
そのために、産業革命後、近代的な労働の確立と共に、法規制が整備されていった。逆に、それ以前の労働は、農業が中心であり、何時間働くかは本人の裁量で決められることであり、法律で規制する必要はなかったのである。
資本主義の先発であるイギリスでは、1833年に工場法が定められ、1日12時間、その後、1864年には、1日10時間の労働時間が定められた。後発の日本では、1911年に工場法が制定され、女子と年少者に対して、1日12時間(1923年には11時間)を超えて労働させることを禁止していた。
1日何時間働くことが適正であるのかということは、マルクスの関心事であった。つまり、工場主はせっかく労働者を雇っているので、なるべく少ない賃金で何時間でも働かせたいという欲求がある。一方で、そんなに長い時間、人は働けるわけではない。体力ももたないし、精神的なダメージを受けることも分かっている。マルクスは、何時間働くのが適切なのか、その対価として、どのくらいの賃金が支払われることが公正なのかということを考えていた*1。
実際、労働時間の長さや休息と作業効率の関係性、疲労の関係性についての研究は、第二次世界大戦前から行われており、長時間労働の生理学的な弊害が指摘され、それが労働時間の根拠となっていた*2。ただし、その際の労働は、ブルーカラーが中心であることと時間だけが健康を脅かす要因ではなく、労働環境の劣悪さや職場の人間関係、監督者のマネジメントスキルも大きな要因であることを考慮すべきであり、注意を要するところである。
戦後、1947年に労働基準法が制定されたことによって、適用対象者の制限は撤廃され、1日8時間、週48時間の法定労働時間が確立された。これは、 ILO創設時の第1号条約(「工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約」)で規定されていた最も基本的な国際労働基準を採用したものである*3。その後、高度成長期を経て、日本の存在がグローバルで急速に拡大するなか、1987年に労働時間規制に関する改正が行われた。労働時間の長さが不当競争であるとやり玉に挙げられ、政府は、国策として、欧米諸国と同等の年間1800時間を目標に掲げた。目標に沿うように、週の法定労働時間は40時間に短縮され、年次有給休暇も最低付与日数が6日から10日に引き上げられるようになった(図表1)。
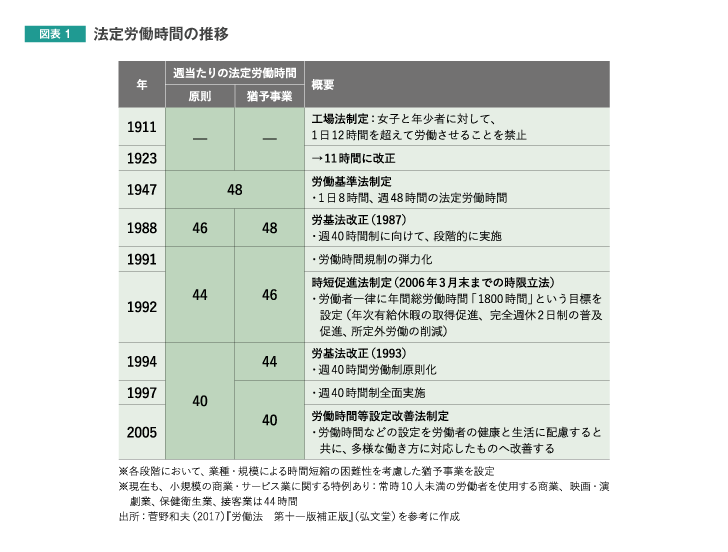
その後、2004年度、年間労働時間1800時間の目標が達成された後には、全体としての短時間促進よりも長時間労働に起因する脳・心臓疾患に配慮することや多様な働き方に合う形に、あるいは世論を反映させる形でワークライフバランスを重視する法律に置き換えられていくことになった*4。
日本人の長時間労働の実態
OECDのデータベースによると、日本の平均年間労働時間は、1980年代後半まで2100時間で推移していたが、その後、着実に減少し続け、2014年には1729時間になっている*5。日本人の労働時間は長いといわれてきたが、アメリカは、同時期、ほぼ横ばいで推移し、 2000年代には日米逆転し、アメリカが日本を上回っている(図表2)。しかしながら、過労死や長時間労働問題がニュースになることが多いことを含めて、労働時間が短くなっているという感覚をもたない人も多いと思われる。
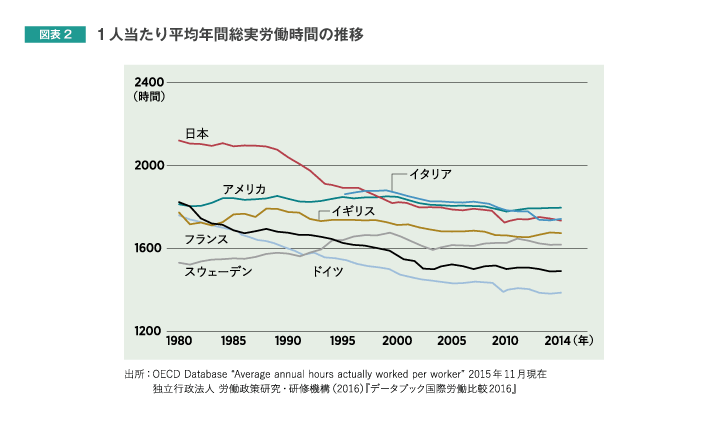
労働時間短縮の主要因は、非正規社員の割合の増加である。1990年に20.0%だった非正規社員は2014年には37.9%まで増えている*6。非正規社員は、パート・アルバイトなどの短時間勤務者が多く含まれており、その割合が増加したことが、日本人全体の平均労働時間を減少させた要因と考えられる。
山本・黒田(2014)の研究によると*7、週35時間以上勤務するフルタイム雇用者の労働時間の平均は、2000年代に入っても、1980年代と同水準の週50時間程度であることが確認された。詳細に見てみると、1日10時間以上働く男性は、1976年17.1%から2011年43.7%に増加していることも確認されている。つまり、短時間勤務者は増えたが、長時間勤務者も増え、日本人の労働時間は二極分化している。
属性別に労働時間を見ていくと、若手(20代)より中堅(30~40代)、中小企業より大企業、低所得者より高所得者、学歴でいうと大学卒の長時間労働者が相対的に増加している。この現象は、他の先進諸国(アメリカ、オーストラリア、イギリス)でも共通して観察されている。
短時間労働をする人の割合は増えているものの、長時間労働をする人の割合も増えているということであるが、人は働くことが好きなのか。働かされているのか。働かざるを得ないのか。長時間労働の要因に関する、いくつかの研究をレビューしてみる。
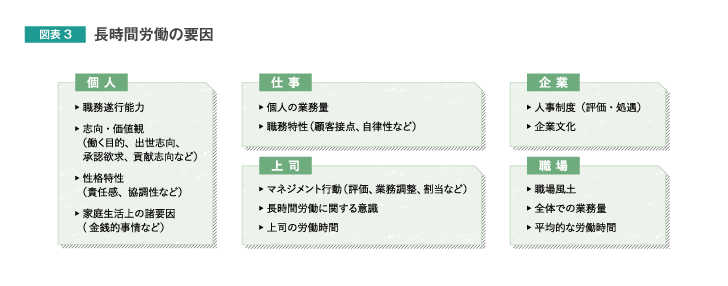
長時間労働の研究
[労働の長時間化のメカニズム]
佐藤(2008)は、労働の長時間化のメカニズムについて考察している*8。長時間化を単に労働者の意識の問題と捉えるのではなく、管理職のマネジメント行動、仕事特性を含んだ構造的な問題として捉え直している。
長時間労働者は偏在しているが、業務量と要員マンパワーの間のアンバランスを基本式とし、仕事の管理様式、管理者の行動と意識、社員の行動と意識などの変数から労働時間の長さが決まっていることを明らかにした。
つまり、1人の業務量が多くて処理能力が遅ければ、労働時間は長くなる。その調整をマネジメントが行っているという構図がベースにある。適切なマネジメントが行われれば、業務量の調整がなされ、労働時間を調節できることを示した。また、社員が出世志向が強い、あるいは残業代を生活費に組み込む傾向が強ければ労働時間が長くなる。加えて、上司が残業していれば部下は帰りにくいし、残業の長さに応じて部下を評価していれば労働時間は短くならない。また、顧客との打ち合わせが多いような仕事特性であれば、労働時間は長くなることを示した。
[労働時間と職場環境]
山本・黒田(2014)は職場環境と希望労働時間に関する研究を行っている*9。
「A:一定の時間のなかで可能な限り高い成果をあげる」
「B:高い成果をあげるために働く時間を惜しまない」
Aの職場が短時間労働志向の職場で、Bの職場が長時間労働志向の職場であるのだが、Bを選んだ労働者の方が、週の希望労働時間が1.61時間長くなることが分かった。
また、顧客志向の影響度についても調査している。
「A:無理をしてでも職場内で調整し、顧客の要望に応える」
「B:職場の状況をふまえて、対応可能なスケジュールを顧客に伝える」
ここでは、Aの職場が顧客(長時間労働)志向の職場で、Bの職場がスケジュール(短時間労働)志向の職場である。この場合は、Aを選んだ労働者の希望労働時間は0.87時間長いことが分かった。
つまり、長時間労働が評価されるような職場や企業で働く労働者ほど、希望労働時間が長いことが分かったのである。
一般的に、同一企業で働く労働者の実労働時間や希望労働時間は類似する傾向がある。自分と同じ職場にいる人が働いているから、自分の仕事が終わっても帰りづらい。あるいは、帰りづらいのが分かっているから、残業できるようにあらかじめゆっくり仕事をしてしまうということが起きるのである。長時間労働は周囲に伝染してしまうものである。そのことを裏付けるように、山本・黒田(2014)は、労働時間の長さに関して、同一企業で働いているという要因で40%以上説明できることを明らかにした。
単純に働くのが好きだから労働時間が長いというわけではなく、労働者を取り巻く環境によって、労働時間が決まってくる。そういう意味では、「働かされている」あるいは「働かざるを得ない」から働いているともいえるし、マネジメントによって、労働時間を短くすることができるということでもある。
[人事制度とサービス残業]
高橋(2005)は、サービス残業に焦点を当てた研究を行っている*10。サービス残業は、賃金の支払いが伴わない残業である。しかも、企業側が不払い労働を強要しているのではなく、労働者が自主的にサービス残業を選んでいる傾向があることが分かっている。
1990年代後半から、多くの会社が成果主義人事制度を導入しているが、その制度の導入と共にサービス残業が増えている。成果主義人事制度を導入している会社では、自らの業績を上げるために、残業しても申告しない労働者は多い。しかしながら、成果を上げることで、報酬を上げることができ、間接的に、報われることになる。
同研究によると、サービス残業を積極的に行っている人ほど、高い成果を上げ、出世を果たし、事後的に報酬が得られている傾向が高いことを見出している。より高賃金を得るために、より長く働くということである。しかしながら、単に高賃金が欲しいから、長時間働いているかどうかは精査が必要である。業績を上げないと組織の一員として認められないのを恐れているということ、業績を高めて仲間から称賛されたいということ、あるいは、組織全体に貢献したいということなどを考慮する必要がある。
[長時間労働をする個人の特性]
日本能率協会(2005)が管理職調査を行っている。そのなかで、「先月最も残業が長かった正社員の部下について、どのようなタイプか」という問いがある。それに対する回答は、「責任感が強い」「仕事を頼まれると断れない」「協調性がある」「てきぱきと仕事をしている」というタイプが挙げられている*11。いわゆる仕事ができる人である。仕事ができる人に仕事は集まるということである。
大竹・奥平(2008)*12は、長時間労働をしている人は継続的に長時間労働をする可能性が高いことを明らかにした。週60時間以上働いている人は、次の週も60時間以上働く確率が高いということである。長時間労働してもそれが苦痛にならずに、その状態に慣れて、長時間労働の習慣を形成してしまう。その傾向は、労働時間を自分で決められる管理職の方に、顕著に現れるとのことである。長く働くことが苦痛にならない。苦痛になるどころか働くことに喜びを感じ、長時間労働を好んで行うようになるということである。
一連の研究を眺めてみたときに、次のようなことがいえる。
自分の労働時間は、単純に自分の好き嫌いで決められるわけではないことが分かる。長時間働くことを良しとしている職場では、よほどの覚悟がないと、自分だけ短時間労働をするのは難しい。加えて、長時間労働をしている人が業績を上げていて、評価されているのであれば、なおさら短時間労働は難しいのである。
*1 マルクス(1969)『資本論』岩波書店
*2 藤林敬三(1941)『労働者政策と労働科学』有斐閣、あるいは籠山京(1944)『勤労者休養問題の研究』千倉書房
*3 菅野和夫(2017)『労働法 第十一版補正版』弘文堂
*4 労働時間等設定改善特措法(2006年4月1日施行)、あるいは『仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章』(2007年12月18日制定)
*5 OECD Database “Average annual hours actually worked per worker”
*6 総務省『労働力調査』
*7、9 山本勲・黒田祥子(2014)『労働時間の経済分析―超高齢社会の働き方を展望する』日本経済新聞出版社
*8 佐藤厚(2008)「仕事管理と労働時間―長労働時間の発生メカニズム」『日本労働研究雑誌』 No.575、pp.27-38
*10 高橋陽子(2005) 「ホワイトカラー『サービス残業』の経済学的背景―労働時間・報酬に関する暗黙の契約」『日本 労働研究雑誌』No.536、pp.56-68
*11 日本能率協会総合研究所 (2005) 『厚生労働省平成 16年度委託調査 賃金不払残業と労働時間管理の適正化に関する調査・研究報告書』
*12 大竹文雄・奥平寛子(2008)「長時間労働の経済分析」『RIETI Discussion Paper Series 08-J-019』 経済産業研究所
※本稿は、弊社機関誌 RMS Message vol.46 特集1「長時間労働」より抜粋・一部修正したものである。
RMS Messageのバックナンバーはこちら。
執筆者
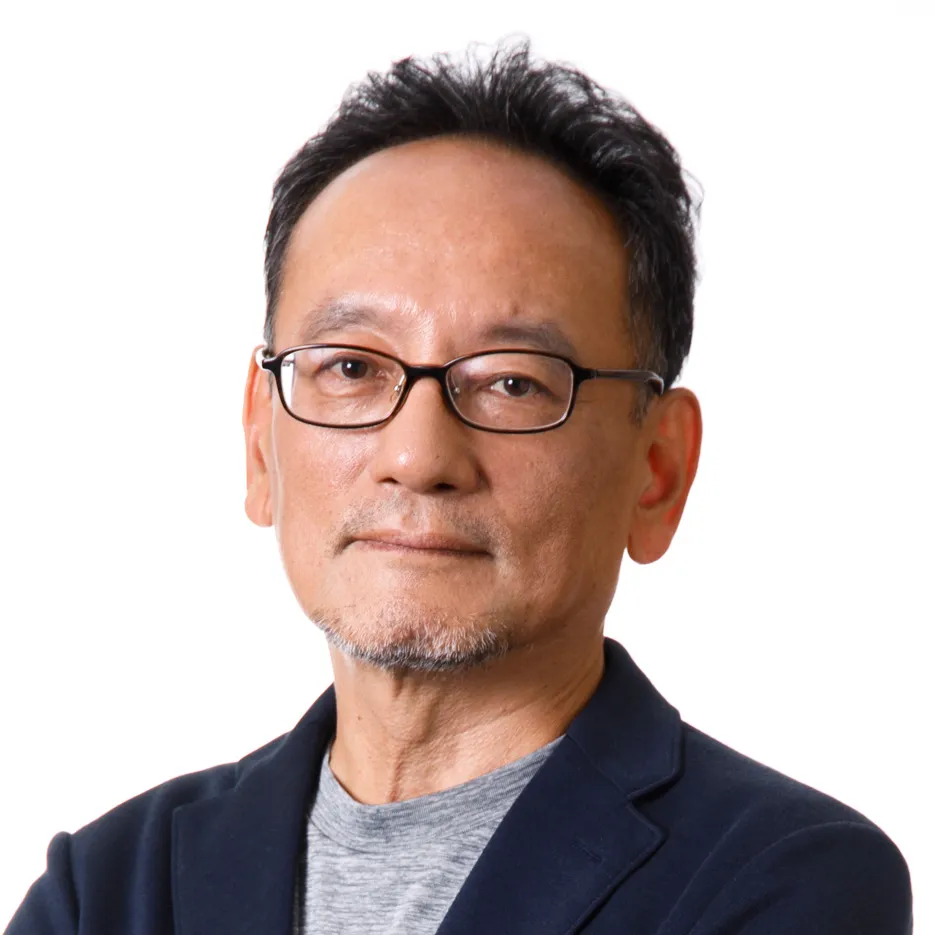
技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主幹研究員
古野 庸一
1987年東京大学工学部卒業後、株式会社リクルートに入社
南カリフォルニア大学でMBA取得
キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事
2009年より組織行動研究所所長、2024年より現職
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)