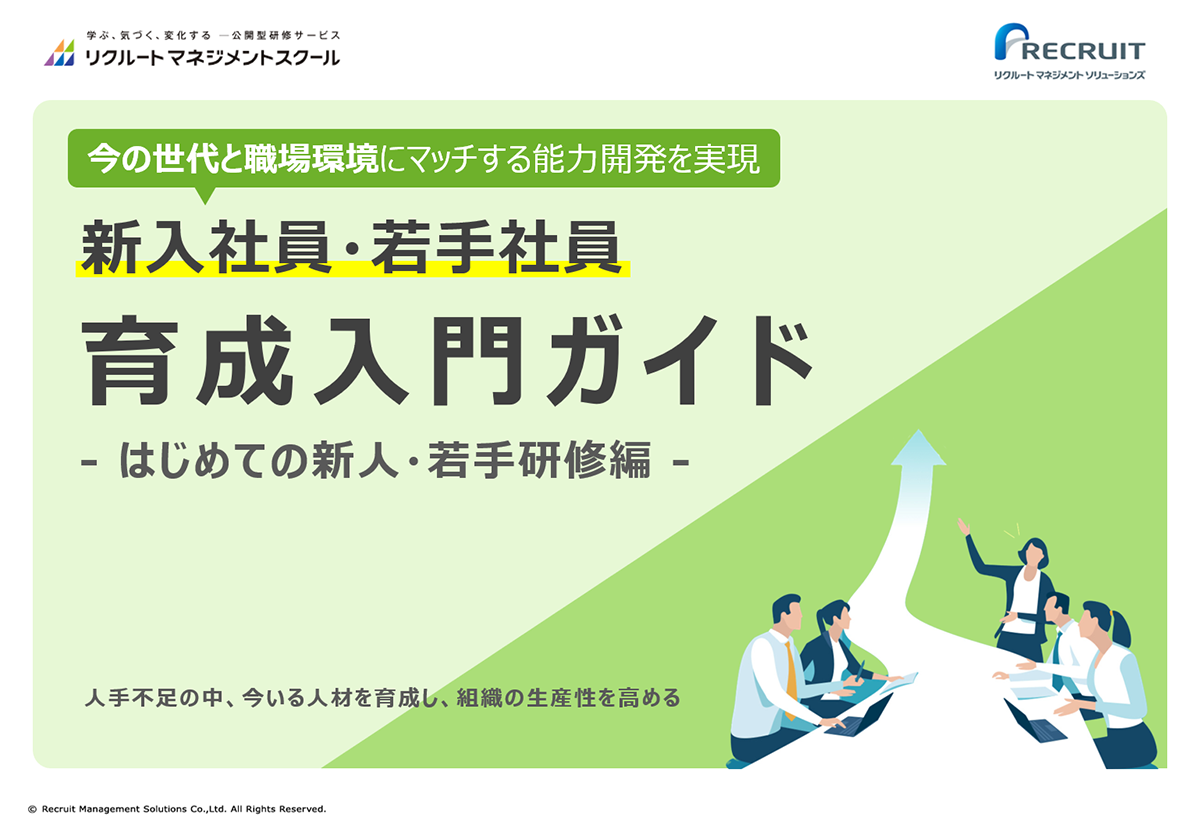連載・コラム
【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 公開日:2025/05/19
- 更新日:2025/08/05

若手育成においてもダイバーシティや対話が求められるなかで、なかなかコミュニケーションがうまくいかないというお悩みをよく伺います。そんな時、どのように視野を広げたらいいのでしょうか。
前編では、大学院大学至善館で次世代の育成に携わられている枝廣淳子氏に、ダイバーシティを職場に浸透させるためのきっかけのつくり方や、ダイバーシティそのものへの向き合い方についてお話しいただきました。今回も引き続き枝廣淳子氏をお迎えし、「若手世代との対話のノウハウ」について伺います。
対談メンバー
●枝廣 淳子氏(大学院大学至善館教授)
●武石 美有紀(リクルートマネジメントソリューションズ 研究員)
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
対話に余裕をもたらす、ネガティブ・ケイパビリティのススメ

武石:近年、育成担当者や上司の方々から「“対話の重要性”があらゆるところで取り上げられているのを受けて、若手社員と積極的にコミュニケーションを取ろうとしている」というお話を伺います。ただ、対話の時間が増えることで「1on1で何を話したらいいか分からない。結局いつも“業務の進捗どう?”と聞いてしまう」というお悩みが挙がることも多いんです。こういった悩みを乗り越えるには、どのような方法が有効でしょうか。
枝廣:対話は確かに大切ですが、急に「さあ、話してください」と言っても難しいんですよね。
ただ話すだけでは、相互理解やイノベーションにはなかなか繋がりません。ですので、対話の作法を知り、せっかくつくった若手社員との対話の時間の質を上げることも大切です。
武石:対話の質を上げるには、どのようなことがポイントでしょうか。
枝廣:そうですね、対話において最低限守った方がいいことがあります。
1つ目は、「多様性は大事だ」という認識を持つこと。自分とは違う相手の話を受け止める気持ちがなければ、対話そのものが難しくなってしまいますからね。2つ目として、「どんどん結論を出すべき時と、ネガティブ・ケイパビリティを使って答えを待った方がいい時を見極めること」も大切だと思います。
武石:枝廣様は著書である『答えを急がない勇気』のなかでも、ネガティブ・ケイパビリティの大切さについて触れられていました。ネガティブ・ケイパビリティについて、あらためてご説明いただいてもよろしいでしょうか。
枝廣:ネガティブ・ケイパビリティとは、答えの出ない、どうにも対処しようのない事態にとどまり続ける力のことです。「何もしない」のではなくて、分からないことがあってもすぐ結論を出して楽にならずに、あえて向き合う力だと考えています。

今の社会は、すぐに決断し、すぐに結果を出すポジティブ・ケイパビリティの力が求められています。さまざまなものをテキパキと、前へ前へ、後戻りせずにどんどん進めていくことが重視されやすい時代なんですね。ポジティブ・ケイパビリティだけで突き進んでいるように感じる組織もありますが、それはブレーキのない車でアクセルを踏んでいるようなもので、非常に怖いなと思うことも多いんです。
対話の作法としても、即断するポジティブ・ケイパビリティと、分からないことに向き合うネガティブ・ケイパビリティを、うまく使い分けられるといいと思っています。即断する力はずっと鍛えられているので、問題にじっと向き合う力も使えるようになれば、選択肢が増えて対話しやすくなるケースも多いのではないでしょうか。例えば、離職を考えている若手社員から「ちょっと相談があるんですが……」とつらそうに声をかけられた時、さっさと結論を出すポジティブ・ケイパビリティを使ったら絶対だめですよね。
武石:逆効果になってしまうことが多いでしょうね。そういったポジティブとネガティブを使い分けるバランス感覚は、どういうプロセスで身につけていくのがいいのでしょうか?
枝廣:ポイントを先に知っておいて、あとは試行錯誤のなかで身につけていくものです。実際にいろんな人と対話してみて、反応を見る。うまくいったことは次も使えるように自分の道具箱にノウハウとしてためておきます。一方で、うまくいかない時は素直に認めて、道具箱から別のアプローチを出せるかどうかも非常に大切です。
うまくいかないことを失敗と思わずに、自分の幅を広げるチャンスだと思って、受け止めてみるといいですね。「うまくいかないな」と思った時は、違う道具を使えばいいだけなんです。性格を変える必要もないですし、無理に自分を抑え込む必要もありません。対話を重ねていくうちに「うまくいきそう」「うまくいかないかも」というセンスも磨かれて、自然とバランスが取れるようになっていきます。ゲーム感覚でできると思いませんか?

武石:多様な世の中だからこそ、選択肢をたくさん持って、自分でいろいろ試していく力が必要ですよね。
実は弊社が実施している若手研修でも、 “いろいろな選択肢を試す大切さ”をよくお伝えしています。ただ、どうしても「正解を教えてください」と質問される方も多くいらっしゃる状況です。
枝廣:私も大学院で社会人を教える時に感じますが、昔と比べて「正解を求める傾向」がとても強いですね。だから「正しい答えはこれですか?」と聞かれた時は、「これが正しい答えになる場合は、どういう条件が揃った時なのかを考えてみて」と教えています。倫理的に絶対にやってはいけないことを除いて、どんな時でも絶対に正しいという答えはありませんから。常に相対化しながら、今の場面での正しさを考えて、選んでもらうことが大切なのではないでしょうか。
常に正解だけを求めていくと、ポジティブ・ケイパビリティだけで突き進む、苦しい世界になってしまいます。試行錯誤や失敗も成長だと認めて、時には待つ余裕を持つこと。それで物事がスムーズに進んだり、救われる人が出てきたりすることも多いと思いますよ。
「5分だけ」ルールが、ジェネレーションギャップと向き合うコツ
武石:対話のノウハウとしてもう1つ伺いたいのですが、昨今の育成現場ではジェネレーションギャップが課題になるケースも多いです。職場のジェネレーションギャップを乗り越えるコツとしては、どんな方法があるでしょうか。
枝廣:職場のジェネレーションギャップに悩んだ時は、とりあえず「“分からない”から始めてみよう」とお薦めしています。「分からない」には、2通りの反応があると思っているんです。1つは「分からない。(以上)」という、思考を止めてしまうタイプ。もう1つは「分からないから、分かりたい」という、前向きに思考を続けるタイプです。後者の前向きな「分からない」なら、「なんでそう考えるんだろう?」と考えるきっかけになりますから、相互理解にも繋がっていきます。
そこで、ジェネレーションギャップを感じることがあっても、5分だけ粘ってみることをお薦めします。とことん相手を理解しようとすると疲れてしまいますけど、「今日は5分だけ話を聞いてみよう」というように積み重ねていけば、お互いの理解も深まっていきます。
武石:確かに。5分だったら気軽で継続しやすいです。上司と部下って、1回の対話で終了という関係ではありませんから、急がずに積み上げていくことが大切なのかもしれませんね。
枝廣:そうそう。少しずつでいいし、選択肢もたくさん持っていいんです。「今まで自分はこうやってきたから、今更それ以外のものはいらない」と頑なになってしまうと、視野が狭まってしまいますから。

多様性の時代だからこそいろんな武器を持って、素直な気持ちを大事にしてほしいです。そういった余裕があれば仕事がもっと楽しくなりますし、生活も豊かになります。
ネガティブ・ケイパビリティも、職場でいきなり試すのが不安だったら、家族や友人など身近な人と話す時に使ってみるのもいいですよ。ネガティブ・ケイパビリティって結構面白くて、周りに伝染するんです。例えば家でいつも「早くしなさい」と急かすことばかりすると、関係性がギスギスしてしまうことがあります。ネガティブ・ケイパビリティを使うようになると、家族の間でも「答えを急がない時間」が生まれやすくなり、自然と対話が増えてきたりするものです。
人間関係は鏡と言うように、職場でも上司の方がネガティブ・ケイパビリティを使えば、その空気感が若手社員にも伝わっていくと思いますよ。
武石:最後に、若手育成に携わる方にメッセージをお願いします。
枝廣:育成する側に立つと、つい「理想のロールモデルにならなければ」という、完璧主義的な意識を持つ方も多いかと思います。もちろんそれはすばらしいことなんですけど、もし疲れてしまった時は「今、完璧である必要はない」と、気持ちを楽にしてみてほしいです。「今はまだ足りないけど、もっと高みを目指している。そのために失敗したり、試行錯誤したりしている」という姿は、完璧に何でもやり遂げる姿よりも学びの多いロールモデルになることも実際に多いんです。結論や結果をすぐに急がない勇気を、ぜひ持ってみてください。
本コラムでは、前後編に分けてダイバーシティと新人・若手育成について枝廣 淳子氏にお話を伺いました。
弊社では、新人・若手のオンボーディング支援や、対話力を強化する研修プログラムなど、さまざまなソリューションを提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
関連するサービス
管理職向けコーチング研修
若手社員向けの研修をご検討の方は、若手社員研修特集ページをご覧ください。
※記事の内容および所属等は取材時点のものとなります。
- 【専門家に聞く】第3回 希望学と新人・若手社員育成
- 若手社員が壁にぶつかったときにどう関わる?~逃げずに“ウロウロ”する考え方~
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【後編】
- AIがコーチングできる時代。“生身の対話やコーチング”に宿る価値とは?
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【中編】
- 部下とのコミュニケーションを円滑にする、“本音”と“ご機嫌”のススメ
- 【専門家に聞く】第2回 対話と新人・若手育成【前編】
- コーチングのパイオニアに聞いた、“考えさせる対話”のコツ
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【後編】
- 「業務の進捗どう?」で終わらない、若手社員とのコミュニケーションのコツとは?
- 【専門家に聞く】第1回 ダイバーシティと新人・若手育成【前編】
- ダイバーシティ実現を目指すなかで、若手をどう育てる?―― “ダイバーシティ”との向き合い方を考える
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- サービス資料・お役立ち資料
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)