連載・コラム
DEI エクイティを考えるヒント
- 公開日:2024/05/07
- 更新日:2024/05/18

前回のコラムでは、言葉の意味からダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンを考えていきました。本稿では、エクイティに焦点を合わせて、エクイティを考える際のヒントを取り上げます。
「エクイティ」を“どこまで行うか”で定義する
ダイバーシティが、多様な人がいる状態、インクルージョンを(それらの)人の力を生かしている状態だとすると、エクイティはそうした状態をつくるための環境整備を指します。エクイティは、ダイバーシティとインクルージョンで目指している状態を支援・取り組みによって後押しすること、と言い換えることもできます。
また、エクイティは「それぞれの人に合わせた支援である、なぜならばそれぞれの人の置かれた状況は違うし、支援が必要なことは違うから」という個別性が強調されることもあります。良く使われる例は、塀の向こうで野球のゲームをやっているが、AさんもBさんも塀があって観ることはできない。その際、身長の高いAさんには低い踏み台を、身長の低いBさんには高い踏み台を設けたらどちらもゲームを観ることができるというものです。このときに、身長プラス踏み台の高さが同じであるような踏み台を用意するのが「公平(エクイティ)」だと説明します。
しかし、こうした例を話したときに、しばしば「なんとなく想像はつくが、実務的にはエクイティと言われてもピンとこない」というお話を伺うことがあります。このピンとこない感じは、「エクイティとは、“何を”“どこまで”行うのかが分かりづらい」ということから生じているようです。
ちなみに、筆者はコンサルティングの現場で企業をご支援する際には、エクイティを以下のように説明しています。
- 支援の度合いが適切か否かの判断は、メンバーに対して「あとはあなたの努力次第」「あとはあなたの頑張り次第」と言えるところまで支援したかどうかである
- エクイティはメンバーの活躍を支援することである。よって、メンバーの望みや困りごとに対応するか否かを判断する際には、「その望みに応えたり、困りごとを解決したりすることで組織のパフォーマンスが上がるかどうか」が1つの基準となる
DEI推進部署や、経営幹部・管理職層の皆さんに上記のようにお話しすると、それだけでピンとくる方々もいます。それは、エクイティといったときに、「どこまで」やったらいいのかという想像がつくからです。
“何を行うか”を考えるうえで妨げとなる2つの問い
それでは、エクイティとは「何を」することなのでしょうか。この一見シンプルな問いは、組織責任者の皆さんが以下のように思い込むことで、さらに難しい問いになってしまっているように拝察します。
- 個々人の望みや困りごとは人によって違うのだから、個別性が高すぎる
- DEIのための施策が思い浮かばない
1つずつみていきましょう。
1点目の「個々人の望みや困りごとは人によって違うのだから個別性が高すぎる」という件、個々人の望みや困りごとが違うのはもちろんですし、それぞれに合わせた支援を行うことで公平な状況をつくれるということもそのとおりでしょう。だからまずは組織のメンバー(部下)が何を望んでいるかを確認しようということ自体は、DEI推進の姿勢として良いものでしょう。1on1ミーティングを実施する組織が増えていることも、こうした背景が後押ししているのかもしれません。
しかし、個々人の望みを知る、イコール、すべて個々人に応じた異なる対応をしなければならないと考える必要はありません。もし、いろいろな人が共通に持っている望みや困りごとがあれば、それを支援することも立派なエクイティです。
多くの人に共通して必要な支援をどうやって考えたらいいでしょうか。そのヒントが「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見・固定的な見方)」です。企業活動、特にDEI推進においては、アンコンシャス・バイアスはマイナスのものと捉えられています。しかし、ここでは、悪いものだと断じるよりも、エクイティのヒントになり得るという見方をしてみます。アンコンシャス・バイアスがあるところには、そのバイアスによって思うように力を発揮できていない人がいたり、何か不自由な思いをしている人がいたりします。だとすれば、自身や周囲が抱いているアンコンシャス・バイアスを見つけることができれば、そこには何か支援できることがあるかもしれない、と考えることができるようになります。
たとえば、「最近の若手社員は……」「中途入社者は……」「女性社員はえてして……」と、主語が大きすぎる場合は、そこに固定的なものの見方や偏見があるかもしれません。例えば、中途で入社したばかりの人に、何も支援しない組織責任者は、「中途入社者は実務経験があるのだから当社でも即戦力として働ける」または、「中途入社者は一人前の社会人なのだから、何か困ったことがあれば、自分から声をかけてくるはず」という思い込みがあるかもしれません。この思い込みがあると、そうした中途入社の人がある仕事を進めるために、社内の誰に声をかけるべきか分からなくて悩んでいることに気がつくことができないかもしれません。でも、こうした思い込みに気がつくことで、「中途入社した人には、最初の1カ月で、部署のみんなと1on1で話す機会をつくってみよう」「組織のメンバーのスキルや経験や関心ごとをタグにして、社内で検索できるようにしよう」といったエクイティ施策が浮かぶかもしれません。
2点目は「DEIのための施策が思い浮かばない」というものです。ダイバーシティ&インクルージョンの施策といえば、女性社員のための〇〇、障害のある社員のための〇〇といった、特定の属性のための施策を思い浮かべる人がいます。または、個々のメンバーの望みや困りごとを知るには1on1ミーティングくらいしか施策はないだろうと言う方もいます。しかし、エクイティはメンバーの活躍を支援することですから、すべての施策はエクイティとなり得るのです。
例えば、ジョブ型の等級制度があり、現等級に何年いたかに関係なく、今期担う予定の役割によって等級が決まるとします。そうしたら、産育休がブランクとならない運用が可能です(職能資格制度など他の等級制度であってもこうした制度は可能なので、あくまで例です)。おそらくジョブ型等級制度は、女性社員の活躍を主目的として導入されたわけではないと思いますが、エクイティとしても機能するのです。
こうして、会社や組織のなかにあるさまざまな施策を、「この施策をこのように捉えると、こうした人の活躍を支援できる」という風に考えることができると、エクイティは会社や組織の至るところに存在していると考えることができ、「DEIのための施策が思い浮かばない」という思いから解放されるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、エクイティをテーマに、何をどこまで支援することなのかということをご紹介してきました。最後になりますが、先ほど述べた、「『あとはあなたの努力次第』『あとはあなたの頑張り次第』と言えるところまで支援があるかどうか」という判断軸は、言い換えると、「それ以上にやりすぎる必要はない」という意味でもあります。今の組織責任者は、メンバーのために時間を割く方々が結構いらっしゃるようにお見受けします。それでなくても組織責任者は業務負荷が高い状況にあります。このコラムが、組織責任者の皆さんが、心身共に健やかに、自分の生活も大切にしながら職責を果たすきっかけになれば嬉しいです。
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



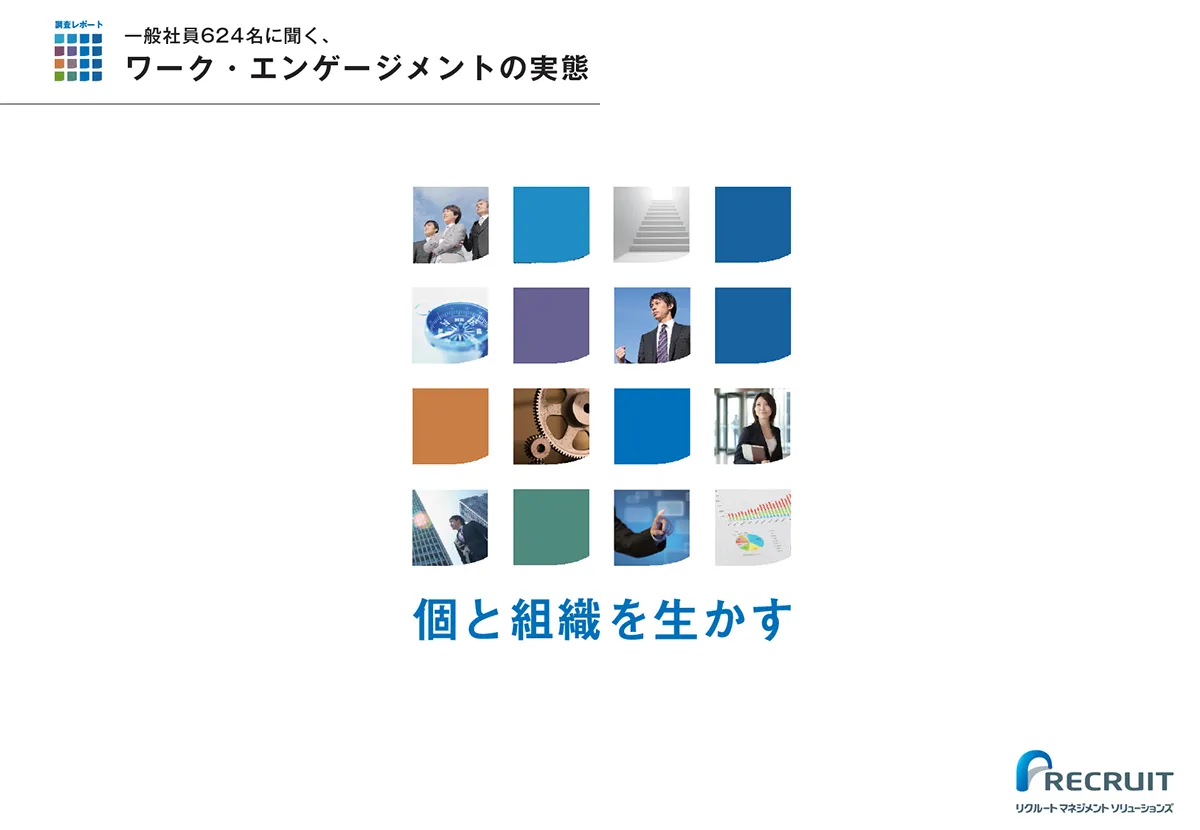
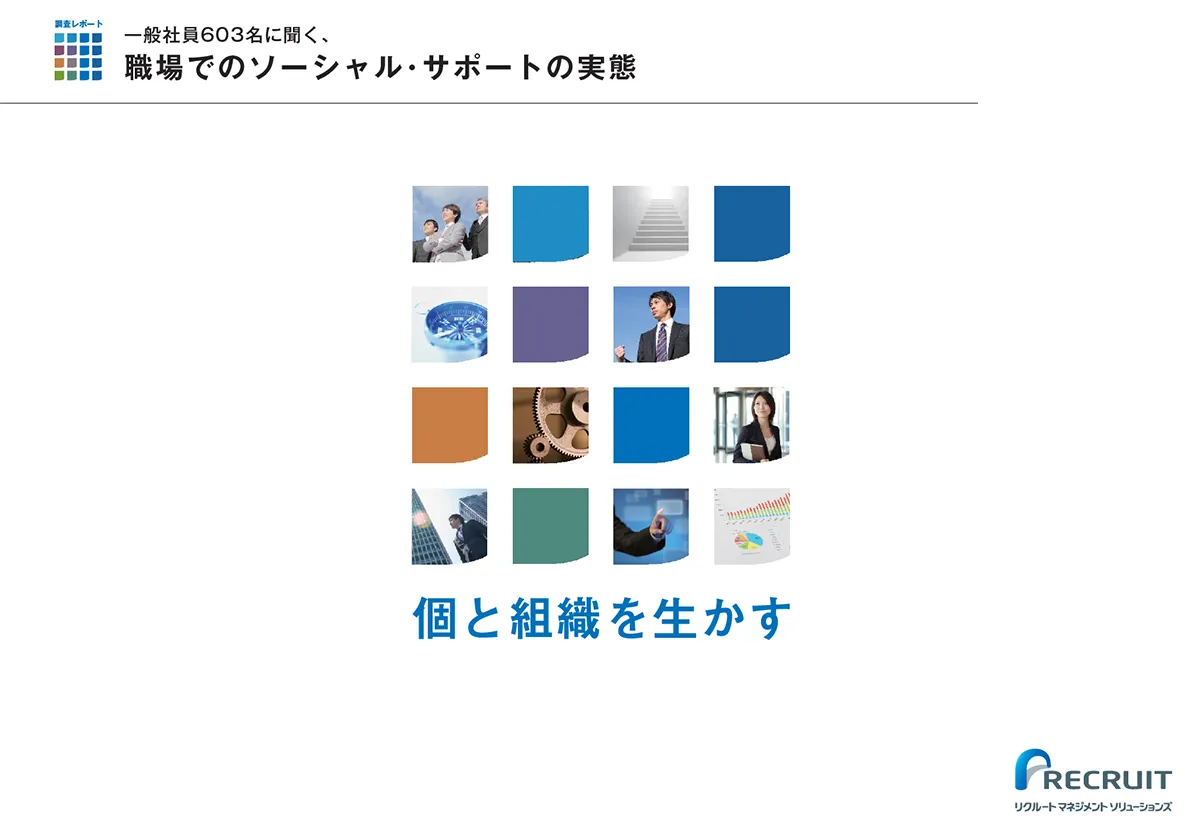









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての