- 公開日:2024/04/08
- 更新日:2024/05/16

DEIは、ダイバーシティ(Diversity)、エクイティ(Equity)、インクルージョン(Inclusion)の頭文字を取ったものであることは、ご存じの方も多いかもしれません。しかし、DEIとは何かについて説明することは意外と難しいのではないでしょうか。特にエクイティが意味するものを説明することは難しい方が多いようです。
ダイバーシティとインクルージョン
ダイバーシティとは「多様性」のことであり、Robersonら(2017)は、「集団内メンバーの特徴におけるさまざまな構成上の違い」と定義しています※1。「構成上の」という言葉には、性別や人種などの属性もあれば、個人の内面に関することもあります。インクルージョンについてShoreら(2011)は、「従業員が所属の欲求とユニークネス欲求の両方を満たすことのできる経験を通して、自身が職場で尊重されるメンバーであると知覚できる程度」と定義しています※2。日本語で「包摂」と訳されることもありますが、インクルージョンとそのまま使われることの方が多いかもしれません。
このほかにもさまざまな定義がありますが、実務上でしっくりくるのは、ダイバーシティとは「多様な人がいること」、インクルージョンとは「(それらの)人を生かすこと」というシンプルな分類かもしれません。
<図表1>インクルージョンフレームワーク
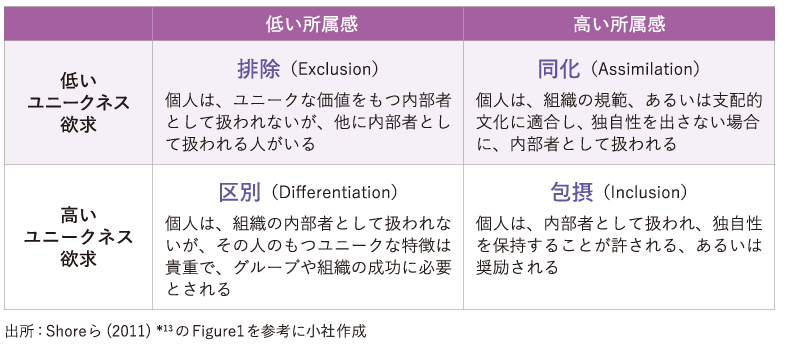
DからD&I、DEIへ
エクイティの定義に移る前に、あらためてDEIへの変遷を振り返りましょう。DEIの活動に以前から取り組んできた企業や組織の方々は、当時は「ダイバーシティ推進」という表現を見聞きすることの方が多かったのではないでしょうか。そういう意味ではD(ダイバーシティ)にインクルージョンやエクイティの意味も含めて語られていたといえそうです。その後、ダイバーシティ&インクルージョンという表現を使う企業が増えてきました。分けることはそこに何かの意味をつけることになりますから、D、つまり多様な人がいるだけでなくて、「その人たちが生かされる状態にしていくことが大事」という考え方が強調されてきたといえます。
そして、DEI(DE&I)という表現を用いる企業や組織が出てきました。エクイティ(Equity)が定義されたのです。エクイティとは、公正性のことです。ダイバーシティほど使われることはありませんが、すべての従業員がバックグラウンドに関係なく、機会を得られ、仕事で成功するために必要な資源や支援が得られることだといわれます※3。よく使われるエクイティの例えとしては、塀の向こうで行われているスポーツの試合を見られるようにするために、身長の高低によって踏み台の高さを変えるといったものや、身体の大きさや特徴に合わせて操作しやすい自転車は異なるため、本人に合ったものを提供するといったものがあります。例えに共通することは、個々人によって支援の内容や程度が異なるということです(もちろんすべての支援を個々人に合わせてカスタマイズするということではなく、多くの人が能力を発揮できない環境があれば、同じ支援を広く講じることになります)。
D&IにEが加わったことで明確になったのは、状態像や目指すことそのものと、そのための支援・取り組みは分ける必要があるということではないでしょうか。ダイバーシティが多様な人がいる「状態」やその状態を「目指すこと」、インクルージョンを(それらの)人の力を生かしている「状態」やその状態を「目指すこと」だとすると、エクイティはそうした状態をつくるための環境整備を指します。環境整備とは、支援・取り組みです。D、ダイバーシティ推進のなかでインクルージョン推進やそのための支援が内包されていたときには、多様な人がいればダイバーシティは推進できていると評価することもできたかもしれません。しかし、ダイバーシティとインクルージョン、エクイティが言葉として分かれてきたことによって、「自社・自組織の人材の多様性は確保されているか」「多様なバックグラウンドや持ち味を持った人が生かされているか」「それを単に現時点の状態として捉えるのではなく、支援・取り組みによって後押しできているか」と解像度を上げて自社・自組織の推進活動を見直すことができるようになってきたのではないでしょうか。
またD、E、Iの関係性ですが、DEI推進を始める前は、組織における多様性の幅が比較的狭いため、インクルージョンなどに必要な施策(エクイティ)も限られてきます。しかし、施策を講じることでインクルージョン度合いが上がると、組織として多様な方を受け入れる態様ができ、多様な方を惹きつけることができるようになります。そうなると、組織のダイバーシティ度合いが上がります。それにともない組織に新たなエクイティが必要になります。また施策を講じるとインクルージョン度合いが上がり、人材の多様性が広がっていく……、というサイクルが生まれます。
実務で使いやすいエクイティの考え方
D、E、Iと分かれたことで、自社・自組織の推進活動を見直すことができると前述しました。一方で、分かれたことでの悩みも出てきます。筆者はDEI関連のコンサルティングや研修講師をしていますが、特に、「エクイティ」という言葉はすぐには理解しづらい言葉のようです。また、今はメンバーの働き方改革進展のしわ寄せや、ハラスメント防止策の策定、法対応など、管理職の負荷増大につながる事柄が増えています。エクイティが、すべてのメンバーに合わせた支援だとすれば、管理職からしたら「どこまで管理職が支援しなければいけないのだろうか」「そこまで自分の役割なのだろうか」と思うのは理解できます。メンバーの活躍を真剣に考える管理職ほど悩むことになるかもしれません。加えて、最近は組織人事の分野でも個々のメンバー側の自律や選択を重視するようになっていますので、「メンバーの要望をすべて叶えないといけないのか」と思う管理職もいるでしょう。
そこで、筆者はエクイティを以下のように説明しています。
- 何らかの支援が必要かどうかの判断軸は、メンバーに対して「あとはあなたの努力次第」「あとはあなたの頑張り次第」と言えるかどうか
- エクイティはメンバーの活躍を支援すること。よって、メンバーの望みや困りごとに対応するかどうかの判断軸は、それに応えることで組織のパフォーマンスが上がるか
これでも判断に迷うところは残りますが、管理職の皆さんが実務的な判断基準だとおっしゃってくださることも多いです。
今回は、D、E、Iの意味や定義というテーマで述べてきました。次はエクイティに焦点を合わせて、エクイティを考える際のヒントを取り上げます。
注
※1 Roberson, Q., Ryan, A. M., & Ragins, B. R. (2017). The evolution and future of diversity at work. Journal of applied psychology, 102(3), 483を訳したもの
※2 Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A., Holcombe Ehrhart, K., & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research. Journal of management, 37(4), 1262-1289を訳したもの
執筆者

技術開発統括部
研究本部
組織行動研究所
主任研究員
武藤 久美子
2005年株式会社リクルートマネジメントソリューションズ入社。組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワーク、人事制度関連の寄稿多数。自身も2013年よりリモートワークを積極的に活用するリモートワークの達人。
(株)リクルート ワークス研究所 研究員(兼務)。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。
おすすめコラム
Column
関連する
無料オンラインセミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)


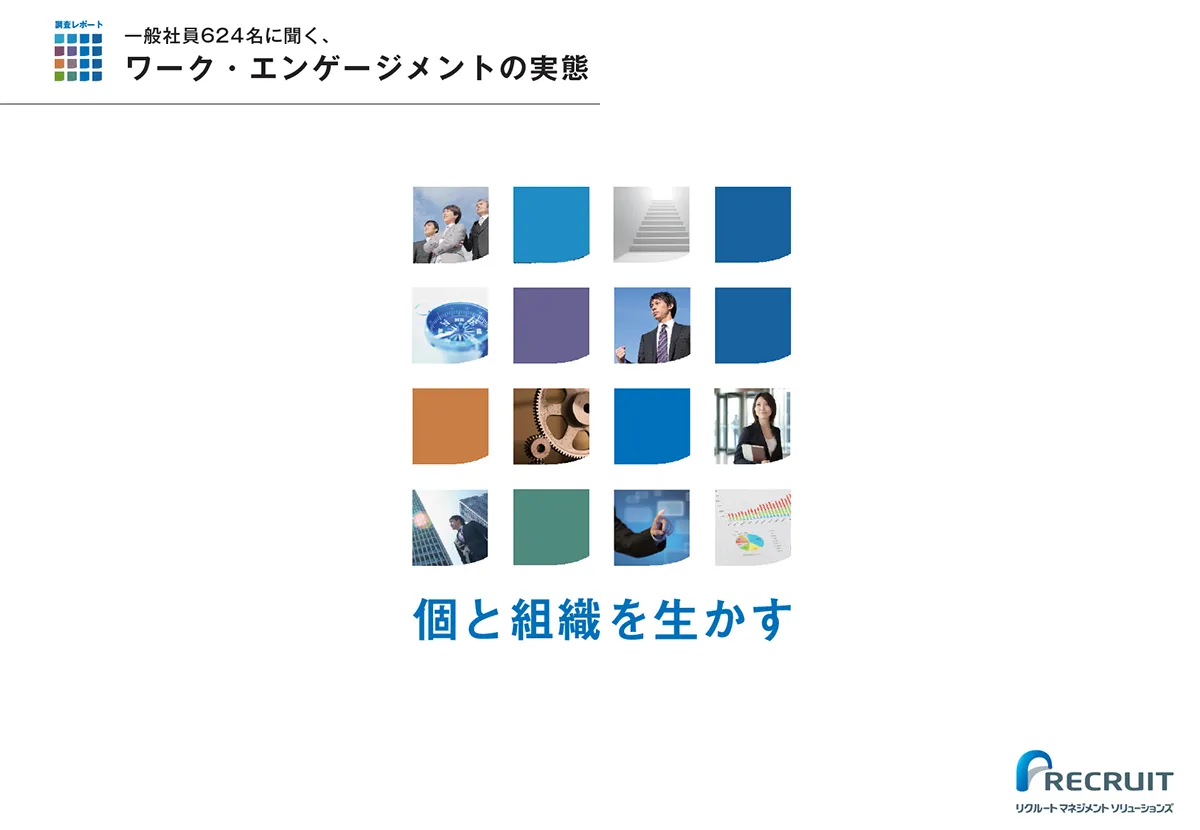
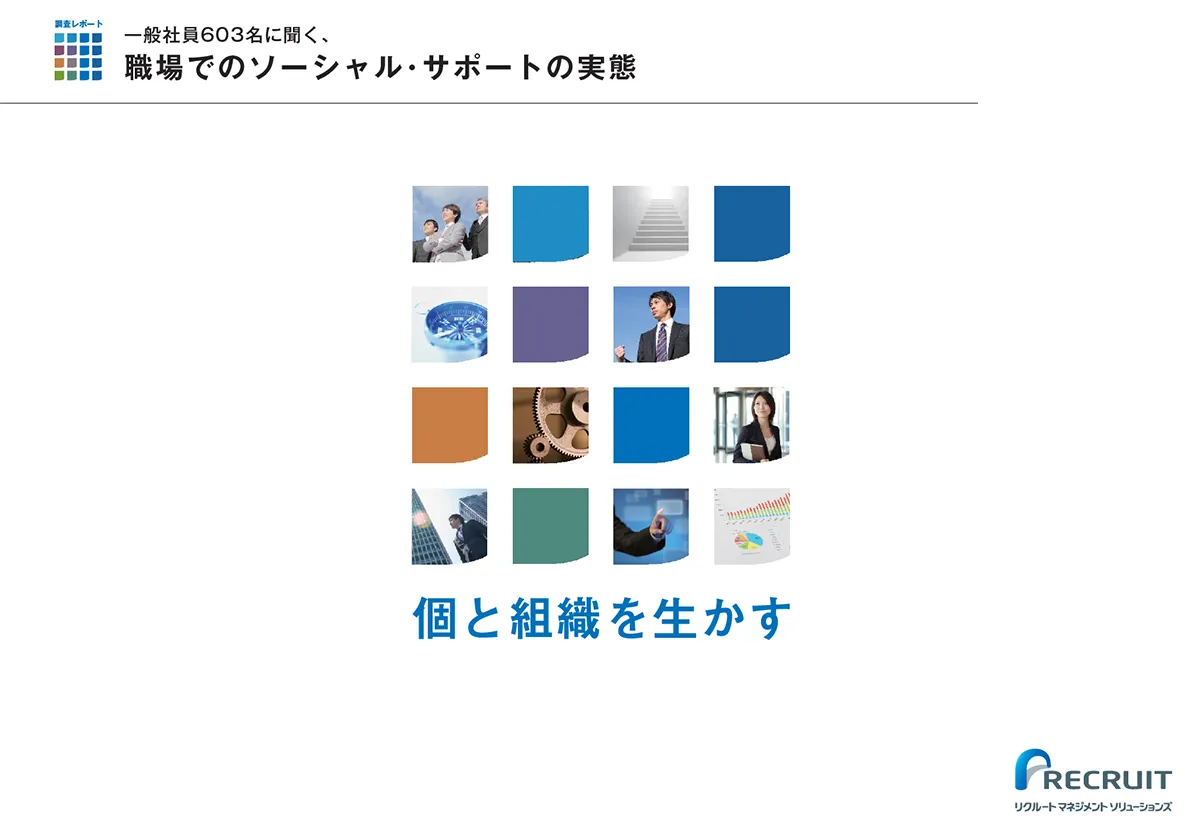
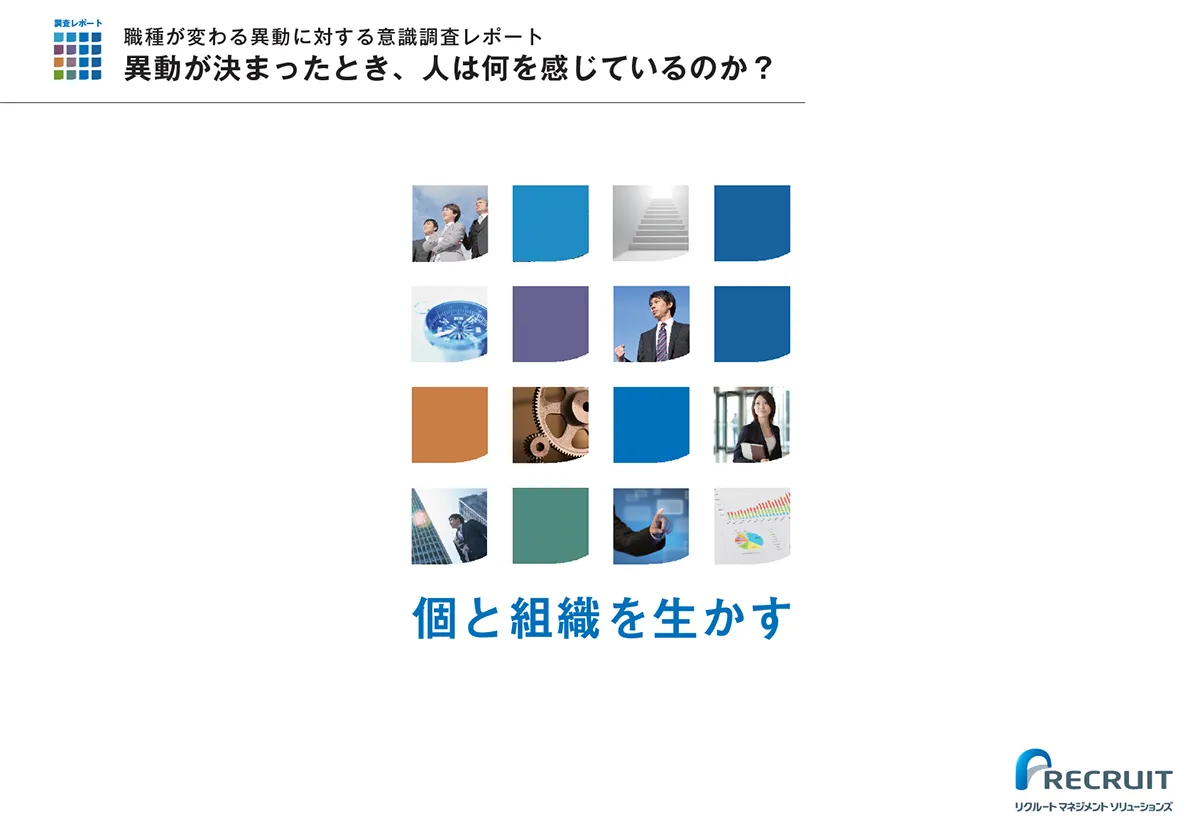









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての