- 公開日:2022/08/15
- 更新日:2024/05/16

50代であっても、あと20年も働く可能性がある時代です。漠然と働くには長い期間であり、人材マネジメントも、働く人の意識も変えていく必要があります。そこで、2022年6月2日の組織行動研究所セミナーは「アフターミドル*の可能性を拓く〜ポストオフ・トランジションを促進するには〜」と題し、人事・人材開発担当部門の方に向けて、アフターミドル・クライシスを乗り越えるための解決の方向性についてお伝えしました。今回はその内容をレポートします。
* RMS Message vol.62(2021)にて提唱した弊社による造語。ミドルからシニアへの移行期である50代〜 60代前半の世代を指す。
- 目次
- 年を重ねても「お金」だけでなく「健康」や「いきがい、社会参加」のためにも働きたい
- 以前と同じように働ける高齢者は実は多い
- 高齢者の雇用は増えているが、キャリア形成支援の余地は大きい
- 50代管理職のポストオフ後のキャリア・トランジションが大きな課題
- インクルーシブな風土、上司からの尊重と期待、本人のジョブ・クラフティングが適応感を高める
- これまでやらなかったことへのトライで ポストオフ後のキャリアの方向性を試行錯誤する
- 会社からの期待と本人の志向の「丁寧なすり合わせ」が大切
年を重ねても「お金」だけでなく「健康」や「いきがい、社会参加」のためにも働きたい
講師プロフィール
古野庸一 リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 所長

1987年株式会社リクルートに入社。キャリア開発に関する事業開発、NPOキャリアカウンセリング協会設立に参画する一方で、ワークス研究所にてリーダーシップ開発、キャリア開発研究に従事。2009年より現職。著書に『「働く」ことについての本当に大切なこと』(白桃書房)、『「いい会社」とは何か』(講談社現代新書)、『リーダーになる極意』(PHP研究所)、『日本型リーダーの研究』(日経ビジネス人文庫)、訳書に『ハイ・フライヤー 次世代リーダーの育成法』(モーガン・マッコール著、プレジデント社)など。
多くの企業で、高齢の社員の活性化が課題になっています。一方の個人にとっても、50代以降にいかに仕事へのモチベーションや職場とのよい関係を保ち働きつづけるかは悩ましい問題です。そこで本セミナーでは、高齢者の就労における企業の実態や先行研究、弊社で実施した「ポストオフ経験に関する意識調査(2021)」結果を紹介し、最後に50代~60代前半の「アフターミドル」の可能性を拓くための具体策についてお伝えします。なお、組織行動研究所では、ミドルからシニアへの移行期である50代~ 60代前半の世代をアフターミドルと定義しています。
今、少子高齢化の進行と共に高齢者が急速に増えています。同時に社会保障給付費があっというまに100兆円を超え、約130兆円にまでなりました。この衝撃的な社会保障給付費の上昇を抑制するためにも、高齢者の就労を促進することが急務となっています。
このような状況を受けて、2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正されました。改正高年齢者雇用安定法によって、企業には65歳までの雇用確保が義務として、70歳までの就業機会確保が努力義務として課せられました。また、企業は次のいずれかの措置を講ずるよう努めることを求められています。
(1)70歳までの定年引き上げ、(2)定年制の廃止、(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入、(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、(5)70 歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
では、働く人の意向はどうなっているのでしょうか。内閣府の調査では、60歳以上の約70%が、一定年齢まで、あるいは働けるうちはいつまでも働きたいと思っています(図表1)。
<図表1>就業希望年齢
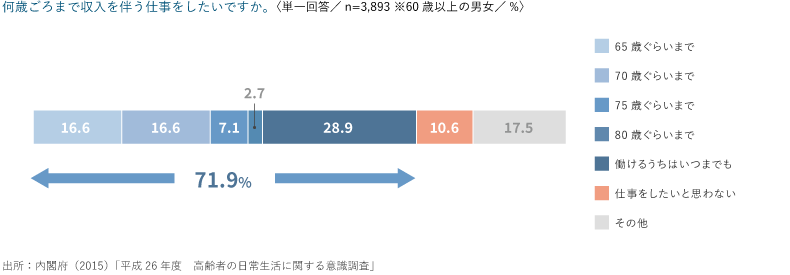
その背景には、お金・健康・孤独の問題があります。50代の最も大きな悩みは、「老後の生活設計について」「今後の収入や資産の見通しについて」「自分の健康について」です(内閣府、2021、国民生活に関する世論調査)。また、日本には60歳以上で「家族以外の親しい友人がいない」と答えた人が31.3%もいます。アメリカ(14.2%)・ドイツ(13.5%)・スウェーデン(9.9%)に比べ、明らかに高い数値です(内閣府、 2021、 令和3年版高齢社会白書〈全体版〉)。つまり、単に「お金」を得るだけでなく、「健康」や「いきがい、社会参加」のためにも働きたい、という意向が強いのです。そのことは、図表2の調査結果からも明らかです。
<図表2>60代の就業理由
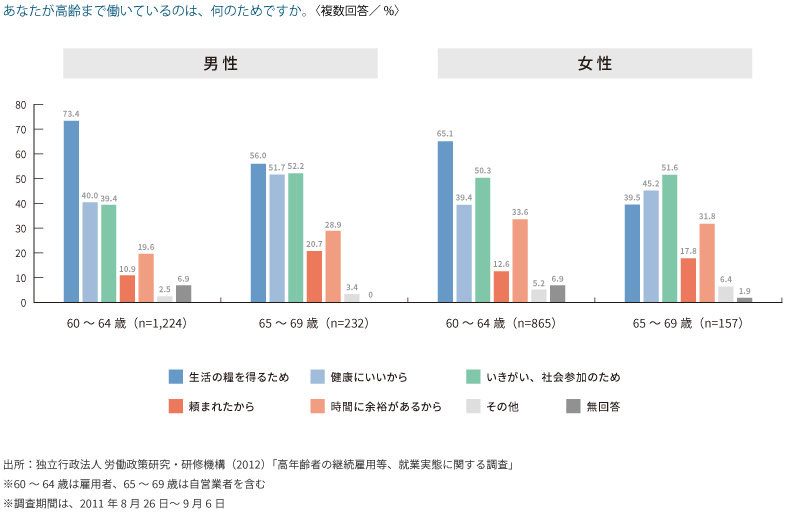
以前と同じように働ける高齢者は実は多い
他方で、経営学・社会心理学などの学術的研究からは次のことが分かっています。
●職務パフォーマンスは、一般的には年齢と共に低下するわけではない *1
●組織市民行動(決められた役割を超えた組織への貢献)は年齢と共に上昇する *1
●誠実性と協調性は年齢と共に高まる *1
●結晶性知能は維持されやすく、流動性知能は加齢にともなって低下していく *2
●職務満足度は30代半ばまではいったん低下し、その後定年直前まで上昇する(U字型仮説) *1
●高齢になると、外発的動機(昇進・金銭報酬)ならびに他者より有能でありたいと思う動機は低下して、内発的動機(達成、他者との関係性、自律など)が上昇する *1
*1 弊社コーポレートサイト「働くシニアの心理・高齢化する職場を考える」
*2 西田裕紀子(2017) 「中高年者の知能の加齢変化」老年期認知症研究会誌 第21巻 第10号
以上の研究成果をまとめると、年を重ねたからといって職務パフォーマンスが低下するわけではなく、むしろ結晶性知能は高まるケースがよく見られます。さらに、組織貢献意欲、内発的動機、誠実性や協調性、職務満足度も上がる傾向があります。つまり、以前と同じように働ける高齢者は実は多いのです。
ただし、高齢の就労者は多様です。職歴、役職経験、家族構成、金融資産、社外ネットワーク、働く動機、不安の要因などが一人ひとりまったく異なります。「物忘れが多い」「テクノロジーに弱い」「変化に弱い」といった高齢者に対するアンコンシャス・バイアスがありますが、こうした傾向も、実際は人によってかなり違います。「アフターミドルは○○だ」と一括りにして扱わないことが肝要です。
高齢者の雇用は増えているが、キャリア形成支援の余地は大きい
では、日本企業による高齢者雇用の実態はどうでしょう。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の「高年齢者の雇用に関する調査(2020)」によると、94.7%の企業が定年制を導入しており、定年制あり企業の75.6%が60歳定年です。継続雇用制度は、定年年齢を64歳以下にしている企業のほとんど(97.2%)が導入済みです。そして、多くの企業で70%以上の従業員が継続雇用を希望しています。60歳前後における仕事の変化はあまりなく、約80%が同じ仕事を続けていますが、「責任の重さが軽くなった」との回答は40%近くあり、雇用形態や職責の変更が一定数行われているようです。
60代前半の雇用における主な課題については、「管理職社員の扱いが難しい」「処遇決定が難しい」、そして「定年者の雇用継続によって若年層が採用しにくくなる」などが挙げられています。一方、キャリア形成支援のための人事制度は、総じて実施率が50%に達していません。自己啓発支援・自己申告制度・目標管理制度・キャリア研修は、実施率40%以上と以前に比べると大幅に増えていますが、高齢の社員のキャリア形成支援の余地はまだまだ大きいでしょう。
50代管理職のポストオフ後のキャリア・トランジションが大きな課題
ここまでは、60歳以降の高齢者の就労における実態や先行研究についてお話ししてきました。こうした問題を考えるにあたり、私たちは、管理職の50代以降のポストオフをいかにスムーズに行うかが、本人にとっても会社にとっても大きな課題であると考えています。そこで、2021年に実施した「ポストオフ経験に関する意識調査」の結果をご紹介します(図表3~8)。従業員規模300名以上の企業に勤める50~64歳のポストオフ経験者766名に聞きました。50代が約6割、60代が約4割で、96%以上が男性でした。
図表3によると、ポストオフ後に80%以上の人が賃金低下を経験しています。周囲からの期待の大きさ、仕事量・労働時間、人事評価、1日に会話する人の数、自分で判断し主体的に進める度合いなども下がった人が半分程度いました。
<図表3>ポストオフ後の変化
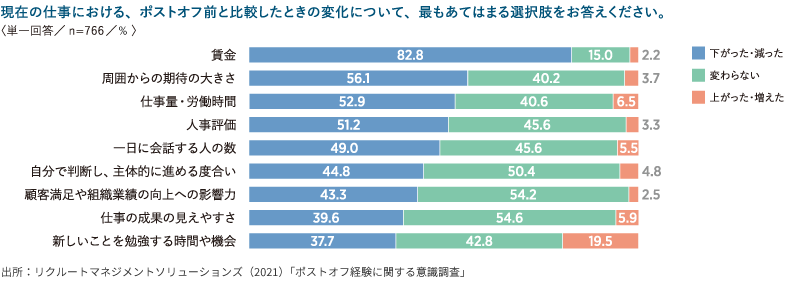
図表4は意欲・やる気の推移を示しています。一度はやる気が下がったとする人は6割前後にのぼり、内訳として下がったままという人が4割前後、やる気が再浮上した人は2割前後にとどまっています。やはり、ポストオフはモチベーションを下げる可能性があります。
<図表4>ポストオフ後の仕事に対する意欲・やる気の推移
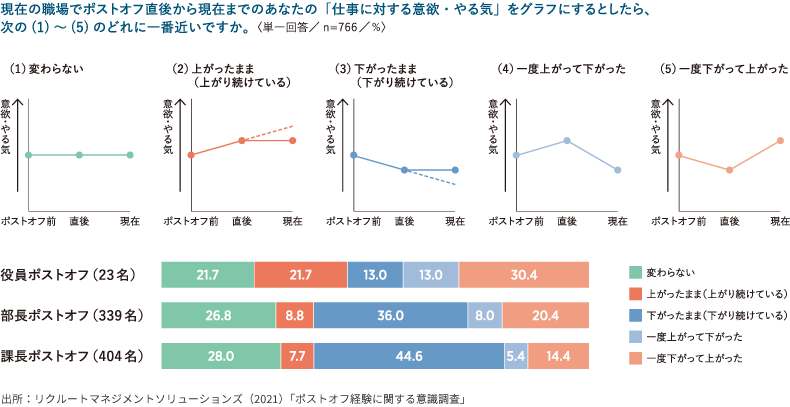
図表5は課長ポストオフの皆さんの現在の仕事や働き方について、実際と希望を聞いた結果です。実際と希望に大きな開きがあるのは、「マネジメント経験を活かす」や「プロフェッショナルとして特定の職務・専門分野を究めていく」「自身が問題意識やこだわりをもっているテーマに取り組む」です。アフターミドルには、挑戦したいことに挑戦できていない歯がゆさのある方が多いようです。一方で、「若い世代の邪魔をしない立ち位置や業務を引き受ける」や「若い世代が積極的に担当しない業務を引き受ける」は、希望以上にやっています。若い世代に気を使っているアフターミドルが多いことが分かります。
<図表5>ポストオフ後の仕事や働き方に関する本人の実際と希望
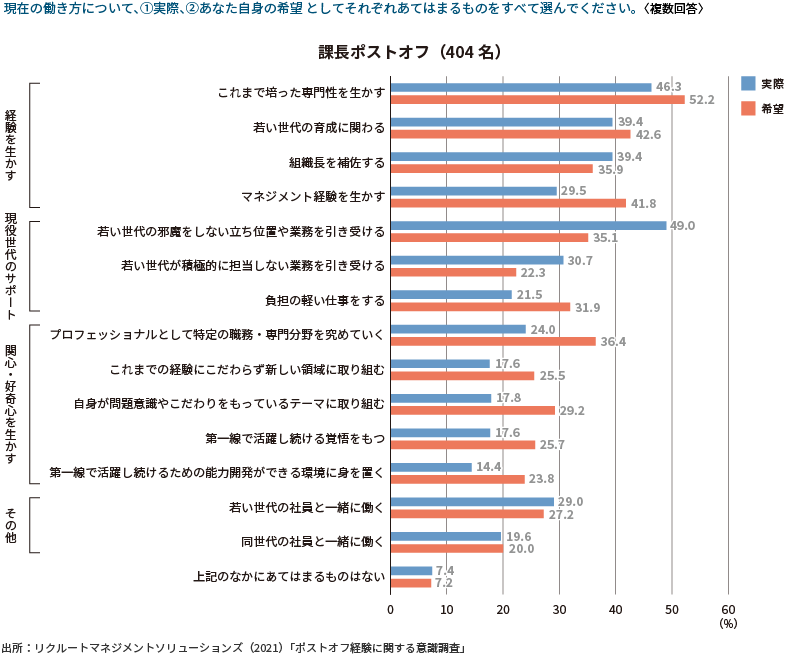
インクルーシブな風土、上司からの尊重と期待、本人のジョブ・クラフティングが適応感を高める
図表6は、ポストオフ前後の労働価値観の変化を示しています。部長・課長ポストオフの皆さんは、「人の役に立ち、感謝される」と「職場環境が快適でストレスが少ない」の順位がポストオフ後に大きく上がっています。「自分が楽しめる、面白いと思える」は、役員ポストオフも含めた全役職で順位がジャンプアップしています。これは、「アフターミドルになると、内発的動機が上昇する」という学術研究の結果と関連性があるでしょう。内発的動機にフォーカスすることが肝要です。
<図表6>ポストオフ前後の労働価値観
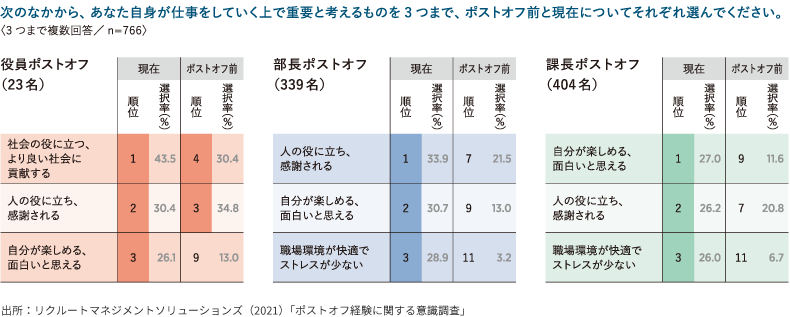
図表7は、ポストオフ前の準備や行動について尋ねました。「専門性の高い知識やスキルを身につける」「最新の知識を学び続ける」「役職や地位などの権威を振りかざすことがないように心がける」にポストオフ後の新環境への好適応者が多いことが目につきます。なかでも私が特に注目しているのは、課長ポストオフの「プレイヤー業務を手放さない」の好適応群の多さです。ポストオフ後につながるようなプレイヤー業務は、ある程度継続しておくことがよいともいえそうです。
<図表7>ポストオフ前の準備や意識して行っていたこと
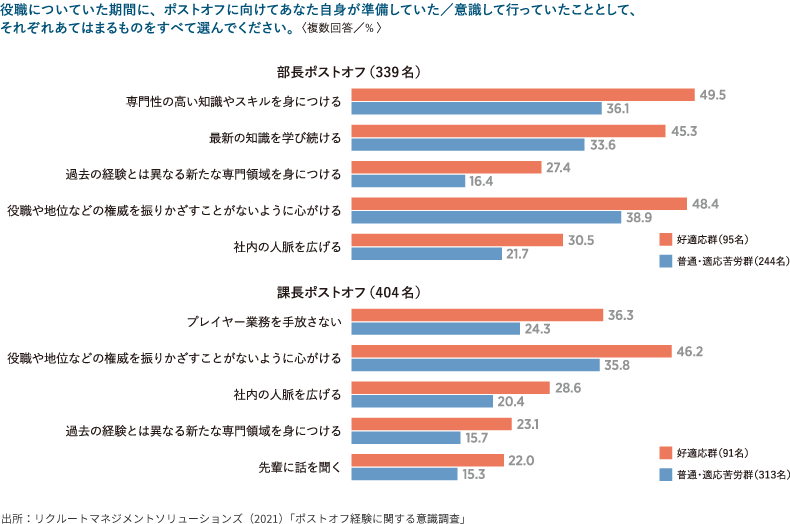
図表8によると、インクルーシブな風土、上司からの尊重と高い期待、そして拡張・協同ジョブ・クラフティングが適応感を高めます。「インクルーシブな風土」とは、誰にでも発言権があり、年齢などにかかわらず成果を公平に評価する職場環境のことです。「拡張・協同ジョブ・クラフティング」とは、周囲と力を合わせながら、自分のジョブやタスクの範囲を広げる行動のことです。
<図表8>適応感に影響する環境要因・本人要因(重回帰分析)
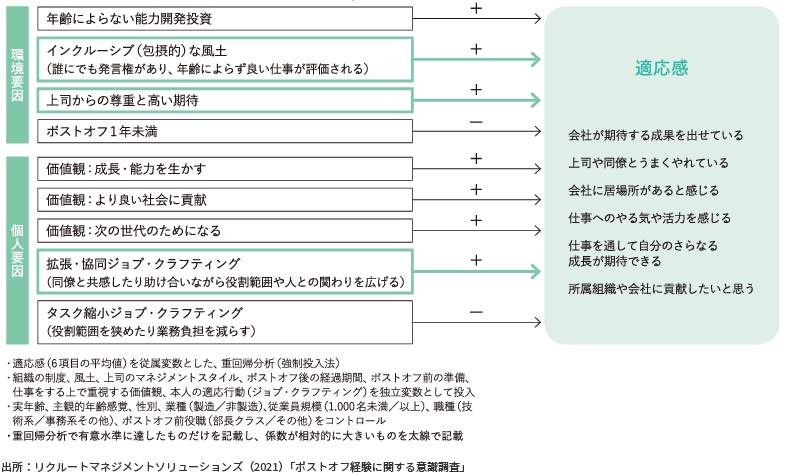
これまでやらなかったことへのトライで ポストオフ後のキャリアの方向性を試行錯誤する
以上の調査結果を踏まえて、「アフターミドルが活躍促進のためにできること」をお話しします。活躍促進策のベースは、本人のキャリア・トランジション支援にあります。
個人の側に立つと、特に50代管理職のポストオフ後のキャリア・トランジションが極めて大きな課題です。なぜなら、管理職の仕事は組織からの明確な要請があることが多いため、その仕事が自分に合っているのか、自分は何をしたいのか、ということはあまり考える必要がないからです。忙しくて、考える暇もないということもよくあります。管理職から降りた瞬間に、目の前の仕事がなくなり、これからどうしたらよいかが分からなくてハッとする方が実に多いのです。
キャリア・トランジションを考えるときに重要なのが、「キャリア・アダプタビリティ」と「キャリア・アイデンティティ」です。「キャリア・アダプタビリティ」とは、環境に適応できるようなキャリアなのかという視点です。やりたいことがあったとしても、その仕事が所属している会社になければ、現実にアダプト(適応)できません。一方で、自分を見失ってもいけません。自分らしさの羅針盤になる「キャリア・アイデンティティ」が必要になってきます。変化の時代にあって、年齢を重ねるごとに自分らしさも変わっていきます。そういう意味で、行動を通じて「キャリア・アイデンティティ」を何度も作り替えながら進む必要もあります。キャリア・トランジションの際には、図表9のように、これまでやらなかったことにトライし、内省と試行錯誤を繰り返すことで自己理解を進め、将来の方向性を描いていくことをお勧めします(図表9の詳細は前回の組織行動研究所セミナー開催報告「キャリア自律施策の展開~なぜキャリア自律が進まないのか~」をご覧ください)。
<図表9>キャリア自律を進めるサイクル
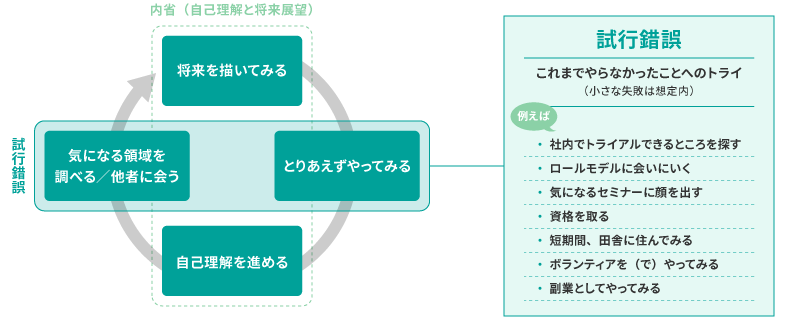
会社からの期待と本人の志向の「丁寧なすり合わせ」が大切
企業側からすると、アフターミドル問題の深刻度は各社さまざまです。アフターミドル層の人員数・割合、人材不足感、キャリア自律支援制度、人材マネジメントポリシー、貢献に応じた報酬、役職定年制、高齢者でも活躍できる仕事、社外への転進制度・慣習などの違い・有無によって、課題の重大さが異なります。また、アフターミドル問題は組織活性、若年者雇用、リテンションとも関わってきます。
その前提を踏まえたうえで、アフターミドルの可能性を拓くための具体的な施策をご紹介します(図表10)。
●短期的施策の第一歩は、自社のアフターミドルにインタビュー・調査などをして、彼らの気持ちや実態をよく把握することです
●次にワークショップなどを活用した、会社からの期待と本人の志向の「丁寧なすり合わせ」が大切です。多くの場合、会社からの期待はアフターミドルに明確には伝わっていません。一方で、本人もやってみたいことがはっきりしていないことが多く、たとえ明確に分かっていても会社にどこまで言ってよいのか躊躇するのが普通です。丁寧な対話によってすり合わせることで、期待と志向の両方が明確になり、一人ひとりに合った将来が具体的に見えてくるはずです
●加えて、カウンセリング・研修・出向・学び直しなどのキャリア・トランジション支援が効果を発揮します
●長期的施策としては、今後は若いころからキャリア自律を促す必要があります。1on1制度・研修・自己申告制度・各種休業制度・留学制度・副業支援・出戻り支援・自己選択型の働き方・カウンセリング・他の仕事やモデルになる人の情報提供など、多面的な支援が可能です
●また、アフターミドルの可能性を拓くような人材マネジメントポリシーを作ったり、管理職以外の仕事を傍流扱いにしないような風土を醸成したり、貢献報酬型、デュアル・ラダー、役職定年制度などの人事制度を見直したりする施策にも効果があるでしょう。
<図表10>アフターミドルの可能性を拓くための具体的施策
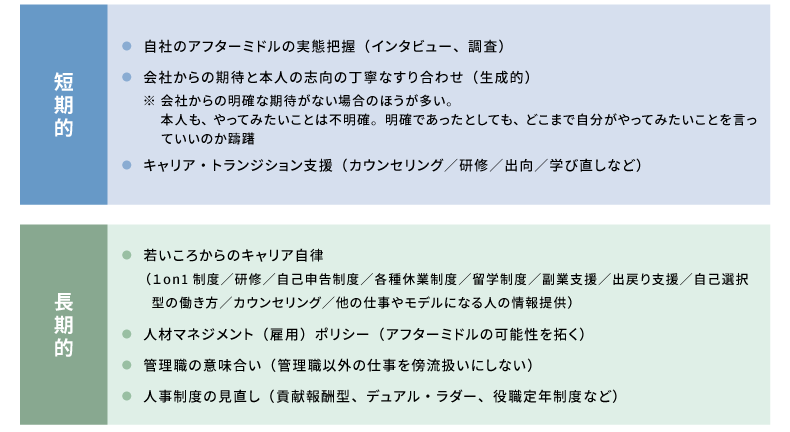
アフターミドル活躍促進施策は、人事施策の集大成です。ぜひアフターミドルの可能性を拓くべく取り組んでいきましょう。
【text:米川 青馬】
この記事で引用した調査
『ポストオフ経験に関する意識調査』
◇次回の組織行動研究所セミナーのご案内
■ 2022年9月14日(水)13:30~14:30
「個人選択型HRMのこれから」
> 詳細、お申し込みはこちら
バックナンバー
キャリア自律施策の展開~なぜキャリア自律が進まないのか~(2022年3月開催)
自律とエンゲージメントを促進するために 変わるマネジャーの役割(2021年12月開催)
コロナ禍で注目される自律的な働き方とエンゲージメント(2021年9月開催)
おすすめコラム
Column
関連する
無料セミナー
Online seminar
サービスを
ご検討中のお客様へ
- お役立ち情報
- メールマガジンのご登録をいただくことで、人事ご担当者さまにとって役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。
- お問い合わせ・資料請求
- 貴社の課題を気軽にご相談ください。最適なソリューションをご提案いたします。
- 無料オンラインセミナー
- 人事領域のプロが最新テーマ・情報をお伝えします。質疑応答では、皆さまの課題推進に向けた疑問にもお答えします。
- 無料動画セミナー
- さまざまなテーマの無料動画セミナーがお好きなタイミングで全てご視聴いただけます。
- 電話でのお問い合わせ
-
0120-878-300
受付/8:30~18:00/月~金(祝祭日を除く)
※お急ぎでなければWEBからお問い合わせください
※フリーダイヤルをご利用できない場合は
03-6331-6000へおかけください
- SPI・NMAT・JMATの
お問い合わせ -
0120-314-855
受付/10:00~17:00/月~金(祝祭日を除く)



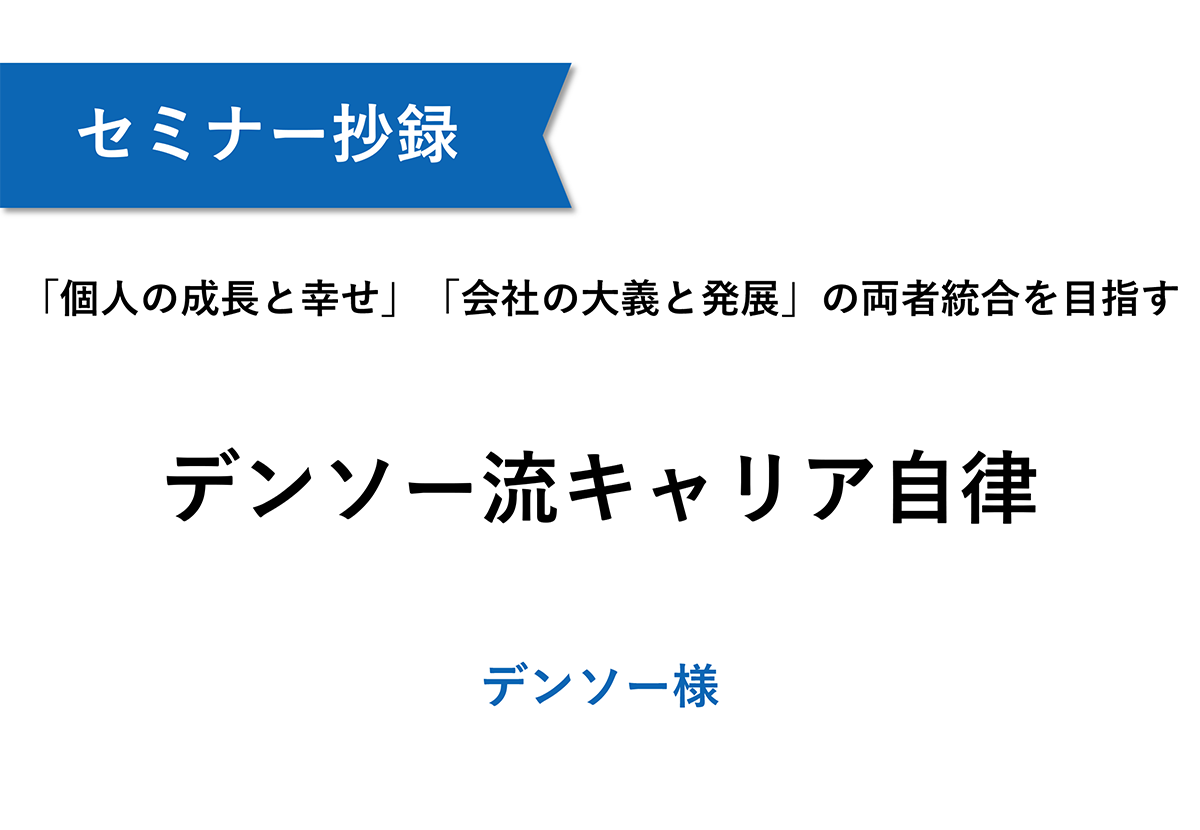









 動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
動画セミナーだからいつでもどこでも視聴可能
 メルマガ会員登録で全ての
メルマガ会員登録で全ての